
白と黒(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 13)
※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。
白と黒
岐阜城が大戦の前に騒然となっている中、熊千代は津田坊の甲冑姿がこちらへ来るのを見て自分から駆け寄った。
「ついに、初陣でございますな!」
幕の影にいて、こちらを振り向いたのは信長で、熊千代はあっと膝をついて頭を下げた。からかうような声が降ってきた。
「どうだ、あれから会えたのか?」
明智の珠子のことだと瞬時に悟って真っ赤になった。熊千代が純情な顔を見せるのを、信長は楽しそうに眺める。
「おまえのような目利きが目を付けたのだからよほどの器量なのであろう」
腰を上げ、二人を置いて去って行く前に、信長は言い残した。
「元服、初陣の心得は七兵衛に聞くがよい」
津田坊が元服した時、烏帽子親を務めた信長は、落とした前髪痕を名残惜しそうに見ながら「荷が軽くなったであろうが」と言った。
早ければ十二、三ですませる他の家に比べ、遅い元服ではあったが、信長はから十八まで年齢の少年たちを好む性質から、お気に入りはなかなか元服を許さず、十八前後まで小姓として置いておくのが常だった。少年が大人に変わってゆく過程において、彼らは不思議な輝きを放っている。
「お坊どのをこれから何と呼べばよいのですか?」
熊千代が聞くと、
「七兵衛でよい」
前髪を落とした涼やかさで津田信澄は笑った。そして熊千代を近くへ差し招いた。耳に囁く。
「あのな、ひとつ頼まれて欲しいことがある」
◇
五月十三日に織田軍は出発と決まった。戦に継ぐ戦を重ねている今、いつでも出られる準備はあるが、今回は規模が違う。支度を整えながら信長は明智十兵衛に聞いた。
「お前は後で参るのであったな」
「島津家久どのが京に来られているとのこと、一つ饗応してからゆるりと参りまする」
信長は九州の島津までが、この騒乱の気配を伺いに来ていることに気をよくした。そうだ、日ノ本は武田のみにてはあらず。
「如何する」
「琵琶湖を屋形船で遊覧せしめた後に、風呂でもてなそうかと思うております」
明智の坂本城の豪華な風呂は有名だ。
この大戦の前に、随分な余裕を見せる豪胆な饗応が気に入った。さぞ度肝を抜かれるであろう。
明智は未来を見据えている。
信長は、よかろう、と言い捨てて部屋を出た。
◇
「このたびのこと、大いに不満でござる。なぜ我等は留守居役なのか!父が、父が、おれは情けのうて!」
「畿内を抑えるのも重要なお役目なれば、そなたも心するようにせねばなりませぬぞ」
ぶんむくれで口を尖らせて文句を言う熊千代を穏やかに諭しながら廊下を歩く。明智十兵衛はまだ甲冑もつけていない。先に出立した主力軍を追って立つのは島津家久への饗応を終えた五月十六日、奈良で大和国衆の鉄砲隊と合流をすることとなっていた。
こうして熊千代の相手をしているのも、この廊下を歩き終わる短い間でのことだ。
信忠の近くで雑務をしながら、織田家の中枢にいる熊千代は、この少年期での経験において、のちの世でも必要となるすべてが養われていた。
取次一つとっても、大名たちの相性、好み、縁戚関係、また係争に到るまで、細かく把握せねばならない。熊千代の気性を思いやり、表立たないようにしながら、明智はこと細かにこつを教え、情報を与えてくれた。
俯瞰して広く、寄り添って細かく、それは、父が及ばない精密さと情を伴う気配りを保っている。いつしか熊千代は、明智が父を抜いて信長に評価されていることの理由を、実感をもって理解するようになっていた。
公家や寺社とのやりとりをするためには、彼らの考え方、視点、流儀を知らねばならず、あらゆる方面での知識を身につけておかねばならない。父が必要以上にうるさく手紙で伝えてくるが、細部に拘りすぎていて、熊千代には、明智の教えてくれるゆったりと要点を絞った教えが好ましかった。
わずかな時間を割いても必ず相手をしてくれる明智だが、その頃の熊千代には、こうして会話することで明智が彼から得ている情報にまで思いは及ばなかった。
◇
珠子は目を丸くして香袋をつまんだ。
「あのな、こっそりだぞ」
熊千代は、珠子にささやいた。
「おれなら明智の家に気安く出入り出来るであろうと、七兵衛どのからこれを預かってきたのだ」
小さな香袋を引っ張り出したとき、ふっと逆さまになって、ゆるんでいた紐の間から何かかがこぼれた。あっと戸惑うより、珠子が拾う方が早い。床に当たって軽い音を立てたそれを、二人で額を合わせてしげしげと見る。黒の碁石がひとつ入っていただけで、熊千代はほっとした。
ひそかに危惧していた、恋文か和歌のようなものではなさそうだ。
「わかり申した。お待ちくだされ」
珠子はすましておとなぶった態度で言うと奥へ引き返す。
そう長く待つ必要はなかった。
すごい勢いで珠子が走って逃げてくるのが見え、あとを追いかけて若い娘が走ってきた。なんだ、いつも気取ってつんとしておるが、あんなに早く走れるのではないか。熊千代は妙なところで感心した。
「熊千代どの、これは何のいたずらか?」
「いたずらではありませぬ!」
むっとして熊千代は聡子に言い返した。
「七兵衛どのから預かってきたのだ」
聡子は香袋の口を開き、中身を押し込むように再び入れて熊千代に押し付けた。
「お返しして!」
「せめて、返答なりと……」
「いらぬ。確かに返すのですよ、必ずね」
仕方なく、熊千代は信澄のもとに香袋を返しに行った。軍は既に完璧に準備を整えており、甲冑姿で歩き回る荒武者の間を、小姓姿で歩くのが恥ずかしくてならなかった。もう、二度とこのような役目は引き受けたくないと思う。
信澄は、磯野員昌の軍と共にいる。浅井家臣として働き、佐和山城主であったが降伏をして今は軍門に下っている猛将だった。若手の面倒を見るように命じられたのだ。
「あのう……。七兵衛どの、返されてまいりました」
「そうか」
信澄はこともなげに言うと、熊千代の目前であるのもかまわず袋を開いて石を取り出した。そして笑顔になる。磯野が呼ぶ声がして、信澄は香袋を懐にねじ込むと立ち上がった。
「いま参る」
鎧が音を立て、気迫が漲って出陣前の荒々しい緊迫した空気とともに、抗い難い興奮が周囲を包む。
熊千代は邪魔にならぬよう、膝立ちでさっと後にすざる。素早い目は信澄が籠手の中にそっと握り込んだ石の残像をとらえていた。
その色は黒ではない。白だった。
◇
長篠の大勝利は機内を沸かせ、明智の婿になる津田信澄は、初陣を勝利で飾ることができた。
一報は二十二日明け方には藤孝のもとへ届き、信長が自ら勝利を伝えていた。帰り次第の婚儀を控えたお聡は、既に岐阜城へ入っている。
明智家の奧屋敷は、長篠で殺された長篠の娘おふうの噂でもちきりだった。
奥平信昌は人質に送った妻を離縁して徳川方につき、敵方は見せしめとして殺したそうな。新たに縁付いた亀姫は、上様が三河殿に命じたそうな。
煕子はここの所少し調子が良いと、少し夏日が挿しはじめた庭を見に縁側まで出て、この話を眉を寄せ、目を閉じて聞いていた。
「まことにむごい。片や、岩村城では上様の伯母上が武田方に嫁がれましたでしょう?」
「城主として守っておられた女丈夫。秋山殿は猛将。開城するが得策と判断なされたのでしょう。さような色めいた話ではございますまい」
ここに姉がいたら、どう答えるであろうかなあ。
珠子はひそかに想像した。口やかましい姉だが、こうしていなくなると肌寒いほど骨身に寂しい。
三姉妹いち肝の据わった、決断の早いお聡は、いつも誰にも想像できない一手を打ってくる。
負け戦でいざ逃げねばならぬことになっても、姉上は落ち着いて指図なさるのであろうなあ。
「わたくしは戦はきらいです。ですがいざ、というときにも思いきった手を取れば活路が開けることがあるやもしれぬ。それがわたくしのやり方ゆえ」
お聡はきっぱりと言う。
「このたびは大勝利であったが、からくも得た勝利、まずは越前、それから丹波、これは大仕事になるであろう。父上も休む暇なく戦い続けねばならぬ。我等もいつでも覚悟をしておらねばならぬこと。よいか?たま?」
珠子はひとりひとりの顔色とことばを鋭い目で見ていた。
こうして水を向けられると唇を噛み、言い放った。
「ただ人質となり、むざむざ殺されるぐらいならば、何としても一矢報いて死にたいと思いまする!」
◇
「あの石のこと、わかったのよ」
大真面目な顔で、珠子は熊千代にささやいた。
「おさとお姉さまに根掘り葉掘りききました」
「おれも七兵衛どのに聞いたぞ。有岡城で顔を合わせたことがあったそうだな」
珠子と熊千代は、子雀の囀りに花を咲かせていた。
──明智の二女はな、容にすぐれているのみならず、表情ゆたかにて態度も堂々としておった。姉の方が万事控えめながら譲らぬ。
まだ結婚より前、荒木の城に、使者として津田坊が赴いたときのことだった。
荒木の家は気さくで大らかな雰囲気であり、村重の側室で美人と有名の千世保、村重の長男村次も、男女取り交ぜて賑やかに津田坊を迎えた。その中に、明智の長女お岸がおり、いま次女のお聡も来ているとあって、奥向きは沸き立っていた。
津田坊も、あれが噂の三姉妹の一人か、と顔を伺わずにはいられない。
ただ美人と一口に言っても、まるで違う。千世保は小柄で目尻が優しく下がっており、芯の強さがありながら花のように明るい。
明智の長女は美しさは群を抜いていたが、うつむいて慣れない様子でいる。嫋やかだが顔色が悪く、伏し目がちで苦しそうに見えた。
津田坊に対し、荒木の息子の村次だけは屈託なく接していたが、荒木家中はそろって警戒する様子を見せている。何しろ、津田坊は荒木が止めを指した和田是政の孫なのだ。(母親が和田是政の娘だった)
態度がかたく、わずかな動作だけではっと緊張が走り、目を見開いて顔を見合わせる。下手な対応をすれば、何の難癖を付けて信長に報告されるかもしれない。
恐れられるのには慣れている。津田坊は平気な顔をしていた。
「あぁ、負けた負けた!」
村次が、津田坊相手に打っていた碁を投げ出した。
「誰か変わってくれ。おれはもうやめた」
皆、交互に顔を見交わすが相手を申し出る者がいない。
そばに侍る一塊の女衆の中から、十四、五の少女が立ち上がって前に進み出た。
「差し出がましいとは存じますが、お相手つかまつりまする」
──怖がってだれも津田坊さまのお相手をしないから、わたくしが名乗り出たの。ああいう雰囲気は嫌いです。こそこそと耳打ちをして、顔色を見て様子を探って。堂々としておればよいものを。
「容赦はせぬからな」
「お手並拝見いたしまする」
だが、お聡の攻勢が次第に顕になるにつれ、周囲の顔色があやしくなった。あからさまにお聡に目配せをしたり、つついたり、そっと袖を引いたり、咳払いをして、しきりと止めようとする。
ついに、ご挨拶したいという者がいると取次が現れて伝えに来た。場の誰もがほっとした顔をしたのに、
「これが終わってから参る。待たせておけ」
言下に一蹴されて、場に控えていた旧臣がむうっと気を悪くした顔になる。
津田坊は白石を打ちながらお聡に語り掛けた。
「将棋は戦だ。どう部隊と兵を動かすか。囲碁は覇権争いよ。こうして陣地を取り合う。領地が広ければ豊かさも増す。明智の娘御の意見はどうか」
「政も戦もわかりませぬ。この盤上がすべてにございます。どう駒を差すか、石をどこに打つか、一投に心を込めまする」
「そなたは将棋も嗜むのか?」
石を置きながら津田坊は前髪の間からちらっとお聡の顔を伺った。
「この前、南蛮商人が持ってきた盤を使う遊戯が、将棋にそっくりであった。駒の種類も動きもなお少なく、ゆえに一投の意味が重い」
あまりにも敗色が濃いので、周囲はただの平和な言い回しにも、そのことばの裏に何事かあるのではないかと勘繰っている。
千世保だけが、ニコニコとした笑顔を崩さずに見守っていた。
津田坊は、お聡の顔を覗き込む。
「そなたの手はこうしてぐいぐいやりこめるにも、あまりに落ち着き払った顔ゆえ、氷で出来ておるのかと思うたわ」
ぱらっと碁石を投げ出した。
「やめた。おれの負けだ」
津田坊が傍らの刀を取り上げたとき、鋭い緊張が走って、彼にというより、その気配に斬られたかとお聡は思った。
彼はお聡の目の前の、最後に置いた黒石を取り上げ、袖口に入れる。
「記念にこれをひとつ貰って行こう」
◇
「あの訪問を報告するとき、明智の次女どののことを皆の前で誉めたかもしれぬ」
目をぱちぱちさせている熊千代に、信澄は、少し照れたような顔をした。
「少し顔に出ていたかな。叔父上は敏感だ」
眇を使って気配で嫌悪を見せ、そのくせおそれて視線を避ける。
有岡城は、村重や、岐阜の若手に比較的馴染んでいる村次も抑えることができない、織田家への不満や疑い、不信や反感が渦巻いている。津田坊は冷静に見て取っていた。
明智家の者であるから、失礼があっても荒木とは直接関係がなく、気を使って面倒を引き受けたと取れなくもないが、まっすぐに向かってきた挑むような気配は、津田坊にというよりも荒木家中に向けているようだった。
ついぞ誰かを羨ましいなどと思ったこともなかった彼が、次女をもらうことになるのであろうと言われている左馬之助をはじめて羨む気になった。
じっと話を聞いていた珠子は、熊千代を見上げて言った。
「女は結婚すればその家の子になるの?姉上はもう戻って来られないの?岐阜にずっとお住まいになるの?わたしは熊千代の城に住むのね?」
熊千代は一瞬、不安になった。この坂本城の豪華さと美しさに比べて、雑然とした小さな平城である、勝竜寺に入って、珠子はいったいどう思うのであろう。熊千代は、ひそかにさらに決意を固めた。
一刻も早く偉うならねばならぬ。このままでは間に合わぬ!
「熊千代は岐阜城でお勤めでしょう?姉上はいま、どうしておられるの」
「帰蝶さまのもとにおられる」
信忠の弟、信雄が北畠の家督を相続して田丸城へ移り、信澄は変わらず側近として叔父信長の近くに仕え、政務を支えている。信澄とお聡は、信雄の空いた後の屋敷に入る予定であるようだ。
気落ちした様子の珠子を、一生懸命慰めようと熊千代は寄り添った。
「おれも様子をみて、必ず珠子に知らせるゆえ、そんな顔をするな」
「姉上のことを見ていてね。教えてね?わたしは待っていますゆえ」
珠子は熱心に言い、熊千代は、必ず手紙を送ると約束をした。
◇
岐阜城へ入ったお聡を、帰蝶が迎えた。
「よく来られました。わたくしがすべて整えておりまする」
広い、そして人が多い!
お聡は壮大さに呑まれていた。これほど女人も男子も入り乱れて、あちらへこちらへ歩き回っている城は初めてだ。襖はすべて狩野派の絵で占められ、ところどころに南蛮渡来の器物を置いてある。
「でもここもおそらく仮住まいなのですよ。上様は新しい城を築く場所を探しておいでです」
お聡は、傍らにまだ幼い小さな娘が控えているのに気を取られた。
「これなるは、どなたにございますか?」
「神戸の娘です。鈴与どの。十になる。ここには人質として来ておるのじゃ」
人質、という響きにさっと冷たいものが背中に走る。
「でも大丈夫。神戸どのは上様に臣従を誓っておりまする。三介どのに嫁がれるということで、話がついておるご様子です」
小さな娘はその名前を聞いた途端にがっかりした顔をして肩を落とした。あまりにも気落ちしているため、お聡はかける言葉を失う。
「わたくしと遊ぶ?」
小さかった頃のたまを思い出し、思わずかがんで声をかけると、悲しげな顔が少しほころんだ。
では、三介どのは北畠、三七どのは神戸、そして、七兵衛殿は……?
「七兵衛どのもいずれは畿内に城を頂くでしょう。いずれかの養子となられて、家督を継ぐのです」
あまりにも静かに口にしたため、お聡はその意味を察するまでに少し時間がかかった。少し奇妙な気がする。養子になるならば、娘をもらうが習い。まさか、明智の……。さっと青ざめ、また頬が紅潮したお聡の手に指を置いて、帰蝶はなだめるようにささやいた。
「上様は、磯野員昌どのに目星をつけておられる」
「それもおかしな話でございますな。なぜ、七兵衛どのは磯野の娘をもらわなかったのでございますか」
「さようにはっきりものを言うては困る」
帰蝶は苦笑した。
「そなたの話が先だった故に、あとで思い付きなすったのよ。上様にはよくあることでございます」
騒ぎが起きて、どたどたと誰かが足音荒くこちらへやってくる音がした。
信澄と年の変わらない若者が現れて、語気荒く「はいる!」とだけ言って踏み込んでくる。無礼さ、荒っぽさにお聡は目を見張る。坂本ではありえないことだ。
「三七どのではないか。いかがされました」
「御妻木殿!その娘は、父上が母、坂氏のもとに置くように言われたのではなかったか」
苛々した顔の若者は、額に青筋を立てて喚きたてた。
「決めごとは守らねば、示しがつかぬ!この場でお引渡し願いたい」
「引き渡してどうします」
「母がおらぬと騒いでおる」
「それでそなたが母上の使いにやらされたのか?ご苦労なことよのう」
帰蝶が先ほどまでとは別人のように背筋が伸び、居丈高な声になったのをお聡は見た。あくまで笑みは崩さない。
「こちらに来てもう三日も経つというに、今までおらぬことに気付かぬのだから、面倒を見るのは大変なのであろう。まだ幼いし、他の姫たちとともにここで過ごすのに何の不都合があろう。上様には私からお話いたしまする」
「ですが御妻木どの」
「お下がりなされ!」
お聡はそっと声をかけずにはいられなかった。
「あのう、この新参ものが挨拶をしていたゆえとお伝えくださいませ」
信孝は、穴が開くようにお聡の顔を凝視した。癇性な眉がぴくぴくと動き、決して醜くはないのにひどく歪んで見えた。
「そなたは?父上の新しい側室か?にしては態度が大きいな」
「これなるは、わたくしの姪にて、明智の娘、七兵衛どのの正室となる方。三七殿も無礼な物言いは為されるな」
「七兵衛の!」
そう、ひとこと言った信孝の顔色がみるみる変わって、お聡と自分の妻になる娘とを、代わる代わる見比べているのがわかった。顔色が赤黒く染まって唇が震え、お聡には困惑しかない。恐ろしいと思っていた七兵衛の姿が、まだ残っていた前髪とともに思い出され、早く逢いたいと一心にそう思った。
◇
織田の連枝が並んだ婚礼の式の中、新郎の顔をみてぱっと明るくなった若いお聡の顔に七兵衛も胸を突かれる。信長は至極満足そうに眺めていた。一座の中には信忠の小姓として参加して些事を執り行いながら、自分のことのように目を輝かせる熊千代の顔もあった。
二人きりになって、信澄は妻に、彼らしくもない控えめな調子で聞いた。
「そなたは嫁ぎたい先があったのではないのか」
お聡の顔は輝いていた。そっと手の中に握った石を見せる。
「あったとしても、どこかへ飛んで行ってしまいました。これをもらったその日から」
第十三話 終わり
画像(ルビつき・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。









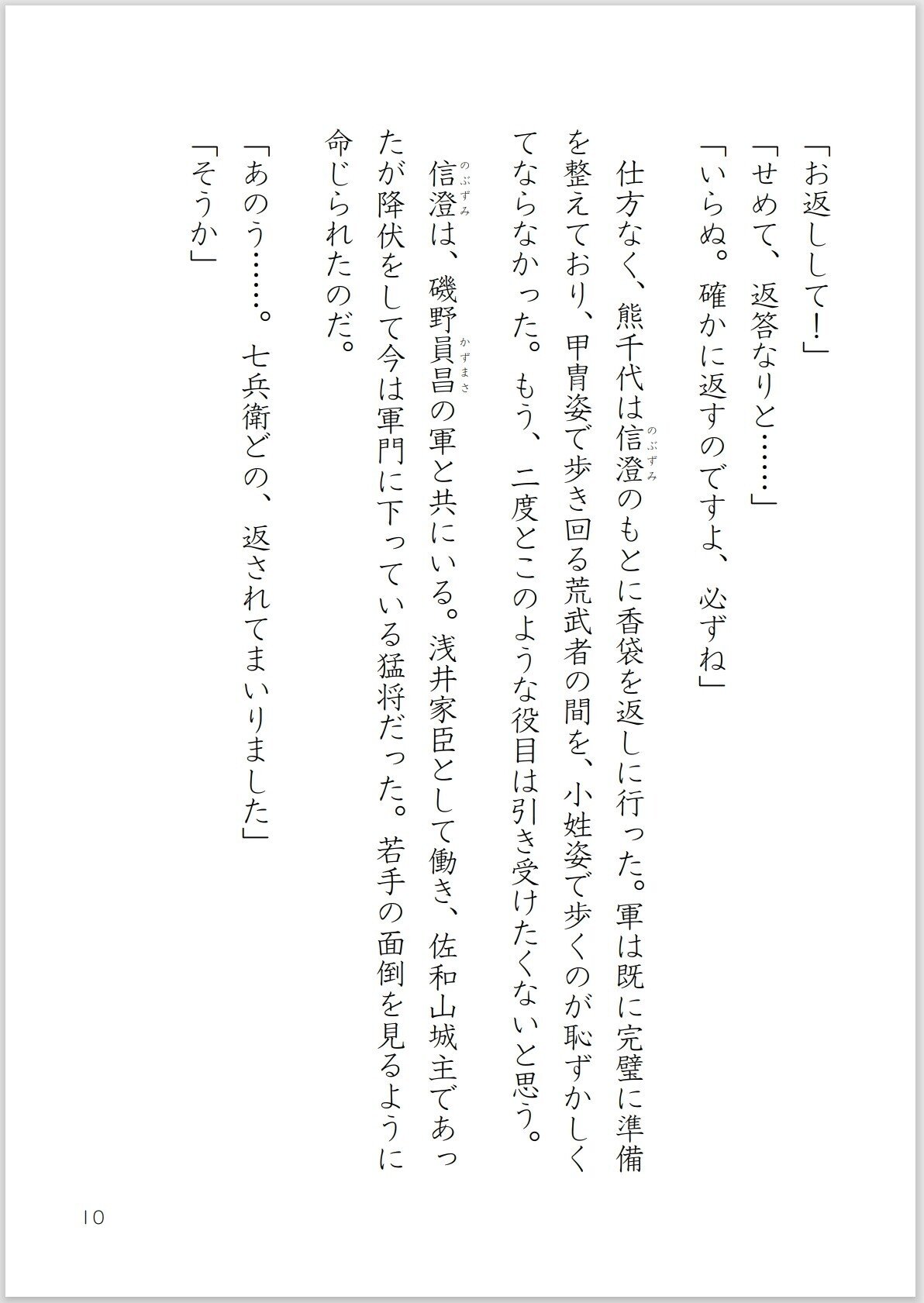







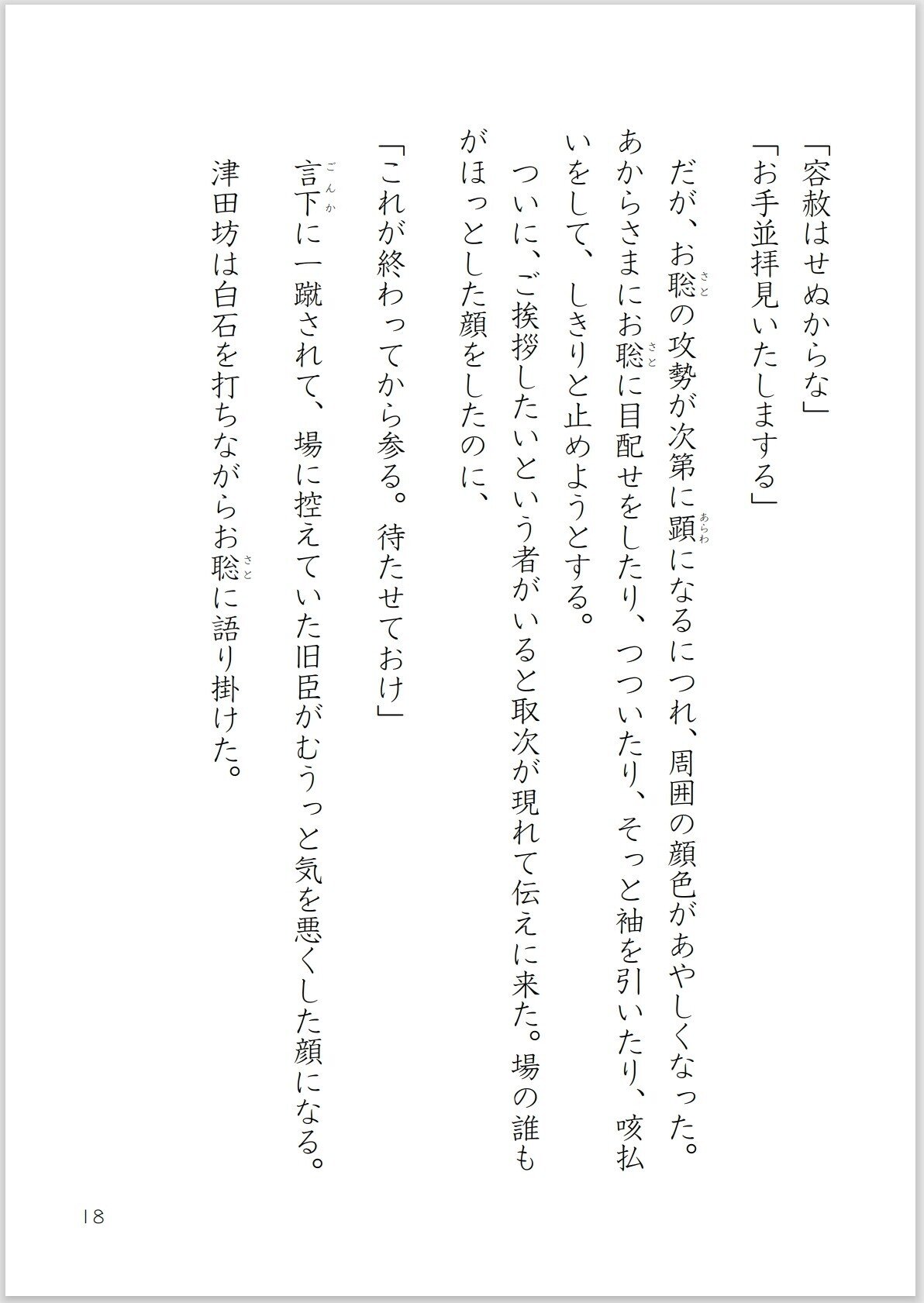












画像。本型。見開き版。









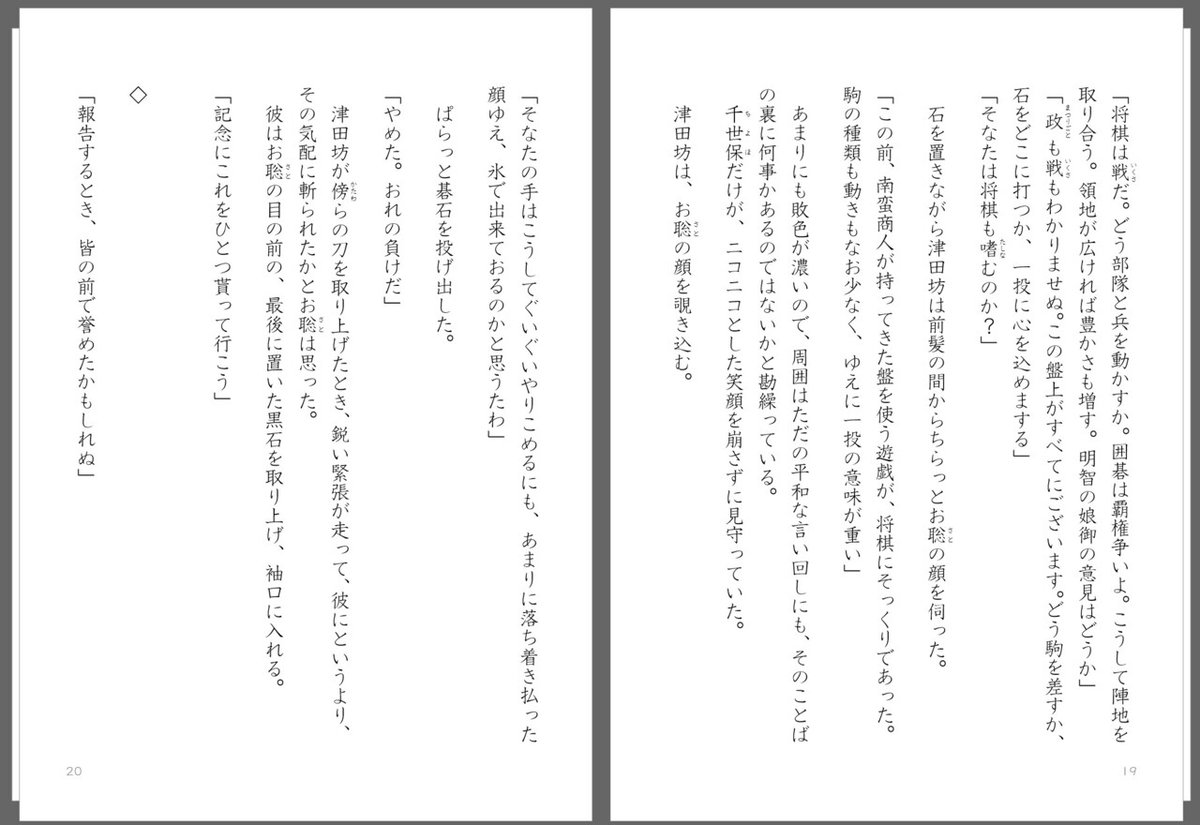





児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
