
鉄砲と癇癪(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 11)
※画像では、「ルビつき縦書き全文」をお読み頂けます。
鉄砲と癇癪
お珠さま、お珠さま。呼び声をよそに、人気のない方へ、ない方へ。珠子がちょろりと入り込んだ奥の間の一室は、床もひやりと冷たく、思わず指先をひっこめてしまいたくなった。部屋の奥には長持が二つ、珠子は少し考えて、蓋のない方の長持に這い込んだ。上からふわりと打掛をかける。
ここは前まで、お岸姉上のお部屋だったのになあ。
「おたまさま、ここじゃな?」
「あれ、おらぬ」
あっちに行ったりこっちに行ったり、珠子は常に探され、彼女自身も何かを探している。自分が求めているのが何なのかよくわからなかったが、今はそれが長姉のお岸であるような気がしている。
──お珠、おいで。
母や次姉のお聡からきついお小言をもらったあとに、いつもお岸はそっと誰にも見られないように珠子を呼んだ。膝に乗せては頬ずりをして撫でて可愛がってくれた。
可愛いたま。わたしのおたま。おまえは何と美しいの。なんと良い匂い。柔らかくてこの上のう優しい抱き心地よ、たまは。
美しいのも、柔らかいのも優しいのも、良い匂いがするのも、皆わたしではのうて姉上のことだ。胸に顔をうずめると、安らかになってまぶたが重くなった。
珠子が十の年を数えるとき、お聡は十四、長姉のお岸は十六となっていた。
荒木の家に嫁いだお岸は病気がちとのことで、お聡がよく姉のもとを訪れている。だが珠子は連れて行ってもらえなかった。会えもしない、文も来ない。姉上はどこかに消えてしまったのだろうか。会えねば死したも同じこと。
荒木の伊丹城から帰ってくるたびに、お聡は固い表情で考えてはため息をついている。
「ぜったい、いやです」
お聡の強い声が聞こえる。
どうしたの?と珠子が訪ねても、
「お珠に言うてもわかるまい!」
突き放すように叫んだお聡だったが、そっとあとで耳打ちをしてくれた。
「母上がわたしをどう思うかと左馬之助にさりげなく尋ねたと言うの。姉上が聞いたら何と思われるか。決して耳に入れてはならぬ。たまもだめよ!何を言われても断るのよ!いい?」
嫁入り先がいやならば戻ってきて、抱っこして欲しいのに。
母上はお身体がよくなくて、父上はすごくお忙しい。わたしには姉上たちだけだ。それも、優しくて甘やかすお岸姉上と、厳しくてお小言ばかりのお聡姉上、どちらもいないとだめなのに。
何かが欠けてしまったこの広く美しい城に、奇妙な寂しさが吹き荒れている。
◇
熊千代は廊下を歩いていた。父の部屋から素っ頓狂な甲高い大きな声が聞こえて来る。
「ご折檻?いやいやいや、細川さまに限ってそんなことはありえないでしょう。こんな教え上手な人はいませんよ」
羽柴藤吉郎だ。
「指摘はいつも的確だし、こっちの理解の程度に合わせてくれるし、辛抱強いし。何より偉そうにしない!いつも気さくで冗談が上手うて、わしゃいつも細川さまに教えを請うのが楽しみなんじゃわ。わしのような成り上がりにとっては、そういう、分け隔てならさんという、どうでも良いようなことが沁みますのでな」
甲高い声をうるさいな、とちょっと顔をしかめて縁側に座る。出立の挨拶をしなければならない。
「信じられない!へえ?やっぱり我が子だと違うんですかね。と、と、と…」
近習が耳打ちで囁いたので、羽柴藤吉郎は手を挙げてひらひらと振り、剽軽に挨拶をした。
小さな男で、顔は皺だらけ、頭は禿げ上がっており後ろにはガチャガチャとした、品も礼儀も何もあったものではない郎党を従えている。野党の群れかと陰口を叩かれることもあるが、彼は軍を率いては抜群に強い。
熊千代は鋭い目で見て、きちんと礼をし丁寧な態度を取った。武将は恰好ではない。実力だ!
「明智殿もな、隔てはなさらん。じゃが、あっちは四角四面に真面目でなあ。冗談が通じぬ。まあ聞いてくだされ、明智殿にお邪魔した時にま~~、あとからあとからひっきりなしに挨拶がやってきおって、息つく暇もない。転職しやすきようにとの配慮とか。さような寛大な心はわしは持てぬなあ。敵に仕官でもされたらかなわんわい。余裕というか、苦労されてるはずじゃが、そんな生まれつきなんですかなあ」
羽柴と明智は熾烈な競争相手と周囲は見る。
本来なら譜代の重臣はいくらもいるはずなのに、尾張出身とはいえ、いかにも成り上がりで身分の低すぎる羽柴、美濃出身とはいえどことなく得体が知れず、京周辺に交わりが深い明智。この二人がそれぞれみるみる出世を遂げて変貌すると同時に、織田家は大きく版図を広げていった。
父は尾張者と話している時に、奇妙に明智家と距離を取るような気配を出すくせがある。相手の望みそうな方向を探るのだ。
長浜一国の城主となったはよいが、わしは作法も知らん、言葉もなっとらん、意味もわからん。たっぷり礼ははずむゆえ、ひとつ師匠となってもらいたい。そう秀吉が言ったとき、飛び付きたいほど嬉しい申し出を、藤孝は軽く見られないよう、偉そうに見えぬよう、丁寧に謝意を述べた。
低い出自から腕一本で成り上がってきた者らしく、秀吉は高位の公家に憧れがあるとみえる。熱心にあれこれとたずねてくるので、藤孝は出来る限り親切にするようにしていた。
「そう言えばな、近衛様が言っておったが、島津の家久どのが京に遊山に来られるらしいですぞ。お伊勢詣りとの事でござるが」
「様子見じゃな」
「然り」
「しっかし、細川殿は西は島津、東は伊達まで、日ノ本どこまでも手紙を送りなさる。使番も大変なことじゃなあ」
頭を掻いて誤魔化し笑いをするが、噂通りの秀吉の情報網にどきりとさせられた。藤孝には、義昭の時代からの、大名と取次をこなす人脈がある。情報を流し、芸事の指南もすれば、向こうの情報も手に入るのだから、この手に付けた諸芸百般、最大限に使うしかない。
この秀吉という男を、周囲は侮りをもって遇している。だが、藤孝は秀吉の容易ならぬ非凡さを見通していた。もともとの家柄や身分、地縁といった後援がないからこそ、ここまで頭角を示すのはそれこそ並々の者ではない。
藤孝は、そのことを信長も十兵衛も十分に理解していると確信していた。
◇
二人の娘に同時に信長が命じた縁談に、坂本城の奧屋敷は一時、騒然となった。だが、お聡は清々しい顔で言う。
「これで話はなくなった、さっぱりじゃ。気が重うてならなかったわ」
たまは疑わしげに姉を見上げた。
「なぜ?姉上は本当は左馬之助がお好きでしょ?」
いつもならカッとなって言い返すお聡が、顔色を曇らせて低い声で続けた。
「姉上を見ているとね、人にはどうしても駄目だっていうことがあるのだってわかるのです。上様のご命令や、父上の決定なら当たり前、仕方ないとみんな言うでしょう。でも、いざその時が訪れてみれば、駄目なものは駄目なんだって、分かるのよ」
お岸は伊丹の城で、やさしい笑顔でいるのに常に蒼白だと言う。
「お珠はいいわ。細川の若君と気が合うてるようだもの、お似合いだと思うわ。わたしは、わからぬ。織田家の連枝さまに嫁ぐならばそれなりの役割も求められよう。津田坊さまは扱いづらく恐ろしいお方と聞くわ。でも……」
お聡は少し口ごもった。 何か考える様子を見せた。
「いいの?」
「仕方ない。やるだけのことです。やってみなければわからぬ。私は姉上やお珠のように特別綺麗というわけでもないし。妻になるとは言ってもね、織田家は上様を見ればわかる、快楽がお好きで側室もたくさん持つでしょう。帰蝶さまはついに御子ができなんだゆえ、ひっそりとお暮しなされておる」
お聡は心得顔で、十四、五の娘がまるで大人のような口のきき方をした。
「たま。結婚とはそういうものなのよ。わたしに求めらるるのは奥向きの采配と織田家での外交じゃ。気をしっかり持っておらねばならぬ」
偉そうに講釈を垂れているのは、どうやら自分に言い聞かせているらしい。それでおさと姉上も駄目たったならば、どうするのだろう、と珠子は考えたが、また怒られるであろうと口にするのを控えた。またふっとお聡の表情が暗くなり、つぶやいた。
「お岸姉上は、死にたいのではなかろうか」
珠子は身体を縮めて、深く身を沈めた長持の中で、額に皺を寄せてずっと考えに考えていた。
答えとは、ひとりにひとつかしら。
正妻は内向きの采配をしっかり取るが勤めでよい妻で?お岸姉上は伊丹でがまんする。お聡姉上は連枝さまに嫁いで役割を果たす。それしかないの、本当に?
嫌ならお岸姉上とて、ただ戻ってきてくれればよいではないか。左馬之助にも誰にも嫁がなくてよい。
珠子はまるで釈然としなかった。
だって左馬之助は平気な顔をしているじゃない。あのときも、今も。
「左馬之助は父上が言うなら何でも応と言うのか?そこで否やと言わぬのか?」
「この左馬之助は殿に仕えて死ぬまで尽くすがつとめでござる」
お聡になじられても、そうきっぱりと言っていた。
母親は体がお辛いのに無理に十五郎を産み、それからずっと臥せっておられる。女の役割なんて、何だ!わたしは完璧にこなすような、よき妻よき母になるよりも、男と肩を並べて戦いたい。熊千代はそんなわたしをどう思うのであろうかな。
穴が開くほど顔を見る、そういう人はよくいたが、大抵ものも言わずに口をあけてそのまま動かない。だけどあの子は違った。
能興行をしていたあの寺で、珠子を見るなりあの子はすごい勢いでこちらへ突進してきた。追いかけっこは楽しかった。庭の奥で顔を合わせると、いきなりきつく問いただした。
「お前は人か魔か、口はきけるのか?」
さらに手を伸ばして肩を掴もうとしてきたのをするりと躱して、気を逸らせようと赤い小さな実をつけた樹の影に入り、実を獲った。
実を受け取ってぐいと鼻を擦ると、頬に血がついた。鼻から血が出ているのではなくて、手についていた血が顔についたのだ。赤い目だった。泥にまみれた中の、鋭い目。この手で人を斬ったのを目の前で見た。これは鬼の子だ。
楽しくなった。
わたしは本物の鬼の子を見ているのだ!
何度も思い出すうちに、思い出は膨らんでやわらかな気持ちがあふれ、胸の中がくすぐったくなって、珠子は声をたてて笑いはじめた。
「御免!」
明智家の玄関にその当の熊千代の声が響き渡り、郎党たち、女房たちがこっそりと陰口を叩いていた。
「でかい声じゃなあ、我が物顔よ」
「胸を張ってとんでもなく威張りくさっておるわ。格下の婿の分際で」
◇
「文選を読みましょうよ!それとも史記がよい?」
あまり気が乗らない様子を見せないように熊千代は元気よく、よし!と答えたが、珠子が手元に持ってきた書を見てほっとした。
おやじが持っていた奴だ。イヤイヤお付き合いしていたけど、やっておいてよかった。
二人で頭をくっつけるようにして床に巻物を広げた。
「字がきれいだ。この写本をしたやつは腕がよい。ここだけ切り取って茶室にかけたい」
「おちゃはよくわからぬの。父上が、熊千代君はたいそうな名手だと言っていました」
天真爛漫に言うこの許婚に、熊千代はおおいに気をよくした。
幼い珠子は、無意識のうちに男性に対する媚や手練手管のようなものを熊千代相手に全開にしてしまっていた。天性の質を発揮してもいい相手が現れたことが嬉しくてしょうがなかった。
そんな仕草も一緒にいるうちに、ただの子供として遊び相手を得た無邪気な嬉しさにとってかわった。
「熊千代は見えないものが見える人なのね」
ふと珠子が言う。
「さっき、藪の中に鳥がおるといって、私はいくら目をこらしてもわかりませんでした。池の奥深くに身をひそめておる主の鯉もすぐ見つけたわ。この字がすごくきれいだというのも、今わかった。言われるまで、中身のことばかり考えていた。この布地ねえ、熊千代が選んでくれたのでしょう。母上が縫ってくれました。わたしはへたなの。縫い目がそろわぬ。不器用なのよ」
「とても……とても、そのう、よく……に、似合うておる!」
「熊千代が見ているもの、選ぶものがわたしはすきじゃ」
家を出入りするようになった、この血の気の多い元気な少年が、明智の城に新しい息吹きを持ち込んだ。
「時間だわ」
珠子は立ち上がる。
「剣と薙刀のお稽古よ」
「何!」
「熊千代うれしそうね。父上が鉄砲撃ちをお見せするとか」
「うん。お約束していたのだ」
◇
鍛錬場にはたくさんの兵がいて、それぞれが年長の者から習っている。
十兵衛は自ら歩き回って、おかしなところがあれば丁寧になおし、構え方の指導をして回っていた。あちこちから声がかかる。
「殿!的を撃ち抜くのを見とうございます。お願いいたしまする!」
用意された的を見て熊千代は驚いた。
遠い。そして小さい。的はただ下げてあるだけではなく、甲冑に詰め物をして杭に立てかけられてあった。すぐにでも実戦に備えるためであろうか。そういえば、この指導の場にちらほら、各家の銃の指南役がいるのが見える。指南役を明智が指南しているのだ。しかしあのような遠い的を撃って致命傷を与えるは至難の業だろう。
明智十兵衛は、一度撃って煙を上げている銃を使い、掃除、火薬に朔杖を使っての弾込めから火縄への点火までをすべて自分でやった。
火ばさみが火皿に落ち、轟音がして火花が散る。皆が駆け寄る中、二十五間(四十五メートル)は離れている的を弾は見事に撃ち抜いていた。
熊千代は舌をまいた。父も武芸全般得意であり、射撃を見たことがあるが、はるかに上回る腕前だ。
一通りの稽古を終えて、十兵衛は熊千代を伴って、珠子のいる女たちの薙刀稽古の方に移動しながら、話してくれた。
「弾の重さ、火薬の量を出来る限り均一にすることが第一でござる。でなくばそのたびごとに弾の飛ぶ道筋が変わってしまいまする。遠くの的であればあるほど、風向きや光の加減も計算に入れねばならぬ」
冷静さ、集中力、計算か。熱心に熊千代はうなずいた。
「早う初陣しとうござる!」
大きく叫んだのを、鉢巻を締め、髪を結い上げた珠子が聞きつけて駆け寄ってきた。
「熊千代はいつ戦に行くの。わたしもゆく!」
十兵衛のたしなめも聞かず、木刀を握り熊千代に向けて構えを取る。
「馬も得意。おたまは強いのよ。ほら!」
浅いが鋭い打ち込みだった。
熊千代はぱっと持っていた木刀で受けて持ち手をおさえた。感情を処理できなくなれば、大爆発することが度々ある熊千代だが、空間認識と動体視力は特にすぐれている。
珠子は目を見張った。
「すごい、熊千代」
内心、大得意で鼻が天まで伸びそうな熊千代だったが、珠子がさっと二度、三度と打ち込みをするのでまた左足をすり合わせてよけ、同時に木刀で勢いを流した。余裕をもってのけた風ではあったが、三度めは渾身の力をこめた激しさに、軽く受け流したように見せるのがやっとだった。珠子は自らの勢いに飲まれることもなく、流されたからといって体勢を崩さずに構え直すので熊千代は感服した。
そこからは何度打ち込んでも同じだった。
珠子はむうっとむくれたようだったが、そのうちに膨れた頬の上の目がみるみる潤んで、大粒の涙が滴り落ち始めた。
「どうして勝てないの?どうして?何が違うの?」
十兵衛が割って入った。
「お珠、落ち着け。熊千代殿はな、小姓組の武術の指南でも抜群の成績なのだ」
困った顔の侍女たちが駆け寄ってきて、手から木刀を受け取ろうとするが、珠子は振り払った。
熊千代だけが、場違いな満面の笑みでいる。あまつさえ、大声で言い放った。
「案じられるな、珠子どの。女は男には勝てぬ。そういう生まれつきなのだ」
これは致命傷で、珠子はわあっと泣き出してしまった。地団駄を踏んで叫ぶ。
「だって背丈だって変わらない!毎日の鍛練も人一倍やっておる!男に負けぬ女武将だって数多おるのに、わたしだって、わたしだって!」
さすがの十兵衛も辟易してちらっと少年の方を見たが、暗に相違してどこまでも上機嫌なので複雑な顔をした。
熊千代の見送りのために廊下を歩きながら、彼らしからぬ、とってつけたような言い訳をする。
「困ったことだ。あのような女で申し訳ござらぬ」
「何とご立派な。珠子どのはまさに強い武将の妻に相応しい。心強き限りでござる!」
また十兵衛は苦笑した。
熊千代が帰り支度をしていると、廊下が騒然となって、城のどこかで何か騒ぎが起きている。右往左往する家臣や侍女たちの間をすりぬけて、赤と白の入り混じった炎のようなものがするすると廊下を抜けてこちらへすごい速さで走ってきた。
「熊千代!熊千代!」
「珠子」
熊千代は手に持っていた草履を玄関先に放り出して廊下を走り戻った。
「どうした?何かあったのか?」
あとを追ってきた乳母が両肩をつかみ、姉のお聡がきつい声を出して、よしなされ!と言う。珠子は、強い力で振り払う。情の強さが透けてみえた。
「みんなが、みんな熊千代がお珠を、嫌いになると言うの。姉上も乳母やも怒るの。熊千代はおたまが嫌いになるか?」
「そんなわけなかろう!」
騒ぎをかき消すほどの大声で、熊千代は力いっぱい怒鳴った。
明智の家はいつも静謐だ。
どの部屋もちりひとつなくゆきとどいている。母も侍女も赤子に追われ、父の汚い屋根まで積み上がった本だの骨董品だのが山とあふれる手狭な勝竜寺城とは大違いだった。
彼女はどこか浮いていた。
皆が静かで礼節を重んじるこの城の空気の中で何をするかわからない無軌道さを持つ珠子はひとり異質だった。周囲が彼女を抑えよう、矯正しようとしているのを感じた。制御しようと苦慮して、しきれずに手を焼いている。あれをしても、これをしても指摘がはいりお小言があり、珠子は息がつける場所がない。同じ年の遊び相手もいなかった。
「強情っぱりでわがままで怒りっぽくてかんしゃくもちで泣いたりわめいたり、そんなの殿方はみんな嫌いなのだそうな。でも、わたしは姉上や母上みたいにはなれぬもの」
熊千代は両手で珠子の細い指をしっかり握った。
「おれは京の下街育ちで暴れていたとき、武芸の指南はだれもしてくれなかった。父母の家に入っておれの武術の鍛錬をさいしょにしたのは誰と思うか?母だ!ものさしでうちかかってくるのだぞ」
珠子は少し泣き止んで、熊千代の言葉を真剣に聞いている。熊千代はまたいちだんと笑顔になり、ことのほか上機嫌でなぐさめた。
「今ならわかるのだが、物差しは刀、ほうきは薙刀であった。わが母は鎧もつけるし刀もふるう。父も勝てぬ。そんな母上が妹の伊也をはじめ城の女どもを集めてやっておる薙刀稽古を見たが、珠子は誰よりも太刀筋がするどかったぞ!負けるのが悔しゅうて泣く、何が悪い?その意気込みこそ頼みとなろう。天地がひっくり返ってもおれが珠子をきらいになろうはずがない」
語気強い熊千代の言葉に、珠子は頬を手の腹でこすり、涙をふいて少し笑った。
幼い言葉の限りを尽くして懸命に訴えながら、熊千代に突然、美への憧れや神の化身としてではなくて、この少女の姿が見えた。何一つない不自由な生活をさせられるはずのこの壮麗な美しい城の中で、類稀な容姿に生まれついた少女が、ひとりで立ってもがいている姿を見た。
天地がひっくり返っても!
もう一度、熊千代は口の中で繰り返し、ぎゅうっと指先を握った。
珠子はもう泣いてはいなかったが、何事も突き詰める執念深さはやはり変わらなかったとみえ、さらに付け加えて訪ねた。
「嫌いにならぬ?お珠のこの顔が潰れて、二目と見られぬ醜い顔になってもか?」
「何を言う!」
熊千代は珠子の手を離し、自分の目を指でさした。
「おれのこの目はな、特別なのだ。上様にも師匠にも言われたぞ。ものを見おぼえておる力は誰にも負けぬ。珠子が誰よりも美しいことはこの目がはっきりと知っている。たとえ容貌が変わろうと、おれには同じ珠子にしか見えぬ。忘れることなど絶対にないし、おれの心が変わることなどありえない」
うなずいた珠子は懐紙で洟をふき、涙を払いながら、廊下を走り戻ろうとして、振り返って付け加えた。
「おたまが熊千代をすきなのは、熊千代がおたまをすきでいてくれるからではありませぬぞ。よいな?」
「おう!」
珠子の泣き叫ぶ金切り声も、渾身の大声で怒鳴った熊千代の声も、坂本城を抜けて琵琶湖まで響き渡っていた。
◇
岐阜城では、来たるべき武田と決戦を前に、側近中の側近のみが集まって、ひそかに軍議を重ねていた。そこには、柴田勝家、河尻秀隆をはじめとして、羽柴秀吉と、明智光秀の姿がある。
「明知城を握られ、高天神を取られた。武田はさらに突き進んで来ましょうぞ」
「どちらもいやな場所だ」
「今は図に乗らせておくのが肝要ぞ。我等が負けることなどあり得ますまい」
明知城の名前を聞いて、信長はことのほか嫌な顔をした。岩村城が落ちたのは三年前のことで、足利義昭の信長討伐の真っ最中、義昭を追放したというのにその時の始末がまだ尾を引いている。信長の五男は武田本国に送られ、叔母のおつやの方は城に入った秋山の妻となっているとの話だった。それが岩村まで行くどころか明知城までも取られ、武田の一歩を許す羽目になった。
信長が歯噛みするのも無理はない。
「秋山め、この信長と縁戚でも結んだつもりか。保険か、人質になるとでも思うたか。わが子を武田に渡し、あまつさえ祝言まで上げるなど、口に出すのも厭わしい。もはや叔母とも肉親とも思わぬわ」
「武田との一戦は不可避。ここで、命運が決まりましょう」
信長が激昂した時には、鬼武者でさえ首をすくめる。そんな時にはいつも明智の静かな声が場を鎮めた。
「真正面からぶつかればわからぬ。若造に率いられているとはいえ、武田の主力部隊の精鋭は無傷で残っておる」
「勝つとすれば、絶対確実に勝たねばなりませぬ。最小限の労力で、もっとも効率的に最大の打撃を与えるように陣を張る必要がありましょう」
河尻が口を出した。
「長篠城からは、救援を求めて矢の催促とか」
「山城一つなど、どうでもよいわ!」
「これまで上様には耐えて頂いていた分、準備は怠りなく進んでおりまする」
秀吉が明るい口調で明智を横から肘でつついた。
「明智どのは鉄砲の名手じゃからなあ」
「いや、いかにわたし一人がうまく撃てたとて、戦にてはものの役に立たぬ。銃の数は多ければ多いほどよい。一度撃った者は後ろへ下がるよう命じ、入れ替わり立ち替りながら撃てる者が撃つがよかろう。弓隊と息を合わせるよう訓練を施しております」
「兵をどう配置すればもっとも効果的に弓と銃が働くか。敵の動きはどう来るか」
「山城に向かうような戦い方は駄目じゃろう。引っ張り出せれば勝機はある」
秀吉の言葉に明智がうなずき、地図上に指をさした。
「徳川殿は、設楽原がよいとの仰せ。三河をようご存じだ。湿地帯が広がり、動きにくいとか」
「それは我等も同じでは?」
秀吉が負けじと指をさす。
「本陣は川に柵を設けて食い止める。それもただの柵ではないぞ。三段に設けてはいかがか。動きにくいのに加えて、土塁も盛り申す。弓と鉄砲隊を潜ませて、力を削ぐだけ削いだ後に各個撃破していく。ただこれは、あちらが突進してきてくれねば話になりませぬ」
信長は低く地を這う声で命じた。
「よいか、ここにいる面々は、妻子、与力、いかに親しい側近にとはいえ、この軍議の内容を決して、一言たりとも漏らしてはならぬ」
さっと皆、一様に頭を下げた。
「対抗策が決まらず、ぐずぐずしていると思わせるのだ。この軍議は極秘中の極秘と心得よ。よいな」
信長が席を立つ瞬間に、ちらと明智の顔を伺ったのを、鋭い秀吉の目は 見逃さなかった。
なるほど。いかにも上様のお気に入りそうな意見よな。そして何事にも周到な明智殿らしいわい。
◇
「さてわしの土塁と柵を三段に設けるすすめが、そなたと半兵衛が練ってくれた策なのだと、大っぴらに言えなくなった」
秀吉は長浜に戻ると、黒田官兵衛にそう言った。
「黒田殿の謁見はこの武田との戦がひと段落するまで待つしかないな。誰にも言うな、とよ。これでお主が誰かに漏らしたら、わしの首はあっという間に 天日干しじゃ」
秀吉はひっくり返って嘆息した。
「ああいうところが田舎武者どもにはないところなのよなあ~。公家の受けもよいわけじゃ」
黒田官兵衛は、ゴロゴロしている秀吉を足を組んで膝に手を置いたまま、見下ろしていた。
「……顔も良いしな」
「上様ひとりに気に入られたとて何事であろうか。明智殿は上様のお気に召すかもしれませぬが、殿は人の心を掴むのが上手い。それこそが最大の利点でござる」
秀吉の目が細くなり、閉じられてゴロリと体が上を向いた。彼の小さな体は大の字になってもさほど幅は取らない。一見、眠ったようにも見えたが、黒田は決してそうではないことをわかっていた。
第十一話 終わり
画像(ルビあり・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。







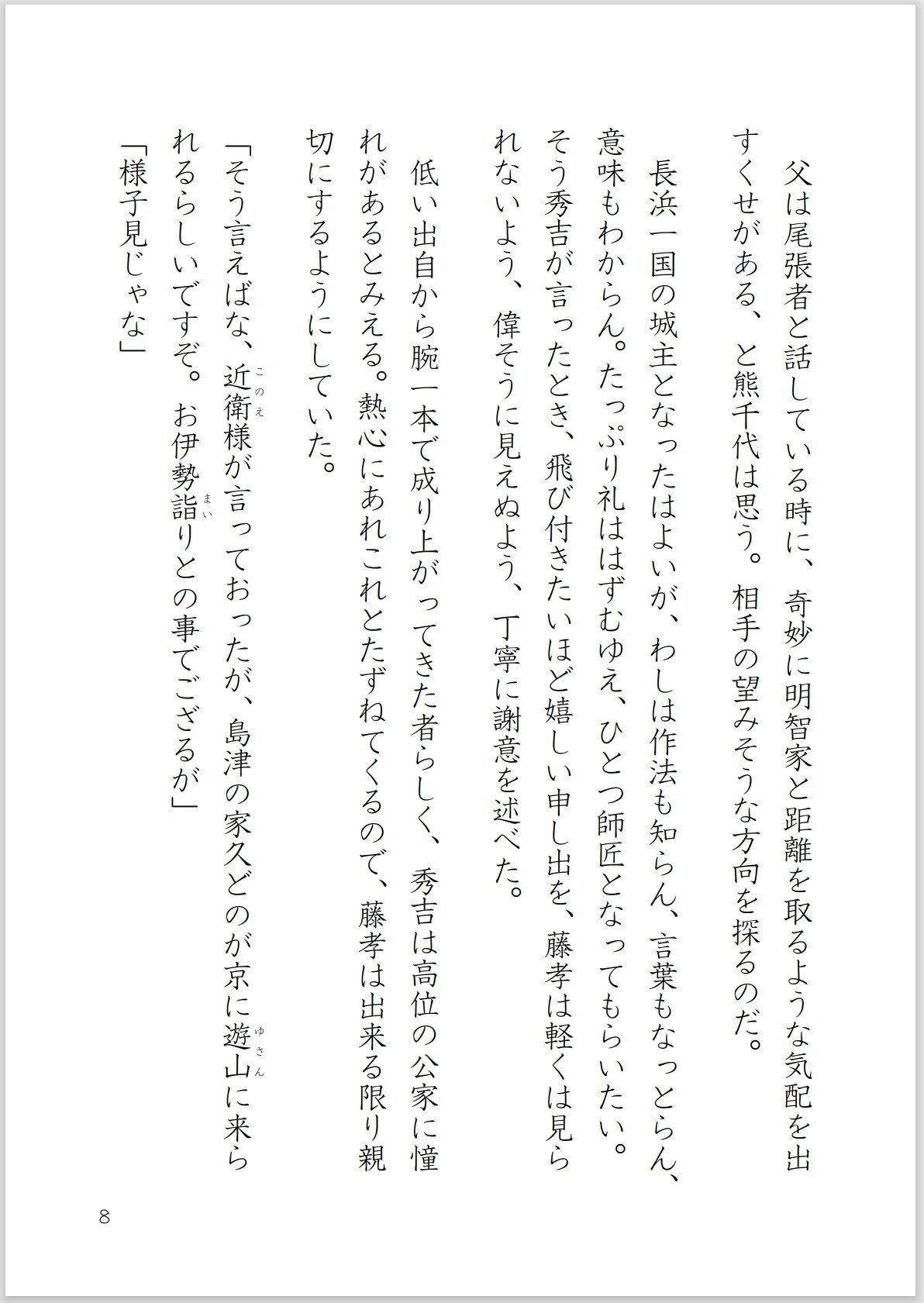






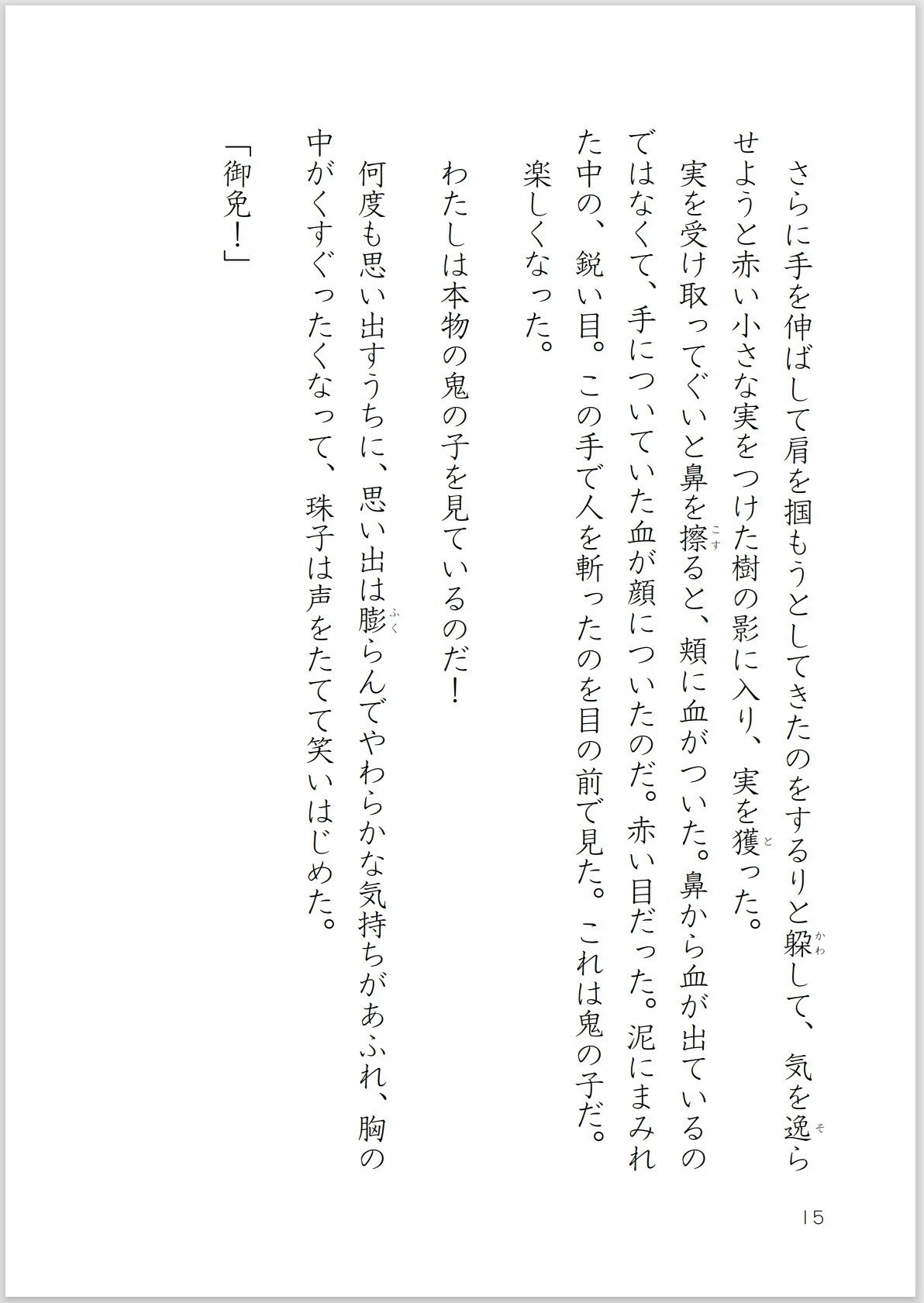























画像。本型。見開き版。








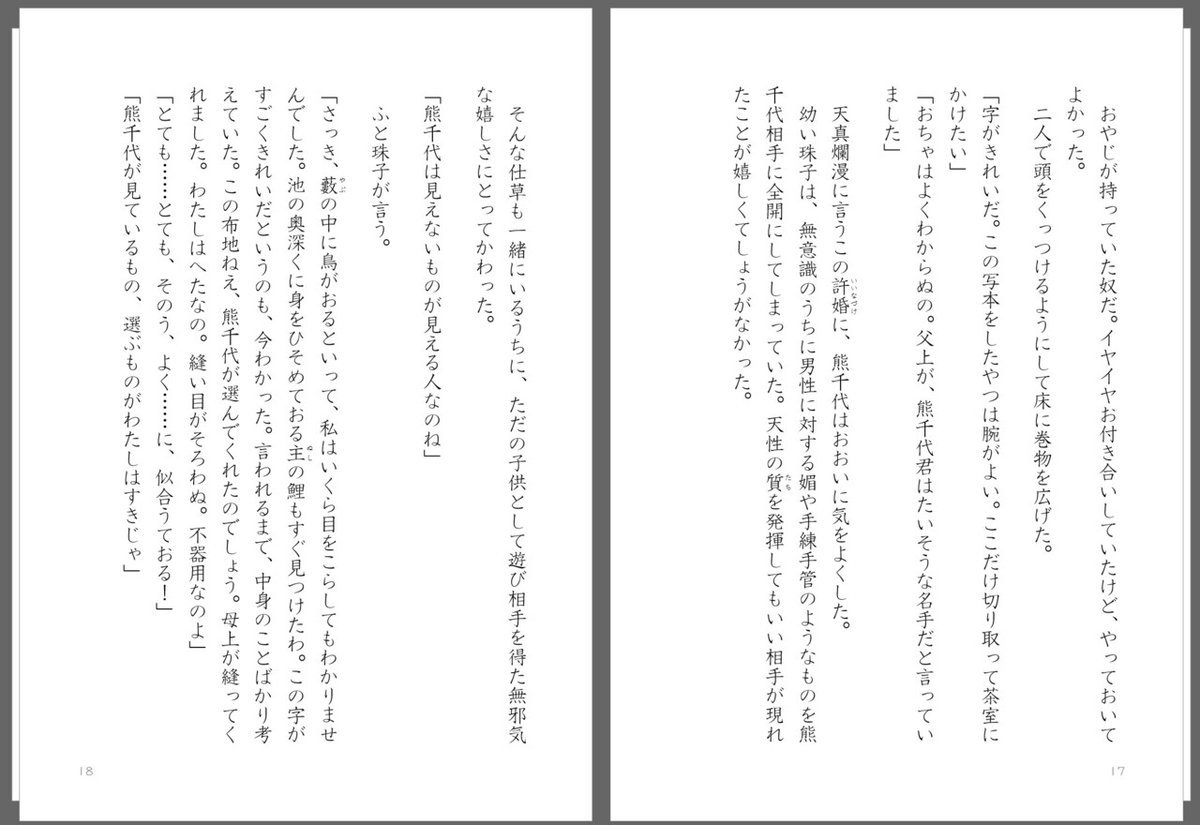










児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
