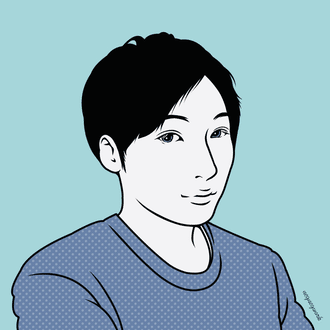むかし苦手だった紫色の文字。
子供のころ、ひらがなには色があった。文字を見て色を感じるみたいな特殊能力とかではなく、イメージとしてなんとなく色が決まっていた。
僕の記憶が正しければ、「あ」は赤色で、「い」は黄色、「う」は水色、「え」はオレンジ色で、「お」は濃いめの青色だったと思う。とにかく、僕にとってのひらがなはカラフルな文字だった。
よく遊んでいた「あいうえお」の書かれた木製の積み木に色が付いていたからなのか。それとも、はじめて文字を覚えたときに色が施されていたからなのか。理由は今でもよく分からない。
ひらがなの中で一番苦手だったのは、「む」という字だった。色というよりも形が苦手で(ちなみに、「む」は濃い紫色をしていた)、「む」の積み木だけはあまり触らないようにしていた。
怖さというよりも、不吉な予感がした。
鬼ヶ島に生息してそうな怖い鬼というより、薄暗い森の中で毒りんごを持ったお婆さんのような、怪しげな雰囲気をまとっていた。だから、むやみやたらに近づいてはいけない。そこに「む」があるだけで、あたりの空気が濁ってしまいそうな存在だった。
当時、その話を両親にしていたが、あまり取り合ってもらえなかった。「む」が苦手というのは、自分だけの感覚かもしれないと、そのときに僕は悟った。
「む」みたいな人もいた。当時よく遊びに行っていた友達のお母さんは、「む」みたいな雰囲気を醸し出していた。いつも優しい人だけれど、心の奥にはダークな生き物を飼っているのではないかと想像した。
彼女が「む」だという理由だけで、僕は警戒した。出された食事も食べる気が起きず、少ししか口にすることができなかった。
成長するとともに、「む」を克服した。嫌いなにんじんが食べられるようになった時のように、苦手を克服した瞬間はなかった。けれど、小学校に入って友達と遊んだり、勉強をしたりしているうちにその感覚は次第に薄れていった。
子どもの頃に経験した言葉にできない感覚は、言葉の習得ともに自然と消えていくものである。シャボン玉のように儚く消えていく。そんな感覚があったことすら忘れてしまう。
最近、街を歩いていると、遠くの方で「む」っぽい女の人が歩いているのが見えた。やがて、僕たちはすれ違った。その瞬間、僕は幼少の頃をふと思い出した。嫌な気持ちはしなかった。
思わず吹き出しそうにもなった。今でも、「む」の感覚がかすかに残っていたとは。
「む」に対する嫌悪感や苦手意識は消えてなくなったけれど、「む」の持つ独特な雰囲気は今でも感じ取ることができた。
こんばんは。雨宮 大和です。今日もnoteを読んでくれてありがとうございます。
さて、文字に色を感じたり、音に色を感じたりする感覚のことを共感覚と言います。これは、赤ちゃんなら誰しも持っているそうです。大人になるにつれて失っていきます。僕はほとんど失ってしまいましたが、「む」の感覚だけは今でも残っています。でも、「む」の感覚は色だけでは説明が難しいんです。「む」という文字には特別な雰囲気があって、あまり近づいていけないんです。なかなか上手く言葉で説明できないんです。みなさんも、子どもの頃に感じていた感覚ってありますか?あれば、ぜひコメントで教えてください。
あと、僕は毎日18時半にnoteを投稿しています。最近は「読書日記」が多くなりましたが、Short Story (短い小説)も書いています。マガジンに過去の作品が収録されているので、お暇があれば読んでみてください。
また明日!!
次に読むなら
noteに文章を書き始めて学んだことを文章にしています。短いので、すぐに読めると思います。ぜひご覧ください。
いいなと思ったら応援しよう!