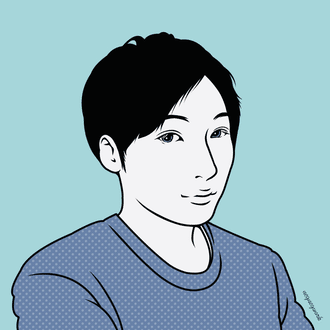超短編小説|白紙の小説
『白紙の小説』という短いお話をお届けします。
おそらく、1分くらいで読めると思います。
わたしが初めて白紙の小説を見たとき、びっくりして言葉も出ませんでした。だって、あまりにも可笑しいんですもの。
少女はそう話すと、おじいさんの方へ顔を向けた。おじいさんは、「まぁ、それはびっくりですね。世の中はお嬢様が思っているよりずっと広いですから、そんな本があっても不思議じゃありません」と言った。
「でもね」
少女はつづけた。
「パラパラとページをめくっていると、1ページだけ文字の書かれたページがあったの。それを読むのがとても好きなの」
不思議な本があるものですね、とおじいさんは微笑みながら答えた。
その日から、白紙の小説は少しずつ色を染めていった。まるで生命が宿ったかのように、一つずつ物語が紡がれていった。毎朝ページが増え、新しい物語が更新する度に、少女はおじいさんと小説の話をした。
小説って面白いわ。自分が体験したことじゃないのに、まるで身近に起きたことのように感じるの。漫画とは違う。物語の舞台は、わたし達の家の近所なのかもしれないわ。小説の作者は、わたし達のために文章を書いてくれたんじゃないかしら。おじいさんは、どう思う?
ある日、少女はそんな質問を投げ掛けると、おじいさんは頬を赤らめて嬉しそうに答えた。
「なかなか面白い質問です。お嬢様がいつも読んでらっしゃる漫画も面白いですが、小説世界はずっと奥深くて、自由なのです。だから、10人いれば10通りの読み方ができる。お嬢様が主人公を自分だと感じたのなら、それが正解なのでございます」
おじいさんは、いつも丁寧に小説について話してくれた。おじいさんと会話をした日々は、今でも鮮明に覚えている。
おじいさんが天国へ旅立ったとき、小説の更新はぱたりと止まった。白紙の本に書かれた物語は、200ページをとうに過ぎていた。それは、もう白紙の小説とは呼べなかった。
その日から、少女は残りのページを自分の字で埋めていった。朝目が覚めると、少女は本を取り出して白紙のページを探す。そして、そこに物語を一つ書く。おじいさんとの日々を思い出しながら、少女は丁寧に言葉を紡いでいった。
〈了〉
雨宮 大和です。最後まで文章を読んでくださり、ありがとうございます。
この小説が良かったら、右下のスキ♡を押してもらえると嬉しいです。次の創作への原動力にもなります。
昨日のnote
読書日記を書きました。主に、村田沙耶香さんの小説『信仰』を紹介しました。村田沙耶香の作品は、日常に潜む不思議な話が多くて好きです。しかも、ただ不思議さが際立っているのではなく、奥深いテーマが眠っていると感じています。
おすすめnote
いいなと思ったら応援しよう!