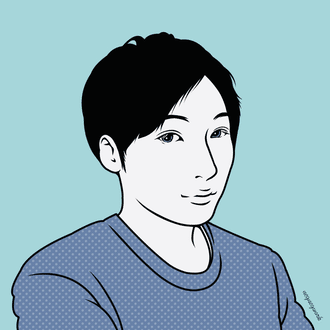Photo by
waratsutsumi
超短編小説|人工知能
『人工知能』という短いお話をお届けします。
おそらく、1分くらいで読めると思います。
人間にそっくりのロボットを買ってから、3年が経った。いわゆる人工知能というもので、姿かたちだけでなく、話し方や考え方まで人間そのものだった。
ロボットの年齢は25才くらいで、背がものすごく高かった。だから、彼と話すとき、わたしはいつも見上げていた。彼はロボットの癖にとても不器用で、掃除や洗濯が苦手だった。けれど、重い荷物を運ぶときに手伝ってくれるのは、男性ロボットを選んで良かったと今は思っている。
人工知能は、どこまでも人間に近かった。
「それがこの商品のセールスポイントなのです。人間らしくていいじゃありませんか」と家電量販店のおじさんが話したとき、わたしは彼を交換しようか迷っていた。
契約の際には、不満があれば3回まで無料で交換できると聞かされていた。だから、交換しようと思えばすぐにできた。より出来の良いロボットに替えてもらえれば、きっと家事は楽になるし自由な時間が生まれるだろう。
けれど、彼の少し気の利かないところも悪くはなかった。迷った末、わたしは販売員のおじさんの言葉で思いとどまった。
わたしは悩みを抱えると、いつも彼に相談した。彼は長い間、わたしのつまらない話を聞いてくれて、最後にいつもこう言った。
「間違ったことをするのが人間だもの」
〈了〉
雨宮 大和です。最後まで文章を読んでくださり、ありがとうございます。
この小説が良かったら、右下のスキ♡を押してもらえると嬉しいです。次の創作への原動力になります!!
昨日のnote
ショートショート(超短編小説)を書きました。
タイトルは、『白紙の小説』です。おそらく、1分くらいで読めると思います。小説の魅力が詰まった物語です。
おすすめnote
いいなと思ったら応援しよう!