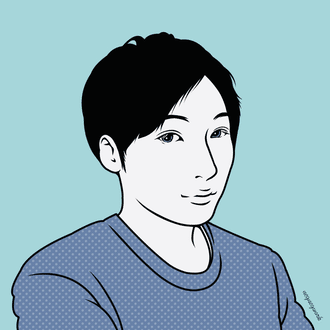生きるために、"物語"を作っていると思う。
書店に足を運ぶと、ずらりと並んだ本棚にはたくさんの小説が置かれている。それは古典から最新作まで、国内の小説から海外の作品まで、多岐にわたっている。この世に存在する物語をすべて読むなんて、物理的に不可能だ。本棚を眺めていると、ついそんなことを考えてしまう。
ところで、聞き慣れた話かもしれないが、以前から若者の活字離れが言われている。インターネットの台頭にともなって、電車の中で本や新聞を読んだりする人は見かけなくなった。その代わり、揃いも揃って皆スマホを片手に何かを見ている。
おそらく、それはネットニュースかSNSの通知だろう。暇を持て余して、好んでもいない文章をただじっと眺めている。それでもいちおう活字を読んでいるのかもしれないが、まともな文章を読む習慣はずっと減ってきているように思う。
新聞を購読している人も減っている。ある調査によると、1世帯あたり部数は約0.6部らしい。かく言う僕も新聞を取っていないので偉そうなことは言えないが、活字を読む習慣が減ってきたことを示すデータと言ってよいだろう。
実際僕のまわりには、新聞はおろか、小説を読んでいる人すらいない。「最近読んだ小説は?」と聞くと、その大半が子供の時に読んだ小説の名前を挙げるくらいだ。彼らは休みの日になると、NetflixやAmazon Primeで映画やドラマを観たり、Switchやプレステでゲームをしている。そう考えると、物語とは無縁の世界で生活を送っているようにも見える。
しかし、僕たちは物語とは切っても切れない関係にある。むしろ、誰しもが毎日の暮らしのなかで自身の物語を作りながら、生きている。僕は、そのことを『生きるとは、自分の物語をつくること』という対談本を読んで気づかされた。
この本は、小説家の小川洋子さんと臨床心理学者の河合隼雄さんの対談が収録されている。そのなかに、「二人のルート」という小川さんによるあとがきがある。そこでは、小川さんが対談を通して、河合先生から学んだことがていねいに綴られている。
小川洋子さんや河合隼雄さんが一貫して言っているのは、生きるには物語が必要だということだ。僕たちは、科学的に正しいことばかりにとらわれて生きているわけではない。自分たちが物事に折り合いをつけるために、自らの物語を作っている。
亡くなった人に対して、「あの世で元気に暮らしているよ」と思うのは、自分たちが納得できる物語を作っているからでしかない。死んだことがある人は生きていないのだから、実際のところ死んだらどうなるかなんて誰も知り得ないからだ。
また、余命宣告を受けた人に治ったら何をしようかと語りかけるのも、お互いが分かち合う物語をつくるためだと思う。医学的には「もう余命わずかなので叶わない」という答えが存在していても、生きている人間が精神を保つためには物語が必要なのだと思う。
あとがきには、小川洋子さんが考える小説のあり方についても語られていた。彼女がまだ二十代のとき、「なぜ小説を書くのですか」とインタビュアーに質問され、上手な答えが思い浮かばず、自分を少しでも大きく見せようと思って答えていた時期があったそうだ。それから、河合隼人氏と出会ったことが大きな転機となり、小説家としての役割を考えるきっかけとなった。
小川さんは、あとがきで自身の小説のあり方を次のように述べている。
ふと私は想像します。名前も知らないどこか遠い町にある、ひっそりとした治療室で、傷つき途方に暮れた誰かが、迷い込んだ迷路の風景を語っている。たった一人うす暗がりに向かい、自分の言葉にどんな意味があるのかも分からないまま、ただ語り続ける。暗がりの奥に身を潜めた私は、それをひたすら書き取ってゆく。誰かの心を支えるために必要なその物語が、間違いなくこの世に存在していることを証明するため、一字一字丁寧に書き留めてゆく。それが、私の小説だ……と。
(『生きるとは、自分の物語をつくること』新潮文庫 p130より引用)
小説家が創り出す物語は大半がフィクションであり、嘘である。しかし、良い小説には血が通っており、まるで現実に起こっているかのような臨場感がある。誰しも日々の暮らしのなかで、"物語"を作っているわけだが、一字一句丁寧に言葉を選びながら書き留めて作り上げていく作品は、それを生業としている小説家のなせる業なのだと思う。
2021.7.1
こんばんは。雨宮大和です。今日から7月に入りましたね。それにしても月日が過ぎるのが早いです。もう夏なんて。たしかに、外へ出ても半袖で十分な季節になってきました。
さて、今日は「僕たちは、"物語"を作っている。」というテーマでお届けしました。いかがでしたでしょうか。最近、小川洋子さんの小説の何冊か読んでいるのですが、小川さんの作品を読んでいると、言葉を一つひとつを丁寧に紡いでいるのがひしひしと伝わってきます。しかも、文章も比較的読みやすいです。興味のある方は、ぜひ書店で手に取ってみてください。個人的には、『密やかな結晶』がオススメです。
次に読むなら.....
過去のオススメ記事を紹介します。
どうしても、掴みきれない言葉がある。それは、掬(すく)いだそうとしても消えてしまう。まるで金魚すくいをやっているかのように、水面の底にあるものを掬い出そうとすると、すぐに破けてしまう。つかみきれないのだ。
いいなと思ったら応援しよう!