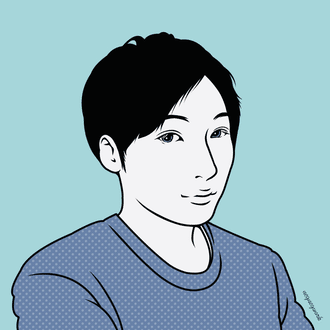はじめてワックスを付けた日。
午後2時。父と一緒に、行きつけの理髪店へ行く。僕は、小学校3年生だった。父の高校の同級生が営んでいたそこは、こぢんまりとしていて、居心地がよかった。
基本的にはマスターとアシスタントの二人しかいないので、美容室にありがちな隣の人の会話が丸聞こえみたいな窮屈さもなかった。
おかげで、僕は注文の仕方を知らずに過ごした。「いつもの感じで」と言えば伝わるし、たいていの場合、その会話すらもなかった。生まれたときから知っているマスターは、僕の髪質のことを誰よりも知り尽くしていたし、僕も任せる以外の方法を知らなかった。
だから、初めて実家を離れて暮らし始めたときに行った美容室は緊張した。自分の髪型のイメージを伝える言葉を持ち合わせていなかったのだ。僕は、髪型について話しているあいだ、カタコトの日本語になった。だから思い通りの髪型にならず、美容室を転々とすることになった。
月に一回の散髪の日。僕はこの時間がたまらなく好きだった。切ってもらっている間は、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんのアニメを見せてもらえたからだ。
髪を切ってもらった後は、父や弟の散髪がはじまる。僕は、その待ち時間も退屈はしなかった。知恵の輪とか子どもが遊べる様々なグッズで時間をつぶした。
お会計の時間がくると、お菓子がもらえた。好きなスナック菓子を一つ選ぶ。いつもサッポロポテトのつぶつぶベジタブルを選んで、帰りの車のなかでバリバリ食べる。
ある日、生まれて初めてワックスをつけることになった。僕が風呂場で髪を洗っているあいだ、泡立ったシャンプーで髪を立てて、ウルトラマンみたいにしていると父が言ったことがきっかけだった。
マスターは、飴玉が入ってそうな銀の缶を持ってきた。ふたを開けて、白い紙粘土みたいな物体を少しだけ手に取る。それを手のひらで広げていく。髪の毛の根元からそっと付けていく。
髪の毛が重力に逆らって上へ上へと立ち上がっていく。大人たちは僕の髪型を見て「かっこいいやん」と絶賛していたが、僕は鏡に写っている人物が自分ではない別人のような気さえした。
僕は家に帰ると、すぐに洗面台に向かった。蛇口をひねり、ゴシゴシと頭を洗った。そして、何事もなかったかのように、毎週通っていた書道教室へ向かった。
雨宮 大和です。今日は、「はじめてワックスを付けた日」について文章を書きました。僕はこの日の出来事をよく覚えています。お風呂場でウルトラマンみたいな髪型にするのは楽しかったのですが、実際にやってみるとそうでもなかったんですよね。懐かしいです。
次に読むなら
僕は小学生のころ、書道教室に通っていました。字の下手な僕にとって、書道は苦行の一つでしたが、通っていたのには理由がありました。それは、書道教室は小さな駄菓子屋だったからです。ひまな時にぜひ記事を読んでみてください。
いいなと思ったら応援しよう!