
歳食っちゃ悪いか?-U.K.SUBS
世間で問題になっている「老害」に真っ向から異を唱えるかのような表題になってしまったが、いい機会である。本題に入るマクラとして、「老害」について思う所を述べてみたい。
誰が言っていたか忘れてしまったが、人は年を取ってくると脳みそが固くなって柔軟な思考が出来なくなり、それが原因で老害になるのだという。一理あると思うが、私の見立てでは、そもそも老害を起こす人間は、若い時から人格上問題を持っているものである。若いときに害を与えないとみなされていたのは、単に運が良かったか、世渡り上手に周囲に対してゴマをすったりして火の粉がかからずにおき、自からも火を起こさずにしているのである。ところがめでたくキャリアを重ね、人の上に立ち、あるいは人の上に立たなくても自分より地位の高い者や年長者といった、自分にとって頭の上がらない者がいなくなるにつれ、わざわざ世渡りのための小刀細工なりゴマすりをしなくても済むようになる。もう他人に気を使う必要はない、いまや我がままのしほうだいだ、となって生来持っていた他人に害を与える要素が前面に噴出してくるようになる。こうして「老害」が発生するようになる。悪口が聞こえてきても、もはや権力を握ったのだから、はたまた怖い奴はいなくなったのだから、クソうるさい御託を並べてくる輩は無視していればよい俺の方が偉いんだからと、「老害」人はふんぞり返る。これが己の権力を、安寧を脅かしそうだとなったときには、今度はその権力を遺憾なく行使して相手を排斥することになる。せっかくこれまで鈴木健二氏の著書よろしく気配りのすすめの精神で頑張ってきたのに、今やそんなものは幽玄の彼方である。では権力を持っていなくって「老害」を起こす者はどうするんだとなると、彼らはすべからく何らかの権力を持ってしまっているのである。例えば職場で彼しかできない技術を持っているとか、彼がいなければどうにもならないとかいったものを持っている時、彼は肩書上何も持っていなくても、ここでは確たる権力を有するのである。周りが勝手に気を使ってくれるから、彼も増長することになる。もっと厄介なのは、自分が老害を起こしていても気付かない場合である。遠巻きに周囲が批判し悪口を言っていても俺には関係ないと能天気に日々過ごしてしまうケースも多いのである。直接忠言したくても、みんな彼の権力が怖くってようようできないから、本人は余計気が付かないのである。会社や学校、その他組織のある所、こうした光景はいたるところで現出していることだと思う。
老害を起こす可能性は、誰にでもある。権力が孕むところ、どこにでも起こりうる。たとえ一対一の関係においてもである。だから俺は大丈夫だとタカを食っていない方がいい。老害は若者であっても起こしうる。より立場の上の者はすべからく「老害」候補者である。
しかしだ。「老害」を起こしている人―「老害」だと忠告をありがたく(!)受けている人―は、あまり無様な境涯に陥らないうちに軌道修正した方がよかろう。知ったことか、俺様は偉いんだ、せっかくとったこのオイシイポジションを手放してたまるか、彼らはそう吠えるだろうが、「老害」者は最期には周囲から見放されるものである。歴史上独裁者と呼ばれた者たちを見てみるがいい。遠藤ミチロウは独裁者の中で唯一、スターリンだけがのうのうと天寿を全うしたと生前語っているが、そのスターリンにしてからが、晩年は哀れの一言に尽きる。常に暗殺者の影におびえ、誰も寄せ付けようとせず、ついには自ら脳梗塞を起こしたのに側近は、何かヘマをやらかしたら自分が消されるからと怯えて何の対処もしてくれず、スターリンは命を落としてしまった。彼もまた周囲から見放されたのと同然の最期を遂げたのである。
こんなことを記したのも、私自身がさんざん「老害」の被害者であり加害者であり続けたからである。被害者であること、加害者であること、この両者でい続けることに我ながら嫌気がさしたのも、職場を離れる一因になった。あのまま働き続けていたら過労死しなかったとしても、私はとてつもなく品性下劣な人間に成り下がっていたにちがいない。
さんざん回り道をしてしまったが、さてやっと本稿の主人公であるU.K.サブスに移る。いや厳密にはリーダーであるチャーリー・ハーパーとするべきであろう。
何故表題のような文言を記したのか。お察しの事であろうが、ハーパー自身の年齢によっている。彼の誕生日は1944年5月25日だから今年(2024年)80歳である。80歳!年齢と心身の若さ活力のほどは必ずしも正比例するとは限らないと思うが、それにしたって80歳でパンク・バンドのリーダーである。いや単にバンドをやっているだけではない。年間200のライヴをこなし、ドスのきいたヴォーカルをぶちかます。人は変わりゆくことが自然であり、変化することがパンクだと大義名分をかざしてどんどん方向転換していった他のパンク連中の中で、時代によりマイナー・チェンジをしつつも結成以来ほぼ50年間にわたり一貫してエッジの立ったロウなロックンロールをつくり続ける。50年と今記したが、ハーパー個人は60年代前半から音楽活動を始めていて、その時点で既にロウな音楽を志向していたというから、60年間「あの音楽」をやっていることになる。それでいて本人にはロックンロールを続けるにあたっての悲壮感は全く感じられないし、自分のキャリアをひけらかしたりふんぞり返ったりする態度もとらない。実にフランクに、飄々とした自由人の趣でロックンロールを楽しんでいる。同じパンクでも、かつてのクラッシュやストラングラーズのようなかたっくるしさはない。今年の2月にいきなり来日してマイケル・モンローのステージに飛び入りしたと思ったら、今度はTOKYOサブス名義でのライヴを日本のみでやってしまう軽やかなノリ。去年U.K.サブスとしてのツアー活動に終止符を打つと宣言し、ああさすがになあと思ったところ、フェスティバルとか小規模なライヴで条件に合うなら今後もやっていくという。さらには春以降も年末近くまでライヴの予定がU.K.サブス名義で入ってもいる。おや、これってツアーではないのか?辞めたのではなかったのか?と突っ込みを入れたくなるのだが、御大いわくステージに立っていないと調子が悪い、これは俺にとっていい運動になっているのだと語っていたりする。世間の評価に関しては、無視してはいないが深刻に受け止めたりもしていない。レジェンドだと言われ持ち上げられることに関しては、笑って受け流すという。[1]その佇まいから「老害」臭は漂ってこない。真に感動に値する姿である。そして、たいした爺さんである。
チャーリー・ハーパーを語るにあたって、重要だと思える事実がある。ひとつは幼少時にサセックスの田舎に引っ越して、そこの中学校の課外活動として農業クラブに所属しリーダーを務めたこと、ひとつは成人してバンド活動と並行して美容師の職を得ていることである。少年時代のクラブ活動でのリーダー経験は組織運営のノウハウを身に付けさせ、その後のバンド活動~U.K.サブスの結成・存続に当たっての大きな糧になったであろうし、美容師としてのスキルは、ロックに代表されるポップ・カルチャーは音楽だけでなく、ファッションも含めた複合的な表現主体であり、ロックを単に音楽としてだけでなく複眼的・俯瞰的視点でとらえることを彼に教えたと思われるのだ。そしていまひとつは、先にも記した、彼の生年月日である。パンク・ロッカーとしての年齢の高さと、そのエキセントリックさばかりが強調されて語られてきたが、ロック史とを照らし合わせて考えると、もっとはるかに重い意味が付与されてくると思えるのである。
あらためて、チャーリー・ハーパーの生年月日を見てみよう。1944年5月25日である。ザ・フーのロジャー・ダルトリーと同い年であり、ピート・タウンゼンドより一つ年上である。ハーパーが幼少期に夢中になった音楽はエルヴィスに代表される50年代のロックンロールであり、60年代初頭には当時のストーンズの追っかけをやり、キンクスやヤードバーズ、マンフレッド・マンのライヴを観まくり、第一期ブリティッシュ・インヴェイジョンのエキスを存分に吸収しつつ、自らも64年には最初のバンドを作り、シーンに参入してきたのである。加えて、70年代初頭にブームを迎えたパブ・ロックの中にも身を置いていたのであって、ハーパーの人生行路はある意味60年代以降のブリティッシュ・ロックの歴史そのものだ。70年代後期にパンク・ロッカーとして改めてデビューした時にはすでにそのキャリアは10年を余裕で超えていた。U.K.サブスの音楽は一貫してロックンロールだが決して一本調子で単線的なそれではない。そこには60~70年代のブリティッシュ・ロックの滋味を湛えている。特に、歌詞面での多彩な切り口は、彼の生きてきた時代の濃密さとイギリスの光と影が複雑に交錯する。サブスの音楽の、最初期から醸し出される深みは、ハーパーの人生経験によるところ大と考えることは不思議なことではない。
Warhead
[Verse 1]
Soldiers of Islam are loading their guns
They're getting ready
But the Russian tanks are mowing them down
They're getting ready
There's children in Africa with tommy guns
Getting ready
While the Islam armies are beckoning on
They're getting ready
[Chorus]
There's a burning sun
And it sets in the western world
But it rises in the east
And pretty soon
It's gonna burn your temples down
[Verse 2]
While the heads of state are having their fun
Are they ready?
We're looking at the world through the barrel of a gun
Are we ready?
And you stand there beating on your little war drum
Are you ready?
And it won't be long before your time has come
Are you ready?
[Chorus] (X2)
[Verse 3]
Warhead, warhead, warhead
Warhead, warhead, warhead
Warhead, warhead, warhead
Warhead, warhead, warhead
Well I don't know what it is but i feel something coming
Stuck in the middle of the Yankees and the Russians
Better get moving guns are getting loaded
Fast to the border where the tanks are a rolling
There's a nation in fear another nation crying
One nation killing and another nation dying
Talk about guns and escalation bye bye planet let alone a nation
U.K.サブスの代表曲とのひとつとしてよく挙げられるのが「ウォーヘッド」である。シングルとしてチャート入りしたことやその演奏のパワフルさの他に、歌詞面での批評性においても、代表曲と呼ばれるにふさわしい。
「ウォーヘッド」がテーマとしているのは、曲が発表された1980年当時、世界を騒然とさせていたイラン―イラク戦争である。これに付随して当時のアメリカ―旧ソ連の対立も織り込む。戦争には名のなき人々ばかりが駆り出され、矢玉に晒される。戦争を起こした国のトップたちは高みの見物にしゃれ込み何の痛みも被らないで、勝手なことをほざいていると歌われる。歌詞の内容は発表から40数年を経た今でも極めて現代的であり、2024年の今、解決を見ていないロシアーウクライナ戦争やイスラム・ガザ地区の紛争をも照射しうる。しかも曲の語り手の目線は下から上を見上げているのであって、いわゆるお偉いさんの、お気楽にして尊大な上から目線的な視点で語られることはない。この、下からの目線で対象を語るのもU.K.サブスの一貫した歌詞作りの特徴である。
U.K.サブス~チャーリー・ハーパーが広く新旧のファンから支持されているのは、こうした下から目線の歌詞作りによるところの他に、歌詞の題材も、決してお堅い政治性だけではないところも重要な要素であろう。時にはあけすけにセックスを歌い、ホームレスや失業者の嘆き節もある。そのどれもが絵空事ではない市井の人々の情けない日常なのである。
ILive in A Car
Well i live in a car
Yeah i live in a car
Well i ain't got no television set or stereo
Cos i live in a car
Don't try to call me up on the telephone
Cos i won't be home
I live in a car
234
Well i live in a car
Yeah i live in a car
Well i ain't got no yard
No i.d.card cos
I live in a car
Cops try to get me
But i don't care
I'm never there
Yeah i live in a car
234
Well I live in a car
Yeah I live in a car
Cops try to get me but I don't care
I'm never there I live in a car
「アイ・リヴ・イン・ア・カー」は1分半くらいの短い曲である。歌詞も極めてシンプルである。そこには語り手の虚飾のない心情が叩きこまれている。「俺はクルマの中で生活してるんだ。家に電話かけたって無駄だよ、身分証明になるモノだってない、警察に睨まれたって知ったことか」ここで効いてくるのが‘a’の単語である。‛the’ではない。俺が寝泊まりしているクルマはこれ一台だけじゃないんだよ、っていう暗喩がさりげなく差し込まれる。「アイ・リヴ・イン・ア・カー」は、元々バンドのツアー中、ライトバンに乗りっぱなしで他に気晴らしになるモノがないことがネタになっているということだが[2]、ひょっとしたらハーパー自身の実体験を歌ったのではなかろうか。というのも、ハーパーは最初の結婚生活に破綻をきたし、家を追い出されて友達の家とか空き家をスクワットしたりとかして、住むところを転々としたと語っているからである。[3]いずれにしても、こういう下から目線の人々の歌の数々があったればこそ、確たる人気を得たのであろう。
かくのごとくパンク・シーンの中で確たる地位を獲得し、ほぼ50年間一度として解散することなく活動を続けてきたU.K.サブスだが、その代償というべきか、呆れるほどのメンバー・チェンジをくりかえしてきた。日本語と英語双方のウィキペディアには歴代メンバーの一覧が掲載されているが、特に英語版は驚くべき人数である。それだけ長きにわたって倦むことなく活動を続けてきた証明でもあるのだが、それにしても、である。御大曰く、80人はいると言われたが、大体40人くらいではないか、ということだが、ではウィキペディアの情報は・・・・。どちらにしても凄い人数ではある。ふつうこれだけのメンバー・チェンジともなれば途中でバンドは解散するところであろう。それをハーパー御大は今日までサブスを存続させてきた。それは市井の人が持つ感情を掬い取りつつロックンロールの原初的高揚感を維持することを、高次のレベルで可能にするメンバーをハーパーが選んできたこと、換言するならハーパーの、オーガナイザーとしての卓抜さにある。さらに、そうしたバンド~ハーパーの方向性を具現化した楽曲を常に生み出し続けえたところにある。サブスの残したアルバムの数の膨大さがそれを証明している。―各タイトルの頭にアルファベット文字を順番に入れていくのをモットーにしていたサブスだが、すでにアルファベット最後のZで始まるタイトルのアルバムは出し終えている。しかもその後でさらにカバー曲集を含め、複数枚出しているのである。断定的な言い方が許されるのであれば、U.K.サブスはチャーリー・ハーパーの思想・信条を具現化させたバンドであり、彼さえいれば他のメンバーは、彼の手足になってくれさえすれば誰でもよいのである。他のメンバーの意向が反映されない―されることがあるならば、ハーパーの意向に沿う形での―いわばハーパーの専制的なバンドになることによって、サブスはほぼ50年を生きながらえてきたのである。

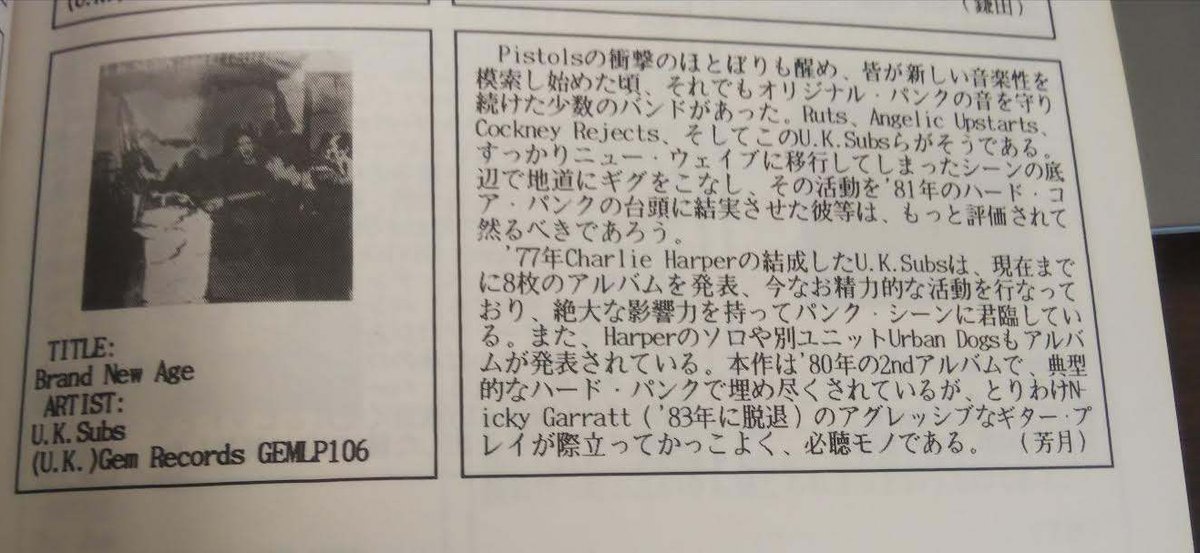
U.K.サブスの名を知ったのは1986年末、以前にも記した雑誌『MUSIC VISION VOL.1』においてである。まだパンクの事はろくすっぽわかっていなかった当時の私にとってこの雑誌で紹介されたバンドのほとんどが未知の存在であったわけだが、一つ一つの写真、文章が私を大いにそそらせるものがあった。U.K.サブスもその一つであった。だがサブスのレコードを、私は学校時代一枚も聴くことはなかった。地元のレコード店にあれば手に入れたかもしれないが、置いてはいなかった。それでは都心のレコード店はというと、それがあったか否か、記憶が全くない。当時は他に欲しいレコードが山のようにあり、ジャンルもパンクだけにとどまってはいられなかった。古本屋巡りもやめられなかった。いくらカネがあっても足りなかった。サブスの、特に初期作品は、思うに当時廃盤でろくに市場に流通していなかったのではないだろうか。結局はより手に入りやすい方からレコードを、としているうちにやがて学校を出て就職、ロックやパンクは聴かなくなって・・・・という経路は、今までさんざん記した。だからサブスの作品については、全く知らないままに過ごしてきたのである。
いや。一曲だけなら、曲としてだけなら、知ってはいた。「ダウン・オンザ・ファーム」か?あれはガンズ・アンド・ローゼズがカバーしたことで有名になった。だが私はガンズをまるっきり好きになれなくて、彼らのカバー・アルバムを聴こうとしなかった。一度ラジオで「ニュー・ローズ」―ダムドの、ですね―を聴いたのだが、余りに大味な感じで、余計に連中のアルバムを聴く気が失せた。だから、ガンズ版「ダウン・オン・ザ・ファーム」は聴くことはなかったのである。ではその一曲とは?「ウォーヘッド」なのである。かのエクスプロイテッドがライヴでカバーしているのをヴィデオで観て、うっすらと認識したのである。ヴィデオは90年代に入ってから買ったのだが、2~3回観ただけである。エクスプロイテッドというバンドにこれまたそれほどの魅力を当時の私は感じなかったからである。ただ、「ウォーヘッド」はそのメロディの端々が頭にうっすらと残った。それだけ優れた楽曲だったという事なのであろう。ただヴィデオの内容全体が余り楽しめず、そのままほったらかしになったまま、いつしかヴィデオは我が家から消えていた。おそらく捨てられてしまったのであろう。
そのまま30数年間、私はU.K.サブスとのかかわりを、全く得ることなく打ち過ぎた。既にパンク・シーンで確たる影響力を確立していたとされるU.K.サブスを、私はずっと知ることはなかった。その状況が一気に変わったのが昨年、2023年の春である。何気なくYouTubeを覗くと、「あなたにぴったりの再生リスト」の中に、U.K.サブスの動画が一本貼りついていた。それはおそらくドイツのテレビ局に2001年頃出演したと思しきライヴ映像であった。
「ふーん、U.K.サブスかあ。そういや聴いたことなかったな」
何の気なしに視聴してみることにした。それが―
「・・・・これは!」仰天した。重量感にスピード感が加わってとんでもない状態である。御大の歌とバックとの阿吽の呼吸、気の世界。30数年間名前は知っていて一度として接してこなかったバンドがこれか。その日はこの映像を10回は観た。そしてサブスの音楽を―ノロクサと―digし始めたのであった。いまさらかよってところだが、出会いなんて人それぞれである。そういうめぐりあわせだったのだ。いやなんであれ、出会えたことは幸福であったとするべきなのだ。
サブスの映像、特に近年のものをいくつか見て改めて思うのは、チャーリー・ハーパーの千両役者ぶりである。そこにいるだけでその場全体を自分の色に染め上げてしまう。元からの資質ももちろんあるのであろうが、ほぼ50年、いや60年ロックンロールをやり続けてきた男だからこそ獲得した希求力というべきか。
私はU.K.サブスをまともに聴き始めてまだ1年たつか経たない案配である。これまでnoteで書き連ねてきた999やバズコックスよりさらに一層ペラペラである。堂々と語れるレベルにまるっきり達していない。だからこうして抜けしゃあしゃあと書き散らすのは、恥さらしといえよう。それでも行為に及んだのは、ちょうどいいタイミングでハーパー御大が来日し、さらにはサブスの諸作品がフィジカルとして発売されるからである。世間がヒートアップしているであろう(?)今の時期が良かろうと、勝手に解釈したのである。サブスのファンならとっくにご存じであろうが、ヴィンテージ期のアルバムをまとめた『ALBUMS 1979-1982』が、さらに2023年のライヴも発売される。[4]作品ならわざわざ大枚(?)はたかなくてもYouTube上で全部ではないが聴けるのだし、ライヴ映像もその内YouTube上にアップされるであろうし、どうしても欲しいなら配信の方が手軽だ、いまやCDにDVDなんて、となるのであろうが、私は古い人間なのである。アーティスト作品はヴァーチャルでは納得しないのである―これも老害とされるのであろうか。ただ、サブスの作品は膨大な数であるから、そのすべてをフォローするのは、今の私にはとても無理である。やはり私はペラペラ野郎なのである。
そのペラペラ野郎の私が今、よく聴いているのはというと、これが自分でも意外だが、初期作品だけではない。近年の作品は80年代の諸作にみられた焦点ボケしたかのような弛緩がなくなり、統一感がとれるようになったと思う。それはやはりガンズが曲を取り上げたのが何よりも大きかったのであろうし、さらには同じ時期に台頭してきたグランジ勢からの後押しもあったからであろう。個人的には目下のラスト作『REVERSE ENGINEERING』(2022年)が好きである。もう新作は出さないと言っておきながら出した曰く付きの作品だが、添え物感はない。もはや安定なサブス節。冒頭の曲だが「Sensei」というタイトルが笑える。ハーパーの奥さんは日本人らしいが、それでこうなったのか。

だが世間一般ではやはりU.K.サブスは70年代パンク、のカテゴリーで語られることが圧倒的であり、あの時代の作品が一際強烈なのもまた事実である。とりわけ最初の3枚、となるのはやむなしか。

ここでは3枚目にして最初のライヴ『CRASH COURSE』を挙げたい。アナログ盤1枚に20曲がぶち込まれ、そのほとんどが2分弱。矢継ぎ早に連打される演奏。ラモーンズの『IT‘S ALIVE』に通ずるカタルシスを味わえる。ハーパーの歌も息切れしないのはさすがだし、ニッキー・ギャレットのレッド・ゾーンを振り切ったギターも文句なしである。なお、初回盤には4曲入りのEP(こちらもライヴ)が付属していたが、今は全曲簡単にYouTubeで聴ける。当時、イギリスではナショナル・チャートで8位まで上がったとされるが、インディーなのによくそこまでと思っていた。ところが所属のGEMレーベルは大手のRⅭAのサブ・レーベルだったのをつい最近知った。デリバリー面ではまるで問題なかったのだね。ところでこのジャケット・デザインだが、エクスプロイテッドの『PUNKS NOT DEAD』とよく似ている。おそらくエクスプロイテッドが真似をしたのであろう。エクスプロイテッドは「ウォーヘッド」をカバーしていることも含め、相当サブスから影響を受けていたにちがいない。

そういえばサブスの音楽を聴いていて、ダムドの連中が、同じパンクのくくりで語られるエクスプロイテッドはコケにしていたのに、そのエクスプロイテッドが好んでカバーしたサブスを賞賛していたのがずっと腑に落ちなかったのだが、ようやく理解できた気がした。サブス~チャーリー・ハーパーの音楽への姿勢は、ダムドらと共通するものを持っているのだ。繰り返しになるが、ロックンロールの持つカッコよさ、いかがわしさ、それらをひっくるめた原初的高揚感を無理なく、自然に素朴に体現するハーパーへのシンパシーなのだ。その、同じシンパシーを、数多の同業者も、ファンも、共有しているのだ。キャプテン・センシブルがかつてサブスのレコーディングに参加したのは、不自然なことでも何でもないのである。ロックンロールって楽しいねー。そんな気持ちを多年にわたって聴く者に味あわせてくれるチャーリー・ハーパーは、だから常にリスペクトされるのである。
今後U.K.サブスはどうなっていくのか、私にはわからないが、チャーリー・ハーパー御大のことである。しぶとく、かつしなやかに活動を続けていくであろう。アルバムだってreverseのまたreverseで出すかもしれない。写真や映像を見た限り、元気いっぱいである。何だかこちらもうれしくなってくるというものだ。
2023年のライヴだが、先の2001年と比べても、御大の声、体型に変化がないのはすごい。やっぱりたいした爺さんである。
[1] ‟U.K. Subs frontman Charlie Harper looks back on four decades at punk's frontline” on the Classic ROCK,5August 2016.
[2]‟Alex Ogg's Unedited History Of The Subs”on the Time and Matter website.
[3] ‟Charlie Harper looks back ”.
[4] DVDのタイトルは『THE LAST WILL TESTAMENT OF U.K.SUBS』訳すと「遺言」・・・・らしくないのだな。
