
アニサキスアレルギーについて 後編
こんにちは、あじさいです。
前回に引き続き、アニサキスアレルギーについての解説です。
(前回はこちら アニサキスアレルギーについて 前編|あじさい@アレルギー専門医)
今回は
・アニサキスアレルギーの診断法
・アニサキスアレルギーと診断された後、どう生活すれば良いのか?
などについて、まとめています。
前回よりも、少し踏み込んだ内容になっています。
気になる方は是非読んでみてください。
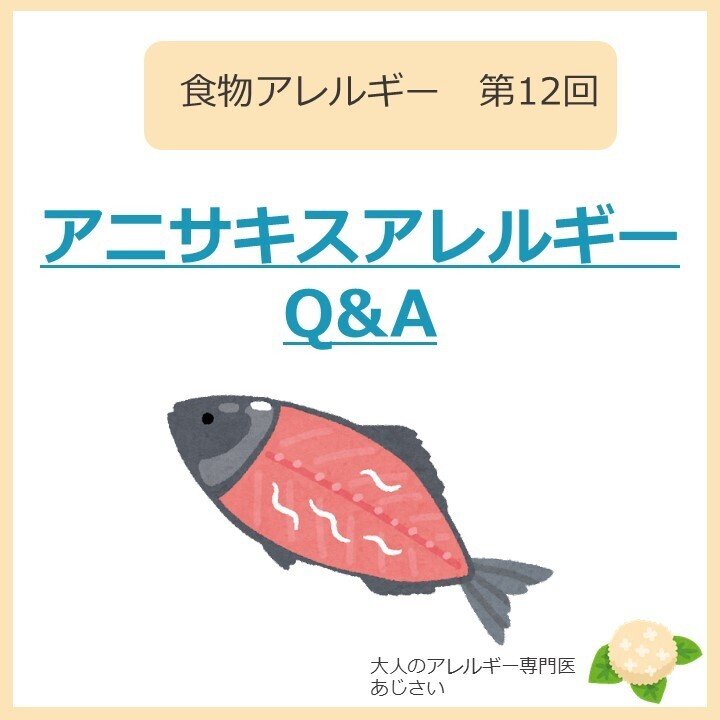

アニサキスIgE陽性の割合が高いことが分かっています
(経皮的に感作している可能性が示唆されています)

アニサキスIgEの上昇が経時的に見られた場合には
「アニサキスアレルギーの可能性が非常に高い」と臨床的に判断することが多いです。



虫体が存在している(死骸が残っている)場合は、反応する可能性があるところです。
そのため、加熱や冷凍などの加工をしても、反応する方はいます。
どこまで食べてよいか、必ず主治医に確認してください。

本来は「いま現在発症しているアニサキスアレルギー」を診断できれば良いのですが……アニサキスのプリックエキスは存在しておりません。
またアニサキスそのものをプリックテストとして用いることや、アニサキスの経口負荷試験も、倫理的・衛生的・医学的な観点から行われていません。
そのため、アニサキスアレルギーの診断は特に難しく、
・原因不明のアナフィラキシー → アニサキスのIgEが上がっている! → アニサキスアレルギーと誤診
・魚アレルギーだと診断されて魚を除去 → 実はアニサキスアレルギー → 魚を除去してもアナフィラキシーを繰り返す……
なんていうことも。
不必要な除去はQOLを下げるばかりか、栄養面でも大きな問題を生じます。
本当にこの診断で正しいのか?
どこまでの除去が必要なのか?
加工食品なら、少しでも食べられる可能性はないか?
いつも色々なことを考えながら診療しています。
まだまだ分かっていないことが多いアニサキスアレルギー。
また新たな情報が出たら、更新していきますね。
今回もお読みいただき、ありがとうございました。
