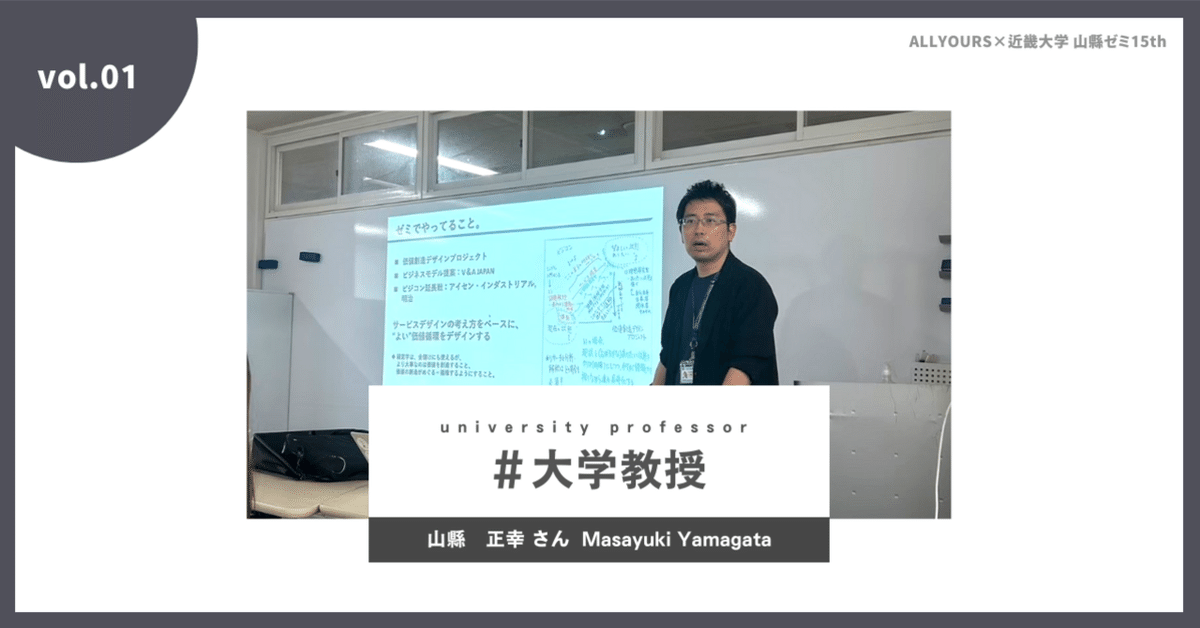
自分の好きに忠実に生きる
皆さんは、自分が望んだ道に進めずに挫折した事や退屈な時間を過ごしてしまった経験はありませんか?
こんにちは、ALL YOURS 2ndです!
私たちが取り上げる、記念すべき1人目は、近畿大学経営学部教授である山縣正幸先生です。
山縣先生のSNSを見ると、ほとんどの投稿が
能とお酒と本のこと。
山縣先生がどのような、人生を歩んできたのかどのような考えをもって、学生に接しているのか深掘りして聞いてみました。
能との出会い
幼少期から祖父が本屋さんだった影響でたくさんの本に囲まれる生活を送っていました。
昔から日本的なものや、歴史が好きでテレビで相撲をよくみたり、袴が履けるからという理由で剣道を始めたりするほどでした。
能との初めての出会いは、小学3年生の時に生駒にある宝山寺に行った時でした。本来は屋外で行われるはずの薪能が雨の影響で屋内で行われました。そのおかげで間近で見ることができ、とても迫力を感じ、興味が湧いたそうです。
人生の転機になる高校、大学時代
詩や和歌に興味を持っていたこともあり、文学部を受験するが失敗。練習で受けていた商学部に進学することになりました。
商学部でしたが、文学に興味があった山縣先生は、単身で教授や大学院生が集まる日本文学科の研究室に入り浸っていたそうです。そのため周りからは「商学部 日本文学科」と呼ばれていました。
行動力がすごい…!
ちなみに、現在でも日本の古典には関心を持っていて、よく能を観に行くだけではなく、国立能楽堂の解説も執筆しているそうです。
この大学時代の経験のおかげで教授や院生と研究を進めることが身近になり、研究することに関心を持ち、院進する事を考えたそうです。
そして、お世話になった学部の教授や歴史が好きだった背景からドイツの経営学史を学び始めました。
サービスデザインに対する思い
ところが、ドイツの経営学史が専門の研究テーマだった山縣先生が現在、なぜゼミで展開しているのはサービスデザインなのか。
そこには、このような背景がありました。
2016年、自身が参加したワークショップでサービスデザインを学んだ時のことです。
色々なステイクホルダーが存在し、それがどのようにつながるのか
この考え方が、自分が研究していたニックリッシュの理論と重なる部分があった。
当時、理論ばかり行なっていてもなと、感じていた時に経営学史の理論研究とサービスデザインという現代の実践面とのつながりがみえた。
これは企業とプロジェクトを行いたいと考えている学生のためになるのではと感じた。
と山縣先生はキラキラとした眼差しでおっしゃられていました。
どんな状況においても自分の関心がある方に忠実に進み続ける事で、新たな関心を見つけることにつながるということですね。
大学教授の 仕事 とは
学生を育てる事はできない。育つのは本人だから。でも育つようにサポートする事はできる。学生が育つことができる環境や機会をつくってあげるのが仕事だよ。
そうおっしゃっていた山縣先生は、メインで担当されている企業行動論などの科目の他にも教養特殊講義C(デザインマインドが拓く価値創造)というバイオコークスを題材とした文理融合型の科目の授業を開講しています。
これは、他学部の学生同士が一緒にワーク形式の授業を取り組む機会になってほしいという願いから始まったそうです。
講義だけではなく、ゼミにおいても学生に面白いと思ってもらえるプロジェクトをしたいと考えているそうです。
山縣先生は、学生に対して制約や指示を与えないようにしているとおっしゃっています。その代わりに学生が相談しにきてくれた際には、視野を広げたり、凝り固まった頭をほぐせるように意識しているそうです。
愛用のハイキックジーンズ
山縣先生のメガネに次ぐトレードマークといえばジーンズだと言えるでしょう。
そんな山縣先生は、ALL YOURSのハイキックジーンズを絶賛しています。
普通のジーンズは履くのがしんどくなるし、かといって大きい物を買えばダボダボになるし…
そんな時にこのハイキックジーンズを初めて履きました。すっと寄り添ってくれるような履き心地のとりこになり、即座に注文したそうです。
最後に撮った写真はなんですか?
山縣先生のディープな私生活をのぞこうと思い、この質問をしてみました。
すると、まさかの一枚が、、

これは、ゼミ終わりに学生が忘れていった物をLINEで教えようと撮った一枚だそうです。
以上、山縣正幸先生の記事でした!
自分が望んだ、学部に進めなくても自分が好きな事に忠実に進み続け、今現在も文学に関わり続ける山縣先生の姿は、とても勇気をもらえます。
自分が望む道に進めなかった時や今置かれている状況に満足していない時こそ、その中で自分の関心がある方に進む。
それが、本当に自分がやりたい事につながるのかもしれません。
編集 ゆうせい
