
クラウドファンディングのために限界肉体労働をすることになった件 #限界シェアハウス文学
35歳手取り2万6千円の独身男性、望月陽光。彼にはVTuber事務所"ライヴラリ"の経営者という顔がある。ライヴラリを現存する事務所として扱うかは諸説ある。彼の事務所はある日、タレントの演者が全員飛んだのである。
飛んだタレントのひとり、通称「もちまる」は歴史的なクラウドファンディングの成功プロジェクトの主役だったが、プロジェクトの終了をまたずに事実上の引退となった。その残ったプロジェクトを完結させるために日々を過ごしている。

そんな彼には大きな悩みがあった。もちまるのクラウドファンディングの予算が毎月80万円ほど減少する状態であるという事実だった。
この危機をどうやって乗り越えるべきか。クラウドファンディングは遅々として進まない。大人の事情によって詳細は伏せるが、参加クリエイターのモチベーションは落ちていた。自分たちの作品を送り届ける場所が崩壊しており、楽曲が今後歌われることはほとんどありえないのだから無理もない。
一方でもちまるが用意した弁護士は「自分たちは積極的な対応をしている」と主張している。とはいえ、クリエイターの面目を取り戻す行動にはまだ至っていない。ただただ調整事項が多すぎる。
大切なのは関係者が気持ちよく動き始めるまでの時を待つ必要があることだ。とはいえ、人間は存在するだけで金がかかる。デザイナーが常駐して、クラウドファンディング最後のイベントを行なうためのスタジオの確保だけでも資金が枯渇することは明白だった。切り詰めた役員報酬分の差額で埋め合わせたとしても焼け石に水である。
そんな悩める望月のもとに偶然にも一通のメールが届く。
その仕事は、東京都内でも最も治安の悪いサイタマ帝国西部のステーション清掃である。過酷だが、高収入が得られる悪くない仕事だった。
「こうなったら、俺達でやるしかない。資金作りを…!」
そして望月は西部ステーションの闇に飛び込む。その背後にアインツベルン城の男たちを引き連れて…。

登場人物
望月陽光(筆者):
タレント0人のVTuber事務所"ライヴラリ"の経営者。どこにでもいる普通の手取り2万6千円の中年男性。もちまるクラウドファンディング成功のために西部ステーションで清掃を行なう。
属性:秩序/悪

がんばるくん(旧名 G藤くん):
ライヴラリで働く事務員にして、アインツベルン城の住民。いつも顔色が悪く、なぜか慌てているマメな性格のドジっ中年。もちまるクラウドファンディングを乗り越えるために西部ステーションの車両清掃に従事する。
属性:秩序/中庸

出だしから事故
「ええ!?作業量が4倍に!?」
思わず筆者は素っ頓狂な声をあげてしまった。
「いやあ誤差だよね、誤差」
とんでもない言葉を口にしたビッグダディ氏は、さほ単純な事務連絡をするような態度だった。
埼玉内装界のドンとされる彼は、筆者の共通の知人の紹介で知り合って西部ステーションの車両清掃を仲介してきた人物である。
当初来た話では、1日4度来る電車のうちの特定の号車を担当して、計4本の清掃を行なうという話である。「1日午前2回、午後2回の特定の時間に西部ステーションに来てくれれば大丈夫です」と書かれたメールもくっきりと手元に残っている。
それが勘違いで1日16本だったというのだ。あまりにも誤差というには異常である。
「わ、私もそう聞いていました」
傍らで困ったようにつぶやくがんばるくんは、いつもに増して顔色が悪い。
仕事量を4倍に増やした男、ビッグダディ氏はというとキョトンとしていた。何をおかしなこといっているのか理解できないという様子である。
1日4回、決まった時間にやってきて掃除をして戻る仕事は、蓋を開ければ1日8時間3人の大人が365日休むことなく出勤するものに変わっていることがどれだけ大変なことか何も理解できていないのである。

「元々10、11、13、14時の清掃というので社長と私+お手伝いで見ていましたが、365日フルタイムは絶対に無理ですね…」
震えるがんばるくんに乗じて、畳み掛けるように続ける。
「本番数日前にいう話じゃないですよ。さすがに手に負えませんよ」
強めの言葉で返したが、流石のビッグダディは何も意に解さない
「なんで始まる前から弱気なのw 頼むよ、なんとかしてくれたら"アレ"の件も融通するから」
彼のいう「アレ」が何かは今回の記事の焦点ではないので敢えて伏せるが、アインツベルン城で転がっている"彼"にとって都合のいい代物だった。この話はまたの機会に語りたい。
問題ない要素がなにひとつ存在しないが、ひとまずはこの誤差を承諾した。せざるをえなかったともいうが。
話を強引にまとめてニコニコしながら帰って行くビッグダディを見ながら、がんばるくんが彼の人間性についてぼやいた
「ビジネスマンとして信用できるレベルじゃない…」
とはいえ、もはややるしかないという事実は変わらない。
クラウドファンディングが停滞することは目に見えているし、その間もがんばるくんたち社員を食わせながらクラウドファンディング予算を可能な限り守る必要があった。
イカれたメンバーを紹介するぜ!
業務開始目前の異常な仕様変更に対して対応するべく、発狂しながらも36時間ほどの時間で首都近郊の知り合いに片っ端から会っていた。
もちろん成果は芳しくない。そもそもすぐに集まってくる人間は労働者として働けるレベルの人間が極めて少ない。ましてや毎朝7時に集合できるほどの社会性を持った人間など皆無だった。
徒労に暮れて帰路を辿っていると、深夜の浅草橋駅の交差点にひとりの男が待ち構えていた。
大福のようなオーラとベイマックス体型。淡いベージュのジャケットを着た中年男性が死んだ魚の眼をして闇の中で嗤っていた。
「モッチー、困ってるね」
友人の大司教である。
「フリーター三銃士を連れてきたぜ。人員で困ってると思ってさ」
サムズアップする大司教の背後から、見知らぬ3人の男が姿を見せる。
目が死んでる若者が前に出る
「介護の専門家、すごいひと」
「うっす、よろしく」
目が爛爛と輝く笑顔の若者が前に出る
「言語の専門家、チェンソーマン(ペンタリンガル)」
「火ってキレイですよね~(うっとり)」
俯いた無表情の若者が前に出る
「受験の専門家、犬口くん(26)」
「IQ110以下の人とは喋りたくありません」
「彼らは東日暮里にある"アフガニスタン大使館"というシェアハウスの関係者です。今は全員働いていないし、犬口くんに至っては大学受験生です」
「受験するほうのプロなんですね」
極めて不安になる要素しかない援軍である
「僕はお給料いらないです〜。ライヴラリ復興のためにつかってください~」チェンソーマンがおどけて宣言した。
「毎朝のめざまし役をやりますね」すごいひとが静かに語る
「IQ110以下の人とは仕事したくありません」犬口くんが憮然とつぶやいた
こうして我々は一団となり、西部ステーションの車両清掃業務が始まることとなったのである。
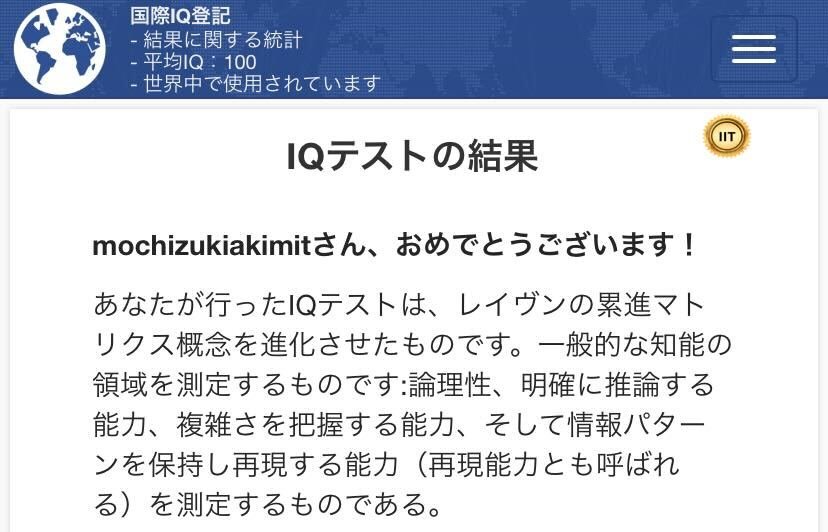
限界!清掃生活
2024年4月1日から西部ステーションの清掃が開始した。清掃の旗印はもちまるクラウドファンディングの成功と、ライヴラリの復興である。御旗の下にアインツベルン城と東日暮里アフガニスタン大使館の両関係者がひとつとなって、掃除機とモップを振り回す…とは都合よくいかなかった。
引継ぎ清掃指導員A「窓は汚れがなくてもしっかり全部拭く!これくらい皆やってるよ!」
がんばるくん「はい!全部拭きます!」
引継ぎ清掃指導員B「アンタ馬鹿ぁ!?無い汚れまで拭いてたら日が暮れるわよ!意味のない作業なんて誰もやったことないんだけどお」
がんばるくん「はい!汚れてる場所だけ拭きます!」
引継ぎ清掃指導員C「アイツらの言うことは真に受けちゃいけないよ。1分後に特急車両が来るから清掃員は背筋を伸ばして並び出迎えるのさ」
がんばるくん「はい!真に受けません!電車を迎えます!」
直立不動で並ぶがんばるくんと清掃助っ人メンバーの眼の前を特急車両が通り過ぎていく。
副駅長「なんだこれは!?清掃のため停車するはずじゃないのか!?」
指導員A・B・C「運転士は狂ってるのか!?こんなこと資料にないぞ!」
がんばるくん「はわわ」

我々が赴任した初日から現場はとてつもなく混乱していた。
一貫しない指導と、駅員たちさえ困惑する予想外の出来事の数々にもちろん我々も大混乱である。
そこにひとりのひとりの老婆が現れた。
「いっひっひ。若いの、苦労してるようだね」
これはいったい、何が起きているのですか。
筆者の問いに老婆は答える
「これは西部ステーションが背負った"呪い"さ」
意味深に老婆は語り出した。
西部ステーションは100年近い歴史を持つ古い鉄道である。その名残か組織内部に整備された業務の仕組みが存在しない。なんとなく慣習でやっている仕事を延長することでなんとなくステーションは成立しているのだという。
そして我々が参加している清掃プロジェクトは100年近いステーションの歴史上文字通り初の駅構内の業務を外部にアウトソーシングした案件だという。そんな組織で歴史上初の引き継ぎに右も左も分からない大人たちが大混乱してトラブルが頻発しているのだ。
「ここではまっすぐした奴ほど心が壊れるのさ。駅長が演説した魅せる清掃なんて忘れて時間通りやってきて手癖で仕事だけすることさね」
それだけ言い残すと老婆は去っていった。
後に知ったことだが、彼女は我々の着任によって任を解かれた先代清掃員だという。
果たして我々は西部ステーションは無事に清掃業を引き継げるのか?
そして100年余りの歴史上初めての相手が我々で良いのか?
事故と困惑の中で我々の清掃生活は幕を開けた。
【清掃開始にあたっての話と違ったこと】
①実際の業務量が誤差約4倍
②清掃ごとの休憩時間に仕事や勉強ができる仕事という触れ込みだったが、実際は待機行動多・事前行動多・現場への移動時間長く不可能
③普通の清掃業だと聞いてきたら、駅長から「魅せる清掃」を頼むといわれる
閑話休題
その後、男たちは清掃に打ち込んだ。
その原動力は時にもちまるクラウドファンディング成功のため、時に不条理な社会への怒りだった。
がんばるくんは清掃の中で「界王拳」を習得して、すべての矛盾した西部ステーションからの要求を4倍速のオーバーワークで処理するとともに顔色をみるみる悪化させていた。
もう一方はというと、清掃助っ人のすごいひとが頭角を現した。朝起きることができない犬口くんを起こして現場まで同伴することが期待されていた彼だが、介護対象の仕事のできなさの結果、『助っ人のサポート要員が一番の現場戦力』という妙な状況になった。

筆者はというと、サイバイマン級の電車にも界王拳を使用するがんばるくんの体調配慮や、犬口くんが現場関係者に行なう無礼へのアフター処理や、彼が突然仕事を欠席したときの穴埋めをしながら黙々と働いた。
時折「なぜクラウドファンディングのために車両清掃をしているのか?」と考えて無性に虚しくなったが、合間に西部ステーションの社員たちの生活の法律トラブルの相談を聞いておじさんやおばちゃんたちとの絆ポイントを高めて誤魔化した。
そんな日々が2週間ほど続いた。続いて欲しかった。
事件は深夜に鳴った清掃メンバーからの1本の電話だった。
「相談事がある」というその電話は不吉な臭いをまとっていた。
スマホの向こうで電話の主は語り始める。
「正直、彼が焼死してくれたらトラブルから開放されてありがたいんですよね。今やっているステーション清掃的には人死には困りますか?」
そして次の混沌が始まるのです…

←番外編その1 第4話(この記事) →第5話(coming soon…)
