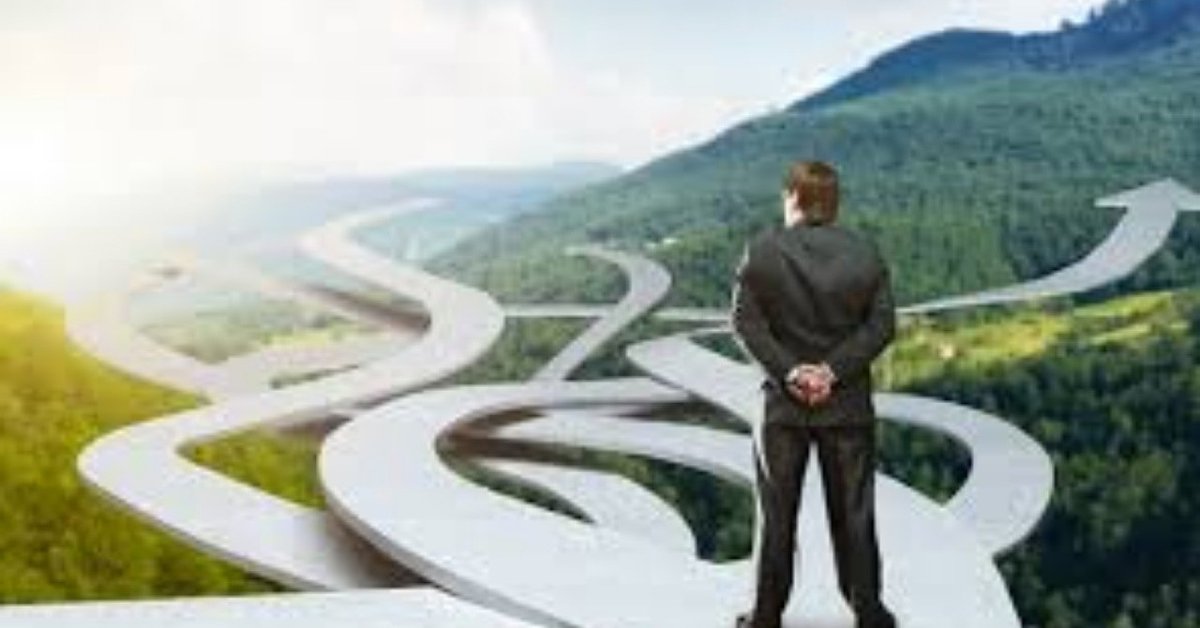
情報リテラシー論(3) 長岡造形大学
こんにちは!あきぽんぬです。
(3)「検索エンジンの変遷と進化」について先々週の授業があったのでレポートにまとめていきたいと思います!
指導教員``よこたん``のサイト→https://yokotashurin.com/
今回は、1088文字のレポートになりました!
さて、まず、検索エンジンとは「情報を検索するシステム」のことです。
変遷とは・・・移り変わること
進化とは・・・物事が一層すぐれたものに発展すること
※いずれの語義もwikipediaを引用しました。
さて、みなさんは、safariやgoogleなどで情報を検索する際にどのようにして画面にある複数の選択肢を見てリンクを選んでいますか?
わたしは自分が気になるキーワード(単語)を探してみています。
スクロールしながら気になる言葉が目に入ったらリンクを見ます。
しかし、余計な広告がスクロールしている内に入ってくると、時間の無駄だと思って気持ちが萎えたりしてしまいますよね。
わたしが言いたいのは、「無駄なく自分の目的に添うものが検索できる検索エンジン」が大衆に受け入れられ、それ以外は衰退していくということです。
結果的に、検索エンジンの二大巨頭であったうちのYahoo!はGoogleに追い越されてしまいました。
なざなら、Yahoo!は無駄な広告(閲覧者が必要としていない情報)が多く目に入ってくるからです。
Googleは検索エンジン最適化SEO(Search Engine Optimization)対策が行われていたことが功を奏しました。
私は、大学で建築環境デザインを学んでいます。
そのため独自の視点として
情報×建築
というテーマで考えていくことにしました。
検索エンジン最適化と建築外観の本質は同じような気がします。
建築外観に収まりきらない情報は「看板」になったり、「照明」になったり、建築自体の「形」になります。
人の多くくるような大型商業施設は人の活発な動きが見えるための透明性があることで、外部の人は建物の情報を得ることができます。
反対に集客を目的としないオフィスや公衆トイレは目立つようなことをする必要がありませんから、外観に表れる建物の情報量は少ないです。
建築も検索エンジンも、いずれにしても使用者、閲覧者の目的に即した情報のあらわし方や情報量にすることで、より良いものを提供できると考えました。
これからの設計課題の際には、建物を「情報」という概念として見る事で、ダイアグラマティック的になり、シンプルで伝わりやすい設計ができるようになるのではないかというのが私の考えです。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
あきぽんぬより
