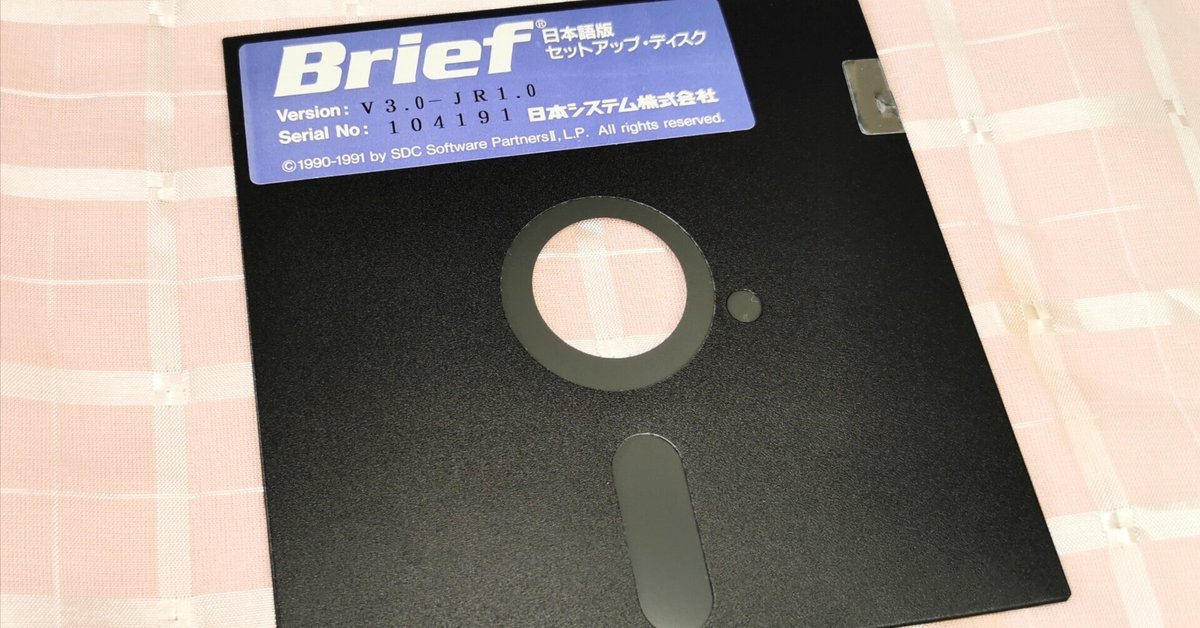
懐かしい記録メディア 「フロッピーディスク」
今はほとんど見かけなくなった記録メディアの「フロッピーディスク」
サイズも、8インチ、5インチ、3.5インチがありました。
世代的には、8インチ→5インチ→3.5インチです。
8インチはLPレコードみたいなとても大きなサイズでした。
残念ながら8インチは手元にないので、今回は5インチと3.5インチを紹介します。
まずは5インチ。

ペラペラな磁気シートで、ホコリや傷がつきやすく、レコードのように取リ扱いは注意が必要でした。
フロッピーディスクにアクセスすると、ガチャガチャというけっこう大きな音がして、あ〜今読み込んだり書き込んだりしてるんだなぁって実感できました。
当時のパソコンには、ハードディスクドライブなどはなく、フロッピーディスクドライブが2台装備しているのが多く、Aドライブにはシステム用のディスクを、Bドライブにはデータ用のディスクをセットして使うのが一般的でした。
今のパソコンで事実上の欠番扱いになっている【A:】と【B:】という名前は、実はフロッピーディスクドライブに割り当てられていたものなんですよ。
今のパソコンのハードディスクドライブがなぜ【C:】から始まっているのかというと、【A:】と【B:】が今は使われなくなったフロッピーディスクドライブに割り当てられていたからなんです。
次は、3.5インチ。

3.5インチは、サイズもコンパクトで、硬いケースに入り、シャッター付きで、ホコリや傷もつきにくく5インチに比べてとても取り扱いが楽になりました。
3.5インチは使ったことのある方も多いと思います。
これは、Windows3.1が記録された3.5インチフロッピーディスクです。数えたら12枚ありました。
当時はOSもアプリケーションソフトも自分でインストールするものでした。

1番目から12番目までのディスクを、画面の指示通りに差し替えてインストールします。
そのためにパソコンの前からなかなか離れられず、けっこう時間もかかりました。
途中で操作を誤ったり、ディスクが読み込めなくなったときは、まだ最初からチャレンジしないといけませんでした。
12枚のうち1枚でもディスクが不良になると、インストールできません。
なので、多くの人はオリジナルのディスクをコピーして、ディスクが不良になったときのために備えてました。
私は不安症なので、コビーを作っても不安で、コピーを2セットは作って使ってましたね。( ̄ー ̄)
今思うととても不便ですが、それがまた楽しみの一つでもあったなぁ〜と思ったりもしてます。
