新居浜に来てみてよかった!と思ってもらうために【別子銅山をガイドする】
マイントピア別子をメインに、別子銅山に関する様々なガイドを一手に引き受ける観光ガイドの会。その対象は、観光客だけにとどまらず、住友企業の社員へ向けたものまで、幅広く引き受けています。
会の発足から13年間、多くの会員たちを率いてきた、会長 石川潔さんにお話を聞いてみました。
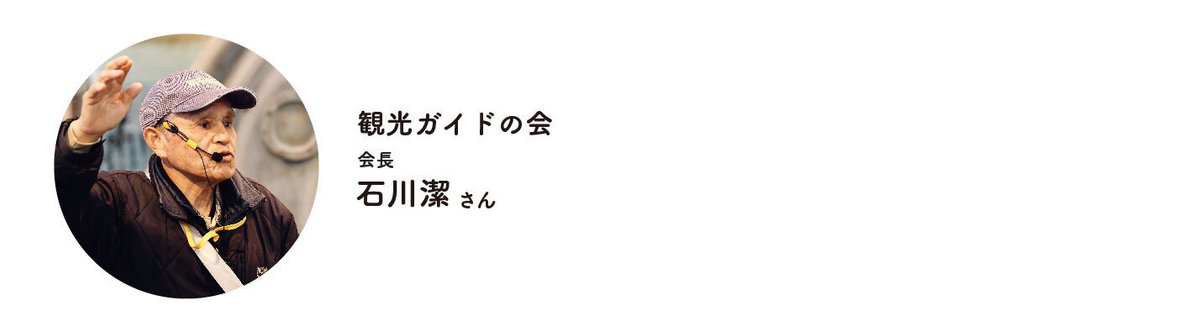
お客さんの質問に答えられない
―銅山のガイドに興味をもったきっかけは何だったのでしょうか?
もともと仕事でタクシー運転手をしていたんです。会社が西原の方にあってね、住友関係の方も多かったからなのか、銅山のことを、色々質問されるんです。
「別子銅山っていつ閉山したの?」とか、「銅山の跡ってどの辺にあるの?」とか、「住友は新居浜発祥なんですか?」とかね。でも、何一つ答えられなくて。
「うわー、せっかく新居浜に来てくれたのに、これはお客さんに失礼なんじゃないか…?」って思いまして。
それで、一念発起して、銅山の勉強をはじめました。そのころ「とっておきの新居浜検定」を知って、テキストを見ながら、図書館で勉強したり。
ここに載っている場所は、全部行ってやろう!って。
四阪島以外は、本当に全部行きましたよ。3年かかりました。
そんな風にしていると、いつのまにかお客さんに満足してもらえる話ができるようになっていましたね。乗車時間の短い間でも「おもしろいね」って喜んでもらえるようになって。
それで、60歳のとき「ボランティアガイドの会」(「観光ガイドの会」の前身)に入ったんです。先輩から「できん思ったら、やめたらえんだから」って誘ってもらって。
閉山後の街の明暗をわけた決断
―銅山を勉強していく中で、特に心を掴まれたものはありますか?
鷲尾勘解治の存在でしょうか。「共存共栄」の理念には、感銘を受けましたね。
この人は、昭和2年に別子銅山の支配人になった人です。当時行われた鉱量調査で、銅をこのまま掘り続けると、あと20年くらいで枯渇する、という調査結果がでましてね。住友は閉山後のことを考え始めるわけです。各事業を大阪に持って帰り、新居浜からは引き上げよう、と。
ところが、鷲尾勘解治が猛反対したんです。これまで270年も、新居浜の人にお世話になっておいて、あまりにも人情がないと。
そして、当時の市長、白石誉二郎らと相談しながら、閉山後も新居浜がやっていけるように、道路をつくったり、港を整備したり、たくさんの取り組みをしたんです。会社のお金で。こんなことをした企業、他にないんじゃないかな。しかもそのせいで、実質、住友をクビになってますからね。
鷲尾勘解治が作った昭和通りには4つの橋がかかっていて、うち2つに「共存橋」「共栄橋」と名が付けられてます。この理念をずっと大事にしようと。
今も海岸沿いには住友の工場が連なっていて、たくさんの人が働いていますよね。閉山後も人口が減らなかった。そんな鉱山跡はめずらしいですよ。
昭和初期に、すでにこんなことを考えていたのかと、驚きます。
あの時、事業がすべて大阪へ引き上げられていたら、今のような新居浜には、絶対になっていないでしょう。このことは、多くの人に知ってもらいたいですね。


↑「共存共栄」の理念を忘れず継承していくため、昭和通りの橋にその名がつけられています。
マイントピア別子」と観光ガイド
―「観光ガイドの会」はどういった経緯で発足したのでしょうか?
「観光ガイドの会」は「ボランティアガイドの会」の後を継ぐ団体です。
「ボランティアガイドの会」は、平成11年に発足した「マイントピアを楽しく育てる会」の部会のひとつで、ほかに物産、お茶、炭焼きなどの部会がありました。
最初は、マイントピアの「トロッコ列車」のガイドをしていたんです。土日だけね。平日は市で雇われた職員さんがされてました。
でね、市の職員さんは、当然ですけど賃金をもらうじゃないですか。一方、我々はボランティア。無給です。でも、我々が担当する土日の方がお客さんが多くて、忙しいわけですよ。だから、だんだんとみんなの不満も溜まっていってね。
有償ボランティアにしてくれって、当時の会長がかけあってくれたりもしたんだけど、結局、平成23年に「マイントピアを楽しく育てる会」は解散して、「ボランティアガイドの会」も解散しました。

現在は水樹奈々さんのアナウンスが流れる
これを継ぐ形で「観光ガイドの会」が生まれたんです。
現在は、マイントピア別子からの依頼を受けて、有償で端出場や東平のガイドを担当しています。
ほかにも、旧広瀬邸や、山田社宅の案内もしていますし、住友グループからの依頼を受けて、社員さんのための、山(旧別子)のガイドも、年間かなりの数を引き受けています。


―マイントピア別子は、別子銅山の跡地のなかでも、気楽に楽しめる貴重な施設ですね。
伊藤武志市長(1984年に市長就任、以降4期務める)の時代に、南部観光開発という「別子銅山の産業遺産を、観光資源にしよう!」という構想があったんです。新居浜には、温泉もないし、これといった観光地もないでしょう。それで、住友の協力を得て、市がお金を出して、端出場と東平を観光施設として整備したんです。
最初は、ロープウェーをつけるという案もあったんですよ。でも「やまじ風」ってあるでしょ。この土地のね。それが、ロープウェーを揺らして危ないから、やめておいた方がいいということになって、ナシになったんですよね。
なんにせよ、この「マイントピア別子」があるから、我々のガイド活動も存在していると言えますね。

わかりやすくおもしろいガイドが好評です

2023年3月に耐震補強工事を終え、内部が公開されるようになった。
ガイドのなり手、定年延長の意外な弊害。
―ガイドにはどのようにしてなるんでしょうか?
年2回、養成講座を開講しています。まずそれを受講してもらって、実際にガイドをやっていけるようになるまでには、半年〜1年くらいはかかりますかね…。
私も何ヶ月か練習しました。自分で車を走らせて、このタイミングでこれをいう、ここに着いたらこれを言うって、そんな練習を何十回と繰り返してね。台本もなく、自然と言葉がでてくるまでには、3〜4年はかかるんじゃないかな。
会のみなさんは、みな60歳以上です。50代以下の方は、お仕事がありますからね。興味があっても、難しいと思います。最近は、定年が伸びたことで、私たちのところにきてくれるときに、70歳を超えている方も多くなりました。
60歳からはじめれば、10年以上できますけど、70歳をすぎてからだと数年が限界ですよね…。東平は斜面や階段が多いですし、旧別子ガイドは登山ですから。体力面で断念される方もいます。ガイドとして活躍できる年数が、だんだんと短くなってきていて、後進の育成もなかなか難しい時代になってきていますね。
対話を大事にすることで、グループが強くなる。
―会を長く続けるために、工夫されていることはありますか?
「対話」を大事にしています。
ふだんはガイドとして、それぞれバラバラに動いていますし、勉強会も年に数回。みんなで一緒にいるタイミングというのが、意外とたくさんはないんですよね。
意思疎通ができてないと、ちょっとした言い方でも「上から目線だ」とか、嫌な風に取ってしまったりするでしょう。でも、ちゃんと関係ができていれば「ふんふん、わかったよ〜」って、できるんですよ。そういう人間関係を築いておくことが大事です。
そのために、毎年1回、必ず研修旅行に行くようにしています。旅行だと1日とか2日を、ずっといっしょに過ごすでしょ。
今年は山口県にある最古の銅山「長登銅山」にいきました。勉強もしつつ、バスでわいわいやって、宴会もして、何人かずついっしょに寝て。ガイドの話もするし、ガイドに関係ない話もいっぱいして、楽しくやるんです。
こういう機会をもつことで、みんなのつながりが深まっていくと感じます。研修旅行の前と後とでは、会の雰囲気が全然違いますからね。

会長に必要なもの=「情熱」&「負けん気」?
―会長として、リーダーシップを発揮し続けていくのは、大変だったのでは?
会長になったのは、ほんとに寝耳に水でした。
「観光ガイドの会」を立ち上げるとき、前身である「ボランティアガイドの会」の会長は、引くことが決まっていて。じゃあ誰が適任かとなったとき、なぜか私に白羽の矢が立ったんです。
当時は、まだ駆け出し。1年半くらいの経験しかなかったんですよ。他にもっと長くやっている先輩がたくさんいましたから。いやいや、なんで私が?って。
私は、銅山で行ってみたいところや知りたいことがたくさんあってね。会のみんなに声をかけて、あそこ行こう、ここ行こうっていろいろ企画してたんです。べつに、誰かにそうしろって言われたわけじゃないんだけど。
そしたら「石川さんは情熱があるね!」って言われて。…私はただ行ってみたかっただけなんですけどね。こういう情熱のある人が、会長のやるのがいいって言うんですよ。
私は、負けん気が強い性格でね。どうせやるのなら、お客さんに楽しんでもらえる、良い会にしたい!って。そんな気持ちだけで13年間やってきました。
最初の3年は、かなり苦労しましたね。活動資金もなかったし。楽しいことよりも、しんどいことの方が多かったかも知れないね…。
4年目からは補助金をいただけるようになったのですが、当時は本当にしんどかったです。実はポケットマネーから活動費を出したりしててね、奥さんにずいぶん怒られましたね…。
そろそろ会長を次の人に譲りたいなって思っています。みんななかなかやりたがらないけど(笑)。これで終わりにするわけにはいかないから。この先も長く続いてほしいからね。
最近は、会の中に「部署」を作って、たとえばイベント立案はこの部署がやってよ、という風に、仕事を分担しています。今年は私が体調をくずしまして、半年ほど、ガイドが一切できなかったんですが、会のみなさんがその分がんばってくれました。そんな風にして、次を担ってくれる人たちが育っていってくれています。心強いですよ。
この先も人に喜ばれるガイドを
―今後、どのような未来を思い描いていますか?
今以上にガイドが増えてくれて、そして、人に喜ばれるガイドをしていってほしいですね。
「人に喜ばれる」という意識がすごく大事なんです。説明する時、一方的に、本を読むみたいに話してはダメ。調子をつけて、ゆっくり喋る。ときどきおもしろいことを言う。歌ったりすることもありますよ。すると、お客さんはけっこう笑ってくれるんです。
楽しい空気になってくると、お客さんからも、質問が飛んでくるようになります。言葉のやりとりが生まれると、さらにお互いが楽しい時間になります。
新居浜に来てみてよかったって思ってもらいたいですよね。
今度南高のユネスコ部と観光ガイドの会がコラボして、修学旅行のガイドをやろうという企画があるんですよ。テレビ局の企画で、そこに市とか、旅行、交通の企業が関わってね。
修学旅行生は中学生でしょ。だから、同じ年代の子がガイドするというのがいいかなと思ったんです。私たちは裏方にまわって、高校生のサポートを担当します。
どんな風にすれば、子どもたちに、わかりやすくたのしく伝えることができるだろうって、いま、色々と思案しているところです。
