
<藍染自由研究①>2番液・3番液・4番液に染力の差はあるのか?
はじめに
昨年から「種蒔きから始める藍染ソウタシエジュエリー」の制作を始めました。素材であるソウタシエコードと呼ばれる幅3mm程の紐を染めるのですが、色が要です。
綺麗に染めるにはどうしたらいいのか?
色のバリエーションを作るのはどうしたらいいのか?
色をコントロールするにはどうしたらいいのか?
っというテーマで研究を進めます。

素材のコードを藍染で染めています。

基本的な「乾燥葉による化学建て」の工程
藍染にはいくつかの染色方法がありますが、私は蓼藍を育て乾燥させ化学建てで藍染をしています。
染色液を作る
鍋に湯を沸かし乾燥葉を入れて煮る。→絞る→液は捨てる(1番液)
この工程はあくやゴミをとるためなので、液は捨てます。鍋に新しい湯+1で絞った葉+ハイドロサルファイトコンク+ソーダ灰を入れて煮る。→絞る→2番液
鍋に新しい湯+2で絞った葉+ハイドロ+ソーダ灰を入れて煮る。
→絞る→3番液
鍋に新しい湯+3で絞った葉+ハイドロ+ソーダ灰を入れて煮る。
→絞る→4番液
2~4番液までを一つの容器に入れ、これが染色液となる。

染める
染色液に染めたいものを入れてる。
空気にあてて酸化させる。
洗う→乾燥
実験課題
お茶や紅茶を入れる場合、最初にいれたお茶が一番濃くてだんだんと薄くなっていきます。
同じように2番液→3番液→4番液とだんだんと薄い液になっているのではないか?
その場合濃い液だけで染めたら、濃い色に染められるのでは?
2番液から4番液までの染力の違いを比べます。
実験方法
必要なもの
木綿布(今回はダ使用するものイソー購入のインド綿) 4枚
蓼藍乾燥葉 20g
湯
ハイドロサルファイトコンク 2g×3回分
ソーダ灰 2g×3回分
鍋、ボウル(染め用)、ザル、生ごみ用ネット、バケツ、箸、ゴム手袋
方法
染めるものを準備。木綿布をよく濡らして絞っておく。
鍋に400mlの湯を沸かし、20gの乾燥葉を入れて煮る。
→ザルに生ごみ用ネットを掛け、中身を濾して絞る。
→液は捨てる(1番液)鍋に新しい湯400ml+1で絞った葉+ハイドロサルファイトコンク2g+ソーダ灰2gを入れて煮る。
→絞る→2番液2番液の実験。
2番液に木綿布①を入れる。
10分放置。
絞ってそのまま酸化させる。
水でよく洗う。
乾燥。
鍋に新しい湯+2で絞った葉+ハイドロ2g+ソーダ灰2gを入れ3番液を作る。
木綿布②で2番液と同じように染める。
鍋に新しい湯+3で絞った葉+ハイドロ2g+ソーダ灰2gを入れ4番液を作る。
木綿布③で2~3番液と同じように染める。
染色前の布、①~③の布の染まり具合を比べる。

結果
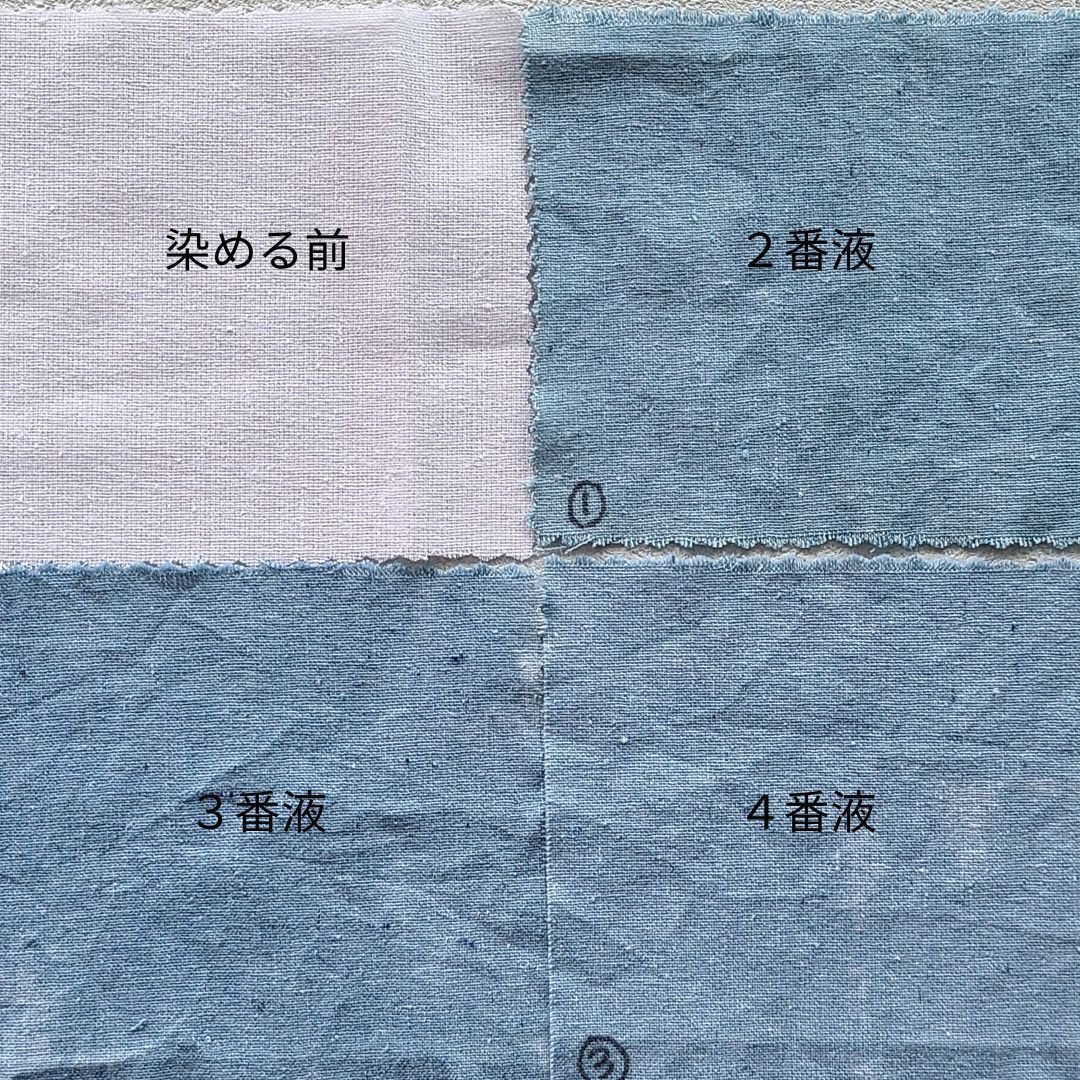
1番濃い色に染まったのは、3番液。
次が2番液で、最後が4番液。
2番液→ややくすみ色。
3番液→明るい青、一番濃い
4番液→やや薄い青色
わかったこと
2番液・3番液・4番液、染力に大きな差がないことがわかりました。
本やインターネット上での情報の通り、2番液+3番液+4番液と全部混ぜて染色液を多くして染めるのが良さそうです。
