
【令和6年王祇祭レポート】④両座の当屋豆腐
2024年2月1日
さて、王祇祭当日です!午後から仕事のお休みをもらい、夜からの本番を前に「当屋豆腐」と言われる黒川名物の行事食、凍み豆腐をいただいてきました。
王祇祭当日は当屋は能舞台などができあがっていて、早朝に王祇様を春日神社からお迎えして、様々な神事などが執り行われます。
そのため、当日の奉納の受付やふるまいなどをするための「脇宿」の家があります。
当屋豆腐は、当屋に奉納をした方に王祇祭当日に振舞われるもの。
当屋への奉納の他に、黒川能保存会経由で申し込んだ方には、受付時に両座の当屋豆腐がふるまわれますので、一般の人はそちらだと当屋豆腐を食べることができますよ!
・・・私は事前に両当屋に奉納済みなので、【国司号】が押されたハガキをもって伺いました。
(補足説明:王祇祭では上座下座、それぞれの最年長の氏子の家が当屋として当てられ、それをつとめる氏子を【当屋頭人】といい、この王祇祭の主人公になります。神様を迎える重要な役で、あらかじめ宮司から国司号(*江戸時代の大名の役職名)が与えられます。)
上座と下座で同じなのは凍み豆腐とごぼうと山椒ですが、味付けや提供方法が各座で違います。

〇上座:温かい凍み豆腐を、山椒・クルミなどで作ったタレをかけて食べる。(濃い目の味付け)

○下座:冷たい凍み豆腐を、酒と醤油で味付けして山椒をきかせた熱い汁につけて食べる。(薄めの味付け)
上座に行ったら、器に盛りつけられて出てきて、たれは小皿に入れて豆腐にたれをつけながらいただきました。
下座に行ったら袋に入ったままお膳が出てきて、熱い汁をそそいでもらい、それにつけて食べるのでした。
あと、違う事と言ったら・・・ごぼうの位置でしょうか。
それは、当屋での王祇様の祀られ方に由来しているとのこと。
上座は横に、下座は縦なんだそう。
今回下座は袋に入っていたので、自分で出して写真撮りましたが笑
次回以降の当屋編で、王祇様の祀られ方がわかるかなーと思います。


どちらの脇宿でも、奉納に来られるお客様でにぎわっていて、饗応のおじさんたちが、杉の樽に入ったいい香りのする熱燗のお酒を注ぎまくり、お酒が飲める人は気を付けないとつぶされるほど飲むことになります笑 みなさんもてなしがすごい!
私は2020年の王祇祭で、つぶされかけたので、学習して甘酒です笑
ビールやお茶などの選択肢はないのです。酒か甘酒か!
ちなみに、私は王祇祭でいただくこの甘酒がどこの甘酒よりも好きです!
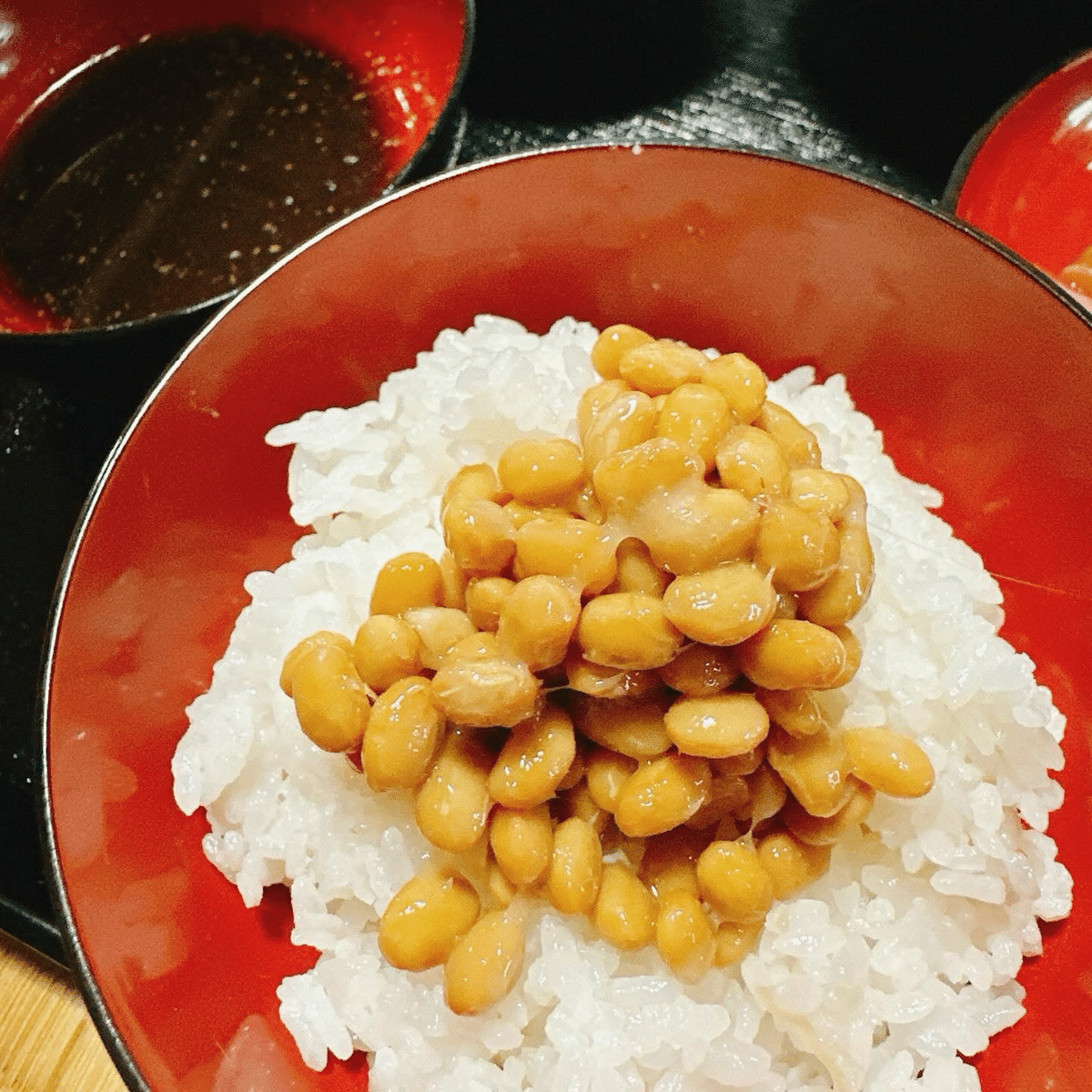


そのほか、お漬物もあるし、お酒を飲まない人にはご飯とガツンと塩の入った納豆をいただいたりします。
個人的に注目したのは、下座のお膳に「きりあえ」があったこと。
きりあえは、王祇祭に欠かせない一品のひとつ。赤こごみ・くるみ・青豆等を細かく刻んだもの。
これ、優しい味で大好きなので、嬉しかった!
・・・・これら、王祇祭全般のお料理ですが、当屋の人たちの他に、祭事に関わるすべての仕事は、「世帯持ち」と呼ばれる4人の男女のチームの責任で進められます。食材の準備や豆腐焼きなどを一年かけて準備するのです!
想像するだけでも膨大な仕事量に違いないことは明白。
裏方さんのおかげで、この王祇祭は成り立っているのだな…といっても過言ではないのだと思います。
・・・さて、ごちそうもいただきましたし、そろそろ当屋に向かう事にします。
次回は下座当屋編です。
