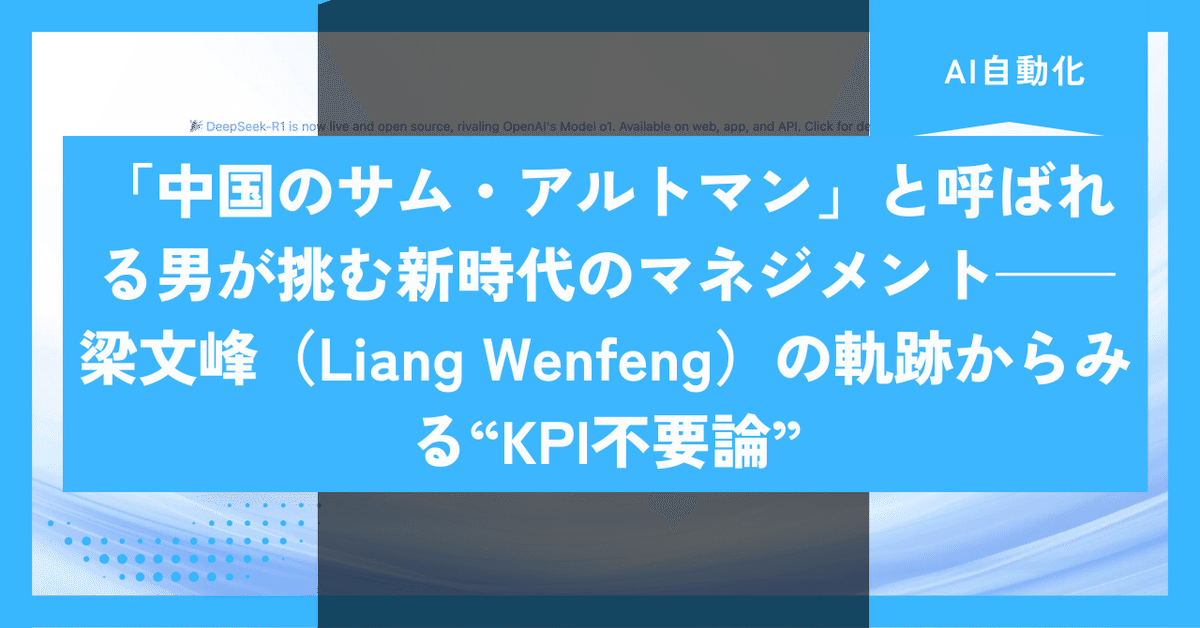
「中国のサム・アルトマン」と呼ばれる男が挑む新時代のマネジメント——梁文峰(Liang Wenfeng)の軌跡からみる“KPI不要論”
「KPI(Key Performance Indicator)」は長年、企業の目標管理や組織運営におけるスタンダードな手法として広く浸透してきました。売上高、利益率、生産量など、定量的な指標を軸に組織を動かすことは、確かに合理的なメリットが多く存在します。しかし最近では、破壊的イノベーションが求められる時代において、KPI偏重のマネジメントがイノベーションの芽を摘んでしまうリスクも指摘されはじめています。
そんな折、「中国のサム・アルトマン」と呼ばれる存在として近年注目を集めている人物がいます。AIスタートアップ「DeepSeek(深度求索)」を創業した梁文峰(Liang Wenfeng)です。彼は量化投資で巨額の資産を築きながらも、AI研究のために莫大な投資を惜しまない“技術オタク型リーダー”として知られています。そして、そんな彼の組織マネジメント手法には「KPIをほぼ設定しない」という特徴があるのです。果たしてこれは「常識破り」なのか、それとも「新時代のスタンダード」に向けた大きな潮流なのか。本記事では、梁文峰の軌跡をたどりながら、“KPI不要論”の可能性を探っていきます。
1. 梁文峰(Liang Wenfeng)とは何者なのか
梁文峰は1980年代に中国の五線都市と呼ばれる地方で生まれました。幼少期から数学やコンピュータに並外れた興味を示し、名門・浙江大学(Zhejiang University)へと進学。当時から「AIは必ず世界を変える」と確信し、大学在学中からプログラミングや人工知能の研究に没頭しました。卒業後、まだディープラーニングのブレイク前夜であった時代に、大企業への就職を選ばず独自の研究に没頭したことが、彼の運命を決定づけたのです。
2015年には友人とともに量化投資ファンド「幻方量化(High-Flyer Quant)」を創業。AIと数学を駆使し、わずか数年で運用資産80億ドル規模へと急成長を遂げます。この成功は中国の投資界に衝撃を与えたと同時に、裏では1万枚以上ものNVIDIA A100 GPUを保有する「隠れたAI巨頭」としての顔も持つようになりました。つまり量化投資にとどまらず、AI研究に対しても積極投資を惜しまない稀有な企業家だったのです。
こうした礎をもとに、2023年に創業したAI特化企業「DeepSeek(深度求索)」では、投資部門を完全に切り離し、「研究」に集中しています。さらに大手投資家からの資金調達をそれほど必要とせず、これまでに得た潤沢な資金とGPUリソースを背景に「資金は問題にならない」と豪語。若手の登用やオープンソース化など、常識破りの施策を次々と打ち出すことで、一気に注目度を高めているのです。
2. KPIを設けない、フラットな組織マネジメント
梁文峰が率いるDeepSeekのマネジメントスタイルは、極めてフラットかつ自由度が高いことで知られています。これは彼が大手IT企業や伝統的なファンドに所属した経験をほとんど持たず、大学時代の研究室の延長のようなスタートアップを自ら作り上げたことに起因しています。
また、彼は「KPIをほとんど設定しない」という大胆な戦略を採用しています。一般的には「KPIを掲げないと組織は動かない」と考えられがちですが、DeepSeekの場合、梁自身を含めた研究者・エンジニアが日常的にコードを書き、論文を読み、ディスカッションを繰り返すカルチャーを構築しているため、数値目標よりも“研究の面白さ”や“ビジョンの共有”がエンジンとなっているのです。
大企業や多くのスタートアップが「売上目標」や「ユーザー数」「シェア拡大」といったKPIを細かく設定するのとは対照的に、DeepSeekは「AI研究に革新をもたらす」という抽象度の高いビジョンを中心に掲げ、「試行錯誤の自由度を高める」ことで成果を出しています。これがまさに「KPI不要論」を象徴するマネジメントの形だと言えるでしょう。
3. なぜKPIに頼らないのか——その背景と思想
KPIは本来、組織の目標達成を効率的にモニターするための有用なツールですが、急激に変化するテクノロジー環境では「半年や一年単位の定量目標」自体がすぐに陳腐化してしまうリスクがあります。特にAIの研究開発では、大きなブレイクスルーが予期せぬタイミングで起こる一方、どれだけ時間をかけても成果が見えづらい期間が長引くことも珍しくありません。
梁文峰はこの不確実性を前提に、「無理に数値管理するのではなく、研究の面白さや自由度を担保したほうが結果的に大きなイノベーションが生まれる」と考えています。また、かつての量化投資ファンド「幻方量化」で大きな成功を収めた経験から、「短期利益に直結しなくてもAI研究への投資を惜しまない」というリスクテイクの姿勢を持っており、これが“KPI不要論”を支える原動力となっています。
4. DeepSeekの成功例:低コスト&高速開発の「DeepSeek V3」
このアプローチが成果として結実したのが、2024年12月に発表された大規模言語モデル「DeepSeek V3」です。6710億パラメータというスケールを誇りながら、わずか2か月という短期間で開発され、費用は558万ドルという低コストに抑えられた点が世界を驚かせました。一般的に大規模言語モデルの開発は億単位の投資と半年〜数年の開発期間が必要とされることを考えると、まさに破格の実績と言えます。
梁は「成功要因は圧倒的な自由度と若い才能の発想力」と語ります。KPIがないからこそ、エンジニアたちが独自のアイデアを遠慮なく投入できたことが、短期間での高性能モデル実現に寄与したというのです。大企業のように厳格なプロセス管理や承認フローがないぶん、「面白そうだからやってみよう」というスタートアップ的なスピード感が生まれました。
5. KPI不要論は普遍化できるのか?——独自の分析
もっとも、このような「KPI設置をしない組織運営」がどんな企業や組織にも当てはまるわけではないでしょう。製造業や金融業の一部など、明確な利益目標や品質基準を管理しないと競合に負けてしまう領域が多いのも事実です。
しかし、AI・IT技術をコアとするスタートアップや、研究開発型の組織においては、梁文峰式の「リスクテイクを前提にした自由な環境」が大きな成果をもたらす可能性があります。筆者の独自分析としては、以下のようなポイントが今後のKPI論を左右していくと考えられます:
不確実性の高さ: AIの進化スピードは極めて早く、明確なロードマップを描きにくい。そのため、KPIよりも好奇心や発想の飛躍を重視したほうが有利になる。
若い才能の台頭: 新卒やキャリア初期のエンジニアが、従来の常識に囚われないアイデアを生みやすい環境こそが競争力になる。
文化と心理的安全性: 失敗を恐れずに挑戦できる環境は、KPIで締めつけるよりも革新的な成果を導く。
KPI不要論は極端にも聞こえますが、特定の業界や領域では成功事例が徐々に増えつつあるというのが現状です。そして梁文峰が率いるDeepSeekの躍進は、その象徴的なケーススタディと言えるでしょう。
6. 「中国のサム・アルトマン」と呼ばれる理由
梁文峰が「中国のサム・アルトマン」と呼ばれるのは、その成長速度やAIへの情熱だけではありません。OpenAIのサム・アルトマンが掲げた「世界中の研究者との協力」「一部テクノロジーのオープンソース化」「AGI(汎用人工知能)の実現」というビジョンを、中国という巨大市場を舞台に実践しているからです。
さらに、梁はDeepSeekのモデルを一部オープンソース化し、商用利用も比較的自由に行えるライセンスを採用。これはかつてのOpenAIが「安全なAIの発展」を目指し、一部技術を公開した方針と通じるものがあります。「AI技術を独占せず、広く社会に浸透させたい」という考えが垣間見える点で、サム・アルトマンと重なって見えるのでしょう。
7. KPIを超えた組織マネジメントの未来
現代のリーダーシップ論や組織論は、「人間中心」「文化醸成」へとシフトしています。厳格なKPI管理によって短期目標にコミットするマネジメントは、製造や販売など安定稼働が求められる領域では引き続き力を発揮するでしょう。しかし、イノベーションや研究開発においては、あまりにもKPIを強調すると人材の創造性が損なわれるというリスクが大きくなっています。
梁文峰のように「自由度を優先し、失敗から学ぶ文化」をつくりあげることが、最先端の技術開発で成果を出すうえでの鍵となっているのです。KPI不要論はあくまで一つのアプローチにすぎませんが、固定観念を打ち破る選択肢として注目され始めているのは確かです。
8. まとめ——KPIを「超える」力が組織を変革する
「KPIを持たない組織は動かない」「目標を数値化しなければ従業員の意欲を維持できない」——こうした通説は、破壊的イノベーションが生まれにくい環境を作り出す可能性があります。中国の地方出身の“AIオタク”として量化投資を成功させ、さらにAIスタートアップで次々と大規模言語モデルを生み出す梁文峰の成功例は、従来の常識を疑うきっかけになるのではないでしょうか。
もちろん、KPIそのものが「もう古い」と切り捨てるのは極端です。事業の安定や進捗管理には相応の定量指標が必要な場面も多々あります。ただ、技術や社会があまりにも速いペースで進化し続ける今、梁文峰のように「好奇心やビジョンを最優先する組織づくり」を意図的に行うリーダーが増えていくことはほぼ間違いありません。
「在我们有生之年,AGI一定会实现」
(私たちが生きているうちに、AGIは必ず実現する)
— 梁文峰(インタビューより)
KPIでは測りきれない“未知への探究心”を原動力に、一大ムーブメントを起こしつつあるDeepSeekと梁文峰。彼の存在とマネジメントスタイルは「KPIありきの組織運営」からの脱却を模索するリーダーたちにとって、新たなヒントを与えてくれるでしょう。
KPI至上主義がもたらす効率性のメリットを認めつつも、それにとらわれ過ぎない柔軟さを持てるかどうか。梁文峰が体現する「KPIを超えたマネジメント」は、今後の組織運営の在り方を大きく変えていくかもしれません。
