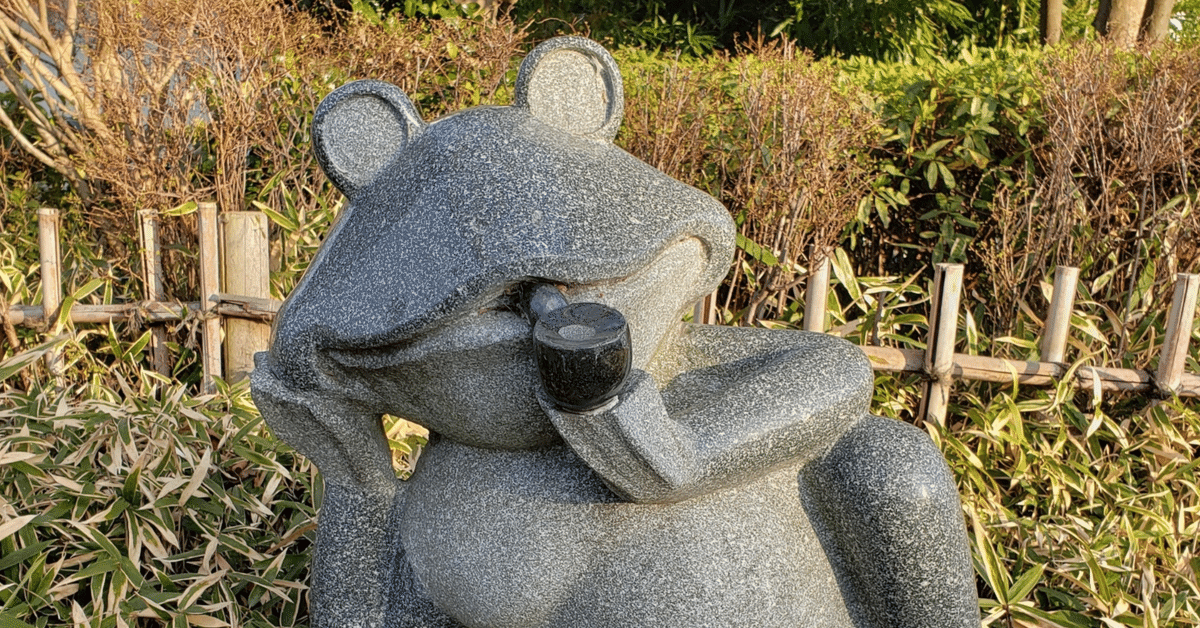
世にも奇妙な物語 ~論理的に考ガエル~
ところで、論理的に考えるっていうのは、性質なのだろうか。それとも、訓練すれば身につく類いのものなのだろうか。
論理的な思考というのは、例えば、探偵ガリレオの湯川准教授みたいに、解決困難と思われた事件をバシッと解決するような場面では、とても役に立つだろう。湯川准教授は物理学者なのだから、もちろん物理の知識は豊富なのだろうけれど、知識だけじゃ事件は解決できない。事件解決には、論理的な思考が必要だ。
ちょっと話は逸れちゃうけれど、探偵ガリレオって、ある種のギャグ小説だと思っていたんだ。物理学の専門家が、その専門知識と論理的思考で、警察にも解けない事件の実行方法を推理する。その推理は、物理の実験的な話としては、筋が通る。物語の中では、実際に犯人は湯川准教授の仮説通りの方法で、その犯罪を実行している。犯人が捕まって、めでたしめでたし。で、そのあとに読者はつっこむ。
「そんなわけ、あるかい!」
それがなぜだか、ドラマではシリアスなまま終わる。うんん。ボクの解釈は、おそらく間違っていたんだろう。まあ、いいんだけど。
世にも奇妙な物語
ところで、物理学者でもなければ、難事件を解決するなんて機会もない、そんな一般の人にとっても、論理的な思考というのは必要なのだろうか。
いやいや。一般の人だろうが物理学者だろうが名探偵だろうが、論理的な考え方を身につけるっていうのは等しく必要なことだと、ボクは思うんだ。
例えば、世の中では、こんなことが起こっている。
episode 1:
ある雑貨屋さんで働いている、パートの女性の話。結婚前はメーカーで事務をしていたが、子供が産まれてからは専業主婦をしていた。ところが、子供が高校生なって手が掛からなくなると、家にこもっていても面白くない。それで、パートを始めた。
働き始めて6ヶ月。大分、仕事にも慣れてきたようだ。完璧とは程遠いが、それでも一通りの仕事は覚えた。そこで、店長は考えた。「時給をアップしてあげよう!」
店長は、時給アップを伝えようと、そのパートの女性を呼んだ。
「〇〇さん、いつもお仕事お疲れ様です。もう、大分、慣れてきたみたいですね」
「おかげさまで、いろいろ教えていただいて慣れてきました」笑顔で返すパートさん。
「お仕事もいろいろ覚えていただいたんで、〇〇さんの時給をアップしようと思っているんです」
ここの店長は、スタッフの時給を上げることには、かなり積極的だった。人件費を削りたいという思いで、スタッフの時給を上げたがらない店長も少なくない。もちろん、人件費というのは、お店の経費として計算される。人件費がアップすれば、当然、毎月の売り上げ目標もアップする。
それでも、ここの店長は、「時給アップでスタッフのやる気やお店の士気もアップするのなら安いもの。それ以上の売り上げにつながるはずだ」という考えで、仕事ができるスタッフの時給は積極的にアップする。
とはいえ、自分の一存だけでは決められないのも事実。だから、事前にエリアマネージャーに根回しもしてある。〇〇さんにとっては、初めての時給アップ。きっと喜んでくれるだろう。
ところが。
「店長、なんでそんなことを言うんですか」
そう言うパートさんの表情は、とても「喜んでいる」とはいえない。むしろ、怒っているようだ。でも、どうして? パートさんは続ける。
「私は、旦那の扶養の範囲内で働きたいって言ってあるじゃないですか。今の収入でギリギリ扶養内なのに、時給をアップされたら、扶養から外れちゃうじゃないですか!」
「それなら、シフトに入る時間を減らせばいいんじゃないですか?」
店長がそう言っても、このパートさんは納得しない。
「私にシフトを減らせって言うんですか? 私は、扶養内でギリギリのところまでシフトに入りたいんです!」
さらにヒートアップするパートさん。店長は説明を試みるが、パートさんは、「時給が上がるのは困る」の一点張り。
店長は、このパートさんの時給を上げるのを諦めた。
え?
episode 2:
さっきとは別の店。だけど今度も、登場人物はパートの女性と店長。
今度は、パートの女性が店長に噛み付くところから始まる。
「店長、これどういうことですか?」パートの女性はシフト表を指差しながら、強い調子で言う。
「どういうことって、XXさん、シフトに問題がありましたか?」
「なんで私、こんなところが有休になっているんですか!」パートの女性は、声を荒げる。
この女性はバツイチで一人暮らし。さっきの主婦のパートさんとは違い、生活のためのパートだ。シフトもフルで入りたいと思っている。この会社の場合、「パートがフルにシフトに入る」というのは、基本的には、「月に136時間以上入るという契約で働いている」ということを意味する。
少し話は逸れるが、この女性、年も60歳を超えていて、老後の不安からなのか、もともとの本人の性格なのか、とにかく「損得」にとても敏感だ。特に「自分が損だ」と考えると、過剰ともいえる反応をする。仕事もあまり覚えないしチームの輪も乱す性格。この店長の本音としては、できれば辞めてもらいたい。本来なら雇うべきではなかったとさえ、考えている。しかし、前の店長がフルで入ると言う条件で採用してしまった。生活もかかっているだろうし、そう簡単には辞めてくれそうにない。
さて、話は戻って。このパートさんは、通常は月に17日、シフトに入っている。本人の都合で月・木・金はシフトには入れない。そして、2月は他の月より日数が少ない。そんな事情が重なって、今度の2月のシフトは、16日しか入れないことになる。
店長は、シフトを確定する前に、その旨を本人に伝えた。本人は、それでは生活がキツくなる。困る。何とかしてくれと訴えた。しかし、月・木・金は休みたいという。まったく無茶な言い振りなのだが、それでも、かわいそうだと思った店長は、こう提案した。
「それなら、有休を使ったらいかがですか?」
「そうしたら17日分のお給料になるんですか?」
「16日出勤+1日有休にすれば、17日分のお給料と同じになりますよ」
「じゃあ、そうしてください」
今、このパートの女性が声を荒げているのは、その有休についてだ。
「店長。なんで私、こんなところが有休になっているんですか! ここは木曜日だから、もともと休みのところじゃないですか!」
「XXさん、16日分のお給料だと生活がきついから、有休を1日使っていつもと同じお給料にするって決めませんでしたか?」
「だからって、木曜日はもともとお休みじゃないですか」
「そうですよ。だから、そこを有休扱いにして、17日分の給料に……」
店長が言い終わらないうちに、パートさんは責め立てる。
「もともと休みのところを有休にしたんじゃ、有休の取り損じゃないですか」
「でも、17日分の……」
「そんなことを言ってるんじゃないんです。出勤になっているところを有休にしてください」
「でも、それじゃ……」
「こんなやり方で有休を取らせようとするなんて、信じられません。ひどいです」
「じゃあ、2月は16日出勤するシフトになっていますが、そのうち1日を有休ににすればいいんですか?」
「当たり前です!そうしてください」
「わかりました」
え?
episode 3:
とある地方都市の老舗のお肉屋さん。小売りもしているが卸がメインの会社だ。この地域では元々、お肉といえばほとんどの場合、豚肉のことだった。とはいえ、今では、精肉に関しては鳥も牛も売れている。ただ、ホルモンだけは、今でも豚ホルモンが主流だ。実際、牛ホルモンを扱うお肉屋さんは、未だに少ない。
そこに目をつけた新社長、といっても家族経営なので先代の息子なのだが、この新社長は牛ホルモンを扱うことに決めた。牛タン、ハラミ、小腸、シマチョウ、ギアラ、レバー等々。最初は周りの反対もあったが、思いのほか人気が出て、新社長本人もびっくりするくらいによく売れている。
ところで、この地域の食肉市場は、昔からの習慣で老舗4社が実質仕切っている。この新社長のところも、そのうちの1社だ。
豚肉は昔から食べられていたこともあり、地元の養豚場から仕入れたものを、物凄く安く仕入れることができる。対して牛肉、とくに牛のホルモン系は、豚肉に比べると大分仕入れが高い。
とはいえ、豚と比べると牛の方が売値も高いため、今年は牛ホルモンでかなりの利益を出している。
ある日、先代のときから務める経理係の一人が、深刻な顔で新社長ところに来た。
「社長、ちょっとお話が……」
「□□さん、お疲れさま。どうなさいましたか?」
社長といえども、自分が子供の頃から働いている社員だ。他の社員と比べても、どうしても丁寧に接することになる。
「実はですね、社長。仕入れが大変なことになっています」
「仕入れが大変なことに?」
どういうことだろう。他社に先駆けて本格的に牛ホルモンを販売し、業績はいいはずだ。
「いや。実は仕入れの代金が、去年の5倍以上に膨らんでいるんです」
経理係は深刻な顔で言うが、新社長はいまいちピンとこない。経理係は続ける。
「社長、こんなこと言うのはあれなんですが、牛ホルモンの仕入れをやめてもらえませんか」
新社長はびっくりして聞き返す。
「今、牛ホルモンは物凄く売れているじゃないか。どうして仕入れをやめなくてはいけないんだい?」
「だから、今言いましたように」経理係は、さらに深刻な顔付きで言う。「仕入れが去年の5倍以上になっているんです。こんなに仕入れ代金が嵩んだことは、私がここにお世話になってから、一度もありません」
「いや、でもね、□□さん。確かに仕入れの代金は掛かるかもしれないけれど、順調に売れているじゃないですか」
「社長。そんなことを言っているんじゃないんです。こんな仕入れ代金、本当に今まで見たことがありません。原因は牛ホルモンです。豚より何倍も高いんですよ」
驚く新社長。この経理係は、何を言っているんだ。新社長は丁寧に説明を試みる。
「□□さん、牛は確かに豚より仕入れが高いです。でも、売値はそれ以上に高いんです。つまり、儲かっているんですよ」
「いえ、社長。だから、そんなことを言っているんじゃないんです。とにかく、こんな仕入れ代金は見たことがありません。仕入れ代金をこんなに支払ったのでは、潰れてしまします」
経理係は興奮で顔を真っ赤にし、唾を飛ばしながら訴える。
「□□さん、落ち着いてください。どれだけ仕入れ代金がかかっても、それ以上の値段でちゃんと売っているんです。だから……」
「いや、社長。社長こそ、ちゃんと聞いてください。とにかく仕入れ代金が……」
え?
世にも恐ろしい物語
「え?」なエピソードが3つ。恐ろしいことにこれらのエピソードは、どこの会社か特定されなようにぼかしてはいるけれど、3つとも実話だ。
どうやら論理的に考えるのって、湯川准教授じゃなくても必要みたいだ。
もちろん、湯川准教授のすごいところは「論理的に考える」というところだけじゃない。「考えるために必要な知識」というのも重要だ。さらにそれに加えて、「何について考えるか」という方向感覚も、湯川准教授は優れている。
「考えるために必要な知識」や「何について考えるか」については、その業界や自分の立ち位置によっても違ってくるだろう。でも、「論理的に考える」という点については、どの業界でも、どんな立ち位置でも変わらない。
ただ、「論理的に考える」というのと、「その考えが合っているか間違っているか」というのは、また別の話だけれどね。
ところで、論理的に考えるというのは、訓練すれば身につくものなの? もしそうなら、自信のない人は訓練したほうがいいし、自信のある人ももっと鍛えたほうがいい。
だけどもし、これは生まれながらの性質で、訓練してどうにかなるものではないとしたら……。
H.E.B. Method
ボクは、論理的思考法というのは、訓練すれば身につくし鍛えられると考えている。どの程度までか、という違いはあったとしても。
その訓練方法も、もちろんいろいろあるのだろうけれど、例えば僕がエバンジェリストをしている「H.E.B. Method」も、その一つです。
--
2021/01/29
Ahiru Ito
