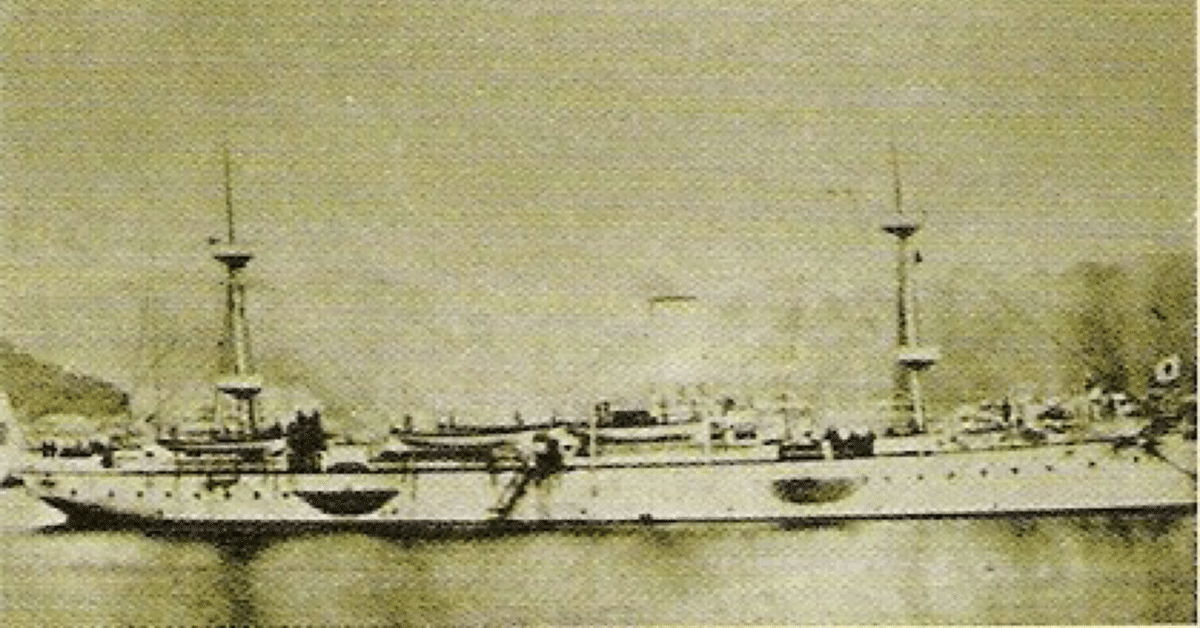
海軍軍人伝 大将(16) 藤田尚徳
これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は藤田尚徳です。
前回の記事は以下になります。
海軍省副官
藤田尚徳は明治13(1880)年10月30日に生まれる。父はもと津軽藩士だが東京に移り住んで、藤田は東京府立一中に学んだ。卒業して海軍兵学校に入校したときの記録では藤田は東京府士族とされている。明治34(1901)年12月14日に第29期生115名の15位で卒業し海軍少尉候補生を命じられた。首席は溝部洋六である。コルベット比叡に乗り組み、翌年2月から半年をかけてマニラ、オーストラリア方面を巡った。フィリピンはスペインからアメリカに割譲されたばかりで反米抵抗運動が繰り広げられている最中だった。帰国すると装甲巡洋艦八雲に配属され、短期間防護巡洋艦高砂に移るがすぐに八雲に戻って明治36(1903)年1月23日に海軍少尉に任官した。その1年後には日露戦争が始まる。八雲は第二艦隊に所属してロシア巡洋艦隊の追跡にあたったが、旅順のロシア艦隊が脱出を図ったときには主隊に派遣されていて、黄海海戦に参加している。その直前の明治37(1904)年7月13日には海軍中尉に進級していた。
旅順陥落後の異動では巡洋艦高雄に移った。高雄は1880年代はじめに建造された近代巡洋艦の成立以前の設計によるもので戦力としての価値は乏しく、第三艦隊に所属して後方の警戒監視にあたった。日本海海戦後の明治38(1905)年8月5日に海軍大尉に進級し砲艦龍田に移ったが、戦争が完全に終結して平時体制に復帰すると砲術練習所の学生を命じられる。これにより藤田は砲術を専門とすることになる。鉄砲屋の表舞台である戦艦勤務を敷島と香取で経験して横須賀海兵団の分隊長に補せられる。鉄砲屋は艦砲だけでなく陸戦も担当するので海兵団には鉄砲屋が配属されることが多い。砲術練習所を改編した砲術学校で高等科学生を修了し、砲術長の資格を得たが配属は第二艦隊参謀だった。長官ははじめ出羽重遠、のち島村速雄に代わった。
呉工廠にはほかの海軍工廠には置かれていない唯一の砲熕部があって、艦砲の製造を一手に引き受けていた。藤田は砲熕部部員と検査官を兼ねたがまもなく海軍大学校甲種学生(第10期生)を命じられた。少佐進級を挟む2年間というのは時期としてごく標準的である。海軍少佐進級は明治44(1911)年12月1日のことだった。
敷島分隊長のあと、横須賀予備艦隊副官に補せられる。予備艦隊は鎮守府に所属する艦船を管理して維持し、あわせて軍港の防御にあたったが制度や名称はしばしば変わった。はじめての中央官庁勤務は海軍省軍務局である。藤田が霞ヶ関で働いているあいだにジーメンス事件が起こり、第一次世界大戦が勃発したが、少佐に過ぎない藤田が政策に影響力を及ぼせるはずもなく、ただ職務に精励するしかなかった。ドイツの租借地である青島が攻略されて極東の戦局が安定すると藤田は戦争の最中のヨーロッパに派遣される。イギリスに駐在してジュトランド海戦をはじめとする英独の争いをロンドンから観察した。結局藤田は第一次大戦のほとんどをロンドンで過ごし、その間の大正5(1916)年12月1日に海軍中佐に進級した。
アメリカの参戦後に帰国し、戦艦摂津副長に補されるがすぐに第五戦隊参謀に移る。旧式戦艦で編成された戦隊の司令官は加藤寛治だった。海軍省に戻ると人事局で将校人事を担当する第一課で勤務する。2年間勤務して大正9(1920)年12月1日に海軍大佐に進級すると巡洋艦須磨艦長としていったん艦隊に出るが程なく呼び戻され、海軍省で出師準備を担当する軍務局第二課長に補せられる。翌年には海軍省内で副官に転じた。副官は官房を統括し、省内全般の事務を整理する役割で3人程度が定員だが大佐の副官は先任副官と呼ばれて海軍省の事務の要だった。藤田の副官在職は2年半におよび、はじめ海軍大臣は加藤友三郎だったが、その後は財部彪と村上格一が交代でつとめた。副官は大臣に日常的に接する立場にあり、大臣のスケジュールを管理したり面会客を取り次いだりするのもその役割で、いろんなことを見たり聞いたりすることになる。
侍従長
いったん巡洋戦艦霧島の艦長をつとめたあと、海軍省外局である艦政本部のナンバーツーの総務部長に補せられる。ワシントン軍縮条約で主力艦の建造が停止させており、かわって補助兵力である巡洋艦の整備が進められていた。大正14(1925)年12月1日には海軍少将に進級している。翌年には本省に戻って人事局長をつとめている。人事局の在職は概して長く、藤田局長も2年度つとめている。
昭和4(1929)年度は艦隊で軽巡洋艦からなる第三戦隊の司令官をつとめた。上司にあたる聯合艦隊司令長官は谷口尚真である。1年で艦隊をおりて昭和4(1929)年11月30日に海軍中将に進級して横須賀工廠長に補された。工廠長は出世コースとは言えないが艦政本部総務部長の経験がある藤田にとっては仕事の内容は馴染みがあっただろう。工廠は鎮守府の隷下に置かれていたが技術に関する事項については艦政本部長の指揮をうけた。
藤田が横須賀に赴任した時にはすでにロンドン軍縮会議が始まっていた。周知の通りこの会議は海軍をふたつに割る激論をもたらし、海軍省と軍令部の首脳部が軒並み交代する結果となる。海軍次官の山梨勝之進が更迭され、その後任は艦政本部長の小林躋造となった。あいた艦政本部長に藤田が補せられることになり、横須賀から東京に戻ってきた。海軍大臣の財部彪は条約の批准をまって安保清種と交代し、満州事変が始まって内閣が交代するとさらに大角岑生に代わった。ほぼ同じタイミングで次官も左近司政三に代わっていたが、5.15事件が起きると海軍士官が首謀者だったことから責任を負う形で大臣も次官も交代した。大臣には岡田啓介が復帰し、次官には藤田が昇格することになる。もっとも大臣の岡田はまもなく定年となり、大角が海軍大臣に返り咲く。
この時期は満州事変も一段落して一見して情勢は安定していたが、満洲国をめぐって国際連盟から脱退し、さらに軍縮条約からも脱退するなど、日本は孤立を深めていった。海軍部内では大角海軍大臣が恣意的な人事をおこなっていわゆる穏健派、良識派を追放していた。軍令部の権限強化がされたのもこの時代である。次官の藤田は極力抵抗したが大臣の意向には逆らえない。大人しい性格もあって押し切られてしまう。ついには藤田自身も長谷川清と交代して呉鎮守府司令長官に親補される。栄典だがていよく東京を追われることになる。
呉での生活は2年半におよび、2.26事件では遠く呉から眺めているしかなかった。事件直後の昭和11(1936)年4月1日に海軍大将に親任され、年度末には軍事参議官として帰京する。翌年には日中戦争が始まった。
藤田は高橋三吉と並んで同期生の出世頭だったが、藤井と高橋が揃って望みをかけていたのは卒業成績115名中68位の米内光政だった。米内は美男子で知られており別の意味で目立ってはいたが、一部で「あれは大物だ」と評判が立つようになるにはかなりかかった。藤田が軍事参議官に補職されるのと同時に聯合艦隊司令長官となり、ついで海軍大臣となってその大物ぶりは広く知られるようになったが、わずかだが高橋や藤田に比べると出世が遅れて順位では下になった。高橋と藤田は、自分たちがいつまでも現役で残っていたら米内が今後なにか重要な役職に就くときに差し障りになると考え、示し合わせて予備役編入を願い出た。将官は自ら予備役編入を願い出ることができるとされていた。大臣の米内は彼らの意図を知ってか知らずか、これを許可して予備役編入の辞令を出した。藤田は昭和14(1939)年4月5日に58歳で現役を離れた。
しかし藤田たちが身を引いて守ろうとした米内は、その年8月にいったん海軍大臣を退いて軍事参議官に転じたが、翌年1月に内閣総理大臣に任じられたときに自ら望んで予備役となる。そうして成立した内閣もちょうど半年で陸軍により潰され、結局29期生の3人の大将は相次いで海軍を離れることになってしまった。
藤田はその後、明治神宮の宮司などをつとめていたが、戦争も終わりに近い昭和19(1944)年夏、侍従長にという話が持ち上がる。侍従長は鈴木貫太郎とそれに続く百武三郎と、15年に渡って海軍出身者が務めてきた。侍従武官長を独占していた陸軍への対抗意識があったと言われる。70歳を超えた百武侍従長が退任することになり、藤田が後継に挙げられたのはその直前に現役に復帰して海軍大臣に就任していた米内の推薦があったのだろう。イギリスをよく知り、穏健で謹厳な藤田は天皇の好みにあったらしい。終戦を挟んだ2年間、苦悩する天皇の側近くで仕えることになる。かつての海軍省副官時代を思い出したかもしれない。戦後、公職追放を受けて侍従長を退く。後任は内務省出身の宮内官僚で、海軍出身侍従長は藤田で終わった。その後は愛知県で隠遁生活を送った。
藤田尚徳は昭和45(1970)年7月23日に死去した。享年91、満89歳。海軍大将正三位勲一等功四級。

おわりに
藤田尚徳も開戦前に海軍を退いた人物ですな。むしろ侍従長として終戦前後に登場するのでそちらで知られているのではないでしょうか。
次回はいったん最終回となります。残りはひとりだけなので必然的に決まります。さて誰でしょう。ではまた次回お会いしましょう。
(カバー画像は日露戦争の後半に乗り組んだ巡洋艦高雄)
附録(履歴)
明13(1880).10.30 生
明34(1901).12.14 海軍少尉候補生 比叡乗組
明35(1902). 9. 3 八雲乗組
明35(1902).12.18 高砂乗組
明36(1903). 1.23 海軍少尉 八雲乗組
明37(1904). 7.13 海軍中尉
明38(1905). 1.12 高雄分隊長心得
明38(1905). 8. 5 海軍大尉 高雄分隊長兼航海長
明38(1905). 9.23 龍田分隊長
明38(1905).12.12 海軍砲術練習所学生
明39(1906). 6.12 敷島分隊長
明40(1907). 4. 5 香取分隊長
明40(1907). 6.18 待命被仰付
明40(1907).10. 1 横須賀海兵団分隊長
明41(1908). 4.20 海軍大学校乙種学生
明41(1908).12. 3 海軍砲術学校高等科学生
明42(1909). 5.25 第二艦隊参謀
明43(1910). 5.23 呉海軍工廠検査官兼砲熕部部員
明43(1910).12. 1 海軍大学校甲種学生
明44(1911).12. 1 海軍少佐
明45(1912). 5.22 敷島分隊長
大元(1912).12. 1 横須賀予備艦隊副官
大 2(1913). 4.22 海軍省軍務局局員
大 4(1915). 3. 1 英国駐在被仰付
大 5(1916). 8. 1 英国駐在帝国大使館附海軍武官補佐官
大 5(1916).12. 1 海軍中佐
大 6(1917).10. 6 帰朝被仰付
大 6(1917).12. 1 摂津副長
大 7(1918). 1. 6 第五戦隊参謀
大 7(1918).11.10 海軍省出仕
大 7(1918).12. 1 海軍省人事局局員(第一課)
大 9(1920).12. 1 海軍大佐 須磨艦長
大10(1921). 8. 6 海軍軍令部出仕/海軍省出仕
大10(1921). 8.17 海軍省軍務局第二課長
大11(1922). 6. 1 海軍省副官
大13(1924).12. 1 霧島艦長
大14(1925).10.20 海軍艦政本部総務部長
大14(1925).12. 1 海軍少将
大15(1926).12. 1 海軍省人事局長
昭 3(1928).12.10 第三戦隊司令官
昭 4(1929).11.30 海軍中将 横須賀海軍工廠長
昭 5(1930). 6.10 海軍艦政本部長/海軍将官会議議員
昭 7(1932). 6. 1 海軍次官・海軍将官会議議員
昭 9(1934). 5.10 呉鎮守府司令長官
昭11(1936). 4. 1 海軍大将
昭11(1936).12. 1 軍事参議官
昭14(1939). 4. 1 待命被仰付
昭14(1939). 4. 5 予備役被仰付
昭18(1943). 8.27 明治神宮宮司
昭19(1944). 8.29 侍従長
昭21(1946). 5. 3 免侍従長
昭45(1970). 7.23 死去
