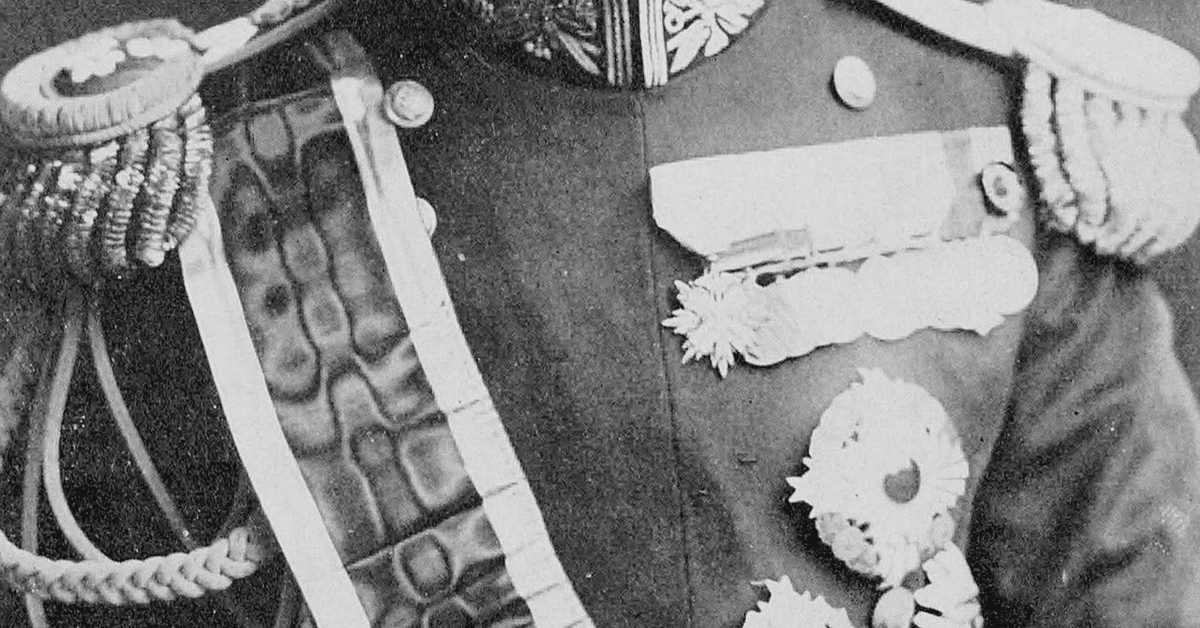
皇族附海軍武官
以前、皇族の海軍武官に関する記事を書きました。
海軍武官である皇族には皇族附海軍武官が附属し、俗に「御附武官」などと呼ばれました。阿川弘之の著作では皇族と御附武官の駆け引きが描写されています。
制度のはじまり
明治のはじめ、皇族が政府や軍の要職を多く占めていた時期にはかえってこうした御附武官の制度は確立していなかった。海軍においてはじめて御附武官が置かれたのは明治22年、海軍兵学校生徒だった山階宮菊麿王と華頂宮博恭王(のち伏見宮)が退校してドイツに留学することになったとき、片岡七郎少佐(のち大将)が両殿下の随員としてドイツ出張を命じられたのが最初と思われる。当時はまだ御附武官は制度化されておらず、辞令としては海軍参謀本部出仕・ドイツ出張被仰付ということで両殿下随員は海軍大臣からの命課という扱いだったようだ。片岡少佐の身分はのちに在ドイツ大使館附武官と変わる。
両殿下の帰国は日清戦争の終了後、片岡大佐(進級)はひとあし早く日清戦争直前に帰国するが、日清戦争が制度整備のひとつの契機になる。開戦を前にして大本営が開設され、天皇が広島に移ると大本営には天皇の軍事秘書役をつとめる軍事内局が設けられ、これが戦後に常設機関となって侍従武官府と称した。天皇の側近として常侍する侍従武官が成立したのは実は明治も半ば過ぎと意外に遅い。ちょうど同じ時期、10代半ばに達してすでに陸軍将校に任官していた皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)のために東宮武官府が設けられた。天皇・皇太子と軍の間に平時からパイプができあがったことで、皇族と軍との関係についても再考されたのではないか。侍従武官府の成立から1年あまり経過した明治29年8月10日、皇族附陸軍武官官制が制定されて陸軍武官たる皇族に皇族附陸軍武官を附属すると定められた。さらに1年おくれた明治30年10月14日、ほぼ同内容の皇族附海軍武官官制が制定された。
制度について
海軍武官たる皇族には皇族附海軍武官を附属させ海軍大尉をもってあてるとされた。
第1条 海軍武官たる皇族には皇族附海軍武官を附属し海軍大尉を以て之に充つ
この内容は陸軍のものとほぼ同様で、ただ武官にあてるのは「各兵科大尉」とされている。なお武官を「大尉」に限定したのは短期間で終わりまず海軍が明治32年に、陸軍も明治33年に「大尉」を「佐尉官」と改めて人事上の制約を緩和した。「日本陸海軍事典」の高松宮附武官の名簿を見ると少佐ないし中佐での補職が多かったようだ。同書の伏見宮附武官には大佐での補職が散見される。
大正4年(陸軍)・大正5年(海軍)に改正があって武官ではない皇族にも皇族附武官を置くことができるとされた。この規定は陸軍士官学校生徒・海軍兵学校生徒・陸軍士官候補生・海軍少尉候補生などの皇族にも御附武官を置くことができるようにしたものと考えられる。昭和7年に陸軍側の規定が「陸軍諸学校の生徒たる皇族」と改められたが海軍側の規定はそのまま残った。
昭和3年、王公族附陸軍武官官制が制定される。ほぼ同内容で、朝鮮王族およびその支流である公族に武官を附属するとされた。
第1条 陸軍武官たる王には王公族附陸軍武官を附属し各兵科佐尉官を以て之に補す
武官に非ざる公には特に王公族附陸軍武官を附属することあるべし
この規定は皇族に対するものとほぼ同内容だが、よく読むと「武官たる公」については何も言及されていないことに気づく。実際には武官たる公族に武官が附属されているので条文と矛盾しているのだが問題にされた形跡はない。なお「王公族附海軍武官官制」は必要がなかったためか制定されなかった。
これ以降、官制の改正はなく終戦にいたる。敗戦後の昭和20年11月末、これらの官制はそろって廃止された。
皇族附武官の役割
皇族附武官は大使館附武官や元帥副官・軍事参議官副官などと同様、陸海軍の組織分類では「特務機関」に位置づけられる。「特務機関」はいわゆる諜報機関ではなく、陸海軍の組織のうち「官衙」(役所)・「軍隊」(部隊)・「学校」のいずれにも属さない組織を総称したものである。
皇族附武官は個人に附属する武官として、同じ「特務機関」とされる元帥副官や軍事参議官副官と似たようなものと認識されそうだが「副官」「附武官」と区別されているのには理由がある。
「副官」は以前の記事にもある通り、秘書のような役割をもっている。副官には元帥や軍事参議官などの個人に附属されたものもあるけれど、海軍省や軍令部・艦隊や鎮守府などの官衙や部隊に置かれたものもあり(むしろそちらが主)、そうした組織の官制には副官の職務が規定されている。一般的な規定の例として艦隊令における副官の職務規定を引用する。
第37条 司令長官の幕僚たる副官は参謀長の命を承け儀制、人事及庶務に関することを掌る
主な職務として儀式や服装のほか、人事や事務処理を担当した、ということになる。これに対して皇族附武官はその任務を以下のように定めていた。
第2条 皇族附海軍武官は其の附属する皇族の威儀整飾を奉助し軍務祭儀礼典及宴会等に随従するを任とす
いちおう「軍務に随従する」とも記載されてはいるが「祭儀・礼典・宴会」と同列に羅列されており、もっぱら儀式における「見た目」を整えること(の補助)が任務とされて軍人としての職務を輔佐するような責任は持っていなかったことが見て取れる。
もっとも、阿川弘之氏の著作などを見ると武官が皇族の日常生活に干渉したり管理しようとすることがままあって当の皇族と確執を起こしたエピソードなどが紹介されている。こうしたことは本来の任務には含まれないはずなのだが、どうも日本人の几帳面さが与えられた以上の役割を果たそうとしてしまうらしい。高松宮は御附武官に厳しかったらしく、しばしば武官をまいてしまい慌てた武官が居場所を探し回ったという。陸軍では朝鮮公族の李鍝公中佐が広島の第2総軍司令部で参謀として勤務していたとき、出勤中に原爆にあって負傷死亡したその責任を負って御附武官が自決するという事件が起こった。当時李鍝公は出勤中で軍務中とは言えず、武官も随従していなかったのだがそれでも責任を感じてしまったのだろう。
武官の人事
武官の辞令は附属するべき皇族を指定されて発令される。以下はその一例である。
海軍少佐 水野恭介
補皇族附海軍武官兼海軍軍令部出仕
宣仁親王附被仰付
昭和4年12月1日
皇族附武官が単独で補職されることは基本的になく、附属する皇族と同じ部署の職を兼ねるのが常である。皇族が軍艦の職員であれば皇族附武官は軍艦臨時乗組、艦隊参謀であれば艦隊司令部附などを兼ねた。上記例の場合、当時高松宮宣仁親王は中尉で海軍軍令部出仕とされたため、皇族附武官の水野少佐も海軍軍令部出仕に補職されている。臨時乗組、司令部附、出仕などはいずれも決まった職務のない補職になる。
皇族が艦隊司令長官や鎮守府司令長官、軍事参議官に補職されたり元帥の称号を得た場合には、艦隊副官や鎮守府副官、軍事参議官副官や元帥副官が皇族附武官を兼ねる。伏見宮附属武官に大佐が散見されていたのは、軍事参議官副官などを兼ねていたことが関係したのだろう。単なる皇族附武官よりも副官のほうが任務の範囲が広いのはすでに見てきた通りである。
やや余談に属するが、皇族が戦隊レベルの司令官職に就任した場合の具体的な運用については実例が乏しく一般化が難しい。実は海軍武官たる皇族の将官への進級は大正2(1913)年8月の博恭王を最後に長く実現せず、次に進級したのは30年後の昭和17(1942)年11月の久邇宮朝融王でしかもこれが最後になった。大正2年は艦隊令に戦隊の規定が追加される以前、昭和17年は太平洋戦争中で、平時の戦隊司令官に皇族が補職されたという例は存在しない。
皇族附武官には華族や華族の子弟が補されることが多いという記述を見かけることがあるが、実際にはそうした条件に合う該当者は多くなく、華族(有爵者)やその子弟たる海軍武官が皇族附武官に補される確率は高かったかもしれないが、その逆向きになる皇族附武官に華族やその子弟が補される比率は目立って高いというほどではなく、大半は平民出身者だった。より条件の厳しい侍従武官のほうが優先されたという事情もあるだろう。
皇族附武官には少佐ないし中佐といった、艦艇では分隊長や科長・副長、駆逐艦や潜水艦では艦長、艦隊などでは参謀、中央官庁では首席部員(課長補佐)などを勤めるはずの働き盛りの時期にあたる兵科将校があてられた。必須ではなかったようだが海軍大学校甲種学生修了者が多い。ただしキャリアという点ではメリットに乏しく、気苦労が絶えないこともありどちらかと言えば敬遠された職だったようだ。「日本陸海軍事典」には高松宮と伏見宮の御附武官のリスト(伏見宮については一部)しか掲載されていないが、少なくともその中には未来の大臣総長は含まれておらず、艦隊司令長官になった者は数えるほどしかいない。
武官を附属するべき皇族とは
官制の条文では「海軍武官たる皇族には皇族附海軍武官を附属する」とあり、これは人事権をもつ海軍大臣に義務と責任を課したものと言える。その一方で「武官にあらざる皇族に皇族附海軍武官を附属することあるべし」とあり、こちらは海軍大臣の裁量を認めている。武官とは厳密に言えば下士官以上だが、皇族が下士官になることは考えられないので実際には皇族が少尉に任官した時点から皇族附海軍武官を附属する必要が生じる。それ以前の候補生や兵学校生徒の時期は海軍軍人とはいいながら「武官未満」で、皇族附海軍武官を附属するかどうかは海軍大臣の判断になる。具体的に実例を見てみると、伏見宮家の傍流山階宮家の当主であった武彦王に対して相良達夫少佐が附属武官としてはじめて発令されたのは大正8(1919)年12月1日で、武彦王が海軍少尉に任官したまさにその同じ日だった。一方、大正天皇の三男である高松宮宣仁親王に最初に附属武官が発令されたのは大正8(1919)年3月26日の田村丕顕中佐で、当時宣仁親王は海軍に進むことが内定していたがまだ学習院に在学中の14歳だった。宣仁親王が海軍兵学校に入校したのは大正10(1921)年、卒業が大正13(1924)年、海軍少尉任官が大正15(1926)年だが、その間ずっと皇族附武官が附属され続けてきた。直宮である宣仁親王と、ヒラの皇族である武彦王の待遇の違いは明らかである。ちなみに宣仁親王の最初の御附武官である田村中佐は子爵の爵位を持つ華族、陸奥一関藩主の家系で伊達政宗の子孫にあたる。
さらに言うと、海軍武官は原則終身でたとえ現役を離れても武官の身分は保持し続ける(俸給は出ない)。官制では武官を附属するべき皇族を現役に限定していないが、実際には予備役に編入された皇族に対して御附武官は発令されていない。元来、皇族たる武官は予備役に編入することなく現役とされて順次進級し最終的には現役定限年齢(いわゆる定年)が適用されない元帥にいたるのが基本で、高松宮は「僕ら黙ってても大将になっちゃうんだから」と語っていたというが、少ないながら病気などで予備役に編入される例も存在した。上の例に挙げた武彦王は海軍少佐で予備役となっている。昭和7(1932)年12月1日附の辞令を登載した官報では、武彦王の「予備役被仰付」という辞令のすぐあとに御附武官である磯部淳少佐の榛名通信長への転出が記載されている。後任の御附武官は発令されていない。
それでも武彦王は山階宮家の当主であり、引き続き皇族であることは変わらない。武彦王の弟(菊麿王三男)である萩麿王は父や兄と同じく海軍に進んで海軍兵学校に入校したが、宮家の次男以降は成人後に皇籍を離れる慣例となっており、萩麿王も海軍少尉に任官してまもなく「鹿島」の姓と伯爵の爵位を賜って臣籍に降下し皇族ではなくなった。海軍少尉任官(昭和2年10月1日)から臣籍降下(昭和3年7月20日)まで半年あまりの時間差があり、官制によれば皇族附武官を附属する必要があったはずだが、実際には発令されていない。臣籍降下が予定されている皇族に対しては、たとえ武官であっても御附武官を附属しないという運用がされていたことがうかがえる。
昭和期に限ってみると、この間に御附武官を附属されるような皇族武官は伏見宮博恭王、久邇宮朝融王、高松宮宣仁親王くらいが主なところで、昭和戦前期全期間(元年~20年)のあいだずっと該当したのはこの3名が全てとなる。伏見宮博義王(博恭王長男)は昭和13年薨去、山階宮武彦王は昭和7年予備役、ほかに萩麿王、博英王(博恭王四男)、朝香宮正彦王、久邇宮家彦王、久邇宮德彦王が海軍で勤務したがいずれも臣籍に降下した。
おわりに
相変わらずネタに苦しめられていますが、皇族附武官についてなんとなく調べていたところ「これは記事にできるんじゃないか」と思ってまとめてみました。性懲りもなく需要に乏しい記事ですがご笑納ください。
ではもし機会がありましたらまた次回お会いしましょう。
(カバー画像は伏見宮博恭王)
