
第6話:もっと徹底的に聞き込んで「あなたの情熱が続く限り、必ず解決策は見つかる」——小説で読む起業
この小説では、主人公の洋子が起業家として成長するさまを描きます。
ストーリーはフィクションですが、起業家としての失敗や苦労、成功法則はすべて、起業や新規事業開発における実際の現場での体験、知見に基づいたものです。圧倒的にリアルで生々しい、洋子の起業家としての歩みを、共に見ていきましょう。
*この記事はGOB Incubation Partnersが運営するメディア「ウゴイテワカル研究所」からの転載です。元記事はこちら。
前話までのあらすじ
洋子は、オンライン上で完結するインテリアコーディネートサービスのアイデアで、miltyを創業した。潜在顧客へのインタビュー結果をもとにサービスを転換しようとする洋子。しかしアドバイザーの美保は焦る洋子にストップをかけた。
第1話〜第5話は以下のリンクから

美保:「洋子さん、どうして普通のサービスに落ち着こうとするの? あなたは一体何に焦っているの?」

洋子:「私もそうしたいわけじゃありません。でもインタビューの結果と、今にも尽きそうな資金のことを考えると、これ以上サービスを止めているわけには……」
美保:「資金が尽きそうだから、一般的なサービスに落ち着いて妥協しようというの?
洋子さんが今話してくれた事業プランは、インテリアコーディネート業界で、すでに存在しているサービスよね。資金がない中で、すでに先行している既存サービス相手に、本当に勝ち目はあるのかしら?
確かに、当初考えていたオンライン完結型のサービスは、顧客の苦痛を掴みきれていない宙に浮いたサービスだったと思う。そして、インタビューを通じて一見オンラインでは解決が難しそうな顧客の声があったことも事実。
でもね、洋子さんは今、これまで掴めていなかった事実をほんの少しだけ掴んだだけなのよ。たった1つの店舗で実施したインタビューで、たった23人の潜在顧客が、利便性と価格についてノーと言っただけ。今回のインタビューでは『耐えがたい苦痛』は見つけられなかったかもしれないけれど、どこかにあるかもしれないし、あるいはインテリアコーディネート業界にもっと他の耐えがたい苦痛があるかもしれない。
それをまだ探し出せていないだけかもしれないのに、またすぐに結論を出そうとしてしまったら、以前の二の舞よ」

洋子:「美保さんがおっしゃっていることは分かります。じゃあ、私はもっともっとインタビューの回数を重ねる必要があるということですか?」

美保:「まったくもってその通りよ。どこかにあるはずの、インテリアコーディネート業界で顧客が抱える耐えがたい苦痛を見つけ出さなければならないわ。結果的にそれがオンラインで解決できるものかはわからないけど、まずは苦痛を掴めなければ、サービスの具体的な形は見えてこないわ」

「まだインタビューをしなくてはならないのか」「もう経営が追い込まれて、早く次の手を打ちたい今この時に……」
洋子は涙を流していた。
いち早くサービスを立て直して資金繰りをなんとかしたいという焦りや、起業家として自分が何者にもなれていないもどかしさ、非力で小さな自分の存在を思い知らされる満たされない承認欲求を抱え、洋子はザラザラとした行き場のない気持ちを溜め込んでいた。
「どうしたらこの状況を乗り越えられるのか。何でもいいから早く答えがほしい……」

洋子の気持ちが落ち着くのを待って、美保は話を続けた。それは美保が、現在経営するフィットネククラブを立ち上げる以前に手掛けていたビジネスについてだった。
***
美保:「母のことは、先日話したわよね。一人暮らしで体調もすぐれない母を見て、母のような状況にある人でも、健康で友人に囲まれて生活できないだろうかと考えた私は、まず『人が集まる場所』がどこかを考えた。
そこでまずは母に、1週間どこで何をしているのかをこと細かく教えてもらったの。すると、引きこもりがちな母でも、買い物には毎日出掛けていることがわかった。以前に話を聞いた時には『普段誰とも話さない日が多い』と言っていたけど、買い物の時は、店員さんや偶然会った近所の人と話をすることもあったみたい」

美保:「そこで私は母に、『お母さん、スーパーに行く代わりに、毎日宅配が届くようになったら便利でうれしい?』と聞いてみたの。
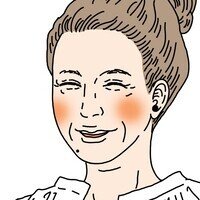
でも母の答えは、Noだった。
ただでさえ人と話す機会がないのに、本当に誰とも話せなくなってしまう。唯一の楽しみを奪われてしまう、って。
とはいえ、母の家からスーパーまでは遠かったし、足腰も弱ってきている中で、買い物が負担になっているだろうとも思った。
そこで私は、ひらめいたの。もし、家の目の前までスーパーがやってきてくれたら、移動の負担もないし、会話もできるんじゃないか……! 私はすごいアイデアを思いついた気分で、飛び上がりたい気持ちだった」

美保:「でも調べてみると、移動型スーパーはすでに全国にたくさんあることがすぐ分かった。私が知らなかっただけで、実際には世の中にはたくさんあったのね。
そこで、休日に、車で1時間ほどの距離にある移動型スーパーに、レンタカーを借りて向かった。
移動型スーパーのある場所までたどり着くと、数人のお客さまがいた。お店の近くでインタビューするのは迷惑になると思い、少し離れたところで、買い物を終えたお客さま、中でも母に近い年齢の方にインタビューをした」
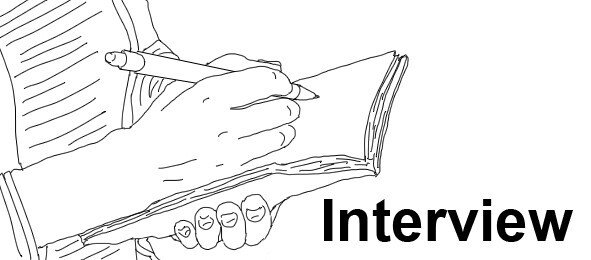
***

洋子:「インタビューはどうだったんですか?」

美保:「結果は惨憺たるものだったわ。誰ひとり、会話を求めて移動型スーパーに来ている人はいなかったの。それどころか、利用している人はほぼ固定で、大半の人は、移動型スーパーが来ていてもわざわざ遠くのスーパーまで出掛けていた。
思い付いた時には『私、天才!』と小躍りしたアイデアだったけど、世の中にはすでにたくさん存在していて、そして思っていたような、苦痛を解消するサービスにはなりえそうもないということが分かったの。リソースを投入する前に仮説の誤りに気づけたのは幸いだったわ」

同じ失敗をしてきた洋子は、当時の美保の気持ちが痛いほどよくわかった。
美保は話を続ける。
美保:「インタビューを通じて収穫もあった。
移動型スーパーが使われていない理由を知れたし、少ない顧客ではあっても、その固定客はお互いに顔見知りで、よく話すということが発見できた。
もちろん移動型スーパーが使われていない理由は、移動型スーパーを使っている人からは聞けない。だからこそ、移動型スーパーが来ている時間帯に、遠くのスーパーまで歩いて行っていたシニアの女性数人に声をかけ、インタビューをしたわ。すると口々に「品揃え」が問題だと話してくれた。
これらの収穫を通じて、私は仮説の誤りに気づくと同時に、新たな仮説を思いついた。『スーパー並みに品揃えが豊富な移動型スーパーなら、みんな使ってくれるのではないか』『しかも移動型スーパーなら、お客さん同士は近所の人だと分かるので、会話も弾み、友人関係が作りやすくなるのではないか』」
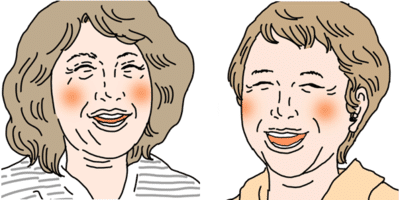
美保:「私はすぐにこの新しい仮説の検証を始めた。とはいえ、巨大な移動型スーパーを作るわけにもいかないから、その代わりに、以前話題になっているのを聞いたことがある移動型スーパーへ向かうことにした。
そこは、地域住民に人気で、お客さんは買い物ではなく話し相手を求めてやってくるということだった。ネットで調べると、そのスーパーは、運良く、私が当時勤めていた会社が広告制作を請け負ったことがあるお店だった。
担当者の方はすでに退職していたが、新しい担当の方を紹介いただき、アポイントをとってそのスーパーを訪問したの」
***


美保:「鈴木さんはいらっしゃいますでしょうか?」
新しい担当者は、鈴木信弘さんと言った。もともとは自治体の地域振興課に所属していたが、地域振興を民間でやりたいと思い、転職をしてきたらしい。入室してくるなりに手を差し出し、強く握手を交わした。熱い人という印象を受けた。

鈴木:「はじめまして。御社には、以前に大変お世話になりました。今日は弊社の移動型スーパー『賑わいの森』についてのお話、ということでよろしかったでしょうか?」

美保:「お忙しい中お時間をいただきありがとうございます。そうなんです。私の母が一人暮らしをしているのですが、話し相手がいてくれたら娘としても安心と思っていたところ、移動型スーパーが近所の人同士での集いの場になっているということを知りました。私にも何かできることがあるかもしれないと思い、実績が豊富な御社の移動型スーパーについてお話を伺えたらと思いまして」

鈴木:「なるほど、お母さまの対話相手を見つけてあげたいということですか。すごく分かります。私の母も、スーパーではありませんが、コーラスに通うようになってからは見違えるように明るくなりました」
美保:「そうでしたか」

鈴木:「移動型スーパーは、実は買い物客のために作られたわけではありません。もともとはスーパーの売上が不振だった時に、その解決策の1つとして考えた打ち手でした。それが、今では結果的に地域の皆さまの会話の場となったんです」
私が、移動型スーパーの問題点としてインタビューで「品揃え」が挙がっていたことを話すと、鈴木さんはその点についても説明してくれた。
鈴木:「例えば生協は自分の家まで商品を運んでくれますが、その時に1週間分の食材をまとめて注文する仕組みです。1週間くらいなら、必要な商品も予測できますし、半数の人は、毎回同じ商品を注文します。
ごく単純な発想ですが、移動型スーパーは品数に限界があるので、だったら1週間分まとめて注文を受け、その注文分だけ店舗型スーパーから仕入れ、移動型スーパーに積んで運ぶことから始めました。
ただ、それでは事前注文の方だけが欲しい品ぞろえになってしまい、より多くの地域住民の方に利用してもらうことはできませんでした。
そこで、地域の学区ごとに欲しい物をアンケート調査しました。上位の品物からできるだけ多く揃え、地域の回覧板でも品揃えを周知していったんです。
そうすることで、多くの地域住民に利用してもらえるようになり、定期的に購入いただくことで、『買い物に来るいつもの人たち』同士での会話も広がっていきました」

鈴木:「でも、工夫はそれだけではありません。毎週決まった日に決まった商品を買いに来るだけでは、人は満足できなくなります。
買い物は、必要な物を仕入れるだけでなく、楽しみで、ワクワクする瞬間でもあります。それを感じてもらうために、いつもの商品以外に、揚げ物や鮮魚などを品種を絞って仕入れました。売れ行きも好調です」
***

美保:「鈴木さんの話を聞いていると何も奇をてらったところはなかった。ただ、住民の方々がどうすれば移動型スーパーに来てくれるのかを真剣に考えた結果だと感じたわ。
そして、商品数は必ずしも重要ではなく『欲しい商品があるかどうか』と『買い物の楽しみ』が重要だということもわかった。
そしてもう1つ大事なのは、移動型スーパーが単独で運営されているのではなく、店舗型スーパーの売上を補助する役割を担っていたことだった。つまり、鈴木さんたちの移動型スーパーでは単独での仕入れをしておらず、そのため移動型スーパーのための在庫も存在しなかったの。
鈴木さんたちの移動型スーパーは、顧客に対しては、必要な品揃えと買い物の楽しみを提供しながら、同時に事業としては、単独での仕入れをせずに売ることで利益をあげていた。顧客への価値提供と、自社のビジネスモデルを成立させる仕組みの両輪が大事なのだと気付かされたわ。
こうして私は『欲しい物が目の前までやってくる、代理販売型移動スーパー』を立ち上げることにした」

***

美保:「具体的な仕組みはこうよ。
地域を学区ごとに区切り、1週間ごとに顧客ニーズを踏まえて品揃えを決めることにした。これは鈴木さんたちの『賑わいの森』から学んだやり方ね。
そして形態は『代理販売型スーパー』。『賑わいの森』のように、自前で店舗を持って移動型スーパーを組み合わせるのではなく、地域の複数のスーパーと契約して、自らは仕入れずに代理販売をするモデルにした。
というのも卸売業者から仕入れて売る場合、移動先で売れるかどうか分からないから、最低限の仕入れをして移動することになる。けど、最低限の仕入れだから買い手がつかず、結果的に仕入れをさらに限定せざるを得ないという悪循環に陥ってしまう可能性があった。一方で、品揃えを増やそうとすると売れ残るリスクが高くなってしまう。
その点、『賑わいもの森』は仕入れをしないからこそ在庫リスクがなく事業が安定していた。それを参考に、私の場合は、仕入れをせずに近隣スーパーの商品を代理販売するモデルを作った。
『賑わいの森』は自社スーパーの商品のみを扱っていたけど、複数のスーパーと提携すれば、顧客にとってよりワクワクで楽しい買い物体験を提供できると考えたの」
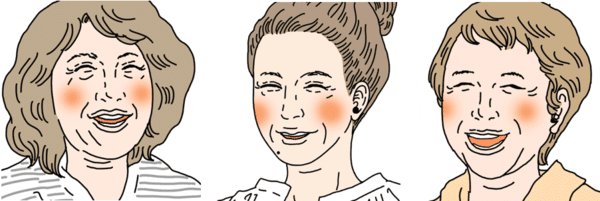
美保:「モデルを考案したらすぐに、今度は実験を繰り返した。もちろん、実験費用は最小限に抑えたわ。実験段階で多額のリソースを投入するのはご法度だからね。
その結果を踏まえて修正を繰り返し、その後、移動型スーパーを正式にリリースした。結果は上々だったが、結論から言うと、このサービスは、成長しているタイミングで、鈴木さんたちの会社に売却したわ。まだまだ成長の余地はあったし、社会的な価値も強く感じていた。けど、鈴木さんたちの会社のリソースを加えることでよりスケールする見込みがあると思ったし、私は前々から、また別の事業を立ち上げたいと思っていたから。
売却資金は、構想していたその事業の立ち上げに投入することにしたわ」
***

洋子は、注文したアイスティーにまだ口もつけられていなかった。
美保の話に聞き入っていたのだ。
買い物の楽しみを提供するという顧客視点と、在庫を持たないという事業の視点の両方から合理的に事業を組み立てるやり方。インタビューでの言葉をただ鵜呑みにするだけではなく、仕入れたヒントを顧客のために組み合わせていく柔軟性。美保のやり方に感動すら覚えていた。
それと同時に、洋子は自分が1年やって来たビジネスが顧客の苦痛を解消するようなものではなかったこと、解決策を作るときにあらゆる情報をヒントにできていなかったこと、実験して結果を見極めることもなく最初から大きなリソースを投入してしまっていたこと……これまでの自分の過ちを改めて悔いた。

洋子:「miltyはこのままもう終わりでしょうか……?」

美保:「それは誰にも分からない。唯一わかるのは顧客だけよ。そしてもう1つ言えるのは、洋子さんの情熱が続く限り、解決策は、必ず見つかるということよ」
***
洋子は美保と別れた後、大学時代の友人であった、仏像彫刻師の謙介に連絡をした。謙介ととりとめのない話をしていると、次第に気持ちが整理されて、前向きになれたことがこれまでなんどもあったからだ。
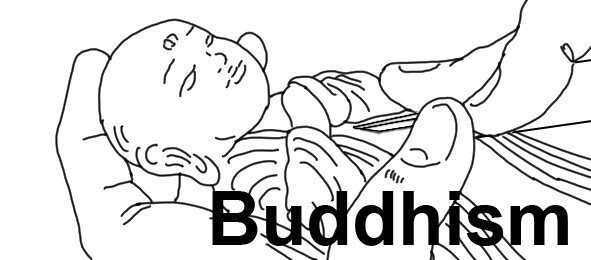

洋子:「謙介に仏像彫刻を依頼されるお客さまって、どういう人が多いの?」

謙介:「本当に色々だから、ひとくくりにはできないかな。でも、これだけは言えるのは、一生懸命生きている人。一生懸命生きていると、どうしても周りに頼れなかったり、自分1人で頑張ってしまったりする。でも、人間そんなに強くないから、どこかで自分のことを支えてもらえないと立っていられない瞬間があるよね。そういう瞬間を今まさに迎えている方、かな。
ちょうど昨日依頼をいただいた方は、おばあちゃん子だった40代の男性の方でね。おばあちゃんがお亡くなりになったから、どうやって心の穴を埋めたらいいのか、という相談だったんだ」

洋子:「謙介は、どういうお客さまのどういう苦痛を取り除きたいのかが、とてもはっきりしているのね。すごいと思う」

謙介:「もちろん最初からそうだったわけじゃないよ。この仕事に就いたのも、最初は東大寺で仏像に感動したからだったし、『誰のために』はおぼろげだった。でも仏像を彫り始めて、お一人ずつから伺う話や思いを形にしているうちに、『自分はこういう人のために仏像彫刻師になったんだ』っていう確信が日に日に増していったんだ。
お客さまと接していると、目の前のお客さまの後ろに、同じような苦悩を抱えた方の姿が行列になって見えることがある。それが洋子の言ってくれた、お客さまが見えているということなのかもしれない。
この人たちのために、自分は永遠に時間を使う必要があるんだと気が遠くなることもあるけどね」

洋子は、顧客とその顧客の耐えがたい苦痛についてはっきりと言葉にできる謙介も、最初からそうじゃなかったこと、顧客と直接触れる中で徐々に見出していったことを知り、勇気をもらえた気がした。
第6話のポイント
・潜在顧客の苦痛は1日程度の顧客へのインタビューでは見えてこない
・耐えがたい苦痛を見つけ、解消するためには、まず乗り越えるべき壁を見つけ出す必要がある
・その壁を乗り越えるための解決策を、あらゆる情報をヒントに作り出す
・解決策は検証結果を見極めるまで、大きくリソースを投入してはいけない
・はじめは顧客の苦痛についてはっきり言葉にできなくても、顧客と直接触れる中で徐々に見出されていく

第7話はこちら
第1話〜第5話はこちら
*この小説はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。
