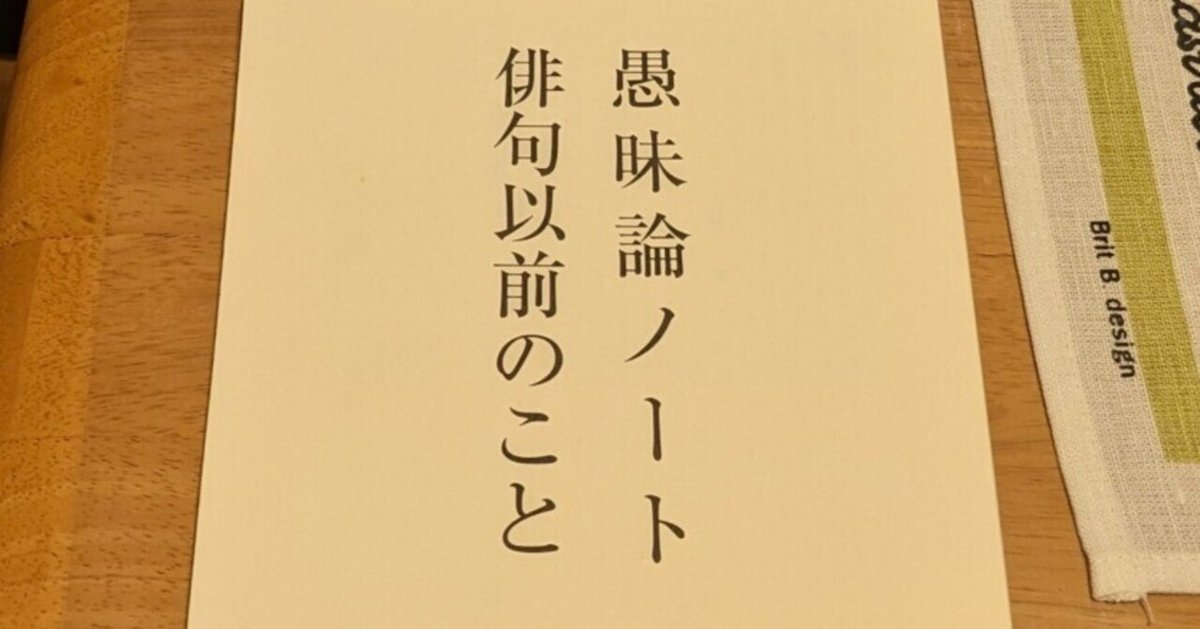
恥をかきたくなる『愚昧論ノート・俳句以前のこと』
鷹では毎月の例会やイベントの際に、物販コーナーが設けられる。そこで鷹会員の新刊や、かつての有名俳人の句集が売られる。例えば飯島晴子の全句集が売ってたりする。
基本的には市場に流通する本が扱われるが、市販していない冊子もたまに置いてある。先日の新年句会では、藤田湘子の『愚昧論ノート・俳句以前のこと』という2つの評論をまとめた冊子に遭遇した。
パラパラめくって、「破顔一笑の句をつくりたい」という言葉が書いてあるのを見て即買いした。僕もそんな句をつくりたい。
この『愚昧論ノート・俳句以前のこと』という2つの評論は今はもう絶版となった、
に収録されているそうで、湘子が晩年に読み直されることを望んでいたらしい。読んでみて面白い箇所がたくさんあったので、まとめます。(多少編集している箇所もあります。原文の意図と異なるところや解釈違いがあったらごめんなさい…!)
愚昧論ノート
虚子はしばしば「あるがままに」と言った。あるがままに句を成して、わずかな佳句を見せ、夥しい駄句を積み重ねた。積み重ねられた駄目なもの、愚かなものの中に、俳句を肥やすエネルギーがあるのではないか。そうとしか私には思えぬ。
ふりかえって私自身は、駄句は捨て愚かな部分は一切顧みることなく歩いてきたように思う。澄んだもの、カッコいいもの、見栄えのするもの、美しいもの、高いもの、はるかなものをいつも求めつづけてきた。しかし、そういう求め方では、厳として重く高い山地を築き得ぬのではないかという不安が、このごろ徐々に拡がっている。
それにしても、と思う。虚子と言えども、
山国の蝶を荒らしと思はずや
海女とても陸こそよけれ桃の花
去年今年貫く棒の如きもの
などの句が出来たときは、「よし」と思ったであろう。快哉を叫んだであろう。それは容易に想像しうるのである。けれど、では、
眠れねば夜長話や老二人
夏の浜人出少く淋しけれ
風の樹につくつく法師せはしなき
といった句を活字にして発表する前の虚子は、いったいどんなことを考えていたのであるか。「よし」と思ったのであろうか。何も感じなかったのであろうか。そのへんが私には読めない。わからない。そういうことに想いをめぐらすと、虚子はどんどん遠くへ行ってしまう。離れてしまう。どうしたら虚子へ近づくことが出来るか。あるいは、どうしたら愚昧な俳人になれるのであるか。
虚子の(特に終盤の)句集に駄句が多いのは有名だが、そこに前向きな意味があると考えたことはなかった。
確かに言われてみれば、『ホトトギス』で誰よりも選句し、「選は創作なり」という言葉さえ残した虚子が、自分の句集の選を疎かにするということは考えにくい。
それは虚子の悪戯心だったのか、それとも湘子の言うように何か深い意味が隠されているのか。ダ・ヴィンチ・コードならぬタカハマ・コードと言うべき秘密があると想像すれば、俄然面白くなってくる。
虚子の俳句に馴染みはじめたときからもっている、一つの疑問がある。判るようでもあるけれど、突きつめていくとどうも解せないところである。それは、
「笹目」とは鎌倉の谷戸読はじめ
「佐助」とは鎌倉の谷戸読はじめ
という二句であり、
虹立ちて忽ち君のある如し
虹消えて忽ち君の無き如し
であり、さらにまた、
虹消えて音楽は尚ほ続きをり
虹消えて小説は尚ほ続きをり
という二句である。どの句も相当に人口に膾炙している。とくに後の二組は、句の成立した背景をも含めて、有名すぎるほどの作である。私もそれなりに納得しているわけであるが、どうしてこうした同型同想の句を並べたのかという疑問は、拭いきれない。虚子の平然とした(と思われる)態度に戸惑いを感じる。こういう句があるから、虚子という人は実に面倒である。厄介である。
(中略)
虚子に対する嫌悪や反撥がそのままで終っていればいいのだけれど、やがて、それが大きなエネルギーになって向ってくるという感じも、私は否めないのである。「笹目」「佐助」の二句を並べた虚子の姿の底には、濁ってドロドロした、文学や詩とは遥かに遠いものが渦巻いているように見える。見えるからこそ嫌だと思い、反撥するのだが、あるとき、それが虚しい抵抗のように思えてくる。蟷螂の斧。あの濁った渦巻きの中には、ある種のエネルギーが潜在する。それを見捨ててしまうわけにはゆかぬ。そのエネルギーの正体は何か。そのエネルギーを生かす手段は、今日の俳句には無いのだろうか。
俳句の自由自在さを謳った人は歴史上たくさんいたし、今の俳壇でも結構な数いると思う。だが虚子ほど大胆不敵に、抜け抜けと、実作した人はいるのだろうか。花鳥諷詠を唱えながら、およそかけ離れた、ポピュラーな詩を残していく。
さっきの選の話もそうだが、虚子は結社システムを促進するための最適な手段やコンセプトとして、選や花鳥諷詠を用いただけだったのかもしれない。それも徹底的かつ考え抜いて。
だからこそ、その限界にもいち早く気づいて、対処方法を模索していたのではないか。その打開策が、既存の俳句観での「駄句」を積み上げていくことだったのかもしれないし、同型同想の句を並べることだったのかもしれない。
己が大成功させてしまった結社システムのせいで、俳句が痩せ細らないように。
俳句が豊穣に栄えていく方向へのヒントを残すために。
実作者としては、ひたすら実験していたのかもしれない。
そう考えると、虚子の一筋縄でいかないところに合点がいく気がした。
俳句づくりということは本来、もっとゆったりしたものではないのか。もっと大らかなものではないのか。もっと自然で自在なものではあるまいか。そういう思いが浮かんでくる。かなり執拗に問いかけてくる。
私はこれまで、想いを煮つめ煮つめして、そのギリギリの一点を狙って作句してきた。そうやって三十七年間つづけてきた。それは多分間違ってないと思う。そう思うほかはないのだけれど、しかしまた、ギリギリでないところにもっと大きな宝石が匿されているのではないか。俳句を豊かにするなにかがあるのではないか。そういった疑念も拭い去ることも出来ないのである。
(中略)
そうした思案の挙句、見当をつけたのは、ギリギリに至る、ほんの一歩手前のところであった。ギリギリの一点が、鍼のように鋭く細くならぬところ。一息、というけれど、一息では多すぎる。ハッと、息を呑む、そんな一瞬の手前。そこらあたりではあるまいか。
(中略)
こうした私の胸裡の相剋を、徳田秋声の言葉は見事に溶解せしめた。「手拭をしぼって、ふっとテーブルの上に置く」「しぼりっ放しではいけない」「しぼって、ふっと机の上に置く」「そうすると、ふくらみが出てくる。裂け目が見えてくる」。そこでつくる。書く。
愚昧論ノートを読むとわかるが、ここでいう自然さや自在さとは、例えば即吟や取り合わせで発想を広げることではない。そうした修養はトレーニングとしてたっぷり取り組んだ前提で、その先の話をしている。
例えば虚子のように、いわゆる駄句を完成形の自分の作品として公開することや、そもそも、それを厭わぬスタンスで俳句に臨むことが必要なのではないか。そうした「愚昧」になることで得られる自然さや自在さがあるのではないか、というのが湘子の考察である。
とはいえ一大結社の主宰が、そのまま虚子の方法を真似するのは難しい。例えば句会で「こんな句は駄目だ」と指導しているような句を、自分が堂々と発表してたら示しがつかないだろう。しかも本人ですら、それがどう俳句を肥やすのかを、明確に見据えられていないというのに。
そうして苦慮した末に、湘子が自分なりの実践方法として辿り着いたのがこの手拭の比喩なのだろう。この趣きは面白いと思う。「ギリギリの一瞬手前を攻める」というのは、頭の片隅に置いておきたい。
俳句以前のこと
今日の俳人は概して作句数が少ないのではないかと思う。もっとたくさん俳句をつくる必要がある。ひたすらつくる、馬鹿になってつくるなんてことが、きわめて少なくなってしまった。たくさんつくれば当然、凡作ができる。凡作ができることを恐れている気配が、俳壇に漂っているように思えてならない。
漫画『柔道部物語』で、
「俺って天才だああああ!」
「俺ってストロングだぜえええ!」
「俺ってバカだあああ!」
と、練習で絶叫するのを思い出した。
凡作がいかにたくさん並んでいようとも、秀句が少しでもあれば、「いい句集だ、いい作家だ」と思いこまされてしまうのである。そうではなかろうか。まして秀作が群を抜いたものであれば、他の凡作はかすんでしまい、秀作のみが年を経るごとに輝き出すのである。
(中略)
虚子がいくつかの大傑作によって、凡百の愚作を自ら葬った結果になったことはまちがいない事実である。このような例は虚子ばかりではない。前に触れた誓子の『激浪』『遠星』『晩刻』『青女』の多作期においても、まったく同じことが言えるのである。誓子といえども、数多い類想、類型、陳腐、浅薄なる作を見出すに事欠かない。
そう。結局のところ、一般的な読者が普通に句集を読んで、翌日も暗誦できる句というのは、せいぜい数句だ。その数句に、長い時が経ってもたくさんの人から思い出してもらえるような、大傑作が含まれていたら、とてもいいなと思う。
そんな作品をものに出来るなら、あとの句は全部0点でもいいという気持ちはわかる気がする。悪魔に魂を売り渡すまでいかずとも、それくらいの代償で、後世に傑作を残せるならば、僕は喜んで句集に愚策を投入するだろう。
実は、私がいま、いちばん狙っているところが、おもしろい句を、なのである。おもしろくあたたかい句をつくりたい。どういう質のおもしろさかでいうと、難しい言いようはぬきにしてひとことで言うならば、破顔一笑、そういった感じの句である。
(中略)
笑わせようと思って仕掛けてくる笑いは、どうしたって底が浅い。作者は、だから平静であらねばならぬ。平静の中から滲み出てくる笑いでなければ、破顔一笑というわけにはいかない。いま、そういう句を挙げてみろと言われれば、私は躊躇することなく、
天心にして脇見せり春の雁 永田耕衣
を抽く。
僕は、俳句を始めたときから今まで、おもしろい句をつくりたいというのは、かなり優先順位が高いところにある。破顔一笑というのはわかりやすいイメージの1つだ。
リズム感がたっぷり沁みこんでいるな、という印象をうける俳人に出遇うことが、この頃きわめて稀になってきた。早い話、句会で披講のうまい人が少なくなった、ということがある。
以前は、どこのどんな句会へ行っても、披講上手、披講自慢の作者が三人や四人はいた。披講することが楽しみで句会に出て来るという人がいた。ところが最近はまったく逆だ。抑揚のないコンピューターの出すような声で俳句を読んでは、名句も台無しである。
(中略)
俳句を朗誦する習慣がなくなって、身体の中に俳句のリズムが通っていない俳人がふえてしまったのではあるまいか。口の中でボソボソ読んで、意味だけで俳句を鑑賞しようとする人が増えてしまったのではあるまいか。
名句のすべてが、必ずしも朗誦向けの俳句ではないと思う。だが幸い、僕は披講が好きなので、そこを拠り所の1つとして、俳句と向き合っていけたらいいなと思う。
いまのままで便々と齢を重ねて行ったのでは悔が残りそうな気がする。大虚子を鏡とし、その中からなんらかの方途を見出そうとしているのである。
そのような思いの果てに泛んだ実験の方法や目的を、私はいくつか書いてきた。それらをひとまず整理してみると、おおよそ次のようなことになるだろう。
(1)長期にわたる多作を実行する
一日十句以上つくることを最低一年はつづけたい。毎月の結果をそっくり「鷹」に発表しなければならない。
(2)失敗を怖れてはならない
恥をたっぷりかいて図太くなれ。そしてたった一句でいいからずば抜けた作を成せ。
(3)破顔一笑の句をつくりたい
いままであまりにも正直すぎ真面目すぎたと思う。眉間に深い立皺をつくって作句していたと思う。
(4)瞬発力、集中力を大切に
軽いタッチで、作品もまた薄っぺらというのでは困る。軽いタッチでもキリリとした鋭い句が欲しい。
(5)リズム・声調を忘れるな
ただ文字をつらねただけの句ばかりではなんにもならない。内容にふさわしい響きをもった句を心がけねばらなない。
そうして湘子は実際に、一日十句を開始して、3年間継続して「鷹」に全句掲載したそうだ。その結果、湘子がどういう境地に至ったのかは知らないが、思い切った取り組みだと思う。
日本最大級の結社の主宰が、それまでの句作スタイルを捨てて、多作に挑んだというのは、1つの壮大な実験と言えるだろう。その実験に懸ける思いが克明に記録されているのは、後進にとってありがたいことだ。
この(1)~(5)は、やろうと思えば自分も今すぐに始められることである(発表の場はさておき)。虚子の秘密に迫ろうとした湘子が、行き着いたポイントを実際に試して吟味してみたくなった。
以上です!他にも、
・昭和21年のホトトギスの二席がおもしろ俳句でびっくりした話
・波郷の「風切宣言」の話
・晩年の波郷の俳句が虚子に近づいているように見えた話
など、興味深い話がありました。
鷹の物販コーナーで、今度はどんな書物に出会えるのか楽しみです。
