
あの日飛び出したこの街と君が正しかったのにね。
小学4年生のわたしは、分厚いメガネをかけ、大人ぶった本を抱える優等生だった。
人よりもよく回る口を武器に、こわいものなしといった風情で学校生活を過ごしていたが、そのせいで友だちが多くなかった。
長すぎる放課後を持て余し、当時我が家に彗星の如く現れた初代ノートパソコンとプレイステーション(やりすぎて映像端子の接続が悪くなったので、テレビ台にコードを引っ掛けて引っ張って使っていた)が最大の友だちだったと言っても過言ではない。
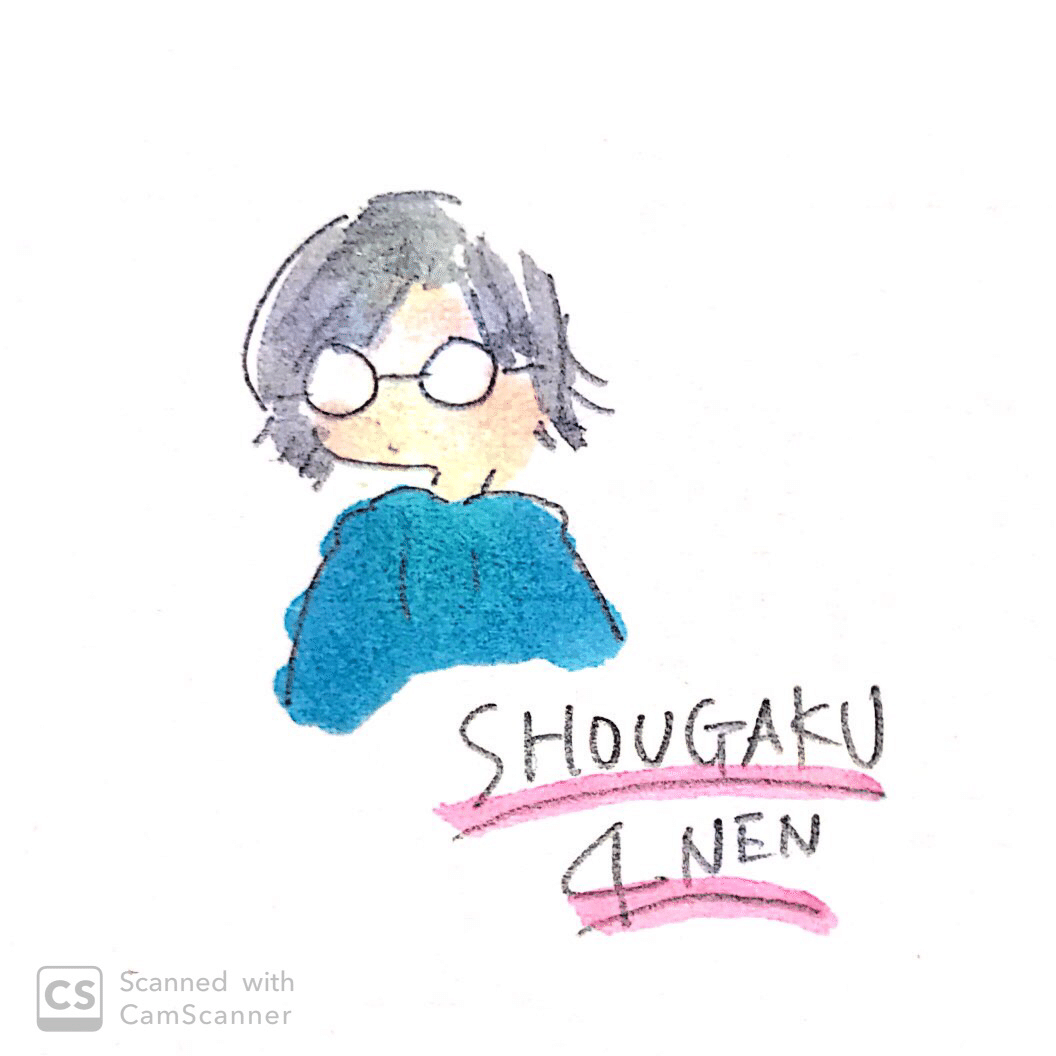
そんな、目からの刺激だけで生きていた10歳のわたしの聴覚が、はじめてぶん殴られた日を覚えている。
兄のMDを、聴いてみたのだ。
真四角の板をコンポに飲み込ませると、突然音が爆発した。
「あの日飛び出したこの街と君が正しかったのにね」
あわてて音量を調整して、どうやらこれが適切な音の大きさだというところで落ち着かせる。とどまることなく流れていくメロディ上に、わかることばとわからないことばとがちりばめられていることに、はじめて気づく。
これは歌なんだ。
学校で使う「かしゅう」には、こんなの載ってないけど、多分そうだ。
これが音楽なんだ。
何故だか胸がばくばくして、知らない場所にきてしまったような気持ちになった。
映画アラジンの途中にある、くちびるがムジュッとなるキスシーンを延々みているような気持ち。
「可愛い人なら捨てるほどいるなんて言う癖に」
「どうして未だに君の横には誰一人いないのかな」
そう、「かわいい」子と、そうでない自分に、やや気付き始めていたのも、この頃だった。
なぜだか足をもじもじさせながら、わたしはMDを聴き続けた。

そのうち、耳で聞いたとおりのことばをノートに書き写すようになった。
ませた10歳だったとはいえ、知らないことばが多かったから、それはそれは誤りの多い、人生初の「耳コピ」である。(わたしは歌詞カードの存在も知らなかった。だから、曲のタイトルを知らなかった。かなり長い間。)
たとえば、歌舞伎町の女王。
正確には、
「女になったあたしが売るのは自分だけで」
なのだが、当時のわたしには、
「おんなになったあたしが夜の街ぶん投げて」
ときこえていた。
たとえば、シドと白昼夢。
「昔描いた夢であたしは別の人間でジャニス・イアンを自らと思い込んでた」
を、
「昔描いた夢であたしは別の人間でいやにすいあんを三つからと思い込んでた」
と歌っていた。(「すいあん」という甘いものが世の中にはあって、それは三つからしか買えないものだと思っていた、という解釈である。)
そうして、勝手に補完を繰り返し、どうにか歌えるようになると、ノートに書き連ねられた文字をあらためて眺め、謎の達成感を味わった。

「椎名林檎」という名前も、しばらくしてから覚えた。その「無罪モラトリアム」が録音された兄のMDをもらい受け、まみどりの正方形を、わたしはお守りのように持ち歩いた。

やがて、TSUTAYAの存在を認知し、カラオケに出会い、曲のタイトルと椎名林檎の顔を知って、ようやくわたしは「椎名林檎が好き」という嗜好の言語化に成功した。かなり長じてからのことである。
ずいぶん長いことアウトプットしなかったせいなのか、わたしの椎名林檎愛は小学四年生のあの頃とほぼ同じ純度を保ち続け、わたしの外側だけがやたらに成長した。

ファンであれば当然知りたいインタビュー内容や、彼女の生誕を祝う集いや、ライブや、そういうものに近づかないまま、彼女の音楽だけをひたすら聴いていたのは、今考えると特異な気がする。そういうものがあると知らなかった10歳のまま、わたしは「椎名林檎道」を歩み続けた。
たぶん、打ちのめされるのが怖かったのだろうと、今ならわかる。
思春期真っ盛りの自分は、同い年の少女が、あの「正しい街」をつくっていたと知るだけで、己の存在意義を疑いたくなっただろうから。
そうして(かなり正規ルートを外れる形ではあるが)なんとか大人になり、自分の受け入れに成功した頃から、彼女のことばを拾い始めた。姿かたちや、話す内容や、彼女を構築してきたものを好み、愛で、憧れるようになった。
たぶん、今までの人生で一番歌った歌は「ここでキスして。」。
「女子高生」は「おねえさん」だった頃から、「教え子」になった今に至るまで。
長いこと、あの音楽と生きているのだな、と思う。
あの頃から、20年たった。
30歳になって、もう一度「正しい街」を聴く。
ほんとうはわたしはなにも変わっていなくて、それでいて大人にもなっていて、ああうう、ううああ、と頭を抱えて平伏したくなってしまう。それと同時に、くっくっと笑いたくもなるし、泣きたくもなる。
最終的に泣くのが一番いい気がして、先日のミュージックステーションを見た後は、頑張って少しだけ泣いて、そのあとお風呂に入って丁寧めに顔を洗った。
夜の街をぶん投げ、「すいあん」を三つからと思い込んでた、と歌っていた10歳の頃のわたしに挨拶するようなきもちで、お風呂で二曲ほど、鼻歌を歌った。

いいなと思ったら応援しよう!

