
モーツァルト:ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 KV452・ラルゲット 変ロ長調 K.452a (Anh.54)
2005年に書いた解説原稿をweb用に大幅に加筆修正しています。
♣️モーツァルト ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 KV452
ピアノと4本の管楽器(オーボエ・クラリネット・ファゴット・ホルン)という珍しい編成で書かれたこの作品は、1784年、モーツァルトがウィーンで超売れっ子だった頃に作曲されました。作曲家として以上にピアニストとして人気者だった彼は、自作自演用のピアノ協奏曲をこの年だけで6曲(ピアノ協奏曲の第14番から19番まで)を作曲し、ソロ曲でもピアノソナタ ハ短調K.457という傑作があるなど、ピアノ曲の分野で目ざましい成果をあげていました。こうした中で書かれたこの作品は、室内楽的なスタイルと協奏曲的なスタイルとの絶妙な融合の図られた傑作として仕上がっています。
自分でも手紙で、
「自分の最良の作品だ」
と誇らし気に書くほどでした。
モーツァルトは、この作品を細心の注意を払って作曲しました。管楽器のブレンドの仕方や生かし方が絶妙で、非常に色彩的に仕上がっています。彼はこのために7ページもスケッチを残しています。こうした管楽器の繊細でカラフルな扱い方は、同時期に書かれたピアノ協奏曲のオーケストラパートにもそのまま反映されています。1784年以前に作曲されたモーツァルトのピアノ協奏曲のオーケストラパートは弦楽器主体で、管楽器は基本的に和音の補強といった役割にとどまっており、場合によっては「管楽器は省略も可」などと作曲者自身による註が書き込まれているものもあります。しかし、この五重奏曲の頃を境に作曲方法は一変します。管楽器の比重が格段に大きくなり、場合によっては、協奏曲の内部で木管楽器とピアノの室内楽的な掛け合いのような場面も多く見られるようになってきます。そして、その成果が有名なピアノ協奏曲第20番以降の後期の傑作群として結実することになるわけですが、まさにこのピアノと木管のための五重奏曲はその端緒となった作品だったのです。この五重奏は、弦楽四重奏の分野の金字塔である「ハイドンセットKV. 387、KV. 421、KV. 428、KV. 458、KV. 464、KV. 465」と同時期でそれは「フィガロの結婚」直前の作品ということですから、モーツァルトは作曲技術と創作意欲が最も高揚した絶頂期にありました。彼は前衛的な手法や複雑な対位法や和声法も臆さず作品に取り込み続け、その感情表現の複雑な豊かさは限界を知らないかのように拡張し続けていました。
二楽章で、いつ果てるともしれない息の長い歌を五つの楽器でとてつもない繊細さで受け渡しながら歌い交わしてゆく様は圧巻です。メロディが受け渡される度に色合いがどんどん変化していくところが見所といえるでしょう。天国的な陶酔と仄かな官能性が微妙に絡み合って音楽は進行し、最後は童心に帰ったかのように素直になってあっさり終わってしまう。凄い!
この時期・1784年に、モーツァルトはフリーメイソンに入会します(「慈善」という名のロッジでした)。この五重奏曲が初演されたトラットナー館の予約演奏会には、モーツァルトも出演し、自作を発表していました。このトラットナー館には多くのフリーメイソンの会員たちが集っていたのです。観客の4人に1人がフリーメイソンだったそうです。モーツァアルトの後を追うようにハイドン、父のレオポルド、クラリネットのシュタートラーが相次いでフリーメイソンに入会しています。
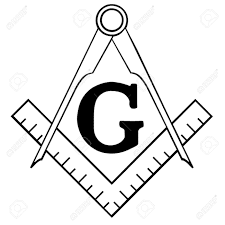
この時期からモーツァルトの作品からはフリーメイソン的なシンボルが聞き取れるようになってきます。この五重奏曲にもはっきりとフリーメイソンのシンボルが表れています。まず「3」という数字の重視、変ホ長調(フラット三つ)であること、冒頭で重々しくフォルテで奏される三つの和音。管楽器の重視。序奏部の荘厳な付点音符の音型など。
ブレンデルの録音は大スターを揃えた管楽器陣の豪華さが凄いです。ホリガー、ブルンナー、バウマン、トゥーネマン。この豪華さを凌ぐ録音は今後もなかなか出てこないような気がします。
♣️ラルゲット 変ロ長調 K.452a (Anh.54)
1784年に書かれた断片です。KV452と同編成で書き始めたものの、何らかの事情で序奏部だけで中断してしまったのではないかと言われています。冒頭のユニゾンの音型が印象的で、ゆったりとした天国的な雰囲気が美しい作品です。断片といってもそれなりにまとまっていますので、ちょっとしたアンコールには最適かもしれません。
♣️ベートーヴェン ピアノと管楽のための五重奏曲 変ホ長調 Op.16
この12年後の1796年、若きベートーヴェンがこの作品をお手本にして同編成の作品を作曲しています。編成だけでなく、調の選択、3楽章構成で、第1楽章はゆっくりとした序奏付きのソナタ形式、フィナーレはロンドという構成まで、モーツァルトの作品と同じです。
内容としても先輩モーツァルトに倣って、管楽合奏の「ハルモニームジーク」の要素と、古典派室内楽の様式を統合し、同時に協奏曲的な要素を加えていくという路線で作曲を進めています。もちろん、ベートーヴェンも自分らしさを出すべく、様々な工夫を凝らしましたが、アインシュタインは以下のように述べて、先輩モーツァルトの優位を述べています。
『モーツァルトがこの作品で協奏曲的なものとの境界線に触れながら、しかもこの線を踏み越えない感情の繊細さはただ感嘆すべきもので 凌駕しうるものではない』
〜A. K. (-_-;)
余談 様々な録音
ウィーン・フィルとベルリン・フィルの名手たちが結成したアンサンブルとレヴァインが組んだ演奏も良い。近年の管楽器の名手たちの凄いアンサンブルが聴ける。レヴァインはウィーン・フィルとモーツァルトの交響曲を録音していたので、この演奏はもちろんその共演関係の上にある演奏。おれはレヴァインの弾くピアノが好きなので、この録音もけっこう好きだ。
指揮者のピアノならプレヴィンも最高。プレヴィンのピアノも素敵だー。レヴァインかプレヴィンの二択なら、この曲の場合はおれはプレヴィンになるかもしれない。
プレヴィンのモーツァルト、素敵だー。大好き。
内田光子さんとマレイ・ペライアは二人ともイギリス室内管の首席奏者たちと録音してる。彼らはイギリス室内と協奏曲をまとめて録音していて、
その一連の録音の流れの中でこの曲も併せて録音した。「協奏曲の録音の延長上」ってところが意義深いと思う。そう、この五重奏の性質(後期の傑作ピアノ協奏曲群との深い関係)を考えると、このお二人の録音は、まさに「そうあるべき」姿の録音のように思う。実際、どちらの演奏も最高だ。室内楽的な「親密さ」に満ちたやりとりに溢れた録音。おれははっきり言ってしまうと聴くなら内田さんかペライアの録音のどちらかって感じ。やっぱりふだんから室内オケのサイズ感・距離感で考えてるプレーヤーと、世界一の大オケでトップ張ってる人たちとはちょっと感じ方に違いがあるのかなあとも思う。
