
朱欒
――お別れは握手? それともキス?
――忘れるだけ。

ぱ・ぱらん・ぱら、と雨は小説の冒頭に似てやたらとたどたどしい音をたて、何億年を経てもなお慣れないでいるような覚束なさで降りはじめる。合成皮革の安っぽい、ベージュ色のトートバッグに折りたたみ傘が入っていることを美湖都はおもう。いつかの旅先のコンビニエンスストアで間にあわせで買った五百円の黒くてかさばる可愛くない折りたたみ傘だ。どうしたものかと逡巡し、けれど雨は降りはじめることさえできてしまえばあとはもう熟れて、たとえばだれかへの愛憎の、そのかなわなさを認めざるをえなくなったときの憔悴までもを肯定するように周辺は文字どおりの悪天候となり、不器用だった雨声も安定してくる。だから美湖都はバッグから折りたたみ傘を取りだして持ち手についている大きなボタンを押しこみ、ばん、と勢いよくひらき、雨の降りはじめの覚束なさ、とあとで手帳に書きつけておこうと決める。パンプスやストッキングを履いた脚がじゅくじゅくと冷たく濡れそぼっていくきもちわるさを携えながら帰路を歩いているうちにメモをとろうとおもったことなんてもう頭から消えていると確信しながら。毎日のように通る道沿いの、通れば絶対に目にしていたはずの建物なのに、足場が組まれて幕がかけられるとそこにどんな建物があったかおもいだせなくなることとおなじだった。
橙色の煉瓦調の分譲マンションは雨にさらされると明度が二段階ほど落ち、いつもはしない黴の、鼻孔の奥の奥まで乾かしていこうとするざらついたにおいがエントランスに漂いはじめて、築五十年近く経つその古臭さが露呈する。元は美湖都の父親が物置代わりにと購入したセカンド・ハウスで、駐車場とエレベーターがついていてとにかく安いということだけが決め手だったけれど、女ひとりで住まうには充分すぎるくらいに部屋もベランダも広く、駅からもそこそこ近かった。美湖都は玄関を開けてパンプスを脱ぎ、ついこのあいだの休日に施したばかりのピンクベージュのネイルで引っかけてしまわないようにストッキングを脚から慎重に剥いていく。ストッキングのどんなときでも健康的でいられる肌色から解放された太腿は寒さで粟立って血管の蒼さが目立っていた。シャワーを浴びたい、と美湖都はおもい、でもその前に喉が渇いたからお茶、ともおもい、そういえばお茶を沸かしていなかった、と気がついて、ふらふらと、肩まわりが濡れてしまっている服のままでベッドに倒れこんだ。枕に鼻をうずめると薄荷飴のような爽やかで甘い、けれど口に含んだらきっと舌をぴりぴりと刺激してくる苦みを想像させるような銀のにおいが残っていて、においとはそのひとの気配なのだ、と書かなければならないきもちになり、美湖都はベッドから起きあがってダイニングテーブルの上で開きっぱなしになっているノートパソコンの前に移動した。スリープ状態になっていたノートパソコンをつけると書きかけの原稿が表示される。神さまへの懺悔を綴った冒頭の、最後の句点にカーソルをもってきてバックスペース・キーを長押しする。そして真っ白になったデータに〈においとはそのひとの気配なのだ〉と打ちこみ、いや、〈そのひと〉では不特定多数に当てはまってしまって特別感が弱いから〈においとはあなたの気配なのだ〉と打ちなおし、しかし思考はそこでふっつりと途切れてどう書き進めればいいのかわからず、バックスペース・キーに指をふたたび押しつけた。締切を過ぎて二週間にもなるのに担当の編集者から催促の連絡がひとつもこないことがここのところ頭の後ろのほうにこびりついて離れない。まるでどこかの無人島にひとり取り残されてしまったかのようだった。ノートパソコンの前でねばってみても文章はいっこうに生まれなくて、結局先ほど消去した文章をもう一度打ちこんで、やはりこれでいいのだ、たとえ滅茶苦茶であっても書かなければ進まないのだ、と言い聞かせて、なよなよと、佳さそうにみえる綺麗なことばを連ねていく。書いていることのなにもかもが、間違っているような気がしてならず、そのくせ入れ墨のように痛く滲みこんで正すことも難しかった。

部屋にあがるなり銀は口許を手で覆ってもわかるくらいとびきり大きな欠伸をひとつした。ほら、上着かけるから脱いで、なんておせっかいをしたら夫婦のようにみえるので一生しないと美湖都は堅く誓う。歓楽街に掲げられているホスト・クラブの案内の看板に写る男の子たちはみんな王子さま風のつり眉に筋のとおった鼻にとがった顎ときていて、銀も例に漏れない顔立ちをしているけれど、源氏名のとおりに染めあげられた銀髪が飛び抜けて派手で美湖都は銀と顔をあわせるたびにぎょっと驚いてしまう。仕事どうだった、と会話を切りだしかけて、これも所帯じみていて嫌だなと口をつぐんだ。
「先生は雨平気だった? 降ってたの、ちょうど帰る時間だったんじゃない?」
話題を選んでいるうちに銀のほうが先に口をひらいた。
「ん、折りたたみ傘持ってたから大丈夫だったよ」
「そ。よかった」
シャワー借りるね、と銀は脱衣所へとむかう。銀がここにやってきたということはもう日が変わっているのだろう、美湖都が壁かけ時計を仰ぐと時計は一時五分を示していた。
あなたが死んだと、それも一か月も前に死んでいたのだと連絡を受けた翌日のことだ、美湖都は勤務ちゅうにふと涙が出てきてしまいお手洗いに逃げこみ、ひとしきり泣いて戻ってきたら、本間ちゃん大丈夫、と契約社員仲間の秋山うららに声をかけられて晩に飲みにいくことになった。金曜日に華を添えるように定時ちょうどにタイムカードを切り、たわいもないお喋りをしながら駅前の飲み屋街を歩いているうちにいつの間にか立ちならぶ店の種類が変わっていき、まさかな、と美湖都がおもっているとうららはNMY YOURSという名前のホスト・クラブの前で足をとめた。うららが配偶者の目をかいくぐってホスト・クラブに通いつめていることを美湖都は知っていたけれどまさかじぶんみたいな外見も内面も地味な人間が同行することになるなんておもってもみなかった。うららは心悟という黒髪で小柄な男の子を指名し、美湖都のほうは何人かのホストが入れ代わり立ち代わりに隣に座ってはお酒と会話を交わすという初回特有の流れとなり、ホスト・クラブ初心者の前で目まぐるしい接待が繰り広げられた。
――雨、めっちゃ降ってますけど帰り大丈夫ですか?
おもえばあのときも雨のはなしだった。うららと心悟がどこかに移動して、美湖都の隣に座るホストが途切れたとき、ヘルプ役の銀が注文したカシス・オレンジを持ってきたついでにそう言ったのだった。
――え、全然気づかなかったです。どしゃ降りですか?
――どしゃ降りですね。傘持ってきてますか?
――いや、持ってないです。降るなんておもってなかったから。
――おれ、このあと抜けても大丈夫なんで送り指名してもらったら駅まで送りますよ。傘ないときついとおもうんで。
――えっと、じゃあ、お願いしてもいいですか?
――喜んで。
美湖都は持ってきてもらったばかりのカシス・オレンジをぐいと飲みほして、アルコールによる眠気でぼやけていく視覚と聴覚を、頭のなかに居座る、いくら飲もうが酔いきることができないところにいる強烈な自我のようなもので制しながら先の会話のとおりに銀を送り指名して店を出ると、外は雨の一滴も降っていなかった。一緒に出てきた銀の顔をおもわず見上げると膨らみはじめて五日目の、繊月とも半月ともとれない月の光が銀の髪を硬質にきらめかせて、退店すればすぐにわかるような嘘をついて一体なにが目的なのか推測しなければならないというのに綺麗な光景を見ているということしか考えられず、書きたい、と表現欲がふつふつと湧きあがるばかりだった。書きたい? あなたが死んだのに? あなたはもう、読んでくれないのに? 鼻の奥に涙の源となる熱が溜まってみるみるうちに瞳が潤んだ。
――駅まで送るのは本当ですけど、怖かったら逃げてください。
――え?
銀は美湖都に目もくれず、ズボンのポケットに両手をつっこんでただ前を見ている。
――なんていうか、騙してる感じなんで。でも、うららさんと心悟くんも席離れちゃって、あんまり楽しんでもらえてないなっておもったから。
――いや、そんなことないですよ。はじめて見る世界で、刺激的で面白かったです。
――ふうん。あの、もしかしてライターさんとか記者さんだったりします?
――あ、えっと、ちょっと違うんですけど……。
小説家です、と美湖都は喉許まで出かかった職業の名前をごっくりと、頬張りすぎた食べものをいっぺんに嚥下しようとしたときの食道が無謀に膨らむ痛い息苦しさを伴う呑みこみかたをした。新人賞の受賞を切に求めていたころはここでじぶんの肩書きが生まれ、じぶんに身分が与えられるものと信じていたのに、いざ受賞してみると受賞作が文芸誌に掲載されただけの人間が小説家を名乗るのはおこがましいような気がしてとてもじぶんからは言い出せなかった。
――じゃあ、作家さん?
――そう、ですね。
受賞したことをSNSに書きこんでもあなたからのいいねはつかなかった。自らの書きこみのほとんどいいねをつけてきたあなたの無反応が、不安を煽り、よからぬ想像を生んで、落ち着かないきもちにさせた。
――へえ、すごい。作家、先生ですね。
――そんな大それたものでも……ていうか、なんでわかったんですか?
――目が、ぽいなって。そこにあるものをそのまま感知するんじゃなくて、その先にある物語を追うような目をしてるから。店にいるときも、たぶんいまも。
――へえ……。
そんなことがものを書いていないであろう人間にもわかるものなのだなあ、ホストだから洞察力が優れているのかなあ、と美湖都が暢気な感想を抱いている傍らで、ふうう、と銀が重たい溜め息をついた。
――書くのって、面白いですか?
そして美湖都も堂々と名乗れずにいるとはいえ小説家の端くれであるがゆえに、これまでの文脈と、たったひとつの台詞に孕んだやや敵意のある薄暗い声色と物言いから銀の事情を鼓膜の震えとともに察して、このひとは他人に語るに値する傷痕をもっているのだと、それは書く人間によってつけられたものなのだと把握して、カフェインを摂取しすぎたときとおなじ眼球の奥がちかちかと眩めくような感覚に襲われた。
――小説を書くのは、楽しいですよ。
だからわざとらしく主語を補って質問に応じた。駅前で銀から、ご来店以外のことでもなにかあったらいつでも電話してくださいね、と名刺を渡されながら、ホスト・クラブに行く用事はきっとないだろうからもう二度と銀とは会わないと美湖都は予想し、それは有名な占い師の星座占いくらい正確な推察だったのに、けれど、夕立の日の天気予報みたいに外れた。
がちゃん、と浴室の折り戸の開く音がして銀がシャワーを終えたことを耳で知り、なにも進んでいない原稿のデータを保存する。美湖都はベッドに潜りこみ、銀も脱衣所から出てくるなりベッドにむかう。どちらからともなく枕許のリモコンで電気を消し、ふたりは夜景を不揃いにして、相手の躰の温かさと、自らの躰の輪郭を確かめあう。
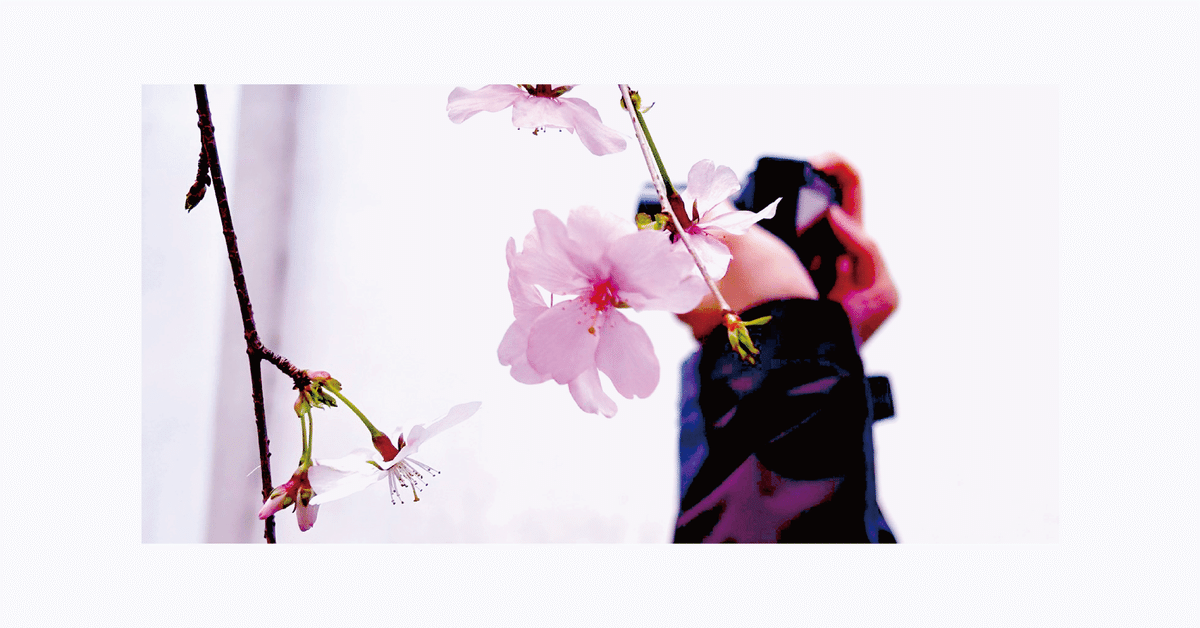
この世でしてはいけないことのひとつは、死んだひとの名前をインターネットで検索することだ。しかしあなたの本名を知っていた、読まなくなった本を譲りあうのに名前と住所を聞いていたから。あなたはどこでじぶんの小説を見つけてくれたのだろう、ついに聞くことはできなかったけれど眩いことのようにおもった、どの小説にも丁寧な感想を送ってくれるあなたのことを奇跡のように感じていた、それがいつの間にか、あなたがいるから書けるのだという勇気にすり替わって、この小説はあなたがすきそうだとか、この小説はあなたに読んでほしいだとか、なんならあなたのために書いていない小説なんてないくらいだったのに、でも、あなたはもういないのだ。そのくせSNSでしか関わりのないあなたの素性を知らず、つい、血筋を示すための名字と両親の愛としての名前を検索窓に打ちこんだ。事故、というサジェストを横目にエンター・キーを押すとある自治体のお悔み情報サイトが最初に出てきて、二〇二三年五月二十一日午後十時十五分に二十九歳をもって急逝しました、と書かれていた。それはあなたの死についてメールを送ってくれたあなたの学友が教えてくれた情報と相違なく、あなたは間違いなく死んでいるのだった。じぶんよりも一歳か二歳、若くして。検索一覧に戻ってほかのホームページを閲覧してみると、就職先、大学、高校、中学校と、どこに所属して生きてきたのかが一目でわかるほどあなたは非常に優秀な人間だったのだと知った。もし凡庸な人間であれば名前で検索をかけたところでなにも出てきやしない。知れば知るほどに死後のあなたは存在を確かにしてこころのなかで大きく膨れあがっていく。無知は罪と言うひとがいるけれど、知は無知に戻ることができず、知もまたひとつの十字架だった。
このような昏い文章を読んで、あなたはどうおもうだろう。
あなたのすきな小説を書く作家のままでいられているのだろうか。
一度目の命日を迎えようとしているいまもあなたの不在が頭から離れない。仕事をしているときも、休日にどこかへ出かけているときも、うまく書けないながらノートパソコンにむかっているときも、だれかと過ごしている夜も……常夜灯だけをつけてふたりは真夜中の素肌に触れあって、静寂をゆるさず、全身を支配しようとするまどろみを振り払いながら朝がやってくるのを待つ。
「小説は進んだ?」
「いいや。全然書けない」
「書けない書けないっていつも言ってる」
「言ってるね」
「やめないの?」
「やめないよ」
「ふふ。おれ、先生がなんか書いてるタイピングの音、すきだよ」
美湖都は左腕を銀の頭に貸し、右手で銀髪を撫で、犬みたいだ、とおもうけれど犬に触ったことはなかった。知らないはずのことが想像しただけで感触として身に迫ってくるのはどうしてなのだろう。たとえば、遠方の生家に送り届けるためにエンバーミングを施されたであろう遺体のあなたの不躾なほどの美しさや、硬く冷え切った肌触りを、わかっているような気がするのだ。それからあなたの葬儀のためにきのうのきょうで飛行機に搭乗することになった友人たちの緊張と、遺体と対面したときの戸惑いと悲しみが綯い交ぜになった頭をがんと殴ってくるような感情も、別れ花のいきいきとした蒼くささも湿り気も、実際に目の当たりにしたのだと錯覚しそうになる。じぶんが記憶している光景や感覚の、なにが本当でなにが嘘なのか判別がつかなかった。ふっと美湖都が頭を撫でるのをやめると銀がその手をとって指を絡める。
「おれのことはちゃんと書ききってね」
「え?」
「じぶんの都合のいいときだけあることないことてきとうに書いてさ、それでひとの人生壊すくせにあとは知らんぷりってされるの、もう嫌なんだよ。だから先生にはおれのこと最後まで書いてほしい。髪、染めなくてもいいくらい爺さんになるまで」
「……うん。努力する」
銀の手が離れたのを契機に美湖都は右手を腰にまわして眼前にある躰をそっと抱き寄せ、他称二十三歳の銀はおそらくもっと若く、二十歳にも満たないのかもしれず、それだのに安全に眠れる夜を、受けるべき健康な愛を、野生の動物よりも知らないのではないかと、闇夜に似た恐ろしさをおぼえる。きっと死もおなじくらい暗いところにあって、光があたらないでいるうちに過去へと消滅してしまうのだろう。

業者用の問いあわせダイヤルが鳴り、美湖都は反射神経で受話器をとる。
「お電話ありがとうございます、ルドン住宅販売です」
先方から、物件確認、という語を聞きとり、資料を準備いたしますので少々お待ちくださいませ、とことわって保留ボタンを押すと簡単な電子音に変換されたカーペンターズの「青春の輝き」が流れだす。電話を待たせるがわが運命の相手を待つという首が痛くなるまで未来を望み見上げつづけるような歌を流すのはいかがなものかと何度聞いても奇妙な心地がするけれど、問いあわせダイヤルとして使っているこの固定電話はかなり古いもので説明書も残っておらず保留音の替えかたをだれも知らなかった。美湖都は自席のパソコンで自社の物件情報をまとめているファイルをひらいてふたたび保留ボタンを押す。
「お待たせいたしました。それでは住所からどうぞ」
そうして早口ことばみたいに淀みなく物件の住所と金額を告げられていくのに対して、ご紹介可能です、そちらは成約済みとなっております、と美湖都は淡々と返事をしていき、回答を終えて受話器を置く。ふと視界に入った、告知事項有り、という注意書きに、あなたが暮らしていたアパートの一室もそうなったのだろうかとおもいを馳せ、しかし数百年前はどこでだって合戦だといって、そうでなくても寿命や病気や怪我でひとびとは命を落としていったわけで、ひとは生きているかぎりだれかの死を踏み固めた土の上に立っているはずだ、なんていうのは至極当たり前で発見がなく、小説の一文には使えないなとおもう。なにか小説を読まなければならない、小説はじぶんがもつことばの世界だけでは結実することができない、先人たちのさまざまな作品を受けとって練りあげることによってまた一新して生まれてくることができるのだ、家系図がたったひとつの家族では完成せず複数の〈夫になる人〉と〈妻になる人〉を結んだ線で紡がれていくことに似て。美湖都にもかつて二重線で結ばれていたひとがいたけれど次の線を引っぱってくることができず、卵管造影剤が、ちりちりと、じくじくと、暇をもてあました神さまがやたらと繊細に変てこりんにつくりあげた生殖器に痛みを押しひろげ、しかし問題は見つからず訳もなく孫を為さない女だと判明した時点で義父母から見放され、両親に孫はいなくてもいいとふたり善がりの愛を信じてやまなかった夫にも耐えきれなくなって実家に出戻り、物置代わりになっていたセカンド・ハウスを譲り受けた。それがちょうど、新人賞を受賞して、SNS上のあなたの沈黙に死の疑いをかけはじめたころのできごとだった。
このあいだ倉橋由美子の『暗い旅』を読んだから次はミシェル・ビュトールの『心変わり』を読むべきだ、ということが電話もかかってこず勤務時間ちゅうにもかかわらずやることがちっともない美湖都の意識にのぼり、退勤後は書店へ行こう、ということにした。できれば規模の大きな書店で、岩波文庫がずらりと並んでいるようなところがよかった。

〈しばらく離れます。すべてのひとを照らし導く灯台になることはできなかったけれど、そこからはぐれてしまっただれかにとっての二番目の明かりになれていたなら嬉しい。ありがとうございました。
二〇二三年五月十六日
指先に初夏のあなたが溶けこんで朱欒は結ぶ杲杲として〉
あなたが書いた文章や短歌を遺言のように読むつもりはないけれど、最後のブログはどうしてもそのように決心したひとのことばに読めてしまっていけない。命日が近づくほどに何度もブログを読み返し、やってはならないことだと己を戒めたにもかかわらずあなたの本名を検索窓に入力する。お悔み情報サイトは変わらずあなたの訃報を載せており、あなたがいないことを伝えつづける。あのころ、あなたが住んでいる方面に行く用事があって食事をともにしたいと考えていたけれど、SNSの投稿時間を見るにあなたはかなり忙しいひとのようで、無理をさせないようにと、断る理由をつくれるようにと、その誘いは直前にする計画だった。馬鹿だった、会いたくても会えないひとは墓と変わらず、それならば死んでしまって会えないひとなんてものはもう完全に墓になるというのに、どうしてもっとはやく対面しようとしなかったのだろう。そしてあなたは小説の感想のなかで言っていたのだ、墓は憶えているほうのひとが時には何度も訪れて手入れをすることがあると。正直なところ、会わなくなったひとに対する記憶や感情が長くて三年しかもたないような人間にあなたを憶えつづけていられる自信はこれっぽっちもなく、文章はどうしたって過去形だから書くことも憚られる、書くことは決して残すことと同義ではないのだから。しかし、時は流れ、こころは動く……買ったばかりのビュトールの一行めがあまりにも麗しく、これを読み、そして書くためにじぶんは生まれてきたのだと美湖都は都合よく勘違いをしながら、続きは週末の旅行で新幹線に乗るときに読もうと決め、猫の刺繍が入ったブック・カバーを分厚い文庫本にかける。ねえ、と背後から呼ばれて、なに、と振り返ると、素肌のままベッドに入っていた銀が上体を起こして美湖都のほうを見つめている。眠たい目をこすってサンタクロースを目撃しようとするような子どものあどけない顔をしていた。
「先生は来年もこうしてるとおもう?」
「どうだろうね」
返事に苦笑を混ぜてしまったことに銀はきっと気づいただろう、あなたが急にいなくなるようなことが起こるのだから未来を約束することはできない。銀は悲しいとおもっただろうか、それともほっとしただろうか。
「でも、信じるしかない」
「なにを?」
「嘘も本当も」
何度も真っ白にしてきたデータの一行めに題名を、二行めに香賀地りさと筆名を、三行空けて、六行めのはじめでスペース・キーを押す。
「ごめんね、ちょっとしばらく集中する」
「なに、書くの?」
「うん。頑張る」
「じゃあ静かにしてる」
脳裏にちらついている小説のかけらを順序正しく拾いあつめるために、深く深く、限界まで息を吐いて集中する。不用意に手を伸ばすと反発してひょいと遠ざかったり、逆にいくつもくっつきすぎてごちゃついたり、まるで磁石みたいだ。つかないように、離れないように、モチーフのひとつひとつを慎重に摘まんで並べていくと、きょうこそうまくやれそうな気がしてくる。す、と息を吸いこんだ。
これは、あなたを忘れるための物語だ。
と、わたしは書きはじめる。
【写真について】
撮影機材:iPhone14、標準のカメラアプリ
編集ソフト:Adobe Photoshop 2024、Adobe Illustrator 2024
撮影地(掲載順):
●特急北斗 ブラインドを下げた座席にて(2024.4.27)
●横浜市 マリンウォーク付近(2024.1.28)
●新千歳空港-関西国際空港間機内より 関西の夜の撮り損じ(2024.4.28)
●京都市 六角堂(2024.3.31)
●函館市 金森赤レンガ倉庫(2024.4.25)
●新千歳空港-関西国際空港間機内より 夕陽の色が刻まれた東北の上空(2024.4.28)
【本作がとくに影響を受けている作品】
●『橋の上の娘』(1999年、監督:パトリス・ルコント、配給:UGCフォックス、シネマパリジャン)
●金井美恵子『岸辺のない海』(2009年、河出文庫)
●倉橋由美子『暗い旅』(2008年、河出文庫)
●村上春樹『街とその不確かな壁』(2023年、新潮社)
●カート・ヴォネガット・ジュニア『スローターハウス5』(1978年、ハヤカワ文庫、伊藤典夫訳)
●ミシェル・ビュトール『心変わり』(2005年、岩波文庫、清水徹訳)
●リチャード・ブローティガン『西瓜糖の日々』(2010年、河出文庫、藤本和子訳)
【筆者について】
夏迫杏(なつさこ・あん)
1992年生まれ、京都市在住。書くひと、てんびん座。
京都造形芸術大学文芸表現学科卒業。蒼海俳句会所属。
第6回ブックショートアワード最終候補(萌し)、第65回群像新人文学賞5次選考通過(日向にいる)、第40回太宰治賞1次選考通過(INLAY)。
〈あなた〉との出会いは二〇二〇年ごろだったようにおもいます。正直なところ、〈あなた〉がどうやってわたしを見つけてくれたのかまったくわかりません。『nice meeting you』という個人制作誌を通販で購入してくださった綺麗な名前のひとが〈あなた〉であればいいなとおもっていたらほんとうにそうだった。その後発行した『海峡の恋』、『日向にいる』についても、とても丁寧で、小説の世界をさらに広げていくようなご感想をくださり、なんて心強い読者なのだろうと感激しました。わたしの小説を好いてくださっているかたがたがほかにも存在していることは重々承知のうえで、けれど、どうしたって〈あなた〉は特別でした。一年が経ったいまでも〈あなた〉の不在による静けさに戸惑ってしまいますが、もし死後という世界があるのであれば、そこはどんな本でも読み放題の楽園で、〈あなた〉がこころ穏やかに過ごせていたらいいなとおもっています。
ところで、朱欒は自らの花粉による受粉ではしっかりとした実がならず、ほかの柑橘類の花粉を与えられることでゆたかに結実するのだそうです。それは小説を書いたり、あるいは読んだりする、ひとつ手間のかかる行為に似ています。ひとによっては煩雑に感ぜられるかもしれませんが、少なくともわたしは先人たちの小説を読んで書いてきたことで、また、〈あなた〉をはじめ皆さんがわたしの小説を読んでくださったことでここまで生き抜いてゆくことができました。すこし前のいじけてばかりいるわたしの口からではとても言えなかったけれど、小説はだれかを救うことができる。それはもしかしたら皆さんのうちのだれかかもしれないし、わたし自身かもしれない。大きすぎる祈りをこめて、〈あなた〉の命日に際し本作を書きおろしました。
二〇二四年五月二十一日
朱欒咲く此の世でめくる日誌かな
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
