
意外と知らないロゴレギュレーションのこと
こんばんわ。さて今回は、「意外と知らないロゴレギュレーションのこと」というタイトルでお送りいたします。
レギュレーションとは何か?
レギュレーションとは、予め決められた規定のことです。ロゴやアイコンなどに設定されていることが多く、視認性や可読性などに基づいて、色の規定やマージンの取り方などが定められています。
ロゴの縦幅などを基準として、マージンをどれくらい取ればいいのかや、背景色がどの数値を超えたら色を反転させるかなど、事細かに決められている場合や、都度デザイナーや現場判断に任せて使用するように定められているものなどまちまちです。
独学でデザインを勉強されている方は特に、意外と知らないのかもと思い今回この記事を書くことにしました。
主なレギュレーション
先ほども述べましたが、ロゴのレギュレーションとして定められているのは主に以下のようなものがあります。
⚫︎ロゴ(アイコン)の最小使用サイズ
⚫︎ロゴ(アイコン)のマージン(余白)
⚫︎ロゴ(アイコン)の色について
⚫︎ロゴ(アイコン)の背景色について
etc…
最小使用サイズについては、主に印刷用で記述されていることが多く、例えばよく見かける以下のようなフリーダイヤルロゴの場合は、横幅が3mm以上で使用するように定められています。
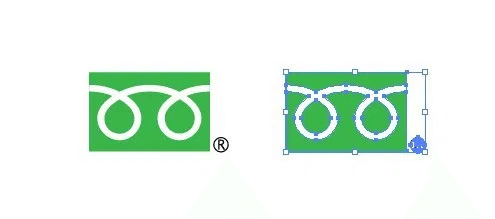
マージンについても、ロゴを使用する際の横幅や縦幅を基準値Aとして、0.1Aは最低余白をとるなど、ロゴとその他の要素が一体になって見えてしまうことを防ぐために定められている場合が多いです。ロゴと余計な要素が一体で見えてしまうと、ブランドとしての認知を阻害してしまう可能性があるためです。

色については、例えば白地の上に置くのか黒地の上に置くのかで著しく視認性が下がってしまうことなどを考慮して、ロゴなどに複数のカラーバリエーションがある場合もあり、その際の色のRGB値、CMYK値が定められています。
印刷の場合、紙によって発色が異なる場合もあるので、少し狂っていても見た目ではわからないことも多いですが、データ上間違えているとあとで追求された際に問題になることも多々あるので十分注意した方が良いです。
背景色についても同様で、例えばCMYK値で言うとK50%からは白のロゴを使うのか、K60%からなのかなど、細かく決められている場合もあります。
レギュレーションに書いていなくても守るべき事項

実際にレギュレーションの資料として公開されていなかったり、そもそもレギュレーションが存在しない場合でも、ロゴの所有者に許可を取らない場合は基本的に避けた方がいいものもいくつか存在します。
⚫︎縦横比率を変更しない
⚫︎黒のロゴを勝手に白にしない(勝手に色を変えない)
⚫︎タイポグラフィーのロゴの場合、読めないサイズにしない
⚫︎背景を明度差のあるオブジェクトでセパレートしない
⚫︎要素を勝手に組み替えない
言われなくても当たり前のようなことも多いですが、基本的にはロゴの縦横比を弄ったり、色を勝手に変えることはNGです。ロゴの作成者に対して失礼であると同時に、先ほども述べたようなブランド認知の阻害行為となってしまいます。
10年間赤一色だったロゴが急に緑になったら、ユーザーはきっと違和感を感じてしまいますよね。それで顧客が離れる事態に繋がる場合もあります。
また、企業やサービス名がロゴになっている場合は、読めて初めて成立するロゴの場合もあります。余裕を持って読めるサイズは担保しておくことが求められます。
タイポグラフィーとモチーフの組み合わせで成り立っているロゴなども、要素の勝手な組み替えは厳禁です。例え別の場所で組み替えVerが利用されていたとしても、特例的な措置の場合もあるので、支給されていない状態のロゴを使うのは避けましょう。
まとめ
レギュレーションは意外と知らないまま使っていることも多いですが、基本的にブランドイメージを守ることや、支給されたものを改変しないことを大前提として使っていれば問題ない場合も多いです。
わからなければクライアントや所有者に必ず確認をとって使用するように心がけましょう。
【運営会社】 合同会社meno
:https://www.meno-inc.com/
