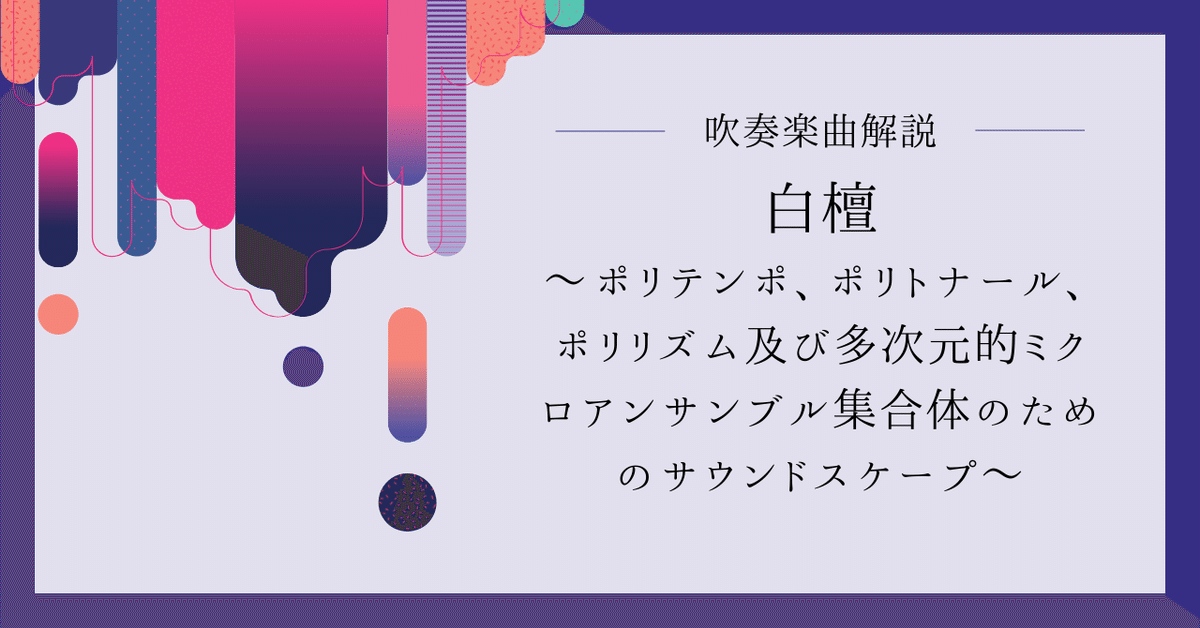
【吹奏楽曲解説】白檀~ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズム及び多次元的ミクロアンサンブル集合体のためのサウンドスケープ~(天野正道)
楽曲解説のnoteも気付けば20本目になりました!今回は天野正道『白檀~ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズム及び多次元的ミクロアンサンブル集合体のためのサウンドスケープ~』という楽曲を紹介をします。
中学生でも演奏可能な「現代音楽入門」とも言える作品です。
■参考音源
加養浩幸指揮/海上自衛隊東京音楽隊による演奏
YouTubeの音源は以下です。
AppleMusicでも聴くことが出来ますのでリンクを貼っておきます。(音源自体は一緒です。)
■作品について
タイトル:白檀~ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズム及び多次元的ミクロアンサンブル集合体のためのサウンドスケープ~
作曲:天野正道
時間:約7分
難易度:グレード4
出版:CAFUAレコードよりレンタル
初演:神奈川県綾瀬市立北の台中学校吹奏楽部
天野正道作品というと『ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイドスコープ(La forme de chaque amour change comme le Kaleidoscope)』など、フランス語由来の長いタイトルの作品が多いですが、今回も『白檀~ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズム及び多次元的ミクロアンサンブル集合体のためのサウンドスケープ~』という長いタイトルが目を惹きます。
ただ、この長いタイトルは無闇に長くしている訳ではなく、作品の内容を正確に表現している"意味のある"タイトルです。タイトルの意味を分解して見ていきましょう。
ポリテンポとは
まず、「ポリテンポ」という単語。
ネットや音楽用語辞典で調べてみると「複数の異なるテンポの音楽が同時に演奏される状態」と出てきます。
読んで字の如くではあるのですが実際にポリテンポを用いている楽曲を聴いてみましょう。
後藤洋作曲の『ウインド・アンサンブルのための シャドー・ソング』を例に挙げます。
上記の動画を見てもらうと冒頭の木管アンサンブルと比べてその次に出てくる金管アンサンブルは1段遅いテンポで演奏されているのが分かると思います。
以下でスコアを確認してもらうと分かるのですが、木管アンサンブルは四分音符=56、金管アンサンブルは四分音符=48で書かれています。
「木管のアンサンブルよりも遅いテンポで演奏し~」という注意書きまであるので、この部分はポリテンポの「ゆらぎ」を効果的に使った音楽です。
ポリトナール(ポリトーナル)とは
次に「ポリトナール」という単語。(「ポリトーナル」と読むのが一般的かもしれませんが、曲名に合わせて「ポリトナール」と記載します)
先ほどと同様に調べると「複数の異なる調性の音楽が同時展開すること」「同じが曲の同じタイミングに異なった調が同時に演奏される状態」といった意味が出てきます。
複数の調が同時に演奏される訳で、なかなか衝撃的な音がします。実際の例としてモーツァルト作曲の『音楽の冗談(音楽の戯れ)』のラスト3小節の音を聴いてみましょう。(19:35以降)
実際聴いてみると「えっ?」となるような凄まじい音ですよね?
楽譜を見てみると楽器ごとに異なる調が同時に演奏されていることが分かります。

上記は極端な例ではありますが、複数の調を同時に鳴らした不思議な響きなんだなー、くらいに思っていただければイメージしやすいです。
ポリリズムとは
最後に「ポリリズム」という単語です。
これまでと同様に意味を調べると「リズムや拍子の異なる声部が同時に演奏されること」「拍の一致しない複数のリズムが同時に演奏されること」といった意味で出てきます。
こちらも実際の実際の例を聴いてみた方が理解しやすいかと思いますので、「ポリリズム」の例を動画で紹介します。
ファリャ作曲のバレエ音楽『三角帽子』の第2組曲より「終幕の踊り」の冒頭4小節を取り出してみます。(6:36〜6:42あたり)
拍の変わり目を「|」で表すとここの弦楽器は、
タンタカ|タンタカ|タカタカ|…という3/4拍子のリズムを刻んでいるのが聞き取れるかと思います。
今度はトランペットが2、3小節目に吹いているリズムに注目してみます。(休符を「(ツ)」と表します)
(ツ)タタ|タータ、(ツ)タタ|タータという6/8拍子のリズムに聞こえるかと思います。
実際にスコアを見てみても上記の通り弦楽器は3/4拍子、トランペットは6/8拍子の楽譜となっているのですが、このように異なる拍子感の楽譜が同時に演奏されることが「ポリリズム」です。

トランペット(赤枠)と弦楽器(青枠)で異なる拍子で演奏される。
ポリリズムの独特のリズム感はクセになりますよね。先ほど動画で紹介したファリャの『三角帽子』は他にもポリリズムのような箇所はたくさんあるので探してみてください。
作品タイトル最後の「多次元的ミクロアンサンブル集合体のためのサウンドスケープ」の部分は後ほど(Part1、Part2部分の解説)で触れますので、楽曲の構成の説明に移ります。
演奏時間7分という短めの作品ですが、曲はPart1~3までの3つの部分に分かれていてそれぞれアタッカで(間をあけずに続けて)演奏されます。
Part1
Part1はSenza Tempo(自由なテンポで)と記載されたテンポも拍子も調性も無いような前衛的な音楽で開始されます。
音と音の間に置かれたフェルマータには「フェルマータの間隔は指揮者の自由」、木管楽器には途中「可能な限りのハイトーン」と注意書きがあり、どんな音楽を作り上げるかは演奏者側に委ねられています。
Part1の冒頭数小説だけでも天野氏が中学生でも演奏出来るように配慮していることが感じ取れます。
まず、木管楽器の注意書き「可能な限りのハイトーン」という記載。特に中学生だと楽器を初めて1年にも満たない奏者がいることが想定されます。
そのような奏者が居る場合でも「自分が出せる中でのハイトーン」を出せば良い訳ですから、具体的に音域が指定されているよりも演奏者側は遥かに気が楽です。
高くて鋭い音を求めている箇所だと思うので、作曲者側としては「そのような響きを出すためにはこの音以上のハイトーン」と指定することも出来たはずですが、中学校からの委嘱ということもありあえてそうしていない(=どのくらいのハイトーンにするかは演奏者側に委ねる)というのは天野氏なりの配慮かと思いました。
同じ箇所の金管楽器が「可能な限りのハイトーン」ではなく「任意の音程」と注意書きの内容をわざわざ変えているあたりも、非常に配慮されて書かれているなぁと思ったポイントです。(金管楽器のハイトーン、木管楽器とはまた理由が違う難しさがありますよね…)
その後、テンポや拍子が出てくる部分に入ると「ヒュー」「ガサガサ」という効果音や擬音が耳につくかと思います。
「ヒュー」という正体はハーモニックパイプという楽器です。この楽器はこの曲の後半でも印象的な使われ方をしています。

「ガサガサ」というノイズのような音は「パラフィン紙を揉む」という指示で演奏されています。
パラフィン紙という単語自体はあまり聞き馴染みが無いかもしれませんが、クラフト紙にワックス(ロウソクの"ロウ"に似たもの)を染み込ませた紙のことで、お菓子や食品の包み紙として良く使われるあの紙を思い浮かべていただければと思います。

様々な道具を使って音風景(=サウンドスケープ)を表現するのは現代音楽あるあるですが、今回それらの表現のために使われているのはハーモニックパイプとパラフィン紙という準備するのが比較的安価な道具というのも良いですね。
Part2
Part2の部分のスコアには以下の作曲者コメントが記載されています。
PartⅡは6つのグループに分かれる。
それぞれ scoreの形で配布される。
全体のイメージはカーニバルなどで色々なグループが同時演奏している中を練り歩いて聞こえてくる印象に近い。特定のグループに近づくと、その演奏は他よりも大きく開こえるが、他の演奏も遠くに聞こえている、という感じが臨機応変変化していくというプロセスを再現する。
繰り返しの回数は自由。また、演奏順は練習番号通りで無くても構わない。
適度に休みを入れても良い。
他のグループとのテンポ、拍子などは違って構わない。
強弱は指揮者の指示に従うか、他のパートを聴いて自主的に判断する。
特に強調したい時に行うスタンドプレーは、寧ろ推奨される。
木管グループはステージ上の移動も可。
Part II 後半、指揮者の合図で練習番号Eのハチャメチャに入る。
最初は音数少なめで徐々に音数を増やし、盛り上げる。
但し、短い突然のスフォルツァンドは推奨される。
ホイッスルが聴こえたらそろそろ Part IIは終了する。
鞭の音を合図に Part IIは終了する。
6つのグループに分かれる、と記載されていますが具体的には以下の通りです。
グループ1:ピッコロ、フルート、クラリネット属
グループ2:サクソフォーン属
グループ3:ホルン、トランペット
グループ4:トロンボーン、ユーフォニアム、テューバ、コントラバス
グループ5:打楽器群
グループ6:ヴィブラフォン、ピアノ
それぞれテンポの指定、拍子、調性など微妙に異なります。これが前半で単語の意味に触れた「ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズム」を用いた部分な訳です。
「みんなやっていることが違うのにそんなのどうやって合わせるの?指揮はどうするの?」と思うかもしれませんが、答えは「各グループで良い感じにアンサンブルして合わせる!」です。これが曲名の「多次元的ミクロアンサンブル集合体」を表しています。
ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズムを用いて各グループ良い感じにアンサンブルする、というアイディア自体はオーケストラでも古くから使われています。有名な例だとニールセン作曲『アラジン組曲』の5曲目「イスパハンの市場」です。
この楽曲は最初はオーボエ、イングリッシュ・ホルンなどのグループのみで演奏されていますが、しばらくすると全く異なるテンポで弦楽器が入ってくるのが分かるかと思います。(7:30ごろ)
そして、続けて金管楽器などのグループが加わり(8:15ごろ)、最後ピッコロが加わる(9:00ごろ)という仕掛けになっています。
4グループ同時に演奏される部分はなかなか凄いことになっていますね。笑

赤枠のグループ1は曲が終わるまで何回も繰り返し。

青枠のグループ2はグループ1の次に演奏を開始し、グループ1より先に演奏を終える。

黄枠がグループ3、緑枠のグループ4。
グループ3は2の次に演奏を開始し…(以下同様)
このように、『アラジン組曲』の5曲目「イスパハンの市場」は作りとしては似ているものの、天野正道『白檀』はこれより2つグループが多く演奏順も奏者側に委ねられている訳ですから遥かにカオスです。
こうやって書いてみると何だか難しそうに感じますが、意外と子供たちの方が頭が柔らかかったりするので『各グループで良い感じにアンサンブルしてみて』というざっくりな楽譜でもすんなり合わせられてしまうのだと思います。
(むしろ大人たちの方がこの手の楽譜を難しく考えすぎてしまうのでしょうか…?)
カオスなPart2ではありましたが笛と鞭の音を合図に終了し、Part3移ります。
Part3
Part3冒頭はPart1でも聞こえてきたハーモニックパイプの音で始まります。ハーモニックパイプの音が鳴りやむとピアノの伴奏の上でジャジーなソロがバリトン・サクソフォン、フルートなどによって奏でられます。
ジャジーなソロが終わるとPart1で演奏されていた金管楽器の打ち込み系のリズムが再び演奏されます。このあたりは他の天野正道作品でもあるあるな雰囲気の音楽なので、現代音楽の雰囲気を楽しみながらも天野正道作品らしさも楽しむことが出来ます。
曲の後半、各楽器が即興的に好き勝手演奏する部分を経て一瞬の静寂が訪れます。ヴィブラフォンが静かに壊れたオルゴールのようなメロディを奏でてそのまま静かに曲を閉じる…かと思いきや結局ハチャメチャで終わる。というドタバタ劇のような内容になっています。笑
■収録CD
冒頭に参考音源として紹介した加養浩幸指揮/海上自衛隊東京音楽隊の演奏は以下のCDに収録されています。
演奏自体はどちらも同じなので、CD自体の値段やカップリングの曲の好みで選ぶのが良いかと思います。
■最後に
現代音楽・前衛音楽の吹奏楽作品は巷に溢れかえっているとは思いますが、天野正道『白檀』は
25人程度という小~中編成での演奏が可能で
極端な高音域、低音域や超絶技巧を使わず中学生でも演奏可能な技術で
ポリテンポ、ポリトナール、ポリリズムといった現代音楽でよく使われる要素や様々な道具を使用した擬音、効果音での表現を学ぶことが出来て
前衛的な部分だけでなくポップな音楽も含んで親しみやすい、聴きやすい部分を含んで
それでありながら7分という短い時間の中で自然にまとまっている
という点が優れていると思います。冒頭でも書きましたが『現代音楽入門』としてピッタリな作品だと思います。(もっと演奏されても良いのに…!)
楽譜はCAFUAレコードよりレンタルされています。スコアもサンプルの透かしはあるものので全ページ閲覧可能なので興味を持たれたら以下から楽譜を見てみると面白いかと思います!
