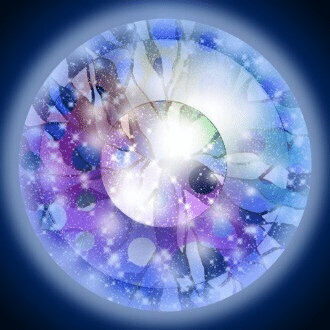~イラ立ちやストレスとの付き合い方~
![]()
皆さん、どうも!! にゃむですっ♬ お元気ですか?(・∀・)あはっ♬ 最近、雨が降る日が多くなり、低気圧のせいで頭痛に悩まされるなんてことがちょいちょいあるにゃむ。 今回はね、そういう意味での頭痛ではなく、普段の生活においてイライラしてしまったり、ストレスを感じて疲労感が蓄積してしまったりする多くの人たちに向けて、どんなふうにイライラやストレスと向き合っていけばいいのかについて触れていきたいと思うにゃむ♬
![]()
ボクはね、イライラやストレスを【NOISE~ノイズ~】と表現するんだ。 ノイズっていうと音声なら「ザザザザッ・・・ザザッ・・・」てな感じの雑音が入ることを言うよね? 映像や画像なんかでも画質が悪く、解像度が低いとキレイに映らなかったりする。 人は日々の生活において、何かにつけこのノイズをキャッチしてしまう。 そう、人が普段からキャッチしてしまうほど、精神的平穏を阻害するイライラやストレスといったノイズはそこら中に存在しているのである。 この自覚こそ、意識の中に留めておく必要があると考える。
季節的に、シーズンは梅雨。 高い湿度によるじめじめと暑さが、素晴らしいほどにマッチして不快指数を上昇させる。 これも一つのノイズと解釈できる。 こんな季節に、例えば、朝の通勤ラッシュの時間帯、コンビニのレジ前には長蛇の列ができていて、数分では自分の番が回ってこない状況をイメージしてほしい。 そんな時に、店員が会計処理をチンタラやっていたり、対応や商品の扱いが乱雑だったりすると、ただでさえ不快指数が高いこの季節、条件が一つまた一つと揃う度に、客のイライラは加速的に高まっていく。
そして中には、耐えきれずに怒りが爆発してしまい、大声を張り上げて店員に怒鳴りつけてしまう人もチラホラと見かける機会がある。 それだけではない。 そんなふうにあーだのこーだのと喚き散らかしている横暴な態度の客に対して、後ろに並んでいる客がさらにイライラを募らせる始末。 「いい加減にしろ! 後ろが待ってんだよ!」と言わずにはいられない人もいるかもしれない。 イライラはそんなふうにして連鎖するのである。 しかし、考えてもみてほしい。 彼らは、その時にはすでに「イライラの原因」を考えることを放棄しているのである。
イライラの原因は何か。 店員の会計処理が遅いせい? 長蛇の列ができていて待ち時間が長いせい? 店員に対して喚き散らかしている客のせい? 違う。 この3つのどれもイライラの原因ではないのである。 もともと不快指数が高いじめじめした日であり、尚且つ、時間帯は朝の通勤ラッシュ。 このタイミングでコンビニに入り、朝食を買おうとして長蛇の列に並んだ人の選択思考、これこそがイライラの原因なのである。 毎朝の習慣で、いつものようにコンビニで朝食を買う人の選択行動によって、自らイライラする条件下に身を置いたことがイライラの本当の原因なのである。
![]()
何かっていうと人のせいにする人、何かっていうと状況のせいにする人は、自分の選択思考そのものを疑うことをしないため、日頃からイライラする機会が多く、自らストレスを生み出していることに気付きもしない。 実に滑稽な話である(笑) このイライラを解消するための選択行動とは何か。 そんなことは言うまでもなく、毎朝の習慣を別の行動に変えるだけでいいのである。 朝食を自宅で済ませてから出かけるとか、朝の通勤ラッシュの時間帯でも客数が比較的少ないコンビニを選ぶとか、前日のうちに翌朝分の朝食を買っておくなど、方法はいくらでもあるのである。 しかしながら、習慣とは恐ろしいもので、たとえ自身がイライラする条件下に身を置くとしても、毎朝の行動を変えようとしない「選択思考の手抜き」をしたがるのも人間の性なのである。
確かに、選択思考というのは毎日一定で同じであるならば、行動そのものも考える必要がないため楽なのかもしれない。 しかしながら、イライラするような状況に直面しても行動を変えようとしないのは、全て自分の責任なのである。 コンビニ店員のせいでもなければ、喚き散らかしている客のせいでもないということが断言できる。
そして、毎朝の習慣は、その日一日の過ごし方すら左右するとも言われている。 早起きは三文の徳と言われる所以はそこにある。 如何にして、その日のノイズを避けて過ごすかは、毎日の朝という時間帯にかかっていると言っても過言ではない。 起きるのが遅くなり、始業時間に間に合うか、間に合わないか、心臓をバクバクさせながら走って会社に向かう、そんな経験をしたことがある人はたくさんいるだろう。 そんな時、始業時間に間に合おうが間に合うまいが、アドレナリンが分泌された状態ではまともに思考が働くわけもなく、スムーズに業務にとりかかることは難しいだろう。 おまけに、遅刻して上司に怒られてしまおうものならば、一日は台無しになったと言ってもいいくらいにモチベーションは下がってしまうことだろう。
![]()
そんな、当たり前とも思えそうなことが自覚できていない状態では、無駄にストレスを感じイライラする機会を増やすだけで、何も良いことはない。 では、一体誰がその自覚を持たせてくれるのだろうか。 身の周りにいる人たちのうち、親身になって声をかけてくれる人でもいるだろうか。 否!! ポジティブな思考やモチベーションを高めてくれる人などそう滅多にいるものではない。 そういう人がそばにいるという人は、ただそれだけで幸せ者であり、何を言う必要もあるまい。 じゃあ、どうすればそんなイライラデイズから抜け出せるのだろうか。 (イライラデイズwww まるで地獄だなwww ストレスフルデイズを過ごしている人たちは本当に可哀そうだ。)
ノイズだらけの社会を生き抜くためには、少しでもストレスを軽減したり、イライラする機会を避けて過ごす、そういう意識付けが求められるのではないだろうか。

※ 【ハーバード流ボス養成講座】/定価:2,000円(税抜)/発行所:日本経済新聞出版社
本日、ボクはこの本を3冊購入した。 大型ショッピングモール内にある書店に、今から1週間前に取り寄せの注文をしておいたのである。 2012年初版のこの書籍を、その書店は置いていなかったのである。 結構規模の大きい書店であるにもかかわらずここに置いていないということは、この書籍の存在を知っている人もほんのわずかしかいないのかもしれない。 買おうと思って立ち寄った日、ビジネス書が置かれているエリアを何度探してもないため、店員に聞いたところ「お取り寄せに1週間ほどのお時間を頂きますがよろしいでしょうか。」と言われたため、その場で手続きをしたのである。
手に入れたばかりでボクもまだ読んでいない。 にゃむ父と電話で話していてこの本の存在を知ったのだが、この1週間がとても長く感じたものだ・・・(っておいおいおい!! こらっ!! 急に話が飛んでしまってるじゃないか!! どういうことだっ!!) まぁまぁ、落ち着きなさいな♬ 今からなぜこの本を買ったのか、そしてなぜ3冊も買ったのかについて触れていくよ♬
![]()
自慢するつもりはないし、自慢したところで何の意味もないのだけれど、にゃむ父が読む本のジャンルの幅も過去読んできた本の数も、おそらくは一般の誰よりも圧倒的過ぎて、尚且つ、何を質問しても即具体的に説明できるほど知識も豊富であり、ただ具体的なだけではなく、裏付けまでしっかりした説明ができる上に、ある程度の予測を可能にする、謂わば【歩く図書館】みたいな人なのである。 そんな父が絶賛する本が【ハーバード流ボス養成講座】なのである。 せっかく自分の父が教えてくれた本を読まないわけにはいかない。 内容は難しいかもしれない。 これまでこういう類の本をそれほど読んできたわけではないし、読めない漢字や文章の難易度によっては理解できない部分もあるかもしれない。 だけど、読んでみたいという好奇心のほうがずっと勝った。
昔から「本を読め、本を読め」と、文字数にしてたった4文字の言葉を、耳にタコができるくらいに聞かされてきて、今では本の素晴らしさを実感してはいるものの、まだまだ足りない。 活字中毒になるくらいに本を読みたい。 そう思っているボクがこの本を手に入れ読むことで、きっとボクの思考は新しい回路を作ることができるかもしれない。 その点に対する期待感がこの本を買った理由に相当する。
では、なぜ3冊も買ったのか。 それほどの本をボクが読むだけで最大限に活かせるだろうか。 まずもって自信がなかったし、ボクには読んだ本を今置かれている環境でのびのびと活かす機会がないことにも気付かされた。 だから、別の部署で仕事をしているほぼ同世代の知人に貸してみようと思い立ったのである。 もちろん1冊はボクが読むわけだが、残りの2冊は2人の知人に。 2週間だけ貸すよ、という前提条件を説明した上で渡すつもりだ。 およそ400ページの本であるため、もし彼らが普段から本を読む習慣がないのだとしたら、2週間では読み切れないかもしれないし、全体の8割以上を理解することは困難だと思われる。そこで、2週間経った時に、ボクは彼らに質問を用意しているのである。

どこまで読み進めたかに関わらず本人の意思を確認し、彼らが「欲しい」と言った時には、タダでは譲らない。 税込み2,160円のうち半分、1,080円でその本を譲るという2つ目の条件を提示する。 一切の金銭を投じずに手に入れるモノというのは、残念ながら大事にはされない。 お金をかけるからこそ、モノを大事にしようとする。 その「人間の本質」に従って、彼らには半額でこの本を渡そうと思う。 まだボクも読んでいないため憶測の域を超えないが、きっと彼らがこの本を読み進め、脳にインプットし、仕事に活かせるようになった時、支払った1,080円が何倍何十倍もの価値へと高まると期待する。 なぜなら、彼らにはインプットした知識を活かす機会がボクよりも圧倒的に多いからである。
ボクがこの本を渡した相手が、この先、どんなふうに仕事をするようになり、仕事についてどんな話し方をするようになるのか、その変化を見てみたい。 無論、ボク自身も読み、理解に努め、極力彼らとの会話に役立てるようにしていきたいところ。 今ターゲットとしているのは、20代30代の若い3人だけれども、ボクのこの取り組みのゴールはそれでは終わらない。 この本に対する期待値ばかりが高くても、革命級の変化、つまり職場に変革が起こらなければ満足できない。 この本は安くはない。 ボクの給料じゃ毎月2冊が限度であり、今月3冊買ったことは目先の生活をやや圧迫するほどだ(笑)
そこで、ボクは、noteを閲覧してくれている方々やTwitterのフォロワー様に資金提供を呼び掛けたいと考えている。 もちろん、協力をしていただいた方々にはSNS上で可能な限りの還元を実施したい考えでいる。 例えば、note投稿者の多くは、自身のnoteをより多くの方々に閲覧してもらいたいと願っているに違いない。 noteユーザーによる資金提供を得られた際には、そのお返しとして、ユーザー紹介も兼ねてnoteのシェアを積極的に実施していきたい考えでいる。 しかもこれは、ボクからの紹介だけでなく、他ユーザーに資金提供者のnote紹介の協力を仰ぐことも含んでいる。 如何なる形であったとしても、協力をしていただける方は多いに越したことはない。
また、提供して頂いた資金を書籍購入に充当し、ボクが本を貸し与えた人たちの声を集めたレポートを作成し、noteにおいて公開するという取り組みも検討中。 金銭的に、ボク個人の利益は1円もない。 ただただ、素晴らしい本を一人でも多くの人に読んでほしい。 今の社会、ペーパーレスが進み、本を購入する人が減ってきており、多くの人たちがネット上の書籍ダウンロードアプリを利用するようになっているため、出版業界は厳しい状況に追い込まれているのが現実。 それでも、「本を読むなら現物がいい!!」といったこだわりを持つ人もいる。 それくらい本を好きになるきっかけを、ボクのアカウントがそのポータルとなって広めていきたいと考えている。
![]()
ボク個人の金銭的利益は1円もない。 ボクのアカウントは、もしかすると「定価の半額で素晴らしい本を多くの人たちに読んでもらうアカウント」に成り得るのではないかと思い始めている。 事業として成立させるためには、より多くのプロフィットを得なければならないものの、利益が先行し過ぎてしまっては本来の目的から逸脱してしまいかねない。 こういう取り組みを実行していく中で、知恵を貸して頂ける方がいるならば、是非ご協力いただきたい。 まずは、自分の身の周りから攻めてみようと思う。 この取り組みによって、安くで素晴らしい本を読む人たちが増え、知的な人物を増やすことができたなら、「変革を起こす大元にはにゃむがいた」そんなふうに陰で働きかけた甲斐が生まれるのではないだろうかと、そこまで想像を掻き立てられている。
本とは、紹介するだけなら誰でもできる。 しかし、金銭を投じて本を買い与えるということは簡単ではない。 でも、世の中には素晴らしい本がたくさんあるというのに、それを読むことなく今を生きているということに対し、もったいない思いしかない。 ならば、多少の身銭を切ったとしても、多くの方々のご協力の下、一人でも多くの人たちに安く買い与え、読んでもらうことが可能ならば、やらない手はない。 そのことに気付かされた。 どれほどの協力を得られるかはわからないけれど、やれるだけやってみようと思う。 ダメならまた一からやり直せばいいだけのこと。 組織に偉人の才やノウハウを、ワクチンとして投与し、悪習や大して効果の得られない取り組みを辞め、無駄な会議やミーティングを減らしていくことができれば、企業のコストパフォーマンスは上がるはずである。
組織が人で成り立っている以上、人が学ぶことを放棄し、これまでの習慣や仕来りに固執すれば組織の成長は期待できない。 現状把握ができる人材が考え、変化を加え成果を見出せる人材へと成長していく、そういう人材が一人でも増えていけば、組織全体が変わっていく。 現状に満足しない、ハングリー精神の強い人間にこそ、本を渡したい。
職場におけるイライラやストレスといった精神的なノイズをどんなふうに処理していけばいいのか、それはこの本を読めばきっとヒントが見えてくるだろうと思われる。 上司との関係や部下との関係におけるヒント、チームを構成し引っ張っていくためのヒントがね。 知り得た知識を活用し、自身で体感した時に、「この本を読んで良かった」と思える時が必ず来るとボクは信じている。
![]()
最後に、一言。


【にゃむのTwitter】

いいなと思ったら応援しよう!