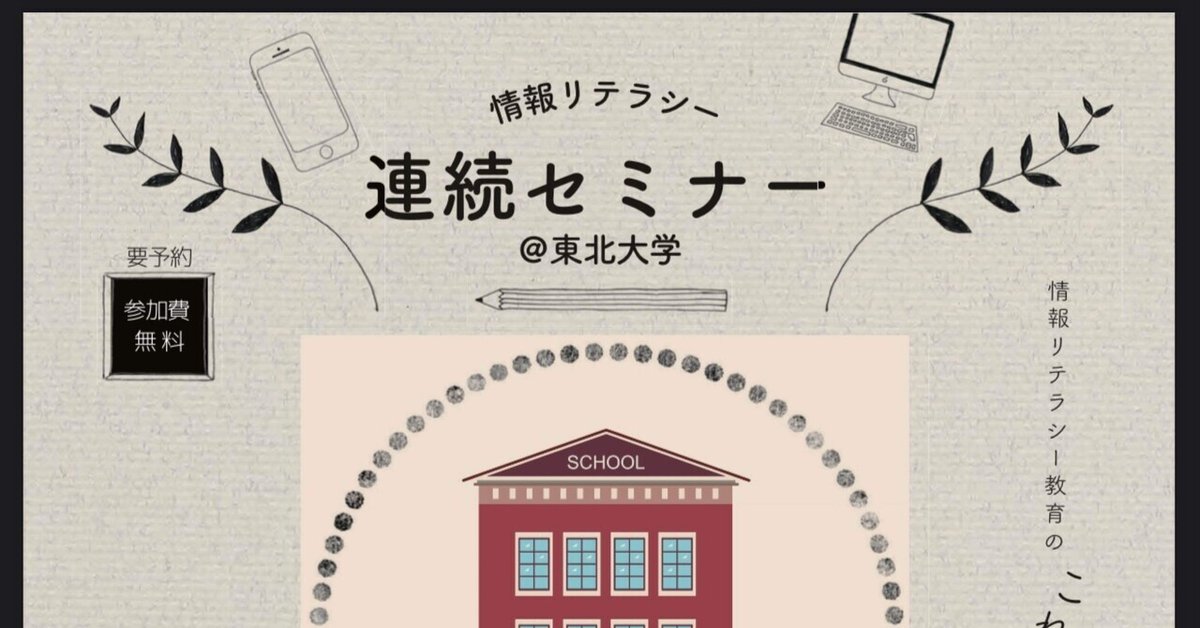
教育YouTuber「とある男が授業してみた」葉一さんの講演に参加して
2021.7.10
東北大学情報リテラシー連続セミナー By教育YouTuber葉一さん「とある男が授業してみた」
普段、時々講義動画をみたり、自習室(LIVE)に参加して勉強させてもらっていた葉一さん。
こちらの連続セミナーも、3月に私が通う大学の先生が講師を務めて以来2回目の参加。
今回は運良く質問させてもらい、葉一さんと直接(オンライン通して)会話出来たこと、熱い講演を聴けたこと、感動でした。
そんな感じで気持ちが昂っている中の、支離滅裂な感想です。
お許しください。
授業づくりについて
これから先生に求められる、オンライン授業のやり方・工夫だけでなく、普段の授業づくりでも大切にしていくべきことを学んだ。
「授業動画を見終わった子どもたちに何を残すのか。」
「余計な話は削ぎ落とす。」
「ネット社会にいて耳と目が肥えてる現代の子どもたちにとって魅力的な授業をすること。」
「100点のクオリティを目指すのではなく、80点のクオリティを目指すこと」
「子どもの集中力を考え、授業動画は15分以内で。」
「授業の終わりが見通せるよう、板書はホワイトボード1枚のみ。」
教育について
『授業とはこういうものだ』『公教育とはこういうものだ』というものはなく、子どもたちが学びやすい、生きやすい環境に応じて変えていくべき。
だけどトップダウンの学校社会を中から変えていくのは大変な現実…
伝統を重んじる文化は素敵な事だが…
考えたこと
公教育、民間教育(塾等)、そして無料コンテンツによる教育(YouTubeなど)の3本柱で互いに補完しあえるのではないか。
そこで出てきた議論「強制力」
YouTubeで勉強することは「強制力」がない。
やる気のない子は動画をクリックさえしない。
じゃあ学習の「強制力」を学校が担えば良いのか?
学校が本来担うべきことは、「強制力」ではなく、「子どもたち自身が継続的に能動的に学び続ける力を育てること」だろう。
学校からでても持続可能な学ぶ力を身につけることは不可欠だろう。
自由な教育について
例えば、葉一さんのYouTubeチャンネルの講義動画を学校の授業で活用するアイデアが浮かんだ。
授業の冒頭で葉一さんの動画を流して、問題の解き方や知識を先に子どもに与える。
その後で、「なぜこの答えになるのか。」「なぜこの解き方が正しいのか。」という観点で、思考・判断・表現活動をさせる。
いわゆる「反転学習」だ。
このような従来の一斉指導とは異なる自由な学習形態は、現在の学校でどのくらい受け入れられるだろうか。
まだまだ受け入れられない厳しい現実が容易に想像できる。
私は近い将来教壇に立つだろう。
厳しい現実に抗っていきたい。
