
銀河フェニックス物語【出会い編】 第三十一話 恋の嫉妬と仕事の妬み (まとめ読み版①)
・物語のスタート 第一話「永世中立星の叛乱」
・第一話から連載をまとめたマガジン
・第三十話「修理のお礼は料理です」
フェニックス号に乗ったティリーは、気分が落ち着かなかった。
「わぁい、両手に花だぜ」

レイターは、わたしと後輩のサブリナの顔を交互に見て笑った。
わたしたちは、ヨマ星系の大手洗剤メーカー「コッペリ社」へ向かっている。
たまたま同じ時間に、別々にアポイントが入った。
サブリナが明るい声で挨拶する。
「レイターさん、厄病神が出てこない様に、よろしくお願いしま〜す」
今回、彼女は新型船七隻の契約を締結する。大きな仕事だ。厄病神の船には乗りたくなかっただろうな。
サブリナがわたしに話しかけた。
「ティリー先輩、わたし、仕事でフェニックス号に乗るの初めてなんです。いろいろ教えてくださいね」

「ホストコンピューターのマザーに聞けば何でもわかるわ」
ぶっきらぼうに答えてしまった。
「俺が、手取り足取り教えちゃうよ」
おちゃらけながらレイターが言った。
「荷物、整理してくる」
わたしは自分の船室へと向かった。
*
気持ちを落ち着けよう。
今回、後輩のサブリナは船の多数購入契約。
一方、わたしは、フレッド先輩に頼まれて、資料を受け取ってくるという雑用仕事。
サブリナは要領がいい。
元々、コッペリ社へはわたしたち営業企画課が、フレッド先輩を中心に新型船購入の話を持ち込んでいた。
ところが、先方の担当者が誤って隣の法人営業課に問い合わせをし、たまたま窓口となったサブリナが、トントンと話を進めてまとめてしまった。
わたしたち営業企画課は面白くない。陰では契約を横取りしたサブリナの悪口が飛びかっていた。サブリナは営業成績がいい。
はあぁ、ため息をつく。

サブリナはすぐ下の後輩。
わたしは彼女のメンターに選ばれ、入社当時、社内のことを教えた。明るくて、よく気が付くサブリナ。わたしは彼女が好きだった。
サブリナが初めて契約を取った時は本当にうれしくて、祝勝会を開き、彼女に夕食をおごった。
「ティリー先輩、ありがとうございます。先輩の様になれるようにわたし、頑張ります」と言われて喜び、そんなサブリナをかわいく思った。
けれど・・・。
サブリナが隣の課で月間賞を取ったあたりから、素直に喜べなくなった。
サブリナは変わらない。
「ティリー先輩のおかげです」と明るく話しかけてくる。
*
学生時代の出来事が頭に浮かんだ。思い出したくない記憶。
化学が苦手だと言うクラスメートに、わたしはテスト前、一生懸命教えた。
テストが終わってみたら彼女の化学の成績は、わたしより良かった。
たったそれだけの小さな話。
「ティリー、ありがとう」と礼を言う彼女に「今度はわたしに教えてね」と明るく笑顔で応えた。
けど、心の中は違った。
悔しさと恥ずかしさと苛立ちが入り乱れ、彼女がわたしをあざ笑っているように感じた。教室で彼女の顔を見るだけで気持ちが塞いだ。
そんな自分が嫌だった。彼女は何も悪くない。力が足りなかったのは自分だ。頭ではわかっている。
なのに、彼女が恨めしいという気持ちを振り払えない。
あのどす黒い感情。
誰にも知られたくない自分。しばらく忘れていたのに。
*
わたしは営業企画課で、サブリナは隣の法人営業課。
部署が違っていてよかった。
「契約取れちゃったんです」と笑顔で報告するサブリナ。同じ課だったら「おめでとう」と言う余裕がなかっただろう。
今では社内事情もわたしより詳しい。プライベートでは研究所に勤めるジョン先輩という彼氏もいる。

どこで差がついてしまったのだろう。
*
今回、コッペリ社へ厄病神の船で行くことが決まって、隣の席のベルに言われた。

「良かったじゃん。契約だったら厄病神の船じゃがっかりだけど、どうせ頼まれ仕事でしょ」と。
フェニックス号で仕事に出かけると、失敗するというジンクスがある。
これまでにわたしも大規模デモに巻き込まれたり、環境テロに襲われたり、散々な目に遭ってきた。
ベルの言葉を聞いてわたしは、恐ろしいことが頭に浮かんだ。厄病神の船で出かけて、サブリナの契約が失敗すればいいのに、と。
頭を思いっきり左右に降る。
そういう事を考えていると、自分が失敗するのよ。とにかく、わたしは自分の仕事をしっかりやり遂げなくては。
と、気合を入れてさらに落ち込む。
そんな大層な仕事ではないのだ。
わたしの仕事は、コッペリ社の事業計画資料を受け取ってくる、というもの。
「大事な資料だから。よろしく頼むよ」

と、フレッド先輩は言ったけれど、はっきり言って誰でもできる。
頭が重い。眉間の奥がツンとする。骨に皮膚が張り付いてしまった様な嫌な感じ。
頭痛、いや、これはストレスだ。
*
「食事できたぜ」
インターフォンからレイターの声が聞こえた。二人と顔を合わせたくないな。
ふぅ〜。きょう何度目かわからないため息をつきながら、わたしはゆっくりと腰を上げた。
「すごいですね。フェニックス号のキッチンは」
エプロンをつけたサブリナが興奮している。
「わたし、料理が好きなんです。炎が出るコンロ、憧れです」
フェニックス号には電磁調理器の他に、業務用のガスコンロがある。サブリナは素直に話しているだけ。
わかっている、悪意はない。なのに、料理が下手なわたしへの当て付けに聞こえる。
「料理好きの彼女を持って、食いしん坊のジョン・プーは大喜びだろ」

「わたしの手料理、なんでも、喜んで食べてくれるんですよぉ」
明るくのろけ話を聞かされる。
「今日の生姜焼きは、サブリナさんのお手製だぜ」
レイターがダイニングテーブルへお皿を運んできた。
ジンジャーの香りが漂う。
三人で食卓を囲み、サブリナの作った熱々の生姜焼きを口にする。
しっかりとした味付け。レイターの調理とは少し違う。
「おいしい」
思わず声が出た。

「ティリー先輩、ありがとうございます。やっぱり、火で炒めるのは違いますね。それに、包丁もそろっていて、レストランの厨房みたいです」
「俺、調理師免許持ってるから」
レイターが自慢げにサブリナに伝える。
「プロだったんですか。納得です」
「サブリナさんは、あすの晩はジョン・プーと祝勝会かい?」
「はい、ソラ系のお店を予約してます」
サブリナがにっこりと笑う。
大型の契約を取って、彼氏と祝勝会のディナー。羨ましい限りだ。
「店なんて予約しなくても、俺がプロ並みの料理作ってやったのに。ヨマ牛はうまくて有名なんだぜ。土産に買って帰ろうと思ってんだ」
「どうぞ、ティリー先輩と食べてください」
「そうするかい、ティリーさん」
普段はのんびりできるフェニックス号の居心地が悪い。頭痛がひどくなってきた。
「ティリーさん、どうした?」

レイターがわたしをじっと見た。
「な、何でもないわ」
わたしはあわてて答えた。
「お二人さん、あしたは、朝九時半に船を出るからな」
「よろしくお願いします」
サブリナが頭を下げた。
「サブリナさんが七階の開発管理課で、ティリーさんが十五階の経営総務課だよな。俺、サブリナさんについて行くけど、ティリーさん大丈夫かい? あんた方向音痴だから」
馬鹿にされている。
「大丈夫です。サブリナの契約の方が大切でしょ」

と言ってから、自虐的な発言だったと気付いた。
レイターは気にするでもなく明るく言った。
「じゃ、ティリーさんは仕事が終わったら、一階のロビーで待っててくれ」
どう考えても、サブリナよりわたしの仕事の方が早く終わる。
どうしてサブリナの契約の日に、こんな仕事頼まれちゃったんだろう。
*
翌日、レイターに連れられ、サブリナと一緒にコッペリ社へ向かった。
コッペリ社の自社ビルは、古めかしい石造りの建物だった。今時珍しいけれど、老舗らしいと言えば老舗らしい。
コッペリ社は、創業ニ世紀の大手洗剤メーカー。
去年発売した速乾洗濯洗剤のフイールが爆発的に売れて、今、話題の企業だ。とにかく洗濯物がすぐ乾くのだ。新技術を採用した、というその洗剤を、わたしも使っている。
白い液体洗剤のフイールはクールな香りがする。洗濯機にかけてから自動でクローゼットに並ぶまでの時間が圧倒的に速い。家事の時短は助かる。
「ティリーさんは、仕事が終わったらここで待っててくれ。迷子になるなよ」
「迷子になんてなりません」
一階ロビーの待ち合わせ場所を確認し、レイターたちと別れた。
最上階の十五階。
レイターが言うようにわたしは方向音痴だ。でも大丈夫、このフロアはドアが少ない。
経営総務課と書かれた看板をしっかり確認し、インターホンを押す。
「クロノス社のティリー・マイルドです。十時のお約束で参りました。バッハさん、お願いいたします」
「はいはい、バッハです」

観音開きのドアを開けて、年配の男性が出てきた。優しそうな人だ。カウンターの奥のオフィスにはほとんど人がいない。
「こちらへどうぞ」
資料を受け取るだけだと言うのに、応接室へと案内された。
「温かいお茶はいかがですか?」
笑顔で勧められると、断るのも悪い気がした。
「いただきます」
バッハさんは棚からカップを取り出し、丁寧にお湯で温め始めた。
「フレッドさんから、話は聞いていますよ。資料はこちらです」
ディスクの入った小さな封筒パックを受け取る。
「ありがとうございます」
仕事は終わった。
「わざわざご足労すみませんねえ。フレッドさんには転送する、と言ったんですけどね」
バッハさんの何気ない言葉がわたしを傷つける。転送できる程度の資料ということだ。
でも、せっかくここまで足を運んだのだ、フレッド先輩の狙いは、顔を合わせて営業してこい、ということじゃないだろうか。
「折角ですので、ほかの皆さまにも、ご挨拶させていただければと思いますが、いかがでしょうか?」
わたしの提案に、バッハさんが申し訳ないと言う顔をしながら、ティーポットに茶葉を入れお湯を注ぐ。
香ばしい香りが立ち上る。
「皆、忙しくしてましてね。出払っているんですよ。僕は来月定年で、のんびりさせてもらっているけれど」
フイールの大ヒットで外に出ている人が多いのだろう。オフィスは閑散としていた。
ゆっくりと蒸らして抽出したお茶を、バッハさんが回転式の茶こしを手にしてカップに注ぐ。
仕事中と思えない優雅な時間。
『窓際族』と言う言葉が頭に浮かんだ。お茶を入れてくれるのも、話し相手が欲しかったのでは、と勘ぐってしまう。
真っ白なティーカップに、透き通ったオレンジ色のティーが映えていた。
ほのかな苦みと甘い香りが、苛立っていた気持ちを落ち着ける。
「おいしいです」

バッハさんがにっこりする。
「ゆっくりしていって下さい。今回は残念でしたね」
「え?」
「新型船の契約が、隣の課に決まったと聞きましたよ」
フレッド先輩から聞いたのだろうか。
「弊社から船をご購入いただき、感謝しております」
当たり障りのない応対をしておく。
「この部署へ来る前は営業の第一線にいましてね、私は他社より自分の社の同僚に契約を取られるのが嫌でしたよ」
そう言ってバッハさんが笑った。
サブリナの顔が頭に浮かんだ。

「そのお気持ち、わかります」
つられてうなずく。
「でも、御社の担当者の女性は、丁寧な仕事をされていたようですからね」
サブリナが途中から契約を横取りしたことは知らないのだろう。
わたしはお茶を一口口にして、話題を変えた。
「フイールは素晴らしいですね。わたしも使っています。働く女性の強い味方です」
「ありがとうございます。いい商品でしょ。私は女性だけでなく男性にも評価されているのが嬉しいんですよ」
バッハさんに好感を持った。
家事のほとんどは自動化されているけれど、どちらかと言えば女性が担当することが多い。
家事ができて困ることはない。わたしだって、できた方がいいとは思うけれど、押し付けられるのには抵抗がある。
料理や手芸が得意な女の子は人気がある。わたしはどちらも苦手だ。
料理上手なサブリナの影が頭にちらつく。
今は仕事中。クライアントとしっかり向き合わなくては。
「フイールの大ヒットは、男性客を取り込めた点にあるんでしょうか?」
「そうですね。でも、いい製品もここまで売れると営業としては面白みに欠けますな」

「そうですか?」
「私は、売れないと言われていた洗剤を売った時が一番嬉しかったですよ。営業冥利に尽きますからね。何もしなくても売れてしまっては、営業の出番がないじゃないですか。ははは」
今のわたしには贅沢な悩みに聞こえた。
それにしても、バッハさんは話し上手な人だ。優秀な営業マンだったのだろう。つい、しゃべりこんでしまう。
とその時、
リリリリリリ・・・
火災報知器の音がした。耳障りな音だ。
首をかしげてバッハさんが立ち上がった。
「火事ですかね」
嫌な予感がする。

厄病神の顔が頭をよぎった。
* *
レイターは、サブリナとともにコッペリ社の七階の廊下にいた。
「こちらへどうぞ」
円柱形のボディーに球体の顔が乗った旧式の受付ロボットが、開発管理課のドアを開け、サブリナさんと俺を会議室へと案内する。
さすが今話題の企業。活気あふれる職場ってやつだ。
管理セクションと営業が隣り合わせのこのフロアは、通信機の着信音と忙しそうな会話がオフィスに響いている。
アーサーに集積カメラを極秘に設置しろ、って言われたのが、ここコッペリ社七階の開発管理課。この部署は速乾洗濯洗剤フイールの企業秘密を管理している。
俺は部屋に入る際、ドアの横にこっそりと直径五ミリの集積カメラを張り付けた。ちょろいもんだ。
これで俺の仕事は終わり。あとはアーサーの仕事だ。

去年発売した速乾洗剤フイールは画期的だった。
落ち込んでいたコッペリ社の株が急騰し、フイール特需でこの本社ビルを建て替えるという噂があるほどだ。
確かにこのビルのセキュリティは甘すぎるな。
月の屋敷でかわした、アーサーとの会話を思い出す。
敵のアリオロンがフイールの開発資料を狙っているという。
「フイール? よく乾いて便利な洗剤じゃん。俺も使ってるぜ」
「連邦軍でも導入している。速乾は戦地でも有効だ」

「それをアリオロン軍も導入したいってか? 金出して買えよ。買う金がないのかよ」
「そのようだ」
「あん?」
「冗談だ」
と言ってからアーサーは眉間にシワを寄せた。
「理由がわからないから、探るんだ」
速乾洗剤フイールは、企業秘密ということで原料も製法も明らかにされていない。
そのフイールの資料が入ったデータ金庫に、先日アリオロンのハッカー集団による不正アクセスがあった。
が、最新のセキュリティシステムが機能し、奴らは入れなかった。
アリオロンは情報入手をあきらめてないらしい。
ということで、今度はコッペリ社の本社にある現物の資料を盗みにくる可能性がある、という古典的な話だ。
開発管理課の耐火ロッカーの中に、社員が使えるようデジタルペーパーの資料が保管されているという。
あの壁面ロッカーがそれだな。
俺が張り付けた集積カメラの撮影範囲にばっちり入ってる。
社員が帰る時には三重のロックをかけてるそうだが、勤務時間中の今なら暗証番号キーだけだ。俺でも盗めそうだぞ。闇で高く売れそうだ。
オフィス内を横目で見ながら、サブリナさんと一緒に奥の小さな会議室へ入る。
受付ロボットは人工アームを使って俺たちにお茶を出した。紙コップに入ったインスタントの作り置き茶。
「誠に申し訳ありません。担当者が少し遅れます」
感情のこもっていない声で、俺たちに謝った。
* *
この人のことは、よくわからないな。後ろからついてくるレイターをちらりと見ながらサブリナは思った。
彼氏であるジョンとは学生時代からのつきあいで、セントクーリエの出身。
料理も上手で、使える人物なのは間違いないのだけれど、どこかつかみどころが無い。
「誠に申し訳ありません。担当者が少し遅れます」
旧式の受付ロボットが、わたしたちにお茶を出しながら謝る。
わたしたちは、安っぽいお茶を飲みながら担当者の到着を待った。
すっかりくつろいでいるレイターさんに話を振ってみる。
「ティリー先輩、大丈夫でしょうか?」

「あん?」
「昨日、先輩の様子がおかしかったので」
「サブリナさんは気がついてるんだろ、ティリーさんの元気がなかった理由」
レイターさんがニヤリと笑った。鋭い人だ。
「わたしのせいじゃありません」
「もちろん、ぜ~んぶ、フレッドのせいさ」
一週間前、コッペリ社の購入契約の日取りが決まり、配船室のメルネさんへ宇宙船の予約をお願いすると、ちょうど同じ時間にフェニックス号がコッペリ社へ行くので、同乗するように言われた。
ピンときた。これは、わたしに対する嫌がらせだ。
厄病神のフェニックス号で出かければ、契約がつぶれると考えたフレッド先輩が、わたしの契約に合わせて、どうでもいい仕事をコッペリ社に入れたのだ。
あの人は、厄病神のジンクスを信じている。

情報を集めて調べてみた。
レイターさんが出かける先で、トラブルが多く発生しているのは確かだ。偶然にしては多すぎる。大規模デモ、環境保護団体のテロ、ハイジャック・・・。
危険手当が増額して支払われていた。『厄病神』ではなく、優秀なボディーガードのレイターさんは、リスクの高いところを仕事として選んでいるのだ。
でも、今回向かうヨマ星系をいくら調べても、リスク情報はでてこない。船を変更する必要はない。
いずれにしても、わたしへの嫌がらせで仕事を頼まれてしまったティリー先輩はかわいそうだ。先輩にだってプライドはある。
不機嫌な様子を隠せないところが、ティリー先輩の人間らしいところだ。

わたしのことを妬んで、面白く思っていないことがみえみえ。でも、足を引っ張ろうとはしない人だから、害はない。
「器用なサブリナさんと違って、ティリーさんは不器用だからな。あんたなら、フレッドのあんな仕事受けねぇだろ?」
その通りだ。わたしなら絶対受けない。先輩の頼みと言っても、断る理由はいくらでも見つけ出せる。
あんな資料、転送してもらえばいいだけのことだ。
「好きな人のことを、悪く言っちゃダメですよ」
「いやいや、あれは、ティリーさんのいいところなんだ」
褒めているとは思えない。
「サブリナさんは、ありとあらゆる情報を先回りして集めてるじゃん。そうやって計算してねぇと不安なんだろ?」
当たっている。
「ティリーさんは、アンタレス人のくせに計算が苦手なのさ。不器用な上に感覚や感情が先にくる。人から頼まれたら受けなくちゃ申し訳ない、ってな」
本当にそうだ。真面目で一生懸命なのは伝わってくるけれど、要領はよくない。
「だから、真っ当で強い」

わたしの中に疑問符が灯る。レイターさんの言っている意味がよくわからなかった。
レイターさんは、ティリー先輩のことが好きだ。観察していればわかる。
前の彼女『愛しの君』への想いを引きずっているのは知っているけれど、もう亡くなった人だ。
惚れた欲目か。あばたもえくぼか。恋愛は人の目を曇らせる。
優秀なレイターさんもティリー先輩に関しては、判断がおかしくなるようだ。
と、思ったことをそのまま口に出したりはしない。
「流石レイターさん、ティリー先輩のこと、よく見てますね」
「そりゃ、俺のティリーさんだもの。サブリナさんはジョン・プーのどこが好きなんだい?」
突然の質問に、一瞬答えに詰まった。でも、わたしはこの質問の正解を知っている。
「全部に決まってるじゃないですか」

にっこり笑って答えた。
* *
サブリナさんと話しているとわかる。彼女は仕事ができる。それにかわいい。
ジョン・プーが惚れるわけだ。

しかし、サブリナさんはジョン・プーのどこが好きなんだろう。
俺は興味があった。
「サブリナさんはジョン・プーのどこが好きなんだい?」
「全部に決まってるじゃないですか」
にっこり笑って嘘のつける女性も、俺は嫌いじゃねぇ。
コッペリ社の男性担当者が頭を下げながら部屋へ入ってきた。
「どうもすいません。直前にお客様から通信が入ってしまって」
勢いのある会社、ってのは雰囲気が明るい。男も社交辞令以上の笑顔を見せている。
「フイールのおかげで出張が増えたものですから、ここで一気に船を新しくすることにしたんですよ」
「ありがとうございます」

サブリナさんが契約ボードを開いた。七隻の新型船契約。安い買い物じゃない。
細かい契約書を先方が慎重に確認する。
俺とサブリナさんはじっと待つ。
まあ、事前に契約書は法務部門含めて双方で付き合わせているから、ひっくり返ることはまず無い。特にサブリナさんは水も漏らさない程詰める。ティリーさんとは大違いだ。
それでも、難癖つけられると面倒だから、サブリナさんが緊張してるのがわかる。
先方が顔を上げた。
「確認しました。じゃあ、これでお願いします」
サブリナさんの肩から力が抜けた。
「こちらにサインを」
サブリナさんが渡した電子ペンで、コッペリ社の担当者がサインした。
契約完了だ。
「来週には納船いたします」

二人は笑顔で握手をかわした。
とその時、
リリリリリリ・・・
警報音が館内に鳴り響いた。
「火災報知器ですね、このビル古いんで、よくなるんですよ」
コッペリ社の担当者はのんびりしている。
俺の直感が騒ぐ。嫌な感じだ。
何か起きてるな。
「サブリナさん、急いで帰るぜ」
契約ボードをカバンに入れたサブリナさんの手をとる。
リリリリリリ・・・・・・
警報が鳴り続ける。
「変ですねぇ」
男もおかしいと感じたようだ。部屋の横のドアから一緒に廊下へ出る。
エレベータホールは人であふれていた。上から来るエレベータは定員を超えていて止まらない。
「階段で降りよう」
廊下にできた列に並び、七階からのろのろと階段を下へ降りる。
ティリーさんはどうしてる?

もうこの時間なら、一階のロビーに降りてるはずだ。
腕の通信機でティリーさんの位置情報を確認する。
おいおい、信じらんねぇ。ティリーさんはまだ十五階にいるぞ。
資料受け取るだけだ、ってのに、一体何やってんだよ。茶でも飲んでたのかよ。
俺がさっき七階に張り付けた集積カメラの映像を、アーサーは近くで見ているはずだ。
『何が起きてる?』
人の流れに沿って階段を降りながら、片手で通信機に文字入力し、アーサーに送信した。
即座に、耳に入れた無線からアーサーの低い声が返ってきた。
『コッペリ社の最上階で立てこもりが発生した。今からそちらへ向かう』
な、何ぃ?

俺は思わず声に出しそうになった。最上階は十五階。ティリーさんのいるフロアーだ。
天井を見上げる。このまま駆け上って、すっ飛んでいきてぇが、今は無理だ。人混みで身動きが取れねぇ。
七階に盗人が来るんじゃなかったのかよ。
とりあえず、サブリナさんを安全な場所へ避難させねぇと。
俺は通信機の周波数を警察無線に合わせた。
『緊急通報によると、犯人は銃を手にしている』
『十五階にいた社員らが、人質に取られている』
おいおい、勘弁してくれ。俺のクライアントがいるんだぞ。
階段を降りるゆっくりなペースがもどかしくて苛立つ。
「外へ避難して下さい」
一階ロビーは大混乱だ。人の波に押される。
念のため待ち合わせ場所を見るが、ティリーさんの姿はない。
サブリナさんをかばいながら、ビルの外へ出る。
警察車両のサイレンが、けたたましく鳴り響いていた。
「十五階で立てこもりが発生したらしい」と口々に人が話している。
「ティリー先輩、どこにいるんでしょうか? これじゃ会えないですね」

サブリナさんが心配している。
「ティリーさんはまだ、十五階から降りてきてねぇんだ」
サブリナさんの目が大きく見開かれた。
「資料受け取るだけなのに、どうして? 今、十五階で立てこもりが起きているって、言ってますよね?」
納得できないと言う顔をしている。俺だってそうだ。
「大丈夫、俺が助けに行くから」
「レイターさんって、本当に厄病神なんですか?」
サブリナさんが怯えてる。想定外に備えて情報を集めるサブリナさんの想定を超えた事態だからな。
俺は安心させようと笑顔で答えた。
「そんな顔しないで。せっかくの美人が台無しだ。厄病神の登場がサブリナさんの契約が成立した後で良かったじゃん」

サブリナさんはニコリともしなかった。
その時、俺は見知った顔を見つけた。
「おい、カルロス」
将軍家の下僕のカルロスは、サラリーマンのような目立たないスーツを着ていた。潜入捜査中か。
「レ、レイターさん」
俺に見つかったのが面倒くさい、って思ってるのが手に取るようにわかる。文句は言わせねぇ。
「カルロス、あんた、こちらのサブリナさんをフェニックス号へ送れ」
「僕は仕事中なんです」

「俺のティリーさんが十五階にいるんだよ。勝手に動くぞ」
将軍家秘書官のカルロスの任務は、アーサーの仕事が円滑に回るようにすること。
俺が勝手に動くと聞いて慌てている。カルロスは頭の回転は悪くねぇ。何と言っても天才軍師アーサーの影武者だからな。
「待ってください。女性をフェニックス号へお送りします。ですから、勝手なことはしないでください」
「サブリナさん、こいつ、腕はいいから、安心して船で待っててくれ。俺はティリーさんを連れて帰るから」
「は、はい」
カルロスに任せとけば間違いはねぇ。
さて、ティリーさん待たせたな。
* *
リリリリリリ・・・、と火災報知器の音をティリーは聞いた。
応接室で一緒にお茶を飲んでいたバッハさんが、白いティーカップを置いて立ち上がった。
「火事ですかね。避難しましょう」
バッハさんの後について、部屋の外へ出る。オフィスから騒がしい声がした。異様な雰囲気だ。
ドアの前で男性社員が固まっていた。
「ここから動くな!」」
奥から男の人の怒鳴る声が聞こえた。「動くな」と言われても火事だったら逃げない訳にはいかない。何をもめているのか。
カウンター越しにオフィスをのぞいたわたしは、身体が硬直した。

スーツを着た白髪の男性が、銃をわたしたちに向けた。
「全員人質だ。動くな」
厄病神の発動だ。
レイター、何とかして!! わたしは心の中で叫んだ。
* *
レイターは、コッペリ本社前に停車している警察の指揮車へと向かった。現地対策本部が設置されてるはずだ。
銀河警察は基本的に信用してねぇ。だが、俺はボディーガードだ。警備部とは付き合いがある。
こういう案件の時には、警備部特殊部隊長のあいつが現場へ来てるはずだ。
ほら、いた。
指揮車の前に立つ、背の高い隊長の後ろ姿に声をかける。
「なあ、バルダン、頼みがあるんだけど」
短髪で三白眼のバルダンが振り向いた。

「何だおまえら、二人して」
二人してだと?
振り向くと俺の後ろにアーサーが静かに立っていた。
「ネゴシエーター、交渉人のアーサー・ブラウンです」
アーサーが頭を下げた。
スーツに眼鏡。これで変装したつもりかよ。
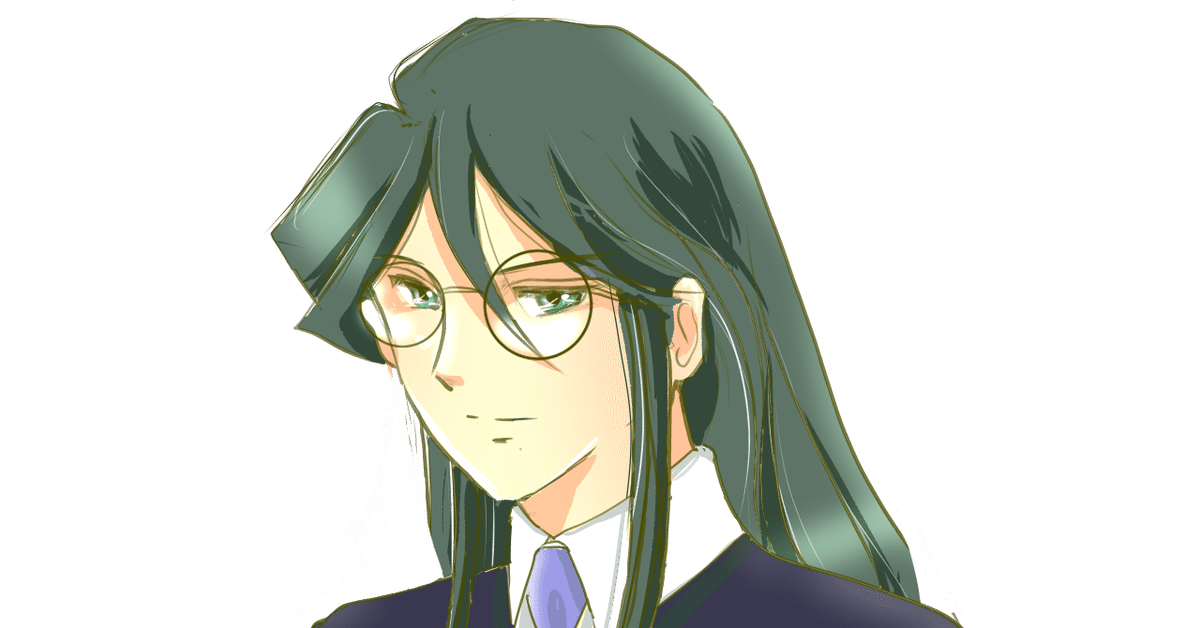
「アーサーの話は警視総監から聞いている。レイター、おまえの頼みってのは何だ?」
「突入部隊に入れてくれ。俺のクライアントが十五階にいるんだよ」
俺一人でティリーさんを助けに行くより一番確かな方法だ。バルダンの部下たちは優秀だ。
バルダンが俺に近づいた。
俺は、慌てて手を引っ込めた。危ねぇ。バルダンの奴、俺の指をつかもうとした。
「ふむ、訓練は怠っていないようだな」
バルダンは鼻で笑った。指をつかむだけで人を殺せる男。今の一瞬で俺は脇の下に汗をかいた。
バルダンとの付き合いは十年以上になる。
ガキの頃にはアーサーと乗ってた戦艦アレクサンドリア号で、格闘技の基礎をバルダンに習った。「一に練習、二に訓練」が口癖だ。
バルダンは連邦軍の特殊部隊に引き抜かれた後、軍を辞め、警察に転職した。
管理職になった今でも全く衰えてねぇ。昔と変わらず訓練を積んでるな。
「じゃあ、俺が教えた通りしっかり働けよ」
「アイアイサー。あんたも張り切り過ぎて、腰痛めるなよ」

「フン、俺を年寄り扱いするな」
懐かしい会話に、俺は思わず笑った。
* *
「全員人質だ。動くな」
銃を向けられたティリーは、心の中でレイターに助けを求めた。
レイター、何とかして!!
十五階のオフィスにはわたしとバッハさんのほかに、コッペリ社の若い男性社員がいた。
その男性社員が、恐る恐る、銃を手にした白髪の男性に声をかけた。
「ワトキンスさん、落ち着いて下さい」
パリーン。
ワトキンスと呼ばれた男性が発砲した。
大きな音を立てて窓ガラスが割れた。身体中が縮こまる。本物の銃だ。
若い社員が震えながら後ずさりした。
男は銃をわたしたちに向けながら言った。
「お前たち、わしの近くへ来い」
逃げられない。
わたしはバッハさんの後ろについて、ゆっくりとカウンターで仕切られたオフィスの中へと入った。手も足も自分のものじゃないみたいだ。
これは、どこからどう見ても、立てこもり事件だ。
どうして、こんなことになっちゃったんだろう。絶対、厄病神のせいだ。
犯人とわたしたちの間は三メートルぐらいしかない。
「おい、女」
「わ、わたしですか?」
この場に女性はわたししかいない。
犯人と目があった。
眼鏡をかけた痩せた男性。真っ白い髪の感じからすると五、六十代だろうか。

「男たちの手を後ろ手にして、テープで縛れ。変な動きを見せるなよ」
犯人から、オフィスにあった太目の梱包テープを投げ渡される。
「早くしろ、撃ち殺すぞ」
「は、はい」
手が震えてテープがうまく巻けない。
「ごめんなさい」
謝りながら、わたしはバッハさんと男性社員の手を背中側で縛った。
「終わったら女は、こっちへ来て、椅子に座れ」
犯人の横にオフィスチェアが置かれている。
バッハさんがわたしの前に出て、身体で庇う。
「この人は、うちの会社の人じゃないんです。私がそちらへ参ります」
「うるさい。コッペリ社の社員じゃなくてもいいんだよ。わしには一番弱そうな奴が必要なんだ。文句言うな」
犯人からすれば、自分の近くに置いておくのに、非力なわたしが都合いいというのは容易に想像がついた。
犯人の隣に座ると銃が突き付けられた。これは、最初に殺される係だ。足が震えてきた。

どうしてこんなことになっちゃったんだろう。
わたしは、フレッド先輩のお使いで、書類を受け取りに来ただけなのに。
* *
レイターはコッペリ社地下一階の警備室に、バルダン隊長、アーサーに続いて入った。
立てこもりの現場である十五階の防犯カメラの映像が、複数のモニターに映し出されていた。
ティリーさんが映っている。銃を手にした白髪男の横に座らされていた。
犯人は一人、人質は三人。
俺の頭ん中はクールだが、胸ん中は怒りで煮え立っていた。
「あの野郎、俺のティリーさんに銃を向けやがって、絶対、許さねぇ」

アーサーがバルダンにたずねる。
「犯人の身元は割れていますか?」
「ああ、入館リストと顔認証から判明した。ノア・ワトキンス、五十八歳。コッペリ社のライバル会社であるハルタナ社の元研究員だ」

コッペリ社の担当者が補足説明する。
「ワトキンス氏は、これまでも弊社の速乾洗剤フイールについて、自分のアイデアがロットリンダ研究員によって盗まれた、と再三クレームを繰り返しておりまして、きょうも総務部が苦情対応をしておりました」
ロットリンダ研究員。
その名前に聞き覚えがある。
テレビで見たな。フイールの開発者だ。

イケメンすぎる研究者、とか言って取り上げられていたぞ。
コッペリ社の担当者が一息入れた後、続けた。
「ロットリンダはワトキンス氏の元部下で、三年前に弊社に転職してきたんです」
アーサーが振り向いた。

アーサーの後ろに、サブリナさんをフェニックス号に送り届けて戻ってきたカルロスが立っていた。
「カルロス、ワトキンス氏とロットリンダ氏について調査を。クレームの詳細を聞き取ってください」
「はっ」

将軍家のポチが姿勢を正して部屋から出ていった。
「とりあえず、ワトキンス氏と交渉を始めますか」
アーサーはゆっくりと立ち上がり通信機の前に立った。
* *
フェニックス号に到着したサブリナは、身体の震えが止まらなかった。
どうすればいいのだろう。
私をここまで連れてきてくれたカルロスさんは
「現場へ戻りますので、失礼いたします」
と帰っていった。
一人にしないで、と言いたい気持ちを必死でこらえる。
わたしは極度の心配性なのだ。不安でたまらない。
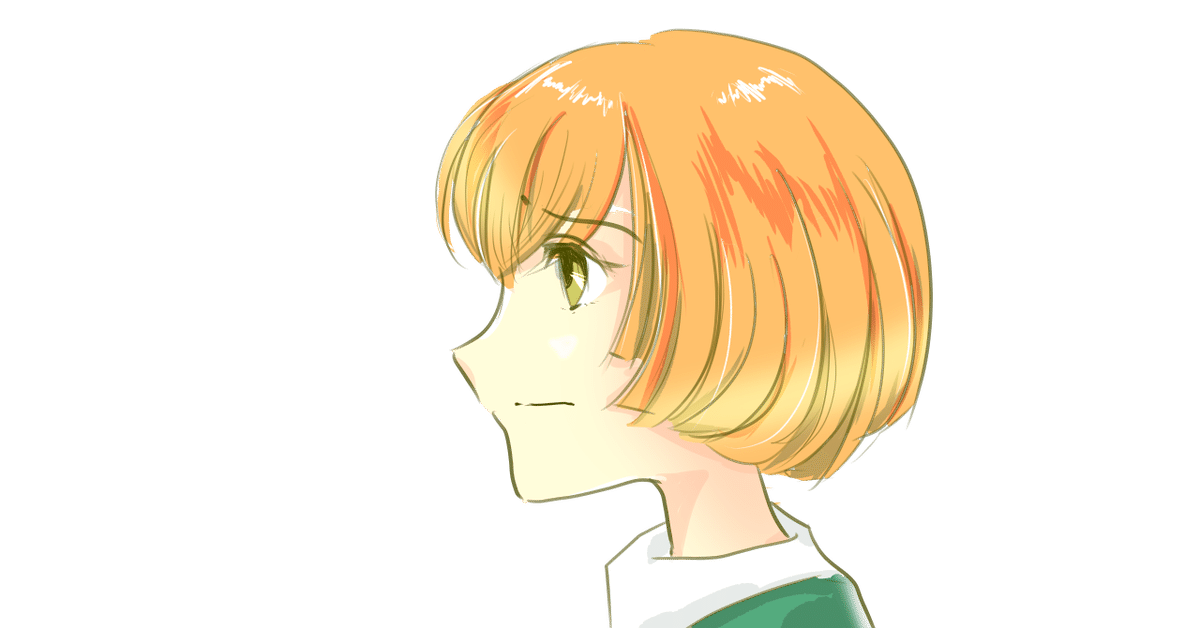
まず、会社に報告を入れなくては。
アディブ先輩に通信を入れる。
「先輩、取引先のコッペリ社が大変なことに」
「レイターから連絡が入ってるわ。サブリナはフェニックス号に着いたのね」
「はい。でもティリー先輩がまだ残っていて」
「大丈夫よ、レイターが救出に向かったから。あなたは、そこで待機していて頂戴」
「わかりました」
「契約が完了してよかったわね。おめでとう」

「あ、ありがとうございます」
よくこんな時に契約のことを笑顔で話す余裕がある。いつも思っていたけれど、アディブ先輩は普通じゃない。
フェニックス号の居間にあるテレビを付けた。
とにかく、情報を集めなくては。
地元チャンネルは、どこもこの立てこもりのニュースを特別番組で放送していた。
コッペリ社から二百メートル以上離れた規制線の外から中継している。
十五階建てのコッペリ社のビルはそんなに高くない。ほかのビルの影になっていて、本社の様子はほとんど見えない。
腕章を着けた記者やカメラマン、あふれ返る脚立と三脚が、現場近くの緊張感を伝えている。
「人質の情報が入ってきました。コッペリ社の十五階では社員ら三人が人質になっている模様です。女性が一人います。この女性は社員ではなく取引先の関係者ということです」
ティリー先輩だ。

そんなに時間のかかる仕事じゃなかったのに、どうして先輩はこんなことに巻き込まれているのだろう。さっぱり、わからない。
ホストコンピューターのマザーを使って、情報ネットワークを検索する。
コッペリ社をめぐっては、速乾洗剤フイールを使用中に人が死んだとか、デマとしか思えない話が溢れていた。
立てこもり犯だ、という顔写真と名前が次々と浮上しては消えている。
どれも、噂の域を出ていない。
人質を全員殺す、という、たちの悪い書き込みもあった。情報ネットワークを見ているだけで不安が増幅する。
さっき、レイターさんに言われたばかりだ。
「サブリナさんは、ありとあらゆる情報を先回りして集めないと不安なんだろ?」

その通りだ。心配性なわたしは、情報の収集と計算をやり尽くさないと不安で不安で仕方がない。
わたしが欲しいのは正確な情報だ。誤った情報をいくら集めても判断を狂わせる。
『コッペリ社 立てこもり情報』というまとめサイトに、大手メディアの情報が整理されていた。ソースが信頼できそうだ。
交渉人が対応に当たると書かれていた。
このフェニックス号にいれば、安全なのはわかっている。
それでも、最悪の事態、という恐怖に押しつぶされそうだ。
誰でもいい。そばにいて欲しい。
彼氏であるジョンの顔が頭に浮かんだ。

きょう、ジョンは大事な舞台に立っている。
連絡はできない。
でも、呼んだらあの人は来てくれる。
レイターさんに聞かれた質問が頭に浮かんだ。
「サブリナさんは、ジョン・プーのどこが好きなんだい?」
レイターさんに答えなかった本当の答えを、自分はわかっている。
ジョンはわたしを好きでいてくれる、それが答え。

わたしに惚れている彼は、わたしの頼みを何でも聞いてくれる。
わたしが側にいて欲しいと言えば、すぐに来てくれる。
無理を言っても、文句ひとつ言わない。
それが、わたしがジョンと付き合っている理由。
* *
コッペリ社十五階の総務部。
ティリーは、立てこもり犯のワトキンスに銃を突きつけられていた。
バッハと若い男性社員は、少し離れた床に座らされている。
オフィス机の上にある固定通信機のスピーカーから、男性の声が響いた。
「ノア・ワトキンスさん、聞こえますか。私は、今回の交渉を務めるネゴシエーターのアーサー・ブラウンと申します」
聞き覚えのある落ち着いた声。
ティリーは、急に目の前が明るくなったように感じた。

偽名を使っているけれど、アーサーさんだ。連邦軍将軍家の御曹司で天才軍師。友人チャムールの彼氏。
「ワトキンスさん、あなたの要求を聞かせてください」
犯人のワトキンスさんが受話スイッチを押す。モニターに黒髪を後ろで束ね、眼鏡をかけたアーサーさんの姿が映った。
「交渉人、よく聞け。要求を伝える。コッペリの社長とロットリンダをわしの前へ連れてこい」
「代表取締役社長とロットリンダ研究員を、本社の十五階へお連れしろということですね?」

アーサーさんがゆっくりと復唱した。
「そうだ、社長はフイールが産業スパイによって開発されたことを認めろ。そして、スパイのロットリンダは私に謝罪しろ」
ロットリンダさん。名前を聞いたことがある。思い出した。フイールの開発者。イケメンすぎる研究者だ。

「二人の所在を確認いたしますので、その間、お待ちください。金品の要求等はございませんか?」
「とにかく、わしの名誉を回復するんだ。早くしないと、人質を殺すぞ。これを見ろ」
ワトキンスさんが、五センチほどの透明なボトルを胸のポケットから二本取り出した。ガラス製だろうか。牛乳のような白い液体と、透き通った青い液体が入っている。
「白い液体は、XKZだ」
XKZ? 聞いたことがない。
人質のバッハさんが目を見開いた。
「ま、まさか」
ワトキンスさんがバッハさんに銃を向けた。
「お前、わかったようだな、これが何に使われているか言ってみろ」
第三十一話「恋の嫉妬と仕事の妬み」まとめ読み版②へ続く
・第一話からの連載をまとめたマガジン
・イラスト集のマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

