
銀河フェニックス物語 【出会い編】 第二十五話 正しい出張帰りの過ごし方(まとめ読み版)
・第一話のスタート版
・第一話から連載をまとめたマガジン
・第二十四話「ようこそ展覧会へ」
わたしが浅はかだったのは間違いない。
フェニックス号で二泊三日の出張が終わって、ソラ系へ戻ってきた。週末の明日は宇宙船レースの最高峰S1グランプリがある。
今晩は前夜祭だ。
どうせフェニックス号で見るのだから、と、深く考えもせずにレイターに提案した。
「もう一泊してもいい?」

「あんたがよけりゃ、構わねぇよ」
ということで、フェニックス号に延泊した。
この船、自宅と同じぐらいのんびりできるし、ご飯もおいしい。
そして、レイターの解説を聞きながら、夜はS1の前夜祭番組を楽しんだ。
フェニックス号の4D映像システムは素晴らしい。
インタビューに答えるS1レーサー『無敗の貴公子』ことエース・ギリアムが、わたしの目の前で語りかけてくる。

かっこよすぎる。
憧れのエースを思いっきり堪能する。
*
翌朝、遅めの朝ご飯を食べている時にレイターが言った。
「そうだ、ジョン・プーが彼女を連れてくるってさ」
「あら、そうなんだ」
好きな人がいると言っていたジョン先輩。うまくいったんだ。知らなかった。
S1レースをフェニックス号の4D映像システムで見る、という楽しみをわたしに教えてくれたのは研究所のジョン先輩だった。
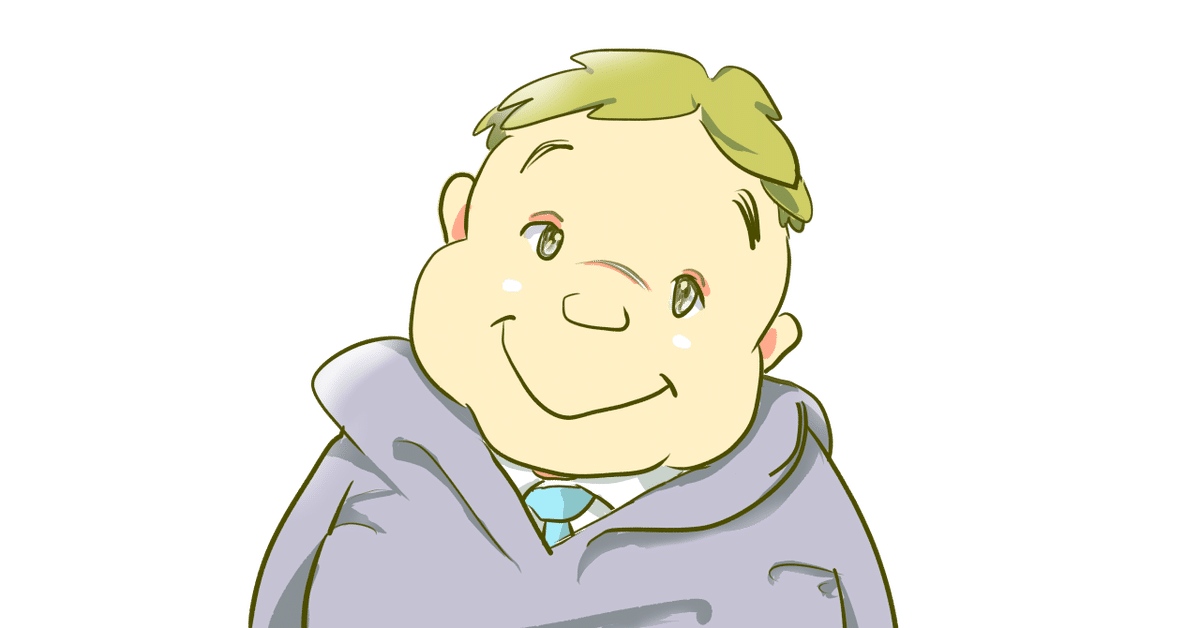
「じゃあ、レイターの部屋、少し掃除した方がいいんじゃないの?」
レイターの部屋は,足の踏み場がほとんどない。
ジョン先輩が彼女と来るなら、座る場所をつくった方がいい。
「そおだなぁ」
気乗りしていない返事だ。めんどくさがっている。
「じゃあ、わたしが片づけるわよ」
「ふがっ」
レイターは他人に部屋のモノを動かされるのが嫌いなのだ。
*
レイターの部屋に足を踏み入れる。
一見、めちゃくちゃに散らかっているように見える。
でも、わかってきた。レイターの頭の中では散らかってるわけじゃなくて、それなりに順序立てて置かれている。
レースのたびにこの部屋へ来ているうちに、何となくその法則がわかってきた。
机の上や近くにあるプラモデルや本は最新理論の検証。
これには絶対触ってはいけない。
ベッドの上にあるガラクタは修理に使う道具。
ソファー脇の床にあるディスクなどは趣味。趣味のモノは場所を動かしても平気。
わたしが片づけ始めた。
レイターはベッドに寝っころがりながら、チラチラ様子を見ている。

気になるのなら手伝えばいいのに、と思いながら、趣味のモノからまとめていく。
レイターは何にも言わない。
それにしても危ないなあ、刃が剥き出しのままナイフが床に落ちてるし。
ソファーに座る場所を確保し、床にできた空間にクッションを置く。
*
そして、ジョン先輩は予定より早くやってきた。
「いらっしゃい」
わたしが玄関でジョン先輩を迎えた。
「ティリーさん、随分早く来たんだね」
「きのうまで出張だったんで、そのまま泊まっちゃいました」
「えーっ!」
わたしの返事を聞いて、ジョン先輩の後ろから女性の声が聞こえた。ジョン先輩の彼女。
その声に聞き覚えがある。
「ティリー先輩。やっぱりレイターさんとつきあっていたんですか?」

「サ、サブリナ!」
ひょっこり顔を出したのは、営業部の後輩サブリナだった。
しっかり者のサブリナと、のんびり屋のジョン先輩。ちょっと意外な組み合わせだ。
「そっかぁ、サブリナとティリーさんは同じ営業だから二人が知り合いでも不思議じゃないね」
ジョン先輩が笑顔でおっとりと言った。

「というか、ジョン。ティリー先輩はわたしのメンターなんだから」
「え? そうなの」
「サブリナの入社当時の話ですけどね」
「いえ、ティリー先輩は、今もわたしのメンターです」
サブリナが営業部に配属された際、わたしはメンターと呼ばれる育成係に指名され、彼女に社内のことを教えた。
今では、サブリナは隣の法人営業課でアディブ先輩の次に営業成績がいい。わたしが教えることは何もない。
「ジョンったら、ティリー先輩のこと知っていたなら、教えてくれればいいのに」
「いやあ、いつも三人で見るのが普通だから、気にしてなかった」
サブリナが頭を下げた。
「ごめんなさい。先輩。噂が本当だなんて知らなかったんです。お二人の邪魔をするつもりは無くて・・・」
噂?
お二人の邪魔?
わたしは慌ててさえぎった。
「ちょ、ちょっと待って。わたしとレイターはつきあってるわけでも何でもないから」
「え? だって、先輩、昨日ここに泊まったんですよね」
「それはそうだけど」
「ここ、レイターさんの家ですよね」
「そうとも言えるけれど・・・」
「先輩、照れなくてもいいですよ」
サブリナがウインクした。
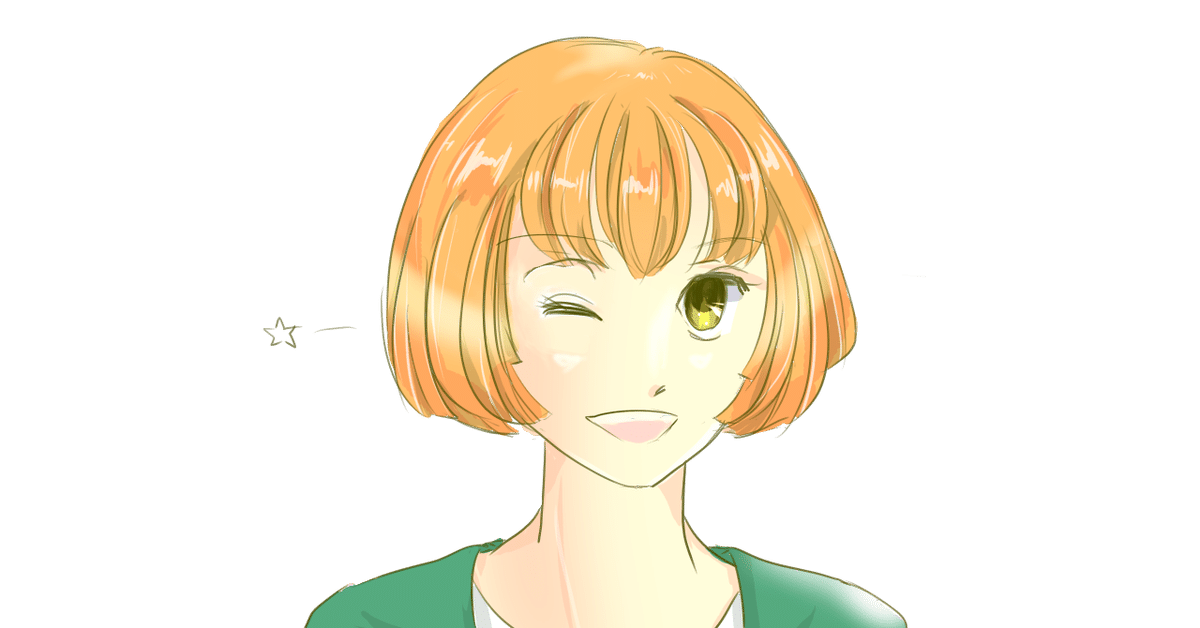
「だから、違うんだってば」
「何してんだい?」
レイターが中から出てきた。
レイターはサブリナを見ても驚きもしない。ジョン先輩の彼女だと知っていたようだ。
サブリナが謝った。
「レイター、ごめんなさい。ジョンがいい穴場があるって言うから来たんですけど。この人、気が利かなくて。ティリー先輩と二人でレース見るはずだったんでしょ」
「あん? 元々、ジョン・プーがティリーさんを連れてきてくれたんだから構やしねぇよ。なあ、ティリーさん」

「え、ええ」
何だか話がうやむやになっている。
*
「あれ、きょうは片づいてるなぁ」
レイターの部屋に入ったジョン先輩が驚いた。
「ああ、ティリーさんが片づけてくれた」
「いつもは僕が部屋のモノを触るだけで怒るのに」
研究所勤めのジョン先輩は、レイターが一番触れられたくない宇宙船の改造部品をいじっては怒鳴られているのだ。
サブリナが納得したようにうなずいている。
いやな予感がした。彼女、勘違いしてるんじゃないだろうか。わたしが泊まり込んで部屋の掃除までしてるって・・・。
「誰がどこに座る?」
レイターが聞いた。
聞くまでもないことだ。
「お客さんがソファーに決まってるでしょ!」

そう言って二人をソファーに座らせてから気づいた。
二人をお客さん、って呼んだけど、ここはわたしの船じゃない。わたしもお客さんだったことに・・・。
*
レイターが4D映像システムのスイッチを入れた。
宇宙空間が広がる。
「うわぁ、ほんとにすごいですね」
サブリナが感動している。
「ここ、いいだろ」
彼女といるからか、ジョン先輩の雰囲気が少し違う。浮かれている感じ。
わたしは床のクッションに座った。
レイターが隣に座って映像を操作する。
「ジョン、画面どうする?」
「サブリナは、プライベーターが好きなんだよね」
「ええ、チーム・スチュワートを応援してるんです」
「へぇ、俺と一緒じゃん」
わたし以外の三人がスチュワートの話で盛り上がる。
チーム・スチュワートは、ベンチャー企業の社長ライネッツ・スチュワート氏がオーナーの個人チームだ。

S1レースはうちのクロノスみたいにメーカーによるワークスのチームが多い中、よくがんばって入賞している。
ただ、表彰台には届かなくて『万年六位』と呼ばれている。
話の流れから、自然と大画面がスチュワートの船の映像になった。
みんなクロノス社の関係者なのに、誰もうちのチームのことを話題にしない。
いつもは専務のエースが大画面なのに・・・。
いつも、この船でS1を観戦しているけれど、きょう初めて気がついた。
ジョン先輩もレイターも、エースの画面を見たいわけじゃなかったんだ。わたしに気を使ってくれていたのか。
少し、気分が落ち込む。
その時、わたしの目の前にサブ画面が開き、エースの横顔が映った。

かっこいい。
サブ画面だけど、目の前で見れば十分に大迫力だ。
レイターは、わたしのためにサブ画面を切り替えてくれた。
「ありがとう」
隣に座るレイターにお礼を言った。
「あん? レース全体の状況を知るにゃ、先頭カメラの映像が一番だからな」

わかっている。
わたしに気を使ってくれたこと。
レイターはよく気が利く。
でも、あまりにさりげなくて、気をつけていないとすぐ見逃してしまう。最近、そのことに気が付いた。
*
レースがスタートした。
わたし以外の三人は大画面を見ているけれど、もうわたしは目の前のサブ画面に釘付けだ。
うっ、きょうもエースは素敵だ。
ポールポジションからトップを独走だわ。
ジョン先輩が、サブリナに話しかける。
「ティリーさんはエース専務の大ファンなんだ」
「へえ。愛社精神に溢れてるんですね」
「というか、専務に憧れて入社したんだそうだよ」
「レイターさん、妬けますね」
「ったくだぜ」
ちょちょっと、その会話止めて欲しい。
レイターたちが応援しているスチュワートの船は、調子がよくなかった。
「バカ野郎! 冷却装置が悪いのにふかすな!」
いつもと同じ様にレイターが罵倒している。
「ったく、俺ならもっとうまく攻めるぞ」
そんなレイターの様子を、ジョン先輩とサブリナが見て笑っている。
「面白いだろ?」
「面白いわね」
二人は楽しそうだ。

胸がキュンとした。いいな、付き合ってるって。
お互いがお互いを一番大切な人、とわかっている状態。
満たされて、安定している関係。
わたしにも学生時代に付き合ってる彼氏がいた。
嫌いになって別れた訳じゃない。遠距離の果ての自然消滅。
サブリナがうらやましい。
彼氏が近くにいて、一緒に時を過ごして、二人で共有するものを積み重ねていく、って素敵なことだと思う。
好きな人と一緒にレースを見るなんて最高だ。
*
「おっと、面白れぇ展開になってきたな」
レイターの声で画面に集中する。いやだ、エースのタイムが落ちてる。
「右の補助エンジンがうまく回ってねぇな。直線でエースが気がつかなきゃ、楽しいぞ。二位のオクダが追いつく」
レイターがうれしそうに言った。
むかつくことに、この人は『無敗の貴公子』のエースが負けるのを楽しみにしている。
「エース! 右の補助エンジンよ!」

わたしは叫んだ。
わたしの声がエースに届きますように。
直線に入った。
息を飲んで見守る。
握りしめる手に力がこもる。
エースの船が加速した。
迫ってきた二位の船との差が開きだした。
「ちっ、気づいたか。つまんねぇの」
「やったぁ」
わたしはほっとした。
そして気が付いた。

隣にいたレイターの手を、思いっきり握りしめていたことに。
「ご、ごめん」
慌てて手を離そうとしたわたしの手を、レイターが握り返す。
「エースに感謝するぜ」
と笑顔でウインクした。

この人は、わたしに限らず、女の人にはいつもこんな調子だ。『愛しの君』という好きな人がいるくせに。
温かくて大きな手。急に心臓がドキドキしてきた。
レースが緊迫したせいで、心拍数が上がったせいだ。
「厄病神がうつるから手を離してください」
そう言って、レイターの手をふりほどいた。
*
レースは続いていた。
「ああああぁ、バカかよ!」
レイターががっくりと肩を落とした。
「残念だわ」
サブリナもため息を付いた。二人が応援するチーム・スチュワートの船は、コースを大きく外れて棄権となった。
「ふふふふふ」
笑っているのはわたしだけ。
エースは優勝し、無敗の記録を更新した。
「エース・ギリアムは無敵。最高だわ!」

「うるせぇ、うるせぇったらうるせぇ!」
レイターが首を左右に振った。
*
レースが終わると、ジョン先輩がレイターにたずねた。
「なあレイター、ロルダ理論はS1機に使えると思うかい?」
「うーん、現時点じゃ厳しいよな。と、あんたも思ってんだろ」
レイターとジョン先輩は、床にタブレットぺーパーを置いて難しい計算を始めた。
宇宙船お宅と研究者、議論をするのはしょっちゅうだ。
わたしとサブリナはソファーに座り、そんな二人の様子を見ていた。
サブリナがわたしに声をかけた。
「やっぱり、セントクーリエ出身の人は違いますね」
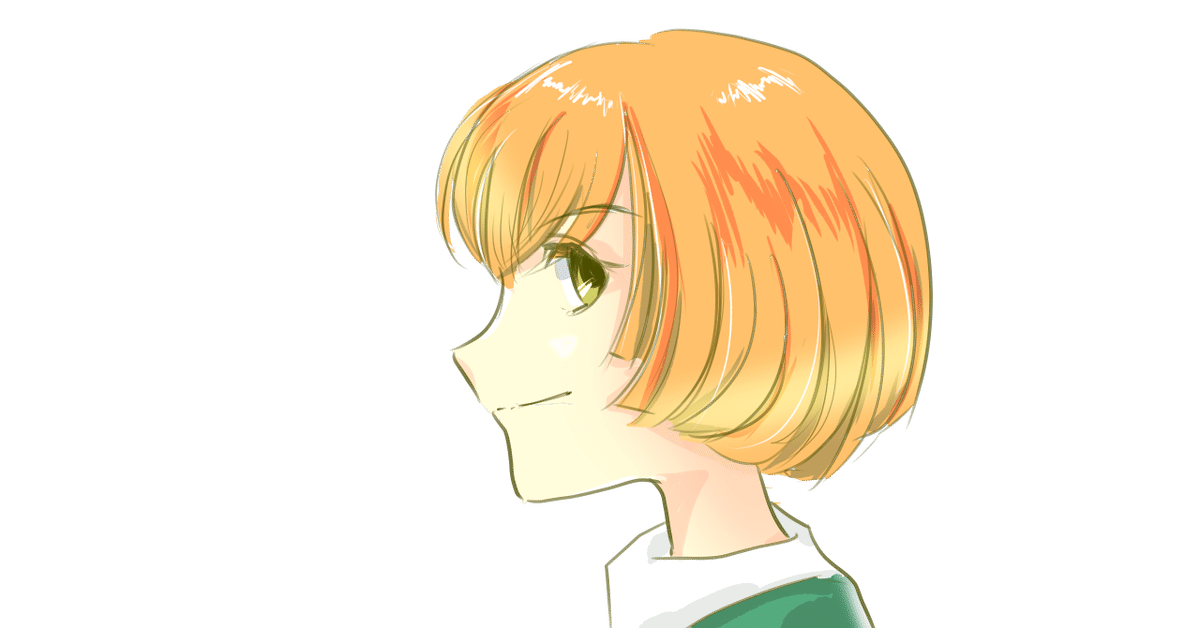
セントクーリエは超難関有名私立校。
ジョン先輩のような研究者のほか、政治家、高級官僚、企業トップといったエリートを生み出す学校で、権威あるキンドレール賞の受賞者を一番多く輩出している。
わたしは納得した。
「ジョン先輩はセントクーリエ出身なのね。頭いいはずだわ」
「レイターさんもですよ」
ん? サブリナは勘違いしている。
耳元でこっそり訂正した。
「レイターは公立ハイスクール中退よ」
「え?」
驚いたサブリナが、話に夢中になっているジョン先輩の服を引っ張った。
「ねえ、ジョン。レイターさんもセントクーリエの一緒の寮にいたんでしょ」
「ああ、そうだよ」
今度は、わたしが驚いた。聞いていた話と違う。
「レイターは、月の公立ハイスクール中退、って言ってたじゃない?」
「あん? そうだぜ」

ジョン先輩が説明した。
「レイターはセントクーリエに入学して、そのあと、公立ハイスクールへ転校したんだよ」
サブリナがわたしに笑顔を見せた。
「納得できましたね」
全然、納得できない。
セントクーリエの入試、と言えばとにかく難しいことで有名で、わたしの地元アンタレスでは合格するだけでニュースになる。
授業についていけなくなって公立学校へ転校、というケースはありそうだ、考えられるのは。
「将軍家のコネで裏口入学・・・」
つぶやくわたしの頭を、レイターが軽くこづいた。
「会社じゃねぇんだ。ちゃんと試験受けて受かったんだよ」
「ええっ?!」
びっくりして声が出せない。
そして、思い出した。
前にレイターがセントクーリエのバスケ部にいた、と話していたことを。
「レイターって、ほんとにセントクーリエのバスケ部にいたの?」
レイターには、まったく縁がなさそうなエリート校の名前を持ち出したから、面白くない冗談だと思っていた。
ジョン先輩が懐かしそうに口にした。
「控え選手だったレイターが出てくると、バスケの会場が盛り上がったよね。レイターはチビだったから」

「ジョン・プー、殴るぞ。一言多い」
セントクーリエ出身の皇宮警備官と、公立ハイスクール中退の飛ばし屋。
この二つが共存しているって、人格が崩壊してるんじゃないだろうか。
*
ジョン先輩とレイターの宇宙船談義が一段落した後、レイターが作った夕飯を4人で食べる。

手羽先、という骨のついた鶏肉のから揚げが、ダイニングテーブルに運ばれてきた。
塩味、甘辛いもの、スパイシーなもの。
手が汚れるのも気にせず、揚げ立てを手づかみで口にする。
普段は苦くてあまり飲まないビールが、なぜかあう。
「エース、優勝おめでとう」
気分は最高。
パリパリとした皮がおいしく、いくらでも食べられそうだ。
「う~ん。うまいよ、幸せだ」
ジョン先輩の前に、見る間に骨の山ができあがった。
よく考えると、わたしがここでご飯を食べるのも四日目だ。でも、全然飽きない。
「いいですね、ティリー先輩は。いつもこんなにおいしいご飯が食べられるなんて」
「いいでしょ」
と自慢げに口にしてから、あわてて否定した。
「だから、仕事とレースを見る時だけよ。レイターとつきあってるわけじゃないんだから」
ジョン先輩がたずねる。
「不思議に思ってたんだ。君たち、ほんとにつきあってないの?」
「つきあってません」
わたしは即答した。
レイターは何も言わない。
「じゃあ、どういう関係なんですか?」
サブリナが詰め寄る。
「どういうって・・・」
ボディーガードとクライアントの警護対象者、というのは間違いないけれど、きょうはプライベートだ。
「宇宙船レースの鑑賞仲間というか・・・」
ぷっ。
わたしの答えにジョン先輩が吹いた。
「それじゃ、僕とティリーさんの関係とおんなじだ」
サブリナが反応する。
「そんなはずないじゃないですか。お二人見てればわかります」
見てればわかるって、一体何がわかるというのだろう。
「なあレイター。お前はどう思ってるんだ、ティリーさんのこと」
「あん?」
レイターはにやりと笑った。
「俺のティリーさんは、怒った顔もかわいいだろ」
「その言い方止めて、って言ってるでしょ」

すかさず反応する。
ジョン先輩とサブリナが、顔を見合わせて笑った。
「面白いだろ?」
「面白いわね」
全然、面白くない。
「デザート食べるかい?」
レイターが聞いた。
「食べたいわ」
わたしは即答した。この船はデザートとコーヒーも絶品だ。
「待ってな」
と言って、レイターはキッチンの奥へ向かった。
*
サブリナがわたしに聞いた。
「ティリー先輩は、レイターさんと付き合う気はないんですか?」
「ないわよ。だって、レイターには『愛しの君』という大事な人がいるんだから」
「え? 先輩以外に好きな人がいるんですか?」
サブリナが目を丸くした。
そんな彼女に、ジョン先輩が声を潜めて言った。
「でも、もう『愛しの君』はこの世にいないんだよ」

わたしは息をのんだ。
今、ジョン先輩は何と言った?
『愛しの君』はこの世にいない?
わたしの疑問をサブリナが確認する。
「ジョン、どういうこと?」

ジョン先輩はレイターに聞かれたくないのだろう、さらに声を小さくして答えた。
「『愛しの君』はレイターの前の彼女だよ。でも、若くして亡くなったんだ。それ以来、あいつ、特定の人とはつきあわないで、不特定多数を相手にしているんだよ」
サブリナがわたしに言った。
「不特定多数? それは、ティリー先輩イヤですよね。わかります」
「う、うん」
深く考えずにわたしはうなずいた。
それよりなにより、わたしは動揺していた。
『愛しの君』はこの世にいない。
わたしには関係ない。関係ないのに。心がざわつく。
*
「ほれ、いちごのミルフィーユだぜ」

デザートを運びながらレイターが戻ってきた。長方形のパイの上に四つのイチゴが乗っている。
「うわぁ、レイターさんのお手製ですか?」
「そうさ。ジョン・プーが、サブリナさんもケーキが好きだって言うから、用意しておいたんだ」
その場で四つに切り分ける。
流れるような動作が美しい。
わたしとサブリナに大きく切って、皿に載せた。
ジョン先輩がレイターに文句を言う。
「僕のが小さいよ」
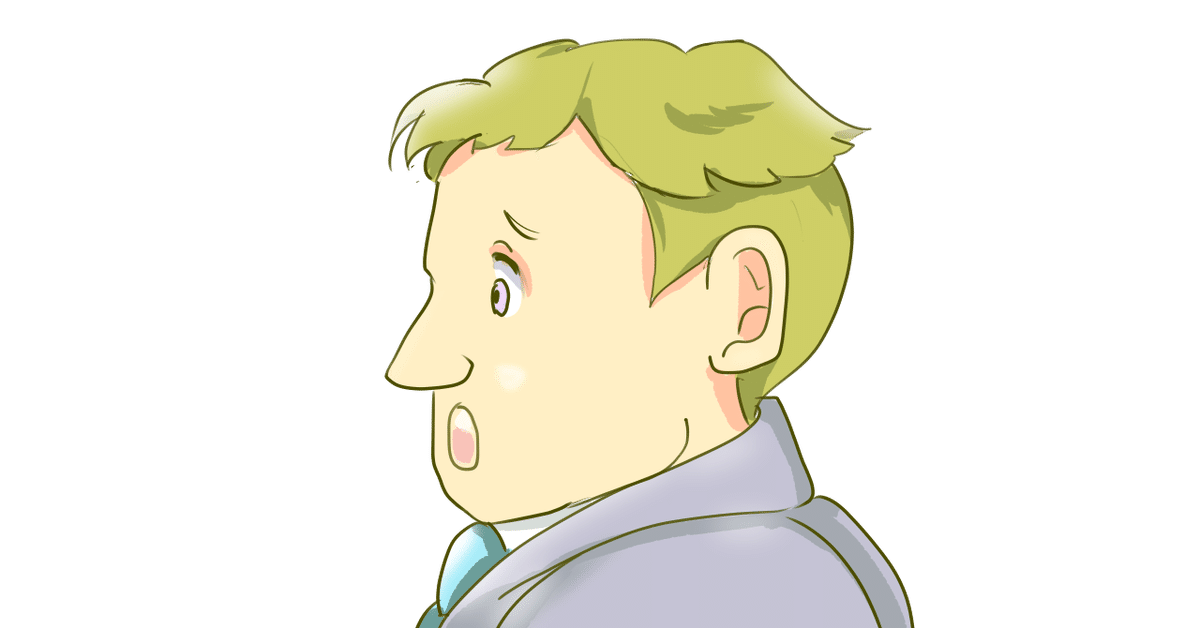
「あんた、カロリー考えな。食いすぎだ」
「そうよ、ジョン。昨日もケーキ食べたじゃない。でも、一口わけてあげよっか」
二人の楽し気なやり取りがうらやましい、と思いながら、わたしはミルフィーユを口にする。
サクサクのパイ生地と甘いカスタードに、かすかなイチゴの酸味。
おいしいのに、酸っぱい。涙の味。
「ティリーさん、どうした?」
レイターがわたしの目をのぞきこんで聞く。
わたしはあわてて言った。
「ど、どうもしないわよ。悔しいほどおいしいわ」
「ならいいけど」
レイターは優秀なボディーガードだ。
表情から、心境や体調を読み取る能力にたけている。
動揺しているわたしを、レイターに気付かれないようにしなくては。
どうしてこんなに心が揺れるのだろう。
『愛しの君』が、この世にいないと聞いて。
*
四日ぶりに自宅へ帰った。
久しぶりに家のベットに倒れ込む。幸せなひと時だ。
いつもならこのまますぐ眠れるのに。

ジョン先輩の声が、耳から離れない。
「『愛しの君』はレイターの前の彼女だよ。でも、若くして亡くなったんだ」
『愛しの君』はこの世にいない。
思えば『愛しの君』の話をするとき、レイターはいつものふざけた表情とは違う雰囲気を漂わせていた。
わたしは思い出した。
ラールシータへ二度目の出張に行った時のことを。
あの時、レイターは口にしていた。
彼女が亡くなったという話を。
「こんな世界消えちまえばいいって、思ってた。てめぇの痛みはてめぇで受けとめるしかねぇんだ」と。
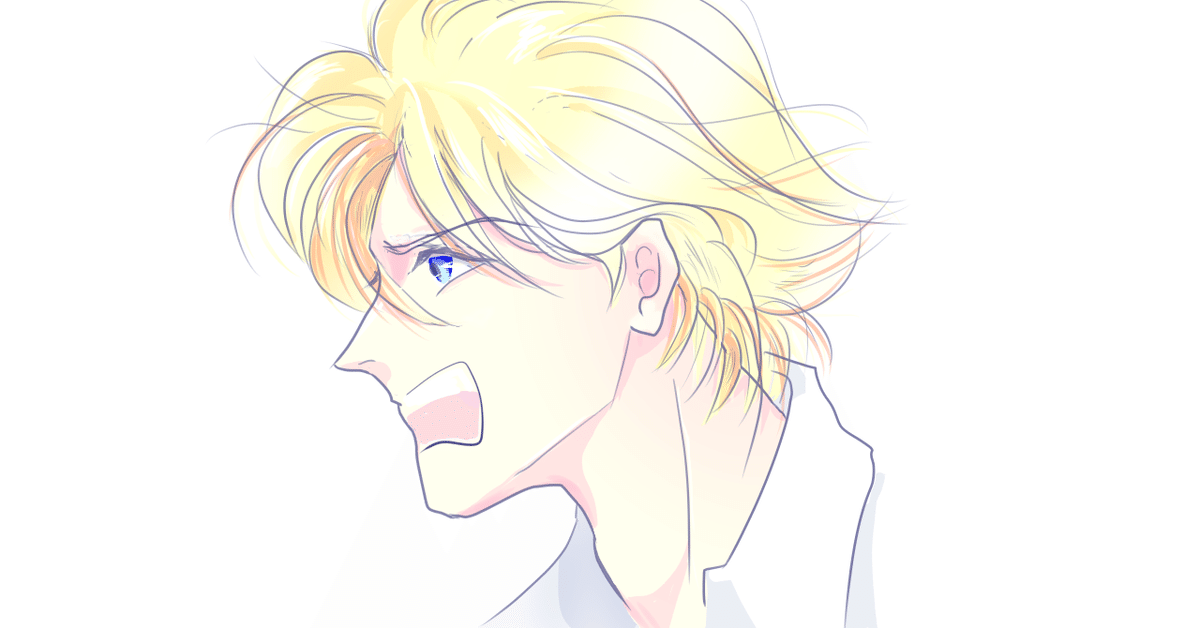
心に残る真剣な声。
あれは、本当の話だったんだ。
眠れない・・・。
レイターは、幻影を追いかけている。
だから、ジョン先輩は、『愛しの君』を追いかけるのをもう止めた方がいい、とレイターに言ったんだ。
断片的な情報が一つにつながっていく。
そして、わたしは自分が嫌になっていた。
『愛しの君』がこの世にいない、と聞いた瞬間、驚くと同時に、なぜか安堵した自分がいたことに。
(おしまい) 第二十六話「将軍家の鷹狩り」へ続く
・第一話からの連載をまとめたマガジン
・イラスト集のマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

