
銀河フェニックス物語 <番外編> おいしいお店 ショートショート
番外編ショートショート
「買ってよかったもの」「つくってみた」の続きです
一口食べてわたしは驚いた。
「おいしい!」

レイターは満足げな顔をした。
どういうことだろう。
「前に、食べた時より全然おいしいわ」
こっそりとレイターに耳打ちした。
こじんまりとした雰囲気のあるお店には、わたしたちのほかに予約客が数組入っていた。
ルク星の五つ星レストラン「リストランテ・ザブリート」には前にもベルやフェルナンドさんと一緒に訪れたことがある。
「そりゃそうさ。この前は、ほとんど俺が作ってたじゃん。ティリーさんにはザブの本気の料理を食べて欲しいと思ってさ」
調理師免許を持つレイターが作ってくれる料理はもちろんおいしいのだけれど、一流のプロはやっぱり違う。
大食漢のレイターが次から次へと注文する。
創作料理が口の中でとろけて、幸せがそのままわたしの身体に染み渡っていくようだ。お酒と合わせて、ゆっくりといただく。気がつくとほかのお客は帰っていなくなっていた。
ザブリートさんがデザートを運んできた。シンプルなプリン。
「お楽しみいただけましたか?」

このおいしさを伝えたい。どう表現したらいいのだろう。
「言葉にできないほどおいしいです」
ダメだ、ボキャブラリーが足りなすぎる。
ザブリートさんが笑った。
「いやあ、お嬢さんからお誉めの言葉をいただけてうれしいですよ。きょうは力入れて作ったからね。こいつ、あなたの好みの塩加減とか、細かくオーダーして来やがって」
「おい、ザブ」
レイターがあわてて遮る。
「料理ってのは相手を思って作るのが一番だからね。どうしたら喜んでくれるだろうって、今回はあなたのことずっと考えながら作ったんですよ。ティリーさんは、いつもレイターの料理食べてるんでしょ?」
「ええ」
わたしはうなづいた。
「『銀河一の料理人』が『操縦士』に負けるわけにはいかないからね。緊張したさ」
「大丈夫です。大勝利です!」
力強く答えると、レイターが舌打ちした。
「そこまで、力説しなくてもいいだろが」
「レイター、お前にいい話をしてやるよ」
「何だ?」
「今日の料理、ただにしてやる」
「さすがザブ、あんたは昔からいい奴だぜ」
「その代わり、レンジ磨いてくれ」
「あん?」
「お前さ、うちの料理いくらだと思ってる? 安い居酒屋じゃねぇんだよ」
ザブリートさんが伝票をレイターに見せた。レイターの表情が目に見えて固まった。
「わかったよ、レンジ磨きゃいいんだろ」
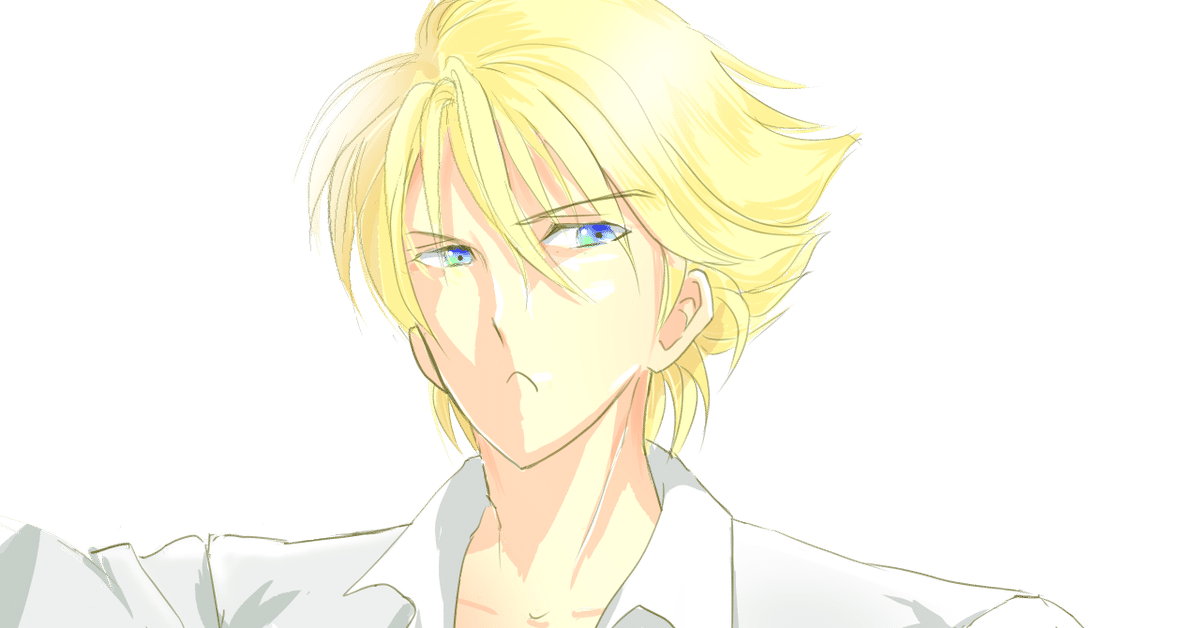
「わたしも手伝うわ」
というわたしをザブリートさんが制した。
「うちのレンジは特殊なんで、あいつにやらせたいんです」
レイターは肩をすくめて厨房へと入っていった。
*
ザブリートさんは自分用のコーヒーカップを持ってわたしの前に腰かけた。ちゃんと料理の感想を伝えなくては。
「きょうは本当においしかったです。ここでいただいた料理の味をわたしは一生忘れないと思います。銀河一の料理人はやっぱりすごいです」
「ありがとう。でもね、一生で一番おいしかった料理を思い出す時、おそらくあなたは俺の作った料理より、レイターの作った料理を思い出す。『銀河一の料理人』ってそんな程度のものなんですよ」
ザブリートさんはコーヒーを口にした。返答に困った。自虐的というわけではない。真実が込められている。
「レイターはガキの頃からプリンが好きでね、俺はいろんなプリンを作ってあいつに食べさせたことがあるんです。でも、結局あいつにとって一番うまいのは母親が作ったプリンだって言うんですよ。俺は、多くの人の『うまい』という笑顔が見たくて腕を磨いてきましたが、結局、家庭の味には勝てないでいる」
ママの作るアンタレス料理が頭に浮かんだ。
最後の晩餐を選べ、と言われて、ママとザブリートさんの料理が並んでいたら、やっぱりわたしはママの手料理を食べるだろう。
「そんな俺がこれまで作った中で、最高の出来だったのは、レイターとアーサーの妹の結婚披露宴の料理です」

わたしは息を呑んだ。
そして、思い出した。月の御屋敷で見た二人の結婚式の写真にザブリートさんが映っていたことを。
「あの時、俺はね、レイターがあんなに穏やかで幸せそうな顔をしているのを初めて見たんですよ。四年間一緒に艦に乗ってて、見ての通りあいつは明るくて楽しい奴だが、懐にナイフを隠し持っているようなところがあってね」
思わず頷く。レイターはおちゃらけて薄っぺらに見えるけれど、近づくとどこまで奥が深いのか、深淵さに立ちすくむことがある。
「そのあいつが、何て言ったらいいんだろう、とても普通の少年だったんだ。いつもは普通のフリをしていたのに。俺はそれがうれしくて、奇をてらわないオーソドックスな料理をたくさん用意したんです。あいつが好きなフライドチキンとポテトを山盛り作って、ウェディングケーキのほかにもちろんプリンもだしてね。レイターのハイスクールの友人たちというのがやってきましてね、こいつらがガツガツガツガツ気持ちいいほどよく食べたんです」

友人というのはロッキーさんだろう。彼といる時、レイターはいつも普通の人になる。
「あの日の何のひねりもない普通のメニューが、俺が作った中で忘れられない料理です。二人が心から喜んでいるのが伝わってきて、俺も料理人冥利に尽きるというか、幸せでした……それから一週間後です。アーサーの妹が亡くなったのは。そしてまた、レイターは尖っちまった。だけどね、あなたが初めてうちの店に来た時、あれって思ったんですよ。あいつがあなたを見る時の表情が、優しく普通になっていた」
ザブリートさんが真正面からわたしの瞳を見つめた。
「お願いがあるんです。あいつは食に執着があって、何でも自分でうまいこと作っちまうと思いますが、たまでいいのでレイターに料理を作ってやってください」
返事に迷う。レイターが買ってくれたフライパンでオムレツは作れるようになった。先日はミルフィーユづくりにも挑戦したけれど、生クリームを泡立てるのが面倒で市販品を買うようなわたしだ。うつむいてしまう。
「わたし、料理が得意じゃないんです」
「構わないですよ。それでも、レイターは俺の料理よりあなたの料理を選ぶから」
「ザブ、終わったゾ。あんた、俺に磨かせるためにレンジ掃除サボってたんじゃねぇのか」
レイターが手を拭きながら戻ってきた。
「おお、サンキュー。また、頼むよ」
「わかってると思うが、俺のバイト代は高ぇからな」
ザブリートさんがレイターにレンジを磨かせた理由がわかった。わたしにこっそり伝えたかったんだ。
愛する人のことを思いながら料理を作る。それが一生で一番忘れられない味へ続く道だということを。 (おしまい)
裏話や雑談を掲載したツイッターはこちら
<出会い編>第一話「永世中立星の叛乱」→物語のスタート版
イラストのマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

