
銀河フェニックス物語【出会い編】 第八話 唇よ、熱く営業トークを語れ (一気読み版)
<これまでのお話>
第一話 第二話 第三話 第四話 第五話 第六話 第七話
はああぁ。
深いため息をつくとティリーは目の前に浮かんでいる三次元映像を指で弾いた。

新型宇宙船『グラード』の宣伝用画像がゆらゆらと乱れた。
同期の女性設計士が初めてメインで造った星系外航行船のグラード。
いい船だと思う。
この船には二カ月で二隻という販売ノルマが課せられていた。
わたしは一隻目を営業部で一番早くに売った。ちょうどわたしの顧客が星系外を飛べる船を探していたのだ。
でも、その後はどんなに売り込みをかけても契約には至れず、ノルマの月末が目前に迫っていた。
明日が最後のチャンスだ。
先方の邸宅があるパル星へ向かう船の中で、わたしは呪文のように宣伝文句を唱えていた。
「居住空間性は抜群な上に、燃費もよく安全性には絶対の自信があります・・・」
はああぁ。また、ため息が出る。
デジタルパンフレットを閉じると、グラードの映像は空間に吸い込まれるように消えた。
「何、しけたため息ついてんだよ。 パル星には明日の昼に、予定通り着くからな」

居間に入ってきたレイターがわたしに声をかけた。
どうしてこんな大事な時によりによって厄病神のフェニックス号で行かなくちゃいけないのだろう。
厄病神の船で行くと契約が成立しない、と言うジンクスが営業部にある。わたしも大規模デモにテロ攻撃にハイジャックとこれまで散々な目に遭ってきた。
「いいわよね。レイターは」
「あん?」
「ノルマも何もなくて」
嫌味の一つも言いたくなる。
「ノルマねえ。ま、しょうがねぇよ。グラードは売りにくい船だ」
グラードの販売は部員のみんなが苦戦していた。だからと言って船のせいにするわけにはいかない。
「レイターに何がわかるのよ。フレッド先輩は早々とノルマを達成してるんだから」
ビジネススーツを隙なく着こなすトップ営業マン。フレッド先輩の姿が頭に浮かんだ。

「あいつはノルマが生きがいだからな」
フレッド先輩を馬鹿にした口調がわたしの癇に触った。
「そんな言い方しないで頂戴!」
「ティリーさん言っとくけど・・・」
レイターの話を聞いている暇は無い。わたしは忙しいのだ。
「わたし考えなきゃいけないことがたくさんあるの。一人にさせてくれる」
「へいへい」
レイターは肩をすくめると居間から出ていった。
*
どうしてわたしが選ばれたんだろう。
明日パル星で会う大物顧客のライネッツ・スチュワート氏は、急成長したベンチャー企業のやり手社長でメディアにもよく取り上げられる有名人。
三十代前半で財界にも発言力を持つという切れ者だ。

レイターが宇宙船レースでいつも応援しているプライベーター「チーム・スチュワート」のオーナーでもある。
これまではフレッド先輩が担当していた。
そんな大物に会いに行ってくれ、と部長から言われたのはニ日前のこと。
ほとんどアポイントがとれないという超多忙なこの社長に会うための時間と場所がすでにセッティングされていた。
スチュワート氏の予定を空けるために部長が持つルートをどれだけ駆使したのだろうか。
部長がわたしの目を見ながら言った。
「とにかくスチュワート氏に顔をつないできてくれ」
「はい。あの、でもどうしてわたしが?」
担当のフレッド先輩の都合がつかないにしても、こうしたVIPにはもっと場数を踏んだ先輩部員があたるはずだ。
「行きたくないのか?」
「いえ、行きます」
もしかしたら一番早くグラードの一隻目を売ったわたしのことが評価されたのかもしれない。
次の部長の言葉が信じられなかった。
「あ、言い忘れたが、船はフェニックス号だ」
「え、ええっ!?」
こんな大事な交渉に部長は一体何を考えているのだろう。
*
考えなきゃならない事がたくさんある。
出張が決まってわたしはすぐにスチュワート氏の顧客情報を社内データベースで検索をかけた。
担当者はフレッド先輩。
前回の購入契約日は四年前。船種はデルベガ。
デルベガはほとんど売れずにすぐ生産中止となった星系外航行船だ。
そろそろ買い換えを考えてもいい頃だからグラードを売り込むタイミングとしては悪くない。
不思議なことに、データベースにその他の情報が一切記載されていなかった。
営業時のやりとりや注意事項、実売価格も納船日もすべて空欄だ。
やり手のフレッド先輩がミスをするはずがない。
何かある。
『スチュワート氏の顧客情報が知りたいので、当時の状況を教えてください』
出張中のフレッド先輩にメールを送った。
先輩から簡単なメッセージが届いた。
『忙しいのでよろしく頼む。隣の法人営業課の分まで頑張ってくれ』
何の解決にもならない回答だった。
隣の法人営業課はスチュワート氏の会社と取引がある。失敗は許されないということだ。
プレッシャーがかかる。
けれど、裏を返せばこんな大切な仕事をわたしは任されたのだ。部長に期待されているのかもしれない。
わたしの取り柄は真面目と努力。
スチュワート氏の新聞記事や著作などあらゆる情報に目を通した。
時間が足りない。
残業して、家に仕事を持ち帰って必死に資料を作成した。
* *
高級別荘地として名を馳せるパル星。

宇宙半世紀前に発見されたこの星は知的生命体が住んでいない自然豊かな惑星だ。
環境の良さに目をつけた高収入の人たちが、五十年かけて高級別荘地を作り上げた。
この星には政府が存在しない。全て民間企業が運営している。
費用はかかるけれど税金はない。
パル星に別荘を持つのは一つのステータスだ。
ライネッツ・スチュワート氏も絵に描いたような豪邸をパル星に持っていた。
そこが今回の約束の場だった。
*
フェニックス号がパル星の中央空港に到着した。
船室でスーツに身を包んだわたしはバッグの中から小さな箱を取り出して封をあけた。
憧れの一流ブランド『アンナ』の口紅。
ずっと憧れていた。
いかにも高級そうなアンナの通信販売のページ。何度見ただろうか。
完全無欠のデパコス。一本五千リルだ。愛用しているプチプラコスメの口紅が十本買える。
わたしには分不相応だとあきらめていた。
けれど、昨日『仕事も恋も、きっとうまくいく』というアンナの広告を見かけたら、突然弾かれた様に欲しくなった。
閉店間際のデパートへ駆け込んだ。
「あなたにはこの色がお似合いよ」
アンナの美容部員が勧めてくれた色は普段使っているピンクとは色合いが違った。深みがあって落ち着いて見える。
仕事が上手くいくなら安いものだ。と自分に言い聞かせてカードで購入した。
そのアンナの口紅。
銀色のスティックをすっと回すと鮮やかでそれでいて大人びたピンク色がせりあがってきた。
美容部員のお姉さんに言われた通りリップブラシを使って輪郭を描く。
鏡に向かい、ゆっくりと唇の上に色をのせた。
いつものミルキーピンクとは顔の印象が違うように思う。

よし。がんばろう。
働く女性に圧倒的な支持を得ている『アンナ』の口紅。
「仕事はきっとうまくいく」
わたしはコピーを思い出してつぶやいた。これはおまじないだ。
*
エアカーの助手席に乗り込むと運転席のレイターがわたしの顔を見た。
「いいじゃん。その色、似合うじゃん」

ドキっとした。
自分が気合いを入れるために引いたリップにレイターが気付くとは思っていなかった。
「今度、俺とデートする時もそのルージュできめてくれよ」
「誰があなたとなんか!」
お調子者で女好きのレイター。きっと何人もの女性に同じせりふを繰り返しているのだろう。
わかっていても嬉しい。張り詰めていた緊張が少し和らいだ。
*
高級別荘地であるこの星に車の渋滞はほとんどないはずだった。
なのに大通りを走るエアカーの前に長い列が出来ていた。
「ねえ、どうしてこんなに混んでいるの?」
「事故だな」
ナビゲーションを操作しながらレイターが答えた。
「えええっ!!」
「こりゃ裏道もびっしりだ」
「先方に間に合わないってこと?」
背中に冷たいものが走った。厄病神が発動した。
「そうは言ってねぇよ。あんたを時間通りに届けるってのが俺の仕事、ノルマみたいなもんだからな」

「シートベルトつけてるな」
とわたしのシートベルトを確認すると、レイターはいきなりエンジンをふかしてエアカーを浮上させた。
「きゃあ」
渋滞の列を眼下にエアカーが飛行する。
「ねえ、飛行申請してるの?」
「んにゃ。サツにばれなきゃ平気だろ」
「着陸はどうするのよ」
「スチュワートの家なら何とかなる」
「えっ?」
レイターは操縦しながらテレビ電話を架けた。
「ハロー、スチュワート。俺だ」
モニターにあらわれたのはスチュワート氏本人だった。
「レイターか? 久しぶりだな。どうした?」

夢にまでみたスチュワート氏本人だ。
二日前、担当が代わったことを先方に伝えようと挨拶の連絡を入れた。
超多忙なスチュワート氏がでることはなく、対応は女性秘書のメリー・アンさんだった。
「これから三分三十秒後、あんたんちに到着するからな」
「これまた随分と突然だな」
「十三時半にアポが入ってるだろ」
「お前が来るとは聞いてないぞ」
スチュワート氏は嬉しそうに笑顔を見せた。
「僕ちゃんは運転手さんよ。時間通りに営業さんをお連れするからな」
「わかった。ただし、今あいてるのは垂直離発着用の五番ゲートだぞ」
「了解」
明らかに親しい間柄の会話だ。
驚くと同時に怒りがこみ上げてきた。

「ちょっと、レイターどういうこと。あなたスチュワートさんと知り合いなの? どうしてわたしに話してくれなかったの!」
「怒るなよ。昨日話しとこうと思ったのに、あんた、俺の話聞こうとしなかったじゃねぇか」
昨日のレイターとのやり取りを思い出した。確かにレイターは何かを言おうとしていた。
*
エアポートには白いポロシャツにベージュのチノパンという普段着の格好でスチュワート氏が迎えに来ていた。
「お久し」
レイターが手を挙げて挨拶をした。
「あのエアカーでよく垂直用に着陸できたなあ。相変わらずお前はいい腕してるよ」
スチュワート氏が感心している。
レイターがわたしを紹介した。
「お客さまはこちら」
「初めまして。クロノス社のティリー・マイルドです」
緊張しながらわたしはスチュワート氏と握手を交わした。
スチュワート氏の自宅に設けられた広々としたエアポートには五隻の星系外航行船が留めてあった。
その中に弊社のデルベガがあるのを確認した。
レイターはスチュワート氏に船を見せてくれと言うと、勝手に出かけてしまった。
*
案内された広いリビングは現代美術と思われる絵画や彫刻が飾られていて美術館のようだ。
大きなガラスのテーブルを挟んでスチュワート氏と向かい合った。
お客様との距離が想定より遠い。
約束は三十分間。
美しい秘書のメリーアンが飲み物を運んできた。

高そうなグラスだ。
わたしは口もつけず、すぐに本題に入った。
「スチュワート様が弊社のデルベガを購入されてから四年が経ちますけれども、そろそろ買い替えをお考えになるのにいい時期かと思いまして」
「デルベガの調子はいいよ」
即座に返事が返ってきた。
落ち着いて、落ち着いてと、自分に言い聞かせながら販売用のパンフレットを広げる。
グラードの三次元映像が浮き上がった。
「今度発売となりましたこちら新型のグラードは下取りのキャンペーン中でお勧めです。いかがでしょうか?」
スチュワート氏との間に距離があるせいで不自然に声が大きくなる。
「デルベガとランク的には変わりませんし、何と言っても居住空間性が優れておりまして・・・」
パンフレットの次のページをめくるとグラードの室内部分が映像となって現れた。
「私はデルベガを買い替える気はない」

張り上げているわけではないのによく通る声。強い意思を感じさせる。
このままでは秒殺だ。あわてて次の言葉を探す。
「デルベガを気に入っていただきありがとうございます。ただ、ご購入いただいてから年数も経っておりますし・・・」
「まだまだ、デルベガに乗り続けたいと考えているよ。私は船にはこだわりがあるからね」
スチュワート氏はS1チームのオーナーで宇宙船に詳しい。
そして、百戦錬磨の交渉を乗り越えてきた経営者。
隣の法人営業課の大口顧客でもある。
引き際を間違えて機嫌を損ねてもいけない。
次につなぐことが大切だ。
「そうですか。それでは、こちらへパンフレットを置いていきますので、興味をお持ちになりましたら、いつでもご連絡ください」
「ああ、見ておくよ」
パンフレットを閉じるとグラードの三次元映像が消えた。
セールス開始からわずか五分。わたしの仕事は不発に終わった。
厄病神のせいだ。
スチュワート氏はグラスの飲み物を一口飲むと笑顔で言った。
「レイターから買ったデルベガは飛ばしがいいんだよね。あいつが手を入れてくれたってこともあるが」
「え?」
耳を疑った。
「あの、失礼ですが何か勘違いされているのでは・・・」
今度はスチュワート氏が驚いた顔をした。
「あれ、知らないのかい? ま、レイターはすぐに営業部を辞めたからなあ」
レイターが営業にいた? クロノスの社員だったということ自体初耳だ。
「・・・わたしどもの資料によりますと、当時の担当者はフレッド・バーガーということになっておりまして」
「ああ、そうだ。そう言えば書類上そうしたんだっけ」
「え?」
「ノルマがあるからとフレッド君に頼まれたんだよ。レイターはノルマはどうでもいいって言うから、フレッド君から買ったことにしたんだ」
「・・・・・・」
頭が凍りついたように働かなくなっている。
*
忙しい中スチュワート氏はわざわざエアポートまで送ってくれた。
でもそれはわたしのためじゃない。レイターと話をするためだった。
「あんた、よく手入れして乗ってんじゃんか」
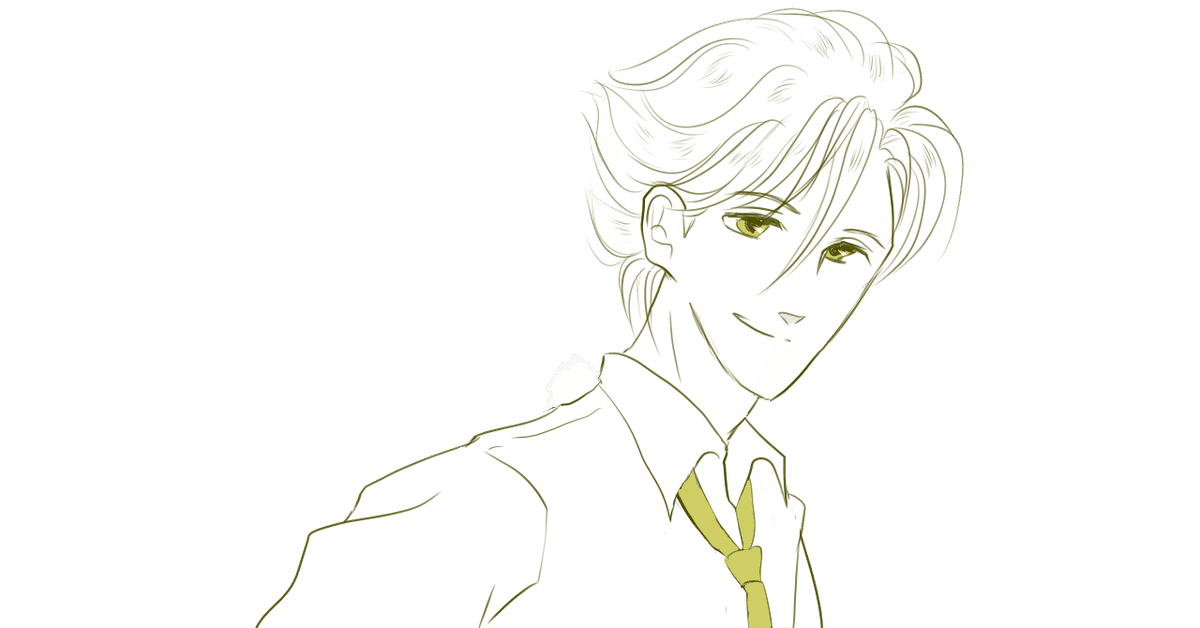
レイターの言葉にスチュワート氏は本当に嬉しそうな顔をして応えた。
「そうさ、お前が来ないから自分で調整しているんだぞ。もう少し顔を出せよ」
「俺も忙しいのさ」
「はははは、俺とどっちが忙しいと思ってるんだ」
笑顔で話す二人の会話を聞きながらわたしは部長が自分を選んだ理由に気がついた。
血の気が引いていく。真っ直ぐ自分が立っているのかもわからない。
それでもつとめて明るく振る舞った。
「スチュワートさんがレイターとこんなに親しいなんて知りませんでした。ぜひまたお声をかけて下さい。よろしくお願いいたします」
わたしは深々と頭を下げた。
*
レイターの操縦するエアカーが動きはじめると大粒の涙が頬をつたった。

情けない。悔しい。
交渉が失敗しノルマが達成できなかったからじゃない。
部長が今回自分を選んだ理由。
それはわたしを適任と判断したのではなかった。
レイターの船であればわたしじゃなくても誰でも良かったのだ。
銀河一の操縦士はクロノスの営業にいた。
どおりでわたしたちの業務に詳しいはずだ。
思い起こせば部長は「顔をつなぐように」とは言ったが「グラードを売れ」とは言わなかった。
その本当の狙いはレイターとスチュワート氏を引き合わせることにあったんだ。
おそらくこの四年間スチュワート氏とフレッド先輩はうまくいっていなかったのだろう。

このままでは折角の上客が逃げてしまうことをおそれた部長は、レイターを使うことを思いついたのだ。
わたしは何の期待もされていない名目だけの営業部員。
レイターもそのことは気づいていたに違いない。
わたしだけが何も知らずに気合を入れていたのだ。ばかみたいだ。
徹夜で情報集めて読み込んだのに・・・。
あんなに必死に資料を作ったのに・・・。
何も伝えられなかった。
涙が止まらない。
「せっかくの化粧が台無しだぜ」
レイターの声も耳に入ってこない。
渋滞は解消し、行きの混雑が嘘のように空港までの道が流れていた。
*
フェニックス号の居間のソファーに座るとマザーがホットココアを入れてくれた。
味がよくわからない。
無言ですするわたしにレイターが声をかけた。
「これからどうするよ?」
「どうって仕事は終わったわ」
両手で持ったカップを見ながらぶっきらぼうに答えた。

「スチュワートはあんたの客だ。あんたが終わりと言うなら俺は帰る準備に入るが・・・」
レイターはわたしの真ん前に座った。
「あんた、この仕事のためにいろいろ準備してきたんだろ」
「だったら何よ?」
目を合わせたらまた涙が出そうだ。
「本当に帰っちまっていいのか?」
「だって、彼はデルベガを買い替える気なんて少しも無いのよ!」
泣きそうな気持ちを隠そうすると口調が強くなってしまう。
レイターはわたしをなだめるようにゆっくりと話した。
「ティリーさん。あいつ、ひとつきどのくらい儲けてるか知ってる?」

「・・・・・・」
「超~大金持ち、金が余って困ってるんだぜ。スチュワートの頭ん中にゃ買い替えとか下取りとかそういう発想が無ぇんだ。さっき、あいつんち見ただろ。自宅に二十隻おける発着場を持ってる奴だぜ。あんたがグラードについて満足に説明した結果、あいつが買わないって言ったのかどうか気になったからさ・・・」
満足な説明。
その言葉がわたしの心をとらえた。
きょうは想定と違うことが多くてペースがつかめないうちに終わってしまった。
大物相手と言う気負いもあって自分らしい営業ができなかった。
「デルベガの調子はいい。買い替える気はない」と言われて、わたしは諦めてしまった。
レイターの言うとおりだ。
買い替える気の無い相手ならもう一隻売るという姿勢でのぞめば良かったのだ。
わたしはグラードの長所をどれだけアピールできただろうか。
絶対にお勧めの安全性についてすら話していない。
一生懸命準備してきたのに、満足なんてしていない。
契約がうまくいかなかったのは厄病神のせいじゃない。
余裕の無かった自分の力不足だ。
「ちょっと考えさせて」
わたしは自分の部屋へと戻った。
『スチュワートはあんたの客だ』
頭の中でレイターの声がこだまする。
部長がどう考えたかなんて関係ない。これはわたしの仕事だ。
鏡に写った自分の顔を見た。ひどい顔だ。
もう一度アンナの口紅をひきなおした。
通信機のスイッチを押した。
「きょう、スチュワート社長に新型宇宙船の件でお話にあがりましたクロノス社のティリー・マイルドです。先程の説明に足りない部分がございましたので、あらためてお時間をいただきたいと思い、ご連絡さしあげました」
スチュワートの秘書のメリーアンさんがモニターに映った。

「お時間は何分必要ですか?」
隙のないメリーアンさんはどこか近寄りがたい。
「三十分いただけますでしょうか?」
「三十分ですと半年先になります」
半年・・・。
機械的な反応だった。
半年先。その時スチュワートさんはわたしのことを覚えているだろうか。
「あの、十五分で結構です。いえ十分で」
「そうですか。それでしたら三カ月先に十分間お時間をおとりできますが」
「今月中はいかがでしょうか?」
必死に頼んでみる。

秘書のメリーアンさんの声は冷たかった。
「無理です。明日も銀河系を離れますし予定が詰まっておりますので」
「わかりました。そちらのご都合のよろしい時間でお願いします」
「では三カ月後の四日十三時に十分間、今日と同じ場所で」
「よろしくおねがいいたします」
通信を切ると脱力感に襲われた。
*
「どうするよ?」
居間に戻るとレイターがわたしにたずねた。
「帰るわ」
「そうか」
気持ちは吹っ切れていた。
レイターに笑顔をみせるだけの余裕も戻っていた。
「わたしね。スチュワートさんともう一度話してみようと思って、今、秘書にアポイントを頼んだのよ。だけど、三カ月先まで空いてないっていうから。出直しね」
「何ぃ? 三カ月先だと!! メリーアンの野郎かよ」
レイターが怒りはじめた。
「ふざけやがって。おい、おふくろさん。メリーアンにハッキングするぞ」
「ハッキング?」
「メリーアンはスチュワートの会社のホストコンピューターだ」
「えっ?」
「あの秘書のメリーアンは融通のきかねえアンドロイドさ」
無機質でそして完璧に美しいメリーアンの顔が思い浮かぶ。
「ティリーさん。俺が絶対スチュワートに会わせてやる」
「レイター」
「ただし、会わせるだけだ。後はあんたの仕事だからな」
大きくうなずいた。
と、その時ピーという電子音がして画面上にエラーの文字が浮かんだ。
「パスワード入力が必要です」
マザーがレイターに指示を求める。
「ばっか野郎。俺に破れねぇわけねえだろが、スチュワートごときのパスワードがよお」
レイターがすごい勢いでキーボードを叩くと画面が次々と開いていった。
「ざまあみろってんだ」
この人は何をしているのだろう。おそらくハッキングだ。そんなことが許されるのだろうか。
レイターがわたしに顔を向けた。
「なあ、ティリーさん。パーティードレス持ってる?」
「ドレス?」
「明日、デートしようぜ」
レイターはそう言うといたずらっこの様な顔でウインクした。
* *
翌日、フェニックス号は銀河系外域のAPポイントに到着した。
『ルルの湖』と呼ばれる小さな歪み重力場が紫色の怪しい光を放っている。

そのすぐ隣に目的の宇宙ステーションが浮かんでいた。
レイターによればここで開かれるパーティーにスチュワートさんが出席するという。
宇宙ステーションの駐機場にはハイグレードな高級船がずらりと並んでいる。
「すごいわね。これだけ高級な船が集まると壮観だわ」
「さて、行きますかお嬢さん」
レイターがわたしをエスコートして歩きだした。
何だかほんとにデートみたいだ。
新型船のお披露目パーティのために買ったフォーマルなアンサンブルを着てきたけれど、大丈夫だろうか。
レイターがいつもと違う。
ネクタイをきちんとしめていて、ちょっと見違える。しかも、このスーツ・・・。

「レイターったらよくそんなブランド物のスーツを持ってたわねぇ」
「こういう場所に忍び込むにゃ必要だからな」
忍び込む?
「っつっても、アーサーの奴が着ねぇって言ったのをもらっただけだけどさ」
将軍家の御曹司であるアーサーさんならいいスーツをたくさん持っていそうだ。
*
ステーションに一歩入ると足がすくんだ。
まるで観光地の王宮のようだ。
無駄としか思えない高い天井。その内装の豪華さに驚く。
こんな贅沢な宇宙ステーションは見たことが無い。
新型宇宙船の発表パーティーとは格が違う。場違いな雰囲気に胃がキリキリしてきた。
*
会場の入り口では何人もの黒服が厳重に入場者のチェックしていた。
「チケットあるの?」
「ほれ」
レイターがカード型のパーティチケットを取り出した。チケットがセキュリティーシステムを通過する。

黒服に案内される。
「レイター・フェニックス様ですね。こちらへどうぞ」
パーティ会場に入ると中は一段と華やかさを増していた。
わたしでも顔を知っている有名な財界人や文化人、それに映画俳優らがグラスを片手に談笑している。いわゆるセレブという人たちだ。
女性の着ているドレスに目が眩んだ。
わたしの月収、いや年収でも買えないものに違いない。ここは本物の社交界なのだ。
パーティチケットは一体いくらだったのだろう。経費で落ちるだろうか。
「右手奥にお飲み物が用意してございます。ごゆっくりおくつろぎ下さい」
黒服が立ち去るとレイターはすぐにネクタイを緩めた。
「レイター。あのチケットどうしたの?」
「あん? 決まってるじゃん、偽造さ」
思わずレイターの顔を見つめる。
「違法なことは止めて頂戴」
わたしたちアンタレス人は順法意識が高い。レイターはにやりと笑った。
「冗談だよ」
この人はどこまでが本当でどこまでが冗談なのかよくわからない。
*
食事はビュッフェスタイルだった。有名ホテルの一流シェフがその場で調理している。
レイターはものすごく早いペースで次から次へと食べていく。
「ティリーさんも遠慮せずに食べなよ」
料理はおいしいのだけれど落ち着かない。
「まあレイターお久しぶり」
年配の品の良い貴婦人がレイターの首に抱きついてきた。
「マダムもお変わりなく」

レイターも婦人に頬を寄せる。さらに連れ添っていた男性ともレイターは親子のように抱き合った。
「いやあ、レイターどうしていた? 最近はちっとも遊びに来ないじゃないか」
恰幅のよい白髪の男性は見たことがある。誰だったろう。
「こちらのお嬢さんは?」
「俺のティリーさんさ」
レイターがいい加減な紹介をした。やめてほしい。
「初めまして、クロノス社のティリー・マイルドです」
「ヤルドローネです」
握手をしながら思い出した。
この人、サリナス星系の前の大統領だ。ヤルドローネ前大統領と言えば大物政治家。今は銀河連邦評議会の理事をつとめている。
アンナの口紅をつけてきてよかった。
レイターに声をかけてきたのはヤルドローネ氏だけでは無かった。次々と親しげに挨拶をしてくる著名人の顔触れに呆気にとられる。
「俺、バイトでいろいろボディーガードやってるから」
そうだ、この人はボディーガード協会のランク3Aで皇宮警備にもいたのだ。
*
大広間の片側の壁は硬化ガラスになっていた。外に広がる『ルルの湖』が一望できる。
紫色の空間がゆらゆらとゆらめきながら放電し光を発している。
巨大なオーロラのようだ。
「きれぃ」

思わず見とれる。
「ほんと金持ちの考えることってわかんねぇな。こんな重力場見ながら酒飲んで嬉しいかよ」
「だって、美しいわ」
「はっきり言うけど、ここものすごく危険でやばいぜ。あの発光状態はほとんどエネルギー飽和ぎりぎりだ。俺は食うもの食ったらこんなところさっさと退散したいよ」
「仕事が終わったらね」
そう、わたしはパーティーを楽しむためにここへ来たわけじゃない。やるべき仕事がある。
「そう怖い顔しねぇで、ティリーさんこれ飲んでみなよ」
レイターはカウンターから取ってきた赤ワインをわたしに差し出した。

いつもは子ども扱いするのに、どうしてこういう時にお酒を勧めるのか。
「わたしはこれから仕事なんだってば」
「まあ、だまされたと思って」
一口深紅の液体を口に含んだ。
に、苦い。
美味なワインを想像していたわたしはあまりの渋みの強さに眉をしかめた。
「・・・レイター、あなたほんとにだましたわね」
わたしはレイターにグラスを返した。
「とんでもねえ。これ地球産の赤ワインだぜ」
「え? 地球産のワインですって」

お酒に詳しくないわたしだって知っている。地球産のワインは希少で高価。
「普通このグラス一杯で十五万リルはくだらねえ代物さ」
十五万リル・・・。ほぼわたしの手取り月収だ。
「もう一口飲ませて」
「まずいならもういいじゃねぇか」
といってレイターはグラスを渡してくれない。
「意地悪ね。どうせ、わたしには高級品の味がわからないって馬鹿にしてるんでしょ」
面白がるようにレイターは言った。
「怒るなよ。あんたは正しい。あんたの言う通りこのワインはまずい」
「まずいの?」
「輸送状態が悪かったんだ」
レイターはグラスを回してもう一口飲んだ。
「どうしてそんなことがわかるのよ」
「俺は地球人だぜ。地球で飲めばこんな味じゃねえ。もっとも、俺が運べばこんな味にはしねぇけどな」
レイターはほかの客を見ながら言った。
「みんな、地球産だ地球産だ、ってありがたがってうまそうに飲んでる。おもしれぇよな」
レイターの言葉に不快感を感じた。
「人を馬鹿にして面白がるなんて感心しないわ」
「馬鹿になんてしてねぇぜ。人間って案外単純なことで幸せになれるもんだって思っただけさ」

そうかも知れない。
時に人は口紅一つで晴れやかな気分になれるものだ。
わたしは聞いてみた。
「レイターはうちの社に勤めてたのね」
「一年だけな。フレッドと同期だぜ。俺はハイスクール中退で入ったから大学出のあいつと年は違うけど」
「レイターはスチュワートさんと知り合いだから、いつもS1レースでチーム・スチュワートを応援してるの?」
「違うよ。知り合う前からあいつのチームを応援してた。ワークスと張り合うために奇抜なこと始めたりして面白いじゃん。で、実際にスチュワートに会ったら気が合ったからデルベガを売ったんだ」
昨日のスチュワート氏の話を思い出す。
ノルマにこだわるフレッド先輩にレイターはデルベガの販売を譲ったという。
「レイターはノルマを気にならなかったの?」
「別に会社のノルマが果たせなくても命をとられるわけじゃねぇからなあ」
それはそうだけど・・・。
「わたしはレイターのように割り切れないわ。ノルマには振り回されるし、他人が自分をどう評価するのか気になって仕方が無いの」
「俺だって人から認められればうれしいぜ。ま、俺は生きていくために働いてるが、働くために生きているわけじゃねぇ。そこがフレッドとは違うところさ。なんて言ってるうちにお仕事がやって来たぜ」
レイターの視線の先にスチュワート氏が立っていた。

心臓がドキンと音を立てた。
スチュワート氏は昨日とはうってかわってタキシードを着ている。
その横には真っ赤なイブニングドレスをまとった美しいメリーアンが寄り添っていた。
レイターと目が会うとスチュワート氏は驚いた顔をし、わたしたちの方へと歩み寄ってきた。
「ほお、こんなところでレイターお前に会うとは。さては昨日のハッカーはお前か?」
「ご名答」
悪びれる様子もなくレイターは答えた。
メリーアンは無表情のまま立っている。
「ほんとお前は敵にまわしたくないよ」
「じゃあ、彼女の話を聞いてやってくれ」
スチュワート氏がわたしを見た。
「折角のパーティのお時間にすみません」
「全然構わないよ。ここは飲み物が最低だ。上のフロアーへ行こう。VIP室がある」
*
わたしたち以外誰もいないVIP室でわたしは一生懸命に説明をした。
「安全性に絶対の自信があります」

グラードの三次元パンフを近くで見てもらう。
「居住空間性は抜群によく、どの船にも負けません」
とにかく自分の知る限りグラードの長所をアピールした。細かなところまで丁寧に作られていていい船なのだ。
下手な駆け引きが通じる相手じゃない。誠意を持って理解を求めるだけだ。
スチュワート氏は時折質問をはさみながらわたしの話を聞いてくれた。
説明が終わった。
スチュワート氏はレイターに質問を投げかけた。
「なあ、レイターお前はグラードをどう評価してるんだ?」
ドキっとした。
銀河一の操縦士であるレイターはグラードのことを何と言っていただろうか。
レイターはわたしがこの仕事にどれだけ賭けているかわかっている、わたしの足を引っ張るようなことは言わないでくれるはず。
レイターはスチュワート氏に言った。
「居住空間性も飛ばしも確かにいい」
答えを聞いてほっと胸をなでおろした次の瞬間、レイターの言葉に驚いた。
「ただし、全然売れてねえ」

「レ、レイター!!」
叫んだ後、わたしはあわてて口を押さえた。
後悔したが遅かった。今の自分の動揺でレイターの言葉が本当だと裏付けてしまった。
やっぱりレイターを信用するんじゃなかった。
彼は厄病神なのだ。
何と無神経なのだろう。
彼は今、自分がどんなに大変なことを言ったかわかっているのだろうか。
平然とした顔のレイターに憎しみすら感じた。
覆水盆に返らず、落花枝に返らずだ。
わたしは二人に割り込んだ。
「先程も説明いたしましたように、スチュワートさんのようにお忙しく宇宙を飛び回っていらっしゃる方は船で過ごされる時間も長くなられると思います。船内の快適さは出張先で厳しいお仕事をなさる方にこそ必要です。安全性の高さは経営のリスク回避の面からも有効です。自信を持ってお勧めします!」
もうこれ以上話すことはない。
しばしの沈黙の後、スチュワート氏が静かに口を開いた。
「メリーアン。カードを」
「はい」
「で、これはいつ納船されるのかい?」

スチュワート氏の質問がわたしの頭に入ってくるのには数秒かかった。
「ら、来週にはご自宅へお届けできます」
「そう、どうせならレイター。お前が運んできてくれよ」
「暇だったらな」
バッグから契約ボードを取り出し、スチュワート氏のサインをもらう。
カードを通すと、ピッという聞きなれた電子音が聞こえた。
身体中から力が抜ける。あとはデータを本社へ転送するだけだ。
メリーアンが突然口を開いた。
「スチュワート様。お時間です。早く退避しないと危険です」
「もうそんな時間か。急ごう」
「何がそんな時間なのさ?」
レイターが聞いた。
「お前、知らないのか? 今日のパーティーのメインイベントの時間だよ。ここの動力を切って宇宙ステーションを『ルルの湖』にとりこませるんだ。贅沢の極みだろ」
「何ぃ? そんなことしたら臨界点越えてクリティカル爆発おこすじゃねぇか」
「そうさ。それを鑑賞するためにみんな集まっているんだよ」
これほどゴージャスな宇宙ステーションを爆破させるとは。
「正気じゃねえな」
「安心な中にもスリルを味わいたいのさ」
スチュワート氏の言葉が終わるか終わらないかという時、突然全員の体が浮き上がった。
「スリルどころの話じゃねぇぞ。重力調整できなくなってるじゃねぇかよ」
わたしの体がくるくると揺れた。
「きゃあ。レイターどうすればいいの?」

厄病神が発動した。
「スチュワート、メリーアンに重力制御させろ」
レイターの指示通りメリーアンが重力制御装置で床に着陸した。
わたしたちの身体は浮かんでいる。
レイターは右手でメリーアンの左手を握り、左手でわたしの身体を抱きかかえた。
スチュワート氏も不安定な体勢のままメリーアンの逆の手を握る。
「さて、メリーアンちゃん、船まで走って頂戴よ」
レイターの声に反応し、メリーアンが高速で走り始めた。赤いドレスには深いスリットが入っていた。
無重力でナイフやワインの瓶などがぷかぷか浮かんでいる。
その中をメリーアンは平気で進んでいく。けれど生身のわたしたちは当たったら大けがだ。凶器となって飛んでくる物からレイターが身体でわたしをかばう。
「メリーアン私を殺す気か」
「これ、俺の一張羅だぜ」
「どうしてこんな目にあうの・・・」
三人の声を無視してメリーアンは猛スピードで走る。
脱出できなかったら命はない。
階下の大広間はすでに避難を終えていて誰もいなかった。
*
どこをどう走ったのか駐機場へ到着した。フェニックス号の船のタラップには軽い重力制御がかかっていた。
二百メートルほど先にデルベガが留まっているのが見える。
あんなに並んでいた高級船は他に一隻も無い。
レイターがマザーに呼び掛けた。
「おふくろさん、出発準備に入ってくれ」

フェニックス号を目を細めて見ながらスチュワートさんがレイターに話しかけた。
「なあ、レイター。頼むよ。フェニックス号売ってくれよ」
「あんた船買ったばかりだろが」
「金はいくらでも積むと言ってるだろ」
「駄目っつったらだ~め」
「俺は他人と同じ船に乗りたくないんだよ」
スチュワートさんのつぶやきを聞いてはっと気づいた。
思えばデルベガも売れていない機種だった。
レイターは人と違うものを欲しがるスチュワートさんの性格を考えて、「グラードは売れていない」と言ったのだ。
そして、スチュワートさんはレイターの読み通りに購買意欲をそそられた。そこには巧妙な駆け引きが存在していた。
レイターを無神経だと思った自分が恥ずかしくなった。
「クリティカル爆発まであと七分です」
メリーアンが警告を発した。
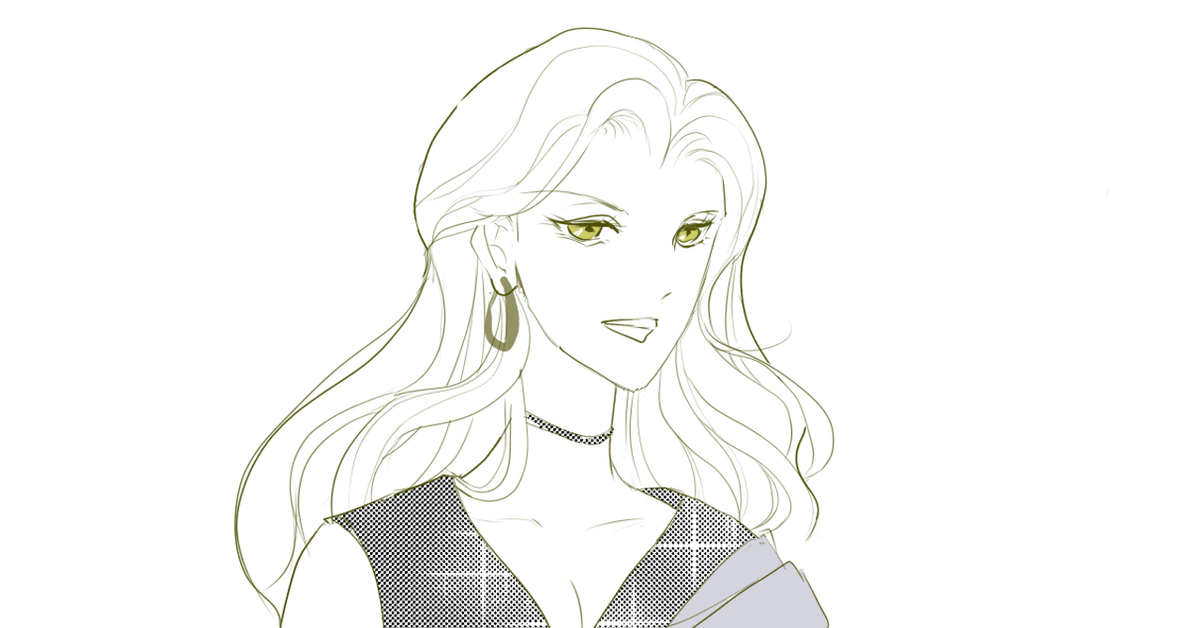
「スチュワート、どうする? とりあえずフェニックス号で安全圏まで逃げるかい」
「いや、大丈夫だ。メリーアン、船へ戻ろう」
メリーアンがスチュワート氏を軽々と抱き上げた。
「じゃあ、レイターまたな」
「ああ」
メリーアンはフェニックス号の側面を思いっきり蹴った。
すごい初速。慣性の法則だ。無重力の中を一気にデルベガへと飛んでいった。
レイターが驚いてメリーアンが蹴った船のボディをなでていた。
「メリーアンの野郎、船に傷がついたらどうすんだよ!」
*
レイターとわたしが乗り込むとフェニックス号は宇宙ステーションを離れた。
「それにしても大変なデートだったなぁ」
「デートじゃないわ仕事です」
反論したその時、レイターが驚いた声をあげた。
「ティリーさん。あんたかばん・・・」

「え? ええぇぇっつ!!」
肩から下げていたバックを見ると、止め金がはずれふたが開いていた。そして妙にバッグが軽いことに気がついた。
恐る恐る中をのぞく・・・。
「きゃああ、何も無い」
「契約ボードは?」
「・・・な、無い! まだ、契約データを本社へ送信してないのよ!」

無重力のごたごたの中でハンドバックの中身が全て飛び出していた。
わたしの契約どうなっちゃうの?
スチュワート氏に何と説明すればいいの?
本社にどう報告すればいいの?
頭の中がぐるぐると回りパニックになる。
レイターは非常口に掛かっている宇宙服を着はじめた。
「おふくろさん、一旦停止しろ」
「ど、どうするの?」
「俺がとってきてやる。爆発まで後何分だ?」

「四分二十三秒です」
マザーが答えた。
「退避時間は三十五秒でいけるな。おふくろさん、十五秒区切りでカウントダウンを頼む」
レイターはジェット・パックを背負うと入り口に立った。
「ちょ、ちょっと」
「心配すんな。コーヒーでも飲んで待っててくれ。俺はプロだ」
ウインクをしてレイターは宇宙空間へと飛び出した。
*
わたしは腰が抜けたようになって非常口のホールに座り込んだ。
時間が経つにつれ少しずつ思考が戻ってきた。
「ねえ、マザー。クリティカル爆発ってどういうこと?」
「ルルの湖がエネルギー飽和を起こして重力臨界点を超えたときに発生する爆発です」
「それが、これから起きるわけ」
「三分十二秒後です」
「レイターは大丈夫なのよね?」
「わかりません」
マザーの答えにむっとする。
「わからないってどういうことよ」
「重力崩壊に閉じ込められる可能性とクリティカル爆発に巻き込まれる可能性の双方から計算すると、現時点での生還率は十五・二%です」
全身から血の気が引いていく。
「ちょ、ちょっと待って」
フェニックス号の操縦席へと走った。
メインスクリーンにはルルの湖に少しずつ飲み込まれていく宇宙ステーションの姿が映し出されていた。
さっき見た時より明らかに放電の光が強くなっている。

紫色の空間が心臓の鼓動のように大きく波をうっている。
重力波がかなりの力で振動しているのだ。
あの中にレイターがいる。
「マザー、お願い! レイターに連絡して。戻ってきてって伝えて!」
「現在、カウントダウンを進行中です。それ以外の通信回線はレイターが開かない限り使えません」
「契約なんてどうだっていいのよ。そんなもの、そんなもののためにレイターが死んだらわたしどうすればいいの・・・何とかして! ねえ、マザー答えてよ!」
わたしは泣き叫んでいた。
ノルマで命をとられるわけじゃない。
レイターの言葉が実感を伴って迫ってきた。
彼にとって仕事とは死と隣あわせの存在なのだ。
「レイターお願い。戻ってきて!」
「クリティカル爆発まであと十秒」
宇宙ステーションはすでに飲み込まれ姿が見えなくなっていた。
エネルギーを得た『ルルの湖』は紫色から白色へと光り輝き始めた。
「・・・三、二、一。時間です」
マザーのカウントダウンが終わった。
白くなった『ルルの湖』の中心からオレンジ色の光が何本もの柱となってほとばしる。
思わず目を見張る。
学生時代、古くなった高層ビルを人工的に爆破し解体させるという催しを見に出かけたことがある。迫力ある光景だった。
安全な中でスリルを楽しんだ。
似ているけれどスケールが桁違いに違う。壮大な現象。
お金持ちだけが見られる人工的な天体ショー。美しいと言えば美しい。
でも、わたしには悪魔の光に見えた。
レイターは? レイターはどうしているの?
メインスクリーンの画像にノイズが走り乱れる。
安全圏にいるフェニックス号にも衝撃波の振動が伝わってきた。
そして、
光の放出が終わった。

光を乱反射していた塵すらきれいに重力場が吸い取り、そこには何もない宇宙空間が横たわっていた。
*
「マザー、レイターと連絡をとって!」
「先程から呼び掛けていますが応答がありません」
もう通信回線は開くはず。
「ど、どういうこと・・・」
マザーは答えない。
スクリーンをじっと見つめる。どこかにレイターが映っているのではないかと目をこらしてみる。
動くもの何一つ無い暗い空間が映っているだけだ。
安全圏まで退避してフレア爆発を見ていた高級宇宙船が一隻、また一隻と帰っていく。
「レイターは必ず帰ってきます」
そう言うとマザーはコーヒーをいれ始めた。
とにかくレイターを信じて待つしかないのだ。わたしは非常口へ向かった。
*
そして、マザーの言うとおりレイターは帰ってきた。
「よっ、ただいま」

出かけた時と同じようにレイターは普通に帰ってきた。
通常の船外点検を終えた後のように、何事も無かったかのような顔で帰ってきた。
「ほら」
レイターは宇宙服のポケットから契約ボードを取り出した。
「こ、こんなもの」
「こんなものとはこれまたひどい言い様だねえ」
わたしは混乱していた。ずっと胸が張り裂けそうな緊張の中にいたのだ。
「だって、だってだって・・・。心配したんだから」
「さすが俺のティリーさん、俺のこと心配してくれたんだぁ」
笑ってあおるレイターに腹が立ってくる。
「連絡ぐらい入れなさいよ!」
「爆発ん時の電磁波障害で通信機がやられちまったんだ。経費で落とさねぇとな」
気持ちを整理しよう。
レイターはわたしのために命懸けで契約ボードを取ってきてくれたのだ。きちんとお礼の言葉を言わなくては。
その時だった。
「そうだティリーさん。これ、あんたのだろ?」
レイターは銀色の小さなスティックを取り出した。
それはあの『アンナ』の口紅だった。「仕事はきっとうまくいく」とわたしを支えた高額コスメ。
わたしは震える手で口紅を握り締めた。

「馬鹿よ馬鹿。あなたは大馬鹿よ!」
*
契約ボードのデータを本社へ送信した。
スチュワート氏との契約が成立した、という連絡をフェニックス号から入れると、部長の興奮した返事が返ってきた。
「そうか。いやあ、ティリー君、君ならやってくれると思っていたよ」
モニターに映る部長の笑顔を見ながら白々しい言葉だ、と思った。
部長はわたしでは無くレイターがうまく立ち回って契約を成功させたと思っている。
そして、それは事実。
レイターと一緒で無かったらおそらく契約をとることはできなかった。
それは、自分が一番よくわかっている。
「これでノルマも達成だ。おめでとう。帰ったらゆっくり休んでくれ」
「ありがとうございます」
今回の契約はわたしにとって大きな仕事だった。
ノルマを達成した安堵感もある。
だけど心から喜ぶ気持ちにはなれなかった。
*
居間のソファーでコーヒーを飲んでいるレイターに声をかけた。
「仕事は終わったわ」
昨日も同じ場所で同じ言葉を言った。
あの時レイターが止めてくれなかったら、今頃わたしはどうなっていただろう。
契約もノルマも何も果たせず自信もプライドも無くして会社へ戻る自分。
それを思えば契約ができた今は天と地の差だ。
でも、自分一人では何も出来なかったことに変わりはない。
「了解。じゃ帰る準備に入るぜ」
レイターはわたしの前に立った。
「ティリーさん。もっと嬉しそうな顔したらどうだい。仕事はうまくいったし、部長も褒めてくれたんだろ」
「口ではね」
「俺なんか客が無事に戻ってきて当たり前。誰も褒めてくんねぇから、自分で褒めてやるんだぜ。レイター君、君は素晴らしい、ってな」
この人は、仕事をきちんと務め上げる。けれど、評価は「厄病神」だ。
出張に来る前はレイターのノルマの無い生活をうらやましく思っていた。
自分は本当に何もわかっていなかった。
レイターの手がわたしの髪に触れた。見上げると澄んだ海のようなレイターの瞳があった。

「あんたはほんとよく頑張ったよ。俺がほめてやる」
その言葉を聞いた瞬間、こらえていたものが一気に吹き出した。
感情に押し流されるまま、レイターの胸で泣いた。
今度あらためてレイターにお礼を言おう。
そして、あの口紅でデートを誘ってみよう。
『仕事も恋も、きっとうまくいく』 (おしまい)
第九話「風の設計士団って何者よ?」へ続く
あわせて聞きたい こちらが「唇よ、熱く君を語れ」 ↓
いいなと思ったら応援しよう!

