
銀河フェニックス物語【少年編】第九話「金曜日はカレーの日」まとめ読み版
銀河フェニックス物語 総目次
<少年編>第八話「ムーサの微笑み」
<少年編>マガジン
戦艦アレクサンドリア号、通称アレックの艦。
銀河連邦軍のどの艦隊にも所属しないこの艦は、要請があれば前線のどこへでも出かけていく。いわゆる遊軍。お呼びがかからない時には、ゆるゆると領空内をパトロールしていた。
*
将軍家の坊ちゃんは、ソツがないと言う言葉がぴったりの少年だった。

アーサー・トライムス少尉。十二歳の彼が絶滅民族インタレス人の血を引き、僕たちには想像も出来ないような知能を持つ天才少年だ、と言うのはこの艦の誰もが知っている。
彼はそれを殊更に目立たせない様に、もちろん鼻にかける事も無く、ひっそりと暮らしている様に見えた。それでも艦内における存在感は圧倒的だ。
坊ちゃんの任務はアレック艦長とモリノ副長の補佐で、通信兵の僕は、坊ちゃんとの接点はほとんどない。
バルダンに聞いてみた。
「将軍家の坊ちゃんと話したこと、あるかい?」

「あるぜ。ヌイはないのか?」
「挨拶しかないな」
「坊ちゃんの戦闘能力はただ高いだけじゃねー。考えてることが面白いんだ。話していて勉強になる」
白兵戦部隊のバルダンは訓練の後、坊ちゃんと戦術の話で盛り上がるのだという。天才軍師である坊ちゃんの頭の中にはありとあらゆる星系で起きた過去の戦闘の具体例がインプットされているのだそうだ。
バルダンが熱く語る。
「検索するより坊ちゃんに聞く方が早くて便利なんだよ」
少々失礼な感じがするが。
「仕事以外の話はするのかい?」
「趣味の格闘技の話もするぞ。身体の使い方を見直すのにいいんだ」
「それは、お前さんにとっては趣味かも知れないけれど……」
坊ちゃんにとっては仕事の一環なんじゃないだろうか。
僕が坊ちゃんに興味を持ったのは、彼が食堂のアルバイトのレイターと同じ十二歳で、同室で暮らしている。と言うことからだ。
「レイターと同い年には見えないよね」
「そうだな、レイターは十二歳に見えないほどガキだし、坊ちゃんは下手すりゃ大学生でも通じるぞ」

二人は一体どんな会話をしているのだろうか。
*
お腹が空いた。
残業を終えて自分の部屋に戻るとレイターがギターを鳴らしていた。同室のバルダンが僕のベッドに腰掛けて弁当を食べている。
ああ、今日は金曜日か。
バルダンはカレーライスが嫌いだ。
「辛いし、臭いし、見た目もグロいし、あれは食い物じゃねー」

戦闘機乗りだったモリノ副長が前に乗っていた艦では、週末との区切りになる毎週金曜日の夕飯がカレーと決まっていたそうだ。
この話を聞いた料理長のザブリートさんが喜んで取り入れることにした。メニューを考える手間が省けるということらしい。
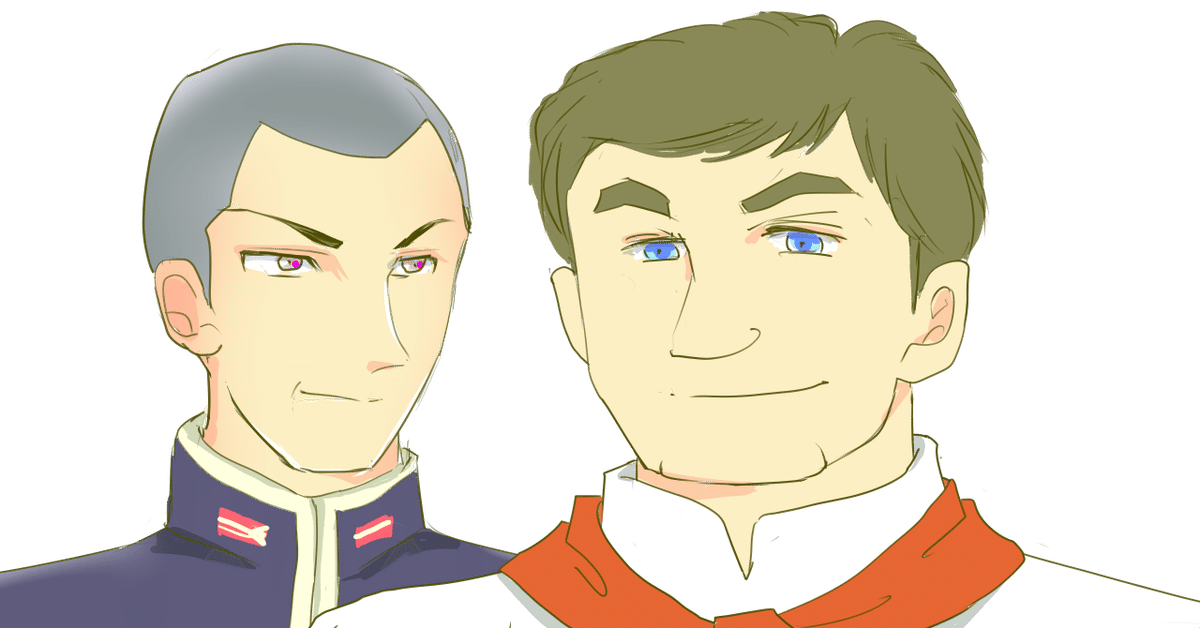
バルダンは怒っていた。
「こんなまずい食い物が毎週出るなんて話は聞いてねー。知ってたらこの艦志望しなかったぞ」
って。
だから、金曜日はバルダンは食堂に近づかない。レイターに別の弁当を部屋まで持って来させて食べている。
「カレー、おいしいのに」
と言うレイターをバルダンは殴ろうとした。
「止めろ! 俺はその言葉を聞くだけで嫌なんだ」
カレー、と聞くだけで匂いがしてくるのだそうだ。そんなことはあるはずないが、バルダン本人は感じるらしい。
「ちっ、俺、昨日泣きながら玉ねぎ刻んだんだぜ。スパイスは身体にもいいんだぞ」
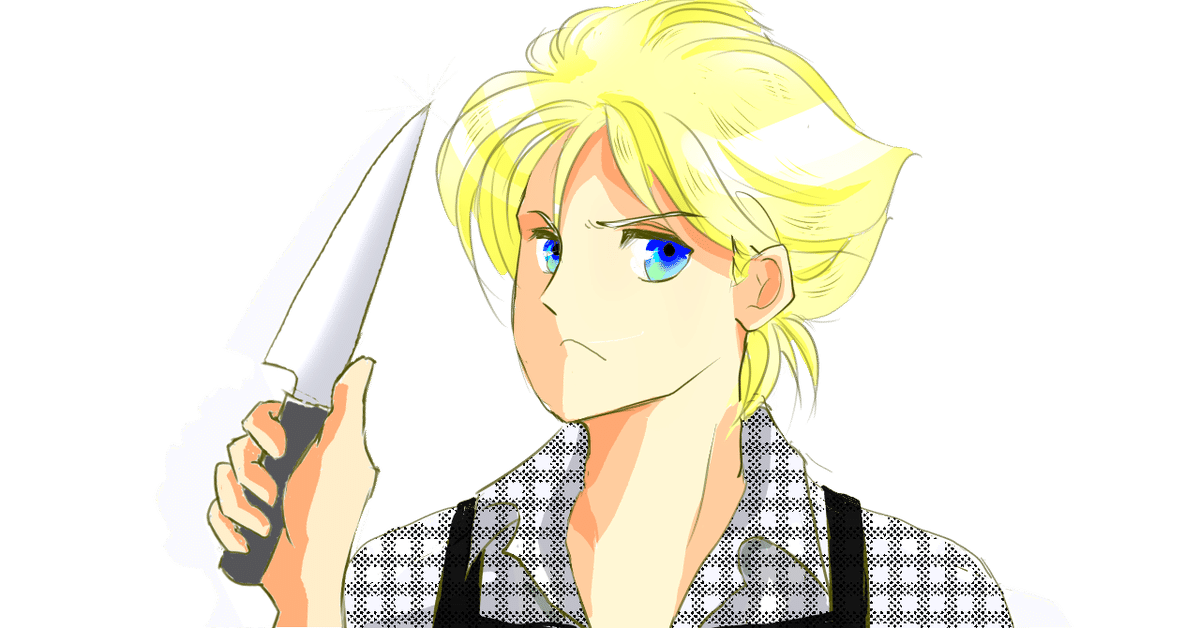
レイターが文句を言っている。話をしていたら無性に食べたくなってきた。カレーには圧倒的な誘引力がある。
「じゃ、僕は食堂へ行ってくるよ」
「食べた後はうがいしてから帰ってこいよ」
「わかった。わかった」
バルダンは僕からカレーの匂いがするだけで気分が悪くなるという。
食堂に近づくとカレーのスパイシーな香りが漂ってきた。
条件反射的に楽しい気分になる。金曜カレーの効果だ。今週末は勤務のシフトが入っていない。
バルダンがカレーを苦手とする理由はわかっている。
僕とバルダンが育った星は温暖で、郷土料理に激辛のような刺激的な食べ物がないのだ。僕も初めて口にした時は戸惑ったけれど、いろいろな星系を飛び回っているうちに食べ慣れるものだ。今では辛い料理がクセになっている。
時間の遅い食堂に人はまばらだった。
僕の前に坊ちゃんが並んで姿勢良くカレーを受け取っていた。

僕はつい、声をかけてしまった。
「通信兵のヌイです。ご一緒してもよろしいですか?」
坊ちゃんは少し驚いた顔をして振り向き「ええ」と答えた。
この反応から察するに、これまでバルダン以外に隊員から声をかけられたことがないのかもしれない。
坊ちゃんは十二歳で士官学校を首席で卒業して、軍曹の僕より階級が上の少尉だ。ほかの隊員と談笑をしているところを見たことがない。いつも一人で本を読んでいる。
一見すると成人男性に見える。身長も僕より高い。まだ、伸びるのだろう。声変わりも終えて少年ではなく男の声だ。
向かい合って座った。
「いただきます」
坊ちゃんは礼儀正しい。
「いただきます」
スプーンですくって口にする。
料理長のザブリートさんが『アレクサンドリアカレー』と名付けた色の濃いビーフカレー。
ブロック肉が柔らかく煮込まれていて、口の中でほどける。ライスと相性抜群の辛さだ。

食べ始めてから気がついた。坊ちゃんとの話題を何も考えてなかったことに。
さて、どう切り出そうか。
「美味しいですね」
坊ちゃんが僕の顔を見て言った。
絶妙のタイミングだ。無言の空気で場が重たくなる寸前に言葉を投げかける。計算、と言う言葉がチラリと頭に浮かんだ。会話のタイミングも完璧に管理しているんじゃないだろうか。
「そうですね。レイターが泣きながら玉ねぎを切ったそうですよ」
と、僕も言葉のキャッチボールを投げ返す。
彼は軽い笑顔を見せた。微笑むと少年らしさが残っている。
父親譲りの黒い髪。知性を湛える緑がかった黒い瞳。美しく整った顔立ちは目を引く。少しだけ芸能界にいた僕が見てもスターの要素が満載だ。
坊ちゃんを特集した軍の広報誌が、一般女性陣による購入で見る間に売り切れたことは話題になった。

「ヌイさんは暗号通信士としてトップレベルとうかがっています。オグランド戦線で活躍されたんですね」
「活躍と言うほどではないですが」
彼は一目見ればすべてを記憶する能力の持ち主だ。履歴書を書いた僕より僕のテキスト情報を持っているに違いない。
「僕は実戦に出るのは初めてなので、色々と教えてください」
「いやいや、少尉にお伝えできることなんてありませんよ」
人当たりもいい。けれど、そこにも作り物のような完璧さが漂っている。
坊ちゃんは思わぬ提案をした。
「仕事でなければ階級で呼ばなくていいですよ」
「何とお呼びすれば?」
「坊ちゃん、でも」
「え?」
隊員たちは陰で少尉のことを『将軍家の坊ちゃん』と呼んでいる。それは、親しみを込めて、というよりは揶揄している。坊ちゃんもそのことはわかっているはずだ。
「冗談です」
一瞬、聞き間違えたのかと思った。
僕はうまく笑えているだろうか。完全無欠な彼は人間らしさを示すために、わざと僕に欠陥を見せようとしているのだろうか。
「アーサーと呼んでください。バルダンもそう呼んでいますから」
坊ちゃんが僕たちと距離を縮めたいと思っていることはわかる。が、恐れ多くて僕には無理だ。次期将軍を呼び捨てにできるバルダンはすごいな。
「そうなんですね。知りませんでした」
さらりと受け流す。
坊ちゃんはオグラント戦線に興味を持っていた。
経験した範囲のことしか話せないが、僕は暗号通信士として現場と上層部の行き違いも見てきた。
カレーを食べながら簡単に伝える。
「ありがとうございます。勉強になります」
と次期将軍は頭を下げたが、何だか聴取されているようだった。
僕は聞いてみたかったことを坊ちゃんに投げかけた。
「レイターと仲はいいんですか? どんな話をしているのか興味があって」

天才少年が初めて言葉に詰まった。
「それは、……レイターに聞いてみて下さい」
カレーが便利なのは、素早く食べ終えることができるところかもしれない。
「お先に失礼します」
坊ちゃんは静かに席を立った。
*
「ぐえぇ」
僕が部屋に戻るとバルダンとレイターが格闘技の技をかけあっていた。いや、かけあっているのではない、レイターが一方的に技をかけられていた。
「バルダン、ほどほどにしろよ」
と僕が言った瞬間、バルダンが叫んだ。
「ヌイ、うがい!」

忘れてた。自分では気づかないが、カレーの匂いがしたのだろう。その隙にレイターが技から抜け出した。
僕は洗面所でミントの香りのうがい薬を口に含んだ。レイターがニヤニヤと笑ってこっちを見ている。こいつが悪だくみを考えている時の顔だ。
「なあ、レイター、お前さんは坊ちゃんと仲は良いのかい?」
「は? いいわけねぇだろ」
即答だった。
裏を返せば、坊ちゃんは他人に対して否定的な表現をしないよう教育されているということだ。彼は将軍家という権力が人を傷つけることを自覚している。
*
週明け、月曜日のことだった。
訓練を終えたバルダンが部屋へ入ってくるなり、タオルを床に投げつけた。
「くっそー。レイターの野郎」
こんなに怒っているバルダンを見るのは久しぶりだ。一体レイターは何をやらかしたんだ。
「どうしたんだい?」

バルダンは僕をじろりと見ながら言った。
「言えるか!」
言いたくないんだ。これは一人にしておいた方がいいな。僕は静かに部屋の外へと出た。
バルダンが怒っている理由はすぐにわかった。艦の中はその話で持ちきりだった。
レイターが格闘技訓練でバルダンに勝ったというのだ。
これまでレイターがバルダンに勝ったことはない、というか一点も入れたことはないはずだ。身長が三十センチ以上離れている二人の間合いは違い過ぎて、レイターの突きや蹴りは届かない。
そのバルダンにどうして勝つことができたのか。
理由はすぐにわかった。
レイターは金曜カレーの残りを食べて格闘技訓練に臨んだのだ。「カレー」と息を吹きかけながらの攻撃に、バルダンは耐えられなかったらしい。隙だらけだったという。

金曜日、僕がうがいをしている時に、悪だくみを思いついた顔をしていたのはこれか。レイターは訓練中に坊ちゃんの目に砂を投げつけたこともある。小狡い くそガキ。実にあいつらしい。
それをまたレイターは「バルダンに勝った」と自慢げに自分で触れ回っている。
部屋に戻るとバルダンは床に座ってまだ落ち込んでいた。
「実戦だったら殺されていた。俺もまだまだだな」
夕飯の片づけが終わる夜のこの時間は、いつもならレイターが部屋に顔を出す頃だ。だが、バルダンに卑怯な手を使ったレイターはしばらくこの部屋に遊びに来ないだろうな。と、思った時だった。
「バルダーン、元気ぃ?」

レイターが勢いよくドアを開けた。
あいつの神経の図太さに驚く。子どもって奴は何て単純なんだ。バルダンがレイターをにらみつける。
「怖い顔するなよ。ってもともと怖い顔なのか。大丈夫だよ。うがいしてきたから」
そう言いながらバルダンに飛びかかった。

技をかけようとするレイターをバルダンはあっという間に力で押さえ込んだ。
狭い部屋の中で二人はいつもの様に技をかけあい、いや、いつものようにレイターが一方的に技をかけられていた。
「ぐげぇ」
「参ったか?」
「イタタタタ。降参、こうさーん。もうカレー攻撃はしねぇから、離せやい」
それで二人は仲直りしていた。
バルダンは単純なところがある。
僕は気がついた。レイターはバルダンとの関係を良好に保つために、わざと技をかけられにこの部屋へ来たのか。
あいつは、人の懐に飛び込むのが上手い。それに見た目より色々なことを考えている。両親を亡くし、あの年で苦労して生きてきたのだろう。バルダンよりよっぽど大人なんじゃないのか。
見た目が幼いレイターは、隊員たちにかわいがられている。
一方で、見た目が大人という同い年の少年は、他人を近寄らせないものをまとっていた。
*
将軍家直轄の特命諜報部からアレック艦長へ暗号文が届いた。

暗号通信士はこの艦に僕しか乗っていない。艦長室へ呼ばれた。緊張しながら部屋に入ると艦長と坊ちゃんがいて、すでに暗号は坊ちゃんによって解読されていた。
小惑星帯に紛れている敵アリオロン軍の武器庫の座標と内部情報だ。音階暗号符ではなく通常暗号文だった。
「ヌイ軍曹。解読文の確認を頼みたい」
艦長から命令を受ける。
「はい」
前線に近づいていることを感じる。
間違えるわけにはいかない。
座標の数値符丁は難解だ。一つずつ誤らないようにほどいていく。手元に数字を写して変換させて次の数値にあてはめる。
アレック艦長がいらだった声をだした。
「結構時間かかるんだな。アーサーは一分で解いたぞ」
これを一分で解く? 無理だ。僕が無理なのではなく、普通の暗号士では無理だ。
「申し訳ありません。五分はいただかないと間違う恐れがありますので」

恐縮する僕の横で、坊ちゃんが艦長に説明をする。
「艦長、自分は書き写す作業が必要ないため、時間が短縮されているだけです」
全てを記憶する坊ちゃんは、書き写して変換することを頭の中だけでできるということだ。さすが天才少年だ。
なんてことを考えている余裕はない。暗号に集中しなくては。
結論に近づくにつれてわかる。坊ちゃんの解読は非の打ち所がない。僕がこの艦に乗っている意味はないんじゃないだろうか。プライドが傷つくな。
「解読終了いたしました。少尉の解読に間違いはありません」
僕が答えると同時に坊ちゃんから肩の力が抜けたのがわかった。
「よかった。数値符丁は難しいので」
このつぶやきは謙遜じゃない。
僕はシンガーソングライターだった。いつも創作のネタを探して、人を観察する癖がある。耳もいいから相手の話すトーンから本音を読み取ることもできる。
目の前の天才少年は心から安心し喜んでいた。物事を完璧にこなすイメージがあるから意外だ。と思うと同時に、彼がまだ十二歳だったことを思い出した。
「ヌイ軍曹、ご苦労だった。あす、この武器庫を強襲する。バルダンたち白兵戦部隊に暴れてもらうとするぞ。さあ、天才軍師、すぐに作戦を立てろ」
アレック艦長は坊ちゃんに命令を下した。相変わらず人使いが荒い。
暗号情報によれば、明晩、武器庫から大量の兵器の移動が計画されている。その前に叩くということだ。
*
天才の坊ちゃんが立てた計画は完璧だった。
敵の隙をついて白兵戦部隊が武器庫に突入。
兵器が運び出される前に作戦を終え、意気揚々とバルダンは部屋へ帰ってきた。
「武器庫の見張りは全員捕虜にして、こっちもあっちも人的被害はゼロだ。武器は全部押収してやったゾ。結構ヤバイ物が隠されてた」

「お疲れ、とにかく無事でよかったよ」
「上手くいったのはヌイが解読してくれた情報のおかげさ」
僕より先に坊ちゃんが解読していたけどね。と心の中でつぶやく。
レイターが部屋に入ってきた。
「バルダン、弁当持ってきたぜ」
そうか、きょうは金曜日だった。
「アレックがほめてたぜ、きょうの作戦はバルダンの戦闘能力が高いから成功したんだって」

「あのぐらい屁でもねーよ」
と言いながら、バルダンは満足げにニヤリと笑った。 どこで艦長の誉め言葉を聞きつけたか知らないが、レイターは人たらしだ。艦内の情報にやたらと詳しい。
艦長の評価通りバルダンは優秀だ。
特殊部隊並みの作戦を難なくやり遂げる。精鋭部隊に入隊する能力もある。
「お前さんはどうしてエリートの特殊部隊に名乗りをあげないんだい?」
弁当をかきこみながらバルダンが答えた。
「特殊部隊への憧れはある。だが、ヌイ、お前が一番わかってるだろ。俺がどうやってハイスクールを卒業したか」
思い出した。
「卒業試験で、教師を脅したんだったね」
バルダンがむっとした顔で反論した。
「脅したんじゃない。お願いしたんだ。卒業できないとマフィアに入ることになるから助けてくれって」

レイターが驚いた声を出した。
「バルダンって、マフィアだったの?」
「違うに決まってるだろ」
とバルダンがレイターの頭をはたいた。
「痛てぇな、暴力はマフィアのやることだぞ」

レイターが口をとがらせて屁理屈を言った。
「バルダンは僕たちの英雄だったのさ」
あれは、ハイスクールの卒業が近づいたころだった。マフィアのクロコダイルが毎日校門で張っていた。格闘技部主将のバルダンを探しているという噂だった。
「仕方ねーだろ。殴っちまったんだから」
うちの生徒がクロコダイルの下っ端に絡まれていた。偶然そこを通りかかったバルダンが助けに入り、そのチンピラをのしてしまったのだ。
レイターが目を輝かせる。
「へぇ、かっこいいなバルダン。クロコダイルはなんせクズだ。構成員が質より量だからな」
「お前さん、妙なことに詳しいね。とにかく、クロコダイルのボスがバルダンを気に入ってマフィアに入るよう迫ったんだ」

早食いのバルダンは弁当を食べ終え、自分から続きを話した。
「そん時にはもう軍の入隊が決まっていたから断ったんだが、卒業試験の結果が悪くてな。卒業が入隊の条件だったから、俺は担任の教師に頼みこんだんだ。とにかく卒業させてくれ、と。教師も教え子をマフィアにするわけにいかんから、追試をしてくれたんだが、これも点が悪かった。だから、俺は校舎の手入れを手伝うことで加点をもらって卒業したんだ」
レイターがほっとした様子で肩をすくめた。
「バルダン、よかったなぁ。今、クロコダイルは壊滅状態だぜ。あんなところにいたら、この間の抗争で死んでたかも知れねぇよ」
レイターの地元がマフィアの抗争で戦地のように街が荒れたという話を思い出した。それで裏社会の情報に詳しいのか。
バルダンがスプーンをくるりと回しながら言った。
「まあ、この艦も死には近いがな。今日だって生きて帰れる保証はなかった。自分の能力を高めるためにも、特殊部隊の訓練に興味がある。だが、あそこへ入るにゃ俺の苦手なペーパー試験があるのさ」
それが理由だったのか。
「でも、お前さんは白兵戦の勉強は欠かさないじゃないか」
バルダンは身体能力が高いだけじゃない。天才軍師の坊ちゃんと議論を戦わせるほど戦術にも詳しい。
「俺は勉強が嫌いなんじゃない。文字を書くのが苦手なんだ」
*
懐かしい昔話をしていたら、すっかり遅くなってしまった。
カレーの香りが漂う食堂には誰もいなかった。みんな今日の戦闘で腹を空かせたのだろう。
第四金曜日は、定番の『アレクサンドリアカレー』とは異なる様々なカレーが出る。きょうは明るいオレンジ色のチキンカレーだった。
僕が席に着いて食べ始めると、食堂に坊ちゃんが入ってきた。
お疲れのようだ。
きょうは彼にとって初めての実戦だ。自分の立てた作戦で、白兵戦部隊のバルダンたちが死んだかもしれない。緊張が続いたに違いない。
アレック艦長が坊ちゃんに仕事を押し付けている、という噂がある。仕事の速い天才が残業していたのは、きょうの検証報告書の作成までやらさせられたのだろう。
まだ、十二歳だというのに。
普段は一人で食事をする坊ちゃんが僕に声をかけてきた。
「ヌイ軍曹、ご一緒していいですか?」

彼をねぎらいたいと思った。天才軍師の次期将軍、ではなく、十二歳の少年アーサーを。
「もちろんです。きょうはお疲れさまでした。ヌイでいいですよ。僕もアーサーと呼びますから」
と伝えると、硬かった坊ちゃんの表情が和らいだ。
フルーティなチキンカレーは、口にした瞬間は甘いのにピリリとした辛味が舌を刺す。
「ビーフカレーもいいけれど、これはこれで、おいしいね」
僕の感想に坊ちゃんがうなずく。
「そうですね。このぐらい甘味があってもバルダン軍曹は食べられないのでしょうか?」
「辛さだけじゃなくカレーの香りも苦手だから、無理だと思うよ」
厨房の奥に料理長のザブリートさんの姿が見えた。

レイターはバルダンに弁当を届けに行ったまま戻っていないようだ。「カレーは後片付けが楽だから俺がいなくても平気なんだよ」とうそぶいていたことを思い出す。サボりだな。
それに比べて坊ちゃんは、子どもの頃からずっと自分を律してきたのだろう。
一見、無表情に見えるけれど、その奥に多彩な感情が動き回っているのがわかる。レイターと同じように少年らしい感受性を内に秘めている。
柔らかいチキンの手羽元をくずしながらたずねる。
「アーサーは暗号を解く時、解を事前に予測できるのかい?」
「そうですね。指示暗号文は初見の段階で結論が見えることがあります」
それは暗号学のベテラン教官並だ。
「すごいなぁ。暗号通信士の試験を受けたらいいんじゃないかい? 資格手当も付くよ」
おちゃらけながら勧めてみた。次期将軍の坊ちゃんにとっては資格手当に魅力はないだろうけれど、暗号を扱うのであれば本来は暗号通信士の資格が必要だ。今回の武器庫の暗号も、公式には僕が解読したことになっている。
「無理です」

坊ちゃんは首を横に振って、苦しそうな顔をした。疲れていることもあるのだろうが、彼のこんな表情は初めて見る。
「難関試験と言ったって、僕でも受かったんだよ」
「音階暗号譜が解けないのです」
確かに音階暗号符は絶対音感がないと解読は厳しい。
「基本言語はできるとレイターから聞いたけれど」
「かなり苦労しました。僕は耳から得る情報の再現がうまく出来ないのです」
坊ちゃんは目で見たものをそのまま記憶して再現することができる。一方で、耳から入ってくる情報は思うように扱えないのだと言う。
「レイターの様に耳で聞いた音を当てるとか、楽譜をそのまま音にすることが僕にはとても難しくて」
「絶対音感を得るには幼少期のトレーニングが必要だからね。でも、相対音感なら今からでも身に着けることはできるよ」

将軍家に音楽は必要ない。坊ちゃんはこれまで楽器の演奏や、歌を歌うという経験がほとんど無いのだと言う。音楽に対してコンプレックスがあるようだ。
「アーサーは、歌は歌えるかい?」
「連邦軍歌なら」
「歌ってみてよ」
「ここで、ですか?」
と驚いて目を見開いた様子は、普通の十二歳の少年だった。
「誰もいないから大丈夫だよ」
彼はカレーのスプーンを置くと少し照れながら軍歌の初めのフレーズを小さな声で口ずさんだ。

低くていい声だ。音程も外れていない。音痴と言う訳じゃ無い。
簡単に言うと、演奏を習ったことのない普通の人と同じなのだ。逆にこれでよく、音階暗号譜の基本言語を習得できたなと感心する。「苦労した」と彼が言うのは相当に努力したのだろう。
「全く問題ないよ。相対音感を磨いて音階暗号符を解けるようになった人はいるから、無理というわけじゃないと思う」
坊ちゃんは深いため息をついた。
「どうしてレイターは音階暗号符が解けるのでしょうか?」
珍しい。表情を表に出さない彼がいらだっているのがわかる。
「まあ、レイターには絶対音感があるからね」

坊ちゃんはレイターに出来て、自分に出来ないことに焦りがあるようだ。
僕が軍へ入隊する前、五年以上前に見たテレビの番組を思い出した。
様々な分野の教授陣と議論を戦わせる七歳の将軍家の跡取り。
歴史でも数学でも淡々と澱みなく論破していく幼い姿に驚くとともに、どこかで安心した。
さすが将軍家だ。
『見えない戦争』に連邦軍が負ける筈はないと。

その期待に応えながらアーサーは生きている。
体格にも運動神経にも恵まれた彼は、十二歳ながら士官学校を首席で卒業した。
何事も人並み以上にできてしまうアーサーにとって、よもや、自分と同い年の少年に負けるということはあり得ないのだろう。屈辱的な出来事なのかもしれない。
天才少年であるが故の経験値の低さ。
「レイターは特別だよ」
「特別?」
「うん、特別ムーサに愛されている」
「ムーサ? 音楽の女神ですか?」
「そう。プロだった僕でもかなわないぐらいに。悔しいけれど、自分が得意な分野でだって他人よりできないことがあるのは当たり前だよ」
「当たり前、ですか」
次期将軍は僕らとは違う世界を生きている。でも、僕らの世界と交わらない訳にもいかない。
「そうさ。レイターの母親は、彼の中に音楽の種を植えて丁寧に育てていた。絶対音感もそう。音楽で食べていけるという選択肢、生きていく力を授けたんだ」
「生きていく力……」
「なのに、レイターは音楽の道へ進む気がまるでないんだよ。ほんと、もったいないよなぁ」
「彼は『銀河一の操縦士』になるのが夢ですから」
「あの執着はすごいよね。アーサーに夢はあるの?」
と聞いてから馬鹿なことを口にしたと思った。坊ちゃんには決められた道しかない。
「世界平和に貢献できればと思っています」
ごく自然に彼は答えた。
それが当たり前だ、世の中の真理だ、とでも言うように。
十二歳の高尚な夢。
坊ちゃんは、それを心からやりたい、自らの夢だと思っているのだろうか。
浮かび上がる違和感とともにチキンカレーを口に運ぶ。香辛料の香りが鼻から抜けていく。
ターメリック、コリアンダー、ガラムマサラ、クミン、カイエンペッパー、エトセトラエトセトラ……刺激あるスパイスが混ざり合って一つのカレーが出来上がる。

レイターの夢は単純だ。
本心。
素材そのものの味しかしない。
一方で、坊ちゃんの夢は複雑だ。
建前、思惑、期待、義務感、世間体、エトセトラエトセトラが複雑に融合して形作られている。
もはや、アーサー本人でも嗅ぎ分けられないのではないだろうか。素材である本心を覆い隠すスパイシーな香りが、坊ちゃんから匂い立っていた。
(おしまい) 第十話「二段ベッドの上で見る夢」へ続く
<出会い編>第一話「永世中立星の叛乱」→物語のスタート版
イラストのマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

