
銀河フェニックス物語【出会い編】 第三十九話 決別の儀式 レースの前に まとめ読み版②
・銀河フェニックス物語 総目次
・第三十九話 まとめ読み版①
背後から声がした。
「無理じゃねぇよ。そいつはS1の安全規定充たしてんだから」

レイターが立っていた。
「強度はそうですが、可燃性が高過ぎます」
オットーが反論する。
「レギュレーションに禁止されてなきゃS1は何でもありだろが」
ボリデン合金の船なんて誰も考えないから規定にもない。レイターが続けた。
「メガマンモスのエンジンで、九十三パーセントの馬力を出せればエースと並べる」
オットーが声を荒げた。
「それは机上の計算だ。ナセノミラのコースは直線よりカーブが多い。直線番長が有効とは思えない」
「俺さぁ、S1でメガマンモスふかしてみてぇんだよ。銀河最速だしてぇんだ」
直線番長と呼ばれるメガマンモス社のエンジン。
無骨なデザインでとにかく馬力がある。直線ルートの最速記録はメガマンモスが持っている。昔からそれを売りにしていて、メガマンモスにはコアなファンがついている。
話を聞きながら俺は愉快になった。
「メガマンモスには俺も憧れがある。アラン・ガラン、オットー、何とかやってみてくれ」
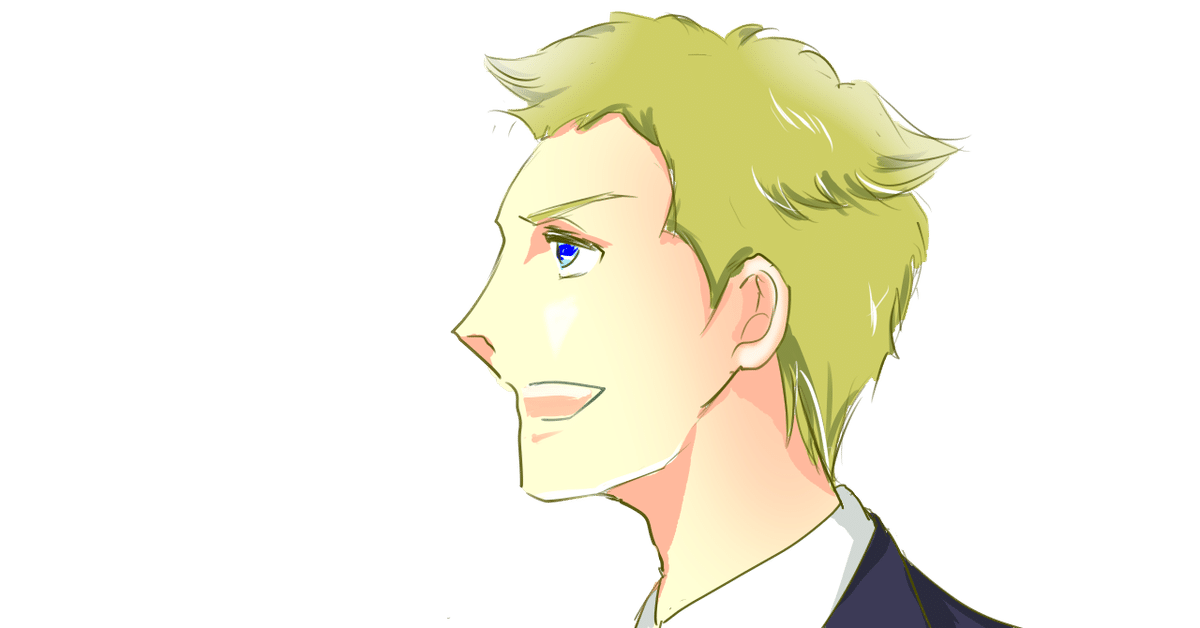
オットーは不満そうな顔をした。
だが、オーナーの俺の言葉は絶対だ。チーフのアラン・ガランは左足を貧乏ゆすりさせながらつぶやいていた。
「九十三パーセント、九十三パーセントなら工夫すればいけるか・・・」
* *
「ティリー、仕事が終わったら食事に行かないか」

仕事が終わると時折エースはわたしをディナーに誘った。
お値段の張るお店、隠れ家的なお店、エースはわたしが普段行かない、いや、行けないようなお店をよく知っていた。
世間の人にはつきあっていると誤解されているから、二人で食事をしてもなんの詮索もされなかった。
フェルナンドさんの運転する高級エアカーで出かける。エースは街の中でエアカーを操縦しない。事故を起こさないためだ。
「専務、明日の会議資料は事前に目を通しておいてくださいね」
「ティリー、専務と呼ぶのはやめてくれ。もう、仕事は終わった。エースでいい」

「は、はい、エース」
普段本人がいないところで散々呼び捨てにしているのに、本人を前にエースと呼ぶには勇気が必要で、なかなか慣れなかった。
エースとの会話は仕事の延長のようだけれど、楽しい。
わたしの趣味はS1レースの観戦なのだ。宇宙船の話は尽きない。
自然と次回のS1の話になる。
「S1チャンネルでギーラル社のオクダがインタビューに答えてました。最後にエースを倒すのは俺だ、って気合入っていましたよ」

「彼とはデビュー戦からずっと一緒だからね。オクダはいいレーサーだよ。僕が勝てているのはうちの技術のおかげだ」
「謙遜してますね」
「謙遜じゃないさ。僕の連勝はクロノスの船が壊れないからできていることだ。ギーラル社の船はムラがある。今季のマウグルアはいい船だけれどね」
「そうですね。マウグルアは若い人にも人気があります」
わたしの頭に真っ白なマウグルアが頭に浮かんだ。レイターとバトルをした飛ばし屋の『白魔』もマウグルアに乗っていた。

あの時のバトルを思い出すと、今でも胸が震える。
コーナーを回ってゴールへ飛び込んだ時に感じた『あの感覚』。
世界が白く輝く幸福感。
あの日「ずっと一緒に飛んでくれ」と言ったのは誰だったか。

「ティリー、どうかしたかい?」
エースの声で我に返った。
「な、何でもありません。『無敗の貴公子』がいなくなったらS1が寂しくなりますよね。わたし個人としてはやめて欲しくないです」
「ありがとう、ティリー。僕自身は引退の会見をして、精神的に随分楽になったよ。レース最終戦に向けての集中も高まった。やることはすべてやってきたから悔いはない」
かっこいい。こんなセリフをさらっと決められるのは、さすがわたしの推し。いや、わたしの友人だ。
「それに、父の具合がよくないからね」
わたしが役員室に異動になってから、エースの父である社長に会ったことはない。自宅で静養しているという話を聞いている。
すでに実態としてはエースが経営を仕切っていた。S1を引退したら、エースが社長に就任することが内定している。
「早く父を安心させたいんだ」
そこでエースは言葉を切ると、わたしを見つめて続けた。
「プライベートでもね」
ドキッとした。
今、暗にエースは結婚をにおわせた。
エースが間合いを詰めてくる。
わたしは気付かないふりをして会話を続ける。
「べヘム社の兄弟ウォールって、二人が一緒に表彰台に上ったことがないんですよね」

「彼らはどちらか一人が勝てばいいと思っているからね」
「エースが引退すると、二人がそろうかも知れないですよ。来シーズンからは表彰台の様子もがらりと変わりますね」
「レイターはどうするんだろうか? 来季も乗るのかな?」
「さ、さあ」
エースの前でレイターの話は避けていた。そうするのが正しい気がしていた。
でも、エースの疑問はわたしの疑問でもあった。
銀河一の操縦士はどうするつもりだろう。
このままS1レーサーになるのだろうか。違和感が止まらない。「人を乗せて飛ぶのが好きなんだ」と笑うレイターの顔が頭に浮かぶ。

「レイターがハールに積むエンジンのこと聞いているかい?」
「いえ、普通に考えると機体と同じギーラル社のマウグルアでしょうか? 今シーズンはエンジンもいいですから」
エースが愉快そうな顔をした。
「僕もそうかと思ったんだが、違った。どうやらメガマンモスが供給されたらしい」
「ハールにメガマンモス?」
思わず大きな声を出してしまった。
面白いけれどありえない。
「研究所のジョンが必死に強度計算を始めたよ。ハールの素材が普通のものとは違うそうだ」

「宇宙船お宅の考えていることはわたしにはわかりません。でも、レイターはハールを熟知しています」
「どう言うことだい?」
「ハールの耐久性が低いことを彼は発売当初に見抜いていたんです」
「ほう」
「あのころ、ハールとの戦いで営業は随分苦労しました」
取引先にギーラル社の魔法使いがハールを売り込みに来ていたことを思い出す。
レイターとアーサーさんに助けてもらって何とか契約にこぎつけたのだ。懐かしさがこみあげる。

「経営も大変だったよ。そのハールも今では不人気船だがね」
当時、レイターが予想した通り、ハールは故障船続出という展開になっている。そんな中、あえてハールを選択したのだ。あの人は。
「レイターはきっと、思いもしないことをしてきますよ」
「どうして?」
どうしてと聞かれると困る。
「銀河一の操縦士ですから」
「ティリーは、レイターの話をするときは楽しそうだね」
「そ、そんなことありません」

あわてて否定する。
エースはそれ以上は踏み込まなかった。
「ティリーたちが頑張ってくれているおかげで、クロノスは成長できているんだ。感謝するよ」
微笑みながらグラスを掲げた。
エースは紳士だ。まさに貴公子。わたしを子ども扱いするレイターとは全く違う。わたしを一人の女性として見てくれる。素直にうれしい。
しかも、それだけではない。
「友だちですから割り勘にしてください」
と言うわたしに
「役員の僕が割り勘にしたら、ケチな男に見えるだろ」
と言ってエースは自分のカードで支払いをした。
そして、帰りのエアカーの中で、
「二千リルもらおう」
と、いくらかわたしからお金を受け取った。
対等な友人でありたい、というわたしの考えを尊重してくれていた。
エースがわたしに宣言したことを思い出す。
「僕は他人の気持ちがわからないことがあるが、人の気持ちを理解したいと思っている」

エースには相手の感情を考えず、正論で追い詰めてくるところがあった。
彼はその欠点を少しずつ修正していた。頭のいい人だ。わたしだけでなく、他人に対する人あたりが柔らかくなっている。
天才の孤独。
無敗の貴公子はずっと一人で戦ってきたのだ。トップを維持するために常に自分で決断し人を導いてきた。
元々の気質とその立場がエースという人格を形作ってきたことが、少しずつわかってきた。
推しのエースが、友人のエースへと変わりつつある。
一方で、充たされていない自分がいた。
レストランでおいしい料理を口にすると、つい比較してしまう。レイターが作るご飯が無性に食べたい。

自分が嫌になる。
あの頃には戻れないのだ。前に進むしかない。
迷いや想いを断ち切るためにも、わたしはいっそ、エースとつきあった方がいいのではないだろうか。
* *
「ティリー、仕事が終わったら食事に行かないか」
誘うのはいつも僕からだな。そう思いながらエースはティリーに声を掛けた。
ティリーと食事をするのが楽しい。

彼女は僕に憧れていて、僕は彼女を好きだ。なのに、なぜこれを恋愛と呼べないのだろう。
これまで僕にガールフレンドがいなかった訳ではない。大学時代にはクラスメートとつきあっていた。
たまたま社会経済学の授業で、隣の席になった女性だった。
授業を休みがちな僕のために、ノートを用意し講義を教えてくれた。時に教授の悪口を交えて話す、その様子がかわいかった。
彼女とつきあい出した頃、僕はS1に乗った。
そのまま連勝して無敗の貴公子と呼ばれ、メディアにも注目されるようになった。
*
僕は幼い頃から、論理的に物を考えることが得意だった。
その一方で、他人を思いやる、という気持ちに欠けたところがあった。
例えば、年下の面倒を見る、というようなことだ。
先生から言われればやるが、自発的に世話をしよう、という考えが浮かぶことがなかった。
簡単に言えば、他人に興味がないのだ。
父の仕事の影響で、僕は三歳の頃から宇宙船のチャイルド機に乗り出した。
僕には人の気持ちより、船の気持ちの方がよくわかった。
「きょうは右に回って飛びたくないんだね」
船とならいくらでも会話を続けていられる。
経営者である父は、他者との関わりが薄い僕に不安を感じていたようだ。
あるべき論をよく僕に語った。
困っている人がいたら、利益を求めず率先して助けろ、というような話だ。
助けた対価をもらってはいけない、その非合理的な理由が本当のところ僕にはよくわからなかった。
尊敬する父の話をもとに、この状況にはこう対処するというパターンをいくつも覚えて実践した。
自分より弱いものが泣いていたら素通りせず「どうしたの?」と声をかける。

なぜ声をかける必要があるのかと言うことを考えてはいけない。僕は対人コミュニケーション力の不足を、丸暗記でカバーした。
十歳の時に、僕はレースのジュニアチームに正式に入った。
いい成績も自分。悪い成績も自分。
自己中心的な僕にとって、そこは居心地の良い世界だった。
僕は船の機嫌をチームに伝える。監督もメカニックも僕の言葉に従って動き勝ち進んでいく。
結果を出していれば、煩わしく人と関わる必要がない。
そして、僕は、孤高の世界にたどり着いた。
多少コミュニケーションに難があっても「天才だから」という言葉で許される世界へ。
S1で勝ち続ける僕を見て、父だけは心配していた。
「お前はレーサーを辞めたらどうする。クロノスを継ぐ意思はあるのか」
「はい、もちろんあります」
僕はクロノスの船が好きだ。僕が父の後を継ぐという結論は一番理にかなっている。
「経営で大切な資源は人だ。そのことをよく覚えておきなさい」
「はい」
僕は父に逆らったことがない。父は常に僕を正しい道へと導いてくれる。
*
大学時代に付き合っていた彼女は、レース、というかそもそも宇宙船に興味がなかった。
彼女とはいつも他愛のない話をしていた。僕は流行りの音楽やドラマを彼女との会話から知った。

「エースは一流なんだから、芸術やファッションを知って、デザインを学ぶべきよ」
という彼女に連れられて、ブランド店を歩き回った。
僕は、彼女にたくさんのプレゼントを贈った。
彼女がチョイスする高級なレストランやバーにも出かけた。
無敗の貴公子と呼ばれ始めた僕は、あり余るほどの賞金を手にしていた。お金を使うことに何の躊躇もなかった。
今、思い返しても、彼女のセンスはよかった。
若手デザイナーとの交流は、その後も僕の仕事の役に立ち、彼女に教わった店は僕の贔屓の店となった。
僕にとって彼女と過ごす時間は有益で、レースの緊張を和らげる息抜きでもあった。
ある時、彼女が突然、僕との結婚について切り出した。
一緒に旅行に出かけ夜も共にする仲だ、不思議な話ではない。けれど、僕は、強烈な違和感を感じた。
僕はずっと疑問を感じていた。
彼女は一体、僕のどこが好きなのだろうかと。
船とレースのことで頭がいっぱいの僕と彼女の間で交わす会話は表層的でどこかピントがずれていた。
「新しいお店がトレンドに上がっていたの、ちょっと遠出してみない?」
「行けるとすれば、次のレースの後だね」
「レースいつだっけ?」
「二週間後さ」
僕にとって彼女は、レースに集中するために必要な存在だった。
彼女は僕の何を必要としているのだろうか。
彼女が僕を友だちに自慢しているのは知っていた。悪い気はしなかった。
だが、そんなある日、彼女の友だちが彼女に送ったメッセージをたまたま目にした。
「優良物件を手放しちゃだめだよ」
人の気持ちを推し量ることが苦手な僕にも、彼女の真意が見えてきた。
彼女は僕ではなく僕のブランドが好きだということに。
大企業クロノス社の御曹司で一番人気のS1レーサー。お金で手に入るものなら迷わずして手に入れられる。

出会った時は、互いに純粋な好意だった。
けれど、僕が段々と有名になり賞金を稼ぐようになるにつれて、関係は少しずつ変遷していった。
彼女はいつしか『無敗の貴公子』と別れることに、恐怖を抱くようになっていた。
手にしたステイタスを手放したくない。そのために結婚という契約で僕を縛りたいと考えたのだ。
一方、僕の中で彼女の利用価値は下がっていた。その頃の僕には息抜きも気分転換も必要なかった。ただ、レースに集中したかった。
結婚という選択肢は取れなかった。
*
大学を卒業し、彼女と別れた僕はレースに邁進した。わがクロノスは船がいい。僕は負けるわけにはいかないのだ。
無敗が続く。
続けば続くほど苦しさが増してきた。「誰がエースの無敗を止めるのか」という記事を見るたびに、世界中が僕の負けを待ち望んでいるように感じた。
勝つ喜びより、負けないプレッシャーが上回り始めた。
二年前のS1プライム。
僕は疲れていた。レースに出るな、という脅迫状が届いたのはそんな時だった。
僕はどうかしていた。
脅迫状を見ながら僕は、自作自演による欠場を思いついた。魅惑的に思えた身勝手な計画。
阻止したのはレイターだ。「あんたが襲われたいのは勝手だが、守るほうは命がけだってこと忘れんなよ」と言われて目が覚めた。

そして、レースに出場した僕は暴漢に襲われ、レイターが替え玉出場した。
混乱の中、たまたま僕の隣にいたのがティリーだった。
ティリーが僕のファンだと言うのは知っていた。
S1プライムに応援部員として彼女が来ることになった時、営業部長は笑いながら言った。
「無敗の貴公子の大ファンですから、少々こき使っても大丈夫です」
他人に興味のない僕でも、人に好かれることは気持ちがいい。
一緒に仕事をしてみて、真面目で一生懸命なティリーのことを可愛く思った。

僕は卑怯だ。
ファンのティリーなら、僕の過ちを許してくれると思ったのだ。
僕は自作自演の罪をティリーに告白した。
そして、思った通り彼女は僕を責めなかった。
不思議なことに、ティリーの前にいると僕は素直になれた。
彼女が見ているのは無敗の貴公子だ。生身のエース・ギリアムではない。わかっている。それでも、僕の隣にいて欲しいと思った。

彼女のことが知りたい。
彼女を喜ばせたい。
自分のためではなく、ティリーのために何かがしたい。何の見返りもいらない。ギブアンドギブで構わない。
こんな気持ちは初めてだ。
これが他者への関心と思いやり、そして愛と呼ばれるものなのだろう。
僕は頭で暗記したことを初めて心で理解した。
「経営で大切な資源は人だ」
父の言葉が自分の中で血肉化していく。僕にはティリーが必要だ。ティリーを契約で僕だけのものにしたい。前の彼女が僕を手放したくないと感じた気持ちが今はわかる。
僕の前を行く父は、まもなくいなくなる。
誘導灯を失っても、ティリーとなら僕は正しい道を歩いていける。
* *
腕組みをしたまま、アラン・ガランは薄っぺらいハールの機体を見つめていた。
左足の貧乏ゆすりが止まらない。
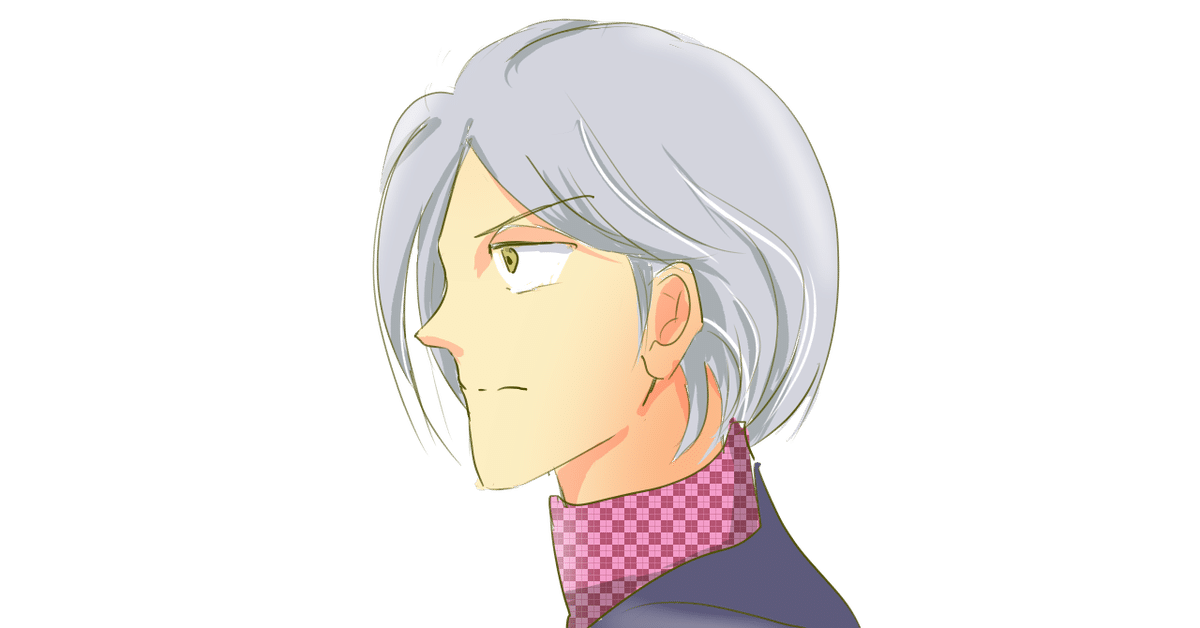
「脳がつぶれるまで考えろ、知力は体力だ」
老師の言葉が聞こえた気がした。あの頃、『風の設計士団』にいた頃。何日もぶっ通しで議論を続けていた。
似たようなことを今、ここ、スチュワートの工場でやっている。
相手は助手のオットーとレイター。
整備士の免許を持つレイターが、船の構造に詳しいことは知っていた。だが、ここまで精通しているとは。
「レイター、お前、ほんとに設計士の免許持ってないのか?」
「俺は銀河一の操縦士だぜ、そんなもん取るほど暇じゃねぇんだよ」

ボディーガード協会のランク3Aというレイターの体力は並じゃなかった。いい意味で、脳が筋肉でできてるんじゃないか、と思うぐらいへばらない。
いろいろなアイデアを次から次へと思いつく。発想が取り柄なこの僕がびっくりするほどに。
ハールとメガマンモスをつなぐため、僕とレイターが出すアイデアを、オットーがぶつぶつ言いながら一つ一つ計算する。

この三日ほとんど寝ていない。
驚いたことにレイターは基礎論文から技術論文まで、きっちり最新版にアップデートしていた。
設計士でもない人間に僕が負けるわけにはいかない。
僕はこれでも風の設計士団で、リーダーを務めていたのだ。
*
あの頃、風の設計士団では僕がリーダー、ルーギアがサブリーダーを務めていた。
思い出したくない名前。ルーギアが僕に言った。
「アラン・ガラン、リーダーである君が、そんな実現性の低いアイデアばかり出していてどうするんだ。我々は、技術を売ることで利益を出しているんだぞ」

僕は反論できなかった。実用化できるという予感はある。だが、いつまでたっても結論にたどり着けない。
ルーギアは不満を持っていた。
僕の下のサブリーダーであることに。
彼は僕よりずば抜けて計算力が高かった。そして、政治的な力にも長けていた。風の設計士団のメンバーが僕を無視し始めた。
「君が実現可能なアイデアを出せば、みんなもついてくるんじゃないか」
ルーギアは蔑むような眼で僕を見た。気がつくと誰も僕のアイデアを議論しなくなっていた。
僕は人づきあいが苦手だ。リーダーの器でないことは自分が一番よく知っている。
僕をリーダーに選んだのは老師だ。
老師の言葉は、今も僕の心の中に残っている。
「アラン・ガラン、お前はすごいぞ。革新的なその発想こそが風の設計士団に必要だ」と。

その言葉を信じてがんばってきた。
だが、この三か月、僕が出した八つのアイデアは一つも技術として実現しなかった。
ルーギアが静かに僕を責めた。
「君は、この結果をどう考えているんだい?」
老師はどこかへ出かけたきり半年以上会っていない。連絡先もわからない。
もう、限界だ。僕は風の設計士団を辞めることにした。
リーダーは老師が決める。
だが、リーダーが設計士団を抜ければ、サブリーダーがリーダーになる。僕が抜けた後、ルーギアがリーダーになった。
設計士としてどこかのメーカーに就職しようと、履歴書を書いていた時だった。知人からスチュワートさんを紹介された。話してみたら面白い人だった。
彼は自分でS1チームを作るのだと言う。一緒に働きたいと思った。
だが、僕にはS1の経験はない。S1は専門性が高い。迷惑をかけるわけにはいかない。
お断りの連絡を入れようと思った時、採用の通知がきた。
「どうして僕を雇ってくれたんですか? S1機を設計した経験はないとお伝えしましたよね」
「う~ん、面白そうだったから」
そう言ってスチュワートさんは笑った。

僕は一からS1について勉強した。S1機の特性、細かいレギュレーション、面白い。
いつしかS1は僕を虜にした。
*
そんな、ある日のことだった。
特許データーベースを検索していた僕は驚いた。

僕のアイデアが次々と登録されていた。
風の設計士団を辞める前に出した八つのアイデア。そのうちの七つがルーギアの名前で登録されていた。
僕は声を立てて笑った。
僕のアイデアは、技術として実現可能なものだったんだ。
ルーギアはわかっていたのだろう。おそらく僕が辞める前に計算ができていたに違いない。
狂ったように笑い続ける僕にスチュワートさんが声をかけた。
「おい、何がそんなにおかしいんだ?」と。
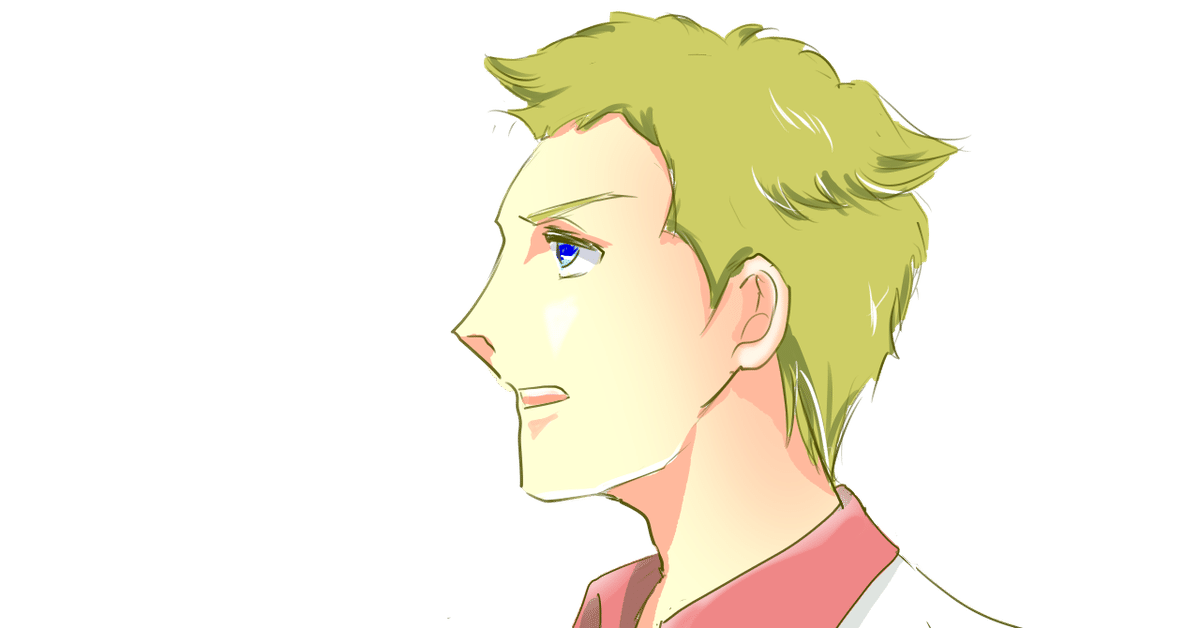
「これ、見てください。みんな僕のアイデアなんです。僕の子どもたちが立派に育っていた・・・」
笑いながら僕は泣いた。
悔しかった。
僕にうまくやるという力があれば、風の設計士団を辞めずに済んだかもしれない。でも、もう時間は巻き戻らない。
そんな出来事があったすぐ後だった。スチュワートさんがオットーを連れてきたのは。
「アラン・ガラン、こいつは、若いが大学院の数学科出だ。お前の助手として雇ったから面倒みてやってくれ」
「オットーと言います。僕、S1ファンなんです。よろしくお願いします」

緑の髪に赤い瞳のアンタレス人。童顔、というか十六歳だという。
「ことし成人したので、仕事を探していました」
聞けばスチュワートさんはS1のコミュニティサイトに「計算が得意な人募集」という求人広告を出したのだという。
「いやあ、面白い就職試験でした」
「オットーだけだったよ、満点だったのは」
そう言ってスチュワートさんはオットーの回答を僕に見せた。
「こ、これは」
設問は僕の特許のアイデアだった。実現可能にするための式と解を求めよ、という問いが七つ。
オットーの解答欄には、ルーギアが導き特許を申請した解と同じものが記されていた。
僕たちはいいパートナーとなった。僕のアイデアをオットーが計算し実現する。
予選落ちが続いていた僕たちの船が少しずつ順位を上げだした。
僕とオットーはよく喧嘩をした。オットーはオーナーにでもはっきりと物を言う性格だった。
「スチュワートさん、チーフのアイデアは無理ですよ。計算できません」
僕の左足が震える。
「無理じゃない。まだ方法は出尽くしていない」
そんな議論の中から生まれたS1の規定ギリギリのアイデアは、しばしば業界を揺さぶった。
いつしか、チーム・スチュワートは決勝進出の常連となり、六位入賞、というところまでやってきた。次は表彰台だ。
*
レイターがずば抜けて操縦がうまいことは六年前から知っていた。初めて銀河一の操縦士の飛ばしを見た時には身体が震えた。うちの船が生まれ変わっていた。
第一パイロットのコルバと一緒に戦闘機を飛ばしていたと言うが、格が違う。天才だ。

出会った当時、クロノス社に勤め整備士の免許を持っているレイターが、スチュワートさんの船を個人的に整備しているというのも聞いていた。
だが、今回議論をする中でハイスクール中退だというレイターが船の設計論に詳しすぎることに違和感を感じた。
風の設計士団の昔の仲間とは、情報交換を兼ねて今も時々連絡を取っていた。
後味の悪いやめ方だったが、中には僕に謝ってくれたメンバーも何人かいたのだ。
「すまん、ルーギアに逆らえる雰囲気じゃなかったんだ」と。
僕は雑談の中で聞いてみた。
「レイター・フェニックスって知っているかい。食事を作るバイトをしていたそうだけど」
「知ってるも何も、老師はレイターに直弟子を名乗っていいって言ったんだぜ」

「な、何だって?」
僕は衝撃を受けた。
直弟子は老師の後を継げるとされていた。だが、僕の知る限り誰一人として指名されなかった。リーダーである僕もルーギアも。
「ただし、レイターが設計士の免許を取ったら、という条件付きだった」
レイターは今も設計士の免許はもっていない。僕はわかった。わざと取らないんだ、彼は。
設計士ではなく、銀河一の操縦士であるために。
「知力は体力」と老師はいつも言っていた。
レイターはひらめきだけでなく、考え抜く持久力も持ち合わせている。老師の直弟子候補か。強いはずだ。
だが、僕だって負けない。一級設計士のプライドにかけても。
老師の言葉が自分を奮い立たせる。
「アラン・ガラン。お前はすごいぞ。革新的なその発想こそ風の設計士団に必要だ」
僕のアイデアでハールとメガマンモスをつないでみせる。老師、見ていてください。
*
いつものように三人で議論していた時のことだった。
「責任分界点を考えようぜ」

とレイターが言い出した。
「船が融合燃焼するリスクのうち、衝突は俺の操縦のせい。宇宙塵と太陽風とダークマターは運だな」
オットーがあきれた声で言った。
「衝突がレイターさんのせいとも限らないです。それより、運による燃焼リスクが多すぎます」

「しょうがねぇだろ。宇宙塵は当たる時にゃ当たるんだ。俺でもよけられねぇよ。あとはパラドマ発火をどこまで抑えられるかだ」
僕は発言した。
「このつなぎでメガマンモスのエンジン馬力は九十二パーセントまでいける」
「九十二だと勝てねぇ。あと一ポイントの上積みが必要だな」
「横G六十五度のリスクは解消できないぞ」
「そんなピンポイントな攻めは、誰もしてこないんじゃないですか?」
「ま、後ろへ下がって逃げりゃいいか」
「安全性が確保できていない」
「そうでもねぇだろ」
安全性は最大の懸案だ。それすら、なかなかクリアできない。しかも、横G六十五度で飛ぶとメガマンモスがエンジン停止する。
課題はそれだけではなかった。
直線番長のメガマンモスはカーブの操縦がしにくい。小惑星帯では暴れ馬に変身する。
ナセノミラは小惑星帯含めカーブが多い。レイターはそれをわかっていてメガマンモスを選択した。
「大丈夫さ。俺、メガマンモス乗せてアステロイドで飛ばしてたから、暴れ馬を乗りこなすの得意なんだ」
その時、急に思い出した。
アステロイドを信じられない速度で飛ばす恐ろしい船、突風教習船のことを。あの船もメガマンモスを積んでいた。
「レイター、君はもしかして裏将軍だったんじゃないのか?」
「懐かしいことご存じだねぇ」
レイターが肩をすくめた。やっぱりそうだ。
六年以上前のことだ。
S1のヒントを探して、僕は飛ばし屋のバトルをアステロイドへ見に出かけた。
ギャラクシーフェニックスという新興の飛ばし屋グループ、その大将である裏将軍の飛ばしは見ておいて損はないと聞いていた。
驚いた。

S1レーサーでもああは飛ばせない。操縦の限界を超えたあれは自殺行為だ。衝突事故を起こさないのは、ただ運がいいだけだ。本人もわかっている。「また、死にぞこなった」という決め台詞はおそらく本心だ。
若者が熱狂するのがわかる。S1を見慣れた僕ですら、目に焼き付いて、しばらく夢に見たほどだ。
「僕は一度だけ裏将軍の飛ばしを見た。怖かった。死を覚悟した、ってもんじゃない。あれは死に場所を探しながら飛んでいた。レイター、まさか君は今度のS1で死ぬ気じゃないだろうな?」
「俺は不死身だから死なねぇんじゃねぇの?」
レイターはニヤリと笑った。はぐらかすような答え。
レイターから死の香りが漂った。ボリデン合金は融合燃焼を起こしたら一気に燃える。死に直結だ。
助手のオットーの言うとおりだ。燃焼リスクが高すぎる。レイターを死なせるわけにはいかない。左足が震え始めた。
「オットー、もう一度計算をやり直すからな」
僕は自分に気合を入れた。
* *
死に場所か。
アラン・ガランの言うことは当たってるな、とレイターは思った。
裏将軍のあの頃、とにかく俺は船で死にたかったからな。シートベルトもしなかった。小惑星に激突して死ねばフローラに会える。って、期待しながら飛ばしてた。
バトルを生きて終えると俺は心底悲しかった。
「また、死にぞこなった」って。

俺は仲間のヘレンを助けるため、悪徳マフィアの事務所に宇宙船で突っ込んだ。本気で死ぬつもりだった。
あの時、フローラが俺を呼んだ。
爆発に巻き込まれて死の淵をさまよったのに、死ねなかった。
あれからだな。どうせ、いつか死ぬんだ。慌てる必要もねぇって思ったのは。フローラはずっと俺を待っててくれる。
けど、この間、ハールにメガマンモスのエンジンを積むってことを思いついた時、俺の心が久しぶりにゾクゾクした。

アラン・ガランの言うとおりだ。
死んでもいいや、って、確かに思ったな俺。
いや、もうちょっと踏み込んだ。死ねたらいいや、死ねたらいいな、って。
このS1は、ティリーさんと決別するための儀式だからな。

ガキの頃から憧れてたS1で、火の玉になっておさらばする。理想的だ。
このハールなら、加速すればいつでも死にたい時に死ねる。
全知全能の『あの感覚』で無敗の貴公子を破る。
燃えながらトップでゴールを切るイメージが、俺の中で固まっていく。ティリーさんのために祝福の花火を打ち上げてやるさ。
フローラ、俺、あんたとの約束果たして『銀河一の操縦士』になったんだ。
S1で優勝したら、もうそっちへ行っていいよな。

フローラに会える。俺は楽しくなってきた。
* *
ティリーはエースが操縦する小型機の助手席に座っていた。
時々、エースはわたしを誘ってテストコースで船を飛ばす。
エースは公道で法令違反をするわけにいかない。飛ばし屋のようにアステロイドで飛ばすことはしないのだ。
ジェットコースターが好きなわたしのために、エースは小惑星帯コースを選択してくれる。
上手い。安定感も抜群だ。でも、どこか物足りなさを感じた。レイターの飛ばしとは違う。一体何が違うのだろう。

操縦席のエースがわたしに話しかけた。
「レイターの飛ばしと僕の飛ばしは違うかい?」
「違います」
即答した。
「どう違う?」
困った。全然違うのだけど口でうまく説明できない。
「エースの方が丁寧です」
「ありがとう」
ふっと、フェニックス号の散らかったレイターの部屋が頭に浮かんだ。
「無敗の貴公子の操縦について、レイターと話したことがあります」

大迫力の最新4DシステムでS1レースを見るのが楽しみだった。レイターは万年六位のチームスチュワートを応援していて、わたしは推しのエース一筋で、毎度口げんかしながらレースの感想を語り合った。
「ほう、何と?」
エースが興味を持って聞く。
「レイターは言ってました。エースは強いけど速くない。S1は遅くても勝てばいいからって、ひどいですよね」
銀河最速のS1でコースレコードをたたき出しているエースのことを「遅い」と言われて腹を立て「レーシング免許もないくせに」と言い返したことを思い出す。
ところがエースは納得したようにうなずいた。
「彼らしいな、的確な分析だ」
「的確ですか?」
「ああ。彼の言う通りだよ。S1はスピード記録を出すことより、ゆっくりでも相手に勝つことが求められるからね。速くなくてもいい」
そういう意味だったのか。
「ティリーから見て、レイターの飛ばしが僕より優れているのはどんなところだい?」
これは仕事だ。
エースはレイターを攻略するヒントを知りたいと思っている。わたしは何度もレイターの船に乗ってバトルをした。
レイターの飛ばしを思い浮かべる。興奮して胸がドキドキしてきた。
「本当にすごい時は、時が止まるんです」
「時が止まる?」
あの日、わたしはレイターの助手席に座っていた。アステロイドで白魔と戦った時。

「あの感覚…」
口にしたら身体が震えた。『あの感覚』がよみがえる。あふれる多幸感。脳内から光がほとばしり恍惚状態となった、あの時…。何が起きていたのだろう。
「レイターは『あの感覚』と呼んでいました」
「もう少し具体的に表現できるかい?」
困った。言語化できないから『あの感覚』なのだ。
わたしは絞り出すように言葉にした。
「すべてを制御する幸せな感覚というか。……全知、全能」
「それを相手にするのは手強そうだな」
エースは船を停めるとわたしを見た。
「ティリーは、僕とレイターのどっちに勝って欲しい?」
仕事としての迷いはない。
「エースに勝ってもらうため、わたし毎日、がんばってます」
「仕事じゃなく、友人として聞いているんだ」
エースの目が真剣だった。
エースに勝ってほしい気持ちは嘘ではない。友人であるエースを喜ばせるために「エースです」と答えることもできた。
でも、わたしは目をそらし、迷いながら答えた。
「……わからないです」
友人だからこそ真摯に向き合わなくてはいけない。
心の奥に、レイターの全知全能の飛ばしを見たがっている自分がいた。
エースが操縦桿から手を離した。
「エ、エース、手放し操縦はダメです」
「停船中だから大丈夫だ」
エースの顔がわたしの目の前にあった。

なんて綺麗に整った顔立ちなのだろう。クールな切れ長の目、長いまつげの一本一本までくっきり見える。
わたしの憧れの貴公子。
エースのブロマイドも生写真も山のように持っているけれど、こんなに優しい表情は見たことがない。
うっとりしているわたしに、エースの顔が近づいてきた。

わたしの頬にエースの手がゆっくりと触れた。手のひらの温もりが伝わる。
学生のころ、サイン会で握手をしてもらった。操縦桿を握るエースの手がわたしに触れている、と興奮したあの時と同じ感触。
さわやかなライムの香り。
エースの整髪料の香りが胸を高鳴らせる。わたしは慌ててまばたきをした。エースの息がわたしに触れ、視界いっぱいに無敗の貴公子の美しい顔が広がった。
* *
きょうもレイターはハールの中にいるのか。
スチュワートは深夜にチームの整備工場へ顔を出した。

本番まであと一週間。
ようやくメガマンモスのエンジンをハールに積んだ。
レイターは一人であっちいじっては試乗、こっちいじっては試乗を繰り返している。
家、というかフェニックス号にも帰らずハールの座席で寝ていることもしょっちゅうだ。食事も適当。
俺は心配になる。
「おい、レイター。お前は操縦士だろ、体調管理も仕事のうちだ。夕飯食ってないんだろ」
「食わねぇ方が、感覚が研ぎ澄まされるんだよな」
まるで飢えた狼だな。
「S1は体力勝負だぞ。短距離の飛ばし屋のバトルとは違う」
「わかってる。でも、今は、一分でも一秒でも船を俺ん中に取り込みてぇんだ」
「折角、プリン買ってきたんだが・・・」
「食う」
レイターは船から素直に出てきた。
プリンを食べながらレイターは俺に不思議な話をした。
「俺、船を自在に操りてぇんだ」

「今だって操ってるじゃないか」
「違うんだ。すべてを支配してぇんだよ。俺は『あの感覚』って呼んでるんだけどさ、その域に入りてぇんだ」
「入ったことあるのか?」
「ああ、先月も入った」
随分簡単な話だな。
「その域に入るとどうなるんだ?」
「時が止まる」
「時が止まる?」
「全知全能ってやつさ。誰にも止められねぇ。銀河一の操縦士ならそれが扱えなくちゃいけねぇんだ」
「そいつはすごいな。期待してるよ」
レイターから返事がない。
いつもなら自信満々で「まかせとけ」というのに。あいつは苦しそうな顔をして頭を抱えた。顔色が悪い。
「おい、どうした?」
「…どうしたら再現できるかわかんねぇんだ。ハールとメガマンモスならいけるんじゃねぇかって思ったのに。…また、入れそうで入れねぇ。俺が銀河一の操縦士であるためには『あの感覚』を俺一人でつかまなきゃ、意味がねぇっつうのに……」

絞り出すような声。どうしたんだ?
焦り? いやまるで怯えているようだ。レイターのこんな表情を初めて見る。
この状態でこいつをS1に乗せて大丈夫なのか。俺は不安に襲われた。
<出会い編>第三十九話(19)「決別の儀式 レースの途中に」 へ続きますが、その前に
<裏将軍編>第一話「涙と風の交差点」へ
・第一話からの連載をまとめたマガジン
・イラスト集のマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

