
銀河フェニックス物語 【恋愛編】 第四話 お出かけは教習船で(まとめ読み)
大手宇宙船メーカークロノス社に勤めるティリーはフリーランスの操縦士レイターとつきあうことになり、恋に仕事に忙しい毎日を送っていた。
銀河フェニックス物語 総目次
<少年編>第十話「二段ベッドの上で見る夢」
<恋愛編>第三話「大切なことの順番」
<恋愛編>のマガジン
「何とかしとくれ!」
「空いてんだからいいだろが」
月の御屋敷で将軍家侍従頭のバブさんとレイターが喧嘩を始めた。

わたしはあわてて仲介に入った。
「一体、どうしたの?」
「ティリーさんからも言ってやってくださいよ。もう駐機場がいっぱいなんです」
「いいじゃねぇか。どうせ使ってねぇ土地なんだから」
月の御屋敷は銀河連邦軍のトライムス将軍家の居宅で、レイターの住所登録地だ。

次期将軍のアーサーさんはきょうは仕事で不在だという。
「あいつがいるとうるせぇから、いねぇほうがいいんだ」
二人の関係が深いことは知っているけれど、仲がいいのか悪いのか、今もってわからない。
御屋敷裏の駐機場にはレイターの船が何機も置いてあった。
さっき、フェニックス号を停める時に上空から駐機場を見た。小型船がパズルのようにきっちりと並んでいた。
「停めるところないわよ。どうするの?」

「あん? そこ空いてるじゃん」
と、レイターが指さしたところは確かに空いていたけれど、中型船が入る場所じゃない。その狭いスペースに、最後のピースをはめ込むように器用に停めた。さすが『銀河一の操縦士』だ。
「もう乗らない船は捨てたらどうだい」
バブさんが嘆いている。
「船を捨てろだと、『銀河一の操縦士』がそんなことできるかよ!」
レイターは船を愛している。彼女であるわたしより愛しているのではないかと勘繰るほどに。
今回、月の御屋敷にお邪魔したのも、デートと言う名の機体の定期点検だ。
*
駐機場を二人で見て回る。
「いろんな船を持ってるのね」
「俺は銀河一の操縦士だぜ」
懐かしいクロノス製の小型ファミリー船をみかけた。
今、フェニックス号には、小型機のガレガレさんの船を積んでいるけれど以前はこの船を載せていたのだ。
ファミリー船といっても、違法スレスレな改造が加えてあって、よくバトルへ出掛けた。最近見かけないと思っていたけれど、将軍家に置いてあったんだ。ここなら駐機代を取られない。
宇宙船メーカーに勤めているわたしが知らないマイナーな船が並んでいる。宇宙船お宅のレイターは銀河の隅々まで船を求めて旅したという。
新型宇宙船が一堂に会するスペースシップショーを二人で歩いたことを思い出す。この人はガレガレさんのような個人メーカーのブースも全部回っているのだ。
つきあう前だったけれど、デートのようで楽しかった。
共通の趣味の力は、理解できない人を好きにさせるほど大きい。

「この船たちの税金ってどうなってるの?」
相当な金額になるはずだ。心配になって聞いた。レイターは将軍家に税金を払わせていたことがある。
「あん? 船舶税はちゃんと払ってるぜ。だからいつも金がねぇんだよ」「そうなんだ」
銀河一の操縦士をちょっと見直す。
いや、納税は市民の義務。この人は当たり前のことをしているだけだ。
わたしが勤めるクロノス社の高級船『スピーダ』がピカピカに磨いてあった。将軍家のようなエグゼクティブな人たちをターゲットとしたハイグレードな船種。五、六年前のモデルだ。
「これ、将軍の船?」
「俺のさ、十八の頃、こいつでクロノスに通勤してたんだ」
レイターは将軍のコネでうちの会社に入社し、一年だけ営業で働いていた。
「十八って新入社員でしょ。随分、贅沢ね。前から思っていたけれど、将軍ってレイターに甘いわよね」
「んにゃ、ジャックが買ったんじゃねぇよ。これ、俺が自分で手に入れたんだ」
クロノスに勤める前、レイターは凄腕の飛ばし屋『裏将軍』だった。
「自分で、ってどうやってお金を用意したの? そもそもスピーダって飛ばし屋が乗る船じゃないし」
将軍が保証人になったのだろうか。
「チッチッチ、こいつ盗品なんだ」
「はっ?」
「大丈夫だよ。盗品を盗んだのさ。ちゃんと警察の許可はおりてる」
全く意味不明だけれど、将軍家がよしとして駐機しているのだから問題はないのだろう。そう思うことにした。
ちょっと変わった見覚えのある船が置いてあった。
操縦棹が操縦席と助手席の両方についている教習船。
「これ、突風教習船?」
「ご名答」
レイターが『裏将軍』を務めていた頃に乗っていた愛機だ。小惑星帯を死をも恐れぬ高速で飛ばしている投稿動画を何度も見た。
「不思議に思っていたのよ。どうして教習船なの?」
「俺、ハイスクール中退して『風の設計士団』で飯炊きのバイトやってただろ、そん時に老師のじいさんがこの船を見つけてきてくれたんだ」
老師というのは伝説の設計士だ。
「それは、老師に操縦を教えてもらったということ?」

と言いながら、自分でおかしいと思った。
レイターは十四歳ですでに戦闘機乗りだったのだ。教習船で手取り足取り教わる必要がない。
わたしの問いにレイターが口をにごした。
「あんましティリーさんに聞かせたくねぇけど、この船だったら、誰が操縦してるかわかんねぇだろ」

そうか、当時のレイターは任務用の仮免許しか持っていなかった。
「無免許を隠すためってことね」
わたしたちアンタレス人は順法意識が高い。無免許操縦という発想自体がない。
レイターとわたしは生きてきた世界と違いすぎて、価値観が全く異なっている。私は深く息を吐いた。
同じである必要はない。許容できるかどうかだ。
彼のやっていることは違法で正しくない。けれど、誰にも迷惑をかけていない。
「ま、そのまま、じいさんがいなくなったんで、もらったんだ」
突風教習船の実物を見るのは初めてだ。ボディがよく磨かれている。
レイターがドアを開けた。
「もう、俺は操縦席には座れねぇんだよな」
操縦席の座席が随分小さい。
「これ、子供用シート?」
「んにゃ、リゲル星人の船から付け替えたんだ」
リゲル星人は小柄だ。わたしに、ちょうど良さげなサイズ。
「座ってみていい?」
「ああ」
使い込まれたシート。十七歳のレイターがここに座っていたと思うと不思議な感じがする。
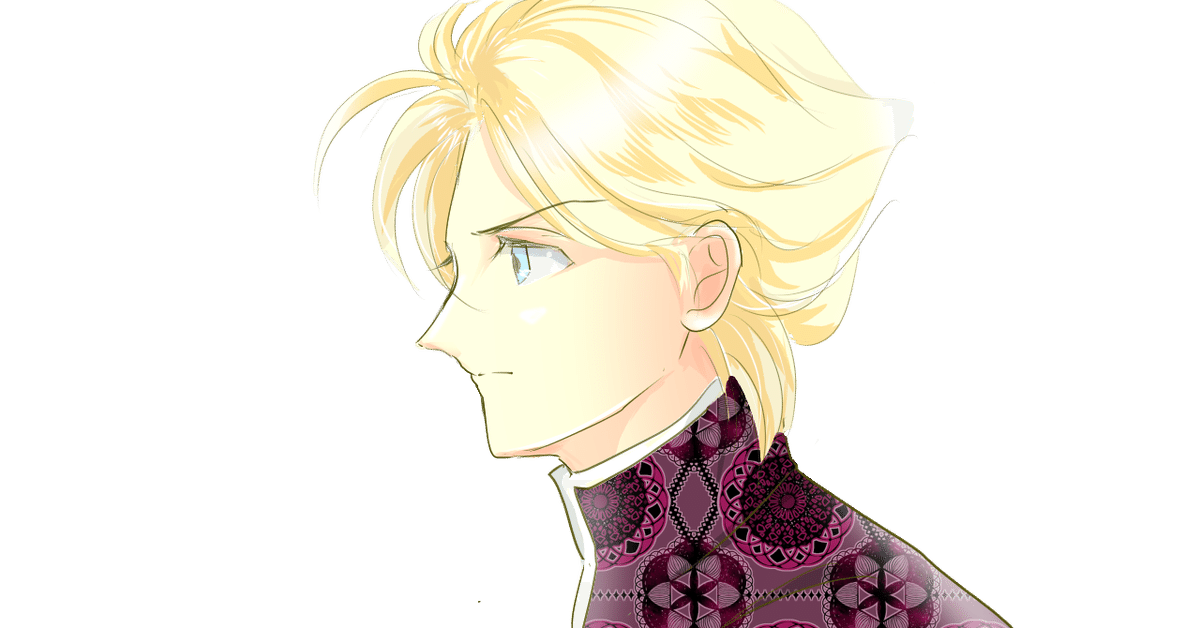
この船で『裏将軍』として飛び回っていたのだ。わたしが知らないレイターの世界。操縦桿に触れると胸がトクンと音を立てた。
レイターは隣の助手席、というか教官席に座った。教官席のシートは普通の大人用サイズだ。教官席にも操縦パネルが設置されている。
宇宙船教習所で教官には随分叱られた。宇宙船メーカーに就職が決まったというのに免許を取るのに苦労した。
実技試験に受からず両親に頭を下げて追加の料金を払ってもらったことを思い出す。あの頃、故郷のアンタレスを出て行きたい、というわたしに、父はいい顔をしなかった。

ちょっぴり苦味に包まれる。
「これ、今でも動くの?」
「もちろん」
「操縦してみていい?」
このやや狭い座席は操縦が下手なわたしでも扱いやすそうだ。
免許取り立ての頃よりは、飛ばせるようになっている。ガレガレさんの船なら、仕事でお客様を乗せることだってできるのだ。
「うーん。いいけど、俺用のセッティングなんだよな」
レイターは渋い顔をした。裏将軍用にシビアに合わせてあるということだ。
「それは無理ね」
「ちょっと、待ってな」
そう言うとレイターはいきなり教官席のコントロールパネルをはずしにかかった。
「何してるの?」

パネルの裏側の配線を付け替えているようだ。
「ふむ。これでいっちょ、やってみるか。ティリーさん、シートベルトつけてエンジンかけてみな。
「こ、こうかしら」
キーをセットしてスタートボタンを押す。
ブゥワンンン
「わっ」
いきなり大きなエンジン音が響いたので驚いた。
「垂直離陸はできるかい?」
「教習所でやったことがあるわ。確か、こうして……」
操縦棹を引っ張った。
「きゃあ」
いきなり船が急上昇した。
加速がすごくて制御できない。月の御屋敷の上空で機体が不安定に揺れている。
これじゃ、防衛システムに撃ち落されてしまう。
必死に機体を立て直す。
横からレイターの手が伸びて軽く操縦桿を支えた。何とか水平を保つ。
「うまい、うまい」
手を離したレイターは面白そうに笑っているけれど笑い事じゃない。
「このまま、周回航路まで行ってみようぜ」
「む、無理よ。やっぱりこの船、わたしにはセッティングがシビアすぎるわ」
「いいからいいから、俺がついてる」
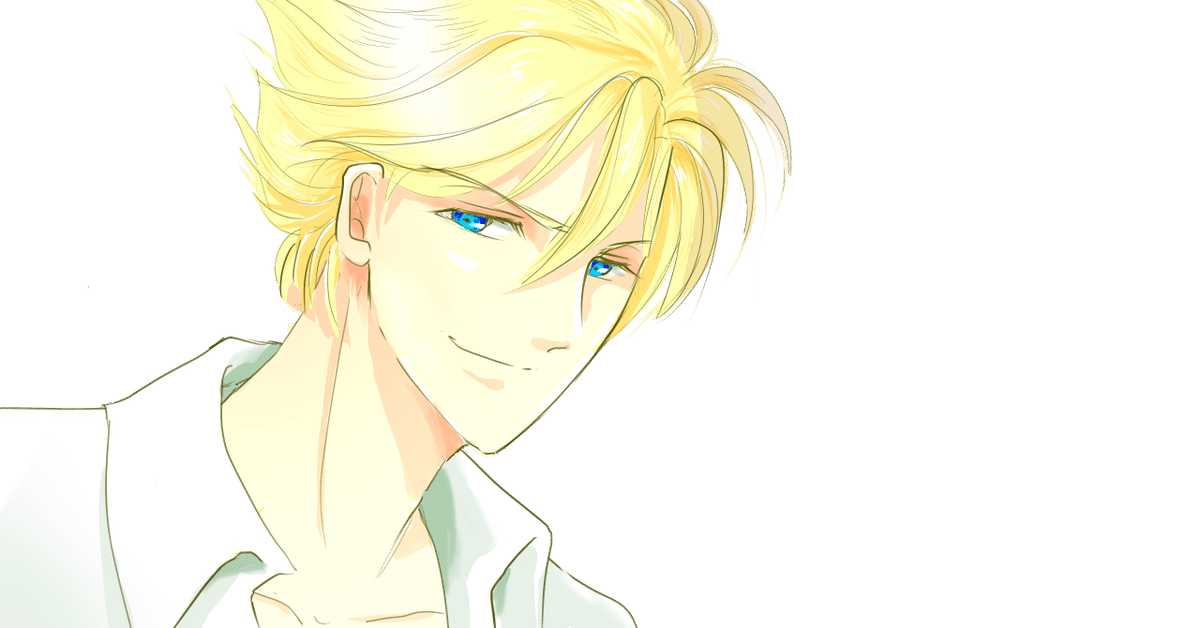
また、トクンと胸が鳴った。俺がついてる、という言葉にわたしは弱い。
「どうなっても知らないわよ」
軽くアクセルを踏んだ。
次の瞬間、いきなり身体が後ろへ引っ張られた。加速Gだ。
「な、何? このスピード」
上昇した時にも感じたけれど、すごい加速だ。見る間に引力圏も抜けてしまった。
「こいつ、メガマンモス積んでるから」
忘れてた。裏将軍の愛機『突風教習船』のエンジンのことを。メガマンモスは馬力が命という直線番長だ。とにかくパワーがあって、初心者同然のわたしに扱える代物じゃない。
レイターが無敗の貴公子と戦ったS1最終戦で機体に搭載していたのもメガマンモスだった。

そのエンジンで銀河最高速度を更新したのだ。めまいを起こしそうになる。
「この船、わたしには絶対無理」
と宣言したところで、あれ? スムーズに動き始めた。
「あんた、もうちょっと肩の力を抜いてみな」
レイターの言う通りに力を抜く。
思ったより加速が制御できる。右、左、と考えている方向に船がきちんと飛んだ。
周回航路に入った。
鳥が風に乗って飛ぶような滑らかな飛行。自分の手足のようにイメージ通りに船が動いていく。ガレガレさんの船より操縦がしやすい。
わたし、メガマンモスを扱えてる?
レイターのアドバイスのお陰だろうか?
それとも、シビアなセッティングの『突風教習船』だからだろうか?
いつもは苦手な操縦が面白い。心が弾む。どこまでも飛んでいきたい気分だ。
力みが抜けて、急に操縦がうまくなったみたい。わたしには実は隠れた才能があるんじゃないだろうか。
と、突然、前を飛ぶ船が右折した。
ぶ、ぶつかる。
ブレーキを踏み込む。間に合わない。頭が真っ白になる。
操縦桿をぎゅっと握りしめた。
と、教習船は勝手に下降し、右折した船の下をスルリと潜り抜けた。
わたしは何もしていない。自動で衝突回避装置が作動したのだろう。それにしても随分となめらかな動きだった。
「ティリーさん、飛ばすだけじゃなくちゃんと他の船の動きも見てろよ。あいつ、ウインカー出すのが遅かったけど右折するってわかってたじゃん」
ちらりと横を見るとレイターが教官席の前にある操縦桿を指で操作している。
「もしかして、教官席が生きてるの?」
「ああ、さっきつないだんだ」
「衝突回避装置が働いたんじゃないの?」
「飛ばし屋がそんなもん積んでたら、攻められねぇじゃんか」
わたしの操縦をレイターが補正しながら飛ばしていたのだ。どうりでうまく飛ぶはずだ。
わたしに操縦の才能がある、なんてことはなかった。

「それならそうと、先に教えてくれればいいのに」
「飛ばしてる間、楽しかっただろ」
レイターがニヤリと笑った。
「……」
彼の言う通り、わたしは自由に操縦している感覚を堪能していた。
思い出した、わたしの彼氏はこういう面倒な性格だ。
「このまま、アステロイドまで行っちまうか」
「え?」
わたしの答えも聞かずに、レイターは船を加速させた。
レイターがわたしのイメージする飛ばしを具現化してくれる。不思議な感覚だ。船が自分の思う通りに動く、って何て気持ちいいのだろう。
普段は助手席ばかりのわたしだけれど、船に乗るのは大好きだ。実はスピード狂の気がある。アクセルを踏んで飛ばしてみる。
助手席を見る余裕はないけれど、レイターが楽しんでいるのが伝わってくる。
「レイターはいいな」
「あん?」
「船、操縦するの楽しいでしょ?」
「あ、ああ?」
銀河一の操縦士にとって当たり前のことを聞かれて、返事に困っている。
「思い通りに操縦できるって、うらやましいな」
わたしが船のバランスを崩すと、あわててレイターが立て直す。
「ったく、あんた、そんなことやってっからエンスト起こすんだよ。ここはアクセルふかしちゃダメなんだ」
はあ、目からうろこだ。
教習船を通じてレイターとつながっているように感じる。
「楽しいわね」
「どこがだよ。こっちは必死だ」
言葉とは裏腹にレイターの声は明るい。思わず口がほころぶ。幸せだな、って思った。
レイターに操縦を教えてもらっているうちに、見慣れたアステロイドベルトに着いた。
「とりあえず、初級コースから行ってみるか」
小惑星帯をレイターの助手席で飛ぶのが好きだ。ジェットコースターのようなスリルと迫力はやみつきになる。
自分で飛ばすのは初めて。と言ってもレイターが操縦しているようなものだから安心だ。
スタート地点から発進させる。
うわっ。見る間に小惑星が迫ってきた。あわてて操縦棹を切る。
「バカ、逆だ!」
「え?」
ぎりぎりのところを通り抜ける。
「きゃあ、またきた」
抜けたと思ったら、次の小惑星が目の前にあった。
「右だ右!」
レイターの言うとおり操縦棹を右へ回転させた。
隣の小惑星にぶつかりそうになる。レイターがあわてて教官席を操作する。
「行き過ぎ! メガマンモスの加速はガレガレの船とは違うんだぜ」
わかっていても反応できない。小惑星帯の操縦ってこんなに難しいの?
「とにかく、あんたの操縦棹がメインなんだからな」

珍しくレイターの声に余裕がない。
「そ、そうなのね」
「こっちは仮で繋いであるだけだ。ティリーさん、頼むぜ」
「頼むぜと言われても」
「ほら、そこは上に逃げんだよ」
上下左右に操縦棹を操作する。
わたしの操縦では全然避け切れていない。激突しないように隣でレイターが必死に補正しているのがわかる。
何とかポイントを抜け出た。
「ふうぅ」
レイターとわたしは同時にため息をついた。緊張したけれど、やっぱり絶叫マシンと似ている。興奮が心地いい。脳内にドーパミンがあふれている。
「ドキドキしたけど、楽しかったわね」

「マジかよ。俺は初級でこんなに手に汗かいたの生まれて初めてだ! ジェットコースターより怖いじゃねえか」
「え?」
ちらりと横を見る。
「何でもねぇ」
前から思っていたけれど、この人ジェットコースターが怖いんだ。『銀河一の操縦士』で銀河最高速度の記録保持者のくせに。
その時、通信音が鳴り、モニターに紫の前髪が印象的な男性が写った。
「レイターじゃないか」
「およ、総長さまじゃねぇの」
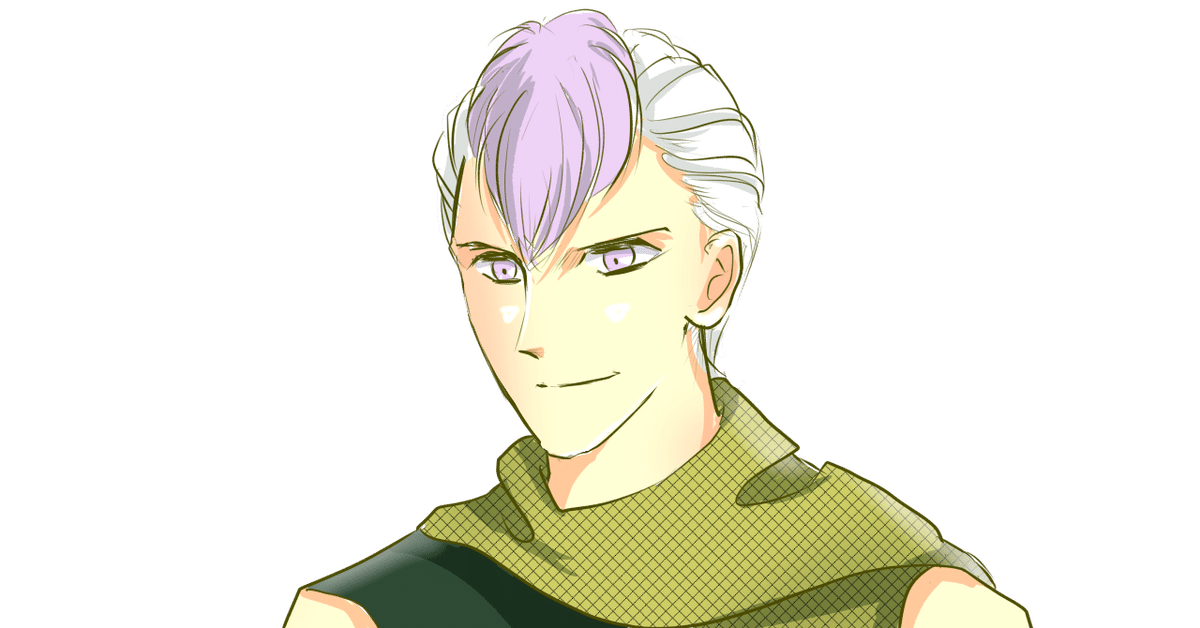
飛ばし屋『ギャラクシー連合会』の総長アレグロさんだ。前に、レイターがバトルをした時にあいさつをしたことがある。荒くれ者の飛ばし屋を束ねているというのに物腰が柔らかい人だ。
アレグロさんの小型機が近づいてきた。
「びっくりしたぞ、裏将軍の『突風教習船』を見つけた時は」
「俺も総長がこんなとこを、うろついてるとはびっくりだぜ」
「たまには一人で飛びたい時もあるさ」
「一人? 武闘派連れてねぇのかよ」
「ああ」
「どうりで地味な船だ」
アレグロさんはレイターの飛ばし屋時代の仲間だ。
かつて裏将軍率いる『ギャラクシー・フェニックス』が銀河中の飛ばし屋を統一したことは今では伝説だ。当時、アレグロさんは裏将軍側近の軍師だったそうだ。

「レイター、久しぶりに上級で飛ばさないか?」
アレグロさんは現役の飛ばし屋だ。
「ふ~む。今、操縦してんの俺じゃねぇんだよな」
「そうか、突風教習船の操縦席はもうお前は座れないからな。誰が乗ってるんだ」
「俺の彼女」
「彼女だと?」
アレグロさんが驚いた顔をした。レイターはわたしと付き合っていることを伝えていなかったようだ。
レイターがカメラをわたしに向けた。
「こんにちわ、アレグロさん」
笑顔で会釈する。
「ああ、ティリーさんでしたか。よかった。今日はいい日だ。僥倖の極みです。レイターを何卒よろしくお願い致します」
丁寧で大仰なあいさつにあわてる。
「こ、こちらこそ」
「レイター、お前に特定の彼女ができたというのは安心したぞ」
「人生いろいろあるのさ」
レイターは特定の彼女を作らない主義だった。
十七歳で前の彼女のフローラを亡くしてから、ずっと……

裏将軍時代、レイターはフローラの後を追って死のうと危険な飛ばしを続けていた。バトル終了後の「また、死に損なった」という裏将軍の決め台詞は、彼の本心だった。
アレグロさんはそんなレイターをずっと見守ってきたのだ。
「ティリーさん、一緒に上級コースで飛ばしませんか?」
アレグロさんに誘われた。無理な話だ。
「いえ、あの、わたし、操縦ものすごく下手なんです。アステロイドベルトを自分で操縦したのも初めてで……」
「え? そうなんですか? いつもレイターと一緒に飛ばしているのかと思いました」
アレグロさんが意外だという顔をした。
レイターの彼女と言えば操縦が上手いというイメージがあるのかも知れない。彼氏と一緒に船を飛ばせたらどんなに楽しいだろうか。
レイターは裏将軍時代には『ギャラクシーフェニックス』のナンバーツー御台所のヘレンさんと付き合っているフリをしていた。フリ、と言っても夜も共にするという濃密な関係だ。

情報ネットを検索すれば、裏将軍と御台所の逸話は山のように記事になっている。
御台所のヘレンさんはわたしに言った。「レイターを愛しているの」と。
その関係が恋愛ではないことを知っている。けれど二人は船を通じて深いところで繋がっている。わたしには立ち入れない世界。
プロの飛ばし屋であるヘレンさんなら銀河一の操縦士とお似合いだ。
心がざわつく。
アレグロさんが続けた。
「残念ですね。前にアステロイドの上級で見た『白魔』とのバトルがすごかったので、ぜひ、ティリーさんとご一緒したかったのですが」
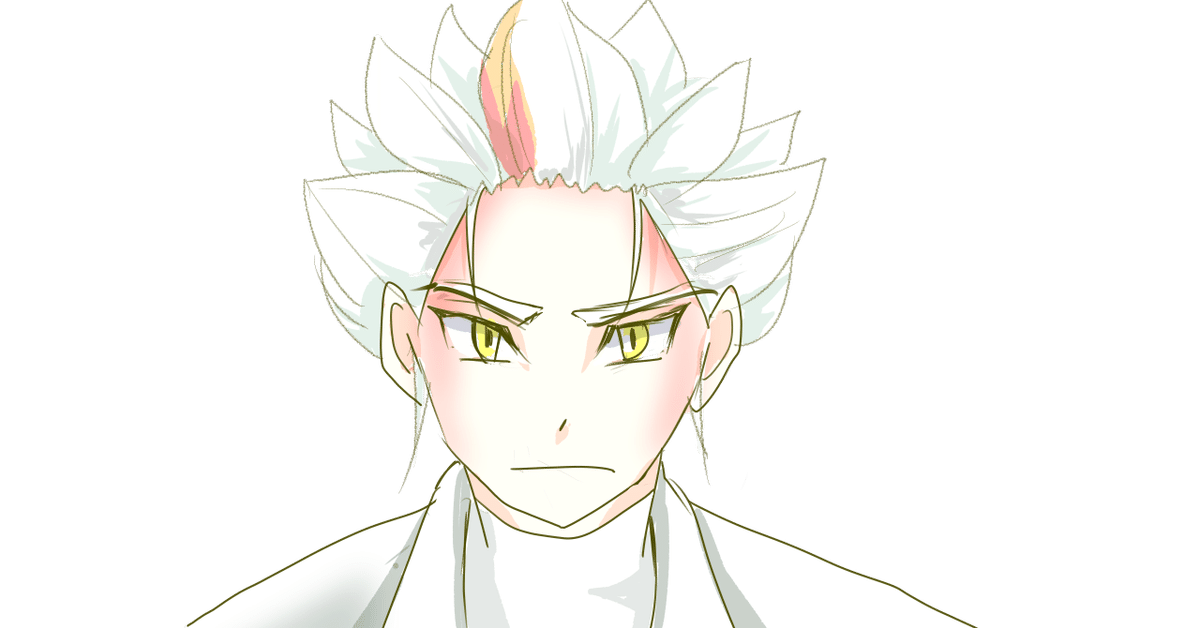
『白魔』とのバトル。
思い出すだけで、身体がしびれる感覚に襲われる。
まだ、わたしとレイターがつきあう前のことだ。
レイターはアレグロさんに頼まれて、御台所の代打ちとして『白魔』と戦うことになった。わたしはたまたま、趣味の船仲間としてレイターの助手席に座っていた。
そのバトルの最中、『あの感覚』をレイターと共有した。
小惑星帯で『白魔』をとらえゴールが見えた時、まるで世界がスロー再生されているようだった。
時が止まる全知全能の感覚。宇宙空間は真っ白に輝き、多幸感に包まれた。言葉では表せない領域をはっきりと感じた。

銀河一の操縦士がずっと追い求めている『あの感覚』。無敗の貴公子との激闘でも感じられなかったという世界は確かに存在していた。
もう一度『あの感覚』に触れたい、と実はその後もレイターと一緒に小惑星帯を飛ばしているけれど、再現はできていない。
「ふむ、折角だから、行ってみっか。上級へ。もしかしたら『あの感覚』のヒントがつかめるかも知れねぇし」
レイターがわたしを見た。
「無理に決まってるでしょ! 初級だって危なかったのに」

レイターったら昔の仲間に誘われて、上級で飛ばしたくてうずうずしている。
「大丈夫、銀河一の操縦士の俺がついてる」
「さっきは死ぬほど大変だ、って言ったくせに」
「平気平気。さっきの飛ばしであんたの下手くそな操縦の癖はつかんだ」
レイターがわたしを見て笑った。その笑顔についつられてしまった。

天性の人たらしだ。
「しょうがないわね」
「じゃあ、話は決まりだ。ティリーさん、アレグロの後についていきな」
飛ばし屋の総長であるアレグロさんは、当たり前だけれど操縦が上手かった。
アレグロさんの通ったあとを着いていくと、小惑星帯を抜けるのが楽だった。わたしのことを考えてコースを選んでくれている。
と言っても小惑星にぶつからないのは横でレイターが必死にルート修正してくれているからだけれど。
アステロイドベルトの上級コースへ着いた。
ここへはしょっちゅう来ている。とはいえ、いつもは助手席だ。見慣れた景色が違って見える。
ほかにも何機か飛んでいた。
アレグロさんから連絡が入った。

「レイター、あそこの一団からバトルを申し込まれたぞ、どうする?」
「バトル? 無理よ、絶対駄目!!」
わたしは大声で叫んだ。
この人たち、わたしが操縦桿を握っているというのに、バトルを受けかねない。レイターがちらりとわたしを見た。
「っつうことだから、丁重にお断りしといてくれ」
残念そうに答えると、アレグロさんが意味ありげに笑った。
「ほう」
彼がバトルを断ることが珍しかったに違いない。少し胸が痛んだ。
バトルではなく、アレグロさんの後ろについてアステロイドの上級コースを流して飛ばすことにした。
上級は小惑星の間隔が狭い。緊張する。
アレグロさんの船がスタートした。は、速い。
「ほれほれ、置いてかれるぜ」
あわてて加速したけれど、やっぱり上級は違う。小惑星の間隔が狭い。次から次へと目の前に迫ってくる。
「きゃあ」
アレグロさんの船を追いかけるどころじゃない。
すっと、船のスピードが落ちた。
「ゆっくりでいいから、落ち着きな」
レイターが減速をかけてくれた。わたしは軽いパニックを起こしていたようだ。
「う、うん」

「大丈夫、俺がついてる」
レイターの声に安心する。大丈夫、レイターが一緒だ。
速度を落として、一つずつクリアしていく。アレグロさんとは完全にはぐれてしまった。
「変だな」
レイターがつぶやいた。
「ティリーさん、ちょっとコースから抜けるぞ」
「え?」
「そのまま上昇させてくれ」
よくわからないけれど、操縦桿を引く。
教習船は小惑星帯から抜け出した。
「アレグロ、おいアレグロ聞こえるか?」
呼びかけに返事が無い。
レイターがモニター画面を切り替えていく。飛ばし屋が小惑星帯のルートに設置しているライブカメラだ。
「ちっ、ばれたか」
レイターが舌打ちする。
アレグロさんの船の周りに黒い船が十機近く集まっている様子が映っていた。
「ばれた? ってどういうこと」
「連合会総長ともなると敵も多いのさ」
相手は船に槍のようなデコレーションをつけていて品がない。
「あの改造は『黒玉』だな」
レイターによると『黒玉』はギャラクシー連合会に所属していない独立系暴走族ということだった。
「ティリーさん、アレグロのところまでショートカットして飛ばすから加速してくれ」
「わかったわ」
小惑星帯じゃなければ、わたしだって操縦できる。
アクセルを踏む。
うわっ。すごいスピード。直線番長のことを忘れていた。
アレグロさんと黒玉のやりとり通信を傍受する。
「総長がひとりでお忍びとは、いい度胸だな。このところ連合会の野郎、勢いづきやがって、面白くなかったんだ」
『黒玉』がアレグロさんに喧嘩を売っている。と言うかこれは喧嘩じゃなく集団リンチだ。
「首をとれ!」
『黒玉』のヘッドが命令すると同時に、黒い船たちがアレグロさんの船に向けて、ライトレーザーを撃ち始めた。
ライトレーザーは船の電子機器を磁場で一時的に動かなくしてしまう。
宇宙海賊への対策用に売られているのだけれど、若者がふざけて一般船に向けて撃つことが問題となっている。
アレグロさんがライトレーザーを必死にかわしているけれど、あれだけ多数から攻められては、逃げ切れない。
「待ってろアレグロ。ティリーさん、アクセル目いっぱい踏んで! 操縦棹動かすなよ」
「は、はい」
言われた通りにペダルを踏み、操縦桿を動かさないように握りしめる。船が加速したまま小惑星帯に突っ込んでいった。
レイターが無線の回線を開く。
「うおおりゃあ、退散しねぇとぶっ殺すぞ!」
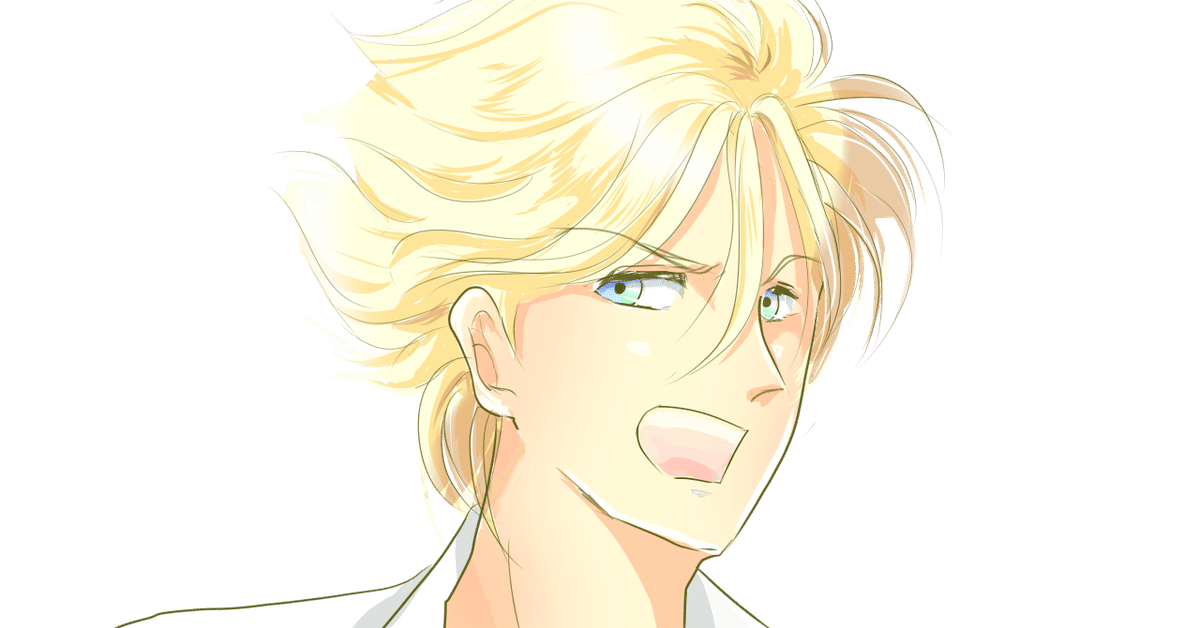
ぶっ殺すとか言わないでほしい。
メガマンモスのエンジンが全開だ。
急降下で身体が浮き上がる。ジェットコースターより速度も体感スピードも圧倒的に速い。その状態で小惑星のスレスレをすり抜けていく。
どう考えてもアトラクションの乗り物より怖い。
この操縦が平気で絶叫マシンが怖い理由がわからない。
猛スピードでアレグロさんを取り囲む敵陣の、ど真ん中を突っ切った。わたしは操縦桿をただ握っているだけだった。
黒玉の動きが乱れた。黒玉の頭らしき人物の声が裏返っている。
「と、突風教習船! 裏将軍だ! ひ、引けぇ。戻るぞ」
黒玉が撤退始めた。
けれど、黒玉のうちの一機がわたしたちの船に近づいてきた。安くて新しい改造船。
「何だよ、このしょぼい教習船」
「ば、ばか、新入り逃げろ」
敵の頭のあわてた声が聞こえる。
かつて、飛ばし屋の間で名をとどろかせていた裏将軍の『突風教習船』。

でも、それは七年前の話。知らない若者には単なる教習船に見えるのだろう。
レイターはちょっかいをかけてきた新入りに向けて、突っ込んでいった。
「退散しねぇと、ぶっ殺すっつったろが!」
「殺せるもんなら殺してみろよ」
新入りはライトレーザーをやみくもに撃って挑発してきた。
レイターはそれを全てかわし一瞬で近づく。人間業じゃない。仮でつないだ教官席だけで動かしている。
感じる。やっぱりこの人はレーサーではなく戦闘機乗りなのだと。
「マ、マジかよ? ぶつける気か」
この船が普通じゃないことに気が付いた新入りが急いで機体を反転させた。
「逃がさねぇよ」
レイターはぴったりと後ろにくっつけた。船間距離が近すぎる。なのに警報音は鳴らない。
死に場所を求めて飛ばしていた突風教習船に安全装置はついていないということだ。
新入りの操縦が乱れている。上下左右、振り切ろうとするけれど、どこへ飛ばしても教習船は牽引されているかのように離れない。
「あ、ありえねぇ」
究極のあおり操縦にかわいそうなほどあせっている。
新入りの前に小惑星が迫っていた。教習船が挟み込む。
レイターがわたしの操縦席まで手を伸ばしてきた。スイッチを押す。形の変わったライトレーザーが出てきた。
この教習船にも積んでいたんだ。
「ぶっ殺すっつたろが」
そう言いながらレイターがトリガーを引いた。白い光の束が発射された。
え? まぶしい。これはライトレーザーじゃない。
黒玉ヘッドの絶叫する声が響いた。
「本物のレーザー砲だ!!」
光の束が、前を行く黒玉の新入りに向かっていく。
ぶっ殺すって、ま、まさか撃ち落す気?
「レイター、やめて!」

次の瞬間、直線番長がうなり、教習船が急旋回した。
Gで身体がシートに押し付けられる。現場から一気に離れていく。緊張で息ができない。
モニターが白く輝き、爆発の瞬間が映った。かけらが飛び散り、近くにいた黒丸たちの船に衝突する。
「あのかけら、結構船に傷が付くんだよな。ざまみやがれ」
身体中から力が抜けた。
「びっくりするじゃないの!」
「あん?」
「こんなレーザー砲、積んでるなんて」
「違法じゃねぇよ。許可はとってある」
この人はボディーガード協会のランク3Aだ。武器の携帯を許されている。
身体の奥が震えている。落ち着こう。ゆっくりと息を吐く。
「怖かった」
「ごめん。Gがかかっちまったな」
「違う……」
レイターがわたしの顔をのぞき込んだ。
「もしかして、ティリーさん。俺が、あいつらぶっ殺すと思った?」

わたしは目をそらして答えなかった。
正直に伝えたらレイターを信じていない、と言うようなものだ。
レイターが撃ったレーザー弾は、新入りの機体のすぐ脇、紙一枚というラインを通り過ぎ、そのまま、目の前に迫っていた小惑星に命中。小惑星は粉々に砕け散った。
あのスピードで新入りの船が小惑星に激突していたら、大惨事になるところだった。
レイターは小惑星をレーザー弾で撃ち砕くことでそれを救ったのだ。
「裏将軍、申し訳ございません。お許しください」
黒玉たちは謝りながら一気に退散していった。
「おい、アレグロ、大丈夫か?」
レイターの呼びかけにアレグロさんの元気そうな返事が返ってきた。
「レイター、お前、また伝説作ったな」

「あん?」
「復活した裏将軍が『突風教習船』で黒玉を返り討ちにしたなんて、当時を知ってる奴は涙流して喜ぶぞ」
「バカ言ってんじゃねぇよ」
「俺は全くざまあないな。ライトレーザーにやられて船が動かない」
「ここはコースだから早いところ移動したほうがいい」
と言いながらレイターはするりと後部へと移った。レイターが隣にいないと急に心細くなる。
「どうするの?」
レイターは服の上から簡易宇宙服を着用し始めた。
「この教習船でアレグロの船をレッカーするんだ。アームは積んでねぇからワイヤーロープを手動で結んでくる」
レイターが船外へ出るということだ。

「わたしはどうすればいい?」
「故障船信号を出して、もう少し船を近づけてくれ、頼んだぜ」
レイターはウインクをすると二重ハッチのエアロックを抜けて宇宙空間へと出て行った。
この船の操縦をわたしひとりでやらなくちゃいけないのかと思うと、気が重い。
とにかく船をアレグロさんの船の近くまでそろりと動かして止める。
「うまいうまい」
無線からレイターの声が聞こえた。
教習船につながったワイヤーを手にしたレイターは、担いだジェット・パックを噴射させてアレグロさんの船へ向かった。
その時、
ピピピピピ
警報音が鳴った。船が高速で近づいてくる。そうだここはコースだった。
「レイター、船が来るわ!」
「故障船信号出したか?」
操縦に気をとられて忘れてた。
信号ボタンが見つからない。
「ど、どれだっけ?」
焦ってパニックになる。
「右の二段目左から三つ目だ」
右の二段目、右の二段目……あった、あわててボタンを押す。
強力なライトが点滅し始めた。近づいてくる船の中で警報が鳴っているはずだ。
グワァン。
船は進路をギリギリで変更した。
さっきレイターが粉砕した小惑星のあたりで旋回し、猛スピードで飛び去っていく。
間に合った。
と息をつく間もなく、船が蹴散らした小惑星のかけらが飛んできた。かけらと言っても石のつぶてだ。外にいるレイター当たったらけがをする。
「レイター、危ない!」
わたしが叫ぶより早く、レイターはジェット・パックを操作して教習船の影に隠れた。
パラパラパラ……
船体にかけらが当たる音がする。
「レイター、大丈夫?」
「ああ。ただ、酸素ボンベの一つが直撃くらった。三分以内に終わらせるぜ」
それって大丈夫なの?

わたしの心配をよそにレイターはアレグロさんの船へ向かい、ワイヤーを取り付け始めた。
手際がいい。見る間に繋がる。セキュリティサービスの職員のようだ。
「よし、オーケーだ。ティリーさん、船の向きを変えて軽く引っ張ってくれ」
「わかったわ」
操縦桿を動かしながらアクセルを軽く踏む。
グォン。軽く踏んだはずなのに、船がいきなり進んだ。
「うわっ」
ワイヤーが鞭のようにしなる。強い力でレイターの身体をはじいたのが見えた。レイターが宇宙空間へ飛ばされていく。
「レイター! ごめんなさい!」

大声で呼ぶ。
「……」
返事が無い。レイターの身体がどんどんと遠ざかっていく。
「レイター? レイター!」
「……」
呼びかけに反応しない。通信機が壊れた? いや、はじかれたショックで気を失っているに違いない。
わたしのせいだ。どうすればいい? とにかく追いかけなくちゃ。
アクセルを踏む。
ガンッッツ。
衝撃が走る。ワイヤーでアレグロさんの船とつながっていることを忘れていた。教習船をうまく動かせない。
「レイター、目を覚ませ! 酸素が無くなるぞ!」
アレグロさんの声があせっている。
「レイター! 起きて!」
わたしは思いっきり叫んだ。
レイターの姿が暗い宇宙空間に吸い込まれ見えなくなった。
「お願いだから、起きて、返事して!」
レーダーが示す光の点がどんどんと離れていく。焦ったわたしは大声で怒鳴った。
「レイター、起きなさいっ!」
「う、……おはよ、ティリーさん」

通信機から声が聞こえた。アレグロさんが指示する。
「早く戻れ! 俺の船のが近い、教習船までは無理だ。急げ! 酸素濃度が急速に低下しているぞ」
「わかってるが、ジェット・パックがうまく起動しねぇ」
「何っ! こちらでできることあるか?」

アレグロさんの声が緊張している。
「とにかく動かねぇで待っててくれ。一回の噴射にかける。間に合うか祈ってくれや」
「お願い間に合って!」
レイターが三分で終わらせると言ってから、もう五分近くが経っている。
「ちっ、目がかすむ」
時間が止まっているかのようだ。
近づいてくる小さなレイターの姿が、ようやく目視で確認できた。
ジェット・パックのライトが消えている。一度だけ噴射させ慣性力だけで飛んできたのだ。もどかしいほどスピードが出ない。動画なら倍速で再生したい。
「はあ、はあ」
通信機からレイターの荒い息が聞こえる。
「レイター、がんばって」
人は何分息を止めていられるのだろうか。酸素のない状態ってどれほど苦しいのだろう。
少しずつレイターの呼吸音が小さくなり、聞こえなくなった。
「レイター!」
レイターの身体はピクリとも動かない。ただ、ゆっくりと流れてくる。
不安と苛立ちで居ても立っても居られない。すぐそこにいるのだ、迎えに行きたい。けれど、レイターはアレグロさんの船までの距離と角度を考慮して噴射したはずだ。下手なことをすれば状況は悪化する。
『銀河一の操縦士』の彼女だというのに、助けることも何もできない。情けなくて涙が出る。
レイターの身体はゆっくりと静かにアレグロさんの船に到着した。
アレグロさんの船内モニターを凝視する。
エアロックでぐったりしているレイターの身体を、急いでアレグロさんが引き上げた。お願い。早く! 早く!
アレグロさんが手際よく簡易宇宙服のボンベを取り換え、ヘルメット内の酸素濃度を高める。
「しっかりしろ!」
目を閉じたままレイターが反応しない。低酸素症だ。
「脈はあるが弱いな」
わたしのせいだ。わたしが故障船信号を出さなかったからだ。わたしがワイヤーを引っ張ったからだ。レイターが死んだら全部わたしのせいだ。
神様、お願い、助けて!
「レイター、死なないで! お願い!」
胸が苦しい。ただ祈った。どれだけの時間が経ったのかよくわからない。実際にはそんなに経っていなかったのかもしれない。
レイターの瞼がピクリと動くのがみえた。
「不死身は、死なねぇに、決まってる、だろ」
ゆっくりとレイターが目を開けた。
「大丈夫か?」
アレグロさんがレイターの身体を支える。
「俺は、銀河一の、操縦士、だぜ。……どんだけ、低圧訓練、受けてると、思ってんだよ」

レイターは口を歪めて笑った。けれど、一言話すのも苦しそうだ。指先が震えている。全然大丈夫じゃない。
とにかく、生きていてくれただけでうれしい。涙が溢れる。
アレグロさんに抱えられ、真っ青な顔をしたレイターが通信機を通してわたしを見た。
「ふぅ。ティリーさん。悪りぃな、そっちへ戻れねぇ。ワイヤーはちゃんとつながってるから、あんた、一人でこの船を引っ張ってくれ」
「う、うん」
泣いている場合ではない。やらなくちゃ。
「ゆっくりでいいからな。さっき入ってきた上昇方向が、早く抜けられる」
「わかった」
操縦桿を握る。船をスタートさせた。
わかった、と言ったはいいけれど、レイターの補正なしにこの船を飛ばすのはわたしにとっては困難の極みだ。

ここは小惑星帯が集まるアステロイドベルトの上級。しかも、船をレッカーしながらの操縦なんて生まれて初めてだ。
レイターが操縦して降りてきた時はあっという間だった。
上下の縦軸方向に抜けるのに、そんなに時間はかかるはずがない、と思いたい。
アクセルを軽く踏む。
ブウォンッ。
メガマンモスがうなり、衝撃で前のめりにつんのめる。あわてて足を離す。
小惑星が目の前だ。よけるために、操縦桿を回す。
ガ、ガタッ、ガタン。
わたしの操縦を補正するのに、レイターがどれだけ苦労していたのか身にしみる。
小惑星一つ乗り越えるのも大変だ。
ようやくかわした。
ほっとしたら、小惑星が眼前に迫っていた。
「きゃあ」
「ティリーさん、操縦桿をゆっくり右回転で四十五度傾けろ」

レイターの落ち着いた声が聞こえる。
「わかったわ」
指示にあわせて動かす。でも、うまくできない。四十五度のつもりが五十度までいってしまう。
ガガガガガガ……
衝撃が船に走る。翼が小惑星にこすった。
「ご、ごめんなさい。大事な船なのに」
レイターの船、しかも大切な突風教習船に傷を付けてしまった。
「気にすんな。どうせその船に俺は乗れねぇんだ」
レイターが気を使ってくれる。けれど、気にするなと言われても無理だ。ピカピカに磨き上げられた思い出の愛機。
わたしの不安定な操縦で、ワイヤーロープでつないだアレグロさんの船が右に左に揺れる。変な加速がかかって絶叫アトラクションよりひどい、というか危険な状況だ。
レイターが苦しそうに口を押えている。低酸素症の上にこの揺れだ。吐き気がひどいに違いない。
「だ、大丈夫?」
どう対処すればいいのかわからない。
「ティリーさん、いいか、こっちの船のことは気にするな。まず自分の船に集中するんだ」
「う、うん」
ふと計器を見て悲しくなった。さっきの場所からほとんど動いていない。埒が明かないとはこのことだ。
その時、いいことを思いついた。どうして今まで気が付かなかったのか。
「ねえ、レスキューサービスを呼べばいいんじゃないの?」
いつでもどこでも二十四時間サービスで、助けに来てくれるはずだ。
レイターとアレグロさんが顔を見合わせた。

「俺たち、レスキューサービスに入ってねぇんだ」
「え?」
信じられない。任意のサービスだけれど、お客様にはいつも勧めている。宇宙空間は死に直結するから加入率は九十八パーセントだ。
「金がもったいねぇんだよ。自分で修理できるし」
「……」
泣きたくなってきた。わたしが自分の船を持っていれば絶対会員になっていたのに。
とにかく少しずつでも進むしかない。
一つ抜けた。
と、一息ついたところで次の小惑星が目の前にあった。
驚いた瞬間、操縦棹を横に倒してしまった。
きゃ、きゃあ。
右方向に初速がかかる。
ワイヤーロープが変なしなりをみせた。先端につないだ船が滑るように流れていく。

危ない! アレグロさんの船が小惑星に激突する!
このままじゃ船が大破する。レイターたちが怪我をする。いや、怪我じゃ済まないかもしれない。
ど、どうすればいいの?
レイターがやったようにレーザー砲で小惑星を撃つ?
そんなこと無理だ。
ぶつかるっ!
為す術もなく思わず目を閉じる。
ガックンと衝撃が船に走った。身体が前につんのめり、シートベルトに引っ張られる。
レイター!
揺れる船内でモニターを確認する。
アレグロさんの船は無傷だった。
どこからか現われた小型機がアレグロさんの船をアームで押さえていた。間一髪、小惑星への衝突は避けられた。
ワイヤーロープで繋がったわたしの船に、その反動が伝わったのだった。
助かった。
全身の力が抜けた。
通信機から張りのある女性の声がした。
「『突風教習船』で裏将軍が飛ばしてるっていうから見に来てみたら、随分とへっぴり腰な教習船だわね」
わたしの知っている声だった。

「ヘレン!」
レイターが叫んだ。
操縦席の前に新たなモニターが開き、真っ赤なレーシングスーツに身を包んだ美しい女性が映った。御台所のヘレンさんだ。
「レイターはアレグロの船に乗ってるわけね。じゃあ教習船は誰が操縦してるのかしら?」
「わたしです」
モニターにタッチしてヘレンさんへの通信回線を開く。
「あら、ティリーさん。お久しぶりね。おかしいと思ったのよ、レイターがあの小さなシートに座れるはずがないもの。苦戦しているようだけれど、あとは、あたしが牽引していけばいいかしら?」
「お願いします」

ヘレンさんがアレグロさんの船をアームでつかんだまま上方向へ向かった。わたしが乗った教習船は一緒に引っ張られていく。
あっと言う間の出来事だった。
ヘレンさんは二台を繋げた状態でものの二十秒もかからず、するするとアステロイドを抜けた。
わたしだったら何分、いや、何時間かかったか、想像もできない。
「ヘレン、あんた、随分都合いい場所にいたじゃねぇの」
レイターがヘレンさんにたずねた。
「そりゃ、総長には悪いけど一人にしておくわけにいかないでしょ」
「後を付けてたのか?」
とアレグロさん。
「木星近くまでね。あとは一人で飛ばして遊んでたけど」
「あんた、相変わらず世話焼き女房やってんだ」
レイターがからかうように言った。
相変わらず、って過去にはレイターの世話焼き女房だった、という意味だ。
「何とでもおっしゃい」
余裕のある大人の声。
心がざわつく。
あれはフェニックス号で初めてヘレンさんを見た時。
二人は挨拶とは思えない濃厚なキスをしていた。
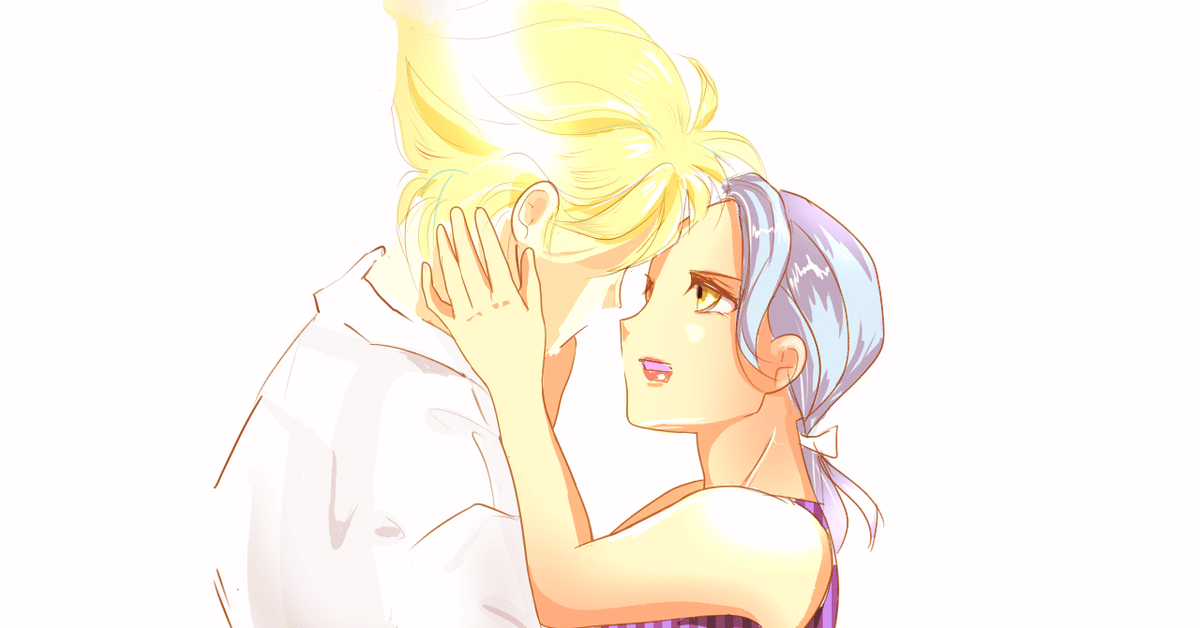
あの場面の印象が強烈だったせいだ。考える必要のないことを考えてしまう。
どす黒い苛立ちが身体の奥底から沸々と湧き上がってくる。
「ねえレイター、折角だから飛ばさない? 教習船見たら懐かしくなっちゃった。バトルでもいいわよ」
ヘレンさんがレイターを誘った。
ここはアステロイドの上級で、プロの飛ばし屋のヘレンさんはレイターと競う腕を持っている。そして、レイターは教官席でも十分に飛ばすことができる。条件がそろっている。
「ば~か。裏将軍と御台所が総長と飛ばしてるなんてギャラリーが騒いでみろ、面倒この上ねぇだろが」
「あたしは構わないんだけどね」
ヘレンさんは名残惜しそうだ。
レイターは本音ではバトルがしたいはずだ。
わたしに気を使っているんだ。非力な自分が突き付けられる。
わたしがいなかったらレイターはヘレンさんの申し出を受けたに違いない。わたしさえいなければ……
*
「ただいまぁ」
レイターが教習船へ戻ってきた。
レイターが外へ出て実際には三十分しか経っていないのに、時間の感覚が麻痺している。
生きているレイターが目の前にいる。うれしいのに、緊張と自己嫌悪が入り混じってうまく言葉が出ない。
「体調はいいの?」
「平気平気。姫さまは待ちくたびれちゃったかい?」
顔色はよくないけれど、話す様子はいつものレイターだ。この人の回復力は並じゃない。
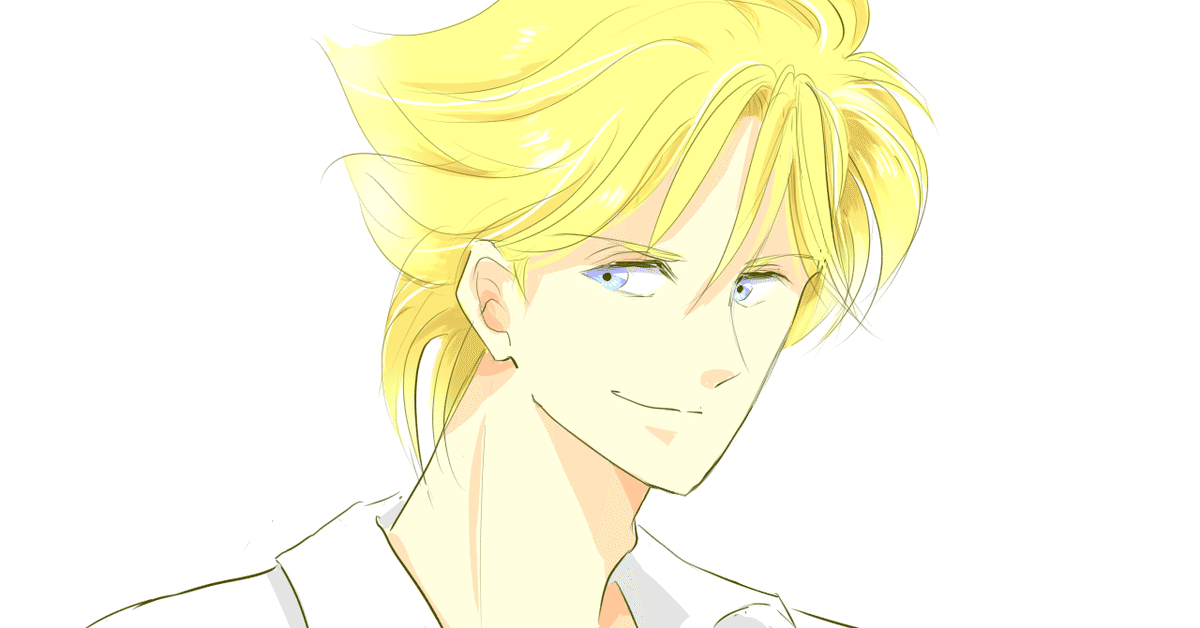
安心すると腹立たしさがこみあげてきた。
「百年待った気分よ」
「じゃ、お目覚めのキスを」
とレイターが顔を近づけてきた。
ヘレンさんとの口づけが頭に浮かぶ。わたしったらプイっと反射的に避けてしまった。
「あん?」
レイターが少し目を見開いた。わたしはうつむいて何も言えなかった。
「ちっ、吐き気はおさまってるし、ゲロは吐いてねぇよ」
肩をすくめてレイターは教官席に座った。それが理由じゃないことはレイターだってわかっている。
どう考えても『銀河一の操縦士』の彼女として、わたしはふさわしくない。窓の外にヘレンさんの船が見えた。手にした操縦桿を力を込めて握りしめる。
彼女は操縦がうまくて、頭も切れて、性格もよくて、美人で、とにかくいい女で、わたしがヘレンさんに勝てる要素はどこにもない。
レイターとヘレンさんは似ている。
船を自分の思うように扱い、そこから得られる自由と幸福の感覚を共有している。
わたしにはヘレンさんのようにレイターと一緒に飛ばしたりバトルの相手をすることはできない。
それどころか、レイターに迷惑をかけてばかりだ。とにかく謝らなくては。
「きょうはごめんなさい。救助信号出し忘れてレイターを危険な目に遭わせたし、大事な教習船を傷つけちゃったし……」
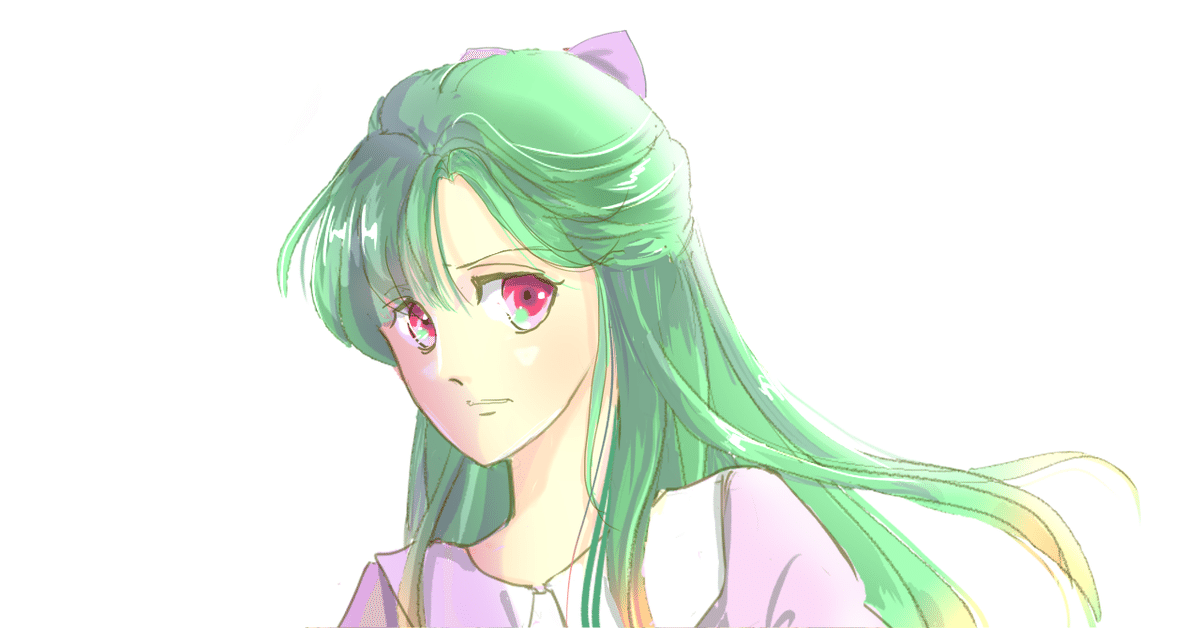
口にしてさらに気持ちが落ち込む。
「謝るこたねぇよ。あんたはよくやってくれたぜ。ここへ連れてきちゃったのは俺だし」
ここ、アステロイドベルトの上級はレイターにとって大切な場所だ。彼は本当はここで飛ばしたいのだ。ため息が漏れた。
「銀河一の操縦士には、操縦のうまい女性がお似合いよね」
「あん? あんた、もしかしてヘレンのこと気にしてんの?」
「……」
レイターと視線を合わせられず、窓に目を向ける。
ヘレンさんの船がアレグロさんの船を牽引して遠ざかっていく。スムーズな飛ばし。さすがプロの飛ばし屋だ。この人たちの間には信頼感がある。仲間が助けに来るからレスキューサービスが必要ないのだ。
「あいつは、ヘレンは、十六の頃から飛ばし屋の頭、張っててさ。操縦もうまいし度胸もあって信頼もできる。隣で飛ばすには本当にいい相手なんだ」
ヘレンさんのことを口にしないでほしい。耳をふさぎたい。

わかっている。二人が深い絆で結ばれていることを。ヘレンさんはわたしに言った。レイターを愛している、純愛の愛だ、と。
彼女としてのわたしの存在価値が薄れていく。
「どうせ、わたしは操縦が下手よ」
自虐的な言葉が口を衝いてでる。
「確かにあんたは操縦がど下手だ。けど一方で、ヘレンは操縦は上手いが、俺と同じで自分で操縦しねぇと気が済まねぇんだよな。つまり、助手席に座るのが嫌いなのさ。同じ船に乗って一緒に飛ばしを楽しむってことができねぇんだ」
レイターの顔をちらりと見ると、彼はわたしをじっと見つめた。

「あんたも知ってる通り、俺は人を乗せて飛ばすのが好きなんだ」
レイターは操縦士の最高峰と称えられる宇宙船レースのS1をあっという間に引退してしまった。わたしはもったいない気がしているのだけれど、S1は人を乗せて飛ばすことはない。
彼は他人の評価より自分の感性を基準として『銀河一の操縦士』を追い求めている。
「俺が操縦する船に乗って、バトルでも何でも怖がらずに一緒に楽しんでくれる、ってのが俺にとって理想の彼女なんだけど」
理想の彼女、と言う言葉が頭の中で跳ね回る。こんなダメなわたしでいいの? 顔がほてってきた。心臓がトクトク音を立て、目の奥が熱くなる。景色がにじんで見えた。
レイターの手がわたしの頭に軽く触れた。
「俺のティリーさん、かわいすぎ」
わたしはあなたの所有物じゃない。なのに何度も聞いたこの言葉がうれしい。涙がこぼれそうだ。

「もっとも、あんた宇宙船メーカーに勤めてるくせに操縦が下手すぎ。だから帰りは特訓だ!」
「ひえええぇ」
まだ操縦するの? きょうだけで一生分操縦したのに。うれし涙が悲し涙に変わった。
帰り道。レイターは頭の上で手を組んで、操縦の補正を全くしてくれなかった。
「こんなところで加速すんなっ!」
月の御屋敷まで、レイターに罵倒されながら帰った。これが、かわいすぎる理想の彼女への対応だろうか。今日の色々な恨みを晴らしているとしか思えない。
疲れた。
「ほんと、あんた銀河一操縦が下手くそだよな。ま、きょうの俺の教えで、ちっとはマシになったかな。つってもこれじゃ近場のソラ系内しか飛ばせねぇよな」
散々罵られて意地悪な気持ちが湧いてきた。
「ねぇ、レイター。ソラ系内でデートしたい場所があるの。わたしが操縦するから、今度、一緒に行ってくれる?」
「もちろんさ。どこ、行きてぇんだ?」
「海王星衛星のトリトンパーク」
「え?」
レイターの表情が石像のように固まった。

老舗の公園トリトンパークに先日、銀河最大、最速、最怖の絶叫ジェットコースターが新設されたのだ。毎日大量のコマーシャルが流れている。
レイターの顔をのぞき込んで様子をうかがう。
「わたし、新型の絶叫コースターに乗りたいのよね。もしや、レイター、怖いの?」
「怖いわけねぇだろが」
絶対、嘘だ。
「そうよね、アステロイドベルトの操縦より怖くないし、来週末にでも行こっか?」
「いや、いい。やっぱり俺が操縦する。何といっても俺は、銀河一の操縦士だからな。海王星と言わず、ソラ系の外でもどこでも連れてってやるよ。そうだ、遠出のデートをしようぜ」
レイターの取り繕う様子がおかしくて笑える。
「はいはい」
きょうはレイターにたくさん迷惑をかけたのだった。これ以上いじめては罰が当たる。
それにしても『理想の彼女』という言葉がよみがえり頬がゆるむ。
「あんた、何、ニタニタ笑ってんだよ?」
レイターが不安げにわたしを見た。何もたくらんでいないのに警戒してる。
「操縦って楽しいね」
はぐらかすようなわたしの答えに、眉をひそめたわたしの彼氏が、理想の彼女のわたしをにらみつけた。 (おしまい)<恋愛編>第五話「発熱の理由」へ続く
裏話や雑談を掲載したツイッターはこちら
<出会い編>第一話「永世中立星の叛乱」→物語のスタート版
イラストのマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

