
銀河フェニックス物語 【恋愛編】 第五話 発熱の理由(まとめ読み)
大手宇宙船メーカークロノス社に勤めるティリーはフリーランスの操縦士レイターとつきあうことになり、恋に仕事に忙しい毎日を送っていた。
銀河フェニックス物語 総目次
<恋愛編>第四話「お出かけは教習船で」
<恋愛編>のマガジン
「ティリーさん、あんた、熱があるんじゃねぇの?」
出張先へ向かうフェニックス号の居間で、レイターがわたしの額に手を当てた。大きな手がひんやりして気持ちいい。

一週間ぶりに顔をあわせた彼氏は、何でもお見通しだ。
「予定じゃ、明日の朝七時に先方の星系に到着するぜ。お袋さんに薬出してもらって、きょうは早く寝ろよ」
「うん、そうする。ごめんね。久しぶりにおしゃべりしたかったんだけど」
ホストコンピューターのマザーにもらった薬を飲んで、個室へ戻るとベッドで横になった。
窓の外を星が流れていく。
今週はとにかく仕事がハードだった。
明日、訪問する取引先は雑貨販売業のムントル社。オーナー社長のハル・ムントル氏の名前を冠したこの会社は「他社より高く売らない」激安で有名だ。
たまたま、わたしの顧客がムントル社と関係があり「営業用に小型船十機の購入を検討しているそうだから、相談にのってやってほしい」と紹介されたのだ。
本来なら、隣の法人営業課が扱う案件だけれど、紹介者の手前わたしが担当になった。わたしは法人営業課のエースであるアディブ先輩に教えてもらいながら、ムントル社へ営業アプローチをかけた。

資料の作り方も個人客とは勝手が違う。残業が続き、徹夜もした。
薄利多売をモットーとするムントル社は、安くて経費の掛からない船を希望していて、弊社ライバルのギーラル社から相見積もりを取っていた。激安ムントルは値切って仕入れるプロだ。
「値引き交渉に備えて、安く見えるけれど余裕のあるラインの価格を提示しましょ。ロゴ入れのサービスも手配しておくわ」
アディブ先輩のアドバイスを踏まえて慎重に見積書を作成した。
先方への資料一式は本社から通信ネットワークでも送れるけれど、お客さまからの紹介の上に慣れない法人案件だ。作業を丁寧に進めるためムントル本社へ出向き、情報ディスクを担当者に手渡すことにした。直接、顔をあわせておくことは大切だ。
そんな忙しさの中、今週はレイターと会う時間が取れなかった。だから、出張に出かける船がフェニックス号と聞いた時は、思わず「ラッキー」とつぶやいた。
この船は本当に乗り心地がいい。久しぶりに生のレイターを見たらほっとして疲れがでたようだ。
身体がだるい。けれど、明日の仕事は顔合わせだけだから大丈夫。
先方の上司が今週は出張に出ていて、込み入った交渉は来週以降なのだ。資料を渡したらすぐに帰ろう。
*
目を覚ますと、フェニックス号はムントル社近くの宇宙空港に到着していた。淡い陽の光が室内を照らしている。
ゆっくりと身体を起こす。まずい。体調が戻っていない。

いや、それどころか悪化している。寒気がする上に頭がズキズキ痛む。
「マザー、鎮痛剤と解熱剤を出してほしいの」
声がかすれていた。
「体温が三十八度を超えています。疲れから来た風邪が悪化していますね。仕事のために無理に体温を下げるのはよくありません。安静第一です。寝てください」
信じられないことに、マザーは薬を出してくれなかった。
寝てくださいと言われて、寝ている訳にはいかない。大丈夫、ディスクを渡しに行くだけだ。
ふらふらしながら居間へ向かう。目の奥が熱い。
レイターが朝食の用意をしていた。

調理師免許を持つレイターの料理。いつもなら喜んでいただくのだけれど、きょうは食欲がまるでない。
「スープだけでも飲んだ方がいいぜ」
レイターが作ってくれた野菜のポタージュスープをすすった。味はよくわからなかったけれどジンジャーがきいていて身体が温まる。
「それにしても、あんた、妖怪みてぇな顔してんな。大丈夫か?」
「失礼ね」
と言いながら鏡を見て、ショックを受けた。レイターの言う通りだった。
もともとわたしたちアンタレス人は瞳が赤い。そこへきて白目が充血して目全体が真っ赤だ。これは、メイクでもごまかせそうにない。

こんなひどい顔であいさつに行ったら、先方に嫌がられるに決まっている。どうしよう。
最善の策は、訪問の約束をキャンセルして、通信で資料を送ることだ。ムントル社は目の前だというのに、一体、わたしは何のためにここまで来たのか。がっくりと力が抜ける。
『厄病神』が発動したのだ。フェニックス号を喜んだ自分を恨みたい。
レイターがクロノス本社と連絡を取っていた。
「見積書を届けるだけなら、俺が行くけど」
モニターにアディブ先輩が映っていた。
「そうね、折角現地にいるんだから、レイターにお願いしたいわ」
結局、わたしはフェニックス号で待機し、レイターが情報ディスクを届けることになった。
彼がネクタイを結んでいる。わたしの代理だからか珍しく第一ボタンまでしっかり締めていた。

だらけたいつもと雰囲気が違う。背筋がすっと伸びている。
要人警護の時の髪を固めた『よそいきレイター』と近い。これはこれでかっこいい。
見慣れないレイターに胸の動悸が速くなる。熱が上がりそうだ。
「ティリーさん、俺に見とれてんの?」
レイターがウインクした。
「そ、そんなわけないでしょ。厄病神を見たってご利益ないもの」
つきあう前からの癖でつい憎まれ口をたたいてしまう。かっこいい、なんて恥ずかしくて口にできない。
「顔が真っ赤だぜ」
「熱のせいです。とにかく、わたしのせいで、ごめんなさい」
「謝んなよ。あんたを届けるか、ディスクを届けるかの違いさ。じゃ、行ってくるよ」
レイターが顔を近づけ、軽く唇を重ねた。あいさつのキス。
「風邪がうつるわよ」
「ティリーさんの風邪なら、いくらでももらってやるさ」
さらりと歯の浮くようなことをこの人は言う。誰にでも調子のいい彼。それでも、愛されている言葉はうれしい。また、体温が上昇しそうだ。
「トラブルがないことを祈ってる」
「軍の仕事は入ってねぇから大丈夫さ。大船に乗ったつもりで、ゆっくり寝ててくれ」
軽く手を振って、レイターは出かけて行った。
ジンジャースープのお陰だろうか。少し身体が楽になった。薬が入っていたのかもしれない。交渉は来週が本番だ。体調を崩したのがきょうでよかった、と思えるぐらいまで気持ちが落ち着いてきた。
フェニックス号のソファーは寝心地がいい。横になると、そのまま眠ってしまった。
*
レイターが帰ってきた音で目が覚めた。
近づいてくる彼の顔を見て不安になった。眉間にシワを寄せている。わたしにどう説明しようか悩んでいる顔だ。まさか、取引先で厄病神が発動した?
「どうしたの? 何があったの?」
あわてて、身体を起こす。頭痛は消えていた。
お客さまからの紹介案件だ。やっぱり無理してでもわたしが行けばよかった。
「これ」
レイターはソファーの真向かいに座ると、ポケットから白い契約カードを取り出した。

「え?」
見慣れたカードを受け取る。契約ボードにかざすと先方のサインが入った契約書が映し出された。熱のせいで幻覚が見えるのだろうか。ハル・ムントル社長の名前が読める。直筆だ。わたしがサインを入れれば契約が成立する状態だ。
目を凝らして確認する。幻覚でも夢でもない。社長のサインは存在している。意味が分からない。
きょうは資料を届けるだけの約束だった。今週は決済をする上司がいないと聞いていたのに。
「どういうこと? これ、偽造の契約書じゃないでしょうね」
この人は、偽造でも何でも得意だ。
「本物だよ」
ムッとした声でレイターが答えた。
契約書の中身を確認する。
燃費がいい小型船アラマット十機の購入を、なんと、値引き前の見積価格で合意していた。ライバルのギーラル社と比較検討した形跡もない。厳しい値下げ要請を覚悟していたのに。
レイターがかつて優秀な営業部員だったことを思い出す。宇宙船に詳しく人たらしなこの人は月間販売記録の保持者なのだ。どんな手を使ったのかわからないけれど、社長のサインがあるこの契約書は有効だ。
内容はクロノスにとって好条件だ。わたしではこんな契約は取れなかったに違いない。
レイターは黙ってわたしを見ていた。いつものようなおちゃらけた顔ではなく、無表情だ。何を考えているか読み取れない。
彼は気を利かせたつもりなのだろうか。
契約が取れればわたしが喜ぶと思ったのだろうか。
でも、これはわたしの仕事だ。
わたしのお客さまからご紹介いただいた、大事な大事な取引で、一生懸命丁寧に準備を重ねてきた案件だ。
行き場のない感情で身体中の細胞が沸騰しそうだ。ただでさえ熱っぽい身体が爆発しそうになる。かと言って、契約を取ってきたレイターを怒るわけにもいかない。
「これは、一体、どういうことなの?」

苛立ちを抑え込んで問い詰めるわたしに、レイターは困った顔をした。
「たまたま、ムントルの社長とエレベーターで乗り合わせたんだよ」
経済ニュースで見たハル・ムントル社長の人懐っこい丸顔が頭に浮かんだ。
「知り合いだったわけ?」
声に不快感が入り混じる。
レイターの人脈の広さには今更驚かない。
知り合いなら知り合いと先に言ってくれればいいのに。
「いや、初対面」
「どうして初対面で、この額で契約が取れるのよ。相手は激安に命を懸けているプロなのよ」
レイターが有能なのか、自分が無能なのか。突っかからずにいられない。
「そのムントル社長が、俺のファンだっつうんだよ」
「あなたのファン?」
「あの親父、S1が好きで、ずっとスチュワートのチームを応援してるんだとさ。俺と話が合っちゃってさ」
この人は前シーズン、宇宙船の最高峰レースS1の最終戦にチームスチュワートのパイロットとして出場し、『無敗の貴公子』と歴史に残るデッドヒートを繰り広げた。

「俺、S1辞めた、ってちゃんと説明したんだけど、そのまま社長室に呼ばれてさ」
レイターはうれしそうだ。なんだかんだ言って『銀河一の操縦士』は、操縦が褒められるのが好きなのだ。
「クライアントを怒らせるのもよくねぇだろ。あの親父、いい客だぜ。燃費がいいってアラマットを勧めたら即決だ」
レイターだから、この条件で契約が取れたのだ。
わたしが必死に徹夜して作った資料は読まれなかったに違いない。不完全燃焼のまま心の奥がくすぶり続ける。
「オーナー社長だからって、契約を精査しないで自分の趣味で決めるなんて、あとでトラブルになるかもしれないわ」
チッチッチ。レイターは人差し指を左右に揺らした。
「あいつ趣味だけで決めたんじゃねぇぜ。ビジネスセンスがある。俺に何て言ったと思う?」
「さあ」
「将軍閣下にもよろしくお伝えください、だとさ」
レイターの後見人は連邦軍の将軍家だ。S1にレイターが出場した際にプロフィールで伝えられたから知っている人は多い。
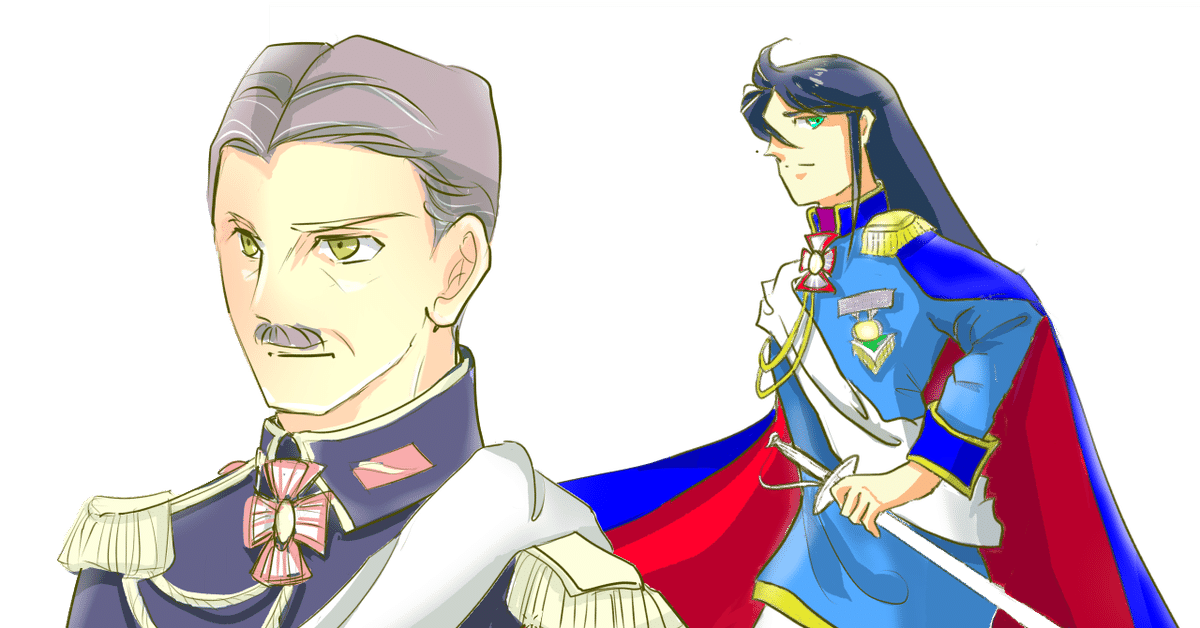
「ムントルは連邦軍と取引したいそうだ。流石、成金。使えるものはエレベーターですれ違っても逃さない。ウインウインな契約ってことさ」
ハル・ムントル社長のしたたかな笑顔を思い出す。ニュース番組の中で事業拡大のコツについて聞かれ「秘訣なんてありません。皆さまとのご縁のおかげです」と語っていた貪欲な経営者。
連邦軍との取引にレイターのコネクションを使うため、うちの船を言い値で買ったということだ。
「で、ティリーさん、どうする?」
レイターが心配げにわたしの顔をのぞきこんだ。
白い契約カードをじっと見つめる。わたしのプライドは納得していない。けれど、先方の社長のサインが入った契約をやり直すなんてできるわけがない。
「レイターのせいじゃないし、受けるしかないでしょ」
わたしは頬を膨らませながらサインを入力した。
「よかった」
レイターが歯を見せて笑った。こわばっていた空気が一気に緩む。わたしに気を使ってくれてたんだ。
「わたしが拗ねると思った?」
「流石、俺のティリーさん、俺の考えてることがよくわかってる」
レイターの手がわたしの頭に軽く触れる。温かくて気持ちがいい。
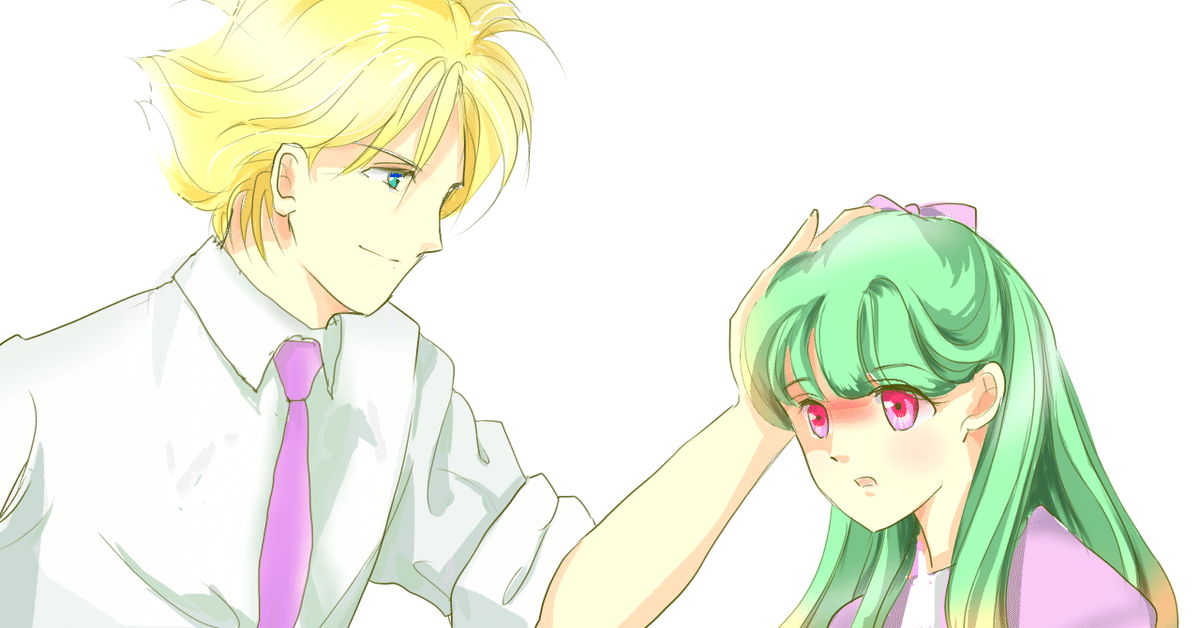
そう、わたしは、あなたの彼女で、レイターの考えてることがよくわかる。だから気がついた。
「それで、あなたはムントル社長と、どんな取引をしたわけ?」
「あん?」
レイターがギクっとしたのを、わたしは見逃さなかった。
「悪いことはしない、って約束したわよね」
わたしの愛しい人は、いたずらがバレた子どものように後ずさりながら両手を広げた。
「悪いことなんてしてねぇよ。普通の商取引さ」
「連邦軍への紹介料を取ったんでしょ」
「大丈夫。口外禁止契約にしてあるから、あんたやクロノスには迷惑かけない、三方よしってやつさ」
「そういう問題じゃないの!」
「落ち着けよ。違法なことはしてねぇよ。けど、あの親父、入札情報を流してやったらいくらでもカネ出してくれそうだな」
ニヤリと笑うレイターを見てわたしは叫んだ。
「そんなことしたら別れます!」
どうして、わたしは、わたしの神経を逆なでするような人を好きになっちゃったんだろう。幸せと苛立ちが紙一重のところに存在している。
折角下がりかけた熱が、また、上がりそうだ。
わたしは頭を抱えて再度ソファーへ倒れ込んだ。
(おしまい)<恋愛編>第六話「父の出張」へ続く
<出会い編>第一話「永世中立星の叛乱」→物語のスタート版
イラストのマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

