
銀河フェニックス物語 【出会い編】第三十八話 運命の歯車が音を立てた (まとめ読み版②)
・銀河フェニックス物語 総目次
・第三十八話 まとめ読み版①
マルグリット王妃はケント君を手招きして抱きしめた。
「怖かったわね。蹴られて痛かったでしょう。大丈夫でしたか?」
「はい、王妃さま。大丈夫です」
「あなたの命はかけがえのないものです。大切になさい」
男の子は緊張しているのか、小さな声で王妃に感謝の言葉を伝えた。
「ありがとうございます」
そしてさらに消え入りそうな声で続けた。
「王妃さま、今の人、僕をかばって撃たれたんです。価値はないと言いながら、僕の命を守ってくれたんです」
近くにいるわたしも聞き取るのがやっとの小声だった。

レイターが撃たれた? そんな風には見えなかったけれど、大丈夫だろうか。あの人は怪我をしても平気な顔で動き回る。
* *
「レイター!」
大広間の扉の外でベルが駆け寄った。
「何だか、大変なことになっちゃったわね。さすが厄病神」
レイターの腕に触れた。
「いてててて。さわんねぇでくれや」

「どうしたの?」
「レイターさん、こちらへ」
控え室の陰からフェルナンドが手招きした。
「手当てを急いだ方がいいです」
「手当て?」
ベルが不思議そうな顔をした。
控え室に入るとフェルナンドがレイターのシャツの上から冷却スプレーを吹き付けた。
「痛ってぇ」
シャツを脱いだレイターの背中から腕にかけて、真っ赤に腫れていた。「あらららら。火傷?」

「あの野郎、レーザー銃をあんな高出力にセットしやがって」
「ガードスーツがやぶれなかっただけ良かったですよ。でも、距離が近すぎましたね。耐熱機能を完全に上回ってる。とりあえず応急処置はしますが、急いで病院へ行った方がいいです」
「ちっ、ついてねぇな」
フェルナンドが手際よく薬を塗って、冷却シートを張りつける。
そこへ、そっと少年が入ってきた。ケントはレイターの前に近づくと礼儀正しく頭を下げた。
「おじさん、ありがとうございます」
「おじさんじゃねぇ。お兄さまだ」
「レイターったらめちゃくちゃよね。あなた、おなか蹴られて大丈夫だった?」
「はい。すぐ痛みがとれました」
「へぇ、あんなに吹っ飛んでたのに」
フェルナンドが説明した。
「警護武術の中にはね、相手にダメージを与えない方法もあるんだよ。とはいえ、なかなか、子どもは蹴れませんけどね」
「フン」
「お兄さん、やっぱりけがしたんですか?」
「見りゃわかるだろ」

不機嫌そうにレイターが答える。
ケントは一部始終を見ていた。オルレアがレーザー弾を発射した瞬間、彼が間に入って助けてくれたことを。
「ごめんなさい」
「何であんたが謝るんだ? 俺に謝るのはあのエセ慈善屋の野郎だ」
ケントはレイターをじっと見つめた。
「僕はお兄さんと同じことを考えてました」
「あん?」
「僕の命に価値なんてないんです。家族もいない僕は、みんなに迷惑をかけるばかりです。いくら勉強をがんばったって、さっき、あそこで殺されたところで、泣いてくれる友だちもいないんです」
廊下から少年を捜す声が聞こえてきた。
「あんた、ガキのくせに頭がいいから考えすぎなんだよ。早く帰って寝ろ」
うながすレイターの前からケントは動かなかった。レイターの瞳をじっと見つめる。自分と似た境遇の大人から何かを得たいという想いが伝わる。
レイターは小さなため息をついた。
「俺は、ガキんころ、街中の人間から死ねばいいと思われてた」
「レイターって、子どもの頃から厄病神だったわけ?」
とベル。
「そう、俺が生きてるだけでみんなが不幸になった」
レイターの声のトーンが冗談めいていない。ベルは突っ込むのをやめた。
「俺が死んだら泣いてくれる人どころか、みんな大喜びさ。ま、それでも俺を助けてくれた大人もいたから、こうして生きてるけどな。あんただって、友だちがいねぇか知らねぇが、誰かが認めたからこうやって晩餐会に来てるんだろ。そもそも命の価値って何なんだよ。誰かの役に立たなきゃ、生きてちゃいけねぇのかよ」
「レイターがさっき、犯人に言ってた話と逆じゃん」
「俺はさぁ、人質としての価値はゼロ、っつったんだ」
「わたし、レイターが死んだら泣くと思うわ」
「うれしいねぇ。ベルさん愛してるよ」
レイターが投げキスをした。
「そういうことはティリーに言いなさい。この人、変だけどいなくなったら淋しいもの」
二人のやりとりを見たケントがクスッとわらった。
「生きてりゃいいこともあるのさ。そうじゃなきゃ、俺の怪我が丸損になっちまうだろが。あんたが死んだら俺が泣いてやる、それでいいだろ」
「ありがとうございます」
ケントは頭を下げると、控室から出て行った。迷いが吹っ切れた軽い足取りになっていた。
* *
フェルナンドが救急箱を片付けていると、ベルが小声で話しかけてきた。
「ねえねぇ、フェル兄はマルグリット王妃のことが好きだったんでしょ?」
「え?」

突然のベルの質問に僕はあわてた。
「きれいだし、かっこいいし、素敵な女性だよね。フェル兄にお似合いだよ」
「ベルは何を言い出すんだ」
「だって、フェル兄、デューガ・スリーから帰ってきて引きこもってたじゃん。お父さんもおじさんも教えてくれなかったけど、失恋したんでしょ」
「さすがベルさん、好きな人のことよく見てるねぇ」
シャツを着ながらレイターさんがちゃかす。
この人は紳士協定のことを、忘れているんじゃないだろうか。
「ちょっとレイターったら、本人の前で好きな人だなんて言わないでよ」
ベルが照れてレイターさんの肩をはたいた。
「痛ててててっ。ベルさん、あんた、ガキの頃から憧れてて今も好きですってフェルナンドに言っちまえ」
レイターさんがベルをたきつける。ほんとに困った人だ。
ベルが僕の正面に立った。
そして、
「好きです! わたしとつきあって」
と、大きな声で僕に告白した。その迫力に僕は気圧された。

ベルは一つ年下の従妹で、家が隣同士の僕らは、よく一緒に遊んだ。「フェル兄のお嫁さんになる」という口癖は親戚中が知っていた。
運動が得意で、子どもの頃には僕が負けそうになるほどのお転婆だった。
性格はいい。単純なところがあるが、人の良さを裏返しているとも言える。突拍子もないことを言い出したりするが、それもまた面白い。
「私のこと嫌い?」
「嫌いなわけ無いじゃないか」
「じゃあ、好き?」
「好きだよ」
「じゃあ、お嫁さんにして」
「おいおい、いきなりプロポーズかよ」

けしかけた張本人のレイターさんがあきれた声を出した。
「わたし、せっかちだから、子どもの頃から、急いては事を仕損じる、ってよく言われた。けど、ずっとフェル兄のこと見てきたんだよ。全然、急いでないよ」
ベルのこんな真剣な表情は初めて見た。
「僕にとってベルは妹みたいなものなんだ」
「格上げして」
「格上げ?」
「ガールフレンドに」
僕は困ってしまった。ベルは押しが強い。
「伯父さんは反対すると思うよ」
「どうして?」
「僕にそんな資格は無いからさ」

一族の信頼を失墜させようとした僕を、伯父は許さないだろう。
「そんなことないよ。つき合ったらしっかり支えてやれ、ってお父さんにも言われてるもん」
「伯父さんが?」
「うん」
ベルが大きくうなずいた。
その時だった。
「キャーーー」
隣の部屋から女性の叫び声が聞こえた。何事?。僕たちは慌てて大広間へと走った。
「屋根に人が!」
広間の窓に出席者が群がって外を見ていた。
中庭を挟んで立つ迎賓館の別棟、その屋根の上を歩く人影があった。
ライトアップの照明が別棟を照らす。制服のドレスを着ていた。女官だ。あの高さから落ちたら即死だ。
「エルゴ!」
マルグリット王妃が叫びながらバルコニーへ駆け出した。人々が道を開ける。
屋根にいたのは王妃の侍女だった。先程、子どもたちに配る菓子を運んできた女性だ。
シチュエーションから察するに、飛び降り自殺をしようとしている。
おそらくレイターさんが調べているスパイ事件に関わっていたに違いない。
王妃が屋根の女性に向かって叫ぶ。
「エルゴ、どうしたというの? そこから降りてきなさい」
侍女は足を止めて王妃を冷たく見つめた。
「私の姉は、あなたの祖国、デューガ・スリー軍に殺されたのよ」
「え?」
マルグリット王妃の身体が固まった。
「王妃は何もわかっておられない。あなたが憎い」
「どういうこと?」
「これでもう、すべて終わり」
侍女の足が屋根を蹴った。身体が舞う。
「エルゴーーー!」
王妃のつんざくような叫び声が響き渡った。
*
女官のエルゴはデューガ・ワン王室に十年以上勤めていた。口数は少ないが仕事は丁寧で王室からの信頼が厚かった。
三年前、かつての敵国から嫁いできたマルグリット王妃の身の回りの世話を担当することになった。
私が仕えることになったマルグリット王妃は聡明な方でいらした。
「戦争で傷ついたデューガを癒すことが、わたくしの使命です」とよく語られた。自らの政略結婚の意味を理解されていた。

王妃は時折、懐かしそうに祖国デューガ・スリーの話をした。
王妃個人に恨みはない。
だが、大好きだった私の姉は十六歳の若さでデューガ・スリー軍に殺された。私の目の前で。何の武器も持たない市民への無差別攻撃。
二十年以上前のことだ。
日常の何気ない破裂音。
それはパンの袋が開く瞬間といったささいなこと。
それが、今も私の神経を逆なでる。
砲撃の音と共に、顔が半分吹き飛んだ姉の姿が、昨日のことのように瞼に浮かびあがる。たまたま姉が盾となって私は生き延びた。
どうしてデューガ・スリーを許すことができようか。
戦争で傷ついた私の心はそんな簡単には癒されない。この星には私のような者がたくさんいる。裏通りを歩けば、足の無い者、手の無い者が物乞いをして生きている。
所詮、若いマルグリット王妃は戦争の現実をご存じないのだ。王妃が語っているのは絵空事だ。
デューガ・スリー出身の王妃に仕えれば仕えるほど、亡くなった姉に申し訳ないという気持ちが募った。
そんな心の闇に、アリオロンはつけこんだ。
「デューガ・スリーに復讐ができる」と。
作業は簡単だ。
マルグリット王妃が子どもたちへ配る菓子の箱の中に、情報チップを入れるだけ。それをオルレアという情報屋が回収する。
王妃は私を信頼し無防備にパスワードをさらしていた。掃除の際でもいつでも、機密は簡単に抜き取れた。
よもや、王妃から情報が洩れているとは誰も疑わない。
きょうもいつもと同じようにお菓子の箱を用意した。情報チップが王妃の手からオルレアに渡ったのを見て私は女官室へ戻った。
少しして騒がしくなった。オルレアが逮捕されたという話が聞こえてきた。来るべき時が来た。
私は裏切り行為を始めた時から、ずっとこの日が来ることを覚悟していた。
「特命諜報部です。お話を聞かせてください」
連邦軍が女官室へやってきた。
私は奥のドアから走って逃げた。
わかっている、逃げる場所などどこにもない。
屋根に上った。
発覚したら死ぬと決めていた。私のしたことは敬愛するデューガ・ワン王室に迷惑をかけた。死してお詫びする。
「エルゴ!」
マルグリット王妃の声が聞こえた。
「エルゴ、どうしたというの? そこから降りてきなさい」
王妃はベランダから私を見つめていた。何も知らない王妃。腹立たしいにもほどがある。
ずっと投げつけたかった言葉をぶつけた
「私の姉は、あなたの祖国デューガ・スリー軍に殺されたのよ。王妃は何もわかっておられない。あなたが憎い」
「どういうこと?」
目を見開いて固まった王妃の顔を見たとき、私は復讐を果たしたと感じた。
もう、満足だ。
「これでもう、すべて終わり」
姉さん、あなたのもとへいきます。
私は屋根を蹴った。
体が宙に浮き、落下した。
その直後、衝撃が走った。
何かが私の身体を引っ張り支えた。
命綱にぶらさがった男性が私を抱えていた。
「放して、私をここで殺して!」
暴れる私を男性ががっしりと抱きしめた。身体が空中でぶらぶらと揺れる。
男性の静かな声が耳元で聞こえる。
「あなたの復讐は終わりました。これ以上、デューガ戦争の被害者を出してはなりません。あなたの命は、誰に守られたものですか? ご令姉が、あなたの死を望んでいるとは思えません」
なぜだろう、荒ぶる嵐が台風の目の中に入ったように静まり返っていく。
本当は、私はずっと、王妃に知ってもらいたかったのだ。
姉のことを。私の苦悩を。姉が殺されて、なぜ、私は生き残ってしまったのか。誰にも伝えられなくて、心が歪んで、苦しかった。
私を抱える男性の横顔に見覚えがある。長髪を束ねた連邦軍人。

この男性は連邦軍将軍家の嫡男で次期将軍。アーサー・トライムス少佐だ。
巨大な力を前に、私の身体から力が抜けていくのを感じた。
* *
国王夫妻は大広間からいったん奥の御休憩処に移動した。
マルグリット王妃は倒れ込むようにソファーに腰かけた。
部屋には二人だけだ。国王はお付きの者も入れなかった。
国王がゆっくりと王妃の隣に座った。
「マルグリット、大丈夫か。きょうの晩餐会はここまでにいたそう」
夫妻の会話が盗聴器を通じて控室のフェルナンドの耳に聞こえた。
「殿、ご心配をおかけしてすみません。そうですわね。デザートはお持ち帰りにさせましょう」
気丈な姫。三年前と変わっていない。目に浮かぶようだ。

どんな時でも朗らかであることを求められ、それに応えていた。
彼女が力を入れてきた慈善事業が悪用され、信頼していた侍女に裏切られた。そして、その侍女の姉は祖国のデューガ・スリー軍に殺されていた。
王妃は傷ついているであろうに、その姿を決して他人には見せない。
*
昔からそうだった。
繊細な心を虚勢で覆う、明るく強がりな姫。あの頃、彼女は僕にだけその弱さを見せた。
姫は僕の胸で泣きじゃくった。

「運命は自分で切り開きたいの。生まれた時に決められた人のところへなぞ嫁ぎたくない。九つも上の殿なのよ。無口で何を考えているのかわからない、あんな人のところへなんて・・・」
姫を警護するのが僕の仕事。
僕は弱き姫をすべてのものから守りたかった。細い身体を抱きしめながら、どんな難題でも姫のためなら完遂できると信じていた。
*
レイターさんが王妃に取り付けた盗聴器の性能は優秀だ。国王陛下の声がかすかに震えていることまで聞き取れる。
「マルグリット、すまなかった。エルゴがあのような思いを抱えていたとは知らなかった」
「謝らないでくださいませ。私のせいです。デューガ・スリー軍に家族を殺されたとあっては私を憎むのも仕方なき事」

「そなたの生まれる前の話だ。そなたのせいではない」
寡黙な国王が強い口調で否定した。その声は王妃への愛があふれていた。
「すべての憎しみと、過去の過ちを乗り越えるために、我らはここにいるのであろう」
敵国の姫に対するデューガ・ワン国民の視線は温かいものではなかった。それを姫は持ち前の明朗さで乗り越えようとし、国王がそれを支えている。
「そうでございました。憎むことを仕方なきなどと口にして、申し訳ございませんでした。この星系から憎しみの連鎖を断ち切ることを、あなたさまと二人でお誓いしましたのに」
王妃の凛とした声。
僕の知らない姫がそこにいた。
泣いていた姫とは違う。
強がって明るくふるまっているのではない。穏やかなのに強靭。
「まだまだ、我々にはやらねばならぬことがあるということだ」
「そのとおりでございますわね、殿」
虚勢ではない。前へ進もうという決意が伝わる王妃の声。
王と王妃。二人の心が通じ合っているのがわかる。無口な王は思慮深い方であられた。デューガの平和と安寧に向けてご夫妻は歩んでおられる。
政略によって結ばれた王子と姫。
二人は、お互いを愛と理想で支え合い、立派な王と王妃になられたのだ。
姫はご自分で運命を切り開かれた。
貴女の隣にふさわしい伴侶がいる。僕は心から祝福いたします。
王妃、貴女の言う通りです「恋は素敵で人生を豊かにする」。一度はすべてを失くした僕だけれど、貴女と恋した日々を後悔していません。
感謝申し上げます。
僕は隣にいたベルの顔を見た。
自分でも信じられないほど自然に言葉が口から出てきた。
「おつきあいしようか」
「え? えっ? どうして? どうして?」
ベルは自分から告白したことを忘れているのだろうか。
目を大きくして詰め寄ってくる。ま、ベルらしくていいけれど。

妹のようなベル。
僕が引きこもった時、学校へ出かける前に毎朝ドアの外から声をかけてきた。「顔を見せて」と。
うっとうしく感じた僕はずっと無視していた。
引きこもりから抜け出した後に気がついた。成績優秀でも何でもない最低な僕に、会いたいと言い続けたベルの言葉が自分を支えていたことに。
僕にとってベルは大切な存在だ。けれど、深入りすることは避けていた。
僕が皇宮警備を辞めた時、一番厳しかったのは連邦保安官のベルの父だ。伯父は一族の恥さらしである僕のことを許さないだろうと、ずっと思っていた。
その伯父が僕を見守っていてくれた。ベルと一緒に。
僕は新たな一歩を踏み出したくなった。
「ベルのことが好きだからさ」
僕は、ベルの唇にそっと大人のキスをした。
ヒュー、ヒュー。

レイターさんが、僕たちを品のないひやかしで祝福した。
* *
晩餐会の出席者にデザートが手土産として配られ、会はお開きとなった。
エースとティリーを乗せたフェルナンドのプレジデント号はそのままソラ系へ向けて帰途についた。
ベルとレイターはクロノスの現地法人へ戻り、残務処理を片付けてからデューガを後にした。
レイターはフェニックス号を自動操縦に切り替えると、居間のソファーに腰かけた。
ふぅ。火傷した背中が痛くて、背もたれにもたれらんねぇ。誰だよ、危険のない任務だって言った奴は。治療費ぼったくってやる。
ベルさんが向かいに座ってテレビのニュースを見ている。デューガ王室を巻き込んだ情報流失事件を報じていた。
「最後の最後で厄病神が出てきたね」
マルグリット王妃は善意の第三者だった。情報屋のオルレアに機密を横流ししていたのは侍女のエルゴ。その身柄は、アーサーが確保した。

「っつっても、ベルさんの仕事にゃ影響なかったし、プライベートも充実して、いい出張だったじゃん」
「あはは、レイターのおかげだよ。怪我は大丈夫なの?」
「平気平気。あとはほとんど自動操縦だしな」
「それならいいんだけど」
ベルさんは素直でいい子だ。ティリーさんだったらこれでは終わらないで突っ込んでくる。
と、思ったところへ通信が入った。スーツ姿のティリーさんがモニターに映る。
「レイター。怪我したんですって」
「平気平気」
「平気なわけないでしょ。やけどで重症だってフェルナンドさんから聞いたのよ」
「あんた、フェルナンドと俺のどっち信用すんだよ」
「フェルナンドさん」
ティリーさんの返事にいらついた。
「へぇ、そおかい、そおかい」
「だって、レイター、熱っぽい顔してる」
「あん? 俺が?」
「目が充血してるじゃないの」
確かに熱はあるが、顔に出てるとは思わなかった。
「ティリーさんの麗しいドレス姿に見とれたからだろ」
「からかわないで!」
よく似合っていた赤いキラ・センダードのドレス。

「エースの隣で楽しそうだったじゃん。もしかしてティリーさん、俺のこと心配になっちゃった?」
俺がおどけるとティリーさんがふくれっ面した。
「誰が心配なんてするものですか。仕事がちゃんと進んでいるか確認したかっただけです」
ベルさんが手を叩いて話に割り込んできた。
「はいはい、そこまで。ティリー聞いて、わたし、フェル兄とつきあうことにしたから」
「え? えええっ? いつの間に。フェルナンドさんはそんなこと一言も言ってなかったわよ」

ティリーさんの大きな目が一層大きくなった。
「ほほほ、できる女は仕事も私生活も充実しているのよ」
勝ち誇ったようにベルさんが笑い、楽しげな女子トークが始まった。
俺はほとんど知っているベルさんののろけ話を、ソファーに腰かけてぼーっと聞いていた。
「今回、レイターが背中を押してくれたんだ。ありがと」
ベルさんが俺に幸せそうな笑顔を向けた。

「どういたしまして」
フェルナンドも俺に感謝しろよ。
「実は、デューガの王妃さまが、フェル兄の元カノだったんだよ」
「え、ええっ?! そんな素振りまるでなかったのに・・・」
ティリーさんがびっくりする様子は見てて飽きない。かわいい。
「ねえ、ティリー。わたし、たとえフェル兄がデューガの王妃のことを忘れられなかったとしても、つきあうことに後悔しないよ。全部を清算しなくても恋はできるもの」
ベルさんが力説する。
フローラを忘れられねぇ俺への当てつけにも聞こえる。

ベルさんの考え方を否定はしねぇ。でも、自分にはできねぇ。
「フェル兄が人殺しでも、わたし構わないし」
のろけすぎだろ。
「だからティリー、レイターとつきあいなよ」
おいおい。話が変な方向に流れてるぞ。
ティリーさんが間違って、俺とつきあいたいなんて言い出したらまずい。
俺はベルさんとモニターの向こうのティリーさんに釘を刺した。
「俺はティリーさんとつきあうつもりはねぇよ。自由でいたいんだ」

軽い調子で伝えたが、恋バナトークのテンションは一気に下がった。
「おやすみ、また会社でね」
ティリーさんの小さな声がしてモニターの映像が消えた。
ベルさんが俺の前に立った。右手が動く。
さっきも、王妃にはたかれたな。
と思ったら、ベルさんは俺の額に手を当てた。ひんやりして気持ちいい。
「フェル兄の言うとおりだ、熱があるじゃん」
「クライアントに心配かけてちゃ、ボディガード失格だな」
「ほんとに心配だよ。ティリーのこと好きなくせに、なんで意地張るの。バカじゃないの」
「バカなんだろ」
って話してたら、身体が急にフラフラしてきた。やべぇな。
「ベルさん、悪りぃが、俺、ちょっと横になる」

ソファーへうつ伏せに倒れ込んだ。背中のやけどが熱を持ってる。少し休もう。
そして、俺はそのまま眠りこんだ。
* *
ティリーは船室のベッドに腰かけたまま、何も映っていないモニターを、ぼーっと見つめていた。
レイターの声が遠くに聞こえる。
「俺はティリーさんとつきあうつもりはねぇよ。自由でいたいんだ」
わたしは振られたんだ。
振られた?
いや、告白してないし。
どういう意味だろう? わかってる。文字通りだ。
レイターはわたしとつきあうより、一人でいる方がいい、ってことだ。
わかっていたことだ。
レイターは特定の彼女を作らない主義なのだ。
状況は何一つ変わっていない。

なのに、どうして涙が止まらないんだろう。
いつのまにか眠ってしまったようだ。昨日のスーツを着たままだった。メイクも落としていない。
ベッドのわきに置いた携帯通信機がブルブルと振動している。
通信機の画面を見て驚いた。メッセージが次々届いている。
クロノスの同僚、アンタレスの友だち・・・。何か変だ。
『この記事は本当?』
似たようなタイトルが並んでいる。張り付けてあった記事を開く。
《 熱愛発覚! 無敗の貴公子のお相手は美人秘書!?》
大きな見出しが目に入った。
え? な、何これ?
記事にはデューガの晩餐会で、エースと一緒にひな壇に並んで笑っている写真が掲載されていた。
わたしの顔には加工がしてあった。けれど、知っている人なら誰が見てもわたしだとわかる。

~関係者によると、デューガ星系で開かれた晩餐会の席で、S1人気レーサーで『無敗の貴公子』の異名をとるクロノス社のエース・ギリアム専務は秘書のAさんに結婚を前提に交際を申し込んだことを明らかにした。Aさんは「専務が大好きです」と応じていたという。この日、会場へ姿を見せた二人は終始笑顔でいい雰囲気だった。Aさんが着ているキラ・センダードのドレスもエースが用意したものだという。Aさんは学生時代から無敗の貴公子のファンで、それがクロノス社の入社理由だというのは社内では知られた話だ。去年のS1プライムでエースの付き人を担当したのが縁で、秘書室に引っ張られ、エースのスケジュールを管理するのが仕事だという。プライベートを管理するのも時間の問題だろう。まさにシンデレラストーリーの展開に目が離せない。~
驚いて言葉もでない。
「・・・・・・」
多数のメッセージは真偽の確認を求めるものだった。
どうしよう・・・。
エース専務に報告しないわけにはいかない。
あわてて服を着替え、乱れた髪の毛を縛り直す。
少し目が腫れてる。メイクでごまかしプレジデント号の中央船室へ向かった。
フェルナンドさんがいた。
「専務は起きていらっしゃいますか?」
「ええ、深夜にスポーツ紙の早刷りが出たという連絡がきましたからね。専務の部屋へ行きましょう」

すでに夜からこの話は出回っていたのだ。
普段着のシャツを着たエースは、いつもと変わらず落ち着いていた。
「おはようティリー、すまないね。騒がせてしまって」
エースがわたしに謝った。
「い、いえ」
どういう反応をしていいのかわからない。
確かにそもそもの原因はエースのせいだ。予定になかった晩餐会への出席をわたしに求めたせいだ。けれど、あれは業務の一環で、エースが悪い訳ではない。
しかも、記事のほとんどに嘘がない。
「この件について、すでに広報のコーデリアと連絡を取っている。きょうの夕方に本社で記者会見をすることにした」

わたしの頭がついていかない。知らない間に話が大ごとになっている。
「そんな顔をしないで。会見の内容は、S1の最終戦についてだ」
「え?」
S1最終戦の会見は来週を予定していた。そこでエースが今シーズンでの引退を発表する段取りを極秘に進めていた。
「最後のS1を前に、プライベートでうるさくされるのは避けたいからね。きょうの会見で、S1を引退し経営に専念することを発表する。そして、僕が君に交際を申し込んだことを認める」
胸がドキンと音を立てた。
逃げられない。
エースがわたしに交際を申し込んだ、と世の中に発表したら、わたしはどうやって断ればいいのだろう。
断る? わたしは断るつもりなのだろうか? 憧れの推しである無敗の貴公子の申し出を・・・。
宇宙船見本市のSSショーに出張した際、エースからつきあって欲しいと告白された。申し訳ないことに、わたしはそれをずっと放置してきた。
「ティリー、君はレイターが好きなんだね」
「え?」
「彼をかばって、マルグリット王妃に意見する君を見て思った」

意味が分からない。
エースはわたしがレイターのことを好きだとわかっているのに、交際を申し込むと言う。
「だが、レイターは特定の人とはつきあわないと宣言している。おそらく彼は彼女を作らず、一生独身で通すつもりだ」
エースの言う通りだ。
わたしが、レイターの彼女としてつきあうことはない。まさに昨晩、振られたばかりなのだ。
「僕は違う。好きな人を幸せにしたい」

エースがわたしを真剣な表情で見つめた。
「君は僕を『無敗の貴公子』としか見ていない。僕をエース・ギリアムとして見てくれないかい」
鋭い指摘にドキッとした。
エースの言うとおりだ。
わたしにとって専務はあくまで推しなのだ。
仕事すらわたしにとっては無敗の貴公子の推し活の延長のようなものだ。
エースはそのことに気づいている。
「僕は君の前で誓うよ。僕は他人の気持ちがわからないところがあるが、人の気持ちを理解したいと思っている。もし、君に嫌な思いをさせていたら、遠慮なく言ってくれ」
現実のエースには上から目線なところがある。受け取る側の気持ちを深く考えずにボールを投げてくる。けれど、推しだから許せた。
エースの本気が伝わってくる。嫌いなところがあればあらためる、だからつきあって欲しいと。
一人の男性としてエースがわたしの前に立っていた。
胸がしめつけられて苦しい。
わたしはレイターのことが好きだ。

けれど、レイターははっきりと断言した。「ティリーさんとつきあうつもりはねぇよ」と。
あの時、レイターはわたしを牽制した。わたしがベルにあおられて告白するかもしれないという空気を察して、先手を打って断ったのだ。
わたしは失恋したんだ。
エースの申し出を断る理由はどこにもない。
きのうからいろいろなことがありすぎて、わたしの脳は判断するということを拒否している。考えることが面倒で投げやりになっていた。
事態を先送りたい。
「お友だちから始めてもいいでしょうか」

「友だちか・・・。それもいいかも知れないね、まずは、友人としてデートをしよう」
エースが白い歯を見せて笑った。わたしにはもったいない、素敵な笑顔だった。
「会見でわたしに交際を申し込んだ話をするのは、止めてもらえませんでしょうか」
心の準備ができていないのに、外堀が埋められていくのが怖い。
エースは困った顔をして首を傾けた。
「それは難しいな、あの交際記事については、はっきりさせておく必要がある。だが、あくまで君は一般社員だ。名前も出さないし、メディアが追いかけることの無いようにきちんと要請するよ。だから、きょうの会見に出る必要もない」
*
エースの記者会見が始まる。
わたしは本社の最上階にある専務室の前で、自席のモニターをつけた。エースが不在の今、訪れる客もいない。
広報のコーデリア課長に先導されてエースが本社別棟の会見場に入る。

カメラのフラッシュが一斉にたかれた。記者席は満席だ。画面の端にフェルナンドさんが静かに立っていた。
朝から問い合わせの嵐で、広報とお客様センターの電話は鳴りっぱなしだったそうだ。
エースがカメラの前に立った。
「本日はお集まりいただきありがとうございます。私から一言申し上げます。私エース・ギリアムは、今シーズンのS1で引退します。次の最終戦が僕の最後のレースです」
会場がどよめいた。
集まった記者は、エースの恋愛記事を確認しようと来ていた。けれど、それ以上のトップ級のニュースが飛び出した。
「どうして引退の決断を?」
記者から質問が飛ぶ。
「僕はクロノス社の専務です。経営に軸足を移すこと、これはもう以前から考えていました」
「今回、恋愛に関する記事が出たことと関係はあるのですか?」
「皆さまにご報告するいいタイミングだと考え、会見を設定しました」
「恋愛の記事については認めるんですか?」
わたしは耳をふさぎたくなった。
想定問答集には「秘書に告白し、回答を待っている」と書かれていた。
エースとわたしは対等じゃない。
もちろんわたしには、エースの告白を断る自由がある。けれど、推しであり、有名人であり、大企業の役員であるエースからの告白。それが銀河中に公表される。
その圧力に胃の奥がぎゅっと締め付けられて吐きそうだ。
社会的にも精神的にも、もう逃げられない。
エースは静かな抑制のきいた声で答えた。
「彼女とは、いいおつきあいをさせていただいています」

想定とは異なる回答。
正答でも誤答でもない。あいまいさを含んだ表現。「いいおつきあい」には友だち関係も含まれる。
「どちらから告白されたんですか?」
嫌な質問だ。つきあっていることが前提の質問。
「これ以上はノーコメントです。あまり騒ぎ立てないでいただきたい。S1の最終戦まで、うつつを抜かしている暇はありませんので。僕は、無敗を守り切りますから」
思わず画面に見とれる。「無敗を守り切る」と力強く言い切る推しは最高に格好良い。
ダメだ。推しという言葉は封印しなくては。友人に使う言葉じゃない。
* *
会見が終わった。
本社のメイン棟へ戻るエースを、フェルナンドは警護しながら歩いていた。
「フェルナンド、どうだった?」
人がいなくなった廊下で、専務は振り向いて僕にたずねた。
「流石です」
僕は頭を下げた。子どもの頃からマスコミ慣れしているとはいえ、長時間の会見を終えて疲れた様子を見せない。専務は強い精神力をお持ちだ。
「ティリーはどう思ったかな」
専務のつぶやきは質問とも受け取れた。けれど、僕は答えなかった。それはティリーさん本人に聞くべき問いだ。
*
僕は、記者会見の前にエース専務に進言した。
「一言申し上げてよろしいでしょうか?」
「フェルナンド、珍しいな」
普段、専務の仕事に口を挟むことはない。けれど、言わずにはいられなかった。
「専務から告白したことを正直に会見で伝えるのは、お控えいただいた方がよろしいかと」
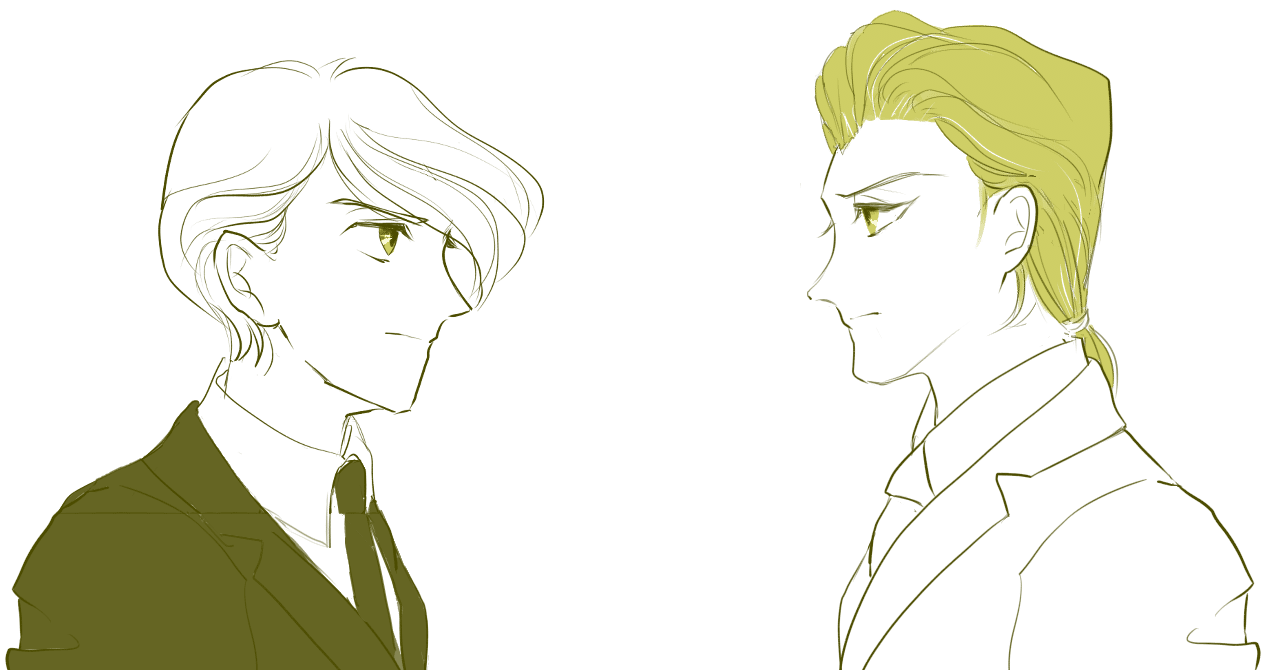
「それは、ティリーが嫌がっているからかい?」
「恋愛はビジネスではありません。ティリーさんの逃げ道を塞いで、追い込まれるのはいかがかでしょうか」
「僕の告白を断るための、逃げ道を作っておけということかい」
専務は頭がいい。
「人の気持ちを理解したいとおっしゃった専務なら、ティリーさんの不安がお分かりになるはずです」
「ふむ、フェルナンド。君はどこで覚えた、恋愛の機微を?」
専務は探るように僕を見つめた。
一瞬の沈黙を経て、僕は素直に口にすることができた。
「過去には辛い恋もしましたので」
「そうか、わかった」
僕は小さく息を吐いた。
レイターさんのために僕にできることは、ここまでだ。
*
人が出払った控室で待機していると、腕につけた携帯通信機が反応した。
ベルからだった。
五センチ四方の空中ディスプレイを左手首の上に立ち上げる。
「フェル兄、ティリーに通信がつながらないんだけど、専務の会見は一体どういうことなの?」
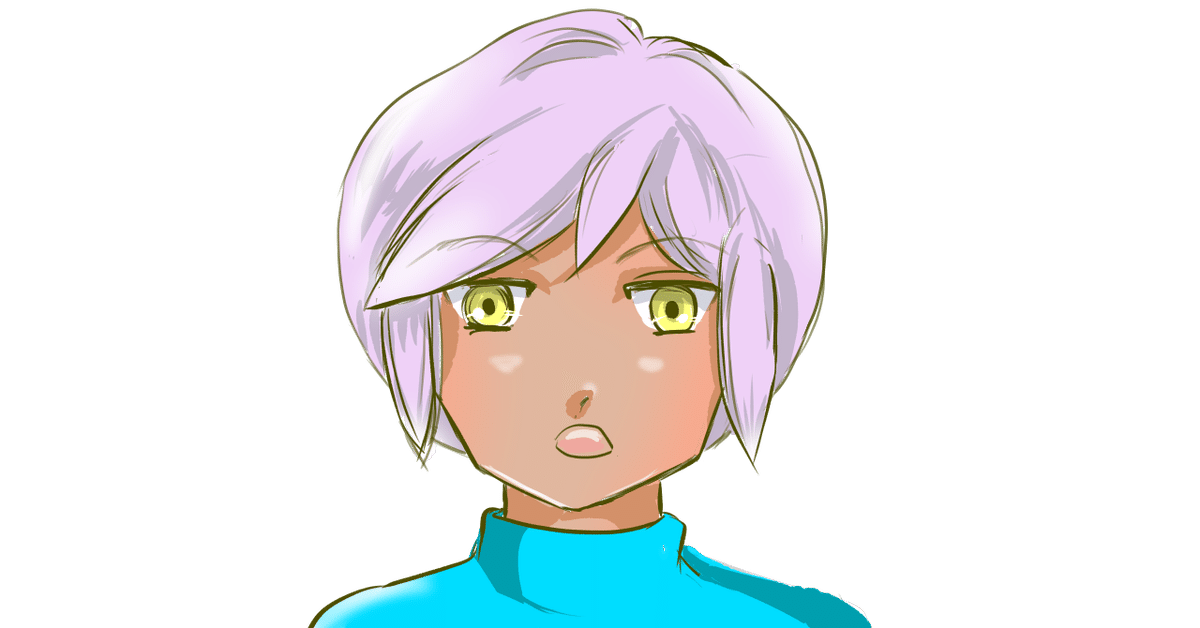
興奮した様子のベルを僕ははぐらかしてみた。
「S1引退のことかい?」
「ちがーう。恋の話だよ。どうして専務とティリーがつきあうことになってるの? 昨日レイターが、ティリーとつきあう気はない、なんて口にしたから?」
僕は少なからず驚いた。
「レイターさんが、ティリーさんに言ったのかい?」
「そうだよ、本心じゃないくせに」
けさ、ティリーさんの目が腫れていたことを思い出した。
もう、レイターさんは限界なのだろう。ティリーさんのことを愛しすぎて。
「レイターさんは、どうしてるんだい?」

「何も知らずに眠ってるよ」
「眠っている? けがの具合が悪いのかい?」
「この船、変なんだよね。レイターがソファーで寝っ転がったところで、マザーが勝手にレイターを治療カプセルに入れちゃったんだ。マザーは三日ぐらい湿潤薬液の中で眠らせる、って言ってるから、しばらく起きてこないと思う」
「それが、一番回復が速いからね」
「レイターは、目を覚ましたらびっくりするだろうな。もう俺のティリーさん、なんて呼べないよ。次期社長の彼女だよ」
だから二人は、早くつきあってしまえばよかったのに。

運命は思わぬ方向に転がりだす。
「レイターさんが眠っていて、ベルは困っていないかい?」
「この船、すごいんだよ。マザーが全部やってくれるから、自宅にいるより全然楽で、わたしこの船で暮らしたいな」
フェニックス号はレイターさんの自宅だ。
「ベル、わかってるかい? 君は僕とつきあうことにしたんだよ」
「あははは、フェル兄妬いてる? うれしいな」
ベルののんきな笑顔が、僕の落ち着かない気持ちを和らげた。
* *
ティリーはニュースを見ながらため息をついた。
結局、どの記事を見ても、秘書のAさん、すなわちわたしはエースの彼女、ということになっていた。
『無敗の貴公子の彼女』というワードが情報ネットワークのトレンドに浮上した。心無い書き込みもあった。「ブス」「死ね」と言われても困ってしまう。否定的なコメントは見ないようにした。
ファンのサイトも荒れていた。
そこには『推しの卒業』にどう対処して、これからの人生を生きていくか、という悲痛な叫びが溢れ「わたしの分まで彼女さんと幸せになってください」という祝福のメッセージが大量に投稿されていた。
『無敗の貴公子の彼女』とは、ファンにとって何と魅惑的な響きだろうか。エースは訂正するつもりはないらしい。

このつきあっていると誤解を与える回答は、実によく考えられていた。
もし、エースが会見で「告白の回答を待っている状態」とか「二人は友人関係」と正直に答えていたら、その後も詮索され続けた恐れがあった。
一方で、つきあっているとなれば、単なる社内恋愛、というくくりになって世間の興味は持続しなかった。
とりあえず、ベルとチャムールにだけ本当のことを伝えた。
* *
「アーサーを呼べ」
将軍執務室へアーサーが入ると、父親のジャック・トライムス将軍は人払いをした。

ペーパータブレットを取り出し机の上に広げた。
「おい、アーサー。これは一体どういうことだ? ティリーさんがエースとつきあうということは、レイターは失恋したのか?」
『無敗の貴公子、今シーズンで引退。美人秘書との熱愛発覚』の見出しが大きく躍っている。
「条件から考えてエースは圧倒的に有利です」
「そんなことはわかっとる。お前、よく落ち着いているな」
「チャムールによれば、二人はそこまでの深い関係ではないようです」
「そうなのか?!」
「ただ、レイターはティリーさんとはつきあわない、と本人に伝えたそうです。フローラを理由として」

「何だと! あいつは馬鹿か。レイターがフローラを今も愛してくれていることはありがたく思っとる。だが、あいつがティリーさんに惚れとることもわかっとるんだ」
アーサーがうなづいた。
「このままではあいつは一生フローラの呪縛からのがれられん。それはフローラの遺志に反することだ」
「父上、レイターが特定の彼女を作らないのはフローラの件だけではありません」
「ふむ」
「ティリーさんに話せないことを抱えすぎていますから」
連邦軍の特命諜報部員。しかも暗殺協定の対象者。
「フローラの時には問題にもならんかったが、相手が一般人となるとそうもいかんな」
「レイターは秘密を抱えた恋にトラウマがあります。隠し事をしてつきあうことは恋愛対象者に対する裏切り行為だと」
「そうだったな・・・」
ジャック将軍は額に手をあてて、深いため息をついた。
娘のフローラは自分の命が残されていないことを結婚相手のレイターに対して秘密にすることを望み、将軍は隠し通した。

フローラの死の間際にその事実を知ったレイターは、自分が信用されていなかったと深く傷つき、将軍に対し「恨まずにいられねぇ」とつっかかった。
あの時の絶望に満ちた声は、今も将軍の耳に残っている。
父親の感情が落ち着くのを待って、アーサーは発言した。
「ですので、その足かせの一つをはずしたいと考えております。服務違反をお許しください」
「何をする気だ?」
「タイミングを見てティリーさんに明かします。レイターが連邦軍の特命諜報部員であることを」
「・・・それは、冗談か?」
「冗談ではありません」
「お、お前。そんなことをしたら、レイターに殺されるぞ」
* *
ティリーは、専務室から出てきたエースに声をかけられた。
「きょうの仕事はこれで終わりだ。今から練習コースで飛ばそうと思うんだが、よかったら僕の助手席に乗ってくれないか。友人として」
「は、はい」
期待と緊張でわたしの胸の鼓動が高まった。何百回と映像で見てきた無敗の貴公子の助手席に座るのは初めてだ。
「専務が操縦する船に乗れるなんて光栄です」

「友だちだろ、専務はやめてくれ」
「そうでした」
エースが愛機のプラッタをスタートさせる。
当たり前だけれど上手い。スムーズに加速していく。
左利きのエース。
『無敗の貴公子』として見ないでほしいと言われたけれど、操縦するエースはわたしの憧れだ。
ちらりと横を見る。かっこいい。ときめきが抑えられない。
レイターとは違う。より丁寧な感じ。コンパクトで安定した飛ばし。
「ティリーはジェットコースターが好きなんだって?」
「はい」
「少し飛ばすよ」
そう言って模擬小惑星帯へと入っていった。
エースの操縦は銀河最速だ。
ぶつかりそうな小惑星のわきをギリギリのラインで通り抜ける。ジェットコースターより迫力がある。
神業だ。その操縦桿捌きに見とれて興奮する。
でも違う。
同じ高速の飛ばしなのに違う。
比べてしまう。
エースは公道を飛ばすことも、飛ばし屋とバトルをすることもない。
思い出してしまう。
レイターと一緒にアステロイドで白魔と戦った時に感じた幸福感を。

『あの感覚』をもう一度味わいたい。
けれど、もうその時はこないのだ。
カチリと次の歯車が噛み合う音がした。 (おしまい)
第三十九話「決別の儀式」へ行く前に、<ハイスクール編>「花は咲き、花は散る」へ
・第一話からの連載をまとめたマガジン
・イラスト集のマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

