
銀河フェニックス物語【少年編】第十三話 銀行までお出かけしたら(まとめ読み版)
戦艦アレクサンドリア号、通称アレックの艦。
銀河連邦軍のどの艦隊にも所属しないこの艦は、要請があれば前線のどこへでも出かけていく。いわゆる遊軍。お呼びがかからない時には、ゆるゆると領空内をパトロールしていた。
地方星系で買い出しを終え、アレクサンドリア号へ戻ろうとした時だった。
「ちょっくらカネ、チャージしてくる」
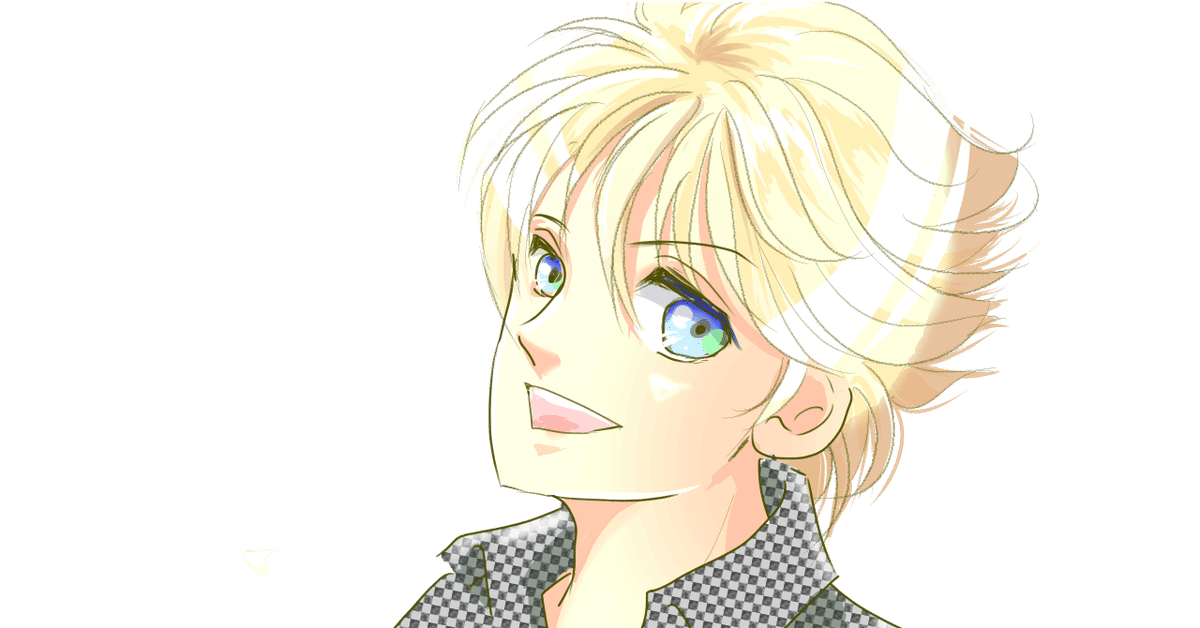
とレイターは銀行の看板を指差して走り出した。
そのままレイターは艦が出航する五分前になっても、帰ってこなかった。
この惑星にはエネルギー補給のため立ち寄っただけで、短時間で出発することはあいつもわかっていたはずだ。
出発の準備に追われる中、乗組員の多くはレイターが戻っていないことに気づいていた。密航者が帰って来ないから、といって出発の時間を遅らせるわけにはいかない。
あいつ、何やってるんだ。腕につけた通信機を押す指に力が入る。料理長のザブリートさんが心配げに僕に近づいてきた。
「どうだ? つながったか?」
「いえ、通信圏外です」

「どこ行ったんだ、まったく」
「銀行へ行くと言っていましたが」
「ふむ、きのう今月分のバイト代を振り込んだところだからな」
大した額ではないが、今、彼は一文無しというわけではない。
「事故にでもあってるんじゃないのか?」
「自分で通信機を切っているかもしれません。彼にはこの艦に戻る義務はありませんから」
そうだ、レイターは密航者だ。戻る義務どころか、ここにいてはいけない存在なのだ。
僕は出航の任務に集中しようとつとめて意識した。
認めたくないが、僕の平常心が揺れているのがわかる。揺れた段階でそれはもはや平常心ではない。
彼がこの艦に乗っていることは、僕には何のメリットもない。一方で、デメリットは次から次へと浮かぶ。彼がいなければ部屋も汚れない。自分の時間を無駄に取られることもない。彼がいなくなっても何の問題もない、むしろ状況は好転するはずだ。ましてや『お友だち』でも何でもない。
なのになぜ、かき乱されるのか。
まさにタラップを引き上げようとした時、彼は息を切らし走って帰ってきた。
みんなが目と目で合図しあう。艦内に安堵の空気が流れた。何も言わないがアレック艦長の口元も笑っている。

そして、何事も無かったかのようにアレクサンドリア号は出航した。
*
勤務を終えて自室へ戻ると、うっすらと鉄のにおいが僕の鼻を刺激した。
二段ベッドの階段に足をかけて上の段をのぞいてみる。レイターは苦し気にうずくまっていた。血の気のない額に脂汗をかいている。
シャツに赤い染みがついている。めくると、わき腹に貼られた止血シートが赤く染まっていた。自分で張ったのか。結構出血している。
「ドジったぜ」
目を閉じたまま、悔しそうな声で言った。人に心配させておいてこいつは一体何をしていたんだ。
「医務室へ行くか?」
いらだった声でたずねると彼は無言で首を横に振った。
居候の彼は艦に迷惑を掛けて追い出されることを恐れている。
僕は静かに止血シートの端をはがした。
「うっ痛ぅ」
傷の状況を観察する。レーザー弾がかすってできた傷だ。銃創ということは何らかのトラブルを起こしたということだ。
マフィアに狙われたのだろうか?
マフィアを牛耳る『裏社会の帝王』ダグ・グレゴリーはレイターに十億リルという多額の懸賞金を懸け、お触れである『緋の回状』を回した。

それを機に第三次裏社会抗争が勃発し、レイターは巻き添えになって死亡したことになっている。その時点で『緋の回状』の効力は消えたが、レイターが生きていることがわかれば、マフィアが再度狙う恐れはある。
「一体、何をしたんだ?」
「チャージ、っつったろ……」

絞り出すように答えるとレイターは意識を失った。なぜ隠す。銀行で撃たれたとでも主張するつもりか。
裏社会から狙われているレイターの身柄を匿うことは、こちらは負う必要のないリスクを抱えているということだ。トラブルに正しく対処するためには正確な情報が必要だというのに。
振り回される自分が馬鹿馬鹿しく、いらだった感情が塗り重なっていく。 レイターが艦に帰ってこなければ全ては丸く収まったのだ。彼がどこで何をしようと僕には関係ない。ゆっくりと息を吐く。
だが、帰ってきてしまったからには放っておくわけにいかない。僕は彼の教育係だ。
内線で医療兵のジェームズ少尉に連絡をいれた。
「ジェームズ。お手数かけますが、他の人に見つからないように野外戦闘用の救急パックを僕の部屋へもってきてもらえませんか?」
ジェームズは部屋に入るなり声をかけた。
「レイター、怪我したのか? 大丈夫かい?」
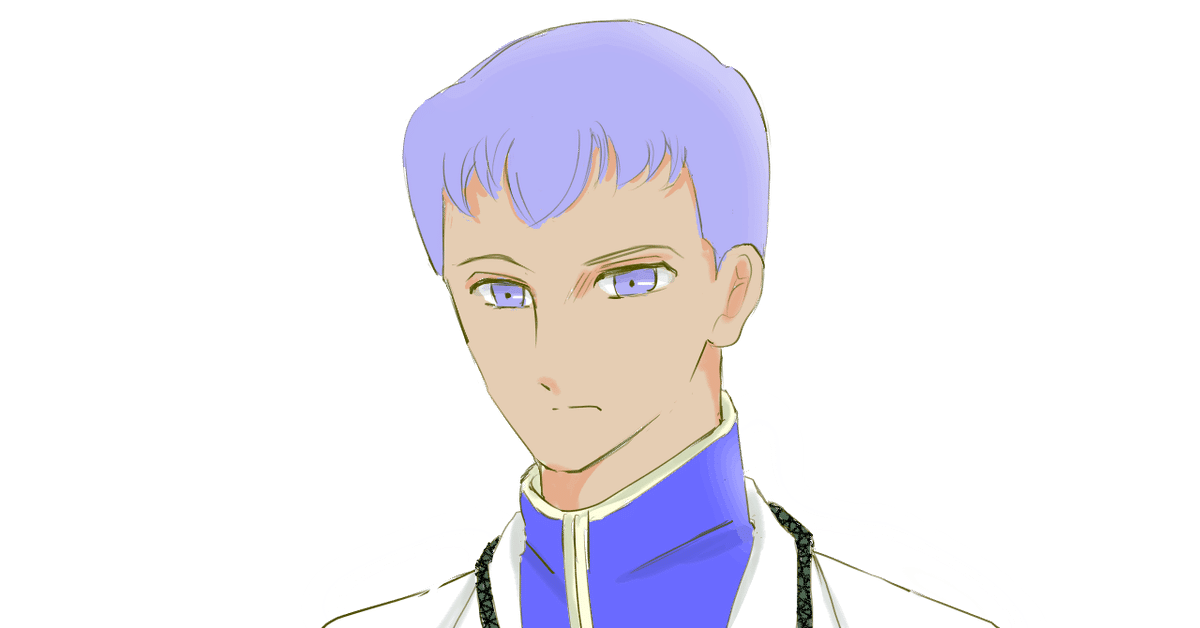
僕はそのとき初めてレイターに「大丈夫か」と声をかけていなかったことに気づいた。
「相変わらず散らかってるなぁ」
ベッドの上段をのぞき込んだジェームズがあきれている。プラモデルや漫画本が散乱する中に、シャツを脱がせたレイターが埋もれていた。
「僕が治療するよ」
というジェームズを制して、僕は片手でつかめる救急パックを受け取った。
「僕がやります」
プロである医療兵の手を煩わせるのは申し訳ない。指導係である自分の責任だ。

階段に足をかけ、レイターの身体を手前に引き寄せた。全身が熱を持っている。化膿させないことが大切だ。
救急パックからピストル型の縫合装置を取り出す。
銃口の部分を傷口にあてて引き金を引くと、人工皮膚でできた糸が圧力で縫い合わせていく仕組みだ。訓練で人型ロボに対して使用したことがある。
僕はレイターが大声をあげないように素早くタオルを口に詰めて、縫合装置に内蔵されている消毒液を傷口に吹きかけた。
「ふぐっ……」
痛みでレイターの身体が一瞬のけぞるように動く。左手でレイターの軽い身体を押さえつけた。銃口そっくりな縫合装置の先端をあてて引き金を引く。
「あっ」
ジェームズが何か言おうとする声が聞こえた。
カシャン。その前に僕の手は動いていた。傷口に沿って即座に五ミリ間隔に引き金を引いていく。
カシャンカシャンカシャン……。
消毒から五秒程度で傷口は縫い合わさった。その上に皮膚の再生シートを張り付ける。手順に問題はないはずだ。
レイターの口からタオルをはずすと彼の首がガクンと垂れた。

振り返ってジェームズの顔を見た。
「問題がありましたか?」
「いや、完璧だ。僕より手際がいい。ただ……」
「ただ?」
「これを習ったのは前線の救護訓練だろ?」
「ええ」
僕はうなづいた。
「今ここは前線じゃない」
ジェームズは救急パックから注射器を取り出すと、慣れた手つきでレイターに痛み止めを投与した。
その様子をただ僕は見ていた。訓練時の設定は薬品も底をつき一刻一秒を争う切迫した状況だった。今は違う。救急パックに常備されている麻酔薬を注入してから治療に当たるべきだった。なぜそんな基本的なところを自分は見落としたのだろう。
「アーサー、気にすることはないよ。前線の応急処置としては教科書通りの満点だ。君の鮮やかな手さばきに僕も声をかけるの忘れて見とれてた。君なら、外科医でもやっていけるよ」
レイターの脈をとりながらジェームズは軽い調子で言った。
「大丈夫、傷は深くないから一晩寝ればすぐ元気になるさ。目が覚めたら化膿止めだけ服用させてやってくれ」
*
食堂に人はまばらだった。
定番の『アレクサンドリアカレー』を食べて気が付く。きょうは金曜日だった。

慣れた辛さが口の中を刺激するが、うまく味わえない。
自分はなぜ、レイターに振り回されてしまうのだろうか。
ジェームズに指摘されるまで麻酔のことを失念していた。自分の経験値が不足していることを自覚する。常に完璧な行動を取ることはできないとしても、最善手が打てなかったことは反省すべきだ。冷静に落ち着いていれば麻酔薬の存在に気が付いたはずなのだ。
焦燥感が判断力をにぶらせた。指揮官として失格だ。
このところ気になっている『お友だち』という言葉。
自分には友人と呼べる関係性の人間が思いつかない。同期のジェームズのことは信頼しているし、友情に近いカテゴリーに位置しているが、友だちと呼ぶには抵抗がある。
「友人がいないのは寂しいだろ」

とアレック艦長に言われたことがある。だが、その感覚は友を失った者が感じるもので、一度も手にしたことがない者には理解し難いものだ。
銃創を負って帰ってきたレイターを見て、身体の心配より、苛立ちが先に立った。友人でないことの証左と言えるだろう。何があったのかたずねても、答えない態度にさらに腹が立った。
艦に戻らないことを心配していた自分が馬鹿にされたように感じたからだ。
僕は自分が思っている以上に自分本位な人間だな。
食堂の壁面モニターでニュースが流れていた。
先程まで滞在していた惑星のローカルニュースだ。パトカーの赤色灯が目に入る。繁華街の現場から記者が中継していた。立てこもり事件があったようだ。
「犯人が客を人質に立てこもったこちらの銀行では、警察の現場検証が続いています。三億リルの身代金が犯人に手渡されたところで、突然の逮捕劇となりました」
銀行というワードが引っかかりモニターを見上げる。
レイターと別れたあの場所だ。
店内にいたという女性客が興奮しながらインタビューに答えた。
「犯人が現金を受け取ったその時ですよ。男の子が飛び出していったのは」
カレーを食べる手が止まった。
女性の甲高い声が耳に入ってくる。
「その子は現金チャージの列に並んでいて、巻き込まれたんです。とにかく、犯人も油断したんでしょうね。だって十歳ぐらいの男の子ですよ。『危ないっ』て止める間もなく走り出して。犯人が発砲したんですけど、気が付くと、その男の子が銃を奪い取っていたんです。ほんと見事に。後はよくわからなくて。三億リル分のお札が宙を舞っていたものですから……」
ニュースでは、お手柄の少年がいつの間にか立ち去り警察が行方を探している、と伝えていた。
記者のリポートが気になった。
「現場で散らばった身代金三億リルのうち十万リル紙幣が一枚回収されておらず、警察が現在も探しています」
僕は部屋に戻った。
椅子の背に血の付いたレイターのシャツがかけてある。胸ポケットを探るとしわくちゃに丸まった十万リル札が出てきた。紙幣に触れるのは久しぶりだ。

「俺のだ。盗るなよ」
ベッドの上でレイターがゆっくりと体を起こした。熱っぽい顔はしているが思いの外、回復が早い。
「大丈夫なのか?」
「ああ、手当てしてくれて、ありがとよ」
ベッドの上にあぐらをかいた彼に薬を手渡す。
「化膿止めだ」
「あんた、珍しく親切だな」

僕が手荒な治療をしたことには気づいていない。彼が元気なのはジェームズが打った痛み止めが効いているからだが、そのことは伝えなかった。
「あせったぜ、出航に間に合わねぇかと思った」
思った通りだった。ニュースで伝えていたお手柄な子どもはレイターだった。銀行でチャージして帰るつもりが強盗に遭遇して帰るに帰れなくなったのだという。
「田舎警察がボケでさ。人命優先だなんだかんだで突入しねぇでやんの」
「犯人が銃を持っていたんだ。警察だって慎重になるさ。そういうお前だって怪我をしたじゃないか」
「だから、ドジ踏んだんだっつうの」
出航の時間から逆算して飛び出したのだろう。よく間に合わせたもんだ。感心すると同時に意地悪なことを言ってやりたくなった。
「もう、戻ってこないだろう、とみんなで喜んでいたのに」
「マジっ?」
充血した目が大きく見開いた。

「冗談だ」
僕の切り返しに、ふぅ、と大きく安堵の息を吐く。
「……ったく、面白くねぇよ。あんたって、ほんと、わかんねぇな」
「わからないのはお互い様だ。ニュースでは銀行強盗から市民を救った少年を探していると伝えていたぞ。あのまま残って、お手柄少年として表彰されたら良かったんじゃないのか」
「あんた、俺に死ねってのかよ。俺が生きてる、ってばれたらマフィアが襲ってくるじゃねぇかよ」
手にした十万リル札をレイターに向ける。
「身代金のうち十万リル札が無くなったと報道されていた。これがそれか?」
「だから、ドジった、っつったろ。カウンターに百万リル札が運ばれたところを狙って飛び出したんだ。けど、行員が置いた場所が悪くてさ。防カメに顔が映るの避けたら、銃弾よけそびれちまった。しかも、つかんだのが十万リル札だったとは、俺としたことがありえねぇよ」
ドジった、というのは百万リル札を奪えなかったことを言っていたのか。心底悔しそうな声だ。だが、彼は大事なことに気づいていない。やっぱり子どもだ。
「仮に百万リル札をつかんだとしても、そのお金は使えないぞ」
「あん? デジタル通貨じゃねぇからいけるだろ」
レイターが言う通りデジタル通貨であれば即座に利用停止措置が取られる。犯人もそれを避けて紙幣を用意させたのだろう。だが、そんな簡単な話ではない。
「紙幣にも記番号が埋め込まれているんだ。使用すればすぐに捕まるさ」
レイターが驚いた顔で僕を見た。
「あんた、まさか、その金、俺が普通に使うと思ってんの? 資金洗浄するに決まってんじゃん。ま、十万じゃ記番号変更の闇口座作る気もしねぇから、しばらくはタンス預金で寝かせておくけど」
前言撤回。こいつはただの子どもじゃなかった。裏社会の帝王が後継者と見込んだ人材だ。足が付くような馬鹿な真似はしない。
だが、この行為は窃盗、紛うことなき犯罪だ。
「不当利得は銀行に返還する」
「どうやって?」
レイターは挑戦的に僕を見た。
手にした十万リル札が重みを増したように感じた。アレキサンドリア号から返金したことが知られるわけにはいかない。デジタル通貨なら細工のしようはある。だが、現物が移動する痕跡を消すのは相当厄介だ。将軍家の秘匿郵便を使用すればできなくもないだろうが、こんな私的理由で使うことの方が問題だ。人が動けば金が動く。それは税金だ。
銀行にとって十万リルは損失だが、レイターは身体を張って強盗犯を捕まえた功労者だ。三億リルの損害を防いだと判断すれば、相殺する価値はある。つまり、僕が目をつぶればすべてが丸く収まるということだ。
もし、あいつが百万リル札を盗っていたら黙認はできないだろう。結果としてつかみ損ねたことが、功を奏したと言える。
「総合的に判断して、今回はこのまま見逃すが、二度とするんじゃないぞ」
「さすが天才少年。俺と同じ考えだ」
ニヤリと笑う顔を殴りつけたい衝動に駆られる。麻酔を打たなかった罪悪感をこれで帳消しにすることにした。
今回、確信したことがある。彼はこの艦から出ていく気がさらさらないということだ。
アレクサンドリア号の乗艦任期は四年。
おそらくこれからも僕は行動も感情も何度も引っ掻き回されることになるに違いない。

けれども、気づき始めた。影響を受ける僕自身がその不安定な状態を実は面白がっていることに。どんな文献よりも興味深い観察の対象として彼との生活は退屈しないだろう。
十二歳の僕たちには、まだたっぷり時間がある。 (おしまい)
裏話や雑談を掲載したツイッターはこちら
いいなと思ったら応援しよう!

