
銀河フェニックス物語 【恋愛編】 第六話 父の出張(まとめ読み版②)
レイターは実は母親が苦手なのではないかとティリーは思った。
銀河フェニックス物語 総目次
ここまでのお話は<恋愛編>第五話「父の出張」まとめ読み版①で
<恋愛編>のマガジン
公園の事務所で事故の被害者として警察から話を聞かれた。
刑事さんによると、タクシー会社の中央コントロールソフトの不具合で暴走したとのことだった。
「感謝状はいらねぇけど、謝礼金ならいくらでも受け取るぜ」
と、いつもの軽い調子のレイターをパパは口を固く結んで見ていた。態度の悪さに文句を付けたいけれど、命の恩人に切り出せないでいる、といったところだ。
駆け付けた救急隊はレイターの右手に止血シートを張って帰って行った。
タクシー会社の役員が頭を下げながら姿を見せ、レイターに見舞金を支払ってくれることになった。
「へへ、大した傷じゃねぇのに、儲かっちゃったぜ」
と機嫌をよくしていた。この人はお金にがめつい。彼のこういうところはパパと同じでわたしも好きじゃない。けど、今日は黙認する。パパに付け入る隙は与えたくない。
警察による聴取やその他の手続きを終えると、もうランチタイムは過ぎていた。タクシー会社の役員は恐縮しながら私たちに声をかけた。
「お食事をご用意させていただきました」
公園事務所の応接室に、朱色の重箱が四つ置かれていた。中心街のレストランへ出かける予定が随分変わってしまった。
「レイターってほんと疫病神なのよね」
ぼやかずにはいられない。
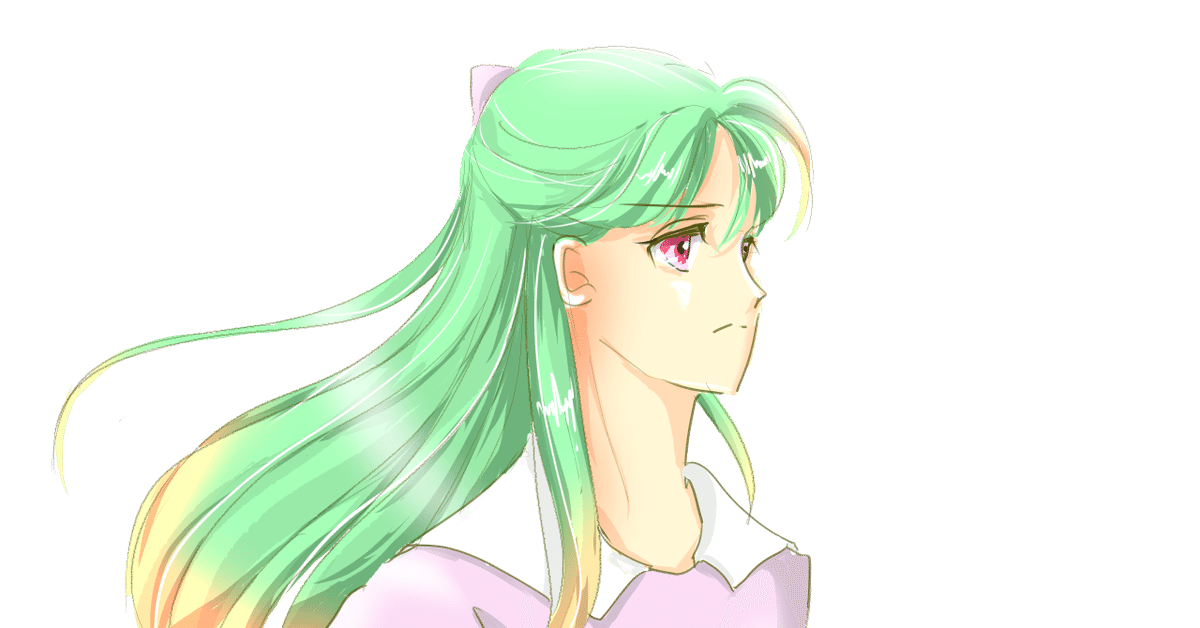
「いやいや、俺のおかげで昼飯代がタダだぜ」
とウインクが返ってきた。
段積みの箱には、指紋を付けるのがためらわれるほど曇りのない塗りが施されていた。そっとふたを開ける。
「きれい」
思わず声が出る。アンタレスの伝統料理が色鮮やかに盛り付けられていた。家庭料理とは違う太陽神に捧げる料理。ハレの日にいただくものだ。アンタレスの二重星を模した野菜が美しい。下の段には俵型に握ったアンタレス米の炊き込みご飯がきれいに並んでいる。
「ほぉ、この飾り切り、今度やってみっか」
食に興味が深いレイターが感心している。揚げ物の下に敷かれた懐紙にはわたしでも知っている有名な老舗料理店のロゴが透かしで入っていた。
薄味だけれど、素材の味がしっかり伝わる。繊細なプロの技。予定していたランチの予算より、このお弁当の方が高額なんじゃないだろうか。
ここで何とかパパの機嫌を取りたいのだけれど。
パパは折角の料理を苦虫を嚙み潰したような顔で食べていた。
「中央制御システムに不具合があるなんて、全くたるんどる」
「でも、よかったじゃないですか。レイター君のおかげでみんな助かったんだから、感謝しなくちゃですよ」
ママがとりなす。
「感謝はしとる。操縦の腕がいいこともわかった。だが、それだけだ」
取り付く島もない。
レイターはパパのことは我関せずという態度で食べ続けている。
「昨日も思ったけど、うめぇな、アンタレス料理は」

「そうでしょ。普段食べる家庭料理もいいけれど、この伝統料理も一つずつ意味があってね、この煮物は大願成就で、こっちのピクルスは食べれば無病息災って言い伝えがあるのよ」
パパとママに教わったアンタレスの食文化をレイターに伝える。
「へえ、面白れぇ。もっと早く教えてくれればよかったのに」
「何言ってるのよ、この間、折角アンタレス料理を予約したのに、レイターがドタキャンしたんじゃないの」
「っていうか、俺としては、ティリーさんの手料理でいいんだけどな」
「……」
アンタレス料理を自分で作ったことはない。返答に困る。
ママがにっこり笑った。
「ティリーにレシピを伝えておきますね」
わたしが作るより、そのレシピを見てレイターが作ったほうがおいしいに決まっている。
アンタレス料理の話題でママとはひとしきり盛り上がったけれど、パパは一言も口をきかなかった。
*
公園事務所から外へ出るとアンタレスAは傾きかけていた。暑さのピークを過ぎて気持ちのいい時間帯だ。午前中の騒ぎが嘘のように落ち着いている。
スパーン。スパーン。
懐かしい。テニスボールの飛び交う音。学生時代、この事務所の隣のテニスコートでよく練習をした。
「ティリー!」
わたしを呼ぶ男性の声に思わず足が止まる。聞き慣れた声にパパとママも振り返った。
テニスコートにラケットを手にした彼が笑顔で立っていた。

「ア、アンドレ?」
毎日会っていた頃より彼の背は高くなっていた。整った顔立ちはそのままで、精悍な男性に成長している。
「あん?」
レイターがわたしに視線を投げかけた。
どう説明をしようか考えている間に、ママがフェンスの向こうに手を振った。
「あら、アンドレ君」
「あ、お母さん、お父さんもご一緒でしたか。ご無沙汰しています」
コートの出入口からスコート姿の女性たちが飛び出してきた。
「ティリー!」
先頭は女子部のキャプテンだったリオだ。面倒見のいい明るい声。変わってない。

「やだ、ティリー、帰ってきてるなら連絡してよ」
学生時代のテニス仲間たちだった。みんなテニスを続けていたんだ。健康そうに日焼けしている。わたしはリオと肩を抱き合った。
「リオ、元気だった?」
「それはこっちのセリフよ。ティリーったら、めったに帰ってこないんだから」
「あら、こちらは?」
リオが隣のレイターを見た。
「もしかしてティリーの彼氏?」
「う、うん」
うなずいた瞬間、フェンスの向こうのアンドレがこちらを見た気がした。
「どうもぉ、銀河一の操縦士レイター・フェニックスです」
レイターがいつも女性にするようにリオの手をうれしそうに握った。

「いやあ、こんなに素敵な女性のみなさんがティリーさんの知り合いとは。もっと早く教えてくれよ」
次々と握手をしていく様子にみんなが噴き出した。まったく、このお調子者ったら。
リオがレイターの顔をまじまじと見つめる。
「この人S1レーサーで、エースのライバルじゃないの?」
「ちっち、ライバルでも何でもねぇよ。俺のがいい男だ」
また、みんなが笑った。見慣れた普段通りのレイターだ。
背後からパパの不機嫌そうなつぶやきが聞こえた。
「あいつは、女性相手に何をおちゃらけとるんだ」
「楽しそうですよ。きっとどこでも人気者なのね」
ママのフォローに感謝する。
リオがわたしの手を取って誘った。
「ねえ、ティリー。ちょっとだけテニスやろうよ。クラブハウスで一式レンタルできるから。彼氏も一緒にどう?」
「えっと……」
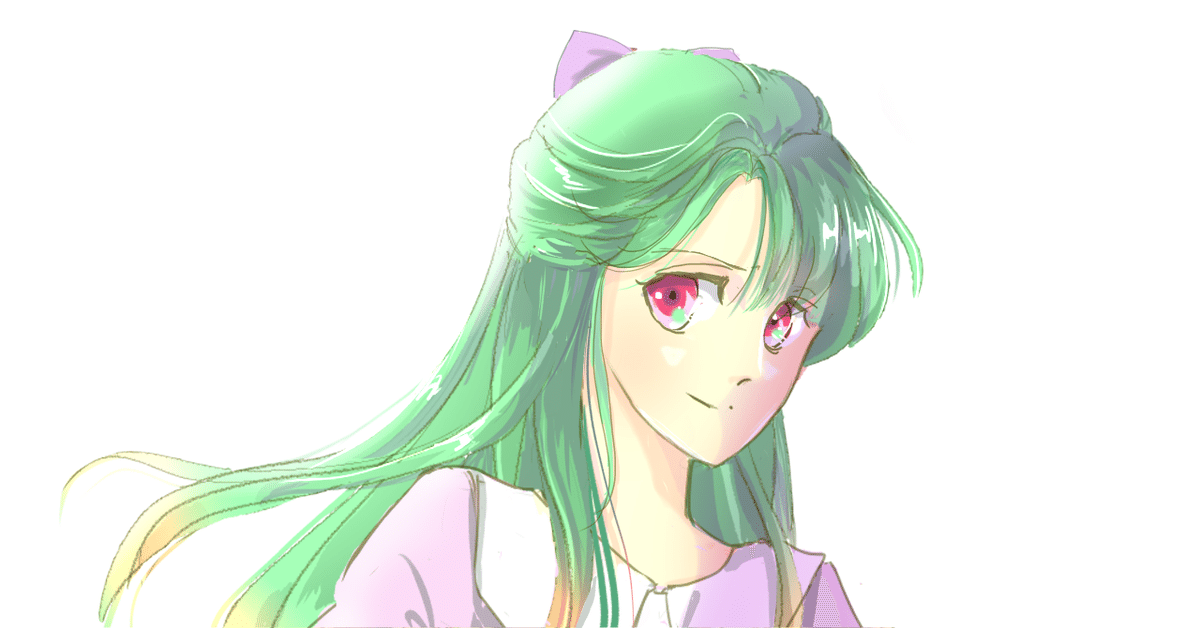
久しぶりにみんなと遊びたい気持ちが湧きあがる。けれど、きょうはパパにレイターを彼氏として認めさせる、というミッションがある。
迷えるわたしの背中をレイターが押した。
「ティリーさん、あんた久々にテニスやりたいんだろ。別に予定もねぇし、やったらいいんじゃねぇの。運動不足を解消したほうがいいぜ」
「レイターもやるでしょ?」
「俺はテニスは好きじゃねぇから、そこで見てるさ」
とレイターはコート脇のベンチへと向かった。珍しい。運動神経抜群の彼のことだ、テニスぐらいできてもおかしくないのに。
振り向いてパパとママの様子をうかがう。
「私たちも構わないわよ、ねえお父さん。久しぶりにティリーのテニスを見ましょうよ」
「じゃあ、決まりね。ティリー、借りま~す」
リオがわたしの手を引いた。
「ちょっとだけ、行って来るね」
とレイターに手を振った。
クラブハウスに入ると目の前のリオが興奮している。
「ティリー、ちゃんと説明してよ。推しのエースの会社に就職するからってアンドレと別れたんじゃないの?」
「う、うん。そうだったわね」
「で、どうしてエースのライバルと付き合ってるわけ?」

「それはいろいろとあって、一言じゃ説明できないわよ」
「彼氏と元彼が遭遇するなんて、普通は修羅場だよぉ」
「関係ないわよ。アンドレとは終わってるんだから」
と口にしてチクリと胸が痛んだ。
彼氏だったアンドレに何の相談もせずにソラ系へ出ていくことを決めた。当時は自分のことで精いっぱいで、そのことが彼を傷つけていたことにわたしは気が付かなかった。社会人になって同級生のキャロルから聞いて初めて知った。
だからと言って、笑顔で送り出してくれたアンドレに今更謝るのも失礼な気がする。
「ふぅ~ん。じゃあ問題ないか」
リオは学生時代から変わらない。アンドレと付き合うことになった時も根掘り葉掘り聞かれたことを思い出した。
* *
大きな木の陰にベンチはあった。アンタレスAの赤い直射日光がちょうど遮られる。
レイターが座る隣にティリーの母親、その隣に父親が並んで腰掛けた。
「アンドレ君は立派になったなあ」

母親に同意を求める父親の声は、十分レイターに届く大きさだった。
レイターはアンドレがティリーの両親を「お父さん、お母さん」と呼んでいたことを思い出した。
母親がレイターに話しかける。
「ご存じかも知れないけれど、アンドレ君は学生時代、ティリーのボーイフレンドだったのよ。よくうちにも遊びに来てて」
父親が母親に聞いた。
「どうして二人は別れたんだ?」
「アンドレ君は地元の研究所に就職したし、ティリーはソラ系へ出て行きましたもの。遠距離で自然消滅したって聞きましたよ」
「そうか、じゃあ、ティリーが戻ってくれば寄りを戻すかも知れんな」
「何、勝手なこと言ってやがる」
レイターが聞こえるようにつぶやく。
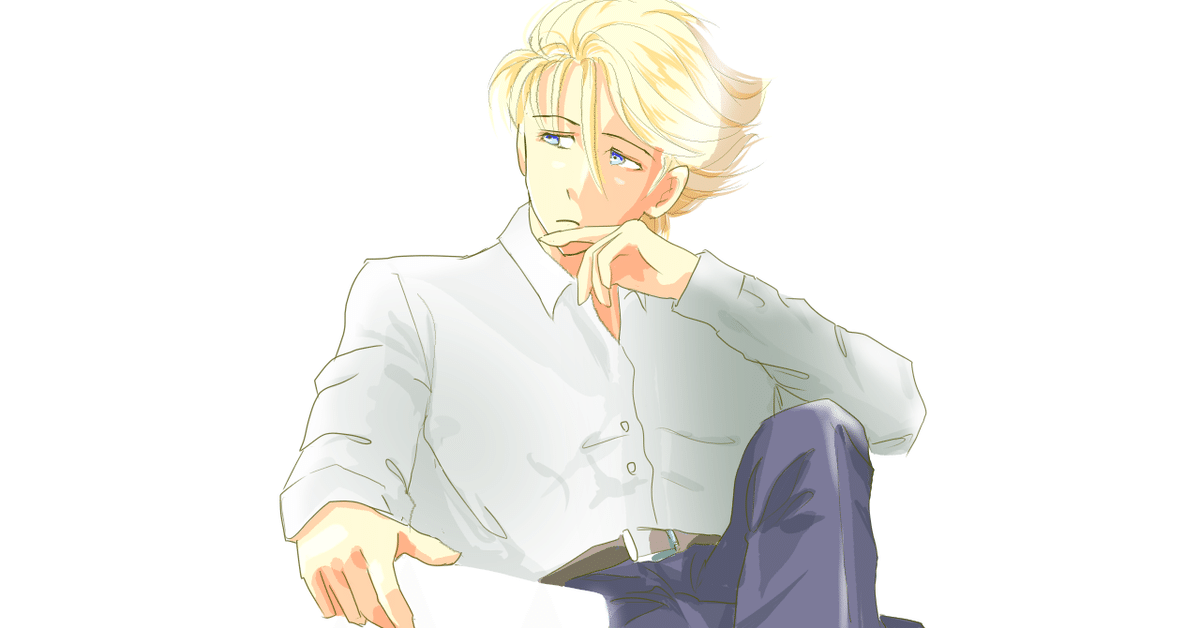
「わしはティリーがソラ系へ行くのに反対だったんだ。心配どおりにこんな奴に引っかかりおって」
「こんな奴ってどんな奴だよ」
レイターが口を尖らせた。
「ティリーにはただ普通に幸せになって欲しいだけだ。お前は知らないだろうが、アンドレ君はなあ、品行方正で成績優秀、学生時代には生徒会長も務めて、今も研究所の有望株だ。ハイスクール中退の暴走族とは全然違うんだよ。ご両親も立派な方で」
「悪かったな、俺に親はいねぇっつったろ」
「お父さん、やめてちょうだい」
ティリーの母はレイターを心配そうに見つめた。
* *
「久しぶりだね、ティリー」
アンドレの声を聞いたのは卒業以来だ。毎日おしゃべりをしたあの頃と、優しい雰囲気は全然変わっていない。
「アンドレも元気そう。テニス続けていたのね」

「ああ、たまにこうしてみんなで集まっているから、今度はティリーにも声をかけるよ」
「ありがと。あまり帰ってはこられないけど」
社交辞令のような挨拶。けれど、普通の顔で話せてよかった。
レイターの視線を感じる。わたしとアンドレの会話が気になるのだろうか。リオが言った修羅場という言葉が頭に浮かんだ。
いや、アンドレとわたしの関係は今は友人だ。レイターとの間でもめる要素はない。
レンタルしたシューズとラケットは悪くなかった。
軽くアンドレとボールを打ち合う。アンドレは相変わらず上手だ。久しぶりにラケットを握るわたしでも打ちやすいところへ返してくれる。昔もこうやってよく打ちあった。気持ちが通う心地よさ。ラリーが続けば続くほど、アルバムを開くような懐かしさに包まれる。
過去が美化されているのかも知れないけれど、アンドレとの間に、嫌な思いをした記憶がまるでない。
* *
レイターの目に映るティリーは普段とは違っていた。
昔の仲間と一緒だからか、いつもみたいに背伸びしてねぇな。笑顔が無防備だ。薄桃色のレンタルウエアがよく似合ってる。ラケットを振る姿はお世辞にもうまいとは言えねぇが、テニスの経験者だってことはわかる。ポニーテールが揺れてかわいい。
元カレか。
前に話を聞いたな。絵に描いたような優等生の彼氏。
テニス部のキャプテンだっただけのことはある。どんくさいティリーさんをうまくリードしてやがる。
俺の隣で、ティリーさんの両親が目を細めて娘のプレーを見つめてる。
『ティリーにはただ普通に幸せになって欲しいだけだ』
親父さんの願いが理解できねぇわけじゃない。
この家族の近くにいると、息苦しくなるほど押し寄せてくる。アンタレスの普通の生活の中にある幸せって奴が。
将軍家ってところは戦争状態が「普通」だ。
そんな中でも俺がフローラやロッキーと過ごしたハイスクールの頃は平時だった。あの頃の俺の暮らしはアンタレスの普通の生活に近かっただろう。

とはいえ、裏番張って家出してマフィアと喧嘩って毎日は、ティリーさんの両親が考える「普通」とはおそらく違う。
ティリーさんは元カレとにこやかに話をしている。この星で平穏と幸福に包まれて暮らしてたってことが突き付けられる。
俺がポケットをひっくり返したってティリーさんに与えてやれないモノ。それをアンドレって元カレはあふれるほど手にしていやがる。
* *
ティリーはちらりとベンチを見た。レイターとパパの様子が気になる。アンタレスの日差しで雪解けた、という気配はない。レイターは無表情だ。何を考えているのだろう。
リオが言う通り、元彼とテニスをしているのを現在の彼氏が見ている状況は不自然かもしれない。わたしだけ楽しんでいることに罪悪感もある。ベンチに近づき声をかけた。
「ねえレイター、これからワンセットマッチで混合ダブルスの試合形式をやるんだけれど、テニスはできないの?」
「あん? 誰ができねぇっつった」
不機嫌そうな声が返ってきた。
「だって、さっき」
「好きじゃねえ、っつったんだよ」
背後からアンドレの声がした。
「ティリー、僕が君とペアを組むよ」
その発言をさえぎるように目の前のレイターがすくっと立ち上がった。
「しょうがねぇな。テニスぐらいやってやるよ」

その態度からわかる。やっぱりこの人、アンドレのことを気にしてたんだ。誘ってよかった。
わたしとレイターは、くじの結果、アンドレとリオのペアと対戦することになった。
「あらら」
リオが意味深な視線をわたしに送ってきた。
ベンチで観戦しているパパとママの会話が耳に入る。
「お父さん、何だか面白い展開になりましたね」
「アンドレ君はテニス部のキャプテンだったんだろ。それに引き換え、何だあいつの構えは。やったことないのか」
レイターは借りたラケットを右手に、コートで仁王立ちしていた。服も靴も普段着のままだ。小声で確認する。
「レイターって、テニスをやったことあるの?」
どこか投げやりな答えが返ってきた。
「あるさ。ただダブルスはやったことねぇから、ティリーさん頼むぜ」
「う、うん。任せて」
思わず返事はしたけれど、テニスは久しぶりだ。しかも上手とは言い難い。一方、リオたちは今も練習を続けていて、アンドレは全国大会で六位入賞の腕前だ。あっという間に勝負がついてしまうかもしれない。
「ティリー、悪いけど手は抜かないわよ」

リオは女子部のキャプテンだった頃から遊びだろうと何だろうと勝負に真剣だ。
「わかってるわ」
まずは、リオがサーバー。わたしがレシーバーだ。
彼女は速くて力強いサーブが持ち味。その代わりコントロールが甘い。トスが上がった。
パシンッツ。
は、速い。学生の頃より上手くなってる。
「サービスエース」
一歩も動けなかった。
「ご、ごめん」
レイターに謝る。
「へぇ、彼女なかなかやるじゃん」
次はレイターがレシーブの番だ。
リオがサーブを打とうとするのだけれど、レイターがまったく構えないのでとまどっている。
「レイター、ちゃんと構えて」
「あん? 俺ならいつでもいいぜ」
ラケットが下を向いている。どう見てもただ立っているだけだ。大丈夫だろうか。
「行くわよ」
リオがサーブを放った。女子とは思えない威力のあるファーストサーブ。
レイターが動いた。素早い。
「ほれっ」
変な構えからバックハンドできれいに合わせる。
スパーン。
気持ちのいい音を立てて、相手コートの角へボールが飛んだ。さすが、運動神経の塊だ。
レシーブエース、かと思いきや、アンドレがぎりぎり追いついて打ち返してきた。
わたしの方へ来た。簡単な球だ。とらなきゃ。ラケットに当たった。
よし、と思ったのだけれど。
「ネット」
自動判定審判の音声が響いた。あ、失敗。せっかく、レイターがきれいに返したのに。
「ご、ごめん」

「謝るなよ。あんたが運動音痴なことは想定の範囲内だ」
失礼なレイターの反応はいつもと変わらない。それにしても新鮮だ。二人でテニスができるなんて。アンタレスに帰ってきてよかった。
バスケ部だったレイターとバスケはやったことがある。これからはテニスにも付き合ってもらおう。
次は、わたしがレシーブだ。
リオがトスを上げた。今度こそ取る。
と思ったのに、コートに突き刺さるような弾に、身体が動かない。
「フォルト」
わずかにはずれた。ふぅ、と安堵の息が漏れた。
「あんた、肩に力が入りすぎ」
レイターの言う通りだ。肩を上下に軽く動かす。
セカンドサーブは威力が弱い。
かろうじて、ラケットに当たった。
返った。
いや、まずい、山なりのボールがアンドレの前に飛んだ。あちゃあ。相手のチャンスボールだ。
ビシッツ!!
アンドレがスマッシュを打つ。やられた!
とその時
パーン
え? 後方に下がっていたレイターが打ち返した。うそでしょ。
アンドレもリオも一歩も動けない。コーナーぎりぎり。
「アウト」
審判の機械音声が響く。わずかにラインを越えていた。
「ちっ、やっぱ調子悪りぃな」
レイターがラケットで肩を叩いている。
この人の運動能力が高いことは知っているけれど、アンドレのスマッシュを打ち返すなんて、経験者でも普通は無理だ。
「これ以上点はやらねぇぜ」
レイターは言葉どおり、リオのサーブからリターンエースを奪った。
一方で、わたしのレシーブはどうしようもない。リオのサーブに歯が立たない。見る間に1ゲームを取られた。
サーブ権が移ってきた。次はわたしのサーブだ。
威力はないけれど、丁寧さだけが持ち味。
ファーストサーブが入る。
リターンが返ってきた。
「そぉりゃあ」

レイターは構えは適当で素人にしか見えないのに、きっちり速い球を打ち返していた。ポイントをとる。
「レイター、ありがとう」
「こちとら肉体労働者だぜ、頭脳労働者に負けられっかよ」
確かにアンドレは研究者で頭脳労働者だけど、ハイスクール選手権六位入賞者なのだ。そのアンドレが押されている。どれだけ重い球なのだろう。
レイターの動きはめちゃくちゃなのに無駄がない。アンドレのような華麗さはないけれど、荒々しくそれでいて美しい。つい目の端で見とれてしまう。
フェニックス号で訓練するレイターが頭に浮かんだ。触れたら火傷するレーザー光線を使った真剣なメニュー。
ボディーガードの仕事は死に直結する。反射神経も筋力も生きるために鍛え上げられている。「プロ」という文字が頭の中で像を結んだ。
* *
レイターの打球の速さに驚いたリオはアンドレに近づいた。

「ティリーの彼氏、結構やるわね。フォームはめちゃくちゃだけど相当な反射神経だわ」
アンドレも困惑している。
「彼が初心者なのか経験者なのかよくわからないが、変化球で攻めてみよう。ティリーもカットボールは苦手だ」
「そうね」
学生時代、へっぴり腰だった彼女のプレイをリオは思い出した。アンドレの言う通りに、回転のある球をティリーに向けて打つ。
ティリーのラケットに当たったボールは、想定通りのはじくような軌跡でネットに引っかかった。ティリーは泣きそうな顔で彼氏に謝っていた。
リオがアンドレにウインクを送る。
「作戦成功ね」
今度はアンドレが回転をかけた。ティリーの彼氏に飛ぶ。お手並み拝見だ。経験者かどうかこれでわかる。
「レイター、変化するわよ」
ティリーが声をかけた。アンドレの球は変化するとわかっていたところで返せるほど甘くはない。バウンドしたボールが低く横滑りする。氷の上で跳ねたようなイレギュラーな動き。
彼はすくいあげる様にしてコンパクトにスイングした。
スパンッ。

うそでしょ。ボールが返ってくる。慌てて前へ出る。だめだ、届かない。ネット際でこちらのコートに落ちた。
アンドレも驚いている。
「あの球が返せるとは、彼は、力任せの素人というわけではなさそうだな」
「コースもちゃんと見て返してきてるわ」
銀河一の操縦士というのは何者なのだろう。彼に球が飛ぶと厄介だった。強打、フェイントを打ち分けてくる。全然初心者じゃない。
ティリーのミスでこちらにポイントは入るけれど、差が開かない。
リオは汗をぬぐうアンドレの横顔を見た。
珍しい。大会でも冷静な彼が闘志をむき出しにしている。
アンドレはティリーのどこが好きなんだろう。学生時代、二人が喧嘩したという話は聞いたことがなかった。ティリーが悪い子じゃないことはわかってる。けれど、推しのエースを追いかけてアンドレと別れると聞いた時は信じられなかった。茫然としたアンドレを初めて見た。
アンドレは未練があるとは一言も言わない。でも、わかるよ。今もティリーを待っていること。そこへあの子は、随分と軽いノリの彼氏を連れて帰ってきた。相変わらず無自覚に人を傷つける。
「アンドレ、この状態を打開するためにわたし、ティリーを狙うわよ」
「仕方ないね」
ボールを持つ手に力が入る。ティリーに集中攻撃を仕掛けた。
* *
「ネット」
「アウト」
ティリーはがっくりと肩を落とした。次々とわたしに変化球が飛んでくる。リオに狙われている。感情をぶつけられるような執拗な攻撃。そして、相手の思惑通りにことごとくミスをした。
「レイター、ごめんね」
「だから言ってるだろ、あんた、もう少し運動したほうがいいって」
「仕事が忙しいの知ってるでしょ!」
コートチェンジのタイミングでベンチで汗を拭く。パパが憤慨しながら話しかけてきた。
「汚いな。彼女はティリーばかり狙っとるぞ」
隣でレイターが水を飲みながら応じた。
「汚ねぇわけじゃねぇよ。弱いところが攻められるのは当り前だ。俺がリオさんにぶつけてやれば、おあいこだぜ」
レイターが本気でリオを狙ったら、あの剛速球で怪我をしそうだ。
「そんなことはやめて」
「ってあんたが言うと思うからやらねぇだけさ。ま、あのアンドレって優等生があんたを狙ってきたら容赦しねぇよ」
と刃物でも投げつけそうな顔でアンドレを睨みつけた。
* *
リオとアンドレも反対側のベンチに下がった。
水分を補給しながら試合内容を分析する。まるで公式戦だ、とリオは思った。
「ティリーは抑えられるとして、彼はなかなかのもんよ。どう見ても我流だけど一流の感覚を持ってる」
とにかく力強くて速い。プロ並みだ。
「大丈夫さ。彼が打ってくるのは直球だけだ。あのスピードにも慣れてきた」
アンドレが追いつき始めている。手練れのアンドレは技を繰り出して器用にしのいでいる。
「技巧派のあなたと直球の彼、全くタイプが違うわね」
「それがどうかしたのかい?」
「どうしてティリーは彼を選んだのかしらって思って。あなたとティリーはお似合いだったし」

ハイスペックなアンドレは人気があったから、ティリーと付き合うことになって女子部員の間に波紋が広がった。テニスの後に楽し気にしゃべって帰る二人の姿はお似合いで、みんなうらやんでいた。
アンドレがポツリとつぶやいた。
「彼が僕に似ていなくて良かった」
「え?」
真意をたずねようとするリオをさえぎるように、アンドレは肩を叩いた。
「さあ、行こう。あのスピードに何としても食らいついていくさ」
* *
ティリーはレイターにボールを渡しながら声をかけた。
「レイター、しっかりね」
ゲームカウント一対ニで負けているところで、レイターにサーブの順番が回ってきた。わたしたちがこのゲームを取るチャンスだ。
相変わらず変な構え。サーブを打ったことはあるのだろうか。
「金賭かってりゃ、もちっとやる気がでるんだけどな」
と言いながら適当にボールを上に放り投げた。何、それ、トスなの?
そこからのアクションは早かった。思いっきり振り切る。
ボールが歪んで見えた。早すぎる。
ズバーン。
リオが目を丸くしている。
「サービスエース」
レイターはいい加減なようで、やる時はやる。すごい集中力だ。
「ナ、ナイスサーブ」
「ま、いつもより的がでかいしな」
さらりと返ってきた反応にひやりとする。ボディーガードの彼にとって、的とは銃で撃ち抜く一点を指す。スポーツ射撃も銃による狩猟も認められていないアンタレスには存在しない的。
レイターの剛速球サーブが続く。アンドレがかろうじてラケットに当てる。
ポワン、とゆっくりボールが飛んできた。前衛のわたしがリオの足元へボレーで返す。ポイントが取れた。
「さすが、元テニス部じゃん」
レイターが歯を見せて笑った。ここはアンタレスだ。銃に狙われる危険も不安も何もない。
「任せなさいよ」
とハイタッチする。何だか、普通のカップルみたいだ。いやいや、わたしたちは普通のカップルだ。恥ずかしがることはない。
なのに、はしゃぎ過ぎてはいけない。と抑制する自分がいる。アンドレの前だからだろうか。
レイターのサーブは圧倒的だった。ラブゲームに抑え込む。ゲームカウントが並んだ。もうこの後はレイターにサーブは回らない。何とかしのがなくては。
ここへきて、徐々にアンドレがレイターの球を打ち返すようになってきた。
「ふふん。やるじゃねぇか」
「速いだけの球、恐るに足らずだ」
「はんっ、これでどうだ!」

レイターの球の威力が増した。恐ろしい速さだ。アンドレも追いつけない。
「くっ」
アンドレが悔しそうな顔をしている。その表情に胸がぐっと締め付けられた。
努力家のアンドレ。彼は真面目で何に対しても一生懸命で、そんな誠実なところが好きだった。
レイターほどの天才じゃない。
でも、彼は一歩ずつ進むことで乗り越えてきた。だからきっとこのままでは終わらない。
レイターの球を打ち返したアンドレの返球がわたしの正面に飛んできた。さあ、ボレーだ。
ラケットを前に出す。
あ、空振り。次の瞬間、身体に衝撃と痛みが走った。
息が詰まる。打ち損ねた球がみぞおちを直撃した。吐きそう。お腹を押さえて座り込む。

レイターがわたしの横に腕を組んで立った。
「あんた、ほんと、どんくせぇな」
それが、彼女にかける言葉だろうか。
その時、
「ティリー、すまない」
アンドレがネットを飛び越えて駆け寄ってきた。
「大丈夫かい?」
そのままアンドレはしゃがみんでわたしの背中をさすった。懐かしい、シトラスの香り。アンドレのシャツから漂う柔軟剤の匂いが時間を引き戻していく。
「う、うん。大丈夫」
わたしたちを見下ろしながら、あきれたようにレイターが言った。
「あんなへなちょこだま、ゆっくり息吐きゃ平気だろが」
アンドレが声を荒げた。
「君、彼氏なんだろ! ティリーのことが心配じゃないのか?」
ベンチでティリーの父親も怒っていた。
「ほんとにあいつは何て奴だ。アンドレ君はあんなに心配しているのに」
「まあまあ、お父さん」
横から母親がなだめる。
*
アンドレに支えられながらゆっくり立ち上がると痛みも吐き気も引いていた。レイターの言うとおりだ。大したことはなかった。ただ、ちょっとぐらい気を使ってくれてもいいのに、と腹が立った。アンドレは昔と変わらず優しい。
「ありがとう、アンドレ。もう大丈夫」
「無理するなよ」
レイターが鼻で笑った。
「けっ、敵に無理するなとは、笑わせるぜ」
「レイター!」
わたしは思いっきり睨みつけた。心配してくれたアンドレに失礼だ。

「フン。ったく『無理するな』は俺が言う台詞だろが」
背を向けたレイターのつぶやきが、かすかに風に乗って聞こえた。
試合が再開した。
暑さに体力を奪われる。
わたしは更に調子をくずして、レイターの足を引っ張ってばかりいた。ボールが当たったせいではない、単なる運動不足だ。ハイスクールの頃は平気だったのに、すぐ息が切れる。足が重たくて思うように走れない。明日は筋肉痛が確定だ。
レイターがわたしの守備範囲までカバーしてくれている。
でも、少しずつ押されている。
レイターの剛速球にアンドレが食らいついているからだ。
* *
いつものアンドレと違う、とリオは感じていた。粘り強いのはいつものことだけれど、きょうは執念のようなものを感じる。
「アンドレ、あなた、ムキになってない?」
「そうかもな。負けたくないんだ」
ティリーの前で無様な姿は見せたくない。でも、それだけじゃない。
*
ハイスクールの頃、女の子と何を話していいのか僕はよくわからなかった。男同士なら馬鹿話もできる。硬派な政治の話も好きだ。けれど、芸能やファッションの話題には疎く、女の子が喜ぶ話というものが想像できなかった。告白されても、受け入れられないでいた。
そんな中、たまたま同じテニス部のティリーとS1レースの話になった。
ポニーテールが似合う彼女は、テニスの腕はそれほどではないけれど、後輩の面倒見も良くクラブのムードメーカーだった。
僕は子どもの頃からS1が好きで観ている。ティリーとならいくらでも話すことができた。実際のところ、彼女が好きなのはS1というより、『無敗の貴公子』エース・ギリアムだった。

ただ、推しに関することならどんなことでも知りたい、という貪欲さから、彼女はどんどんとレースそのものへの興味を深めていった。機体の性能や構造といった話にもついてくるようになった。
S1の翌日は、テニスの練習後にレースの感想を話し合う。身振り手振りを交えてしゃべる姿がかわいくて、その時間が待ち遠しくてたまらなかった。もっと彼女と話したい。
僕は交際を申し込んだ。ティリーは驚いていたけれど僕の申し出を受けてくれた。
他愛のない毎日がティリーといると色づいていた。一緒にS1を見るようになった。推しのエースにお熱なのは少々癪に障るけれど、所詮は夢の話だ。
ティリーの自宅で食事を呼ばれた。優しいお母さん、政治好きのお父さんとも親しく話をした。彼女とは大きな喧嘩をしたこともない。
僕は難関と言われるアンタレス星立研究所の試験に受かり就職が決まった。ティリーも地元の優良企業から内定をもらった。僕はティリーと一緒に未来を歩くことを信じて疑っていなかった。彼女も同じ気持ちだと思っていた。
何がいけなかったのか、今でもわからない。
彼女は僕にも家族にも相談をしないで、ソラ系にある宇宙船メーカー最大手のクロノス社にエントリーシートを送り、合格した。『無敗の貴公子』エース・ギリアムが役員を務める会社で働きたいのだという。
ティリーのお父さんから相談を受けた。彼女をアンタレスに引き留めてほしいと。
僕も引き留めたかった。けれど……
「わたし、やってみたいの、宇宙船に関わる仕事を。クロノスで働きたい」

まっすぐに見つめられて、僕は説得する言葉を失った。僕はエースという彼女の憧れに勝てなかった。だが、彼女はわかっていない。大企業の御曹司と一社員の間に接点はほぼない。
「エースの近くで活躍しておいで、僕は待ってるよ」
彼女が夢から覚めて戻ってくることに賭けて送り出した。幻影に嫉妬する無様な姿は見せたくない。理解ある彼氏として彼女の記憶にとどまりたい。僕の精いっぱいの強がりだった。
その後、僕の見通しがはずれたことがわかった。
ティリーがエースとつきあっているという話が流れた。『無敗の貴公子』の熱愛報道の相手がティリーだというのだ。

不思議とショックは受けなかった。きっとティリーは仕事をがんばったのだ。思いを遂げたその熱量に尊敬の念すら覚えた。相手がエース・ギリアムなら負けても仕方がない。彼がいたから僕はティリーとつきあうことができた。初めから僕は敗北していたのだ。
だが、今、僕の前にいるティリーの彼氏は一体何者なのか。
S1は今も好きだ。エース・ギリアムの引退試合はもちろん見た。それはレイター・フェニックスのデビュー戦であり、手に汗握るS1史に残る戦いだった。
なぜ、ティリーはエースではなくレイターを選んだのだろう。理解できないし納得できない。『銀河一の操縦士』は『無敗の貴公子』とはまるで違う。腕は確かだが、無謀で危険だ。赤信号へ突っ込んでいくような死に直結する飛ばし。

真面目でエース一筋だったあの頃のティリーからは考えられない。ソラ系で一体、何があったのだろう。紳士でもなく、彼女に優しくもない彼氏。ティリーは騙されているのではないだろうか。
この苛立ちが僕に力を与える。彼には負けられない。
球のスピードは恐ろしく速い。だが、単調だ。慣れてきた。
俊足の彼はティリーをカバーするため全面を走り回っている。ダブルスのコートは広い。疲れないはずはない。球威は落ちてきている。
勝機はある。
* *
ったくあいつ、よく粘りやがる。とレイターは思った。
アンドレって奴、誰かに似てると思ったがようやくわかった。エースだ。俺とは大違いの真面目な優等生。ティリーさんの好みのどストライク。
そして、勝負を決して捨てねぇタフさ。こっちの隙を虎視眈々と狙うしたたかさ。

ますます気にくわねぇ。
鈍感なティリーさんは気づいてねぇようだが、あいつが今もティリーに恋愛感情を持ってるのはどこから見ても明らかじゃんかよ。
この勝負、絶対あの元カレにゃ負けたくねぇ。だが、あいつは俺の速度に対応してきた。こちとらこれ以上のスピードは出せねぇ、っつうか落とさねぇようにするので精一杯だ。
ティリーさんは限界だ。ちっ、このままじゃ勝てねぇ。どうする。
* *
コートの脇のギャラリーは静まり返っていた。ボールを打ち合う弾けた音だけが響いている。
大会でも何でもない。ただの試合形式の練習。
なのに、隣のコートのプレイヤーも皆プレーを止めて熱戦に見入っていた。
ここを練習場としているアンドレの上手さには定評がある。ハイスクールの選手権大会で六位入賞という本格派の実力だ。
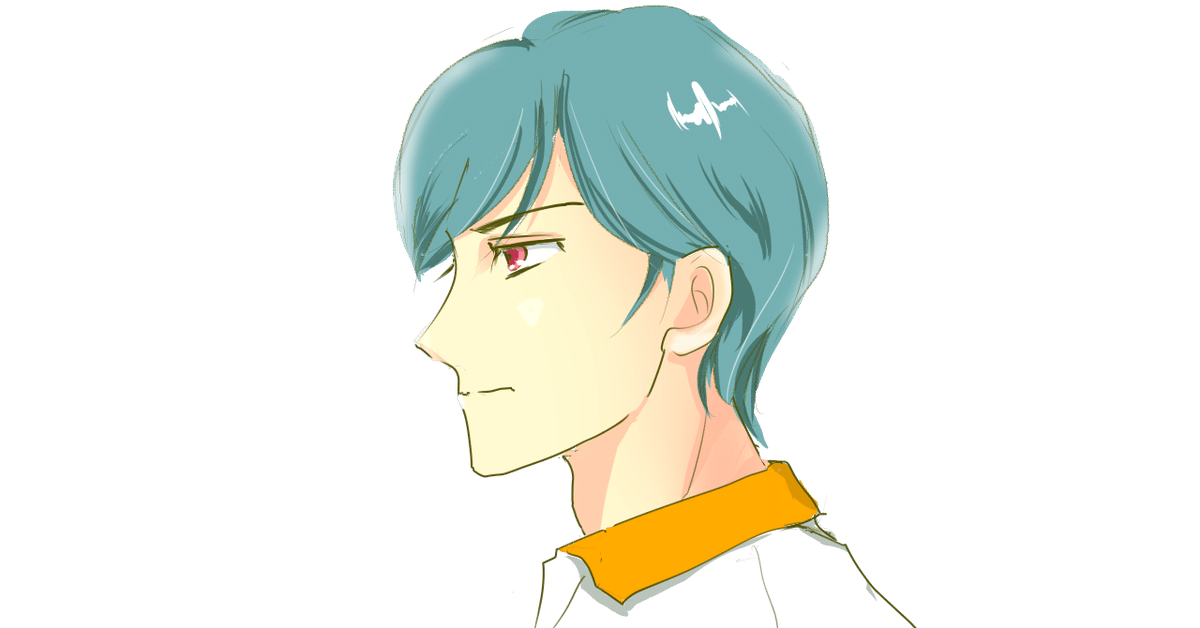
そのアンドレを相手の男性が圧倒的な速さで苦しめていた。まるで初心者のようなフォームから繰り出される球の威力に目を見張る。そして、よく走る。混合ダブルスの試合であることを忘れてしまいそうだ。バテ気味の女性ペアの範囲まで縦横無尽に飛び回る。
変化球を織り交ぜて丁寧に打ち分けるアンドレを、スピードのある球で攻め立てる。殺気のような緊張感。
ベンチに座っているティリーの母親がつぶやいた。
「どちらにも勝たせてあげたいわ」
* *
ハードコートから立ち上がる熱が足に絡みつく。ティリーはあせりを感じた。ビハインドの状態が続いている。
珍しい。レイターの息が荒い。わたしが走らせているからだ。どれだけの運動量なのだろう。
少しでも球が甘いと、リオはすかさずわたしを狙ってくる。わたしのエラーをレイターは曲芸師のように拾う。
でも、いくら彼の足が速いと言っても限界がある。
久しぶりのテニス。
お遊びだと思ってレイターを誘って、最初は楽しんでいたけれど、こんな真剣な状況になるなんて。
レイターのリターンで追いつく。
デュースが続く。
レイターは勝負にこだわっている。『銀河一の操縦士』は負けず嫌いだ。そのメンタルで、レースやバトルで勝ち続けたのだ。わたしは足手まといにしかなっていない。
アンドレは昔と変わらずミスが少ない。ストレートで返してくる。
わたしのカバーに入っていたレイターは追いつけない。
「くっそー!」
いらだった声がコートに響いた。
レイターの様子がおかしい。テロだろうとハイジャックだろうと命がかかった場面でも、基本的にへらへらしている人なのだ。こんなに余裕がない姿を見るのは初めだ。
滝のような汗。顔色も悪い気がする。テニスは嫌いだと言っていたことを思い出す。
「レイター、大丈夫?」
普段なら「平気平気」と強がりが返ってくるところで、レイターは敵のコートをにらみつけた。
「しょうがねぇな。やりたかねぇが……」
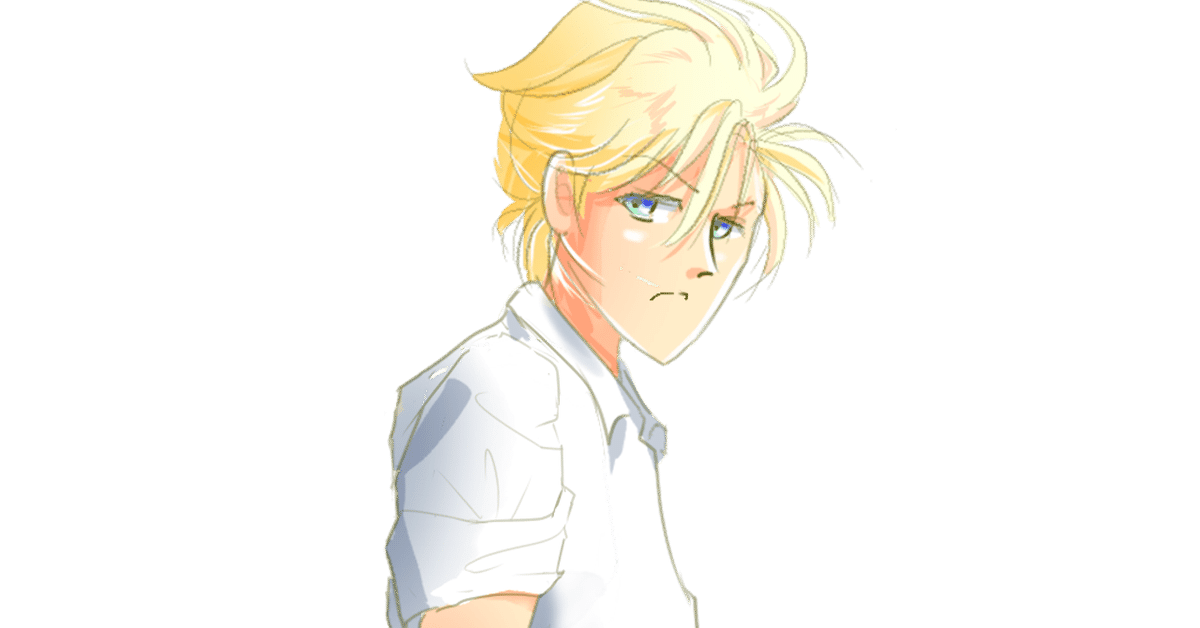
一体何をする気。まさか、リオを狙うつもりじゃ。わたしはレイターに駆け寄った。
「わたしにアンドレの球が当たったのは、わたしが下手だったからよ」
「わあってるよ」
「じゃあ、リオを狙うのは止めて」
レイターがフッと笑った。
「あんた、俺が女性にそんなことすると思うか?」
「思わない」
「さすが、俺の彼女。よくわかってる」
そう言ってわたしの頭に軽く手を置いた。レイターはわたしだけでなく銀河中の女性に優しい。彼女としては複雑なやりとり。
スパンッ。パンッ。パン。
レイターとアンドレのラリーが続く。リオもわたしも入るタイミングがつかめない。
「どおりゃぁ!」
レイターがバックでストレートに打ち返す。アンドレが追いつく。えっ、バウンドした球が滑るように低い。アンドレが空振った。
「バ、バックスライスか」
思わず振り向いた。
「レイター、あなた変化球打てるの?」
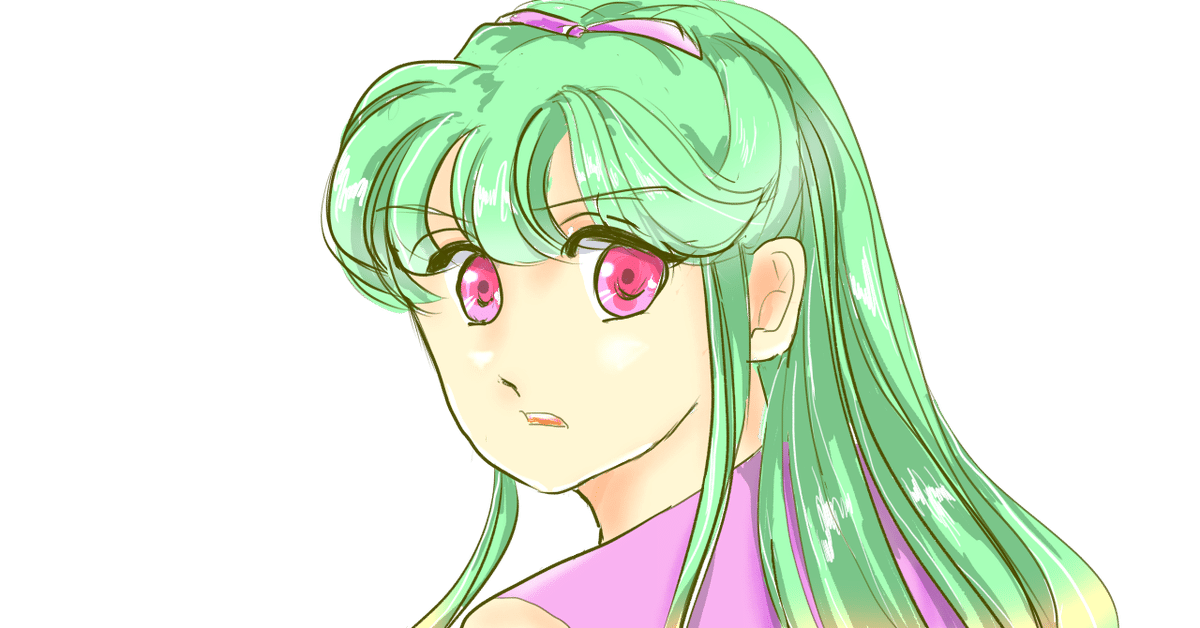
「あん? 打てねぇって誰が言った?」
「だって、今まで打たなかったじゃない」
「嫌ぇなんだよ。けど、あのアンドレの野郎、思った以上に手ごわい。直球一本じゃきかねぇみたいだからな」
レイターはよくわからないフォームから、トップスピンだろうとフラットショットだろうと自在にかけていた。絶対にテニスの経験者だ。

こうなるともう手が付けられない。
そもそも打ち方がめちゃくちゃで予測が立てられない。突然の変化球にアンドレとリオは慣れる暇がなかった。わたしは、レシーブにだけ対応しているうちに、試合が終了した。
テニス部元キャプテンのペアに勝ってしまった。
* *
「はあ、緊張しましたね。それにしても、レイター君、すごいわ」
ティリーの母は拍手をしながら父親に声をかけた。
「ちょっと運動ができるからどうだと言うんだ。ティリーもアンドレ君と会って少し頭を冷やすんじゃないか?」

「どうでしょう?」
「あんな柄の悪い奴より、アンドレ君のが落ち着いていてよっぽどいいじゃないか。あいつは口のきき方からしてなっとらん」
「わたしにはちゃんと話してますよ」
「とにかく、ティリーに対する態度もよくない。彼女を大切に、もっと優しくするべきだろが」
「そうですか? レイター君はよくティリーのこと見てると思いますけど。それに面白い」
「面白い? 母さんは無責任だなあ」
「ティリーは外の世界でいろいろ経験して、随分成長したと思いません?」
「そうだな」
「レイター君がちゃんと見守ってくれているからですよ」
「……」
* *
制汗剤の香りがひしめく更衣室で友人たちに囲まれた。
「ティリーの彼氏、ってすごいね」
「レイターさん、かっこよかったわ」
彼氏だったアンドレがほめられるのには慣れている。学生時代にはおどけてのろけたものだ。けど、レイターの場合、素直に反応できない。
「そ、そうかな」
「彼は一体どこで、テニスやっていたの?」
リオが聞いてきた。
「さあ?」
「つきあってるのに知らないんだ。彼の運動神経、並じゃないよ。『銀河一の操縦士』って一体何者なの?」
知りたがりのリオの追求。連邦軍の特命諜報部員だなんて口が裂けても言えない。
「副業でボディガードをやってるから、身体は鍛えてるのよ」
「どう見ても普通じゃないよね」
そこは同意する。
「うん、普通、じゃないと思う。でも、どんどんわたしの中ではあれが普通になってきてるの」
「ふぅ~ん。その適応力、というか鈍感力がティリーらしいな」
「鈍感? わたしが?」
「気づいてないでしょ」
リオが意味ありげに笑った。
「どういう意味?」
「次、私にシングルの試合で勝ったら教えてあげる」
「えー、それじゃ、一生聞けないじゃないの」
鈍感だから自分の鈍感さに気付けない、ってことがあるのだろうか。昔からリオはみんなの恋愛相談にのっていて観察眼が鋭い。
そんな彼女に卒業の日に言われたことを思い出した。「ティリーとアンドレのカップルだけは、くっついたのも別れたのも、想定外だったよ」と。
* *
クラブハウス脇の水飲み場でレイターは頭から水を浴びていた。
視線を感じて振り返ると、後ろにアンドレが立っていた。
「何でい。不満げな顔だな。試合に文句でもあんのか?」
「いえ、僕の力不足を認めます。ただ、聞いておきたい。あなたは、ティリーを幸せにできますか?」

「あん? 当たり前ぇだろが」
「彼女を泣かせたら、僕、彼女を迎えに行きますから」
「は?」
「別れた僕が言うのも変だけれど、あなたより僕の方が彼女を幸せにできる。あなたからは危険な香りがする」
レイターはくんくんとシャツのにおいを嗅ぐふりをしながら、アンドレをにらみつけた。
こいつは人を殺したことなんてねぇんだよな。俺だって好きでやってんじゃねぇんだよ、あんたらの普通の生活のためだっつうの。
「ったく、何も匂わねぇよ。あんた、お外の空気を吸ったことがねぇんじゃねぇの。チャイルドロックのかかったお部屋にいるせいで」

口の端で笑って挑発する俺を、あいつはぐっと唇を結んでにらみ返してきた。
「僕は本気ですから」
それだけ告げるとくるりと背を向けて歩き出した。アンガーマネジメントもできる欠点のない元生徒会長さんか。
俺は、ティリーさんのように鈍くねぇ。わかってるよ、わざわざ念を押さなくても。あんたがいい加減な気持ちじゃねぇことなんて。
* *
リオに聞かれる前に聞いておけばよかった、と思いながらティリーはレイターの顔を見上げた。
「レイターは、どこでテニスやってたの?」
「うーん、やってたっつうか」
歯切れが悪い。
「あんな変化球、絶対初心者じゃ打てないわよ。経験者なんでしょ」

「セデス王子って知ってるだろ?」
「知ってるわよ『暴れん坊王子』でしょ。王族のプロテニスプレイヤーって有名だもの」
そこまで言って気が付いた。
「警護したことがあるの?」
レイターが肩をすくめて笑った。
「ご名答。あいつ、自主練とか言って、俺ら警護官に球をぶつけて喜ぶわ、変化球が打てなけりゃ首とか言い出すわ、で、みんな嫌がってたんだ」
セデス王子のテニスは随分と荒っぽい。言われてみるとレイターのフォームはどことなくセデス王子と似ている。
「我流で覚えたってわけね」
「テニスなんて二度とやるもんか、と思ってた」
「それで嫌いなんだ」
ママがレイターに声をかけた。
「王子様の警護もするなんて、レイター君はすごいわね」

「だから、レイターは皇宮警備にいたんだってば」
と口にしてから、後悔した。パパの前で軍に関わる話題は避けるべきだった。
パパが不機嫌そうな顔でわたしを見た。
「ティリー、お前は騙されているんだ」
「だまされてる?」
「調べてみたら、皇宮警備官というのはハイスクール中退では務まらんのだ。大卒の学力が必要なんだぞ」
パパったら、昨日の話を聞いて皇宮警備について調べたんだ。
「俺は、皇宮警備官じゃねぇよ。皇宮警備予備官だ」
「なんだ、予備官なのか」
パパが鼻で笑った。その態度がわたしの心に火をつけた。
「パパ、予備官だって、試験は同じレベルなのよ! 調べるならちゃんと調べてよ。レイターはその試験に十四歳といいう最年少で合格したし、ハイスクール中退って言ってもセントクーリエにも入学したんだから」

「セントクーリエだと……」
パパが固まった。優越感で心がくすぐられる。超難関校のセントクーリエは入学するだけでニュースになる。レイターがセントクーリエの出身と聞いた時にはわたしも驚いた。
後ろからレイターのめんどくさそうな声が聞こえた。
「ったく、別にどうだっていいだろが、そんなこと」
「そうね、どうだっていいことだわ」
ママがにっこりと微笑んだ。レイターの学歴でパパに張り合おうとした自分が気恥ずかしくなった。
思い出したようにレイターが胸ポケットから何かを取り出し、ママに渡した。
「あの。これ、ありがとうございました。濡れててすみません」
「あら、洗わなくてもよかったのに」
白いハンカチ。レイターが手を怪我した時にママが渡したものだ。
「レイター君。わたしのことお母さんと呼んでくれていいのよ」
「は? お、おかあさん?」
間の抜けた声。レイターが顔を赤くして目をぱちくりさせている。

「ママったら、突然何を言い出すのよ」
結婚前提でつきあってるわけでもないのだから。
「あら、アンドレ君だって、わたしのことお母さんって呼んでたじゃない」
「それは、そうだけど……」
「絶対に許さん」
パパが口を挟む。
「わしのことをお父さんとは、絶対呼ばせんぞ」
「言われなくても呼ばねぇよ。こっちから願い下げだぜ」
まずい、売り言葉に買い言葉。二人をつなぐ縁という紐は今にもちぎれそうだ。何のために遠く故郷まで帰ってきたのか。
打つ手が思いつかないわたしに代わって、ママが優しくレイターに声をかけた。
「きょうはいろいろあったけれど、楽しかったわ。また、遊びにいらっしゃいね」
そこへ、パパの怒鳴り声が突き刺さった。
「二度と来るな!」
「ああ、金輪際来ねぇよ。とっとと帰るぜ」
レイターはわたしの手をぐいっとつかんでパパに背を向けた。ビリっと紐の繊維が破れる音が聞こえた。今回のミッションは失敗に終わった。
*
帰途に就いたフェニックス号の窓から緑色に輝くアンタレスBを見つめる。パパとレイターの関係を良好にする、というわたしの願いを神様は叶えてくれなかった。都合のいい時だけの神頼みじゃダメということなのだろう。
「アーサーん家に寄ってから帰るけどいいか?」
「月の御屋敷?」
「ああ、みやげを届けに行きてぇんだ」
アーサーさんにアンタレス名物の太陽飴を買ったことを思い出した。
居間のソファーの上でレイターが右足の靴下を脱いだ。びっくりした。足の甲が真っ赤に腫れている。
「どうしたの?」
「ん、ちょっと骨にヒビが入った」
こともなげに言いながら、レイターは足にテーピングテープを巻き始めた。
「骨にヒビって、大丈夫なの? いつやったのよ? もしやアンドレとテニスで対戦した時?」
レイターがむっとした顔した。
「あんたと一緒にすんな。あんなへなちょこテニスでケガなんかするかよ」

テニスじゃなくてレイターがケガをした。とすると……思い当たるのはその前の騒ぎだ。
「暴走タクシー?」
「ああ」
あの時だ。パパをかばってレイターがエアタクシーを蹴り上げた時。無茶なことをする、と思ったのだけれど、あの後、バタバタして忘れていた。
この人、骨にひびが入っているのに、わたしにつきあってテニスの試合をやったということ?
むっとしてきた。
「どうして、平気なふりしてたのよ」
「あん? ふりじゃねぇよ。べつに平気さ。骨なんか固定しときゃ自然にくっつく。さっきレントゲンも撮ったから、タクシー会社に治療費もちゃんと請求できる。ノープロブレムだ」
「そういう問題じゃないでしょ!」
わたしがソファーを叩くと、レイターは顔をしかめた。振動が伝わるだけで痛むようだ。
なのに、そんなそぶりを少しも見せなかった。
その理由はわかる。わたしたち家族に心配かけたくなかったからだ。
アンドレと対戦したテニスの後半、レイターに余裕がなかった訳もわかった。本当に体調が悪かったんだ。使いたくないと思っていた変化球を使ったのは、足が思うように動かなかったからだ。
彼女であるわたしにはちゃんと言ってくれればいいのに、この人はいつもこうだ。
知っていたら、テニスなんてやらなかったのに。腹が立ってきた。自分の鈍感さが嫌になる。
「何、怒ってんだよ」
「怒りたくもなるわよ。あなたのこと心配して……」

「へえ、昔の男に優しくされて、うれしそうにしてたくせに」
「何ですって! あなたなんか、ほかの女性にボールが当たったら、すっ飛んで介抱しに行くじゃない」
「あんたはほかの女とは違う」
「何なのよその理屈!」
興奮してソファーに座ったらレイターの足先に触れてしまった。
「いっでぇ~!」
「ご、ごめん」
何となく喧嘩の空気が途切れた。と、レイターが突然わたしの目を見つめた。青い瞳が近い。
「ティリーさん、あんた幸せか?」
「え?」
質問が突飛過ぎる。レイターの真意がわからず、頭も口も固まった。
「……」
「何でもねぇ」
レイターは下を向いてまたテープを巻き始めた。
頭を冷やそう。わたしは部屋へ戻った。
離れてから気がついた。
『あんた幸せか?』って言うのは『俺と付き合って幸せか?』と聞きたかったんじゃないだろうか。元カレのアンドレと会ったせいでレイターが珍しく神経質になっている。
『もちろんよ』って素直に答えてあげれば良かった。リオの言う通りだ。わたしには鈍感なところがある。
**
月の御屋敷でアーサーさんが待っていた。
「ほれ、みやげだ」
レイターが無造作に紙袋を投げつけた。公園の屋台で買った太陽飴だ。
アーサーさんがその中の一つをとりあげて光にかざした。紫のラインが入ったグレープ味。
「これだな」

アーサーさんが太陽飴を紫のラインに沿って捻ると、飴がカパッと半分に割れたというか開いた。おもわず目を見張る。中は空洞になっていて小さなチップが入っていた。
「そ、それは?」
驚くわたしにアーサーさんは静かに顔を向けた。
「データチップです。アンタレスの新技術がアリオロン同盟に流出して、新型大量破壊兵器の開発に利用されそうだったんです」
「えっ?!」
二つの意味で驚いた。アーサーさんが軍の機密を無関係のわたしに伝えたことと、その内容に。
「セントラルパークの屋台を利用した流出ルートを秘書官のカルロスが掴んだので、レイターにデータチップを取り返しに行ってもらいました」

これがレイターの特命諜報部の任務。
聞きたくない、認めたくない話だった。平和で安全なわたしの故郷アンタレスが、戦争で人を殺すことに加担しようとしていた。
パパとレイターの夕食の会話を思い出した。戦争の影響が銀河中に広がっているという話。レイターは知っていたのだ。アンタレスの技術が大量兵器に転用されかかっていることを。
「ったく、飴買って来るだけの子供の使いだ、っつうから引き受けたのに。ティリーさんの家族まで危険な目に遭っちまったじゃねぇか。一発殴らせろ!」

レイターが立ち上がろうとした、その時、
「そう怒るな」
アーサーさんがレイターの足を軽く蹴った。
「い、痛ってぇ~!!」
あわててレイターが足を押さえた。骨にひびが入っているほうの足だ。アーサーさんは穏やかな顔をしながら容赦がない。
「ティリーさんすみませんでした。ご家族とともに危険な目に遭わせてしまって。銃の使えないアンタレスですから、そこまで危ない任務にならないはずだったのですが……」
アーサーさんが頭を下げた。
わたしたち家族が危険な目に遭った。と言うことは、あの暴走タクシーの件とレイターの任務に関係があったということだ。
「銃がありゃ、こんなケガしなかったぞ。暴走タクシーの動力炉ぶち抜いて止められた」
「どういうことなの?」

わたしの問いにアーサーさんが答えた。
「データチップが連邦に取り返されたことを知って、アリオロン側はそのチップごとレイターをタクシーで轢き殺そうとしたんです」
血の気が引いていく。
「銃が使えねぇから敵さんもいろいろと考えてんだよ。ったく暴走車ってのは一般人に被害が及ぶから、たちが悪いぜ。あのエアタクシーは俺と接触しねぇと止まんねぇと思ったから蹴り上げたんだ」
「そ、そうだったの」
それで、足を怪我したんだ。今更だけれど、じっとりと嫌な汗をかく。単なる事故じゃ無かった。一つ間違えばわたしたち家族も巻き込まれ死んでいてもおかしくない状況だったと。
「アーサー、よく聞けよ。暴走タクシーん中は大変だったんだからな。運転制御がきかねぇ中で、中央コントロールを混乱させてる沿革操作の逆探知をかけて、データをぶっこんだんだ」
上空で不安定に揺れるエアタクシーの中でそんなことをしていたんだ。
「あれは、銀河一の操縦士じゃなけりゃ絶対できねぇぜ」
恩着せがましく報告する。
「お前の逆探知のおかげで潜伏中のアリオロンの工作員を捕まえられた。これまで尻尾がつかめず難航していたから、感謝する」

「誠意は言葉じゃなくて、現物で示せっつうの。手当には技術料と治療費と慰謝料を上乗せしろよ」
その時わたしは気が付いた。
「アーサーさん、治療費はいりませんからね。この人、タクシー会社に請求してるので二重取りになります」
「ティリーさんっ!」
わたしの愛しい彼氏は頭を抱えた。命の恩人だけれど、それとこれは話が別だ。
*
帰りのフェニックス号の中で、レイターがため息混じりにつぶやいた。
「やっぱ、危険な香りがしたのかも知れねぇな」
珍しく神妙な顔をしている。
「どうしたの? 何だか変よ」
「何でもねぇよ!」
レイターの声が荒れている。絶対に変。
「何でもないことないでしょうが!」
わたしもつられて声が大きくなった。どうしてこう喧嘩腰になっちゃうんだろう。
「じゃあ聞くが、あんた、アンドレと何で別れたんだ?」
「は?」
思いもしない質問にわたしは答えに窮した。どうして別れたと聞かれても、遠距離以外の理由はないのだ。
「別に、嫌いで別れたというわけじゃないんだけれど……」
困った。嫌いどころか友情的な感覚は今もある。
「もういい」
レイターが拗ねている。愉快でうれしい気持ちが湧きあがってきた。
「あなた、妬いてるんだ」
「ば~か。あんな坊ちゃんに誰が妬くか」
わたしの頭を軽く小突いて、短いため息をついた。

「俺と付き合ってると危険な目に遭うかも知れねぇ、なんて言ったら、親父さんは絶対に許さねぇだろうな」
「そうね」
わたしは同意してからちょっとドキっとした。
レイターはパパが何を『絶対に許さない』、と言ったのだろう。付き合ってること、それとも……結婚。
聞いてみたい。けれどその二文字を口にすることはできなかった。
南の方角を見ると、わたしの故郷アンタレスAはいつもと変わらぬ赤い光を放っていた。 (おしまい)
裏話や雑談を掲載したツイッターはこちら
<出会い編>第一話「永世中立星の叛乱」→物語のスタート版
イラストのマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

