
銀河フェニックス物語【出会い編】 第十一話 S1を制す者は星空を制す③
第一話のスタート版
S1を制す者は星空を制す① ②
「は、早く、早く救急車を呼んで」
あわてて叫ぶわたしの声を
「駄目だ! 警察にも知らせるな。失格になってしまう」
エースが有無を言わさぬ声でさえぎった。
レイターはエースを椅子に座らせると手慣れた様子でエースの傷を見る。
「骨が折れてるな」
器用にエースの左腕に包帯を巻いていく。
「い、痛いっ」
「固定しときゃ操縦桿は握れるが、レースは無理だぞ」
力なくエースはうなずいた。
「レースは無理って、・・・どうなるの?」

わたしの質問に誰も口を開かない。
「他のパイロットが飛ぶってことですか?」
メカニックが沈痛な表情で答えた。
「無理だ。プラッタ一号機はエースの技術に合わせたシビアなセッティングがしてあるんだ。エースじゃなければ完走できない」
息を飲む。
このレースはプラッタのCMなのだ。
マウグルアに負けることはあってはならない。
エースが襲われたことを正直に報告して失格になった方がまだましじゃないだろうか。
無敗の貴公子のブランドもその方が保てる。
腕を組んで立っていたメロン監督が口を開いた。
「プラッタ一号機を操縦できる者が一人いる」
え? 今メカニックの人がいないと言ったばかりなのに。
「レイター。一号機に乗ってくれ」
「ええっ?」
わたしは思わず驚きの声を上げた。
「あん?」
レイターはエースの包帯の端を口にくわえたまま振り向いた。

どうしてレイターの名前が挙がるの?
確かにレイターは自称銀河一の操縦士で、操縦は抜群に上手い。
でも、レーシングのライセンスは持っていない。
飛ばし屋のバトルじゃないのだ。S1なんて無理だ。
視線がレイターに集まる。
どういう訳か誰一人として異議を唱えない。
「エース。すまないが・・・」
メロン監督が最高責任者であるエースに同意を求めて頭を下げた。
「監督、あなたは最初からこういう事態も想定して彼を呼んだんでしょう。私も同じ意見です。彼なら乗れます」

驚いたことにエースもレイターが操縦できると判断している。
「ちょっと待て。俺はやるなんて言ってねぇぞ」
レイターは口をへの字にまげて監督をにらんだ。
エースと監督の二人が同じ意見ということは、おそらく他に道はないのだ。
「あなた、この状況で断ろうって言うの?」
わたしは腰に手をあててレイターに詰め寄った。

「俺はあんたのボディーガードで・・・」
「エースのボディーガードでもあったんでしょ。エースが怪我した責任はどうとってくれるのよ」
「・・・・・・」
レイターが黙った。
*
スピーカーからレース経過の最新情報が入った。
「アクセス反射圏で二号機がギーラル社のマウグルアに抜かれた」
「抜かれただと」
室内がざわつく。ギーラル社だって必死なのだ。
二号機到着まであと三分。
「レイター、あなた銀河一の操縦士なんでしょ! お願い!」
わたしは必死に頼んだ。
ちっ。レイターが舌打ちした。
「あぁああ。わかった。やりゃいいんだろやりゃ」
頭をかきながら渋々レイターがうなずいた。
「その代わり、勝ったら賞金賞品は俺のもんだからな」
* *
俺としたことが、クライアントにけがさせちまった。
レイターはレーシングスーツに腕を通しながら事件の構図を考えていた。
エースを襲ったのは黒蛇じゃねぇぞ。
アーサーが追ってる汚職の件が絡んでるな。ルト星政府は誰だって会場内に手引きできる。
襲った敵さんはエースが棄権すると思ってる。
俺が影武者になってその裏をかきゃ、動きに乱れが出るはずだ。
* *
エースとレイターの背格好が似ていてよかった、とティリーは思った。
レーシングスーツを着たレイターを初めて見た。

よく似合っている。新鮮な感じに胸がざわつく。
レイターは当然のことながら選手登録されていない。レーシング免許すら持っていないのだ。
けれど、フルフェイスのヘルメットをかぶればわからない。
身代わり操縦がばれたら失格だけれど行けるところまで行く。
これがチームの、そして会社の経営者でもあるエースの判断だった。
「コースはわかるな?」
メロン監督が聞く。
「予選はテレビで見た」
レイターは宇宙船お宅でS1のコースはすべて覚えている。
けれど、このルト星のリレーコースは予選の一回しか使われていない。大丈夫だろうか。
残り二分。
「エースは昔より腕を上げている。パワーバンドは二目盛り以内だ」
二目盛り?

わたしは驚いた。エースは本当に天才なのだ。
通常、レーシング船のパワーバンドは十目盛り程度、速い船でも五目盛りで設定されている。
二目盛りなんて聞いたことがない。
エンジンの能力を引き出すパワーバンドは設定を狭くすればするだけ高出力が引き出せる。
けれど、その幅をオーバーすれば故障につながり、ダウンすれば出力が急激に低下してしまう。
レース中ずっとパワーバンドを二目盛りで維持するというのはまさに神業だ。
エース以外にプラッタ一号機を操縦できる人がいないという意味が理解できた。
それをレイターに求めるのは酷な気がした。
「上等だね。旋回指数は?」
「二十四。コンマ五ずれると操縦桿がぶれる」
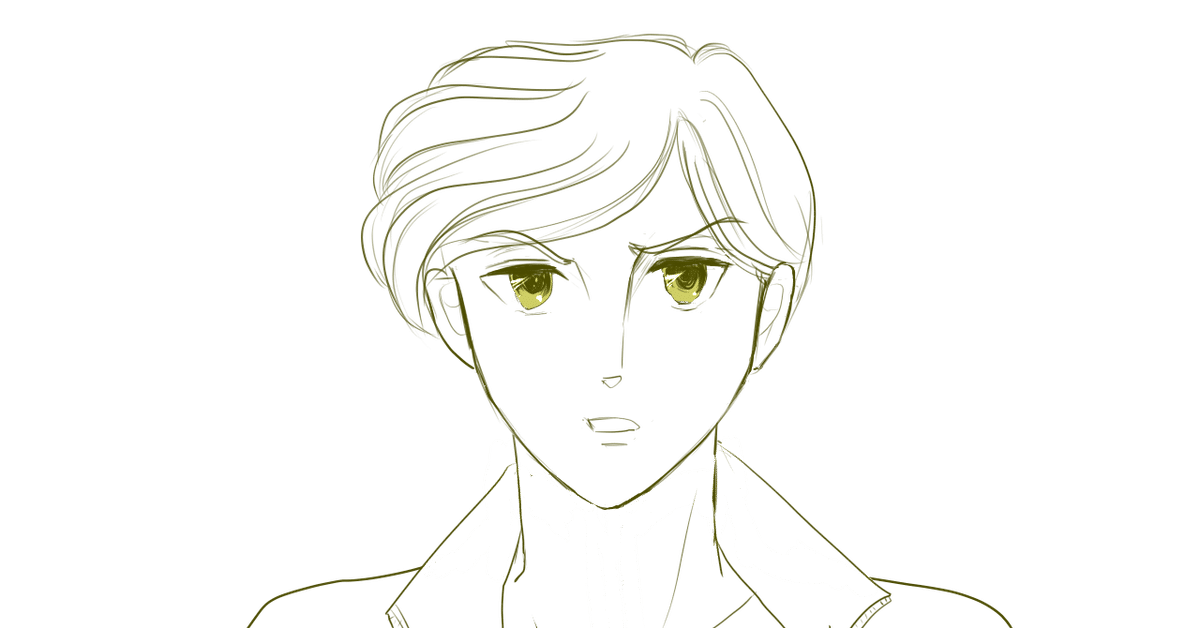
エースが答える。
「ったく、全然中身の違う船を一般のお客さまに売ろうってんだから、詐欺だぜ」
レイターはいつもと変わらぬ軽口を叩きながらヘルメットをかぶった。
船に乗り込むとレイターはわたしの方を見た。
そして、出発前にいつもエースがするのと同じように人差し指を立てて合図をした。
その決めポーズはエースそっくりだった。
胸をぎゅっと掴まれるような感覚に陥る。
あれは、レイターだ。
エースじゃない。騙されてはいけない。
*
『さあ、無敗の貴公子エース・ギリアムが間もなくスタートします。二号機がギーラル社に抜かれトップとの差は一分十五秒。この差はどう見ますか?』
『かなり追い上げないと厳しいタイムだね。といっても相手がエースではギーラル社のオクダも油断はできないが』
『さて、クロノスの二号機が戻ってきました。と、どうしたんでしょうか?アンカーのエースがスタートしません。エンジントラブルでしょうか?』
「レイター!!何やってるのよ。しっかりして!!」
ティリーは叫んだ。
* *
耳の無線がビービーうるさい。
わかってる。わかってるよ。エースが左利きだってのをつい忘れてた。
俺としたことがドジった。さあ行くぜ、プラッタ。
*
『三秒遅れてスタートしました。何があったんでしょうか』
『マシンの問題じゃないなぁ、エースにしてはめずらしいミスだね』
『さて、先頭を飛ばすオクダはすでに重力圏を抜けルトツーへ向かっています。出遅れたエースは間もなく重力圏突破ですが・・・』
『どうもエースの飛ばしが不安定だなあ、これでは追い付くのは難しいよ。何だかテスト走行みたいだ』
* *
暗く細長い部屋。
仲間の間では『闇の制御室』と呼ばれていた。
ズラリと並ぶモニターにS1プライムのレース映像が流れている。
その前に男が二人座っていた。
アンカーのエースがいつも通りの決めポーズで飛び出した。
中継映像を見た小太りの男があわてて声をかけた。
「お、おい、エースが棄権しないぞ」
もう一人の痩せた男が落ち着いて答える。
「よく見てください。エースの操縦がもたついています」
「そうだな、いくら無敗の貴公子でも腕が折れていては優勝できまい。マフィアなんぞに頼まず最初からお宅らが『作戦A』をやってくれれば良かったのに」
「結果的にあなた方は得しているじゃないですか」
「ふむ、確かに、黒蛇がつぶせたのは我々政府にとって瓢箪から駒だ」
小太りの男は愉快そうに笑った。
* *
プラッタ一号機が宇宙空間へ飛び出した。
レーシング船のS1機を飛ばすのは久しぶりだ。
レイターは操縦桿を握りしめた。エースの代わりなんてごめんだと思ったが、やっぱりレースは血が騒ぐ。
パワーバンドの目盛りが二。
初めての経験だが俺は銀河一の操縦士だ。
コースは予選の時に見た。
一度見れば俺は覚える。問題はねぇ。
エースはほんの少し左翼を傾かせて飛ばすんだよな。
テレビで観たエースの飛ばしをイメージしながら操縦桿を動かす。
とにかくプラッタ、ルトツーまでに友達になろうぜ。

勝負はそれからだ。
* *
気を抜いてはいけない。
トップを飛ばすギーラル社のオクダは何度も自分に言い聞かせた。
後からついてくるエースの飛ばしはおかしい。さっき一周目に自分を寄せ付けなかったあの飛ばしとは明らかに違う。
何があったのか知らないがこのまま行けば無敗の貴公子を制するのはこの俺だ。
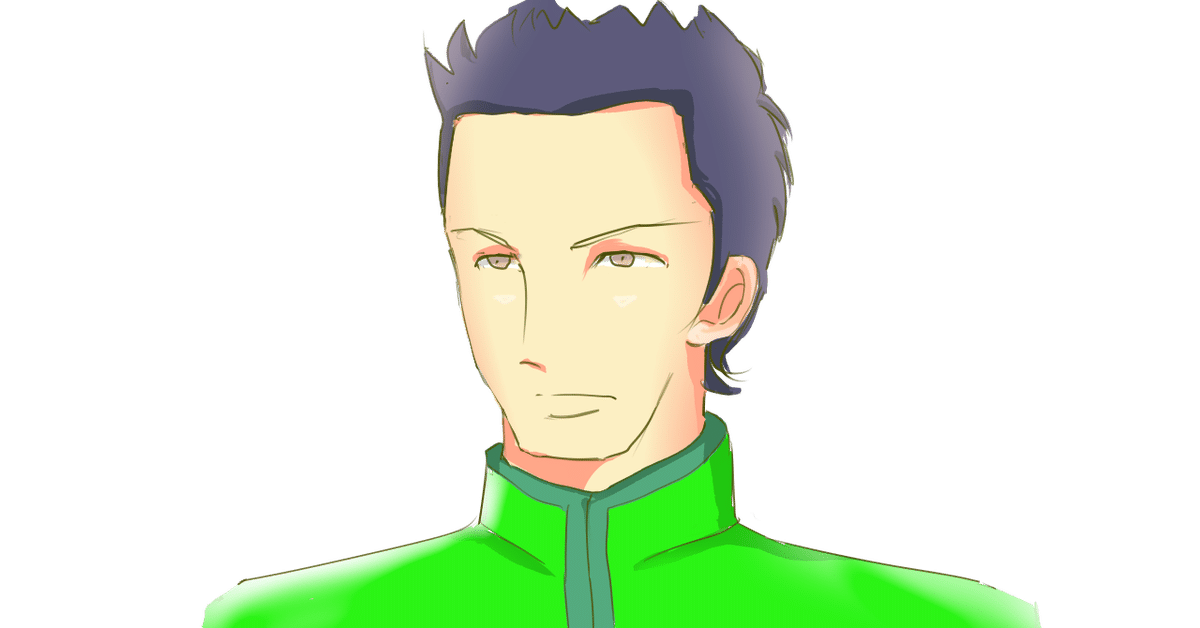
この瞬間をどれほど待っただろうか。
奴が無敗なら俺は無冠。
エースと同じ時期に生まれた自分を不幸だと呪った。しかし今、あいつは俺の後ろにいる。
第一チェックポイントの惑星ルトツーに入る。
滑走路が近づいてきた。減速して着陸体勢をとる。
車輪が地面を走る感触が伝わる。
タッチ・アンド・ゴー。
加速機を思いっきり引っ張る。
両側に並んだ五万人の観客が小旗を振ってトップの俺に声援をおくっている。
気を抜いてはいけない。油断はできない。喜んでいる余裕など無い。
自分に言い聞かせるが口元がゆるむ。
マウグルアはいい船だ。いける。
* *
エースはピットの奥の控え室に隠れていた。
ティリーは付き人としてエースの横でモニターに映る生中継の番組を見ていた。
変な感じだ。
いつもはレイターとエースの操縦を見ているのに、きょうはエースとレイターの操縦を見ている。
『さて、トップのオクダがルトツーの第一チェックポイントを通過しました。ここまでをどうみますか。一位と二位の差は二分近く開きましたね。無敗の貴公子もここで名前を返上することになるんでしょうか』
「何てこと言うのよ失礼しちゃうわ!!」
つい、いつものテレビ観戦のくせでモニターに文句を言ってしまった。
わたしはハッとして隣に座るエースを見た。
無表情のままエースは番組を見つめている。

レイターが勝っても負けても一番辛いのはエースだ。無敗の貴公子は暴力の前にすでに負けている。
* *
プラッタ、あんたの機嫌が手にとるようにわかるぜ。
レイターは船に話しかけた。
さて、ルトツーだ。
本気出すぜ。ついてこいよ。
*
『マウグルアを追うエースのプラッタが間もなくルトツーの第一チェックポイントに到着します』
番組は滑走路へ降下するプラッタ一号機を映していた。
『ああっと低い。これは低い進入角度だ。市街地の安全規制にぎりぎり入ってるか? どうだ?』
興奮する実況のアナウンサーの隣で解説者が落ち着いて言った。
『入ってるな』
『さあ、これから着陸態勢に・・・』
アナウンサーの声が途切れる。
『え? 馬鹿な! 減速しない!! このまま突っ込む気じゃあ』
メロン監督がピットで叫んだ。
「無茶だレイター、やめろ! 車輪が折れる。スピードを落とせ!」
*
「ここいらでお時間稼がねぇと、ティリーさんに叱られちまうんだよね」
レイターが操縦するプラッタはルトツーの滑走路へ超低空飛行のまま飛び込む。
「うおりゃあぁ」
加速機のレバーを引く。
観客が息を飲んで見守る。
トップで飛んできたギーラルとはスピードがまるで違う。
スタンドの硬化ガラスが衝撃波の振動で大きく揺れた。
進入してきたときと同様、低空のまま、滑るようにプラッタの船体が駆け抜けていく。
『しゃ、車輪はどうなっていたんでしょうか? 一度は着陸しないと無効になります』
スロー映像が流される。
『かすっています。間違いなく滑走路に接触しています。いやあ、それにしても捨て身の操縦でしたね』
『う~む、さすが無敗の貴公子はあなどれないねぇ。あの接地のタイミングを読み切るのは、只者じゃないよ』
解説者が感心した声でうなった。
* *
そんな馬鹿な。
トップを飛ぶギーラル社のオクダは状況がよく飲み込めないでいた。
エースのプラッタが目視で確認できる。いつの間に追いついたんだ?
ルトツーに入った段階では二分近く開いていたはずだ。
何があった? 自分は全くミスの無い飛ばしをしているのに、なぜ?
* *
プラッタ、あんたいい奴だな。

針ほどの揺れにも反応するシビアな設定にレイターの感覚が共鳴する。
こいつは俺の要求に余すこと無く応える銀河最速の船だ。
このまま『あの感覚』まで飛び込めれば最高だ。
* *
後ろから追い詰められるオクダは次のチェックポイントまでの最短距離を確認した。
「第二チェックポイントまであと二十四秒」
ルトスリーの三次元チェックポイントは衛星軌道上に設けられた三つのポイントに囲まれた空間を通過する。
3Dモニターのグラフ上をなぞるように走る。このラインを飛んでいる限り抜かれることはない。
「進入角度二十三度」
ナビゲーションシステム読み上げるデータを聞きながらオクダは確信した。
これ以下の深い角度での進入は不可能だ。
「ポイントまで十秒、九、八・・・」
* *
クロノス社のピットにレイターの声が響いた。
「S1の警告アラートは五秒で失格だったな、メロン監督」
「そうだ」
「やっぱ、つまんねぇな」
レイターとメロン監督のやりとりはピットの奥の控え室にいるティリーにも聞こえていた。
ティリーはいら立った。

レイターはこんな時に一体何を言っているのだろう。
S1では安全策として急接近の警告アラートを五秒以上鳴らしたら失格になる。
レイターの声の後ろで警告アラートがビービーと鳴りだした。
見る間にレイターのプラッタはマウグルアに近づいていく。
速い。
いや、近づきすぎでしょ。
モニターに向かってティリーは思わず叫んだ。
「ぶつかるわ!」
* *
「プラッタ、いくぜ」
レイターは目を細めた。
「十秒、九、八・・・」
カウントダウンにかぶせるように警告アラートが鳴りだした。
ルトスリーの三次元ポイントは自由度がきく。
「チェックポイント進入角度二十五度」
パワーバンドに目をやりながらアフターバーナーを点火するタイミングを計る。
* *
「まさか」
オクダは血の気が引くのを感じた。
エースは自分よりさらに深い進入角度で突っ込んでくる。このまま行ったら間違いなくぶつかる。
「後続機との距離百五十」
接近を示す警告アラートが鳴り響く。
五秒鳴らしたらエースは失格になる。
これは、チキンレースだ。
「チェックポイントまで五、四・・・」
カウントダウンの一秒が長い。操縦桿を持つ手が震える。
「駄目だ」
オクダは操縦桿をわずかに外へ切った。
* *
レイターは叫んだ。
「いただき!!」
アフターバーナーのスイッチを押しながら操縦桿を内側に引く。
ギュンッ。
コクピットがきしむ。横Gがかかる。
くっ。
奥歯を噛み締めながら操縦桿を立て直す。わずか一ミリのずれが命取りだ。
急激なGに意識が持っていかれそうになる。
「やられてたまるか、俺は銀河一の操縦士だぜ!」
インコーナーをとる。
オクダの横をギリギリですり抜ける。
警告アラート4秒95。
プラッタが首位へと躍り出た。
* *
『闇の制御室』でモニターを見ていた小太りの男は思わず立ち上がった。
無敗の貴公子の鮮やかなライン取り。
「ばかな。エースの腕を折ったんじゃないのか」
痩せた男がいさめた。
「腕を折ったかどうかが問題ではありません。今、クロノス社がトップにいることが問題です。ご安心ください。作戦は何重にも用意されています」
「では、次は『作戦B』か」
「そう。エースのプラッタを撃ち落とします」
* *
「きゃあ、やったー。レイターえらいっ!」
興奮しながら拍手をしたティリーはあわてて手を打つのを止めた。
隣に座るエースの表情が沈んでいる。
「完全に僕の負けだ」
「な、何を言ってるんですか?」
「これは彼の飛ばしじゃない」

エースはモニターを食い入るように見つめた。
「右旋回の進入タイミング。左翼を少し下げる癖。僕の操縦をそのままを再現している」
エースが飛ばしていることになっているのだからレイターがエースの操縦を真似するのは当然のことだと思う。
でも、おそらくそれは、エースの表情から察するに、技術的に難しいことなのだ。
「レイターは君に何も話していないんだね」
エースの言っている意味がよくわからない。
エースはわたしの目を見て言った。
「無敗の貴公子なんて嘘さ。僕は前にも彼に負けているんだ」
「えっ?」
わたしは耳を疑った。
「五年前の話だ・・・」
* *
エース・ギリアムが初めてレイターのことを耳にしたのは、ちょうど無敗の貴公子と呼ばれ始めた二十歳の頃、今から五年前のことだった。
劇的なS1デビューから二年。
エースは向かうところ敵なしだった。
クロノスのレース仕様技術部、通称レース部に所属しながら、大学で経営学を学ぶ。
何もかもうまくいっている。
人からもうらやましがられた。
しかし、幸せであればあるほど、エースは不安を抱いていた。
頂点に登った者に残されたものは、維持するか下るしかないのだ。
テストパイロット部に上手い新人がいる。という噂を聞いたのはそんな頃だった。
才能がある人材はテスト部からレース部へ引き抜く。
噂の新人の名はレイター・フェニックス。
人事部の社員データベースを検索すると、まだ少年の面影を残す顔写真と共に経歴が打ち出された。

氏名:レイター・フェニックス
性別:男
年齢:十八才
最終学歴:公立ハイスクール中退
資格:宇宙船限定解除免許
家族:なし(身元引受人 銀河連邦軍ジャック・トライムス将軍)
志望の動機:宇宙船が好きだから
所属:営業部
エースは無意識のうちに左手の人差し指で机をコンコンと叩き続けていた。気持ちが落ち着かない時の癖だ。
彼はパイロット採用ではなく一般入社で、テストパイロット部ではなく営業部所属だった。
そして、十八才で限定解除免許を持っている。
子供の頃から宇宙船を操縦している自分でさえ、星系外を飛ぶための大型免許を取得するにはこれから専門コースで宇宙航法を二年は勉強しなくてはならない。
限定解除に至っては十年の実務が必要だ。
それをどうしてハイスクール中退の彼が持っているのか。
そもそも、うちの会社がハイスクール中退という人間を採用していること自体が驚きだった。基本的に保守的な会社なのだ。
エースは身元引受人の欄を指でなぞってつぶやいた。
将軍のコネということか。
しかし、将軍の力で入社はできても限定解除の免許はとれない。
一体彼は何者なのだろう。
*
レイター・フェニックスとの出会いは思わぬ形でやってきた。
その日、僕たちレース部はテスト部と共有するコースで練習する予定になっていた。
雑誌の取材が長引いたため少し遅れて到着すると共有コースが閉鎖されレース部とテスト部が集まってもめていた。
「一体、何があったんだ?」
「ウクランが事故ったんですよ。幸いけが人はでませんでしたけど、S1機が一機おしゃかになりました」
ウクランはレース部のベテランで、ワークスのレースに何度も出場している中核と言える選手だった。
「ウクランが? めずらしいな」
「テスト部がパワーバンドの設定をミスったんです。ところがあいつらそれを認めなくてウクランの技術のせいにするんですよ」
輪の中心へと進む。
「だからあんたの腕が下手くそだっつってんだよ!!」

ウクランに向けて大声を出している若者がいた。レイター・フェニックスだ。
「パワーバンドを三に設定したら壊れるに決まっているだろう。テスト部のミスだ」
「俺はいつも乗ってんだ。壊れたことなんてねぇよ」
「信じられるか」
*
にわかには信じ難い話だった。
S1最速と言われる自分でも、パワーバンドの設定は五にしている。
三に設定しても操縦できる自信はある。
しかし、故障のリスクを考え監督の指示通り五にとどめていた。
僕の心は激しく揺さぶられた。限界の世界を体験したい。
*
テスト部のメカニックが声をあげた。
「レイターの言うことは本当だ、我々が三に設定したんだ」
「何だと、テスト部の分際で!」
「関係無いだろ、レース部が何様だ!」
レース部とテスト部の間にたまっていた目に見えないしこりが、形あるものとなって爆発していた。
「喧嘩なら受けて立つぜ」
うれしそうな顔をしながらレイター・フェニックスが袖をまくった。
*
「喧嘩じゃない、勝負をしよう」

僕の声にその場が静まり返った。
「無敗の貴公子さんじゃん」
レイター・フェニックスは値踏みするような視線で僕を見て笑った。
「相手にとって不足なしだ」
*
共有コースが閉鎖されているため、レース部のコースを使うことになった。
パワーバンドを三に設定したS1機で競争し、負けたチームが今回の事故の責任を負う。
僕は久しぶりに気分が弾んでいた。
パワーバンド三なら自らのタイムレコードを更新できる可能性がある。
気になっていた新人の腕も見ることが出来る。
さらに上手くいけばレース部とテスト部の溝を埋めるチャンスになる。
一石三鳥だ。
*
テスト部も盛り上がっている。
「レイター、頼むぞ」
メカニックは興奮しながらS1機のパワーバンドを三に調整し、テストパイロットたちはレイターに細かくコースの説明を繰り返した。
*
そして、バトルが始まった。
スタートした瞬間エースは驚いた。
新人の加速やライン取りは絶妙だった。まるでS1のレーサー並みだ。
気が引き締まる。
そうだ、彼は限定解除免許を持っているのだ。侮ってはいけない。
横に二機並んだまま重力圏を突破する。
初めてのパワーバンド三。
思った通りエンジンの調子は普段より格段にいい。
飛ばしは最高だ。
しかし、船にとっても自分にとっても初めての体験、うかつなことはできない。
小惑星帯に突入した。エースが先行する。
「さすがエース。新人は口ほどにもないぞ」
地上でモニターを見ていたレース部が盛り上がる。
*
自分を先行させているのはおそらくレイター・フェニックスの作戦だろう。彼はこのコースを初めて飛んでいるのだから。
それならそれで自分は自分のペースで飛ぶだけだ。
エースは操縦桿を握り直した。

後ろの船はぴったりと僕の後を追ってくる。
小惑星をぎりぎりでかわすラインに乱れがない。
見事だな。
今のレース部でここまでついてこられるレーサーはいない。
しかもパワーバンド三。
相当な腕だ。
船の能力は同じ。
であれば、勝負をかけてくるのは、最終チェックポイントのコーナーか。
「最終チェックポイントまであと二十秒」
もうすぐだ、抜かさせない。
突然、警告アラームが鳴り響いた。
「後続機との距離百」
何だと。
後ろの船が猛加速で近づいてくる。
バカな、チェックポイント前のストレートで追い越しをかけようというのか。
定石を無視した飛ばしに、一瞬パワーバンドを失念した。
いかんあわてて立て直す。
コンマ数秒もたついたエンジンはすぐ回転を取り戻したが、この隙にレイターの船は横にならんだ。
最終チェックポイントを同時に抜け、大気圏に突入する。
滑走路の上空五十メートルに設けられたゴールラインが目前に迫る。
*
地上ではテスト部とレース部が集まって空を見上げて待っていた。
点のように見えた二機が轟音と共に近づくと、あっと言う間にゴールラインを通過した。
「どっちだ」
「わからん」
「同時か?」
目視では判断できなかった。全員の視線が計測器に集まる。
青いランプがついた。
「レイターの勝ちだ!!」
「そんな馬鹿な」
テスト部がお祭りのように大騒ぎを始めた。
「やったー!」
レース部、それも無敗の貴公子に勝ったのだ。
パワーバンド三で飛ばしたレイターのタイムはエースの記録を塗り代えていた。
二機が地上に戻ってきた。
船を降りたレイターがテスト部の仲間にもみくちゃにされながら言った。
「事故の責任はレース部がとれよ」

「その必要はない」
低い声が響き、コースは静まり返った。
初老の男性が近づいてきた。メロン監督だった。
「何でぃ。約束は守れよ」
「レイター・フェニックス。君は失格だ」
「あに?」
「接近警告アラートを五秒以上鳴らしたものは危険行為で失格となる。これはS1のルールだ」
そう言ってメロン監督は航行データを示した。
最終チェックポイント直前で追越しをかける際に、五秒ちょうど警告音が鳴ったことが記されていた。
「俺の操縦マニュアルじゃ、接触しなけりゃ危険行為じゃねぇぞ」
「レースにはレースのルールがある。事故の責任はテスト部で取ってもらう」
二人の対決は後味の悪い結末となった。
* *
ティリーは呆気にとられていた。

レース部とテスト部の仲は今もよくない。でも入社前にこんなことがあったなんて知らなかった。
「その後レイターに処分がでたんだ」
「処分?」
「社内を騒がせたとして、三カ月の減給とテストパイロット部への出入り禁止。そして、彼は会社を辞めた」
わたしは勘違いしていた。
彼が今回の仕事に気乗りしていない理由はエースへのコンプレックスなんかじゃなかった。
彼は自称ではなく本当に『銀河一の操縦士』なのだ。
「あのバトルを言い出したのは僕だ。僕が負けを認めればよかったんだ。なのに、何も言うことはできなかった。駄目な人間さ」
エースが力無くつぶやいた。
「そんなことありません! そりゃ、レイターは操縦はうまいですけど、彼は特別なんです」
「特別?」
「特別、変なんです」
エースが吹き出した。
わたしは調子に乗って話を続けた。
「性格が崩壊しているというか、最低最悪。人間的にもどう見てもエース専務のほうが素晴らしいです」
ずっとあなたに憧れて、そしてわたしはこの会社に入社したのです。
と言おうと思った時、思わぬ事をエースは口にした。
「ミラーボールが落ちるように仕掛けたのは僕なんだ」
「へっ?」
その告白にわたしは心臓が止まるかと思うほど動揺した。
「自分が軽いけがをする位置に落とそうとしたんだ」
「ど、どうして?」
エースは心にためていたものを吐き出すかのように一気に話し始めた。

「無敗というプレッシャーがこれ以上続くことに耐えられなかったんだ。それでも、辞めるわけにはいかない。そんな時に脅迫状を見て、これだ、と思った。第三者による不可抗力で無敗が止まるというのは理想的だ。僕だっていつかは負ける時が来る。その時に売上へ与えるダメージのことはいつも考えていた。ケガであればブランドイメージを壊さないでプレッシャーからも解放される。それは会社にとっても必要なことだと思うようになったんだ。馬鹿だとののしってくれてもいい」
わたしにはエースを責めることはできない。
エースはただのレーサーじゃない。
彼は広告塔であり、かつ経営者だ。自分で責任を取らなくてはいけないのだ。
しかし、こんな重大な秘密を聞かされてどうすればいいのだろう。『王様の耳はロバの耳』と叫びたいプレッシャーに襲われる。
わたしの気持ちに気が付いたエースが謝った。
「すまない。このことはレイターが知っている」
「レイターが?」
「彼はステージの僕を助けに来た時、僕がポケットに隠していた遠隔装置に気づいて抜きとったんだ」
警察が必死で探している遠隔装置のことだ。
「ミラーボールが落ちた後の会議で彼が僕に何と言ったか覚えているかい?」
わたしはうなずいた。
レイターは『襲われたいのは勝手だが、守っているほうは命がけだ』と言った。

「あの時、彼は僕だけに遠隔装置を見せたんだ」
エースにかざしていたあの手のひらの中に遠隔装置があったのだ。
「強烈なメッセージだった。二度と馬鹿な真似をするな。巻き添えを食うのは他の人間だってね。そうしなければばらすぞ、という脅しでもあったと思う。わかっただろ、僕は弱い人間なんだ」
わたしはエースの手を握った。
そこにいたのは雲の上の人でも何でもない、わたしと何ら変わらない普通の人間、エース・ギリアムだった。
・第一話からの連載をまとめたマガジン
・イラスト集のマガジン
いいなと思ったら応援しよう!

