
【☆89話☆】12/7中京11R・中日新聞杯(バイトリーダーN)
若者とのジェネレーションギャップは、ここ10年は感じつつも「しょうがないか」と昇華が常も、今回喰らったギャップはなかなかの殺傷能力。もちろん、一般人は何とも思わないだろう事なのだがさて、その事象とは? ぜひご覧ください! #中日新聞杯
今年も、年末の風物詩のひとつである、「流行語大賞」が発表となったが、違う意味でビックリ。
オラも、今年1月~3月。
かつて経験した事のない激震に、プライベート面で毎日苦悩に悶々としたこの時期。そんな地獄の日々の最大の清涼剤として、この「ふてほど」を毎週楽しみに視聴していたが、視聴率7.8%。お世辞にも大衆娯楽とは言えなかつたが、オラはそんな「全国民の7.8%」の一人として視聴していた。
ドラマ自体はたいへん面白かった。
舞台の一角となった1986年。当時、オラは小学生高学年の毛が生える一歩手前のクソガキながら、この時代を全力で生きた者としてはこのタイムスリップはとても共感。というか我々ナイスミドル世代は、誰が見ても共感できるだろう、クドカンらしい仕上がりだった。
今のドラマにしては珍しく「テーマ」をハッキリと主張させた作りは、いわば演劇・劇作としての基本であり、オラも大学の人形劇サークルに所属していた頃は、この話の「テーマ」は何か? そしてその「テーマ」は明確に劇に反映されているのか? という概念にとても拘り、テーマもなくダラダラと垂れ流しされる話がダイキライで育ったこともあり、最終話である「世代間ギャップ、およびそれに翻弄される人々に、みんなどうか寛容であれ!」という最もクドカンが言いたいテーマは程よく伝わった良作だった。
しかし、オラも阿部サダヲ同様に、このドラマを「ふてほど」と称したことは一度もない。今知った。
このドラマ、780万人が観たかもしれないが、それを「ふてほど」と略して発信していた媒体はなかっただろうし、あったとしてもそのアナウンス能力は恐ろしいレベルの極小であり、恐れ多くも流行語大賞にノミネートされるものではなかったと思料している。

でも、選ばれた。選ばれて「ふてほど」という単語を知った。
発表直後、ネット上では、選考委員のやくみつるに対しての「叩き」が始まり、彼がハマったものが毎年次々に大賞となっていく近年の傾向を「やくみつる大賞」だろ?と揶揄され、トレンドワードにも「やくみつる大賞」と祀りあげられたのだが、当のやく氏は、この選考に対する「タネ明かし」的な意味で、下記のようにコメント。
やくみつるさんに厳しいこと言います
— こーるど (@starlight_0180) December 2, 2024
そういう評論は他所でやってくれ
流行語大賞はただその年流行った言葉、その年の新語を選ぶだけでいいんだよ
選考委員は世論を俯瞰して流行ったやつを選べばいいんだ
個人的なお気持ちを吐き出す場所では断じてないよ#流行語大賞 pic.twitter.com/u4AuVpmRsI
愕然とした。お前、それただのドラマの宣伝隊長であり、流行語大賞の審査員としてのスタンスで臨んではいないではないか?
新語・流行語大賞というのは、その浸透具合から極めて普遍的なことが大前提。だから選別が「ああそうだよな」と受け入れられるのであって、やくみつるが作為的に「流行っていないものを、敢えてメッセージ性を込めて」ぶっ放したものなんて、そんな穴狙いが通用する「お前の遊び場」ではないんだよ。
みんなに支持される1番人気を選びましょう!という会なのに、あえて12番人気に◎を打って、勝手に1着にして、国民困惑の中やくみつる一人が「やってやったぜ」とドヤ! これ、もはやファシズムだぞ。
もう、そんなのひとりで有馬記念でやってくれ。カラテにでも◎打って一人で騒いでくれや。独自の穴狙いが1着になる場所では、ないんだよ。

この「ふてほど」によって、せっかくの良いドラマが「困惑の象徴」となり、いちファンとして泥を塗られた気分で一杯。「楽しかったドラマだったなぁ~」という気持ちで10年後あたりに振り返りたかったのに、この「ふてほど」によってそれも不可能になってしまった。なんか桃鉄でいう「貧乏神」にとりつかれたようないらねぇ気分であり、おそらく同じ気持ちでいるだろうドラマ制作者・演者たちがとても不憫でならない。

そして、この暴挙により、この「流行語大賞」という企画・概念が国民感情とはまったくズレた、意義を成さないものへとなり下がったことで確定の赤ランプ。
思えば、2015年の「トリプルスリー」のあたりから、「ん?そうかい?流行ったかこれ?」と審議の青ランプだったものの、これが逸脱のプロローグだったのかもしれない。
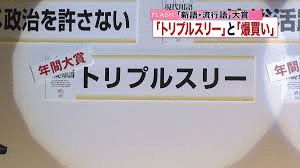

この時から、表彰式に登壇した「流行語を象徴する人」も「ほんとに流行したのかこれ?」と当惑の表情を浮かべ、なんかイヤイヤ担ぎ出された感も容易に読み取れるようになった。やくみつるの遊び場になってきた「初動」がこれ。
時代を、一年を象徴してきた名イベントが、こうして「どうでもいいもの」になっていく。風化ならまだいいよ、それもまた時代だから。しかし今回は独裁者の穴狙い根性によって歪曲されて堕ちたのが残念極まりないし、もうそもそも時代は流行語を必要としないほど、活力のないものへとなっていったのかもしれない。
大衆みんなで楽しむ娯楽ではなく、自分だけが楽しめればよいものへ。
それゆえ「流行」など、それほど起き得ない時代なのかもしれない。

そろそろ「流行語大賞不要論」も巻き上がるだろう。
今後も、この迷走と斜陽ぶりをしかと見届けていきたい。それしかもう楽しみがないよこれ。
そんな中、「大衆娯楽」といえば、大晦日に根強く「NHK紅白歌合戦」が今年もオンエアされ、出場アーティスト達も事前に発表されたが、

このニュースは、ちょっと看過できず。オラにとっては結構なパンチ力だった。
我々世代が、良く知らない若いアーティストを見るたびに、「誰コイツ?」と当たり前のようにこき下ろすことが、いつも「知ることへの第一歩」「最高のキッカケ」だったのだが、いまは若い面々が「イルカって誰?」
まあ、そらそうだろうけれど…イルカだぞ? なごり雪だぞ!?
確かにオラも、この「なごり雪」とは、半世代くらいズレている。
けれど、当たり前に受け継がれ、受け入れ、確実に己に染みたこの曲が、1世代下の者たちからは「イルカ誰やねん?」かぁ…。
オラがこの曲に出会ったのは1992年。
高校3年生の秋。進学校だっただけに、もう学校行事たるものはすべて1学期に終わらせ、完全受験勉強モードとなっていた中、唯一の息抜きとして組まれていた「最後のバス遠足」で、15歳年上だった担任の化学の先生が、バスでこの曲を熱唱したことで、クラス全員が一斉にこの曲を認知。
またその歌いっぷり・美声もものすごいものがあり、仙台の某トンペー大学時代には、各大学対抗のアマチュアバンド大会にもエントリーして、準優勝した強者であり、このとき優勝したのが、東北学院大学からエントリーしていた大友康平率いる「HOUND DOG」だったというのだから、この先生も肩書通り「優勝に準ずる」歌唱力は搭載していた。
この先生まバスでの熱唱が、言わばこのなごり雪が「歌い継がれた」瞬間であり、すっかりシビれたオラは、バスを降りた後も原曲が聴きたくて、勉強そっちのけですぐざまレンタルCDショップにチャリを漕いだことを記憶している。
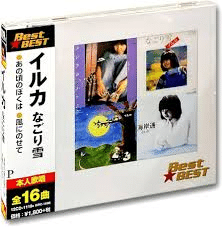
そんな「歌い継がれている」ハズのなごり雪が、イルカが「誰やねん?」扱い。これはかなりショックだった。いや、一般的にはそれほどショッキングなニュースの部類ではないのかもしれないが、オラにとってはショックは強かった。
歌い継がれるべきものが、そうなっていない。
この目論見違いもそうだが、それを引き起こしている時代の虚無さ、歌のチカラのなさ・衰退ぶりに愕然としたんだ。
…がしかし、振り返ればオラも高校時代、紅白の出場歌手一覧を見て、
「アンディ・ウィリアムスって…誰だよ!?」
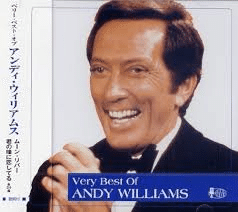
と、一人デカイ声で突っ込んでいて、笑いを取っていたことを思い出した。
…一緒か、これ。言いたいだけなんだな。
というワケで、若者よ。まずイルカを聴いてくれ。
さぁ、中日新聞杯。
◎⑤トーセンリョウ
◯③キングズパレス
△②⑧⑨⑩⑭⑮
明日は香港国際競走がシャティンで組まれていて、3週前に団野タイセイが初G1制覇をもたらしたソウルラッシュも、なんと中2週で香港へ。
19年前の2005年に、マイルCSを制したハットトリックがその勢いそのままにこのスペシャルローテーションで香港のマイルG1を連覇したことがあるが、ソウルラッシュが香港で勝てば、それ以来の快挙。
ただこの時は、鞍上は日本~香港ともともにO.ペリエと不変だったのだが、今回はチェンジ。その「チェンジされた側」の団野タイセイは日本に居残り。どういう経緯があるかはわからないが、団野タイセイはマイルCSでの勝利インタビューで「こうして依頼をいただいた事は嬉しかったし、絶対やってやろうと思っていた」という語り口からは、最初から富士S→マイルCSの国内2戦を依頼し、香港マイルは従前よりモレイラにオファーしていたのかもしれない。春のローテーションも団野タイセイとモレイラを併用していたことからも、この推察は可能。
ただ真実は解らない。団野タイセイとしても、勝って香港に行きたい、ソウルラッシュに乗りたいという思いはゼロではなかったハズ。
ただ、「捨てる神あれば拾う神あり」とよく言ったもので、栗東の池江センセイが捨てても、美浦の加藤征弘センセイは放っておかない。
検索条件:団野タイセイと加藤征弘厩舎の全成績

美浦のリーディング7位のトレーナーと、関西の若手ジョッキー。
それほど接点はなく、ここまで12回しか騎乗依頼していない薄い関係なのだが、それでも加藤センセイは「伸び盛り」の若手を見る眼は鋭く、団野タイセイが東京・中山に乗りに来るときには、積極的にオファー。12回の騎乗のうち10回が今年のオーダーであり、ついにこの◎トーセンリョウで、団野タイセイは加藤厩舎で初白星を献上。ますますこの二者の関係は蜜月になりつつある。
◎トーセンリョウも若い頃から能力こそあったものの、一回レースに使うとダメージが残り引きずる虚弱体質だっただけに大事に大事に使われ、5歳秋なのにまだ11戦。デビュー2連勝で3歳の春に1勝馬クラスを勝った時でも、加藤センセイはクラシック路線に乗せる事はせず、焦らずに長期休養したのはある意味大英断。
とはいえ、市場取引価格2億2000万円の高額馬。
これを預かった立場としては、馬の事を考えながらも、せめてプラス収支にするべく賞金の上積みは命題であり、まだ1/3の7300万円しかJRAから回収していない「赤字馬」であり、カニトップオーナーには頭が上がらないところだろう。
その証拠に、ムルザバエフ、武豊、川田ユウガと5歳になってから一流どころばかり乗せているが、猛暑で熱中症になったりとなかなか結果は出ず、ようやく10/20の東京の3勝馬クラスで、団野タイセイにオーダーしたが、道中クソスローながら後続を0.3秒突き放す内容は、5歳秋にしてようやく訪れた本格化の訪れと断言して良い勝ちっぷりであり、団野タイセイも「返し馬でも背中の良さ、キャンターの柔らかさは感じました。レース内容も良かったし、完勝でした」とべた褒め。
加藤センセイもこれには相当ご満悦で安堵だったのか、この昇級初戦の重賞挑戦もヤネを替えることなく、引き続き団野タイセイにオーダー。シビアに信賞必罰。それゆえ結果を出してくれた鞍上は引き続き頼む。ごく当たり前の姿勢なのかもしれない。
そんな団野タイセイも中京の重賞といえば俺。と思っているだろう。JRA初重賞制覇も、初G1制覇も中京であり、2年前のこの中日新聞杯も18頭のフルゲートの1枠①番という厳しい条件の中、5番人気のキラーアビリティーを後方馬群13番手の中、狭い直線をこじ開けて、ラストは鋭い伸び脚で1着ゴールという味な競馬で単勝7.6倍を演出と、中京巧者らしい落ち着いた騎乗ぶりも光る。
ディープインパクト産駒の「実質ラストクロップ」の現5歳世代で、ようやくオープンにのし上がってきた「最後の刺客」。やはりディープらしい切れ味自慢の馬であり、加藤センセイも「ハイペースだと道中脚を使ってしまうので、平均ペースの方がいいタイプ。坂は苦にしない」と、中京での躍進に期待するコメント。
逃げるのは⑧デシエルトの父ちゃんに、藤懸タカシの①ベリーヴィーナスが追走。このいわくつきの二人、あの事件以降、絶対にハナ争いでケンカをしてやり合う事のない「大人な二人」であることは、古馬3勝馬クラスの芝1400m戦線で、ベガリスとショウランラスボスが決して競り合わなかった2度の東京1400で証明済み。よってここも競り合わず、今度は何が何でもハナという父ちゃんに、藤懸タカシが競らずに今度は2番手と、こないだのベガリスが譲ってもらったゆえ、藤懸は仁義を通す。よって、ハイペースにはならない。これで◎トーセンリョウにとって第一関門クリア。
そして、この◎⑤トーセンリョウ。
どう考えてもハンデは56キロと推察されるのだか、今回なんと55キロ。完成した5歳牡馬が、3歳馬コスモキュランダより3キロ軽いのは相当にハンデキャッパーに見くびられた人為的ミス。他の有力各馬も軒並み重いハンデで、ここはその恩恵を存分に受けて立ちまわれる。
状態面は今が最盛期で、2週前に美浦坂路で3F37.5、1週前で37.9とド派手にデモンストレーション完了。直前は輸送を考慮して軽め。それでも3F39.0と抑えられない勢い。
さあ、あとは初重賞制覇で、カニトップオーナーの回収率を、ようやく獲得賞金を、市場購入価格の50%超えを達成してもらいたい。
当然、団野タイセイにとっては2年前の勝ち馬キラーアビリティのように、中団イン待機から、直線馬群をこじ開けるというミッションは大変だが、2年前に一度クリアしているのだから、できる!
相手筆頭は◯③キングズパレス。さすがに前走の天皇賞は相手が強かったが、G3となると相手なりに確実に走る。追い切り時計もここを目標にしているだけあって2週前から好時計。
今回は、年末ジャンボも発売されたし、ここはとてつもなく大きな配当狙いに、1等賞として3連単6点も買ってみたい。今まで、◎ショウナンバルディなり◎アイコンテーラーで、数々の奇跡のロォン!で読者さんたちを歓喜の渦に巻き込んできた暮れのボーナス重賞。今年も、やってやるぜ!
単勝・複勝 ⑤
馬連・ワイド ③-⑤(本線)
馬連 ⑤-②⑧⑨⑩⑭⑮(おさえ)
3連複 ⑤-②③⑧⑨⑩⑭⑮
3連単 ⑤→③→②⑧⑨⑩⑭⑮
いいなと思ったら応援しよう!

