207が2年前のサービスリリース以降、ユーザー獲得のためにやってきた事
いつでもどこでもモノがトドク、世界的な物流ネットワークを創りたい、207株式会社のイナバです。
弊社207が初めてリリースした『TODOCUサポーター』というプロダクトがあります。配送員を対象とした配送効率UPのためのアプリで、最近、急速に成長しています!!!(うれしい)
今回はこの『TODOCUサポーター』をリリースしてからいつ・何をやってユーザーを増やしてきたかをご紹介します!
ユーザー数10人期(2020年3月〜2020年8月頃)
とにかく機能を増やした半年間
プロダクトリリース当初、体制としてはCEOの高柳(PM)+ エンジニア3名の4人体制でした。(カッコつけて「開発体制」とか言ってるけど、そんな良いものではない 笑)
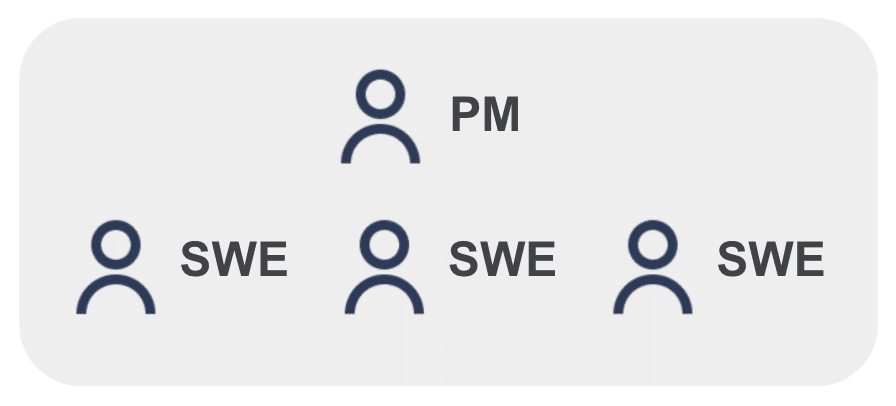
最初の半年は「とにかく機能を増やそう!!」ということに、リソースを割いてました。
QAエンジニアもいなかったので、バグだらけでもそのままリリースしていました…(後述しますが、Androidに関してはほぼ全く動かない状態でした…汗)
当時は機能が足りないことが課題と思っており、「競合アプリができることは全部できるようにしてからがスタート」と考えていたので、とにかく機能開発に明け暮れる日々…。
今振り返ると「機能をひたすら増やす」というのは、正しい判断ではなかったとは思います。どんな機能があればユーザーが使ってくれるかなど、よくわからないまま開発を進めていたな〜と思いますね。
もっとこうすればよかったと思うこと
では、どうすれば良かったのか、というお話ですが。
プロダクト開発の作法としては、「どんな機能があればユーザーの課題を効果的に解決できるのか」を定義して、そのユーザー体験を尖らせて、プロダクトを磨いていった方が、PMFの速度は上がったのではないかと思います。
(ユーザーインタビューに最初から注力しておけば良かった…)
リリースしてから改善するか・改善してからリリースするか問題
スタートアップにおいて、「プロダクトを磨いてからリリースする」か「とにかくリリースしてしまってからプロダクトを磨くか」というのは、1つの問いではないでしょうか?
207は、後者の方法を取ったのですが、それは間違っていなかったと思います。
というのも「自分たちで使ってプロダクトを磨く」という手法には落とし穴があって。
例えば、我々においては、リリース当初はほぼほぼ自分たちしか使っていなかったため、自分たちが持っている配送案件に特化したプロダクトになってしまっていました。
(東京の荷物密度が高い、同じ荷主さんからのダンボールしかない会社だと使いやすい一方で、共同配送している人や地方の配送員だと非常に使いづらいプロダクトになってしまっていた)
時間をかけてそういった落とし穴にハマると軌道修正が大変なので、早めにリリースしてユーザーの声を聞きながら改善できたのはよかったと思います!
今日はエンジニア陣と自社プロダクトを使った模擬配送🚚
— 高柳 慎也 | 207 | 物流Tech (@sinrush) April 25, 2021
実際に使ってみることで気づけなかった課題がみるみる出てくる👨🏫 pic.twitter.com/OJ67toyRsW
プロモーションがんばりはじめた期(2020年秋〜)
ASOをがんばってユーザー数が増えていく
これまでは、まったくプロモーションをしていなかったのですが、それでも少しずつユーザーは増えていました。プロモーションしていなかった時期にユーザーが増えた要因は大きく2つと考えています。
「住宅地図」で検索したら、App storeの下の方に出ていた
口コミ(ある地域でたまたま1人にインストールされると、その地域でユーザーが2人、3人と増えていくというようなことがありました。おそらく、配達の現場で配送員同士が「何使ってるの?」みたいな会話があって口コミでも広がっていたのだと思います。)
その後、ユーザー数を増やすために力を入れたのは、ASO(App Store Optimization)です。
ASOとはApp Store Optimizationの略称で、アプリストア最適化のことを指します。
(「どれくらい伸びたのか」はなかなかオープンにはできないのですが、「結構伸びた!」という事のみご共有します…)
ASOはもっと早くやっておけばよかった?
ASOに力を入れることでユーザー数が増え、吸い上げられるユーザーの声が増えたため、サービス改善につなげることができました。
そこで出てくる「ASOにもっと早く取り組めばよかったか?」という問いに対してはYesともNoとも一概には言えないのですが、、、結論、Yesだった気がします。
ただ、もし時を戻せるとしたら、そもそも最初からiPhoneとAndroidどちらもリリースすることはしなかったと思います。
まずはiOS版のみリリースして、ASOに最初から取り組んで、ユーザーを増やし、プロダクト改善を重ね、ある程度プロダクトのクオリティに自信が持てた段階でAndroidに展開した方がよかったな〜と、今になって思います。
アクティブユーザー増えてきた期(2021年1月くらい)
最初は機能をひたすら増やしていたのですが、その後方向性を変えて、ユーザー観察・プロダクト磨きに注力してきました。
そこで僕たちは不可解な事象を観察することになりました。圧倒的にiPhoneのアクティブユーザーの方が多かったんです。(?????)
「配送員の方はAndroidユーザーの方が多いので、そんなはずない…!!」
というわけで、調べてみるとAndroid版のアプリがバグだらけで動いてなかったことが判明しました…(やばい…)
QA担当がいなかったのと、当時の207のメンバー全員がiPhoneユーザーだったので、そもそもAndroidの動作確認をしていなかったことが主な要因です(やばい…)
そこで、「QAというフローをつくりましょう」ということになり、体制を整えた結果、2〜3ヶ月で一気にAndroidユーザーも増やすことができました。
UI・UXを磨く期

いろんなボタンを押してから離脱する人多い問題
ユーザー観察を通して他にも気づきがありました。
それは、「アプリをダウンロードしてからいろんなボタンを押して操作を試みようとしたあとにチャーン(離脱)しているユーザーがけっこういる」ということです。
必要な機能は揃っているのに!!!!!
ということで、
次に、機能の組み合わせやUIデザインを改善することでUXを向上させることを目指しました。
UI・UX改善を目的としたPDCAの回し方
「どのように改善していったのか?」という点ですが、UX改善はデータを見ながら実行していきました。
例えば、TODOCUサポーターを配送員の方が使用するときは以下のようなフローです。
アプリをダウンロード
アプリを開く
荷物登録完了
荷物配送完了
で、何をやったのかというと。
各フローの数字を追うことで、操作のどの段階で躓いているユーザーが多いかを特定し、その部分を改善して再度数字を見るといったサイクルで改善していました。
(他にも、どれくらいの割合のユーザーが何日連続でアプリを開いてくれているかなども同時に確認して改善)
併せて、「存在しているのに誰からも押されていないボタン」を特定して改善しました。使われていないボタンを特定したら、以下のいずれかのアクションを実行します。
①そもそも使われない機能の場合
→機能自体をなくす
②必要な機能ではあるものの、わかりづらいため使われていない場合
→UIを改善する
UI・UXにはいつからこだわるべきか?
もちろん、できることなら最初からUI・UXデザインに取り組むべきでした。当時はそれができる人材がいなかったので仕方なかったなあとは思います。
おわりに
振り返ると、、、
①ユーザー分析
②プロモーションがんばる!
③UI・UX改善
を地道にやっていくことで、ユーザー数が増えてきたと感じています。
以上、207がサービスリリースしてから、ユーザーを獲得するためにやってきた事でした!
現在、そんな207ではあらゆるポジションで絶賛採用募集中です!!!!!!
本noteを読んで「ちょっとこの会社の事を調べてみようかな」と思って頂けた方はまずは、コチラの動画を見ていただけると会社の事がよくわかるかもしれません!(1:55:15~)
その後、「207に興味が出てきた!」という方は、カジュアルに面談でもしましょう。
もちろん、直接の採用応募も、とっても嬉しいです!
本当の最後に
本記事を「よかった!!」と思っていただけたら代表のツイートにいいねやRT、コメントなどで応援していただけると一同、喜びながら小踊りします…!
サービスリリース以降、約2年間の開発体制の変遷やユーザー獲得施策について公開しました!!https://t.co/t6xmT2fKO6
— 高柳 慎也 | 207 | 物流Tech (@sinrush) April 27, 2022
