
20220411『熱帯』と「熱帯」と熱帯
学生寮の5畳半。狭い室内に不格好な程大きな机。その前に座る上下ジャージの青年。それが私だ。そんな私の手元にあるのは一冊の本。青地の中心に島を模した両開きの本が浮かんでいる可愛らしい装丁。森見登美彦先生による長編小説「熱帯」だ。
読む前にカバーを外し、時計の前に置く。スマホの電源を切る。時間を忘れ、熱帯の世界を目にしつつ作品へと没頭するために。そこまでしなくても良いと思うかもしれない。けれど、これは私が「熱帯」に接続するための一種の儀式なのだ。私が読む限り、「熱帯の中の『熱帯』において明確な時間の描写はない。太陽が昇り、月が沈む世界ではあるけれど、そこがこの世界と同じ時間の流れであるという保証はない。だから私も時間のことは忘れるように心がけている。そんな準備を終えて1頁目をめくる。本の隙間から潮風が漏れ出す。そうして今日、私はまた「熱帯」への冒険を始める。
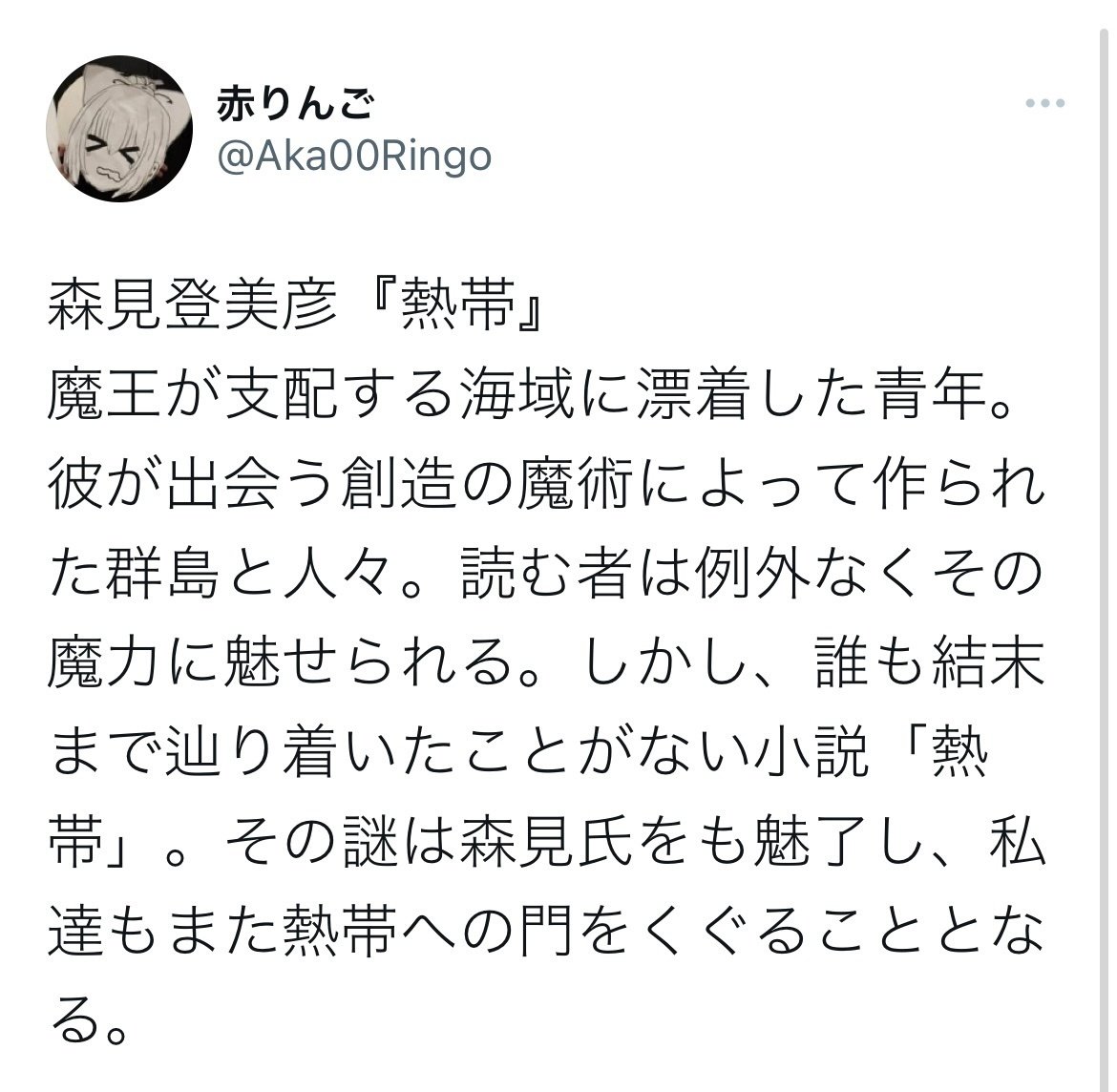
作内では、佐山尚一によって書かれた謎の小説『熱帯』を追い求める人々の姿が描かれる。ただ、ここで私が手にしているのもまた「熱帯」である。これはどういうことなのか。佐山氏の『熱帯』を元にして、森見先生も同名の作品を書くに至ったのか。作内では徐々に『熱帯』について語られていくものの、この「熱帯」は一体何なのかを正確に理解することはできない。作内の『熱帯』の存在と作外の「熱帯」の存在が脳内で絡み合い、読み進める毎に現実と非現実の境目が曖昧になっていくように感じる。
登場人物たちが追う謎を『熱帯』とは何なのか、とするならば、読者にはそれに加えて「熱帯」の謎が提示される。本を閉じ、『熱帯』の世界から離れたとしても、「熱帯」は変わらずそこに存在する。「熱帯」とは何なのか、という問いと共に。そこで初めて、私は自分が既に「熱帯」の中にいることに気が付く。この本を読み始めた時点で、内にも外にも熱帯の世界が広がり始めていたのだ、とも。本を閉じてなお、私の中で熱帯は成長を続けていく。そう言った意味で、「熱帯」は小説というよりも、物語という名前の生き物であるように感じた。それほど、「熱帯」からは生きようとする意志を感じた。
これはあくまで私の熱帯であって、他の人の熱帯とは異なるものなのだと思う。でも、魔王によって創造された島々のように、見えないだけで私の熱帯と誰かの熱帯は同じ海域にあるのかもしれない。ある日「僕」が上陸してきて、私の熱帯と誰かの熱帯が繋がることがあるかもしれない。そう考えると少し暖かくて面白い。
最後の一文を読んで本を閉じる。私は『熱帯』からの冒険を終える。高く登っていた陽も、既に沈もうとしている。部屋には見た事もないような植物が生い茂り、どこからか波の音が聞こえてくる。ふ、と息を吐き、私は机にぽつんと残されたパソコンを前にして文章を書き始める。
私の熱帯の門が開く音がした。
