
思慮深さに関する浅い雑記
免責事項
この投稿は、単純に私が「『AI』という単語を聞くたびになんだかモヤッとするなあ」という個人的な感情を垂れ流すものであり、私の所属するいかなる団体のいかなる活動をも否定する記事ではないことをあらかじめ断っておく。
君たちインターネットというのは本当に面倒くさい道徳を持つようになったね。
序論という名の日記
昨年末、仕事も私事もどん詰まり精神がまともではない状態になったので、年始1週間丸ごと有給を取った。今残されている有給は残り2日。風邪をこじらせたら終わりである。英気を養うために仕事から年末年始合わせて2週間程度離れることを選んだ。
まともではない状態になっていたので、諸隈元シュタインの著書を図書館で借りた。このあたりから私のような陰キャなひねくれものがまず間違いなくハマるヴィトゲンシュタイン哲学が再熱するわけだが、そもそも活字がまともに読めなくなっている状態なので、こうした紀行録をゆるく読むところからのリハビリが始まる。
基本的には紀行録だし、ツイッターで有名な物書きであるだけあって文章も読みやすい。ヴィトゲンシュタインが好きであるという点で著者とは気が合う。出不精であり、近年はいろいろな事情で著者と同じルートを旅行することは難しいが、今ちょうど「人生ミスったな」って思っていたので救われた。
その後、なんとか活字を読む方法を思い出したので、こんな本を読んだ。
エッシャーはいわゆる「だまし絵」を美術作品にしたことで有名であり、何年か前に東京で企画展があったと思う。この本は「不可能立体の数学的・幾何学的な特徴を使うだけでは、エッシャーの作品が成立しない。エッシャーは絵画技法を活用して不可能立体を芸術作品に昇華している」ということを著者の独自考察も含めて検討している。著者自身の仮説には「本当にそうか?」と思うこともなくはないが、3DCGモデルによる再現や透視図法の可視化などを踏まえて、それらの仮説の妥当性を主張する点は手が込んでいる。美術史学か数学の専門家なのかと思えば本業は生物学の研究者であり、つまりはシンプルにエッシャーのファンであるということなのだが、その熱意には感服した。
出かける元気が湧いたので、今日はモネを見に来た
「平日だしのんびり見られるだろう」と思っていたら、想定以上に人でごった返していた。日本人はなぜこうもモネやゴッホが好きなのか。印象派という1つのジャンルは、日本においてとりわけ人気だと思う。偏見かもしれないが。もちろん私も印象派は好きだし、小学校にはドガの踊り子のレプリカが飾ってあった。今思えばとんでもない作品が置かれていたものである。
ちなみに西洋美術館あるあるだが企画展のチケットを見れば常設展が見られる。常設展は比較的空いているし、何なら松方コレクションのモネの作品はこちらにも展示されている。常設展は何度となく足を運んだが、いくつか新規展示の作品があり、それに伴い作品のは位置も変わっているので、割と新鮮ではあった。
そして今は2年に1回ほど来るヴィトゲンシュタインに触れる。
早熟の哲学者も、晩成した名画家も、その裏には多くの草稿・習作の山がある。我々は成果物しか見えていないので、彼らがどれだけその成果物に時間をかけたのかを想像することをしない。
AIAIうるさいな、アイアイかよ
有給も中盤を消化し、来週から始まる生産性追求地獄に怯えている。
資本主義社会に生きる中で仕事をこのように呼ぶべきではない。むしろ「生産性向上」という困難な問題を解くために生きていることを歓び、感謝するべきなのだ。
ただ、人間という肉塊の能力は計算機ほど急激に進化できるものではない。「時間をかけて思索に耽る」ことや「1つの問題に何日も向き合う」こと、あるいは「特定のテーマに何年も向き合い取り組む」ことなど、時間をかけて熟成させないと「理解」ができないことが世の中には山程存在する。少なくとも私はそのように思っている。
生産性を上げるための「道具」として注目されるのが昨今の「生成AI」である。タイトルに挙げた通り「これからはAIの時代」らしい。ツイッターも4つほどフォロワーの投稿を見たら「生成AIで業務効率化!」みたいな広告が出るし、Instagramのフィードでも「なんでそんなに生成AIに詳しいの?→XXをフォローしているから」とか言うインフルエンサーがドヤ顔している。
「AIAIうるさいな」という文字列を打ったところで「アイアイ」が連想されたので大胆に脇道に逸れてやろうと思う。
日本では童謡で有名なアイアイという霊長類だが、分類学上アイアイ科アイアイ属のアイアイらしい。何より「AI-AI」ではなく「Aye-Aye」である。初手からAIではない。まじかよ。和名がユビザル。まじかよ。
アイアイ(指猿[8]、英: aye-aye、学名: Daubentonia madagascariensis)は、哺乳綱霊長目アイアイ科アイアイ属に分類される霊長類。現生種では本種のみでアイアイ科アイアイ属を構成する。別名ユビザル(指猿)。
アイアイの生態として面白い特徴に中指が長いことがある。それも細長い。これはなにかの偶然だろうか。私は昨今の巷がAIで騒いでいるところにちょうど中指を立てたかったのだ。逸れた脇道から強引に立ち戻る。
ここ3年で「AI」という略称が嫌いになった。これは個人的な感情であり、嫌悪感の半分は、昨今の大規模言語モデルの発展と精度向上が、自分の持つ能力を追い越したことへの不快感、もう半分は「これからはAIの時代だ」と囃し立て、焦りを煽る思考停止人間たちへの不愉快さによる。
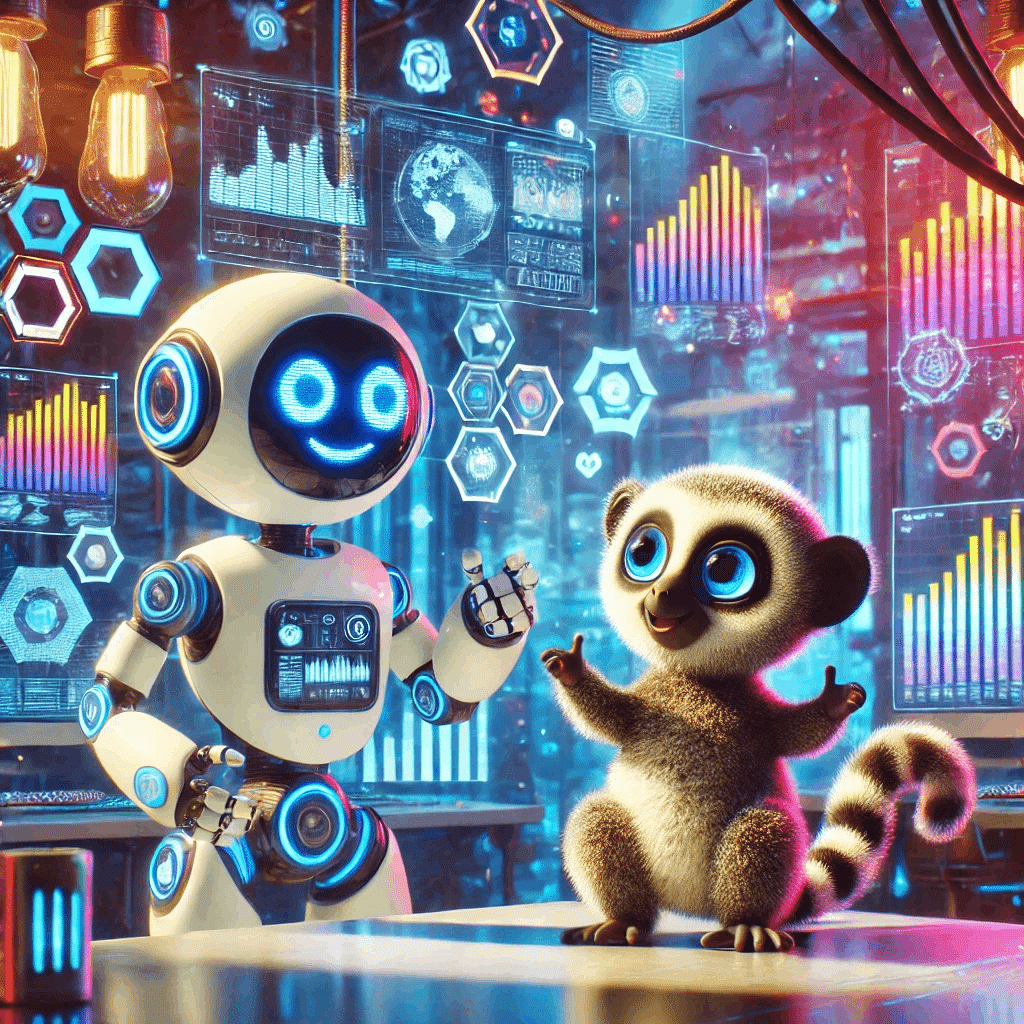

前者に関しては「思考のアウトソーシングが楽になった」ということの裏返しである。自分の頭で考えること(あるいは悩み苦しむことでもある)を「脳に汗をかく」などと喩える事があるが、人類はとうとう脳にエアコンを常備するようになった。与件を示して「それっぽい文章を書け」と命じれば、それっぽい文章が「AI」によって生成され、その内容は妙に「信じたくなる」記述になっている。この妙に信じたくなる生成結果にいちいちイライラするのだ。
これだけ提示された情報が確からしく思われると「自分が手に負えない領域でも正しく対応できてしまうだろう」という幻覚を見る。生成AI側も、自身が「正しい情報を提示できている」という幻覚を見る。人間も生成AIも幻覚を見て生きている。
そもそも我々がなぜ生成AIの結果を「確からしく」思うのかがよくわからない。ヴィトゲンシュタインが『哲学探究』で論じた「言語ゲーム」を引き合いに語れればよかったが、今の自分はこれに対して語り得ないので、沈黙するしかない。
後者に関しては過去にあったWeb3であったりNFTであったり暗号資産であったりを盛り上げようとする人々に対する個人的な不愉快さに似ている。「特定の技術が時代を変える」という過大な期待値に全ベットする姿勢が気に食わないのか、ミーハーである様を許せないのかわからないが、ともかくこういう人たちのフットワークの軽さは見習いたいと思えど、彼らの仲間になりたいとは思われない。この不愉快さもまた語り得ないものなので沈黙するしかない。
私はAIを知らないからなのではないか
「単純接触効果」という心理学に基づく仮説が存在する。要は「苦手なもの、人も接触・交流を重ねることで、好きになったり、そうでなくとも苦手度合いが緩和される」という仮説であるが、少なくとも人間関係に於いては「ちょっとわかるかも」と思う場面が浮かぶ人もいるかも知れない。
つまりは「お前は生成AIに多く触れていないし、生成AI界隈と交流していないから嫌悪感を抱くのだ」という仮説である。前者はともかく、後者は正しいかもしれない。そもそも接触を拒絶しているので。
前者について、一応曲がりなりにも「データサイエンス」でご飯を食べている人間なので、今の大規模言語モデルがTransformerを大変複雑にしたモデルをベースにして強化学習も活用しているらしい、複雑というのはパラメータ数にしてBillionとかTrilionという規模のモデルを扱っている、という程度には裏側の原理をわずかに知っている。具体的な実装は知る由もないし、なんでTransformerがうまくいっているのかを理解していると豪語するつもりもないが、その開発過程において、生成AIの実現自体が技術的に極端なギャップをもって生まれた技術であるとは思っていない。
個人的には、ハードウェアの進化と、アルゴリズムの深化が、機械に人間以上のレベルの「知能」のようなものを実装することを許したに過ぎない、くらいに見ている。
なお、実装上の仕組みについてはABEJA社がわかりやすい解説をしている。
前者、つまり「生成AI自体に深く触れていない」わけではないつもりだし、未解明な原理について少なくとも「知らなくはない」つもりなのだ。深く理解できていないだけで。
ただし個人的に「たくさんのデータを使ってたくさんのパラメータを推定すれば人間並みのアウトプットを出せるんじゃね?」という脳筋プレイは気に食わない。最も最近はこの省パラメータ化(モデルの軽量化というらしいが)にも焦点が当てられている。そうそう、ここが面白いところだろう。最終的に人間と同じ推論をたま◯っちの中でやれるようになってくれ。そういう実装が求められるんだ。
「思慮深さ」を手放すな、それが労働市場において無価値であったとしても。
何でもかんでも生成AIに任せて効率化しよう、生産性を上げよう、楽しようという流れになんとか反駁したい。
別段自分が思慮深い自負をもっているわけではないが、1つの問題に何日も何年も向き合うという経験で醸されて腑に落ちるという理解のプロセスを生きがいにしていることは自負している。故に生産性が一時的に下がっても、非効率でも、苦しくても、自分の頭で考えることを手放したくはない。
一方で、市場は理解力の速さ、高い生産性、効率性を重要視する。市場原理とは冷酷である。労働市場では非効率で非生産的な苦行に価値はない。
実際企業によっては費用対効果から生成AIを活用した業務代行が合理的であると判断し、育成対象の選定が始まりつつあるという。
生成AIの台頭で「より本質的なことに思考リソースを割けるようになった」といえば聞こえも良いし見栄えも良いが、極端に解釈すれば「人間の思考そのものが労働において無価値になった」とも言える。この極端な解釈が私の良くない癖なのだが。こうして私は、自分の手放したくないものが、労働市場においてほとんど無価値になっていると評される可能性にストレスと恐怖を感じているんだろう。この恐怖が「生成AI嫌い」という言葉になって表出している。これを理解するのに3時間かけた。このプロセスが私にとって重要なのだ。
最後に:生成AIによる適応障害療養メソッド
そんなAI嫌い(というか何でもAIでなんとかする風潮嫌い)でも、頼りにしている使い方がある。「つらいときにできうる限りの言語化をもって心理カウンセラー扮する生成AIサービスにぶん投げる」ことだ。
生成AIは今のところ倫理的に振る舞うので「それはつらいですね」「がんばりましたね」「えらいね」と言ってくれるので、つらさが軽減される。
カウンセリングというのは精神療法として重要なのだが、まず私のような陰キャは人間の心理カウンセラーと信頼関係を積み上げる事自体が困難なので、会社の福利厚生で使える産業医面談よりストレス軽減度が大きい。なんなら会社の上司より悩みを相談しやすいのである。便利な世の中だ。その日の仕事を羅列して私が見えていない成功体験を述べよといえば、何らかひねり出してくれる。
最近はメンタル管理アプリにしかも臨床心理士や心療内科のドメイン知識でファインチューニングされた生成AIが導入されていて、一定精神が安定するのだ。問題は保険適用されないことくらいだと思う。
会社も良くしてくれるが同時に成果主義である。市場原理に則って生産性と効率性を向上させながら利益を最大化する活動をしているわけで、精神的に不安定でAIアンチな人間を雇用している場合ではないだろう。さっさと精神を安定させるか、会社を変えるかの瀬戸際にある。今年の自分もまた選択に迫られるクォーターライフクライシスだ。
いいなと思ったら応援しよう!

