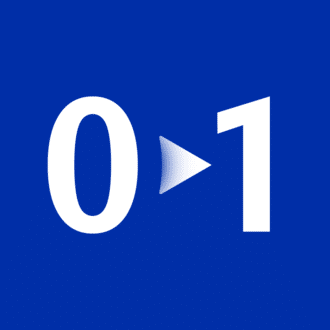【01Night】「地域経済に効く事業創造発展モデルはどのような形か? 〜 実際の活動から見えてきたこと 〜 」
皆さん、こんにちは!
今回は4月27日に開催の【01Night】「地域経済に効く事業創造発展モデルはどのような形か? 〜 実際の活動から見えてきたこと 〜」のイベント内容を再構成し、お届けします。

合田ジョージ
株式会社ゼロワンブースター / 共同代表・取締役。MBA、理工学修士。東芝の重電系研究所・設計、国際アライアンスや海外製造によるデザイン家電の商品企画。村田製作所にて、北米およびMotorolaの通信デバイス技術営業後、通信分野の全社戦略に携わる。スマートフォン広告のNobot社のマーケティングや海外展開を指揮、KDDIグループによる買収後には、M&Aの調整、グループ子会社の海外戦略部部長。現在は01Boosterにて事業創造アクセラレーターをアジアで展開中。

鈴木梨紗
北海道札幌市出身。北星学園大学短期大学部卒業後、JA北海道中央会へ入職、北海道石狩管内の農協女性部事務局を担当。その後スターバックスコーヒージャパン株式会社へ転じ、帯広、札幌すすきの両店でカウンター業務からスタッフ教育まで店舗運営全般に通じる。そのかたわら学んだフィットネスで、心身両面の健康の大切さを感じ、現在もマインドフルネス効果があるピラティスを勉強中。
昨年縁あって上京、株式会社Origamiのレセプションを経て2020年3月01boosterへ参画。〈人間が人間らしくありのまま〉に過ごす未来のコミュニティ作りを目指す。
これからのPost-COVIDの時代において「地域における事業創造はどのような形が良いのか」、「どのように経済を効果を及ぼしていくのか」を、2014年から全国各地で大学、地域行政・金融機関と事業創造プロジェクトを実施してきた01Boosterだからこそ見えてきた知見を中心にお伝えしていきます。
1.スタートアップは何を求めているのか?
スタートアップ支援による事業創造を考え始める前に、スタートアップとは何を目的にしているのか再確認し、そのために地域が何をするべきか、考えていきます。
大前提としてスタートアップとは、「急激な成長を目的とした組織」です。
成長が目的ではなく、堅実な経営によって安定的な雇用を実現するビジネスモデルとは区別し考える必要があります。
更にスタートアップの目的を深掘りすると、「ハッカーと画家」の著者であるポールグレアムはスタートアップの最適な状況として、「大勢の人が欲しがる商品を、欲しい人全員に届ける」としています。
この場合、スタートアップの方向は地域性を持つ方向ではなく、無国籍化、国境を超えて活動する方向に向いています。
つまり、スタートアップにとって最も重要なことの一つは、「どれだけ外とつながることができるか」ということです。
これを実践するため、例えばドイツではプロジェクトを実行する際、ドイツ+他国、もしくは地域+地域、といったようにほかの地域の人間を受け入れなければならないという仕組みが特に行政の分野などにあります。
2.つながりの大切さ
第一章ではスタートアップというビジネスモデルにとって、「つながり」がとても重要な要素の一つであることをお伝えしました。
この「つながり」について時代背景を含めて深掘りしていきます。
この場合の「つながり」は「社会関係資本」のことを指し、これからの時代においては、どれだけ「ネットワークを広域に持っているか」ということが地域にとってもビジネスにとっても、その勝敗を分ける要因となっていきます。
要するに、広がりを持ち、競争ではなく協力して生き残っていく、という方向性へシフトしている、ということです。
事例を一つご紹介すると、
アクセラレーターの世界では"Global Accelerator Network"というネットワークがあります。
このGANでは、世界中のアクセラレーターが集まりナレッジをイベントなどでシェアし、ネットワークに参加する皆でスタートアップ支援などを通じて着実に結果を残していこう、ということを目的としています。その理念の根底には、皆で協力して生き残っていくという考え方があります。
この「社会関係資本」において重要なことは、「信頼」「互酬性」「ネットワーク」の三要素です。

この中で「互酬性」とは、一方的な搾取ではなく、互いに貢献しあうことを指し、これは良好な関係を長続きさせるための基本的な条件といえます。
さて、話を具体的な面に戻すと、地域の新規事業創造の場面で、「地域でイノベーションを起こす」というような文言を目にすることが多いと思います。しかしそもそも、「イノベーション」とは何でしょうか。
経済学者のシュンペーターは、「イノベーション」を技術革新や刷新という意味だけではなく、「新結合」という解釈を用いるべきだ、と主張しています。
事実、「技術革新」の背景では複数の技術の結合や技術と制度の結合、生産要素の結合等が発生しています。その場合、「イノベーション」の本質は「新結合」とみなすことができます。

以上を前提において、地域での新規事業創造の現状を考えた場合、「地域に閉じこもった状態」において新規事業、イノベーションは起こりうるでしょうか?答えはNoです。
新結合を地域において応用すると、その地域の良さや強みは往々にして内部の人間ではなく外部の人間によって発見される、というケースが多いことが指摘でき、地域の内側だけではイノベーションは生まれない、と結論付けることができます。
3.環境の大切さ
スペインの哲学者であるオルテガ・イ・ガセットは「私は、私と私の環境である。そしてもしこの環境を救わないなら、私をも救えない」と説きます。

(合田さんの大切にしている言葉の一つだそうです。)
要するに自分とは、周囲の人間とのネットワークによって形成されるものであるということであり、自分がコミュニティの中で悪いことをすれば、自分に帰ってくる、ということです。
ここまでスタートアップとは何か、つながりとは何かを考えてきましたが、地域の事業創造発展プロセスの具体的な役割に視点を移しましょう。
地域の事業創造発展プロセスのステークホルダーとして、スタートアップの周囲には第二創業、中小企業、地域大手等も存在しています。その役割はどのようなものなのでしょうか?
これについて合田さんは彼ら(周囲のステークホルダー)が変わることこそが重要である、と強調します。

スタートアップを金魚に例えると、その周囲に存在する環境、つまり「地元中小企業」「地域大手」などの存在についても、決して軽視してはいけない、という教えです。
環境が変わらなければ、地域が変わることはありません。
この場合スタートアップは新しい風を取り込むための起爆剤でしかなく、それを原動力に地域の人々が創造的な考え方ができるようになっていく、新しいことを起こしていくことのできる環境に、地域が変容していくことが重要です。
環境が成果を作り出します。
ではその他のステークホルダーである、金融機関や行政、大学についてはどうでしょうか。
これに対して鈴木さんは「その土地でブランドが確立しているため、媒介として新しいカルチャーをアピールしていくことが必要」と主張します。

行政の場合、私企業と違い産業を水平に展開することができるため、より多くの企業を巻き込み、幕藩体制的意識を改善することができれば、周辺地域とも連携することができます。
大学は地域モデルの中で「人材輩出」という役割から中心的な立ち位置を取ります。
しかしながら現実には大学や学生は地域企業と連携しているでしょうか?大学生は地元企業のことを知っているのでしょうか?この問いは、必ずしも地元企業に就職しなければいけない、ということでありません。
「いずれ地元に帰ってきたときに、居場所を作ってあげる」という文脈で重要になってきます。
そして金融機関は、地元企業と大学、学生の媒介者となることができます。金融機関は中立的なつながりをたくさん持ち、かつ産業を応援する立場で、スタートアップに取ってはキーとなる存在です。
更にこれを俯瞰しましょう。
現状のスタートアップ支援の姿は、どこの地域でもほとんど同じようなモデルで展開しているケースがほとんどです。
これに対して、合田さんは香港の例を引用しながら、地域ごとに特化する領域、産業を持ち、水平に助け合いながら皆で成長していくモデルこそ重要だ、と主張します。

画面中央オレンジ色が香港、周囲の地域が産業ごとに色分けされ、特殊性を持っている状況です。
具体例として、2019年に01Boosterが関東経産局様と開催したWIDE ECOSYSTEM ACCELERATOR 2019をご紹介します。
このプログラムでは、つながり、共に成長するをコンセプトに複数の地域における支援機関やスタートアップが人と人でつながることで地域とスタートアップが共に成長すること、「地域のスタートアップエコシステムの構築」の実現にむけて多種多様な組織、人が交流し事業発展へまい進しました。
4.地域経済におけるスタートアップの役割
ここまで事業創造発展プロセスにおいて、スタートアップを取り巻く各ステークホルダーの役割について考えてきましたが、肝心のスタートアップの役割はどうあるべきなのでしょうか。
スタートアップと大企業の能力、性質はほぼ真逆の関係にあります。
スタートアップのような勢いは大企業には実現できない一方、しっかりと裏付けられた能力があります。そこに、スタートアップの考え方を吸い込みながら自己変革を起こすことが肝心だ、と合田さんは語ります。
実際、数兆円という地域経済の中においては、スタートアップの100億円程度の経済規模は小さな存在です。この面からみても、スタートアップのみを支援するのではなく、その地域全体が成長できるような形の支援の必要性が認識できます。
冒頭の問いの答えとしては、
スタートアップは地域経済の発展に、「地域に刺激を与え、価値観や考え方を刷新する」という、新しい風を取り入れる役割という面で必要不可欠といえます。
しかしスタートアップの支援のみに注力するのではなく、地域全体が変らなければという意識のもとで、地域全体に働きかけをすること、スタートアップが地域で孤立することなく、既存の事業体の変化がとても重要です。
5.成長は本当に幸せなのか?
最後に、今回の議論において、たびたび重要視されていた視点を紹介します。それは、「成長は本当に幸せにつながるのか」という問です。
この会の冒頭で合田さんは、「地域では、堅実に経営する所謂ファミリービジネスのようなものと、スタートアップが混同されがちである。」と、
鈴木さんは、「成長は正しいのか?」という合田さんの問いに対して、「成長し続けようとすると、どこかで不幸な思いをする人も出てくる」と指摘します。
成長は必ずしも幸せに結びついているわけではありません。スタートアップだけではなく、堅実な成長を行う企業の存在も必要です。

地域から都会へ人口が移り、工業化が進行する段階では確かに経済は成長します。しかしその後、イノベーションやスタートアップの登場により、状況によっては雇用が奪われる、という自体が発生することもあります。
合田さんは、不安定化する社会においては「長く存続し、生き続けることが重要である」と主張します。
Before COVIDでは、急激に成長するユニコーン企業が重視されてきましたが、After COVID, With COVIDの時代ではキャメル型、つまり普段は堅実に経営し、チャンスは逃さず一気に成長する形の経営モデルへと、シフトする必要性が出てきます。
これからは赤字を深く掘り、高いEXITを目指すのではなく、地域やその周辺の様々なステークホルダーと関わることでつながりを増やし、堅実に成長していく。そしてチャンスは逃さずに一気に目的に向かって進んでいくことのできる体力をつける、そういった経営スタイルが必要になってくるのではないでしょうか。
6.終わりに
最後までお読みいただきありがとうございました!
地域でのスタートアップの役割や他のステークホルダーの関わり方を見ていく中で、それぞれの本質の変化を垣間見ることができたかと思います。
基本的なことですが、時代の流れをしっかりと掴みながら実践していくモデルも変化させていく必要があること、そして地域においてはスタートアップ支援にだけにこだわるのではなく、しっかりと環境を作っていくことが重要だと学ぶことができました。
01Boosterはアクセラレーターとして、スタートアップが活躍できるような環境整備を行っています。文中でご紹介したプログラムもその一例です。

現在はオンラインにて昼と夜に01Nightというスタートアップに役立つトピックを取り上げ議論していくセッションを行っています。
興味のある方はPeatixやYouTube、ほかのnote記事などを覗いてみてください!
>>>>>>>>>>
Writer: 01Booster intern 王 翔一朗(Shoichiro Wang)
>>>>>>>>>>
いいなと思ったら応援しよう!